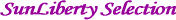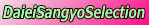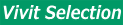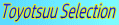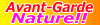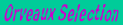頻繁なリロード禁止のお願い
大変お世話になっております。切実なお願いです。
ページのリロードが必要以上に行われるようになっています。サーバーへの過大な負荷でページ更新が滞る状況になっていますので、頻繁なリロードはお止めくださるようお願いいたします。
また、「503 Server is busy」のエラードギュメントページが表示され、一定時間アクセスが制限される場合がございます。いずれ元に戻りますが、そのようなことにならないようお願いいたします。
詳細ページ
ページのリロードが必要以上に行われるようになっています。サーバーへの過大な負荷でページ更新が滞る状況になっていますので、頻繁なリロードはお止めくださるようお願いいたします。
また、「503 Server is busy」のエラードギュメントページが表示され、一定時間アクセスが制限される場合がございます。いずれ元に戻りますが、そのようなことにならないようお願いいたします。
詳細ページ
■新着情報メールサービスのご登録
Noisy wine の新着情報メールサービスにご登録いただきますと、ご登録いただきましたメールアドレスに「タイムリーに」更新情報をお届けいたします。希少性のあるワインをご希望でしたら登録必須のサービスです。
■お届け情報他
現在以下の宛先に対し新着情報メールをお届けするすることが出来ません。世界情勢を反映してか、各社様メールのフィルターを厳しくしています。申し訳ありませんが gmail.com や yahoo.co.jp (yahoo.comは厳しいです) などのフリーアドレスに変更をご検討の上、再登録をお願いいたします。不明な方は最下段中央の「e-mail to noisy」よりお問い合わせください。
■新着情報メール不達の宛先(新規登録も出来ません)
icloud.com nifty.com me.com mac.com hi-ho.ne.jp tiki.ne.jp enjoy.ne.jp docomo.ne.jp plala.or.jp rim.or.jp suisui.ne.jp teabreak.jp outlook.com outlook.jp hotmail.co.jp hotmail.com msn.com infoseek.jp live.jp live.com
etc.
■お届け情報他
現在以下の宛先に対し新着情報メールをお届けするすることが出来ません。世界情勢を反映してか、各社様メールのフィルターを厳しくしています。申し訳ありませんが gmail.com や yahoo.co.jp (yahoo.comは厳しいです) などのフリーアドレスに変更をご検討の上、再登録をお願いいたします。不明な方は最下段中央の「e-mail to noisy」よりお問い合わせください。
■新着情報メール不達の宛先(新規登録も出来ません)
icloud.com nifty.com me.com mac.com hi-ho.ne.jp tiki.ne.jp enjoy.ne.jp docomo.ne.jp plala.or.jp rim.or.jp suisui.ne.jp teabreak.jp outlook.com outlook.jp hotmail.co.jp hotmail.com msn.com infoseek.jp live.jp live.com
etc.
noisy のお奨め

Spiegelau Grand Palais Exquisit
シュピゲラウ・グランパレ・エクスクイジット・レッドワイン 424ML
軽くて薄くて香り立ちの良い赤ワイン用グラスです。使い勝手良し!
Comming soon!

Spiegelau Grand Palais Exquisit
シュピゲラウ・グランパレ・エクスクイジット・ホワイト 340ML
軽くて薄くて香り立ちの良い白ワイン用グラスです。使い勝手良し!
Comming soon!
有 る と 便 利 な グ ッ ズ !
WEBの情報書込みもSSLで安心!


Noisy Wine [NOISY'S WINE SELECTS] のサイトでは、全ての通信をSSL/TLS 情報暗号化通信し、情報漏洩から保護しています。
◆◆Twitter 開始のご案内

時折、Twitter でつぶやき始めました。もう・・どうしようもなくしょうもない、手の施しようの無い内容が多いですが、気が向いたらフォローしてやってくださいね。RWGの徳さん、アルXXロのせんむとか・・結構性格が出るもんです。
https://twitter.com/noisywine
■□新着情報MS 2025年第40弾 Ver.1.0 page5□■
次号発行まで有効です。2025年05月23日(金) より発送を開始いたします。 最短翌日到着地域2025年05月24日(土)! になります。翌々日到着地域で2025年05月25日(日) が最短です。
発送が集中した際はご希望に添えない場合もございます。
◆新着商品は通常の送料サービスと異なります。「ここ」 で確認
◆在庫表示はページ読込時数です。既に完売もございます。
次号発行まで有効です。2025年05月23日(金) より発送を開始いたします。 最短翌日到着地域2025年05月24日(土)! になります。翌々日到着地域で2025年05月25日(日) が最短です。
発送が集中した際はご希望に添えない場合もございます。
◆新着商品は通常の送料サービスと異なります。「ここ」 で確認
◆在庫表示はページ読込時数です。既に完売もございます。
ドメーヌ・ダニエル・エ・ジュリアン・バロー
ダニエル・エ・ジュリアン・バロー
フランス Domaine Daniel et Julien Barraud ブルゴーニュ
● すみません・・2022年もののバローのご紹介で、「過去最高」を口にしましたが、早速修正です。2023年もののドメーヌ・バロー、半端無い仕上がりで・・
「過去最高を更新した2023年!」
をお知らせいたします。
なお・・価格はアンビュランV.V.が少々値上げ、また無理してリーズナブルな価格にしていたマコン=シェントレ・ピエール・ポリが少し値上げになっているほかは、ほぼ同じ価格のはずです。
圧巻な仕上がりですが、マコン=シェントレ・ピエール・ポリでその凄さは判りますし、サン=ヴェランのどのキュヴェでも充分過ぎる旨さです。プイィ=フュイッセに至っては、
「ある意味、アリアンスV.V.で充分!」
です。メディア評価はほぼ見当たりませんでしたが、ジャンシス・ロビンソン・コムでアリアンスV.V.もサン=ヴェラン・アン・クレシェも93ポイントですから、
「上級キュヴェはどんだけ凄いか?」
位は想像に難くないと思います。
アリアンスで良いんですが・・出来れば反逆のマレショード2種・・半端無く凄いですから是非!・・数の無いアン・ビュランとスュール・ラ・ロシュは飲めていませんので・・申し訳ありません。
これほどまでにリーズナブルで高質で、しかも毎年の伸びが半端無いシャルドネは、
「いくら探しても見当たらない!」
と思います。ぜひご検討くださいませ。超お薦めのドメーヌです!
-----
圧巻です!・・過去最高間違い無し!・・と太鼓判を押します。1990年台から延々とテイスティングさせていただいてます、ドメーヌ・ダニエル・エ・ジュリアン・バローのご案内です。
長いようで短いようで・・この30年ほど毎年、テイスティングを欠かさずに続けたドメーヌ・バローです。ついに、
「アン・ビュランが割り当てになって少な過ぎるので、減らさないようにテイスティングを回避」
したものの、
「今まででおそらく最高の12アイテムが入荷」
したので、
「11アイテムのテイスティング」
をさせていただきました。
まぁ、過去最高は変わりませんが、ようやっと入って来た・・昔は「ラ・ヴェルシェール」とだけ入っていたプイィ=フュイッセが、
「2020年ものより1級に格上げ」
され、
「1級ラ・マレショード・クロ・ラ・ヴェルシェールと、1級ラ・マレショード・ル・バ」
のリリースとなっています。このクロ・ラ・ヴェルシェール..ポテンシャルがま~半端無く、
「復活なったレ・クレイとアン・ビュラン、そしてラ・ロシュの間に割って入る存在!」
になったと感じています。
また、10年も前に扱わせていただいた、懐かしいアイテムも全てテイスティングさせていただきましたが、
「2022年のドメーヌ・バローは過去最高!」
です。
そして価格も・・頑張らせていただきました。特にベースのマコン=シェントレは、インポーターさんとの相談で何とか激安に・・ご案内出来ます。ぜひ飲んでみてください!
-----
2021年のドメーヌ・バローが到着です。2020年ものの濃密なスタイルからどのような変化が有ったか・・noisy 的には、
「ここまで変わってくるとは・・20年前には予想もしていなかった・・」
と言えるほど、ナチュール感がピュアな味わいに備わっています。
そのくせ、アヴァンギャルドな・・突飛な感覚を受ける部分が全くなく、さりとて使用しているはずの「新樽」のニュアンスさえも感じないんですね。
そして収穫期の暑さに苦しめられた2020年ものの濃密なスタイルでは無く、実に健康的、健全なブリっとした果実とたっぷりでテロワールそのものを感じさせるミネラリティを豊富に含んでいて、
「個人的には過去最高・・と言いたい・・」
気持ちをグッと抑えなくてはいけない・・そんな感覚を持っています。
その意味は、2021年ものは物凄く素晴らしいヴィンテージで有ることは間違い無いものの、
「鬼っ子的存在の2020年ものを超えられるか?」
と言うただ一点・・です。
濃密さについてはもう・・2020年が圧倒的です。しかしながら、2021年ものが持つそのどこまでも健康的なニュアンスと素晴らしい酸が有り、
「このエレガンスの出方は本当にマコン、プイィ=フュイッセのワインなのか?」
と疑いたくなるほどにコート・ド・ボーヌの最高のシャルドネの姿に似通って来ています。
ですから、濃密な2020年、エレガントで健康的な2021年と言いたいと思います。
「どっちが良いのか?」
と言う点につきましては、お客様本人が・・もしくは10年以上経過してから・・答えが出るんじゃないかと思います。
また、余りの生産量の少なさからの値上げ、為替でユーロが強い背景、世界的な資材の価格上昇・燃料高騰で、価格は上昇していますが、
「Noisy wine もここが堪えどころ!」
と言うことで、自店で可能なできうる限りの最低の価格付けをさせていただきました。数が無いのに価格も適正レベルまで上げられないのは辛いところですが、
「是非2020年と2021年、葡萄の出来の背景を知り比較してみていただきたい!」
そう思っています。アン・ビュラン、スュール・ラ・ロシュ、レ・クレイ..最高です!そしてアリアンス、サン=ヴェラン、マコン=シェントレと続きますが、どれを飲まれてもミネラリティの豊かさ、ナチュラルさが増したピュアさに美味しくいただけると思います。ご検討くださいませ。
<インポーター様より、ドメーヌ・バローについて>
2021年は春の霜や6月の雹の被害でダメージが大きく厳しい年となりました。収穫量も60%減となり醸造できないキュヴェもありました。入荷数量は例年より非常に少ないため、ご希望の数量を調整させていただく運びとなります。
-----
2019年もののブルゴーニュ・シャルドネを振り返ってみると、健康美を誇り完成度の高い見事な出来栄え・・グレートイヤー間違い無しと思わせてくれました。今回ご紹介させていただきますドメーヌ・バローもまた、リリース時からとても美味しく飲めたヴィンテージだったと思います。
2020年ものの先駆けで入荷したバローのシャルドネですが、まず・・これまたビックリするような素晴らしい仕上がりだったことをお伝えいたします。下から上まで、より硬質で非常にポテンシャル高く、どのアイテムを飲んでも楽しんでいただけます。
また、2020年ものからは、スュール・ラ・ロシュとレ・クレイが1級のクレジットが入っています。ですがバローのトップ・キュヴェであるアン・ビュランは1級には認定されなかったようです。・・まぁ、所有者が他にいないとか・・少ないとか・・そんな理由ではないかと想像しますが、詳細は不明です。
2020年もののバローは、素晴らしかった2019年ものよりも、よりポテンシャルが高いと判断しました。ハッキリ言って・・もの凄い出来です。それは下から上まで同様です。
今飲んで圧巻は・・1級スュール・ラ・ロシュ。この数年の凄い出来を見続けて来ていますが、抜栓して15~20分ほど経過した頃に見せる、まるでピュリニーの凄い畑か!・・と思わせるような絶妙に細やかでキラ星のように口内で弾けノーズに抜ける表情には、驚かされました・・本当に凄いです!
トップ・キュヴェのアン・ビュランV.V.はまだ中々弾けてはくれませんが、ムルソー・ペリエールが如き豪奢な表情の蕾をしっかり見せてくれます。
1級になったレ・クレイはその名の通り、白亜土壌由来の非常に細やかな表情を内に秘め、その爆発を待っているタイミングかと思いますが、30年前の植え替え前は、アン・ビュランと並び賞されるヴィエイユ・ヴィーニュの畑だったことを思い起こさせる独特の表情をしています。
プイィ=フュイッセのアイテムの中では最もリーズナブルな「アリアンス」は、流石にトップ・スリーには届かないものの、今飲んでも2020年のバローのプイィ=フュイッセがどんな出来なのかを最も判りやすく教えてくれる存在です。バローのプイィ=フュイッセを今すぐに美味しく飲みたいなら・・このキュヴェでしょう。
サン=ヴェランは、硬質な出来の2020年ドメーヌ・バローに有って、中域の膨らみのある酸バランスを持っていますので、今飲んでも素晴らしい!・・リーズナブルさもマコン=シェアントレと競います。
ベースのマコン=シャントレも2020年のバローらしく、2019年ものよりもミネラリティのコートが感じられる「ツルッツル」のテクスチュア。徐々に開いて行く表情が2019年ものよりも複雑で、若いながらもとても美味いです。
海外メディアの情報を検索してみましたが、まだ中々出て来ていません。完売した頃に出てくるんじゃないかと思います・・
素晴らしい出来になった2020年のドメーヌ・バローです。リーズナブルさは変わらずです。ですが非常に少ないようなので早々に完売すると思います。お早めにご検討くださいませ。
-----
ドメーヌ・バローの2019年をご紹介させていただきます。年を追う毎に美しさ、健康美、ピュアさ、ナチュラルな風味を身に着けて来たこの数年ですが、2019年ものは「さらに・・」と言って良いと思います。素晴らしく健康的でピュア、そしてナチュラルな柔らかさを見せつけてくれますが、noisy もバローのワインを非常に長く扱って来ましたので、ある意味・・
「その変化には相当驚いている」
訳ですね。
1990年代はル・テロワールさんの輸入(ノースバークレイのスペシャル・キュヴェ)だったと思いますが、もっと樽っぽく凝縮感が目立ち、ポテンシャルは非常に高いものの、現在のような健康美・・と言うか、ナチュラルな柔らかさとは程遠い存在でした。もっと素直にポテンシャル感は高く、
「お~・・すげ~なぁ・・アン・ピュランやクレイは、熟したら本当に凄いぞ!」
と・・感じさせてくれたものです。そんなパワフルな味わいが受ける時代でも有ったと思います。
今はジュリアンがダニエルに代わり指揮を執っている性かもしれませんが、とても自然な味わいが全体を包んでいますので、むしろ、
「美しすぎてポテンシャルそのものを取るのは、以前より難しい」
とも言えます。
その辺りはビオ転向組のメディア評価の経緯、移り変わりを見ればお判りかと思いますが、それでもnoisy 的には、
「ポテンシャルは以前と全く変わらない」
と感じますし、
「リリース直後の膨らみ、伸び、美しさは以前より増している」
と感じます。
まぁ、ベースキュヴェのマコン=シェントレで充分美味しいので・・ある意味、ワイン屋泣かせな存在かもしれません。
2019年は2015年ものにも似た健康美に加え、そのナチュラルな膨らみ、柔らかさが以前のものよりも増している点で、より高い評価をすべきじゃないかと思います。是非ご検討くださいませ。
 ■生産者情報
■生産者情報
ヴェルジッソンの岩の近くに位置するバロー・エステートは、ワインへの情熱を受け継いでいます。世代を超えて受け継がれてきた共通の目標は、常に独自のノウハウとテロワールを促進することでした。「うまく働くために、あなたはあなたの時間を節約する」というモットーで、不動産はそのルーツを維持しながらそれ自身を更新することができました。
テロワール
ソルトレとヴェルジッソンの象徴的な岩に囲まれたバローエステートは、フランスのグランドサイトに分類される村にあります。モルヴァンに裏打ちされた古いラグーンに囲まれたこの場所で提供される岩は、古代のサンゴ礁で構成されています。土壌には、石灰岩のガラ場、アグリフォイド石灰岩、斑入りの粘土の3つの主要なタイプがあります。それぞれの土壌は特別な注意と特定の文化を誘発します。バローエステートは、その豊かさと多様性を最もよく表現するために、このテロワールを維持しています。
ぶどうの木
有機農法からインスピレーションを得て職人技で栽培されたこのエステートのブドウの木は、丁寧に作られています。彼らのGuyot-Pushardサイズは、植物の樹液の流れを尊重します。
ブドウ園と土壌を尊重するために、実行される処理は硫黄と硫酸銅のみに基づいています。最近の古いブドウの木では、機械化せずに作業が行われています。可能な限り完全で健康的なブドウを得るために、収穫も手動で行われるため、酸化が制限されます。
ドメーヌ・バローの歴史
1905年
ジャンマリーとマリー・バロー
バロー家のワインの歴史は1905年に始まりました。読み方と数え方を知っていたジャンマリーバローは、小作人として良い場所を見つけ、ヴェルジッソンに定住しました。彼の安定した収入により、彼はお金を節約し、1912年にバロー邸の最初の区画である妻のマリーと一緒に買収することができました。
1922年
ジョセフとマーガレット・バロー
10年後、ジョセフとマーガレットバローが引き継ぎます。大胆な男であり、真の先見の明があるジョセフは、作付けの良い区画を見つける方法を知っているため、ブドウの木を植えるために多数の牧草地を取得します。優れた起業家として、彼はカフェやレストランに売ることの価値をすぐに理解しました。1930年代の終わりに、彼はこの地所でワインを瓶詰めすることを最初に決めた人の1人でした。最初のキュヴェ「LesCrays」は1947年に登場しました。
1959年
アンリとモニーク・バロー
1959年、アンリバローは、フュイセ出身の妻モニークと一緒に家族の邸宅で働き始めました。「うまく働くために、あなたはあなたの時間を節約する」という不動産のモットーの起源で、良い地主であり思慮深い人であるアンリは、彼の努力を数えずに不動産を維持します。1971年、AOCサンヴェランが創設されました。アペラシオン「lesPommards」の区画は、1978年に最初の瓶詰めになります。
1979年
ダニエルとマーティン・バロー
バロー家の第4世代は、1979年に定住し、不動産の一部を相続しました。ダニエルと妻のマルティーヌは、祖父と同じ意志と現代性を持って不動産を開発し、マコンヴェルジッソンとサンヴェラン「エンクレッシュ」と一緒にボトルでのマーケティングを開始しました。1990年に、彼らは家とClosdelaVerchereを買収しました。略語DBがラベルに表示されます。
ワインと環境に情熱を注ぐダニエル・バローは、テロワールの保護に取り組むGEST deBeaune協会の会員です。
2006年と2015年
ジュリアンとアナイス・バロー
彼らの息子であるジュリアンは、2006年に不動産の仕事を始め、家族の技術を習得しました。ジュリアンは、たとえばすべての区画を耕すことで、不動産の職人文化を強調することにしました。現在、ワイン造りは彼の独占的な領域であり、彼も家族のノウハウに従って運営していますが、彼はそれを開発することもできました(偉大なヴィンテージのより長い醸造)。アナイスは2015年に兄に加わり、不動産のすべての管理および商業部分を管理しました。
彼らは一緒に、将来が彼らに要求するかもしれない変化を心に留めながら、テロワールの伝統と尊敬を永続させたいと思っています。
-----
「2018年のダニエル・エ・ジュリアン・バローは、ディディエ・ダグノー風のクリスタルなミネラリティを手に入れた!」
このところのダニエル・バローのナチュラル化は止まりません。年を追う毎に・・美しくなって行きます。
親父さんの頃は素晴らしい果実の風味で、シャルドネの美味しさを見事に表現していました。かのPKさんも、ブルゴーニュ・シャルドネのTOP100に、ダニエル・バローのプイィ=フュイッセを2アイテムも入れていたほどです。
Julien et Anais Barraud
2018年もののバローは、そんな素晴らしい果実の風味も・・実はたっぷりあるんですが、それよりも特筆すべきは、クリスタルのようなミネラリティが膨大な果実の風味を分厚くコーティングしていることでしょう。・・そう、
「もしかして・・ディディエ・ダグノーを目指してる?」
んじゃないか?・・と思えるほど、ミネラリティのクオリティ、量が半端無く増えているんですね。
ですので・・そういう意味においては、メディア評価はむしろ下がっています。物凄い出来の2018年アン・ビュランV.V.でさえ、93点だそうです・・。まぁ、noisy としましては、ハッキリ・・否定させていただきます。「そんな訳は無いす」・・ちゃんと評価してください。
珠玉の「スュール・ラ・ロシュ」は、白眉アン・ビュランに次ぐ仕上がりです。この位のミネラリティの方がむしろ判りやすいでしょう。
そしてまぁ・・それなりの点が付いているアリアンスV.はティム・アトキンさんが91ポイントです。でももう、これで充分!と言えるほどに素晴らしいですし、サン=ヴェラン・アン・クレシェとマコン・シェントレに至っては、
「プイィ=フュイッセ群にそんな低い点を付けちゃったら・・この2アイテム、どう評価するの?」
と思えるほどです。案の定、ネットを検索してみても出て来ません・・。
ですが、2018年もののバローは、どのワインも物凄いミネラリティが豊富な果実をコーティングしていますから、
「つやつや、すべすべのテクスチュアからピュアでナチュラルな果実が漏れてくる、素晴らしいスタイル!」
に仕上がっています。どんどん・・ディディエ・ダグノーに近寄って来ていると感じています。素晴らしい出来でした!
勿論ですが、アン・ビュラン2018は、そんなレベルでは有りません。今回は非常にリーズナブルなので・・いや、少し早いですけど飲んでみていただけたら、noisy の言っている意味が判ると思いますよ。マコン=シェントレでも充分納得の美味しさと美しさを感じていただけるでしょう。超お勧めします!
-----
● 何しろ昨今は、あの・・「赤ワインが基本」だったリアルワインガイドも、だいぶ白ワインを掲載するようになったので、あれだけ
「ダニエル・バローは旨くて安くて素晴らしい!」
と20年近くにも渡って公言し続けてようやっと・・今の状況なんですが、リアルがバローを掲載し始め、今までブルゴーニュ・ピノにしか興味の無かった方々もシャルドネの旨さに気付き始めたのか、
「ダニエル・バローは・・・ラシーヌさんのはいつ入りますか?」
などとお尋ねの電話やメールをいただくようになりました。(基本、電話はお断りしてるんですが・・全ての仕事が中断になっちゃいますんで・・)
で、高い評価がリアルに載ったりすると・・・それも2013年のように極端に収量が低い年だと・・本当に困っちゃいます。
何しろ、アン・ビュランV.V.の入荷ががこんなに少なかったことは今まで有ったでしょうか・・アン・ビュランだけじゃなく、レ・クレもラ・ロシュも全てバラでしか入ってません。
なので、申し訳有りませんが、ダニエル・バロー今までずっと毎年ご購入になられていらっしゃるお客様にも渡らないかもしれません。ご容赦ください。
━━━━━
毎年のように全アイテムをテイスティングしてきましたが、一昨年などはとても少量でしたので、テイスティングを断念せざるを得ない状況でした。
ですが2012年もの・・・価格はそれなりに上がった・・・いや、昔に戻っただけ・・・とも言えますが、数量は結構戴けたんですね。なので、2012年は全アイテムのテイスティングをさせていただきました!そしてもう・・・ビックリです!
全アイテムのテイスティングは出来なくとも、幾つかのワインは飲んできましたので、その傾向は理解しているつもりです。しかも90年代前半から連続して飲んでおりますので・・・そんなnoisy が2012年のバローのワインに感じたことは・・
「近年、経験したことの無い凄い仕上がり!もしかするとダニエル・バローの史上最高のワインになった!」
まず、低価格~ボリュームラインクラスの格上げの美味しさ・・が言えると思います。マコン、サン=ヴェランとも・・今までに無いようなポテンシャルの高さを感じました。そして、マコンはサン=ヴェランを、サン=ヴェランはプイィ=フイッセを喰ってしまいそうなアイテムが有り、完全にクラス越えをしているんです。
そしてフラッグ・シップのアン・ビュランは・・・モンラッシェクラスのビロードのテクスチュアを持つミネラリティでした・・・どれだけ伸ばしても伸ばしきれない・・どこまでも伸張して行くだけの目の細かさを持っていました。
勿論、各アイテム・・・素晴らしいです!ダニエル・バロー史上、きっと最高の仕上がりになったと思える2012年は、必ず飲んでいただきたいと思います。皆さんの・・
「えっ?・・・」
と驚く顔が見たい・・・(^^;; ではどうぞよろしくお願いいたします。
以前ののコラムより転載です。
● 2009年ダニエル・バロー(不)完全ガイド
・・・(不)と入っているのは、幾つかのキュヴェのテイスティングが量的に考えて不可能だったからです。また、プイィ=フュイッセ・ラ・ロシュの入荷は有りませんでした。
結論
良いとアナウンスされた2009年ですが、バローにとっては・・・いや、マコネーの生産者にとっては、普通のヴィンテージなのかもしれません。むしろ、余り良くなかったのかもしれないとさえ思えます。その中で、バローは最善の策を講じ、素晴らしい品質になったのだと理解しています。
2009年のダニエル・バローは全くの贅肉無し、残糖分無し、実に筋肉質でエレガントなマコネーに仕上がっている!・・と言えます。
すなわち、マッチョでは無い、エレガントなムルソーのようなワインで、甘みと云う、人間で言えば「脂肪」のようなものを全く持っていません。これは全てのキュヴェに言えることです。本来は豪奢で、少し残った残糖分が、こってりとした、もしくは甘みの有るフルーツを連想させるものです。ところが、2009年はそうではない・・んです。すべてはエキスへと転化されていますので、今までのような、簡単にいつでも開けて美味しいマコネーでは無いです。きちんと休養させ、揺らさないように抜栓し、エキスを開かせるような飲み方が要求されるかと思います。
それでも、一連のバローのワインは、その隠し事の無いエレガントさが素晴らしいです。贅肉無し、甘み無しのプイィ=フュイッセですが、2008年の仕上がりを考えても、
「ダニエル・バローもエレガント路線に変更か?」
との思いを強くせざるを得ません。まあ、コント・ラフォンのように・・・そっちに行くのかもしれませんよ。
実は昨年、2008年のバローでは、こんなことを書いていました。
━━━━━
ある意味、2008年は、ダニエル・バローの転換となるヴィンテージになったかもしれません。それは、マイナスの方向に働くことはまず考えられず、さらに偉大なシャルドネを目指しての転換期です。本当に素晴らしい辛口のシャルドネに、実は余分な肉は必要無いのです。しかし、本当に素晴らしい辛口のシャルドネは、本当は甘いのです。でも、その甘さは・・・糖分によるものでは無い。エキスによるものです。その意味においては、2008年のダニエル・バローは、自身の過去に有り得なかったバランスのシャルドネを造り出したのです。
最低5年・・・待ってください。3~6千円のシャルドネに5年待てとは・・・なかなか言い辛いです。しかし、途方も無い可能性を秘めたワインで有る事に目を背ける訳には行かないんです。素晴らしい辛口のシャルドネとは、糖分に頼らないポテンシャルを持った甘いワインなんだと・・・理解していれば、この2008年のバローに挑戦してみることに異論は無いはずです。
やはり、アン・ビュランは凄いですし、ラ・ロシュ(プイィ=フュイッセ)もポテンシャルがビシビシ来ます。しかし、やはり今はちょっと厳しい・・・。本当のことを言うならば、あと1~3ケ月、瓶による熟成をしてから出荷すべきでした。そうすれば新酒由来の渋みも消え、綺麗な状態になったはずです。しかし、バローさんとしてみれば、そんな経験は今までにほぼ無かったはず・・・。まあ、我々が判っていれば良いんですが、人によっては、
「駄目・・」
と、早い結論をしてしまうかもしれません。
でもこのバロー2008年、ポテンシャルに掛けて欲しいと思います。2015年にはきっとそれなりの結論が出ているでしょう。焦らず、飲めるものから試し、上級キュヴェは寝かせてください。是非ともご検討くださいね。
━━━━━
自分でこんなことを書いていたとは・・・すっかり忘れてました・・・(^^;;
でも、2009年のダニエル・バローは、お手軽さは無くなりましたが、ワイン本来の美しさが見えてきたとも言えます。是非ともしっかり休めてお楽しみください!お奨めします!
 エージェント情報
エージェント情報
マコン・ヴィラージュ、サン・ヴェラン、プュイ・フィッセの3つの地区でワインを造っている、コート・シャロネーズを代表する造り手・ダニエル・エ・マルティーヌ・バロー。ロバート・パーカーも「コート・ドゥ・ボーヌのグラン・クリュの最も優れたワインと同等か、それを凌ぐ、最上級のワインをつくっている。」と高く評価している。
栽培 ビオロジック
自社畑面積6.7ha
醸造完熟したブドウを収穫した後、澱の上に15ヶ月間そのままにしておき、清澄も濾過もせず、豊かな味わいのワインに仕上げている。
長いようで短いようで・・この30年ほど毎年、テイスティングを欠かさずに続けたドメーヌ・バローです。ついに、
「アン・ビュランが割り当てになって少な過ぎるので、減らさないようにテイスティングを回避」
したものの、
「今まででおそらく最高の12アイテムが入荷」
したので、
「11アイテムのテイスティング」
をさせていただきました。
まぁ、過去最高は変わりませんが、ようやっと入って来た・・昔は「ラ・ヴェルシェール」とだけ入っていたプイィ=フュイッセが、
「2020年ものより1級に格上げ」
され、
「1級ラ・マレショード・クロ・ラ・ヴェルシェールと、1級ラ・マレショード・ル・バ」
のリリースとなっています。このクロ・ラ・ヴェルシェール..ポテンシャルがま~半端無く、
「復活なったレ・クレイとアン・ビュラン、そしてラ・ロシュの間に割って入る存在!」
になったと感じています。
また、10年も前に扱わせていただいた、懐かしいアイテムも全てテイスティングさせていただきましたが、
「2022年のドメーヌ・バローは過去最高!」
です。
そして価格も・・頑張らせていただきました。特にベースのマコン=シェントレは、インポーターさんとの相談で何とか激安に・・ご案内出来ます。ぜひ飲んでみてください!
-----
2021年のドメーヌ・バローが到着です。2020年ものの濃密なスタイルからどのような変化が有ったか・・noisy 的には、
「ここまで変わってくるとは・・20年前には予想もしていなかった・・」
と言えるほど、ナチュール感がピュアな味わいに備わっています。
そのくせ、アヴァンギャルドな・・突飛な感覚を受ける部分が全くなく、さりとて使用しているはずの「新樽」のニュアンスさえも感じないんですね。
そして収穫期の暑さに苦しめられた2020年ものの濃密なスタイルでは無く、実に健康的、健全なブリっとした果実とたっぷりでテロワールそのものを感じさせるミネラリティを豊富に含んでいて、
「個人的には過去最高・・と言いたい・・」
気持ちをグッと抑えなくてはいけない・・そんな感覚を持っています。
その意味は、2021年ものは物凄く素晴らしいヴィンテージで有ることは間違い無いものの、
「鬼っ子的存在の2020年ものを超えられるか?」
と言うただ一点・・です。
濃密さについてはもう・・2020年が圧倒的です。しかしながら、2021年ものが持つそのどこまでも健康的なニュアンスと素晴らしい酸が有り、
「このエレガンスの出方は本当にマコン、プイィ=フュイッセのワインなのか?」
と疑いたくなるほどにコート・ド・ボーヌの最高のシャルドネの姿に似通って来ています。
ですから、濃密な2020年、エレガントで健康的な2021年と言いたいと思います。
「どっちが良いのか?」
と言う点につきましては、お客様本人が・・もしくは10年以上経過してから・・答えが出るんじゃないかと思います。
また、余りの生産量の少なさからの値上げ、為替でユーロが強い背景、世界的な資材の価格上昇・燃料高騰で、価格は上昇していますが、
「Noisy wine もここが堪えどころ!」
と言うことで、自店で可能なできうる限りの最低の価格付けをさせていただきました。数が無いのに価格も適正レベルまで上げられないのは辛いところですが、
「是非2020年と2021年、葡萄の出来の背景を知り比較してみていただきたい!」
そう思っています。アン・ビュラン、スュール・ラ・ロシュ、レ・クレイ..最高です!そしてアリアンス、サン=ヴェラン、マコン=シェントレと続きますが、どれを飲まれてもミネラリティの豊かさ、ナチュラルさが増したピュアさに美味しくいただけると思います。ご検討くださいませ。
<インポーター様より、ドメーヌ・バローについて>
2021年は春の霜や6月の雹の被害でダメージが大きく厳しい年となりました。収穫量も60%減となり醸造できないキュヴェもありました。入荷数量は例年より非常に少ないため、ご希望の数量を調整させていただく運びとなります。
-----
2019年もののブルゴーニュ・シャルドネを振り返ってみると、健康美を誇り完成度の高い見事な出来栄え・・グレートイヤー間違い無しと思わせてくれました。今回ご紹介させていただきますドメーヌ・バローもまた、リリース時からとても美味しく飲めたヴィンテージだったと思います。
2020年ものの先駆けで入荷したバローのシャルドネですが、まず・・これまたビックリするような素晴らしい仕上がりだったことをお伝えいたします。下から上まで、より硬質で非常にポテンシャル高く、どのアイテムを飲んでも楽しんでいただけます。
また、2020年ものからは、スュール・ラ・ロシュとレ・クレイが1級のクレジットが入っています。ですがバローのトップ・キュヴェであるアン・ビュランは1級には認定されなかったようです。・・まぁ、所有者が他にいないとか・・少ないとか・・そんな理由ではないかと想像しますが、詳細は不明です。
2020年もののバローは、素晴らしかった2019年ものよりも、よりポテンシャルが高いと判断しました。ハッキリ言って・・もの凄い出来です。それは下から上まで同様です。
今飲んで圧巻は・・1級スュール・ラ・ロシュ。この数年の凄い出来を見続けて来ていますが、抜栓して15~20分ほど経過した頃に見せる、まるでピュリニーの凄い畑か!・・と思わせるような絶妙に細やかでキラ星のように口内で弾けノーズに抜ける表情には、驚かされました・・本当に凄いです!
トップ・キュヴェのアン・ビュランV.V.はまだ中々弾けてはくれませんが、ムルソー・ペリエールが如き豪奢な表情の蕾をしっかり見せてくれます。
1級になったレ・クレイはその名の通り、白亜土壌由来の非常に細やかな表情を内に秘め、その爆発を待っているタイミングかと思いますが、30年前の植え替え前は、アン・ビュランと並び賞されるヴィエイユ・ヴィーニュの畑だったことを思い起こさせる独特の表情をしています。
プイィ=フュイッセのアイテムの中では最もリーズナブルな「アリアンス」は、流石にトップ・スリーには届かないものの、今飲んでも2020年のバローのプイィ=フュイッセがどんな出来なのかを最も判りやすく教えてくれる存在です。バローのプイィ=フュイッセを今すぐに美味しく飲みたいなら・・このキュヴェでしょう。
サン=ヴェランは、硬質な出来の2020年ドメーヌ・バローに有って、中域の膨らみのある酸バランスを持っていますので、今飲んでも素晴らしい!・・リーズナブルさもマコン=シェアントレと競います。
ベースのマコン=シャントレも2020年のバローらしく、2019年ものよりもミネラリティのコートが感じられる「ツルッツル」のテクスチュア。徐々に開いて行く表情が2019年ものよりも複雑で、若いながらもとても美味いです。
海外メディアの情報を検索してみましたが、まだ中々出て来ていません。完売した頃に出てくるんじゃないかと思います・・
素晴らしい出来になった2020年のドメーヌ・バローです。リーズナブルさは変わらずです。ですが非常に少ないようなので早々に完売すると思います。お早めにご検討くださいませ。
-----
ドメーヌ・バローの2019年をご紹介させていただきます。年を追う毎に美しさ、健康美、ピュアさ、ナチュラルな風味を身に着けて来たこの数年ですが、2019年ものは「さらに・・」と言って良いと思います。素晴らしく健康的でピュア、そしてナチュラルな柔らかさを見せつけてくれますが、noisy もバローのワインを非常に長く扱って来ましたので、ある意味・・
「その変化には相当驚いている」
訳ですね。
1990年代はル・テロワールさんの輸入(ノースバークレイのスペシャル・キュヴェ)だったと思いますが、もっと樽っぽく凝縮感が目立ち、ポテンシャルは非常に高いものの、現在のような健康美・・と言うか、ナチュラルな柔らかさとは程遠い存在でした。もっと素直にポテンシャル感は高く、
「お~・・すげ~なぁ・・アン・ピュランやクレイは、熟したら本当に凄いぞ!」
と・・感じさせてくれたものです。そんなパワフルな味わいが受ける時代でも有ったと思います。
今はジュリアンがダニエルに代わり指揮を執っている性かもしれませんが、とても自然な味わいが全体を包んでいますので、むしろ、
「美しすぎてポテンシャルそのものを取るのは、以前より難しい」
とも言えます。
その辺りはビオ転向組のメディア評価の経緯、移り変わりを見ればお判りかと思いますが、それでもnoisy 的には、
「ポテンシャルは以前と全く変わらない」
と感じますし、
「リリース直後の膨らみ、伸び、美しさは以前より増している」
と感じます。
まぁ、ベースキュヴェのマコン=シェントレで充分美味しいので・・ある意味、ワイン屋泣かせな存在かもしれません。
2019年は2015年ものにも似た健康美に加え、そのナチュラルな膨らみ、柔らかさが以前のものよりも増している点で、より高い評価をすべきじゃないかと思います。是非ご検討くださいませ。
 ■生産者情報
■生産者情報ヴェルジッソンの岩の近くに位置するバロー・エステートは、ワインへの情熱を受け継いでいます。世代を超えて受け継がれてきた共通の目標は、常に独自のノウハウとテロワールを促進することでした。「うまく働くために、あなたはあなたの時間を節約する」というモットーで、不動産はそのルーツを維持しながらそれ自身を更新することができました。
テロワール
ソルトレとヴェルジッソンの象徴的な岩に囲まれたバローエステートは、フランスのグランドサイトに分類される村にあります。モルヴァンに裏打ちされた古いラグーンに囲まれたこの場所で提供される岩は、古代のサンゴ礁で構成されています。土壌には、石灰岩のガラ場、アグリフォイド石灰岩、斑入りの粘土の3つの主要なタイプがあります。それぞれの土壌は特別な注意と特定の文化を誘発します。バローエステートは、その豊かさと多様性を最もよく表現するために、このテロワールを維持しています。
ぶどうの木
有機農法からインスピレーションを得て職人技で栽培されたこのエステートのブドウの木は、丁寧に作られています。彼らのGuyot-Pushardサイズは、植物の樹液の流れを尊重します。
ブドウ園と土壌を尊重するために、実行される処理は硫黄と硫酸銅のみに基づいています。最近の古いブドウの木では、機械化せずに作業が行われています。可能な限り完全で健康的なブドウを得るために、収穫も手動で行われるため、酸化が制限されます。
ドメーヌ・バローの歴史
1905年
ジャンマリーとマリー・バロー
バロー家のワインの歴史は1905年に始まりました。読み方と数え方を知っていたジャンマリーバローは、小作人として良い場所を見つけ、ヴェルジッソンに定住しました。彼の安定した収入により、彼はお金を節約し、1912年にバロー邸の最初の区画である妻のマリーと一緒に買収することができました。
1922年
ジョセフとマーガレット・バロー
10年後、ジョセフとマーガレットバローが引き継ぎます。大胆な男であり、真の先見の明があるジョセフは、作付けの良い区画を見つける方法を知っているため、ブドウの木を植えるために多数の牧草地を取得します。優れた起業家として、彼はカフェやレストランに売ることの価値をすぐに理解しました。1930年代の終わりに、彼はこの地所でワインを瓶詰めすることを最初に決めた人の1人でした。最初のキュヴェ「LesCrays」は1947年に登場しました。
1959年
アンリとモニーク・バロー
1959年、アンリバローは、フュイセ出身の妻モニークと一緒に家族の邸宅で働き始めました。「うまく働くために、あなたはあなたの時間を節約する」という不動産のモットーの起源で、良い地主であり思慮深い人であるアンリは、彼の努力を数えずに不動産を維持します。1971年、AOCサンヴェランが創設されました。アペラシオン「lesPommards」の区画は、1978年に最初の瓶詰めになります。
1979年
ダニエルとマーティン・バロー
バロー家の第4世代は、1979年に定住し、不動産の一部を相続しました。ダニエルと妻のマルティーヌは、祖父と同じ意志と現代性を持って不動産を開発し、マコンヴェルジッソンとサンヴェラン「エンクレッシュ」と一緒にボトルでのマーケティングを開始しました。1990年に、彼らは家とClosdelaVerchereを買収しました。略語DBがラベルに表示されます。
ワインと環境に情熱を注ぐダニエル・バローは、テロワールの保護に取り組むGEST deBeaune協会の会員です。
2006年と2015年
ジュリアンとアナイス・バロー
彼らの息子であるジュリアンは、2006年に不動産の仕事を始め、家族の技術を習得しました。ジュリアンは、たとえばすべての区画を耕すことで、不動産の職人文化を強調することにしました。現在、ワイン造りは彼の独占的な領域であり、彼も家族のノウハウに従って運営していますが、彼はそれを開発することもできました(偉大なヴィンテージのより長い醸造)。アナイスは2015年に兄に加わり、不動産のすべての管理および商業部分を管理しました。
彼らは一緒に、将来が彼らに要求するかもしれない変化を心に留めながら、テロワールの伝統と尊敬を永続させたいと思っています。
-----
「2018年のダニエル・エ・ジュリアン・バローは、ディディエ・ダグノー風のクリスタルなミネラリティを手に入れた!」
このところのダニエル・バローのナチュラル化は止まりません。年を追う毎に・・美しくなって行きます。
親父さんの頃は素晴らしい果実の風味で、シャルドネの美味しさを見事に表現していました。かのPKさんも、ブルゴーニュ・シャルドネのTOP100に、ダニエル・バローのプイィ=フュイッセを2アイテムも入れていたほどです。
Julien et Anais Barraud
2018年もののバローは、そんな素晴らしい果実の風味も・・実はたっぷりあるんですが、それよりも特筆すべきは、クリスタルのようなミネラリティが膨大な果実の風味を分厚くコーティングしていることでしょう。・・そう、
「もしかして・・ディディエ・ダグノーを目指してる?」
んじゃないか?・・と思えるほど、ミネラリティのクオリティ、量が半端無く増えているんですね。
ですので・・そういう意味においては、メディア評価はむしろ下がっています。物凄い出来の2018年アン・ビュランV.V.でさえ、93点だそうです・・。まぁ、noisy としましては、ハッキリ・・否定させていただきます。「そんな訳は無いす」・・ちゃんと評価してください。
珠玉の「スュール・ラ・ロシュ」は、白眉アン・ビュランに次ぐ仕上がりです。この位のミネラリティの方がむしろ判りやすいでしょう。
そしてまぁ・・それなりの点が付いているアリアンスV.はティム・アトキンさんが91ポイントです。でももう、これで充分!と言えるほどに素晴らしいですし、サン=ヴェラン・アン・クレシェとマコン・シェントレに至っては、
「プイィ=フュイッセ群にそんな低い点を付けちゃったら・・この2アイテム、どう評価するの?」
と思えるほどです。案の定、ネットを検索してみても出て来ません・・。
ですが、2018年もののバローは、どのワインも物凄いミネラリティが豊富な果実をコーティングしていますから、
「つやつや、すべすべのテクスチュアからピュアでナチュラルな果実が漏れてくる、素晴らしいスタイル!」
に仕上がっています。どんどん・・ディディエ・ダグノーに近寄って来ていると感じています。素晴らしい出来でした!
勿論ですが、アン・ビュラン2018は、そんなレベルでは有りません。今回は非常にリーズナブルなので・・いや、少し早いですけど飲んでみていただけたら、noisy の言っている意味が判ると思いますよ。マコン=シェントレでも充分納得の美味しさと美しさを感じていただけるでしょう。超お勧めします!
-----
● 何しろ昨今は、あの・・「赤ワインが基本」だったリアルワインガイドも、だいぶ白ワインを掲載するようになったので、あれだけ
「ダニエル・バローは旨くて安くて素晴らしい!」
と20年近くにも渡って公言し続けてようやっと・・今の状況なんですが、リアルがバローを掲載し始め、今までブルゴーニュ・ピノにしか興味の無かった方々もシャルドネの旨さに気付き始めたのか、
「ダニエル・バローは・・・ラシーヌさんのはいつ入りますか?」
などとお尋ねの電話やメールをいただくようになりました。(基本、電話はお断りしてるんですが・・全ての仕事が中断になっちゃいますんで・・)
で、高い評価がリアルに載ったりすると・・・それも2013年のように極端に収量が低い年だと・・本当に困っちゃいます。
何しろ、アン・ビュランV.V.の入荷ががこんなに少なかったことは今まで有ったでしょうか・・アン・ビュランだけじゃなく、レ・クレもラ・ロシュも全てバラでしか入ってません。
なので、申し訳有りませんが、ダニエル・バロー今までずっと毎年ご購入になられていらっしゃるお客様にも渡らないかもしれません。ご容赦ください。
━━━━━
毎年のように全アイテムをテイスティングしてきましたが、一昨年などはとても少量でしたので、テイスティングを断念せざるを得ない状況でした。
ですが2012年もの・・・価格はそれなりに上がった・・・いや、昔に戻っただけ・・・とも言えますが、数量は結構戴けたんですね。なので、2012年は全アイテムのテイスティングをさせていただきました!そしてもう・・・ビックリです!
全アイテムのテイスティングは出来なくとも、幾つかのワインは飲んできましたので、その傾向は理解しているつもりです。しかも90年代前半から連続して飲んでおりますので・・・そんなnoisy が2012年のバローのワインに感じたことは・・
「近年、経験したことの無い凄い仕上がり!もしかするとダニエル・バローの史上最高のワインになった!」
まず、低価格~ボリュームラインクラスの格上げの美味しさ・・が言えると思います。マコン、サン=ヴェランとも・・今までに無いようなポテンシャルの高さを感じました。そして、マコンはサン=ヴェランを、サン=ヴェランはプイィ=フイッセを喰ってしまいそうなアイテムが有り、完全にクラス越えをしているんです。
そしてフラッグ・シップのアン・ビュランは・・・モンラッシェクラスのビロードのテクスチュアを持つミネラリティでした・・・どれだけ伸ばしても伸ばしきれない・・どこまでも伸張して行くだけの目の細かさを持っていました。
勿論、各アイテム・・・素晴らしいです!ダニエル・バロー史上、きっと最高の仕上がりになったと思える2012年は、必ず飲んでいただきたいと思います。皆さんの・・
「えっ?・・・」
と驚く顔が見たい・・・(^^;; ではどうぞよろしくお願いいたします。
以前ののコラムより転載です。
● 2009年ダニエル・バロー(不)完全ガイド
・・・(不)と入っているのは、幾つかのキュヴェのテイスティングが量的に考えて不可能だったからです。また、プイィ=フュイッセ・ラ・ロシュの入荷は有りませんでした。
結論
良いとアナウンスされた2009年ですが、バローにとっては・・・いや、マコネーの生産者にとっては、普通のヴィンテージなのかもしれません。むしろ、余り良くなかったのかもしれないとさえ思えます。その中で、バローは最善の策を講じ、素晴らしい品質になったのだと理解しています。
2009年のダニエル・バローは全くの贅肉無し、残糖分無し、実に筋肉質でエレガントなマコネーに仕上がっている!・・と言えます。
すなわち、マッチョでは無い、エレガントなムルソーのようなワインで、甘みと云う、人間で言えば「脂肪」のようなものを全く持っていません。これは全てのキュヴェに言えることです。本来は豪奢で、少し残った残糖分が、こってりとした、もしくは甘みの有るフルーツを連想させるものです。ところが、2009年はそうではない・・んです。すべてはエキスへと転化されていますので、今までのような、簡単にいつでも開けて美味しいマコネーでは無いです。きちんと休養させ、揺らさないように抜栓し、エキスを開かせるような飲み方が要求されるかと思います。
それでも、一連のバローのワインは、その隠し事の無いエレガントさが素晴らしいです。贅肉無し、甘み無しのプイィ=フュイッセですが、2008年の仕上がりを考えても、
「ダニエル・バローもエレガント路線に変更か?」
との思いを強くせざるを得ません。まあ、コント・ラフォンのように・・・そっちに行くのかもしれませんよ。
実は昨年、2008年のバローでは、こんなことを書いていました。
━━━━━
ある意味、2008年は、ダニエル・バローの転換となるヴィンテージになったかもしれません。それは、マイナスの方向に働くことはまず考えられず、さらに偉大なシャルドネを目指しての転換期です。本当に素晴らしい辛口のシャルドネに、実は余分な肉は必要無いのです。しかし、本当に素晴らしい辛口のシャルドネは、本当は甘いのです。でも、その甘さは・・・糖分によるものでは無い。エキスによるものです。その意味においては、2008年のダニエル・バローは、自身の過去に有り得なかったバランスのシャルドネを造り出したのです。
最低5年・・・待ってください。3~6千円のシャルドネに5年待てとは・・・なかなか言い辛いです。しかし、途方も無い可能性を秘めたワインで有る事に目を背ける訳には行かないんです。素晴らしい辛口のシャルドネとは、糖分に頼らないポテンシャルを持った甘いワインなんだと・・・理解していれば、この2008年のバローに挑戦してみることに異論は無いはずです。
やはり、アン・ビュランは凄いですし、ラ・ロシュ(プイィ=フュイッセ)もポテンシャルがビシビシ来ます。しかし、やはり今はちょっと厳しい・・・。本当のことを言うならば、あと1~3ケ月、瓶による熟成をしてから出荷すべきでした。そうすれば新酒由来の渋みも消え、綺麗な状態になったはずです。しかし、バローさんとしてみれば、そんな経験は今までにほぼ無かったはず・・・。まあ、我々が判っていれば良いんですが、人によっては、
「駄目・・」
と、早い結論をしてしまうかもしれません。
でもこのバロー2008年、ポテンシャルに掛けて欲しいと思います。2015年にはきっとそれなりの結論が出ているでしょう。焦らず、飲めるものから試し、上級キュヴェは寝かせてください。是非ともご検討くださいね。
━━━━━
自分でこんなことを書いていたとは・・・すっかり忘れてました・・・(^^;;
でも、2009年のダニエル・バローは、お手軽さは無くなりましたが、ワイン本来の美しさが見えてきたとも言えます。是非ともしっかり休めてお楽しみください!お奨めします!
 エージェント情報
エージェント情報マコン・ヴィラージュ、サン・ヴェラン、プュイ・フィッセの3つの地区でワインを造っている、コート・シャロネーズを代表する造り手・ダニエル・エ・マルティーヌ・バロー。ロバート・パーカーも「コート・ドゥ・ボーヌのグラン・クリュの最も優れたワインと同等か、それを凌ぐ、最上級のワインをつくっている。」と高く評価している。
栽培 ビオロジック
自社畑面積6.7ha
醸造完熟したブドウを収穫した後、澱の上に15ヶ月間そのままにしておき、清澄も濾過もせず、豊かな味わいのワインに仕上げている。
●
2023 Macon-Chaintre les Pierres Polies
マコン=シャントレ・レ・ピエール・ポリ
【過去一番と評価した2022年ものを、いとも簡単に超えて来た2023年ものです!・・素晴らしい!・・豊満さにキリリとした切れのある表情!・・もはや以前のピエール・ポリでは有りません!】
 因みに上代設定は¥4500-です。昨年と一緒ですが、仕入れ価格は10%以上上がってますので、この価格は Noisy wine には非常にキツイです。でも、「導入」のワインなので、ここは頑張って値を下げてご案内させていただきますが、しばらく後で上げさせていただくかもしれませんのでお早めにお願いいたします。
因みに上代設定は¥4500-です。昨年と一緒ですが、仕入れ価格は10%以上上がってますので、この価格は Noisy wine には非常にキツイです。でも、「導入」のワインなので、ここは頑張って値を下げてご案内させていただきますが、しばらく後で上げさせていただくかもしれませんのでお早めにお願いいたします。いや~・・もはや・・このグラスの佇まいからして、今までのピエール・ポリとは違うでしょう?・・2022年ものまではまだどこか、
「一瞬シャバい?」
と思わせるような色彩感覚が有ります。
しかし、2023年ものは・・もはや「マコン、マコン=ヴィラージュであり得ず!」と書いてあるようなグラデュエーションじゃないですか!・・もう、グラスに顔を寄せただけで・・
「うおっ!」
と唸ってしまいます。
あ、どうでも良いことかもしれませんが、どうでも良いことが気になるボクの悪いクセ・・かもしれません・・
「2021年ものは右、2022年ものは左、2023年ものは・・中央で、上級キュヴェの上のクラスと同じデザイン!」
になっているのをお気づきになられたでしょうか。
そう・・DB(ドメーヌ・バロー)のマークですよ。2021年ものまではずっと右でした。2022年ものでいきなり左に移動し、2023年ものは中央に鎮座しているんですね。これって・・
「きっと何かを言いたいんじゃないの?」
と・・右京さん的に思う訳です・・もっとも何を言いたいのかまではハッキリしませんが、
「スッゴイ上手く出来た!」
と言うことに近いんじゃないかと思うんですね・・もしくは、1990年植樹と言うことで、V.V.と言えるような樹にもなってきましたし・・。
 アロマは自然派的にニュートラルでスピードとふんわり感が有るものです。尖がった部分は無く、マッタリとして柑橘果実が複雑性を帯びて感じられます。
アロマは自然派的にニュートラルでスピードとふんわり感が有るものです。尖がった部分は無く、マッタリとして柑橘果実が複雑性を帯びて感じられます。黒糖のような・・ややビターさと蜜っぽい甘さ・粘度・・黒蜜かなぁ?・・ちょっと黒糖焼酎のようなニュアンスを含む、滑らかな中にも非常に心地良い飲み終わりが有るんですが、これがこのワインの・・
「味わいの幅の広さ、深さ」
を増大しているように思います。
熟した柑橘、果実、石、岩、ハーブなど、有機物、無機物問わずに・・エレガンスを保ちつつも饒舌です。ほんのりと膨らみながらビターさを感じさせる甘く無い黒糖、余韻にはその黒糖が弾けて粉々になるようなイメージで・・余韻がさらに拡がりつつ収束して行きます。
昔のピエール・ポリのように、フレッシュで、豊満さも有りつつもどこか可憐さをも持ち合わせていた味わいとは、全く同一の畑ものとは思えないような高質な仕上がりを感じます。
今飲んでも非常に美味しく、この先1~2年に渡って上昇し続けるでしょう。
「いや・・めっちゃ美味しい!・・マコンの範疇を飛び出した!?」
と言いたいマコン=シェントレ・レ・ピエール・ポリ2023年です!
今はもう扱わなくなってしまいましたが、ヴェルジェのマコン=ピエール・クロが結構好きで、しかもリーズナブルだったんですね。でも・・ん~・・高いし質的に上昇して行く感じはしないし、良い葡萄が採れると上級キュヴェを造ってしまうから、良い年は普通で、イマイチの年は下がる・・のが判って止めてしまいました。そこから言ったら・・
「バローはほぼ常に上昇気流!」
です。例外として「植え替え」によるポテンシャルダウンは在りましたが、価格を下げましたから・・素晴らしいドメーヌです。ぜひ飲んでみてください。滅茶旨い!です!
以下は以前のレヴューです。
-----【ドライ!・・エキスの集中!・・半端無いミネラリティとの統合、バランスが素晴らしいです!過去一間違い無し!・・価格も頑張らせていただきました!】
 ユーロ高の影響は半端無く、ワインの価格にもろに反映していますが、この・・長く愛されてきたマコン=シェントレも、
ユーロ高の影響は半端無く、ワインの価格にもろに反映していますが、この・・長く愛されてきたマコン=シェントレも、「ついに上代4500円」
と言う・・物凄い時代になってしまいました。
流石にそれは急過ぎる・・と感じまして、何とかお願いして・・
「・・下代を下げていただいた・・」
んですね。
なのでこの価格が成り立っています。なのでサンリバティーさんのご協力に感謝して、ぜひ・・飲んでみてくださいね。安いですし・・
因みに2021年ものは新着で「3190円」ですから、
「たったの?・・160円アップ」
です。
つまり、
「1ユーロ以下しか上がって無い」
んですよ。今や165円ほどまでユーロ円はユーロが強く、円が安いです。まぁ、
「マイナス金利をゼロ金利にしただけ」
で終わっちゃいましたから・・この間の某総裁の発表。残念です。
 ですがこの色!・・
ですがこの色!・・「絶、セクシー!」
でしょう?
そうなんですよ・・過去最高の出来、間違い無しです。
マコン=ヴィラージュの村名の名乗り+畑名の名乗りでしかないこのピエール・ポリですが、
「上のクラスのサン=ヴェランも真っ青!」
になるほどの素晴らしい出来です。と言いますか、2022年のドメーヌ・バローのワインの・・
「物凄い密度!」
は、あの100点満点をたたき出しているクリオ=バタールを造るあの人と、テイスティング時にイメージがちょっと被ってしまうほどでした。
その上で、マンモスなミネラリティと、少し有るとより惹きつけられるグラ、ねっとり感が有り、果実・柑橘も嫌味無く冷涼で、蜜っぽく成長して行きそうな密度の高いエキスの集中さも有ります。
「・・げっ・・ピエール・ポリがこれだけ凄いと、他のは・・ヤバい出来か、それとも?」
などと考えてしまい、もし上のキュヴェがイマイチだったらどうしよう・・と・・(^^;; あ、どうしてもテイスティングは下のクラスからやりますので、心配でした・・が杞憂に終わったんですね。
2021年ものは元より、2020年もののグラスの写真とも、ぜひ比較してみてください。照り、涙、ミネラルの感じ・・どうでしょう?・・過去最高も嘘じゃないように思えると思います。ぜひ飲んでみてください。めっちゃ美味しいです!!
以下は以前のレヴューです。
-----
【旨いです!・・2020年の濃密なスタイルから、健康的で細やかな表情がナチュラルに、繊細に見えるスタイルへ変貌しています!。価格も凄く頑張りました・・】
 「価格を頑張って・・これなの?」
「価格を頑張って・・これなの?」そう思われる方もいらっしゃるかもしれませんね。以前は2千円台中盤でしたから・・まぁ、上がっても3千円だろうと踏まれていたんじゃないかとも想像されますしね。
ですが、泣きたくなるくらいの利益率です。相当頑張った価格なんですね・・なのでご容赦いただきたい・・。まぁ、ヘタをするとインポーターさんに怒られるかもしれない・・だって、
「ある意味、昨年の2020年ものの販売価格と今回の2021年ものの仕入れ価格に差がほぼ無い・・」
それ位、仕入れ価格が上がってしまっています。
ですが味わいは素晴らしいです。このところのドメーヌ・バローは、ジュリアンさんが頑張っているんだと思いますが、
「よりナチュラルに・・余分な付け香はしない・・」
と言う、葡萄そのもの、もしくはワイン本来の美味しさを生かす造りに徹するようになって来ています。それを強く感じます。
ですから、香りのふくよかさや柔らかさ、スピードの速さが素晴らしく、優しくも柔らかなミネラリティを含んだアロマがノーズに飛び込んで来ます。
 一段とミネラリティが洗練されたようで、ちょっと無理したマコンの少しコッテリしているが酸が乏しい感じ・・がゼロ。どこまでも自然で有りながら、マコンのミネラリティ溢れる大地のニュアンスを感じさせ、また2021年の健康的な葡萄由来の柑橘のニュアンスに満たされている感覚です。
一段とミネラリティが洗練されたようで、ちょっと無理したマコンの少しコッテリしているが酸が乏しい感じ・・がゼロ。どこまでも自然で有りながら、マコンのミネラリティ溢れる大地のニュアンスを感じさせ、また2021年の健康的な葡萄由来の柑橘のニュアンスに満たされている感覚です。より深い黄色をしている2020年もののグラスの写真と比較してみると良く判ると思います。2020年ものも、
「・・いや~・・ずいぶんナチュールっぽくなって来たなぁ・・」
と感じたものですが、2021年ものは・・明らかに、
「さらにSo2が少ないしなやかで繊細な味わい」
になって来ています。
その上で、
「アヴァンギャルドな味わいに没しない・・ディテールを壊さない美しい造り!」
を感じます。
日本もようやく「大企業は賃上げ」で世界標準の収入を目指す時代に入って来た・・そんな気がします。まぁ・・日本ではラーメンは1000円ほどですが、海外では3000円が当たり前です。つまり・・ちょっと乱暴では有りますが、
「日本の物価は海外の1/3」
ですから、インバウンドは好調でしょうし、徐々に製造業も日本での製造に回帰して行くんじゃないかと思います。もっともその最中にも様々な問題をクリアにしないとなりませんが、是非とも優秀な人材を取り立てて、正しい方向に旗を振っていただきたいものです。是非ご検討くださいませ!超お勧めします!
以下は以前のレヴューです。
-----
【カリテ・プリ大賞はこれでしょう!・・これほどのリーズナブルな高級シャルドネは他に見当たりません!】
 ピュアでミネラリティの高い高級シャルドネです。しかも非常にリーズナブルなので、毎年数多く販売させていただいています。
ピュアでミネラリティの高い高級シャルドネです。しかも非常にリーズナブルなので、毎年数多く販売させていただいています。ですが・・このところの世界情勢で、色々と変化が生まれています。
勿論、温暖化も影響も有ります。今までには余り無かった気候変動が有り、2021年などは平均で対比20%の生産・・全く造れなかった地域も有る訳です。
それに加え、新型コロナウイルスの影響で、色々なモノが不足しています。さらにはウクライナ侵攻..ですね。
「コンテナが無い!」
から送れない・・送ってもらえない・・などと言うことが起きています。
なので、、Noisy wine も、例年に無く、
「入荷の無い時期が時折有る」
ことと、
「すべてのワインの入荷時期が一緒!」
・・・つまり、船が一緒なんですよ・・。だからもう・・荷が入って来る時は、「しっちゃかめっちゃか」に..それが無い時は、
「次の新着・・どうしよ・・」
と頭を悩ませるようになってしまった訳です。
 でも、いつものように素晴らしいバローのマコン=シャントレが、いつもより美味しい!・・と感じられると元気が出ますよ。ウクライナの悲惨な状況を見るにつけ、澱んだ気持ちになってしまいます。
でも、いつものように素晴らしいバローのマコン=シャントレが、いつもより美味しい!・・と感じられると元気が出ますよ。ウクライナの悲惨な状況を見るにつけ、澱んだ気持ちになってしまいます。それでも店での仕事を終え、日が変わってから家にたどりついて、またそこから毎日のようにテイスティングをして・・の繰り返しですが、そのワインが美味しいと判断できると、そんな暗い気持ちも吹き飛ぶんですね・・そんな暮らしを四半世紀も続けています。
そしてこのマコン=シャントレも、四半世紀ほどのお付き合いになるはず・・です。始めた頃は・・
「千何百円・・」
だったと思います。
でも・・今もこんな価格・・。ちょっとあり得ないような気もしますが、
「その頃よりも確実に旨い!」
のは間違い無いですし、
「毎年少しずつ異なる美味しさを見せてくれる!」
んです。
2020年は過去最高だと思います。でもタイミング的に・・少し硬めですから、2~3週間休ませていただくと、グッと伸びてくると思います。是非飲んでみて下さい!超お勧めします!
以下は以前のレヴューです。
-----
【どなたが飲んでも美味しいと言っていただけると思います。高級シャルドネの美しい姿!ブルゴーニュ南部ながらも冷ややかな表情のエレガンスが素晴らしいです!】
 未だにこの位の価格でご紹介できるのですから有難いものです。以前は・・と言っても10~20年も前ですが、このピエール・ポリも今ほどの「強い引き」は無かったように思います。アン・ビュランV.V.とクレイV.V.はあっという間に完売していました。
未だにこの位の価格でご紹介できるのですから有難いものです。以前は・・と言っても10~20年も前ですが、このピエール・ポリも今ほどの「強い引き」は無かったように思います。アン・ビュランV.V.とクレイV.V.はあっという間に完売していました。この10数年の間にクレイは植え替えでV.V.表記が無くなり、2本柱の地位を追われましたが、代わりに「ラ・ロシュ」がアン・ビュランV.V.と並び称されるようになった訳ですね。
確かにアン・ビュランは美味しいし素晴らしいし・・凄いです。でもやはり、「すぐ飲みたい!」と言う要望には応えきれない・・それだけの熟成期待の分がポテンシャルに備わっているからです。なのでむしろ、
「アリアンスの方がさっさと美味しい!」
訳ですし、
「サン=ヴェラン・アン・クレシェがリリース直後から滅茶美味しい!」
ですし、
「・・まぁ・・言っちゃえばピエール・ポリでも充分・・」
と思えてしまう部分も有る訳です。
2019年ものはやはり「健康美」です。まぁ、色々有ったには違い無い2019年だとは言え、非常に美しく、無駄のない・・均整の取れたボディをしています。甘く無く、しかし柑橘の美しいフレーヴァーと柔らかなミネラリティが「すっ」と立ち昇ります。
やはり「シャルドネ好き」は多いですが、どうしても高価になってしまいがちなところ、
「ドメーヌ・バローが有る!」
ので助かっている訳ですね。
ブルゴーニュ最南端です。ローヌと一部重なっている地域です・・が、
「全く暑苦しくない」
冷ややかな果実酸と、やや強い日照による、ほんのりとした「オイリーさ」が特徴です。是非飲んでみて下さい。お勧めします!
以下は以前のレヴューです。
-----
【デイリー価格の高級シャルドネ!・・実に美味しいです!】
 もう・これは常備しておくべきワインでしょう。最もリーズナブルなマコン=シェントレ・・・村名格のシャルドネですが、一般に販売されているマコン=何とかとは、まったく異なるワインです。
もう・これは常備しておくべきワインでしょう。最もリーズナブルなマコン=シェントレ・・・村名格のシャルドネですが、一般に販売されているマコン=何とかとは、まったく異なるワインです。2018年のバローのワイン、全てに言えることは、やはり膨大なガラス、クリスタル風のミネラリティが、冷涼で豊かで凝縮した果実・柑橘をコーティングしていると言うことですが、このマコン=シェントレ2018にも同じことが言えます。
ですので・・いや、この言葉、「サン=ヴェラン・アン・クレシェ2018」のコラムにも書いたので言いたくないんですが・・ある意味、このマコン=シェントレで充分・・美味しさが堪能できてしまうんですね。
そして、その先を探って行っても、確かにまだまだ知らない存在が有ることに新たに気付くんです。だから飲んでいても楽しいし、何より、全くぐだぐだっとした部分が無いので、非常に心地良いんですね。色合いも淡い緑が入った美しい黄色です。
こんなにリーズナブルで良いんだろうか・・と思ってしまいます。2018年のダニエル・バロー、是非飲んでみていただきたいと思います。超お勧めです!
以下は以前のレヴューです。
-----
【定番のリーズナブルワインですが、ベースのワインがこんなに素晴らしいとは!・・と是非驚いてください!】--以前のコメントを使用しています。
 ブルゴーニュのデイリークラスには非常に厳しい・・(^^;; リアルワインガイドも、しっかりポテンシャル点90ポイントを付けているマコン=シェントレです。
ブルゴーニュのデイリークラスには非常に厳しい・・(^^;; リアルワインガイドも、しっかりポテンシャル点90ポイントを付けているマコン=シェントレです。特徴はほんのりと芳醇ながらも美しい酸、ミネラリティもたっぷりで非常に瑞々しい美味しさが有る・・と言うところでしょう。濃密に仕上げることは、温暖化と言われる現在においては特別に難しいことではないと思われますが、
「そこにフィネスが有るか?エレガンスはどうか?」
と言う部分においては、非常に苦労してきたのがマコン各村なんですね。PKさんがシャルドネを貶める言葉として常用していたのが、
「マコンじゃないんだから・・」
でした。言ってしまえば、
「下品」
の代名詞みたいな時代が有った訳です。勿論ですがそこには、努力を続けるドメーヌも多く有り、その代表格がダニエル・バローだった訳です。「シャルドネに 割りばし入れて マコン=ヴィラージュ」などと樽臭いマコン=ヴィラージュを揶揄していた時代が有ったんですね。
そんなマコン=ヴィラージュとは全く異なるのがこのシェントレです。やっぱり旨いですね・・いつもは、タイミング的にはもっと早い時期にテイスティングしていますので、完全には落ち着いていなかった訳です。今回はサンリバティーさんが倉庫に入れっぱなしでオファーを忘れていた?ために、半年以上遅れてのご案内になっています。
でもそんなタイミングなので、しっかり落ち着いてるんですね~・・。リアルワインガイド第62号は2018年4月のテイスティングですから・・そろそろ1年近くで、その位のズレが有ります。
「このワイン、こんなにおいしかったっけ?」
と徳丸さんは書かれていますが・・
「美味しかったですよ」
とお答えしておきましょう。何せnoisy はこのワイン、もう・・どうだろ、20年近く欠かさずに飲んでますから・・。
しかしながらやはり変遷は有りますよ。もっと樽っぽかったし・・いや、樹の若さも感じたかな・・フレッシュだが凝縮感に欠けた印象が最初の頃だったと思います。でも・・千円台だったですしね・・充分にリーズナブルでした。この素晴らしいバランスを見せるシャルドネがこのプライスですから・・しかも、
「アドヴォケイトが選ぶブルゴーニュを代表する生産者」
で有り、
「ブルゴーニュ・シャルドネの傑作」
として、プイイ=フュイッセ・アン・ビュランV.V.とレ・クレV.V.が選ばれている位ですから(レ・クレは改植したため現在はV.V.表記無し)。
下から上のクラスまで、見事に美味しいのがバローです。言いたくないが・・
「マコン・シェントレで充分旨い・・」
ので困ります。是非飲んでみてください!お勧めします!
以下は以前のレヴューです。
━━━━━
【年々、瑞々しさを増しています!滅茶美味しいです!】
 滅茶苦茶瑞々しく、健康的で、伸びの良いワインです。しかも、
滅茶苦茶瑞々しく、健康的で、伸びの良いワインです。しかも、「ん?マコン・・?」
と思えるような冷涼感付きです。
さらには、
「・・これでマコン?」
と思えるような、コート・ド・ボーヌ的なエレガンスの有る果実の風味なんですよ。
価格もリーズナブルですし、これは売れるんじゃないかと!・・コンディションの良さも抜群です。
リアルワインガイド第58号は、ついに今までの最高ポテンシャル点、89+点を付けましたね。noisy的にはそれだとやや低いかな・・と思いますが・・ここはハッキリ、90点付けるべきでしょう。それだけのパフォーマンスをしてくれます。
年々増してきた正当にナチュラルな美味しさ、是非感じてみてください。超お勧めです!
以下は昨年までのこのワインのレヴューです。
━━━━━
【もう単なるマコンとは呼べない!素晴らしい味わいです!】
 いつも安定して美味しいマコン=シャントレ・レ・ピエール・ポリです。もうお馴染みですね。
いつも安定して美味しいマコン=シャントレ・レ・ピエール・ポリです。もうお馴染みですね。ですが、2014年ものの美しい姿はまた2013年の健全さ、バローのベンチマーク的存在を超えて美味しいと感じてしまいました。
もっとも、昨今は自然派と言うの括りの解釈も非常に難しいです。
「自然酵母(畑に自生しているもの、果皮付着)じゃなくて自然派を名乗れるか?」
と言うような基本的なものから、
「ビオロジック + So2の使用有りき」
と言う、既存のスタンスではヴァン・ナチュールとしては不足している・・・と言う考えもあります。
その辺りはとても微妙な問題を含んでいまして、まぁ、いつも言っていますが最終的は、
「醸造結果としての揮発酸値」
に掛かってくると思うんですね。
ナチュラルな畑仕事、ナチュラルな醸造の結果として、ナチュラルなワインが仕上がる・・これが理想です。しかしながら時に、もしくは多くの場合、
「ナチュラルな畑仕事、ナチュラルな醸造の結果として揮発酸値の上昇を招く」
ことにつながり兼ねない状況が見られる訳です。
まぁ、極低レベルの揮発酸値の話しでは無いんですね。ワインのピュアな味わいを損なわない程度の揮発酸値であれば問題は無いと言えます。しかしながら、それはかなり上手く行った場合・・になります。
「ん、私はSo2は使用しないよ!」
と言う最初からのスタンスは非常に綺麗な言葉では有ると言えますが、仕上がったワインの揮発酸値が高いとすると
「唇寒し」
と判断されてしまうかもしれません。
確かに、極わずかの方々は、So2を全く使用せずともピュアなワインを造り上げることが出来ると思います。しかしながら、ほとんどの造り手は、
「最上の葡萄が収穫でき、最上の仕事が出来たときにピュアなワインに仕上げられる」
と言えるかな・・と言うのが、noisy が現在感じていることです。
リアルワインガイドは2013年ものよりも2014年ものをより高い評点にしていますね。理解できる部分では有ります。でもまぁ、
「どちらも相変わらず旨い。敢えて言えば、2014年ものがより凝縮感に長けているかもしれない。」
ですね。
何せ、どうでしょうね・・覚えてませんが、どれだけ長くダニエル・バローのワインを毎年飲み続けて来たか・・・。90年台中頃から毎年必ず飲んでますから・・体の何パーセントかはダニエル・バローのシャルドネでできているかもしれませんしね・・そりゃ無いか。
このシャントレの良いのは、甘く無いし、ミネラルは重く無く軽やかでビッシリ、適度な中域のふくよかさ、充実と余韻の長さ、ダレない酸の美しさが寄与していると思います。揮発酸の存在を感じたことなど・・ございませんしね。
価格も実にリーズナブルです。ワイン屋として困った時の「ダニエル・バロー頼み」も有りがたいものです。何せ、
「美味しく無い!」
「合わない!」
とは、まず言われないですから・・。しかも、このシャントレは、二次発酵のニュアンスが強く出ないので、やや匂いのキツイ魚介にも行ける可能性が大きいんですね。・・まぁそんな場合、安全策を考えるなら二次発酵無しのワインを第一にしますが・
柑橘系果実のしっかり出た美味しい・・甘く無い、しっかりシャルドネです。是非ご検討くださいませ!
以下は以前のコメントです。
━━━━━
いや~・・ピエール・ポリで充分旨いんですが、ヴェルジッソン・ラ・ロシュの石のニュアンス、マコン=フュイッセのクラス超えのポテンシャルも捨てがたい・・・選ぶのは難しいです!
2012マコン=シャントレ・レ・ピエール・ポリ
わずかに樽、凝縮感がわずかに甘みをもたらす。粘性ある滑らかなテクスチュアと程好いスパイス感。軽めながらたっぷりあるミネラリティ。ドライな味筋ながらしっかりと押してくる素晴らしい味わい。
2011&2012 マコン=ヴェルジッソン・ラ・ロシュ
2012は2011よりもかなりドライ・・・2011年は荒れが収まり、熟しつつ有って、むしろ甘みさえ感じる滑らかさ。出来はほぼ同等か?とても美しくバランスの良い仕上がり。締まったミネラリティ・・・単純に美味しいが、岩、石のツルッとしたミネラリティが特徴的。リンゴや洋梨、柑橘。両方を比較すると、渋みと苦味が味幅、土台を作っているのでどちらも必要なものだと判る。リーズナブルなワイン。
2012マコン=フュイッセ
美しい淡い黄色。光り輝いている。格上の味わいはすぐに判るほどのネットリ感とエレガンス。中域が密で味わいの幅が広い。フルーツ表現の精度が高く、よりエレガンスを感じさせているようだ。
ポリはとっても美味しいです!こんなに美味しくなって・・良いのかな?・・と思うほど、格上げされたように思います。価格的にはヴェルジッソン・ラ・ロシュが上ですが、現状の美味しさはマコン=フュイッセに軍配。マコン=フュイッセは・・・マコンじゃ無いす!・・いや、マコンを超えてます。ヴェルジッソン・ラ・ロシュの石、岩のガチっとしたミネラリティが素晴らしい・・・そして2011年は熟し始めていて、凄く纏まりが出てきました!是非ご検討いただきたい4アイテムです。一推し!
●
2023 Saint-Veran Arpege
サン=ヴェラン・アルページュ
【深く熱量を多分に放出していた以前のアルページュとは、また異なった印象・・まさに、「アルペジオ」的な響きを持った見事な表情です。】
 noisy もその昔はギター奏者でしたから、フォーク系のギターを持つシュチュエーションで必要ならば、アルペジオをスリーフィンガーで・・などとやっていた訳です。ギターの弦は普通6本有ります(最近は単純に6本です・・とは言えない、多弦ギターがあるんです・・)から、それを1本ずつ、リズミカルに弾きますとアルペジオです。まぁ、分散和音が基本ですね・・
noisy もその昔はギター奏者でしたから、フォーク系のギターを持つシュチュエーションで必要ならば、アルペジオをスリーフィンガーで・・などとやっていた訳です。ギターの弦は普通6本有ります(最近は単純に6本です・・とは言えない、多弦ギターがあるんです・・)から、それを1本ずつ、リズミカルに弾きますとアルペジオです。まぁ、分散和音が基本ですね・・で、このサン=ヴェラン・アルページュですが、今までは確かにアルペジオだと感じることも有ったんですが、
「むしろしっかりした果実が表面に出ている」
ので、そんなに「アルペジオ」と言う名前ほどは・・単弦ずつでは響いて来ないよなぁ・・とは思っていたんです。ですが、2023年ものは違いました。ちゃんと・・
「単音の響きを感じられるアルペジオ!」
だと思えたんですね。
基本的にミネラリティが抜群に凄く、しかも葡萄が熟すために必要な日照をしっかり得られるのでしょう・・熟度の高い葡萄が得られますから、
「マコンよりもサン=ヴェランが格上」
とされるんです。
 しかしこのところは温暖化の影響でしょう。今まで熟度が今一つだったアペラシオンがちゃんと熟すようになり、そのテロワールの表現がよりクリアに感じられるようになって来たんですね。
しかしこのところは温暖化の影響でしょう。今まで熟度が今一つだったアペラシオンがちゃんと熟すようになり、そのテロワールの表現がよりクリアに感じられるようになって来たんですね。ですから、
「サン=ヴェランはマコン=ヴィラージュよりも熟度の高いワイン!」
と言う今までの常識は、そのまま信じる訳には行かなくなって来ています。
2023年のこのアルページュは、熟度はマコン=シェントレ・ピエール・ポリとほぼ同様かな・・と思います。ミネラリティの繊細さ、細やかな表情と言う部分で、
「きめ細やかで繊細なミネラリティが熱を得て表現している柑橘感」
と、
「まるでポロン、ポロンと細い弦をはじくように響く線状のミネラリティ」
が感じられるんですね。
非常に良い出来だと思います。メディアの評価が見つかりませんが、結構良いポイントが付くんじゃないかと思えるサン=ヴェランでは有りますが、2023年もののバローはすごく良いので・・全体的に高く評価されると期待しています。ぜひ飲んでみてください。お薦めです!
以下は以前のレヴューです。
-----
【こちらも本当に久々ですが、2022年ものアルページュは以前のアン・クレシェさえ凌駕しています!・・狙い目でしょう!】
 久しぶりのご案内になった「アルページュ」です。ラシーヌさんの扱いの時代に一度入って来たのを覚えています。
久しぶりのご案内になった「アルページュ」です。ラシーヌさんの扱いの時代に一度入って来たのを覚えています。繊細さのあるサン=ヴェランで、レ・ポマールが比較的マッチョで重量感が有り、その正反対のような性格なのがアルページュでした。
ですが・・その頃はおそらく2014年ものの頃で、今から8年も前です。少なくとも、
「こんなにゾクゾクっとするようなゴールド的な色彩は無く、もっと淡かった。」
です。
言ってしまえばこれも並みの「プイィ=フュイッセ」の範疇を超えるような出来で、グラや押し出しは少ないものの、ややオイリーで粘性が有り、しかし細かい糸を撚り合わせたような質感、接触感のあるテクスチュアから、繊細なアロマ、表情を浮き出してくれる素晴らしい出来です。
昨年の2021年もののサン=ヴェラン・アン・クレシェさえ超えているんじゃないかと思える素晴らしい出来です。
まぁ・・アルページュって、おそらく、
「アルペジオ」
と言う意味なのかな?と思っていますが、
「ギターのアルペジオと一緒」
の意味なのでしょう。
 たしかに弦を1本ずつ爪弾き、すぐ次の弦に移動して・・と言うのをリズム感良く続けるのがギターのアルペジオです。
たしかに弦を1本ずつ爪弾き、すぐ次の弦に移動して・・と言うのをリズム感良く続けるのがギターのアルペジオです。一般には、楽器の音を高い方から低い方へ、もしくはその逆で一音ずつリズムに乗って出音させる・・みたいな感じだと思いますが、
「このアルページュは繊細なので、まさにアルペジオ!」
と言って良いと思います。
その意味では、サン=ヴェランでもレ・ポマール的では無く、アン・クレシェ的です。
しかし!
「充実した果実に充実したボディ、粘性・オイリーさも有り、ミネラリティももの凄い」
と言うバランスの中で、
「めちゃ繊細!」
と言うことなんですね・・。
いや、2022年のダニエル・バローは凄いです!・・是非、以前のアイテムとの比較もしていただきたい・・超お薦めします!
●
2023 Saint-Veran en Creches
サン=ヴェラン・アン・クレシュ
【素晴らしいバランスを持つアン・クレシェはエレガント系のサン=ヴェランであり、エレガントなプイィ=フュイッセ風!・・フラワリーさ、仄かなスパイス・ハーブ、そして出る所はちゃんと出て引っ込むところがキュッと締まる、素晴らしいボディの持ち主でした!】
 2023年のドメーヌ・バローのプイィ=フュイッセは、ベースのアリアンスからして化け物級の凄い味わいを見せますから、おそらくお客様も相当驚かれることでしょう。
2023年のドメーヌ・バローのプイィ=フュイッセは、ベースのアリアンスからして化け物級の凄い味わいを見せますから、おそらくお客様も相当驚かれることでしょう。「フルな」・・と言う言葉は勘違いされそうなので余り使いたくないんですが、アリアンスでさえ・・フルである・・しかし美しく磨かれ、余分な・・とか、過分な・・と言うネガティヴに繋がる表情が一切無いんですね。
で、サン=ヴェランについて申し上げますと、すべてにおいて・・
「フルで半端無く凄いプイィ=フュイッセをほんの少し小さくしただけだ」
と思っていただいて良いでしょう。つまり、
「エレガントなプイィ=フュイッセ!」
です。
で、サン=ヴェランに移りますが、サン=ヴェラン・アルページュは冷涼です。繊細で美しい味わいです。
サン=ヴェラン・レ・ポマールは、サン=ヴェランの中で最も「フル」で有り、熱量が凄いですから・・まぁ・・ある意味、最もプイィ=フュイッセ的です。果実感もたっぷりです。でもバローのプイィ=フュイッセには少し及ばない・・です。
 このアン・クレシェは、サン=ヴェランの中で最もバランスに優れ、絹ごしのようなミネラリティのアルページュの良さと、レ・ポマールのような熱量からの果実表現を持ち、そのバランスが物凄いバランスになっている・・とお考え下されば・・良いかと思います。
このアン・クレシェは、サン=ヴェランの中で最もバランスに優れ、絹ごしのようなミネラリティのアルページュの良さと、レ・ポマールのような熱量からの果実表現を持ち、そのバランスが物凄いバランスになっている・・とお考え下されば・・良いかと思います。レ・ポマールはリッチなフレーヴァーです。アン・クレシェもリッチですが、リッチさはレ・ポマールに及ばないが繊細さ、ミネラリティの美しさ、バランスに優れますから、
「選択に困ったらアン・クレシェ!」
が正解です。
その上で、繊細なミネラリティが欲しいな・・感じたいな・・と思われたらアルページュを、濃密なプイィ=フュイッセ的熱量、パワーが欲しいと思ったらレ・ポマールを選ぶと良いかと。
因みに、マコン=ヴェルジッソン・ラ・ロシュとプイィ=フュイッセ・スュール・ラ・ロシュと、このサン=ヴェラン・アン・クレシェはそれぞれ目と鼻の先、同じ丘に有ります。アペラシオンはそれぞれ異なるんですが・・面白いでしょう?・・このマコネ地区は少し離れただけで変わってしまうんですね。ぜひ飲んでみてください。素晴らしい出来です!
以下は以前のレヴューです。
-----
【激繊細!・・しかも贅肉無しながら欠損感の無い見事な果実感!・・過去最高のアン・クレシェで間違い無いです!】
 旨いです~・・!・・もう、色彩だけ見比べても、
旨いです~・・!・・もう、色彩だけ見比べても、「過去最高・・でしょう?」
と言えると思います。もう・・2014年もののコラムで、
「2013年ものよりも確実に上!・・三千円超えてしまいましたが・・」
と書いていますが、その2014年ものの写真と見比べてみてください・・。
「この差は・・なんだ?」
と思えるんじゃないでしょうか。
激繊細ですが、豊かさも充分です。素晴らしいバランスに仕上がっていますから、
「げげっ・・サン=ヴェラン・アン・クレシェって・・こんなに美味しかったか?」
と、自問自答してしまいました。
「・・いや・・さすがにここまでは・・無かった!」
と確信したんですね。
しかも、今回はこのアン・クレシェの下のクラスも在りまして、「アルページュ」と言うワインですが、これでさえ、
「今までのアン・クレシェを超えている!」
と感じさせます。
 このアン・クレシェは、標高の高い場所にある「プイ=フュイッセ・スュール・ラ・ロシュ」の南の斜面に降りて行ったところにある畑です。ラ・ロシュとは近いそうです・・。
このアン・クレシェは、標高の高い場所にある「プイ=フュイッセ・スュール・ラ・ロシュ」の南の斜面に降りて行ったところにある畑です。ラ・ロシュとは近いそうです・・。でも、基本的にはサン=ヴェランは、クリュ・ボージョレで有名なあの、
「サン=タムール」
の北に接しています。実際には、「サン=タムール=ベルヴュ」の村です。
なので、ここはボージョレとマコンが混じった・・と言いますか、接した地域になっていまして、これほどまでに、
「シャルドネとガメが接している」
と思っていてください。
まぁ・・この辺りでシャルドネの美味しいのはサン=ヴェランになり、美味しい赤はマコンの赤は少なくて「サン=タムール」や「ジュリエナ」になるんですね。ホント目と鼻の先です。因みにサン=ヴェランの中心からジュリエナの中心までは・・直線で3kmもありません・・。
で、このアン・クレシェですが、レ・ポマールが以前と違ってマンモス・ミネラリティなタイプになりましたので、
「そこまでのマンモスぶりではない」
にせよ、黒葡萄の地域も近くなるイメージで、石灰や岩のイメージより繊細さが感じられるんじゃないかと思います。
2022年のドメーヌ・バローには驚かされると思います。超お薦めです!
以下は以前のレヴューです。
-----
【優しい・・抱かれるような感覚になるサン=ヴェラン!・・高質さ、繊細さに長けた素晴らしい出来です!】
 グラスの写真の中心に、So2 添加量の少なさが僅かに見え隠れしているように・・noisy には見えます。
グラスの写真の中心に、So2 添加量の少なさが僅かに見え隠れしているように・・noisy には見えます。「・・一体この人は何を・・言ってんだか・・」
と思われる方も多いかもしれませんが・・本気で思ってます。・・もしかしたらいつか、「えっ?」と・・その意味が判る場面に出くわすかもしれません。
非常に濃密で、飲む傍から・・
「旨い!」
と言ったに違い無いレベルの2020年ものだったと思います。でも、2021年ものはちょっと違うんですね~・・。
「非常に繊細!」
なんですよ。
それに現状(2023/03中旬)はまだミネラリティの中に表情が半分、閉じ込められているような感じでして、そろそろ美味しく飲める2021マコン=シェントレよりも成長が遅れている感じです。
まぁ・・その言い方は余り正しくはなく、プイィ=フュイッセなどの上級キュヴェは、有り余るポテンシャルからの表情がミネラリティの殻を破って・・もしくはその隙間や割れ目から出てくる訳ですが、この2021年サン=ヴェランのように、
「見事にピッタリ、精緻に仕上がり、素晴らしいバランスで仕上がったキュヴェ」
の場合は、その後、グイグイと成長をして行くパターンが多いと思います。誤解を恐れずに言ってしまえば、ヴァーゼンハウスのワインなどが・・そうです。ヴァーゼンハウスもようやく
最近は早い段階で(その年の2~3月)も美味しく飲めるようになりましたが、2019年ものまでは本当に・・
「販売開始時期決定にとても気を遣うワイン」
でした。・・まぁ、プロの連中でさえそれを理解できない訳ですから、本当に難しい判断になる訳です。
 実は今の開き具合でも大丈夫なんですが、非常に精緻なバランスで仕上がったSo2の少ないワインですから、少しでも休養の時間が有ると大きく変わって行く可能性が高いんですね。
実は今の開き具合でも大丈夫なんですが、非常に精緻なバランスで仕上がったSo2の少ないワインですから、少しでも休養の時間が有ると大きく変わって行く可能性が高いんですね。また、以前のサン=ヴェラン・アン・クレシェは、どちらかと言うと非常に饒舌なスタイルでした。2021年ものは・・と言いますか、ドメーヌ・バローはジュリアンがやるようになってきてからどんどんナチュラル感が増して来ています。
その分、
「ハッキリした味わい」
「判りやすい味わい」
から、少し離れて来ているんですね。
簡単に言いますと、So2 は塩分みたいな効果を持っていまして、これを使用しますと味わいの中心点がハッキリします。使わないと・・ちょっとそのポイントがボケた感じ・・と言いますか、そのポイントが大きく拡がって感じられる?・・そんな感覚なんですね。
その上で熟成..必要な時間を得ますと、So2 を使用した時ほどでは無いんですが、「コアがハッキリ感じられる」的な感覚を得る液体になって行く・・そう感じています。
ですので、飲まれるタイミングで結構に味わいが異なるかと思いますが、美しく、繊細さを感じられる柑橘果実主体の少し柔らかめの石灰系ミネラリティを持ったサン=ヴェランの味わいを楽しめることでしょう。是非飲んでみてください。
「結構、・・コート・ド・ボーヌに寄って来たぞ・・」
的な味わいを感じられると思います。お勧めです!・・量はありません。
以下は以前のレヴューです。
-----
【より温暖なサン=ヴェランのふっくらした味わいにホッコリ・・します!・・2020年ものは最高の出来でしょう!】
 どうでしょう・・今飲んで滅茶美味しいのは、このサン=ヴェラン、アリアンスでしょうか。最も、相当ビックリさせられるのは今の時点ではスュール・ラ・ロシュであるのも間違いないと思います。
どうでしょう・・今飲んで滅茶美味しいのは、このサン=ヴェラン、アリアンスでしょうか。最も、相当ビックリさせられるのは今の時点ではスュール・ラ・ロシュであるのも間違いないと思います。岩や石のニュアンスが素晴らしい、マコンのシャルドネに有って、このサン=ヴェランはやはりより暖かな酸バランスと、より優しいミネラリティを持っている・・と言うか、厳し過ぎないミネラリティと言うべきかもしれませんが、中域の豊かな美味しさを感じさせてくれます。
2020年ものは2019年ものに比較すれば、やはり硬質なのは間違い在りませんが、それでもサン=ヴェランの優しいシャルドネの味わいに触れると安心します。何せ上級キュヴェは物凄いですから・・ついついポテンシャルを取りに行ってしまうんですよね。
バローのワインはそもそも全てがポテンシャル高い訳ですが、それでも・・noisy は、
「2日で6アイテム!」
とかを開けて飲んでいますから、
「・・美味しいのは・・これだけど、普段飲みたいのは・・そっち!」
とか、
「・・うわっ!・・凄い!・・」
と感じつつも、
「(・・ん・・毎日これだと・・ちょっと疲れるかなぁ・・)」
などとも思ってもいる訳です。まぁ、贅沢な悩みでも有ります。
 そんな時に、このような優しい・・より柔らかな味わいの同様なワインを口にしますと、確かにポテンシャルは少し落ちるんだけれども・・凄く安心する訳ですよ。とてもバランス良く美味しいし、疲れないし・・シャルドネだから料理に合わせやすいし・・。
そんな時に、このような優しい・・より柔らかな味わいの同様なワインを口にしますと、確かにポテンシャルは少し落ちるんだけれども・・凄く安心する訳ですよ。とてもバランス良く美味しいし、疲れないし・・シャルドネだから料理に合わせやすいし・・。しかも以前のバローように樽っぽさなどは無いし、硬すぎて飲めないことも無い・・んですね。
ですから、この数年のバローのワインを非常に評価している訳ですが、それにはやはりジュリアンさんの存在が大きいんじゃないか・・と思います。
よりナチュラル、ピュアになって来ているドメーヌ・バローの、優しく暖かいサン=ヴェランです。白、黄色の果実だけじゃなく、やや赤に近い方に色付いた色の果実のニュアンスも感じますし、甘く無くドライですが旨味もしっかり載っています。是非飲んでみて下さい!お勧めします!
以下は以前のレヴューです。
-----
【今(2021年6月末)一番開いているのはこれ!・・素晴らしいバランスです!】
 サン=ヴェラン・アン・クレシェ...今めっちゃ美味しいです!!・・ダレないふくよかさ、ドライなのに旨味たっぷりなエキスから、黄色いフルーツや白、黄色の花のニュアンスに僅かに蜜・・しかも上級のプイィ=フュイッセに通じるような気品や凝縮感も有りますから、
サン=ヴェラン・アン・クレシェ...今めっちゃ美味しいです!!・・ダレないふくよかさ、ドライなのに旨味たっぷりなエキスから、黄色いフルーツや白、黄色の花のニュアンスに僅かに蜜・・しかも上級のプイィ=フュイッセに通じるような気品や凝縮感も有りますから、「3千円以下クラス最強部類のシャルドネ!」
と言っても過言では無いでしょう。
まぁ、マコンとか(マコン何とかを含む)サン=ヴェランとかは、ある程度の栽培面積の広いアペラシオンですから、良いものとダメなものが両極で存在しています。俗に言う、
「ピンからキリまで」
有る訳です。
で、このサン=ヴェラン・アン・クレシェは「ピン」に限りなく近い方です。その上価格も非常にリーズナブルです。
とある生産者のマコンやサン=ヴェランが凄く美味しかったので、しばらく扱ったんですが、しばらくしたらナチュラルなのはとても良いのに、かなりのレベルの揮発酸が目立つようになってしまって・・まぁ、それでも何とか許せるレベルかとも思ったんですが、
「残念ながら・・価格が高い」
ので、それからは入れることを諦めています。
ナチュラルさと味わいのピュアさは、決して比例するものでは無いので、その辺りをお客様にどう説明して判っていただけるか?・・をかなり考えています。その点に置いて、ドメーヌ・バローのワインはナチュラルさとピュアさを同列にして言えるので、ワイン屋にもお客様にも有難いことだと思います。勿論ですが、
「ピュアさを犠牲にしてもナチュラルさを・・So2無しが欲しい」
とおっしゃるお客様にも対応はしているつもりですし、時には、
「どこまでもアヴァンギャルドで行くぜ!」
みたいなビオ系、もしくは「ノン・So2」の生産者さんのワインにも興味は有る訳で、理解できる程度の残存揮発酸量であるなら、やろうと思っている訳ですね。
ですが、このサン=ヴェランには、そんな心配は無用です。どこまでもピュアでナチュラル、ふんわりと、そして確実にスピ―ドの有るアロマをお約束出来ます。是非ご検討くださいませ。一推しでお勧めします!
以下は以前のレヴューです。
-----
【サン=ヴェランがこんなに美味しくて・・どうするの!】
 このサン=ヴェランで充分!・・です。2018年のダニエル・バローの素晴らしさを見るには・・。却って上級キュヴェのマンモスなミネラリティが要素を抑え込むような動きをするかもしれないので、「造り手の傾向を知る」には、このリーズナブルなサン=ヴェランでもOKだと言えます。
このサン=ヴェランで充分!・・です。2018年のダニエル・バローの素晴らしさを見るには・・。却って上級キュヴェのマンモスなミネラリティが要素を抑え込むような動きをするかもしれないので、「造り手の傾向を知る」には、このリーズナブルなサン=ヴェランでもOKだと言えます。やはりジュリアンが参画するようになってから、自然派的アプローチが深まって行ったのでしょう。飲むと葡萄の根が水分を求めて地中深く入って来たのが目に見えるかのように感じられます。
色彩も艶やかな果実がたんまり・・そして白いミネラリティと、透明感バッチリなガラス、クリスタル風のミネラリティがたんまり有ります。色合いも・・緑色の存在が美しく感じられます。これは実にリーズナブル!・・少なくとも90点以上は付けるべきシャルドネでしょう!是非飲んでみて下さい!お勧めします!
以下は以前のレヴューです。
-----
【全方位に外向的!豊かな味わいだがダレ無い酸の美味しさが凝縮した果実を引き立たせています!】
 非常に良いワインです。僅かに映しこまれた淡い緑色が、このワインの素性を語ってくれています。非常にピュアで丸みがあり、ブルゴーニュの南部のワイン特有の暑苦しさは無く、極上クラスの味わいを感じさせてくれます。
非常に良いワインです。僅かに映しこまれた淡い緑色が、このワインの素性を語ってくれています。非常にピュアで丸みがあり、ブルゴーニュの南部のワイン特有の暑苦しさは無く、極上クラスの味わいを感じさせてくれます。ラシーヌさんはダニエル・バローの輸入が出来なくなってしまいましたが、例えばラシーヌさんにお呼ばれされて新年会などに行かせていただくと、サンリバティーさんの社長さん、佐々木さんがいらっしゃったりします。どうやら非常に仲が宜しいようで・・また、ラシーヌさんの合田さんもサンリバティーさんの何かにタッチしてるのかな?・・ハッキリしたことは判らないんですが、関係の深い間柄のようです。
なので、新年会でラシーヌさんのワインを味わっていると・・そのままじゃ済まなくなってしまいます。2年ほど前には・・それまでラシーヌさんの新年会にお邪魔していたはずなんですが、気付くと拉致されていまして、何故か佐々木さんの地元で飲んでいたりします。気付けば日が変わっていて・・何てことになっているんですね~・・。
サンリバティーさんのワインはラシーヌさん同様コンディションも良く、社長さんのお人柄も良く・・何せ工学系出身なのになぜかワインのエージェントをしていると言う、ちょっと変わった履歴の持ち主でおられます。で、2015年ものもそうでしたが、2016年もののバローは完全にサンリバティーさんからの仕入れになっています。
このサン=ヴェラン・アン・クレシェは2015年ものはご案内出来なかったので二年振りと言うことになります。ご存知かとは思いますがサン=ヴェランはマコン各村の近郊に有る村、A.O.C.で有り、A.O.C.プイィ=フュイッセの北に接している村でA.O.C.マコンより上位とされています。また単にマコン=ヴィラージュより上位とお考え下さって結構かと思います。
さすがにA.O.C.マコンで美味しいものは多くは無いですが、マコン=ヴィラージュやマコン=何とか、サン=ヴェランともなりますと、昨今は結構に良いものも散見されるようになってきました。
ただし・・価格も10年前のブルゴーニュ村名並み・・と言う場合が多いので、
「・・いや~・・ダニエル・バローが有るからなぁ・・中々この存在は超えられないでしょ・・」
と言う気も有ります。
年々ピュアさとナチュラルさを増してきているダニエル・エ・ジュリアン・バローですが、20年ほど前の「樽っぽいシャルドネ」とは隔世の感が有ります。非常にピュアなんです。樽は掛かっていますがその存在を言う必要が無いほどまで来ています。
とても良い感じに凝縮しており、冷ややかな酸が柑橘系フルーツの美味しさをたっぷり伝えてくれます。勿論、ミネラリティもたっぷりです。ガラスのような透明感の強いものと白っぽい石灰系のものが半々ほどに感じられ、全てを支える基盤になっているかのようです。
リアルワインガイド第62号では、「現状は少し硬いがすぐこなれて来そう・・」のように書かれていますが、今飲んで充分な美味しさを感じられるバランスです。評価は89+~90 です。これより低いACブルゴーニュ・シャルドネは山ほど・・有ります。noisy のところでも非常に売れているロッシュ・ド・ベレーヌのシャルドネはリアルでは90点には届きません。確かに・・濃密さはこのサン=ヴェランの勝ちです。このちょっとしたシャルドネのマッタリ感にやられちゃうんですよね。
非常に良い出来でした。価格もリーズナブルです。是非飲んでみてください。お勧めです!
以下は以前のレヴューです。
━━━━━
【さすが格上!!マコンから来ると、クラスの違いを感じます!】
 以前のコメントを修正して掲載しています。非常に旨いですが・・非常に少ないです。
以前のコメントを修正して掲載しています。非常に旨いですが・・非常に少ないです。さすがにポエール・ポリをこのクラスと比べると見劣りがしてしまいます・・・結局ミネラリティの違いなんですよ・・・なんだかんだ言っても最後は・・。果実だ酸だと分析しても、ミネラリティの質が自分の中のクラス、判断基準を決めているような気がします。
◆サン=ヴェラン・アルページュ
2012年初登場のアルページュ。少し濃い目の黄色。甘塩っぱいミネラル感がとても強い。ドライだが実に集中していて、それも甘みを感じさせる原因だろう。タイトで逞しい筋骨隆々タイプ。かなり旨い。
◆サン=ヴェラン・アン・クレシェ
ハッキリ言って・・ちょっと舐めてました。3千円超えちゃった・・もう駄目かな・・と思ってたら・・とんでも無い!プライス以上のポテンシャル!トースティ、ドライだがジューシー。しかもかなりなミネラリティ度。現在は少し硬めだが、今までとは異質のポテンシャルを感じる。かなりの延び代のある味わい。フレッシュ感がたっぷり有り、ピュア感に結びついている。2013年までよりも確実に旨い。
◆サン=ヴェラン・レ・ポマール
圧巻。重厚感。質感の高さ。ボーヌの優良シャルドネ並みのミネラリティ。こってり感。中域の透明感。酸の美味しさ、バランスの良さ・・かなり美味しい。ボテっとした南部のミネラリティではなく繊細さを感じる。実に高級な味わい!
サン=ヴェラン3種にも・・ビックリです。アルページュは逞しい、筋肉質の男性のようなスタイルで、プイィ、マコン辺りの暑苦しさが全く無いんですよね。アルページュが以前のアン・クレシェを男っぽくしたような感じです。価格もそんな感じ。
アン・クレシェにはビックリ・・。物凄いポテンシャル・アップでした!
「これでサン=ヴェランかよ~!」
みたいな雰囲気でした。
で、サン=ヴェラン・レ・ポマールですが・・・これをプイィ=フュイッセと言わなくて、何だと言えばよいのか・・もうミネラルの細やかさが異質なんですよ。滑らかでね・・緻密さ、エレガンスもある・・言うことのない味わいでした。
そんな訳で選択は難しいかと思いますが、どれを飲んでも旨いです。えっ?ポマールが高い?・・・いや、高くないです。エチケットが無いと思って飲んでみてください。ビックリされると思いますよ!お勧めします!
●
2023 Saint-Veran les Pommards
サン=ヴェラン・レ・ポマール
【ジュリアン・バローが目指す「バローのシャルドネの将来」が透けて見えて来る素晴らしい出来!・・新樽を抑え、かなりの自然派レベルです!】
 その昔・・そうですね・・1990年代から続けて扱わせていただいているドメーヌ・バローですから、その移り変わりもまた・・しっかり舌と鼻に焼き付いてしまっている noisy です。最初はル・テロワールさんでした。今も続いているアメリカのノースバークレイ社がやっていた「ノースバークレイ・スペシャル・キュヴェ」の中にバローのラインナップが有り、それをル・テロワールさんが入れていた訳です。
その昔・・そうですね・・1990年代から続けて扱わせていただいているドメーヌ・バローですから、その移り変わりもまた・・しっかり舌と鼻に焼き付いてしまっている noisy です。最初はル・テロワールさんでした。今も続いているアメリカのノースバークレイ社がやっていた「ノースバークレイ・スペシャル・キュヴェ」の中にバローのラインナップが有り、それをル・テロワールさんが入れていた訳です。それで飲んだら驚いたのなんの・・。その頃はPKさんがバリバリの頃でして、新樽に入れさせてエルヴァージュ・・これが大当たりでした。ヴェルジェもそうでしたしバローもです。ドラルシェも実はそうです。
でも、バローのシャルドネは人気で、特にアンビュランやレ・クレイはバラで少しずつしか分けてもらえませんでした。それを3年ほど熟成させてから飲むと・・と言うより、昔は今のように、
「入って来たら割り当てて、はい、お仕舞」
みたいな感じでは無かったので、以前のヴィンテージのものが残っていて、それを購入したり・・が出来た訳ですね。
で、少し熟したものを飲んでみますと・・ま~・・超絶に美味しかったです。
で・・新しいヴィンテージのものをテイスティング会などで開けてみると・・
「(・・樽臭っ!)」
と・・やや焦げ臭のする新樽由来の匂いがしていました。ですので、
「最低3年は寝かせてね」
と言っていた訳です。
 ですが、今のジュリアンが造るバローのワインは全く違います。新樽は2~3割くらいじゃないかと。その他は古い樽やイノックス、他を使用しているので、
ですが、今のジュリアンが造るバローのワインは全く違います。新樽は2~3割くらいじゃないかと。その他は古い樽やイノックス、他を使用しているので、「全く樽臭さが無いピュアな味わい」
がします。
そして毎年、テイスティングのたびに感じるんですが、
「年々、どんどんナチュラルになって行く!・・アロマの線が太くなり、スピード感がどんどん高くなり、ふんわりさが増大している」
と感じる訳です。
このレ・ポマールは、1級プイィ=フュイッセ・スュール・ラ・ロシュと同じ丘に有り、非常にミネラリティが高いです。実はサン=ヴェランの中で一番ミネラリティとしては高いはず。
ですが、非常に熟れた果実が収穫できるようで、その熱量から生まれる果実感、柑橘果実感が・・エレガントさはちゃんと備わっているんですが・・マンモスなんですね。
ですから最もプイィ=フュイッセに近い表情を見せてくれますし、「ラ・ロシュ的」な大きな岩、崩れた岩のニュアンスさえあるのに、それをマンモスな果実表現で包んでいる感覚・・です。非常に素晴らしい・・
「サン=ヴェランなのになぁ・・」
と、20年前じゃとてもじゃないが想像も出来ない仕上がりです。ぜひ・・グーグルマップを開いて、あの・・大きな岩山を見ながら飲み比べていただけますと、さらに美味しく飲めるんじゃないかと思います。飲んでみてください。超お薦めです!
以下は以前のレヴューです。
-----
【プイィ=フュイッセより高価なサン=ヴェランです!味わいはベースのプイィ=フュイッセ以上!ティム・アトキン氏は2014年ものが91Pointsでした!】
 2014年のラシーヌさんもの、2017年のサンリバティーさんもの以来のご紹介になります、サン=ヴェランのポマールです。6年ぶりに入荷して来たことになります。
2014年のラシーヌさんもの、2017年のサンリバティーさんもの以来のご紹介になります、サン=ヴェランのポマールです。6年ぶりに入荷して来たことになります。以前は、
「ややファットな・・熱量感と重量感のあるサン=ヴェラン」
と言うイメージでした。
あ、因みに・・このマコン系のワインをレクチャーしますと、
下のクラスから
「マコン」
「マコン=ヴィラージュ」
「サン=ヴェラン」
「プイィ=フュッセ」
となります。
マコン=ヴィラージュと言うアペラシオンも有りますが、マコンの後に村名をつなげて「マコン=ヴェルジッソン」と言うクラスも有ります。今回の2022年ものは「マコン=ヴェルジッソン」に畑名を加えて、「ラ・ロシュ」も届いています。ここの「マコン=ヴェルジッソン・ラ・ロシュ」の真上はなんと、
「プイィ=フュッセ・ラ・ロシュ」
です。
ですので、「マコン」--地方名、「マコン=ヴィラージュ」--村名・・で、サン=ヴェランもプイィ=フュイッセも村名ですが、
「より格上」
とご理解ください。地域は結構に近い・・もしくは隣り合っている感じです。
 サン=ヴェランであることが信じられないほど、
サン=ヴェランであることが信じられないほど、「プイィ=フュッセ的」
です。もちろん、ダニエル・バローの2022年ものの特徴でもある、健康的で冷ややか、ミネラリティが半端無く、果実感・有機物・無機物の香りが繊細にたなびくのは同様です。
ですから、
「わずかに端正・・スタイリッシュな、美しい系のプイィ=フュイッセ!」
と言って良いレベルで、とても・・
「一般に良くあるサン=ヴェランと一緒に出来ない」
と感じます。
何より、このレ・ポマールよりも濃いサン=ヴェランは有るかもしれませんが、プイィ=フュイッセだと言われても納得してしまうに違いないほどの「質感」が有ります。
ん・・書いていて気付きましたが、以前は本当に、
「豊かなサン=ヴェラン」
でした。ぜひ飲んでみてください。滅茶旨いです!
以下は以前のレヴューです。
-----
【プイィ=フュイッセより高価なサン=ヴェランです!味わいはベースのプイィ=フュイッセ以上!ティム・アトキン氏は2014年ものが91Pointsでした!】
以下は2013年もの、リリース当時のラシーヌさんものについてのレヴューです。
━━━━━
【さすが格上!!マコンから来ると、クラスの違いを感じます!】
 以前のコメントを修正して掲載しています。非常に旨いですが・・非常に少ないです。
以前のコメントを修正して掲載しています。非常に旨いですが・・非常に少ないです。さすがにポエール・ポリをこのクラスと比べると見劣りがしてしまいます・・・結局ミネラリティの違いなんですよ・・・なんだかんだ言っても最後は・・。果実だ酸だと分析しても、ミネラリティの質が自分の中のクラス、判断基準を決めているような気がします。
◆サン=ヴェラン・アルページュ
2012年初登場のアルページュ。少し濃い目の黄色。甘塩っぱいミネラル感がとても強い。ドライだが実に集中していて、それも甘みを感じさせる原因だろう。タイトで逞しい筋骨隆々タイプ。かなり旨い。
◆サン=ヴェラン・アン・クレシェ
ハッキリ言って・・ちょっと舐めてました。3千円超えちゃった・・もう駄目かな・・と思ってたら・・とんでも無い!プライス以上のポテンシャル!トースティ、ドライだがジューシー。しかもかなりなミネラリティ度。現在は少し硬めだが、今までとは異質のポテンシャルを感じる。かなりの延び代のある味わい。フレッシュ感がたっぷり有り、ピュア感に結びついている。2013年までよりも確実に旨い。
◆サン=ヴェラン・レ・ポマール
圧巻。重厚感。質感の高さ。ボーヌの優良シャルドネ並みのミネラリティ。こってり感。中域の透明感。酸の美味しさ、バランスの良さ・・かなり美味しい。ボテっとした南部のミネラリティではなく繊細さを感じる。実に高級な味わい!
サン=ヴェラン3種にも・・ビックリです。アルページュは逞しい、筋肉質の男性のようなスタイルで、プイィ、マコン辺りの暑苦しさが全く無いんですよね。アルページュが以前のアン・クレシェを男っぽくしたような感じです。価格もそんな感じ。
アン・クレシェにはビックリ・・。物凄いポテンシャル・アップでした!
「これでサン=ヴェランかよ~!」
みたいな雰囲気でした。
で、サン=ヴェラン・レ・ポマールですが・・・これをプイィ=フュイッセと言わなくて、何だと言えばよいのか・・もうミネラルの細やかさが異質なんですよ。滑らかでね・・緻密さ、エレガンスもある・・言うことのない味わいでした。
そんな訳で選択は難しいかと思いますが、どれを飲んでも旨いです。えっ?ポマールが高い?・・・いや、高くないです。エチケットが無いと思って飲んでみてください。ビックリされると思いますよ!お勧めします!
●
2023 Pouilly-Fuisse Aliance Vieilles Vignes
プイィ=フュイッセ・アリアンス・ヴィエイユ・ヴィーニュ
【もはや色彩からして全然違う・・(^^;; まさに照りのあるゴールド、一瞬むせるようにさえ感じる豪奢なアロマに出会う・・凄いプイィ=フュイッセです!・・あり得ないリーズナブルさ!】
 毎年同じことを書いているような気がして嫌なんですが・・歳を取ると昔のことは忘れてしまいますから良いはずなんですが、嫌だと思っていることは都合悪く忘れないんですよ。困ったものです。
毎年同じことを書いているような気がして嫌なんですが・・歳を取ると昔のことは忘れてしまいますから良いはずなんですが、嫌だと思っていることは都合悪く忘れないんですよ。困ったものです。そもそもダニエル・バローとの付き合いは、もはや30年近くにも及ぶと思うんですね。途中抜けたことが有ったかな?・・思い出せませんが、バローに関しましてはダメになっても何故かまた別のエージェントさんから繋がって来て・・また扱わせていただける・・と言うように続いて来ました。
noisy も3年に一度ほどは凄いドメーヌと出会い・・その都度、
「騙されたと思って・・買ってください。」
とお客様にお願いしていました。最近ではギルベール・ジレでしょうか・・しっかりほぼ切られてしまいましたが・・誰も飲まないから良さがまるっきり判らないワイン屋さんは、安値で叩き売りして・・でも残ってました。noisy はテイスティングしたら・・余りの素晴らしさに驚いてしまい、
「初めて造った1年目のワインですが、とんでもない出来なので・・ぜひ!」
とお願いしたんですね。
そうしたら・・お客様がそれに乗ってくださって・・あっと言う間に完売し、フィネスさんに残っていた分をぜんぶ戴いたんですね。なので、2021年ものは結構いただけた訳ですが、それは良いとしても・・ギルベール・ジレ、海外はとんでもないことになっていまして、
「2021年の区画名無しのサヴィニー=レ=ボーヌが8~12万円」
です。
「・・あちゃ~・・やっちまったな・・」
です。
 素晴らしいワインでしかも価格はリーズナブルなサヴィニ=レ=ボーヌやアロース=コルトン、ラドワ=セリニーのワインを皆さんに知っていただくのには最高のワインだったのですが・・。
素晴らしいワインでしかも価格はリーズナブルなサヴィニ=レ=ボーヌやアロース=コルトン、ラドワ=セリニーのワインを皆さんに知っていただくのには最高のワインだったのですが・・。あ、本筋はそこでは無く・・すみません。
このダニエル・バロー、ジュリアン・バローは長年ずっと続けられていて、しかも日本への供給は・・まぁ・・有る方なので、
「騙されたと思って・・買ってください!」
の手が、あまり効かないんですね。
でも敢えてここは言いたい・・
「この凄いアリアンス2023!・・是非騙されたと思って買ってください!」
まぁ・・一番安いアリアンスを一推しにしてしまうワイン屋はいないはずですが、やはり飲んでいただかないといけませんし・・。
もちろんですが他のプイィ=フュイッセのキュヴェもそう言いたいんです。凄いですよ・・凄い複雑性と気品に満ちたワイン・・それがアリアンスの上級キュヴェたちです。
しかし、その基本はこのアリアンスV.V.に有ります。生半可なプイィ=フュイッセじゃないんです。
柑橘がしっかりあり、ミネラリティも驚くほどにマンモス、味わいの幅も広く・・甘くドライでとことん伸びる・・凄いワインなんですね。もしこれがコート=ドールだったら、数万円するんじゃないでしょうか。
なのでここは・・
「このグラスの色を見ていただき、素晴らしいと思っていただいたら・・買ってください!」
と申し上げたいと思います。
2023年のドメーヌ・バロー・・敢えて言いたいと思います。
「ドメーヌ・バローの2023年、ドメーヌが始まって以来の最高のヴィンテージです!」
どうぞよろしくお願いします。
以下は以前のレヴューです。
-----
【ドメーヌ・バローの2022年もののプイィ=フュッセの素晴らしさは、このアリアンスで充分知ることが出来ます!・・おそらく過去一でしょう!】
 3年前の2020年ものは、まだ3千円代と言う超お買い得なプイィ=フュッセでした。
3年前の2020年ものは、まだ3千円代と言う超お買い得なプイィ=フュッセでした。ミネラリティは半端無く、熱量を果実に変え、繊細さ、伸びも素晴らしい・・まさに・・
「シャルドネの鏡はダニエル・バロー!」
でしたし、
「ポテンシャルと価格が最も釣り合わない唯一のシャルドネ!」
でした。
まぁ・・最近はフイヤ=ジュイヨを見つけましたので、次のヴィンテージが楽しみでしょうがないですが・・あちらはシャロネーズの南のドンケツで、このプイィ=フュイッセとも、さほど遠くは無い・・と言うロケーションながら、どこか、
「コート・ド・ボーヌのシャルドネ的」
と言うニュアンスが強いですよね。
で、昨今のドメーヌ・バローのシャルドネは、
「どんどん北上して来ていて、やがてはボーヌのシャルドネにニュアンスが近くなるはず」
と感じます。
 特に2022年ものはその傾向が顕著でして、
特に2022年ものはその傾向が顕著でして、「プイィ=フュッセと言うよりも美しい感じのムルソー」
と言ったニュアンスですから、ここに・・昔のような新樽率の高さを持って来たとしたら・・相当に見分けは難しくなると思います。
このアリアンスは、プイィ=フュッセのワインの・・
「ある意味、寄せ集めのプイィ=フュイッセ」
ですから、良くも悪くも全てこのアリアンスを飲めば判るんですね。
黄色い柑橘果実、果皮に白っぽい花、スパイス、いつもよりも膨大に感じるミネラリティ。豊かでは有るが甘く無く、しっとりとしつつもパキッとした感覚も。中域は締まりつつも適度に膨らみが有り、ややタイト気味。中盤からの長さは素晴らしい。ノーズへの還りの表情にうっとりする・・
そんな感覚です。
ですので、今やユーロ円が165円の時代ですので、この価格も仕方が無いんじゃないかと感じます。そもそも3千円台の素晴らしいプイィ=フュイッセなどは有り得なかった訳ですから。
ぜひ飲んでみてください。健康的でふくよかながら締まって、徐々に出てくる素晴らしいシャルドネです。お薦めします!
以下は以前のレヴューです。
-----
【「・・アリアンスって・・こんなに美味しかったっけ!?」とおっしゃっていただけるでしょう!・・このキュヴェは過去最高間違い無し!・・飲めば多分・・判ります・・(^^】
 「とんでもなくリーズナブルなプイィ=フュイッセ!」
「とんでもなくリーズナブルなプイィ=フュイッセ!」としてのご理解でいらっしゃったはずのアリアンスV.V.です。ですが、3千円台だったものが4千円台まで上がっちゃいました・・なので、ハッキリ・・申し上げますと・・
「この2021年アリアンスv.v.は、2020年ものの Noisy wine の販売価格より仕入れ価格の方が高い」
です。
なので、販売側としましては、
「・・何だかなぁ・・」
と・・昨年の販売を帳消しにされたような感覚に陥ってしまう訳です。・・まぁ、
「でもそろそろそんなシュチュエーションが多いので慣れて来てしまった・・」
とも言えます。昨年は昨年、今年は今年と分けて考えれば良い訳ですから・・はい・・何とか頑張ります。
では、価格は何でそんなに上がってしまったのか?
そう考えてみることも必要ですよね?・・
「・・そりゃぁ・・収穫量が減って収入が大きく減る訳だから、下のクラスのプイィ=フュイッセを上げたんじゃね?」
まぁ・・その線も無いとは言えないでしょう。でも・・
「甘~~~い!」
 まぁ、こんなことはバローさんも全く言ってませんが・・。でも、
まぁ、こんなことはバローさんも全く言ってませんが・・。でも、「40%ものの収穫減で、キュヴェによっては全く造れなかった」
と・・エージェントさんの資料に書いて有ります。
ですから・・
「通常はアリアンスに使わない上級畑の葡萄が相当量入っている!」
そんな可能性が「大有り」なんですね。
では、どうしたらそれが判るか?・・ですが・・そう、当たり前ですね。
「飲めば判る!」
んです。理由は・・
「滅茶旨いから!」
です・・(^^;;
繊細さと複雑性、そして適度なオイリーさ・・自然な黄色い柑橘果実のハイトーンなアロマ・・旨いですね~・・あ、そうそう・・是非とも2020年もののグラスの写真と比較してみてくださいね。
「・・あっ・・見比べたら・・一目瞭然ってやつ?」
この、Noisy wine を苦しめる値上げの理由、お判りいただけたんじゃないかと・・思います。ですから、アリアンスと言う名前・・英語だとおそらくアライアンス?・・これは「同盟」「連携」と言う意味が有りますので、
「この2021年アリアンスV.V.は過去最高の出来!・・しかも上級キュヴェの格落ち入りを考えられる、滅茶苦茶お買い得なプイィ=フュイッセ!」
と言うことになります。
ですので、
「他のキュヴェより相当高くなってしまったから、選択肢から外す」
のは間違い。
より高質な葡萄を使うしかなかったキュヴェだからこそ、高くせざるを得なかったんだと・・飲めば判るんですね。飲まないと判らない訳で・・飲まないワイン屋さんには絶対に教えてもらえない・・(^^
なので、「noisy激推し確定」です!・・もはやドミニク・ラフォンのA.C.ブルに匹敵する出来。飲んでみてください。利益は余り出ないけど・・超お勧めします!
以下は以前のレヴューです。
-----
【いつもより硬質な2020年のバローのプイィ=フュイッセを理解できる、もっともリーズナブルなキュヴェ!・・勿論、その中で最も柔らかいとも言えます!】
 素晴らしい色合いですよね?・・ヴェルジッソンの畑の2キュヴェが1級になってしまいましたので、ヒエラルキーが少し変わったような気がしますが、それでもこの、
素晴らしい色合いですよね?・・ヴェルジッソンの畑の2キュヴェが1級になってしまいましたので、ヒエラルキーが少し変わったような気がしますが、それでもこの、「アリアンス」
の立ち位置には変化は有りません。
何せ滅茶安いです!・・すでにユーロもドルも、対円で20%ほど値上がりしています。でも・・バローは10%しか上がっていません・・。まぁ、エージェントさんも非常な努力をされてこのリーズナブルな価格を維持しています。
noisy もこの状況は理解しており、20%近いアップを予想していたのですが・・何とか10%ほどのアップで抑えてくれました。まことに有難いことです・・アリアンスは売れ筋ですから・・はい。
ですがやはり量が少ない2020年・・2019年もののように追加はできないようです。お早めにご検討ください。
2020年のアリアンスは、他のキュヴェ同様に、より「硬質」に感じられます。果実感、柑橘果実感の周りにミネラリティのコートが感じられるようなニュアンスです。
なので、noisy がいつも良く言うように・・
「テッカテカ!」
なテクスチュアです。
 ですが、プイィ=フュイッセの他のキュヴェほどでは無い・・そちらと比較すると、
ですが、プイィ=フュイッセの他のキュヴェほどでは無い・・そちらと比較すると、「より柔らかで、要素の様子が判りやすい」
んですね。
で、その粒子の隙間から・・果実、柑橘果実が漏れてくる・・しかも酸もたっぷりでピュア。そして年々ナチュラル感が増しているようにも感じる訳です。
だから、
「A.C.ブル並みの価格で村名(プイィ=フュイッセ)が飲める!・・しかもバロー!」
と言うことに嬉しさを感じるんですね。
勿論ですが・・ワインは好みですから、
「・・ん~・・タイプじゃないんだよな・・」
と思われる方もいらっしゃるに違い無いんです。それはそれで仕方がない・・ネットを徘徊してワインの感想を書かれているブログなどを見ていますと、肯定派が断然多いんですが、否定派もいらっしゃいます。
いつも言っていることではありますが、その瞬間だけを感じていると、その時のその瞬間だけの味わいを切り取ることになってしまいます。でも、記憶と想像を生かすことで、そのワインの先の姿も味わいのひとつであることに気付かれていらっしゃる方も大勢いらっしゃいます。出来ることならそのような飲み方をした方が・・大きなお世話ではありますが、より幸せになれると・・感じています。是非・・想像しながら飲んでみて下さい・・滅茶美味しいシャルドネです!
以下は以前のレヴューです。
-----
【最もリーズナブルで、且つ、評価も高いプイィ=フュイッセ!冷ややかな果実の美味しさを感じさせてくれます!】
 2018年ものはティム・アトキン氏も91ポイント、この2019年ものはジャスパー・モリス氏も上値91ポイントですので、変わらずに・・横滑り的な評価だと言えます。
2018年ものはティム・アトキン氏も91ポイント、この2019年ものはジャスパー・モリス氏も上値91ポイントですので、変わらずに・・横滑り的な評価だと言えます。しかしながら、2018年ものでも相当に美しさがアップして来ていたのは言えますが、2019年ものはさらに・・「さらに」、美しさがアップしていると言えます。「健康美」と言いたいですね。
それも、「何も無くて、何も起こらなくて・・でも結果として美しい」のではなく、
「色々有って・・鍛えられて、その結果として美しい健康体」
と言うようなイメージを受けました。
ですので、少し筋肉が隆々としているような逞しさが備わっているように感じますし、感じる果実にも、「果肉の粒」さえ感じるような感覚なんですね。
なので、2018年ものも非常に美味しかったし、海外メディアも同じように評価しているとしても、
「2018年ものと2019年ものの美しさの違い」
も感じたように思います。
色合いも黄色がやや強めでは有りますが、あまり「樽」を感じさせるものでは無く、果実が受けた短い時間での日照の強さみたいなものを表しているのかもしれません。
少しオイリーで、逞しく、口内ですり潰すと石灰的なミネラリティを基礎に、細やかな表情が零れて来ます。それはまた柑橘果実やスパイスに変化し、ノーズへと抜けて行きます。
中域も適度に膨れてくれ、自然で長い余韻から、また果実のニュアンスとミネラリティを感じさせてくれます。
アン・ビュランV.V.は現在、やや締まっていて、やや優しいムルソー=ペリエールみたいな風情ですが、それでも厳しいミネラリティが、
「飲むのはちょっと早いぞ」
と言っているかのようです。
しかしながらアリアンスV.V.は、現在(2021年6月末)でも、開いているとは言わずとも、結構に膨らんでくれるので、それなりに美味しく飲めてしまいます。
なので、このキュヴェとサン=ヴェランとマコン=シェントレは早めに飲んでも良く、アン・ビュランV.V.だけは2~3年は置いて育てていただきたいと思います。相当旨いし、何よりリーズナブルですので、この夏を乗り切る1本に・・いかがでしょうか。ご検討くださいませ。A.C.ブル並み以下の価格ですが、かなりの出来です。お勧めです!
以下は以前のレヴューです。
-----
【三千円を切ったプイィ=フュイッセが91ポイント評価!・・そして今でも美味しく飲める冷ややか果実+膨大なミネラリティ!超お勧めです!】
 2017年ものはスタートで躓いてしまいまして、あっという間にアリアンスV.V.が無くなってしまいました。世界で最もリーズナブルなプイィ=フュイッセです。
2017年ものはスタートで躓いてしまいまして、あっという間にアリアンスV.V.が無くなってしまいました。世界で最もリーズナブルなプイィ=フュイッセです。そしてやはり2018年ものバローはミネラリティが凄い!・・これだけしっかり有るのに・・硬くならないし、熟度は高いのに全くダレないのも不思議ですが・・真実なんですね。
バローの他のワイン同様、果実もたんまりで冷ややかで美味しいんですが、葡萄の高質感が下のクラスよりしっかり感じるんですね。なのでやはり、上のクラスの他のプイィ=フュイッセの区画並みに畑の状態が良くなって来た・・ことの証拠なのかもしれません。
因みにティム・アトキン氏は、このアリアンスV.V.までは評価していて、91点付けています。まぁ・・アン・ビュランとちょっと、間が詰まっちゃっているように感じますよね?・・それに、noisy 的にはサン=ヴェラン・アン・クレシェで90点以上は付けるでしょうから・・。
写真の方も、今回は何とか良いように撮れたようで、深~い凝縮した果実を冷ややかに閉じ込めているミネラリティが見えるような・・?・・気がしませんか?・・しないか~・・。飲んでいただけましたら、その意味が良く判ると思いますので、
「白ワインはあまり飲まないんだよな~」
とおっしゃる方にこそ、この超リーズナブルな高級シャルドネを飲んでいただきたい!・・そう感じています。きっとファンになってくれると期待しています。ご検討くださいませ。
以下は以前のレヴューです。
-----
【万全でした!アドヴォケイトも90点。A.C.ブル価格の村名区画名付き高級シャルドネです!】
 何故かバローは日本でとても安いので、中々やり辛くなってしまっています。某社は何でそんなに安いのか?・・以前、ラシーヌさんから入って来た頃の価格を見ると、とてもじゃないが理解不能です。
何故かバローは日本でとても安いので、中々やり辛くなってしまっています。某社は何でそんなに安いのか?・・以前、ラシーヌさんから入って来た頃の価格を見ると、とてもじゃないが理解不能です。ですが、今はジュリアンが造っていると思われるこのアリアンスV.V.、年を経る毎に「ピュア」になり、バランスが素晴らしくなっています。
昔のダニエル・バローは、これまた昔のコント・ラフォンを思わせるような大きな造りで新樽をしっかり使っていました。今もそれなりに使用していると思いますが、昔の「バリック臭さ」は全く無く、それでも「適度な酸化」で滑らかに、酸の美しさがリアルな果実酸を感じさせてくれる、「新時代の高級シャルドネ」です。
このアリアンスV.V.より上のラインは、少し寝かせた方が良いのは間違い在りませんので、直近に飲むのでしたらアリアンスV.V.をお薦めします。是非飲んでみて下さい!超お勧めです!
以下は以前のレヴューです。
━━━━━
【ミネラリティ溢れる冷ややかな果実!高級シャルドネの複雑性とフィネスを感じさせてくれるスーパーポテンシャルワインです!】
 あのブルゴーニュを代表するドメーヌのラフォンさんちも、ルフレーヴさんちも、生産量に限りの有るコート=ドールを飛び出し、将来性の高いマコンに新たな活躍の場を得た訳ですから、マコンの地がどれほどのポテンシャルを持っているのか、推して知るべし・・だと思います。
あのブルゴーニュを代表するドメーヌのラフォンさんちも、ルフレーヴさんちも、生産量に限りの有るコート=ドールを飛び出し、将来性の高いマコンに新たな活躍の場を得た訳ですから、マコンの地がどれほどのポテンシャルを持っているのか、推して知るべし・・だと思います。確かにコート=ドールよりも南に位置しますし、マコネーとは言いつつも最も南に有るプイィ=フュイッセは、熟度は心配しないでも、ブルゴーニュ・シャルドネと看板を出せるフィネス、エレガンスが出せるかと言う唯一点が、大問題になってくる訳です。
しかしながらこの、ダニエル・バローのプイィ=フュイッセの入門クラスである「アリアンスV.V.」ですら、そんな大問題を簡単に蹴散らしてしまう品質だと言えるのが凄いですよね。3千円でこれだけの高い品質のシャルドネが買える訳ですから、実にありがたいことです。
2016年もののブルゴーニュは、2018年に到着し始めたものの、当初は非常に心配をしていました。しかしながら・・特にシャルドネは、
「・・もしかしたら・・グレートイヤーか?」
などとの言葉がテイスティング中に浮かんできてしまうほどのクオリティを見せるアイテムが多く存在しています。
このアリアンスV.V.も非常に素晴らしい出来でした。リアルワインガイド第62号では、今飲んで 90、ポテンシャル 91、飲み頃予想 2020~2040 と言う評価で、
「このクラスから上は熟成が必要となる」
と書いています。
noisy 的には、この2019年の正月のテイスティングで、
「このプイィ=フュイッセのクラスは、アリアンスV.V.だけは今から飲んでも充分美味しさを受け取れる!」
と感じました。これより上は・・やはり待ちましょうよ・・(^^;; 勿体無いですから。
アリアンスV.V.は、ガラス系の透明感溢れるミネラリティのやや太い芯が存在し、縦構造の確かさを感じさせつつ、凝縮した果実由来のエキスが、少しずつ崩壊を繰り返し要素を放出、表情を豊かにしてくれる・・発展途上に有ります。勿論全開なんて無理ですが、
「この分子崩壊による表情」
こそが開くと言う意味(に近い)ですから、まだ少ないはずのそれを拾うだけでもたっぷり楽しめてしまうほど、ポテンシャルが充分だ・・と言うことなんですね。
勿論、もう皆さんもたっぷり飲まれていてご存知かと思いますが、バローのワインが熟した時のパフォーマンスは物凄いですよね。そこまでは行かないにせよ、
「若いフレッシュな凝縮したシャルドネの美味しさ」
と言う切り口も有る訳で、その部分において、充分な美味しさだと判断します。是非飲んでみてください。3千円のプイィ=フュイッセ、驚かずにお楽しみくださいませ。
以下は以前のレヴューです。
━━━━━
【凄いポテンシャル!しかもほぼデイリー価格です!】
 息子さんのジュリアンが作ったアリアンスVV・・・旨いです!実に美しいプイィ=・フュイッセに仕上がっています。しっかり腕を上げたなと思います。
息子さんのジュリアンが作ったアリアンスVV・・・旨いです!実に美しいプイィ=・フュイッセに仕上がっています。しっかり腕を上げたなと思います。リアルワインガイド第58号は、
「このクオリティでこの値段・・でいいの?」
とまで言ってます。同感・・!休養後に飲んでみてください。お奨めです。
以下は2008年のコメントです。
【むしろ3年ほどの時間が必要です。】
プイィ=フュイッセ・アリアンス・ヴェ / ジュリアン・バロー
若々しく瑞々しいやや大きめの白・黄色の果実・柑橘。グレープ・フルーツっぽくも有る。ミネラルのアロマが強い。サン=ヴェランよりも構造が大きく、とても伸びやか。いつものヴィンテージよりもかなりドライ。
プイィ=フュイッセ・アン・フランス
やや硬い表情。現在はふくらみに掛けるが瑞々しく・・でも硬い。アリアンス・ヴェよりも青みが有る。いつもよりドライだが、肌理の細やかさは上かもしれない。
中級クラスのプイィ=フュイッセですが、ミネラリティが並みのワインよりも高い分、その殻を破る力に2008年は欠けているのかもしれません。現在はどちらも硬く、厳しいです。しかし、ハードなムルソーだと思えばこれも充分に有り。いつものようにマッチョなバローでは無いと思うべきでしょう。
5~10年の熟成でピークを迎えるでしょう。かなり美味しいタイトなシャルドネになると思ってくださいね。お奨めです。
●
2023 Pouilly-Fuisse 1er Cru la Marechaude le Bas
プイィ=フュイッセ・プルミエ・クリュ・ラ・マレショード・ル・バ
【プルミエ・クリュの真価がまさに発揮されて来た2023年でしょう!・・ムルソーで言わば、「クロ・デ・ペリエール」と「ペリエール」の違い!?・・しかしこのル・バも捨てておけないエレガンスが凄いんです!】
 もしご興味がございましたら是非、ラ・マレショード・クロ・ラ・ヴェルシェール2023年のグラス写真をご覧ください。きっと驚かれるでしょう。
もしご興味がございましたら是非、ラ・マレショード・クロ・ラ・ヴェルシェール2023年のグラス写真をご覧ください。きっと驚かれるでしょう。「・・げげっ・・全然違うじゃん!」
そうなんです・・後光が差しているようなクロ・ラ・ヴェルシェールに対し、こちらのル・バの方は、
「透明感が強く、閉じているかのよう」
に見えるんじゃないかと思うんですね。
しかもですね・・ドメーヌでは、しっかり「差」を付けています。価格だけじゃないんですよ・・。
「コルクがプラスティック・コルクで下級クラスと同じ」
なんですね。
ですので、
「選別や収量まで異なるかもしれない」
んです。もちろん、クロ・ラ・ヴェルシェールの方が上・・と言うことなんですね。
 「・・ですが!」
「・・ですが!」確かに今飲んだら、クロ・ラ・ヴェルシェールの方に挙手するはずです。でも少し時間を置くとどうでしょうか・・これは noisy も検証中ですので、はっきりと断言はできないんです。
ですが経験上、例えばクロ・デ・ペリエールとクロが付かないペリエールです。どっちが素晴らしいかと言われれば、単純にはクロ・デ・ペリエールです。
でも長い熟成を経ますと・・それぞれ、結構に違って熟成します。そして20年以上も寝かせて飲みますと、
「・・どっちも違った美味しさが有って、どちらかに決められない・・」
みたいな感じになることが有るんですね。
ですので、
「すぐに飲むならラ・マレショード・クロ・ラ・ヴェルシェール」
「価格優先でラ・マレショード・ル・バ」
かな・・と。
で、実は・・より凄いラ・マレショード・ラ・ヴェルシェールに感じた要素でラ・マレショード・ル・バに無かった要素はほぼ無い・・ただ「大人しい」だけ・・なんですね。だからこのル・バも・・
「とんでもなく旨い!」「美しい!」
です。
いや・・スュール・ラ・ロシュやアンビュラン、レ・クレイを脅かすとは、とんでもないラ・マレショード・・・ラ・ヴェルシェールです。昔はラ・ヴェルシェール、ここまで凄いとは気付きませんでしたが・・良い勉強になりました。
ここまで素晴らしいシャルドネで、ここまで凄いキュヴェは、そう簡単に見つからないと思います。ご検討いただけましたら幸いです。どうぞよろしくお願いします。
以下は以前のレヴューです。
-----
【おそらく・・クロで囲まれたクロ・ラ・ヴェルシェール以外の部分・・で「ル・バ」ですから・・ヴェルシェールの下部の1級。これが今、滅茶美味しいです!】

 これは今、最高に美味しいです!もちろん、最初から全てにおいて・・と言う意味では無く、抜栓直後から徐々に様々な表情を出してくれる・・・と言う意味合いですね。
これは今、最高に美味しいです!もちろん、最初から全てにおいて・・と言う意味では無く、抜栓直後から徐々に様々な表情を出してくれる・・・と言う意味合いですね。黄色や白、そしてクロ・ラ・ヴェルシェールのようにやや色付いた果実・・橙色とかわずかに赤い感じのする柑橘・果実のニュアンスが入り、ほんのりと蜜に近い感じのアロマのトッピングが有ります。
非常に繊細で・・たるんだ贅肉の無い、締まった味わいで、ラ・マレショードが1級畑で有る・・他のクリマとは違う・・と言うような、ワイン自体からのアピールを聞くことが出来ます。
いや・・昔の話しばかりで申し訳ないんですが、ヴェルシェールって・・そこまで凄いとは思っていなかったですね。と言いますか、そこまで感じないと言ったら良いのか判りませんが、
「アリアンスやシャテニエと、わずかに違うくらい・・」
としか捉えていませんでした。
本当に久しぶりに・・おそらく10年振り位じゃないかと思いますが、この1級昇格でどうなっているのか?・・大丈夫か?・・などと思っていた位でしたから、ちょっと余りに良くてビックリしました。
表情の出方は、トップ・キュヴェのアン・ビュランのような芳醇さを感じさせると言うよりは、
「膨大なミネラリティを前面に出しつつ、繊細で冷ややかに果実・有機物の表情を出してくる」
と言う感じです。
 クロ・ラ・ヴェルシェールの方が見た感じで色合いがわずかに濃く、こちらがわずかに淡いだけ・・で、
クロ・ラ・ヴェルシェールの方が見た感じで色合いがわずかに濃く、こちらがわずかに淡いだけ・・で、「表情はかなり似ている」
と言えますし、
「今飲んでの点を付けるとするなら、こちらが上」
です。
ですが、クロ・ラ・ヴェルシェールの複雑性は相当に半端無く、
「明らかにスュール・ラ・ロシュと総合ポイントでタメを張る・・場合によっては?」
と・・、クロ・ラ・ヴェルシェールのポテンシャルが上です。残念ながらクロ・ラ・ヴェルシェール2022はその半端無いポテンシャルゆえに、未だ全貌を表しきれない・・と言うのが正解だと感じます。
いや・・今回、
「11アイテムのテイスティング」
をさせていただいたんですが・・何か別のアイテムのテイスティングをしているような気になってきました。それは・・あの「密度お化け」のラミーです。ニュアンスはラミーのミネラリティに近いものを感じます。
そもそものバローのワインは、果実がたんまり有って、ピュアだがバリックの風味が効いていて、ミネラリティも半端無い・・でも時に残糖の甘みが有る・・と言う感じでした。
それが今、ジュリアンの時代になって、
「ピュアで徐々にナチュールに近付いてきて、ミネラリティが途轍もない感じに増大し、そこに果実が美しくたなびき、伸び、余韻とも素晴らしい・・残糖はほぼ無い」
と言う・・理想に近い感じになったと感じています。
素晴らしい1級です!・・価格もリーズナブルで狙い目ではないでしょうか。お薦めします!・・是非とも飲んでみてください!
●
2023 Pouilly-Fuisse 1er Cru la Marechaude Clos la Verchere
プイィ=フュイッセ・プルミエ・クリュ・ラ・マレショード・クロ・ラ・ヴェルシェール
【・・す・・凄い!・・このチリチリと口内で感じる複雑なテクスチュアに潜む複雑精妙な味わいに度肝を抜かれるでしょう!・・これも一推し!】
 圧巻です!・・もはやこの「マレショード」2種・・トップ・キュヴェと言って良いんじゃないでしょうか。いずれ確かめるつもりではおりますが、
圧巻です!・・もはやこの「マレショード」2種・・トップ・キュヴェと言って良いんじゃないでしょうか。いずれ確かめるつもりではおりますが、「アンビュランとスュール・ラ・ロシュの数が無い」
し、
「マレショード2種も追加できるかまだ判らない」
ので、身動きが取れないんですね。
しかしマレショード2アイテムに関しては、最近のリリースですから飲んで確かめない訳には行かないので開けてしまいました。
で、この「クロ・ラ・ヴェルシェール」・・・ある意味、コート・ド・ボーヌのグラン・クリュに匹敵するんじゃないか疑惑?・・を持ってしまいました。
「どえりゃぁ・・旨いです!」
アリアンスV.V.の美しいグラス写真を凌ぐ・・まさに
「グラン・クリュ並みの絵」
だと思います。
 表現が非常に細かいです。そして緻密・・品格が滲んで来ます。そしてとんでもなく複雑です。口内を優しくチリチリと刺激する・・ややスパイシーな印象・・なんなんでしょうか・・余り経験の無い表情ですが、非常に心地良いです。
表現が非常に細かいです。そして緻密・・品格が滲んで来ます。そしてとんでもなく複雑です。口内を優しくチリチリと刺激する・・ややスパイシーな印象・・なんなんでしょうか・・余り経験の無い表情ですが、非常に心地良いです。「オレンジの皮を手で捻ったような感覚」
でしょうか。
そして、ミネラリティの組成もちょっとやそっとじゃ分析しかねるほどに複雑だと思うんですね。
精緻でいて豪奢な表情に驚き、グラスを置いてもなお・・その印象を引きずります。これって・・もしかして・・
「クロ・ラ・ヴェルシェールってバローのトップ・キュヴェと言って良いんじゃないの?・・アンビュランやスュール・ラ・ロシュはこれより凄いの?」
と・・(^^;;
「なんだよ・・開けて確かめろよ!」
と言われてしまうと思いますが、何しろ数が無いもんですから・・申し訳ない。
そしてこのクロ・ラ・ヴェルシェールでは無い方のマレショード・ル・バとの違いですが、単純に言って、今・・結構に饒舌なのがこのクロ・ラ・ヴェルシェール、少しだけ大人しい・・重心が少しだけ低いのがマレショード・ル・バです。寿命はマレショード・ル・バの方が長そうで、
「クロ・ラ・ヴェルシェールをマレショードル・・バが熟成でいずれ追い越すか、追い越せずに終わるか?」
と言うところです。
これ、飲まないと損です。素晴らしい!・・いや、ワインって楽しいですね!シャルドネ万歳!・・超お薦めします。今飲んでもしっかりこの凄さ、確かめられますと思います!
以下は以前のレヴューです。
-----
【レ・クレイも復活してラ・ロシュと並んだ?越した?ところに、この1級のクロ・ラ・ヴェルシェールも末脚鋭く走り込んで来て、バローのラインナップは物凄いことに!!】
 その昔は、
その昔は、「プイィ=フュイッセ・ラ・ヴェルシェール」
だったか・・そんな名前で出ていました。noisy も扱っていました。
輸入がサンリバティさんに移ってからは、しばらくはどうだったか・・余り覚えていませんが、気付けば・・
「2020年に1級畑に認定された!」
んですが入荷は無く、
「しかも上部のクロで囲まれた部分と、下部のそれ以外の部分が別々になってリリース!」
されたんですね。
で、ようやくこの2022年もので、昔、ラ・ヴェルシェールとしてリリースされていたワインとご対面・・この1級ラ・マレショード・クロ・ラ・ヴェルシェールになっていた訳です。
 濃密で、繊細さも有りつつ、果実の出方が他のバローのプイィ=フュッセとは違うイメージに感じられました。
濃密で、繊細さも有りつつ、果実の出方が他のバローのプイィ=フュッセとは違うイメージに感じられました。温かみが有り、冷ややかでも有り・・そんな感じが柑橘果実の表情でも感じます。単に黄色や白と言うよりも、少し色付いた感じ・・橙とか、より良く熟した感じが有り、ネットリしていて・・蜜っぽい感じもします。
滅茶複雑感が有り、いずれ様々な表情が出てくるイメージですが、その進み具合はややゆっくりしています。ですので、
「ポテンシャルが凄い!・・そのため、少し表情が出てくるまで待つべき」
かと思います。
反対に・・今飲んでよりまとまっていて美味しいのは、この・・
「クロに囲まれていない方の1級ラ・マレショード・ル・バの方!」
です。
明らかにポテンシャルはこちらですが、開いてゆくスピードが遅いので・・もう少し休めるべきでしょう。早めに飲むなら「ル・バ」、待てるようでしたら、「クロ・ラ・ヴェルシェール」にしたらいかがでしょうか。
あの「ヴェルシェール」がここまで進化しているとは・・驚きでした。飲んでみてください。超お薦めします!
●
2023 Pouilly-Fuisse 1er Cru Sur la Roche
プイィ=フュイッセ・プルミエ・クリュ・スュール・ラ・ロシュ
【アン・ビュランと事実上の「両輪」を成す「スュール・ラ・ロシュ」!・・これを飲めば「バロー...半端無いぞ!」と判ります。】
現在のドメーヌ・バローのトップ・キュヴェはアン・ビュランV.V.であることは明白ですが、
「気付かずにいつの間にかス~っとアン・ビュランの真後ろにピタッと引っ付いていた!」
と言うのが noisy の印象です。昔は単に「ラ・ロシュ」だったり「スュール・ラ・ロシュ」だったりしていまして、確かに大きな石灰岩的なイメージを持った良いプイィ=フュイッセでは有りました。
それがいつ頃でしたでしょうか・・10年位かな・・まぁ・・このラ・ロシュの入荷が無いことも有ったと思いますので定かでは無いですが、
「・・あれ?・・こんなにラ・ロシュって素晴らしかったっけ?」
と感じた瞬間から、毎年のように、グっ・・ググっ・・と伸びて来まして、
「ボトルでの熟成が必要なアン・ビュランV.V.に対し、リリース時にすでに圧巻な表情を漏らしてくれるスュール・ラ・ロシュ!」
と言うことが判明したんですね。
ですから、まぁ・・言ってみれば・・ムルソー・クロ・デ・ペリエールがアン・ビュランで、ムルソー=ペリエール、もしくはムルソー=ジュヌヴリエールがスュール・ラ・ロシュだと思っていただいて良いかと・・あ、表情は幾分異なりますけどね。アン・ビュランV.V.は肥えていて複雑でオイリー・・スュール・ラ・ロシュは肥えてはいないものの充分であり、硬度が高く品のあるミネラリティを多分に含んだポテンシャルをしっかり感じられる1級畑ものです。
ですので、バローのトップ・キュヴェを早く飲みたい方はこのスュール・ラ・ロシュをのんびり飲むのが良いかと思います。ぜひご検討くださいませ。超お薦めします!
以下は以前のレヴューです。
-----
【素晴らしい出来です!・・ヴェルジッソンの厳ついミネラリティを大量に取り込み、熱量をエキスに溶け込ませ、大いなる美しさに変えたブルゴーニュの1級格を直に感じさせる味わいです!】
 バローも2022年もので大きく変化したと感じさせる素晴らしい出来でした。
バローも2022年もので大きく変化したと感じさせる素晴らしい出来でした。
言ってしまえばそもそもはダニエル・バローの白眉と言われたアン・ビュランV.V.と、そして対になるべきレ・クレイは・・植え替えで「V.V.」表記を失い、いつも間にかこの「スュール・ラ・ロシュ」にその座を明け渡していた訳です。
ですが2020年に1級の座を得た「レ・クレイ」は、2021年までスュール・ラ・ロシュの後塵を浴びていたとも言えますが、
「2022年ものは2021年ものまでのレ・クレイでは無い!」
と言い切れるほど変身していますし、このスュール・ラ・ロシュ2022年もまた、そのとんでもないミネラリティの総量を、
「まるで美しく着飾った平安~室町の作り込まれた武将の鎧のよう」
に表現しつつ、適切な熟度を得た冷ややかな柑橘果実の表情を、
「雅びな雅楽の音色」
のように??・・(^^;; 感じさせてくれます。
まぁ・・ヴェルジッソンは本当に凄い丘?・・台地でして、切り立った岩場全体がその石灰の地層を見せてくれます。
 その写真を見ている性もあろうかと思いますが、その石灰岩とほんの僅かな土のサンドイッチを長く持続する余韻で味わっているかのような・・凄い味わいと、その雅楽のような柑橘果実のアロマのノーズが、このラ・ロシュの半端無い魅力で有ると感じます。
その写真を見ている性もあろうかと思いますが、その石灰岩とほんの僅かな土のサンドイッチを長く持続する余韻で味わっているかのような・・凄い味わいと、その雅楽のような柑橘果実のアロマのノーズが、このラ・ロシュの半端無い魅力で有ると感じます。
面白いのは、マコン=ヴェルジッソン・ラ・ロシュは、このプイィ=フュイッセ・ラ・ロシュの下部に接する畑でして、
「このプイィ=フュイッセ・スュール・ラ・ロシュの芯の部分にマコン=ヴェルジッソン・ラ・ロシュも少し同居している」
と感じられるんですね・・久しぶりのマコン=ヴェルジッソンのテイスティングでして・・さらには並べて飲んだので・・(^^;;・・なるほど~と・・改めて感じました。
ニール・マーティンさんは上値94ポイント止まりのようですが、いや~・・どうでしょう・・noisy は低すぎるかな・・と感じます。飲み進めるうちに、
「当初は無かった表情がどんどん変化し、深み、厚み、押し出しが出てくる・・凄い伸び!」
を感じます。
2022年のドメーヌ・バロー、今までに無く素晴らしいと感じました。細かな部分は他のコラムでも書かせていただきます。ぜひ飲んでみてください。超お薦めします!
以下は以前のレヴューです。
-----
【ひっくり返るか、のけ反るか?・・素晴らしいアロマに出会って、取る行動はあなた次第!・・「わおっ!」】
 いつ頃からでしょうか、この「ラ・ロシュ」もしくは「スュール・ラ・ロシュ」がリリースされ、いつの間にか、
いつ頃からでしょうか、この「ラ・ロシュ」もしくは「スュール・ラ・ロシュ」がリリースされ、いつの間にか、
「バローの最高峰、アン・ビュランの地位を脅かす評価を得始めた!」
のは。
いや・・そんなに遠い話しじゃないですよね。リアルワインガイド誌でも、時にはアン・ビュランを超える評価をしていたと記憶しています。ではなぜそんな評価をされるようになったのか・・
それは・・
「・・美味しいから・・」
です。
それを言っちゃ・・実も蓋も無い・・。ですが、
「この超絶に上質なアロマを嗅いでしまったら、ひっくり返るか、のけ反らされてしまうか!」
と言えるほどに・・素晴らしいんですね~・・果実も、
「そんじょそこらのスーパーさんでは出会えないレベル」
と言いたくなるほど高級感がバリバリです。
その高級果実に、
「まさにロッシュ!・・岩・・英語じゃロック!」
を思わせる見事なミネラリティを受け取らされてしまうから・・に違い無いでしょう。
 この何年かの間に、ドメーヌ・バローは大きく変革されてきました。noisy たちが知っている1990年代のバローとは・・
この何年かの間に、ドメーヌ・バローは大きく変革されてきました。noisy たちが知っている1990年代のバローとは・・
「全く違う!」
と言って良いです。
どう違うのか?・・端的に言ってしまうなら、
「アルザスのマルセル・ダイスが辿った道と似ている」
と思う訳です。
マルセルも、それまでのもの凄い評価を捨て、ビオに走った訳です。そのため一時評価を落としましたし、人気もだいぶ落ちた時期が有ったんです。ちょっと早すぎたかもしれませんし、一気にやり過ぎた感も有ったのかもしれません。しかし、ようやく時代はマルセルに追いついた・・そして彼は何となくの引退の時期を迎えたことになります。
ドメーヌ・バローは2010年頃までは、その新樽由来の香りは徐々に減って来ていたことは確かですが、ビオに大きく舵を切ることは有りませんでした。徐々に・・自然な農法に向かっているのは間違い在りませんし、
「So2使用の量の少なさ」
は、毎年のように進んでいると感じます。
この素晴らしい色彩を是非ご覧ください。マンモスな量のロックなミネラリティを、さらに黄色い果実で覆っているかのような見栄えのする画像です。これほどまでにミネラリティが強いと、中々・・黄色い色は付き辛い訳です。しかし、
「2020年ものを凌ぐ色彩!」
をしているんですね・・これが何を物語っているのか・・是非ご自身でお確かめください・・「・・わおっ!」・・間違い無し!です。
以下は以前のレヴューです。
-----
【抜栓後、15~20分後に現れる素晴らしい表情に・・悶絶!・・あのアン・ビュランV.V.を凌ぐ評価が散見されるのも理解できるでしょう!】
 晴れて1級畑を名乗った「スュール・ラ・ロシュ」です。2012年もののレヴューをすぐ下に掲載していますが、5.150円って・・今とほとんど変わりませんよね?・・このユーロが140円に近い時代に・・本当に有難いことです。
晴れて1級畑を名乗った「スュール・ラ・ロシュ」です。2012年もののレヴューをすぐ下に掲載していますが、5.150円って・・今とほとんど変わりませんよね?・・このユーロが140円に近い時代に・・本当に有難いことです。
そしてエチケットもグッとジェントルになった感じがしますが、この数年はアン・ビュランV.V.を脅かす存在になったこのワイン・・
「今飲んでもその素晴らしい姿を垣間見ることが出来る!」
んですよ・・。
そう、抜栓後..15~20分位経過したタイミングでしょうか。
このような高級シャルドネが、リリース直後から最高に素晴らしい姿を見せてくれることは、まずありえません。相当に旨い!・・と感じたとしてもそれはいいところ、40~50%が関の山です。
そう思っていただいた上で・・この、抜栓から少し時間が経った時の表情が、実に悶絶もの・・なんですね。
非常にドライで、まるで石、岩のような鉱物感に柑橘、果実の美味しいワインなんですが、
「口内でチリチリ、キラキラと弾ける微細な表情!」
 が、まるでボーヌの凄いシャルドネが見せる表情と瓜二つ・・なんです。
が、まるでボーヌの凄いシャルドネが見せる表情と瓜二つ・・なんです。
このスュール・ラ・ロシュは、ムルソーの大理石感とはまた違った、ちょっと角の取れた「丸い石・岩」みたいなニュアンスが特徴かな?・・と思っているんですが、それを抜栓直後から感じつつ飲んでいると、時間差で・・チリチリ、キラキラしてくるんです。
これには参っちゃいました・・。レ・クレイもアン・ビュランも素晴らしいんですが、この今のタイミングでどうしても飲むなら、
「このスュール・ラ・ロシュが白眉!」
でしょう。
またこの数年、スュール・ラ・ロシュの評価が鰻登りで、確かでは有りませんが、リアルワインガイドでもアン・ビュランV.V.とほぼ同じか、時により超えた評価も有ったように思います。noisy もまた、この何年かは同じように思っていますが、
「数年経ったらアン・ビュランV.V.が途方もない魅力を連れてくるのは判っているので・・」
やはり結果的には今のところはポテンシャルでアン・ビュランV.V.が上...と判断しています。
でもそれにしてもこのスュール・ラ・ロシュ2020年、滅茶苦茶旨いです。是非飲んでみて下さい!お勧めします!
以下は以前のレヴューです。
-----
【今や評価はダニエル・バローの第二位の地位!ポテンシャル高いです!前回はラシーヌさんものですが¥5.150でのご案内でした!】
かなりリーズナブルです。こちらのご案内はちょうど3年前頃ですので、飲んでOK・・かと思います。サンリバティーさんから条件をいただきました。限定数量ですのでお早めにどうぞ!
━━━━━
【今はまだ飲まないでください・・でも必ず手に入れてほしいアイテムの2~3番目です!】
飲めませんので以前のコメントを掲載しています。非常に少ないです。このラ・ロシュは、以前はバローさんの3番目のワインだったんですが、樹齢の上昇や葡萄の選別により、2番目に躍り出たキュヴェです。ですが、レ・クレとの差は微妙だと思います。むしろ好みの差と言えると思います。
2012プイィ=フュイッセ・スュール・ラ・ロシュ
蜜、高級なフルーツ、コッテリ感・・高級なシャルドネ特有の存在感あるフィネス。ドライで集中している。まだ硬いが要素のバランスが取れている。コルトン=シャルルマーニュ的な硬さのあるプイシ=フュイッセ。
2012プイィ=フュイッセ・レ・クレ
PKさんが「もっとも偉大なブルゴーニュの白ワイン」にアン・ビュランと共に選んだだけのことはある素晴らしいワイン。瑞々しく気高いミネラリティを多く持つ。精緻な質感、中域も適度に膨らみがあるので一応は飲めるが・・3~5年は待つべき。しっとりとした余韻が長く続き残る・・・美味しい。
2012プイィ=フュイッセ・アン・ビュラン・ヴィエイユ・ヴィーニュ
実に美しい黄色。軽やかなエレガンス・・・天使の羽衣?奥深い味わいの構造。凝縮。緻密。精緻。伸び。ドライ。瑞々しく良い表現をタップリと内封した液体。伸ばせばどこまでも延びて行くようなミネラリティ。高級感。ボーヌの頂上クラスに匹敵する仕上がり。
まぁ、どれも素晴らしいんですが・・やっぱりココに来るとアン・ビュランの凄さが光ります。先日飲んだ1986年ビアンヴィニュ・バタール=モンラッシェと同様なミネラリティでした。そしてドライなのに・・・甘いんだな・・・・(^^;; 凄い仕上がりですが、飲み頃はかなり先・・・アン・ビュランは5年後以降に飲まれてくださいね。
以下は以前のコメントです。
━━━━━
【さすがのアン・ビュラン!!しかしこの冷たさは!】
アン・ビュランと同格のレ・クレはいつものように数が無く、飲めませんでした。アン・ビュランですが・・・これにはビックリですよ。こんなアン・ビュランは、毎年のように10年以上飲んでますが・・・切れ味鋭い氷の刃のようです・・・そして、フリーズされた果実を閉じ込めているかのようです。
現在はまだ全くその全貌を見せません。余分な成分を全く持たない、とても硬いムルソー・シャルムのようです。少なくとも2年・・・置いて欲しいと思います。ダニエル・バローもエレガントな味わいに変身中・・本当にそうなのか?・・ちょっと疑念は残りますが、いずれ結果も出るでしょう。少ないのでお早目にどうぞ!
以下は2008年のコメントです。
━━━━━
【この2アイテムは・・・飲むのを躊躇してください!】
プイィ=フュイッセ・アン・ビュラン・ヴィエイユ・ヴィーニュ
やはりこれは凄いワイン。凝縮感とミネラリティの塊。密度の凄みを思い知る。なのに繊細だ。呆然とさせられる。
上記はテイスティング時のメモそのもの・・・です。内容よりも気持ちを読み取っていただいたほうが・・・近いと思います。何せ、テイスティングの最後の方は、同じような表現になってしまうのを避けるために簡略化して書いている場合が多いからです。
ラ・ロシュは飲めるんですが、ポテンシャルを考えると、「勿体無いかな?」という想いが先に立ってしまうほど・・・です。素晴らしいプイィ=フュイッセなので、このコラムではこのラ・ロッシュを一押しに致します。
レ・クレは申し訳有りません・・・あまりに少なく、飲めませんでした。しかし、アン・ビュランと共にPKさんに最高の評価をされているだけのことは・・・毎年のテイスティングで感じています。恐らくですが、アン・ビュランと双璧でしょう。
で、アン・ビュランVVですが・・・これはやはり「化け物」です。どう有っても漲るポテンシャルを隠し通すことを拒絶しています。まさに漲っているイメージは、極上のムルソー1級と同様・・・。もしかしたら今までにバローが生み出したプイィ=フュイッセで一番の品質かもしれないとさえ思ってしまいます。凝縮感とミネラリティの塊。しかし厳しさもしっかり閉じ込めていますので、確実に熟成が必要です。
この3つは・・・最低5年・・・待ってください。でも・・・実は今でも飲めるワインでも有ります。ポテンシャルを隠し切れないから・・です。お奨めします。
「気付かずにいつの間にかス~っとアン・ビュランの真後ろにピタッと引っ付いていた!」
と言うのが noisy の印象です。昔は単に「ラ・ロシュ」だったり「スュール・ラ・ロシュ」だったりしていまして、確かに大きな石灰岩的なイメージを持った良いプイィ=フュイッセでは有りました。
それがいつ頃でしたでしょうか・・10年位かな・・まぁ・・このラ・ロシュの入荷が無いことも有ったと思いますので定かでは無いですが、
「・・あれ?・・こんなにラ・ロシュって素晴らしかったっけ?」
と感じた瞬間から、毎年のように、グっ・・ググっ・・と伸びて来まして、
「ボトルでの熟成が必要なアン・ビュランV.V.に対し、リリース時にすでに圧巻な表情を漏らしてくれるスュール・ラ・ロシュ!」
と言うことが判明したんですね。
ですから、まぁ・・言ってみれば・・ムルソー・クロ・デ・ペリエールがアン・ビュランで、ムルソー=ペリエール、もしくはムルソー=ジュヌヴリエールがスュール・ラ・ロシュだと思っていただいて良いかと・・あ、表情は幾分異なりますけどね。アン・ビュランV.V.は肥えていて複雑でオイリー・・スュール・ラ・ロシュは肥えてはいないものの充分であり、硬度が高く品のあるミネラリティを多分に含んだポテンシャルをしっかり感じられる1級畑ものです。
ですので、バローのトップ・キュヴェを早く飲みたい方はこのスュール・ラ・ロシュをのんびり飲むのが良いかと思います。ぜひご検討くださいませ。超お薦めします!
以下は以前のレヴューです。
-----
【素晴らしい出来です!・・ヴェルジッソンの厳ついミネラリティを大量に取り込み、熱量をエキスに溶け込ませ、大いなる美しさに変えたブルゴーニュの1級格を直に感じさせる味わいです!】
 バローも2022年もので大きく変化したと感じさせる素晴らしい出来でした。
バローも2022年もので大きく変化したと感じさせる素晴らしい出来でした。言ってしまえばそもそもはダニエル・バローの白眉と言われたアン・ビュランV.V.と、そして対になるべきレ・クレイは・・植え替えで「V.V.」表記を失い、いつも間にかこの「スュール・ラ・ロシュ」にその座を明け渡していた訳です。
ですが2020年に1級の座を得た「レ・クレイ」は、2021年までスュール・ラ・ロシュの後塵を浴びていたとも言えますが、
「2022年ものは2021年ものまでのレ・クレイでは無い!」
と言い切れるほど変身していますし、このスュール・ラ・ロシュ2022年もまた、そのとんでもないミネラリティの総量を、
「まるで美しく着飾った平安~室町の作り込まれた武将の鎧のよう」
に表現しつつ、適切な熟度を得た冷ややかな柑橘果実の表情を、
「雅びな雅楽の音色」
のように??・・(^^;; 感じさせてくれます。
まぁ・・ヴェルジッソンは本当に凄い丘?・・台地でして、切り立った岩場全体がその石灰の地層を見せてくれます。
 その写真を見ている性もあろうかと思いますが、その石灰岩とほんの僅かな土のサンドイッチを長く持続する余韻で味わっているかのような・・凄い味わいと、その雅楽のような柑橘果実のアロマのノーズが、このラ・ロシュの半端無い魅力で有ると感じます。
その写真を見ている性もあろうかと思いますが、その石灰岩とほんの僅かな土のサンドイッチを長く持続する余韻で味わっているかのような・・凄い味わいと、その雅楽のような柑橘果実のアロマのノーズが、このラ・ロシュの半端無い魅力で有ると感じます。面白いのは、マコン=ヴェルジッソン・ラ・ロシュは、このプイィ=フュイッセ・ラ・ロシュの下部に接する畑でして、
「このプイィ=フュイッセ・スュール・ラ・ロシュの芯の部分にマコン=ヴェルジッソン・ラ・ロシュも少し同居している」
と感じられるんですね・・久しぶりのマコン=ヴェルジッソンのテイスティングでして・・さらには並べて飲んだので・・(^^;;・・なるほど~と・・改めて感じました。
ニール・マーティンさんは上値94ポイント止まりのようですが、いや~・・どうでしょう・・noisy は低すぎるかな・・と感じます。飲み進めるうちに、
「当初は無かった表情がどんどん変化し、深み、厚み、押し出しが出てくる・・凄い伸び!」
を感じます。
2022年のドメーヌ・バロー、今までに無く素晴らしいと感じました。細かな部分は他のコラムでも書かせていただきます。ぜひ飲んでみてください。超お薦めします!
以下は以前のレヴューです。
-----
【ひっくり返るか、のけ反るか?・・素晴らしいアロマに出会って、取る行動はあなた次第!・・「わおっ!」】
 いつ頃からでしょうか、この「ラ・ロシュ」もしくは「スュール・ラ・ロシュ」がリリースされ、いつの間にか、
いつ頃からでしょうか、この「ラ・ロシュ」もしくは「スュール・ラ・ロシュ」がリリースされ、いつの間にか、「バローの最高峰、アン・ビュランの地位を脅かす評価を得始めた!」
のは。
いや・・そんなに遠い話しじゃないですよね。リアルワインガイド誌でも、時にはアン・ビュランを超える評価をしていたと記憶しています。ではなぜそんな評価をされるようになったのか・・
それは・・
「・・美味しいから・・」
です。
それを言っちゃ・・実も蓋も無い・・。ですが、
「この超絶に上質なアロマを嗅いでしまったら、ひっくり返るか、のけ反らされてしまうか!」
と言えるほどに・・素晴らしいんですね~・・果実も、
「そんじょそこらのスーパーさんでは出会えないレベル」
と言いたくなるほど高級感がバリバリです。
その高級果実に、
「まさにロッシュ!・・岩・・英語じゃロック!」
を思わせる見事なミネラリティを受け取らされてしまうから・・に違い無いでしょう。
 この何年かの間に、ドメーヌ・バローは大きく変革されてきました。noisy たちが知っている1990年代のバローとは・・
この何年かの間に、ドメーヌ・バローは大きく変革されてきました。noisy たちが知っている1990年代のバローとは・・「全く違う!」
と言って良いです。
どう違うのか?・・端的に言ってしまうなら、
「アルザスのマルセル・ダイスが辿った道と似ている」
と思う訳です。
マルセルも、それまでのもの凄い評価を捨て、ビオに走った訳です。そのため一時評価を落としましたし、人気もだいぶ落ちた時期が有ったんです。ちょっと早すぎたかもしれませんし、一気にやり過ぎた感も有ったのかもしれません。しかし、ようやく時代はマルセルに追いついた・・そして彼は何となくの引退の時期を迎えたことになります。
ドメーヌ・バローは2010年頃までは、その新樽由来の香りは徐々に減って来ていたことは確かですが、ビオに大きく舵を切ることは有りませんでした。徐々に・・自然な農法に向かっているのは間違い在りませんし、
「So2使用の量の少なさ」
は、毎年のように進んでいると感じます。
この素晴らしい色彩を是非ご覧ください。マンモスな量のロックなミネラリティを、さらに黄色い果実で覆っているかのような見栄えのする画像です。これほどまでにミネラリティが強いと、中々・・黄色い色は付き辛い訳です。しかし、
「2020年ものを凌ぐ色彩!」
をしているんですね・・これが何を物語っているのか・・是非ご自身でお確かめください・・「・・わおっ!」・・間違い無し!です。
以下は以前のレヴューです。
-----
【抜栓後、15~20分後に現れる素晴らしい表情に・・悶絶!・・あのアン・ビュランV.V.を凌ぐ評価が散見されるのも理解できるでしょう!】
 晴れて1級畑を名乗った「スュール・ラ・ロシュ」です。2012年もののレヴューをすぐ下に掲載していますが、5.150円って・・今とほとんど変わりませんよね?・・このユーロが140円に近い時代に・・本当に有難いことです。
晴れて1級畑を名乗った「スュール・ラ・ロシュ」です。2012年もののレヴューをすぐ下に掲載していますが、5.150円って・・今とほとんど変わりませんよね?・・このユーロが140円に近い時代に・・本当に有難いことです。そしてエチケットもグッとジェントルになった感じがしますが、この数年はアン・ビュランV.V.を脅かす存在になったこのワイン・・
「今飲んでもその素晴らしい姿を垣間見ることが出来る!」
んですよ・・。
そう、抜栓後..15~20分位経過したタイミングでしょうか。
このような高級シャルドネが、リリース直後から最高に素晴らしい姿を見せてくれることは、まずありえません。相当に旨い!・・と感じたとしてもそれはいいところ、40~50%が関の山です。
そう思っていただいた上で・・この、抜栓から少し時間が経った時の表情が、実に悶絶もの・・なんですね。
非常にドライで、まるで石、岩のような鉱物感に柑橘、果実の美味しいワインなんですが、
「口内でチリチリ、キラキラと弾ける微細な表情!」
 が、まるでボーヌの凄いシャルドネが見せる表情と瓜二つ・・なんです。
が、まるでボーヌの凄いシャルドネが見せる表情と瓜二つ・・なんです。このスュール・ラ・ロシュは、ムルソーの大理石感とはまた違った、ちょっと角の取れた「丸い石・岩」みたいなニュアンスが特徴かな?・・と思っているんですが、それを抜栓直後から感じつつ飲んでいると、時間差で・・チリチリ、キラキラしてくるんです。
これには参っちゃいました・・。レ・クレイもアン・ビュランも素晴らしいんですが、この今のタイミングでどうしても飲むなら、
「このスュール・ラ・ロシュが白眉!」
でしょう。
またこの数年、スュール・ラ・ロシュの評価が鰻登りで、確かでは有りませんが、リアルワインガイドでもアン・ビュランV.V.とほぼ同じか、時により超えた評価も有ったように思います。noisy もまた、この何年かは同じように思っていますが、
「数年経ったらアン・ビュランV.V.が途方もない魅力を連れてくるのは判っているので・・」
やはり結果的には今のところはポテンシャルでアン・ビュランV.V.が上...と判断しています。
でもそれにしてもこのスュール・ラ・ロシュ2020年、滅茶苦茶旨いです。是非飲んでみて下さい!お勧めします!
以下は以前のレヴューです。
-----
【今や評価はダニエル・バローの第二位の地位!ポテンシャル高いです!前回はラシーヌさんものですが¥5.150でのご案内でした!】
かなりリーズナブルです。こちらのご案内はちょうど3年前頃ですので、飲んでOK・・かと思います。サンリバティーさんから条件をいただきました。限定数量ですのでお早めにどうぞ!
━━━━━
【今はまだ飲まないでください・・でも必ず手に入れてほしいアイテムの2~3番目です!】
飲めませんので以前のコメントを掲載しています。非常に少ないです。このラ・ロシュは、以前はバローさんの3番目のワインだったんですが、樹齢の上昇や葡萄の選別により、2番目に躍り出たキュヴェです。ですが、レ・クレとの差は微妙だと思います。むしろ好みの差と言えると思います。
2012プイィ=フュイッセ・スュール・ラ・ロシュ
蜜、高級なフルーツ、コッテリ感・・高級なシャルドネ特有の存在感あるフィネス。ドライで集中している。まだ硬いが要素のバランスが取れている。コルトン=シャルルマーニュ的な硬さのあるプイシ=フュイッセ。
2012プイィ=フュイッセ・レ・クレ
PKさんが「もっとも偉大なブルゴーニュの白ワイン」にアン・ビュランと共に選んだだけのことはある素晴らしいワイン。瑞々しく気高いミネラリティを多く持つ。精緻な質感、中域も適度に膨らみがあるので一応は飲めるが・・3~5年は待つべき。しっとりとした余韻が長く続き残る・・・美味しい。
2012プイィ=フュイッセ・アン・ビュラン・ヴィエイユ・ヴィーニュ
実に美しい黄色。軽やかなエレガンス・・・天使の羽衣?奥深い味わいの構造。凝縮。緻密。精緻。伸び。ドライ。瑞々しく良い表現をタップリと内封した液体。伸ばせばどこまでも延びて行くようなミネラリティ。高級感。ボーヌの頂上クラスに匹敵する仕上がり。
まぁ、どれも素晴らしいんですが・・やっぱりココに来るとアン・ビュランの凄さが光ります。先日飲んだ1986年ビアンヴィニュ・バタール=モンラッシェと同様なミネラリティでした。そしてドライなのに・・・甘いんだな・・・・(^^;; 凄い仕上がりですが、飲み頃はかなり先・・・アン・ビュランは5年後以降に飲まれてくださいね。
以下は以前のコメントです。
━━━━━
【さすがのアン・ビュラン!!しかしこの冷たさは!】
アン・ビュランと同格のレ・クレはいつものように数が無く、飲めませんでした。アン・ビュランですが・・・これにはビックリですよ。こんなアン・ビュランは、毎年のように10年以上飲んでますが・・・切れ味鋭い氷の刃のようです・・・そして、フリーズされた果実を閉じ込めているかのようです。
現在はまだ全くその全貌を見せません。余分な成分を全く持たない、とても硬いムルソー・シャルムのようです。少なくとも2年・・・置いて欲しいと思います。ダニエル・バローもエレガントな味わいに変身中・・本当にそうなのか?・・ちょっと疑念は残りますが、いずれ結果も出るでしょう。少ないのでお早目にどうぞ!
以下は2008年のコメントです。
━━━━━
【この2アイテムは・・・飲むのを躊躇してください!】
プイィ=フュイッセ・アン・ビュラン・ヴィエイユ・ヴィーニュ
やはりこれは凄いワイン。凝縮感とミネラリティの塊。密度の凄みを思い知る。なのに繊細だ。呆然とさせられる。
上記はテイスティング時のメモそのもの・・・です。内容よりも気持ちを読み取っていただいたほうが・・・近いと思います。何せ、テイスティングの最後の方は、同じような表現になってしまうのを避けるために簡略化して書いている場合が多いからです。
ラ・ロシュは飲めるんですが、ポテンシャルを考えると、「勿体無いかな?」という想いが先に立ってしまうほど・・・です。素晴らしいプイィ=フュイッセなので、このコラムではこのラ・ロッシュを一押しに致します。
レ・クレは申し訳有りません・・・あまりに少なく、飲めませんでした。しかし、アン・ビュランと共にPKさんに最高の評価をされているだけのことは・・・毎年のテイスティングで感じています。恐らくですが、アン・ビュランと双璧でしょう。
で、アン・ビュランVVですが・・・これはやはり「化け物」です。どう有っても漲るポテンシャルを隠し通すことを拒絶しています。まさに漲っているイメージは、極上のムルソー1級と同様・・・。もしかしたら今までにバローが生み出したプイィ=フュイッセで一番の品質かもしれないとさえ思ってしまいます。凝縮感とミネラリティの塊。しかし厳しさもしっかり閉じ込めていますので、確実に熟成が必要です。
この3つは・・・最低5年・・・待ってください。でも・・・実は今でも飲めるワインでも有ります。ポテンシャルを隠し切れないから・・です。お奨めします。
ドメーヌ・ルシアン・ボワイヨ・エ・フィス
ルシアン・ボワイヨ・エ・フィス
フランス Domaine Lucien Boillot et Fils ブルゴーニュ
● 2022年のルシアン・ボワイヨです・・めっちゃ旨いです!・・今までも激エレガントで美味しかったですが、2022年ものは・・
「格別に旨い!」
です。
来年到着するであろう2023年ものには、ジャスパー・モリスさんが考えられないほどの高い評価をしていますが、この2022年ものですでにその気配がしっかり感じられます。
また、Noisy wine 初入荷の2022年A.C.ブルが凄まじく旨いですので、これはかなりのお買い得、是非飲んでみてください。
この変わり始めが見極められ、そして2023年、2024年(厳しいヴィンテージです)がこなせられるとしますと、ルシアン・ボワイヨの時代が来るかもしれません。希少な1級シェルボードも2023年は上値96ポイントまで付いています。ぜひ飲んでみてください。お薦めします!
-----
激少のルシアン・ボワイヨ2021年です。テイスティングさえ憚られるほどの少なさです。しかし、Noisy wine の扱いが2019年ものからと言う短さですし、
「2021年もののルシアン・ボワイヨの出来は確認しなければならない」
と感じていました。やはり、単純に・・
「2019~2020年と、グレートイヤー~暑い年を見たので、ネガティヴな要素が入る年のルシアン・ボワイヨ」
を観ない訳には行かないんですね。
で、何とか2アイテム飲ませていただきましたが、美しいエキスが出ていて・・超安心するとともに、
「ん~・・こんなに激エレガントなピノ・ノワールを造れる人は今のブルゴーニュにはごく少数しかいない」
と感じました。
まぁ・・やはりゼヴォセルは白眉でした。村名ジュヴレで充分美味しいですが・・。飲んでみてください。お薦めしたいですが無さ過ぎて申し訳ありません。
-----
ルシアン・ボワイヨの2020年です。いや~・・すっごい・・良いです!・・一体どうしちゃったんだろう?・・と想像しますと、やはり昨年の2019年もののご紹介の時にも書いたと思うんですが、今までとは大きく・・
「何かを変えた」
もしくは、
「誰かと代えた・・(^^;;」
かと想像しています。
そしてこの強めのアルコール度数とてんこ盛りの果実のワインが軒並みを占める2020年に有って・・今のところ・・
「もっとも精緻で美しいディテールを見せるワイン!」
を造っている一人じゃないかと思うんですね・・まぁ・・まだテイスティング中なのでハッキリとは言えませんが、フィネスさん扱いのシュヴィニー・ルソーの2020年もそんなタイプですが、
「ただ単に淡くしているとは思えない精緻さ!」
を見せてくれます。
ですので、飲んでいて疲れないし、
「旨いピノ・ノワールを飲んでるんだ・・」
と言う実感を得て、何よりの喜びを感じていただける・・そんなドメーヌ・ルシアン・ボワイヨの2020年になっていると確信しました。
ですが・・noisy もテイスティングはしたが貰えなかったアイテムも有り、また数量が滅茶少なくて、ジュヴレ村名とゼヴォセルが6本ずつ、ジュヴレ1級シェルボードとニュイ1級プリュリエが3本ずつと・・かなりのものです・・。
まぁ・・今まではそんなに人気にはなっていないとは言え、昨年ご案内させていただいた2019年ものは即完売でしたから、2020年もそんな風になってしまいそうです。滅茶美味しいので是非飲んでみてください。コンディションも素晴らしいです!
-----
新規取り扱いのドメーヌをご紹介させていただきます。フィネスさん輸入の「ドメーヌ・ルシアン・ボワイヨ」です。
フィネスさんの取り扱いで有りながら、Noisy wine で今までご紹介させていただいていなかったのには理由があります。それは・・すみません、余り美味しいとは思っていなかったんです。
勘違いの無いようにフォローしておきたいと思うんですが、決して「悪い」と言う意味では無かったんですよ。どちらかと言うとエキス系の樽掛けが少なめの美しい造りをされるドメーヌでした。でも、硬くて平板で・・数年置けば良化するのは伝わって来るんですが、余りやる気が起きなかったんですね。
ですが2019年ものが入って来まして、担当のK君に色々たずねてみたところ、どうも以前と話しの内容が大幅に違っているんですね・・。「人気で無くなっちゃうんですよね」なんて、
「・・えっ?・・ホント?」
そう・・正直、つい最近まで良いとは思っていませんでした。なので、半信半疑で2019年ものをテイスティング分として仕入れさせていただいた訳です。で、この5月の連休中に集中してテイスティングさせていただいたんです。結果・・
「・・マジすか・・これ、ホントにルシアン・ボワイヨなの?」
とビックリ仰天!
そこにはまるでシルヴァン・パタイユ風のミネラリティ溢れるエキスの味わい、しかもしっかり旨味が乗り、酸のバランスに優れ、細かなテロワールの表現がなされた美しいルビー色の液体が存在していました。
「・・狸か狐に騙されたか・・?」
と、次から次へとボトルを開けましたが、どれも一貫したスタイルで、抜群な美味しさを見せていました。
なんでしょうね・・ここまで来ると、フィネス・マジックと言うしかない・・(^^;; 今度、藤田社長にお会い出来たら、「どうしてこうなった」かお尋ねしてみたい・・しかも、フィネスさん扱いの生産者さんたちの、この何年かの躍進ぶりは・・
「革命に近い」
とさえ感じてしまいます。
ただし、今回の仕入はテスト的に入れたものなので、各々3本ずつしか在りません。しかも1本ずつは開けてテイスティングしていますので、販売可能なのは2本ずつのみ・・再度K君に尋ねてみましたが、すべて完売のようでした。
「・・ん~・・取り残されていたのは noisy だけだったか・・・」
と残念に思いますがこればかりは仕方がありません。
是非皆さんも、以前のルシアン・ボワイヨのイメージは捨て、この美しいディテールを愛でてみていただきたい・・そう思います。ご検討くださいませ。
 ■エージェント情報
■エージェント情報
1850年代にフランソワ・ボワイヨ氏がヴォルネー村でワイン造りを始めたことからボワイヨ家の歴史は始まります。彼の息子であるヴィクトール・ボワイヨ氏はワイン造りと並行してヴォルネー村の村長を務めたばかりでなく、当時フランスの生化学、細菌学の権威で酵母がアルコール醗酵を引き起こすことを発見したルイ・パスツール氏とも親交があり、主にワインの健康状態の保持についてのアドバイスを受けていました。また、ヴィクトール氏の甥っ子にあたるポール・マッソン氏はサンフランシスコに移住してワインビジネスを始め、今日でも彼の名前がラベルになっているサンノゼやカリフォルニアワインが販売されています。現在はフランソワ氏の子孫たちがボワイヨ家の名前を冠してブルゴーニュ各地でワイン造りを行っています。
当ドメーヌはジュヴレ=シャンベルタン村の外れに醸造所を構え、6代目当主のピエール・ボワイヨ氏は万人受けするワインよりもテロワールやピノ・ノワールの酸味の旨さを表現できるワイン造りを心掛けています。畑はコート・ド・ニュイのジュヴレ=シャンベルタンからコート・ド・ボーヌのピュリニィ=モンラッシェまで南北に幅広く存在し、様々なテロワールの畑を約7ha所有しています。土壌は基本的に粘土石灰質でどのアペラシオンも古木が多く、最も古いもので樹齢100年を越えるものも多数存在します。樹齢の古い木は1株につき葡萄の房を4つにまで制限し、除草剤は一切使用していません。これらの古木からルビーのような輝きのある、凝縮された味わいのワインが生み出されています。フランス国内ではアラン・デュカスやパリの3つ星レストランであるラセールでも使われています。
収穫は全て手摘みで、葡萄の皮から繊細でしなやかなタンニンを引き出すために100%除梗を行います。また、ピノ・ノワールの色とアロマを出す為に低温マセラシオンを3~5日間行い、自然酵母で18~21日間、最高温度32℃で琺瑯タンクでアルコール醗酵をさせます。櫂入れは1日1~2回行います。熟成は樽で行い、新樽比率は25~30%で18~25ヵ月間寝かせます。そしてノンフィルター、ノンコラージュで瓶詰めされます。
■ 生産者からの新入荷ヴィンテージに対するコメント~
DOMAINE LUCIEN-BOILLOT
2019年は春先に霜が降りる気配もあったが影響がでるような被害はなく、夏はとても気温が上がって暑くなったおかげで素晴らしいクオリティの葡萄が収穫できた。葡萄の収穫は9月6日から開始し、暑く乾燥した影響で収穫量は少なかったものの、葡萄のバランスは良かったので醸造に手は掛からなかった。村名クラスはフレッシュで軽やかな香りと丸く柔らかな口当たり、特に「ジュヴレシャンベルタンレゼヴォセル」はジューシーな果実味ときめ細やかな舌触りで素晴らしいポテンシャルを感じる。1級クラスは完熟果実やジャムのような濃密な香り、リッチな味わいながらも繊細なタンニン、スパイシーな余韻がとても長く続いて柔らかな味わいに仕上がっている。
「2021年もののルシアン・ボワイヨの出来は確認しなければならない」
と感じていました。やはり、単純に・・
「2019~2020年と、グレートイヤー~暑い年を見たので、ネガティヴな要素が入る年のルシアン・ボワイヨ」
を観ない訳には行かないんですね。
で、何とか2アイテム飲ませていただきましたが、美しいエキスが出ていて・・超安心するとともに、
「ん~・・こんなに激エレガントなピノ・ノワールを造れる人は今のブルゴーニュにはごく少数しかいない」
と感じました。
まぁ・・やはりゼヴォセルは白眉でした。村名ジュヴレで充分美味しいですが・・。飲んでみてください。お薦めしたいですが無さ過ぎて申し訳ありません。
-----
ルシアン・ボワイヨの2020年です。いや~・・すっごい・・良いです!・・一体どうしちゃったんだろう?・・と想像しますと、やはり昨年の2019年もののご紹介の時にも書いたと思うんですが、今までとは大きく・・
「何かを変えた」
もしくは、
「誰かと代えた・・(^^;;」
かと想像しています。
そしてこの強めのアルコール度数とてんこ盛りの果実のワインが軒並みを占める2020年に有って・・今のところ・・
「もっとも精緻で美しいディテールを見せるワイン!」
を造っている一人じゃないかと思うんですね・・まぁ・・まだテイスティング中なのでハッキリとは言えませんが、フィネスさん扱いのシュヴィニー・ルソーの2020年もそんなタイプですが、
「ただ単に淡くしているとは思えない精緻さ!」
を見せてくれます。
ですので、飲んでいて疲れないし、
「旨いピノ・ノワールを飲んでるんだ・・」
と言う実感を得て、何よりの喜びを感じていただける・・そんなドメーヌ・ルシアン・ボワイヨの2020年になっていると確信しました。
ですが・・noisy もテイスティングはしたが貰えなかったアイテムも有り、また数量が滅茶少なくて、ジュヴレ村名とゼヴォセルが6本ずつ、ジュヴレ1級シェルボードとニュイ1級プリュリエが3本ずつと・・かなりのものです・・。
まぁ・・今まではそんなに人気にはなっていないとは言え、昨年ご案内させていただいた2019年ものは即完売でしたから、2020年もそんな風になってしまいそうです。滅茶美味しいので是非飲んでみてください。コンディションも素晴らしいです!
-----
新規取り扱いのドメーヌをご紹介させていただきます。フィネスさん輸入の「ドメーヌ・ルシアン・ボワイヨ」です。
フィネスさんの取り扱いで有りながら、Noisy wine で今までご紹介させていただいていなかったのには理由があります。それは・・すみません、余り美味しいとは思っていなかったんです。
勘違いの無いようにフォローしておきたいと思うんですが、決して「悪い」と言う意味では無かったんですよ。どちらかと言うとエキス系の樽掛けが少なめの美しい造りをされるドメーヌでした。でも、硬くて平板で・・数年置けば良化するのは伝わって来るんですが、余りやる気が起きなかったんですね。
ですが2019年ものが入って来まして、担当のK君に色々たずねてみたところ、どうも以前と話しの内容が大幅に違っているんですね・・。「人気で無くなっちゃうんですよね」なんて、
「・・えっ?・・ホント?」
そう・・正直、つい最近まで良いとは思っていませんでした。なので、半信半疑で2019年ものをテイスティング分として仕入れさせていただいた訳です。で、この5月の連休中に集中してテイスティングさせていただいたんです。結果・・
「・・マジすか・・これ、ホントにルシアン・ボワイヨなの?」
とビックリ仰天!
そこにはまるでシルヴァン・パタイユ風のミネラリティ溢れるエキスの味わい、しかもしっかり旨味が乗り、酸のバランスに優れ、細かなテロワールの表現がなされた美しいルビー色の液体が存在していました。
「・・狸か狐に騙されたか・・?」
と、次から次へとボトルを開けましたが、どれも一貫したスタイルで、抜群な美味しさを見せていました。
なんでしょうね・・ここまで来ると、フィネス・マジックと言うしかない・・(^^;; 今度、藤田社長にお会い出来たら、「どうしてこうなった」かお尋ねしてみたい・・しかも、フィネスさん扱いの生産者さんたちの、この何年かの躍進ぶりは・・
「革命に近い」
とさえ感じてしまいます。
ただし、今回の仕入はテスト的に入れたものなので、各々3本ずつしか在りません。しかも1本ずつは開けてテイスティングしていますので、販売可能なのは2本ずつのみ・・再度K君に尋ねてみましたが、すべて完売のようでした。
「・・ん~・・取り残されていたのは noisy だけだったか・・・」
と残念に思いますがこればかりは仕方がありません。
是非皆さんも、以前のルシアン・ボワイヨのイメージは捨て、この美しいディテールを愛でてみていただきたい・・そう思います。ご検討くださいませ。
 ■エージェント情報
■エージェント情報1850年代にフランソワ・ボワイヨ氏がヴォルネー村でワイン造りを始めたことからボワイヨ家の歴史は始まります。彼の息子であるヴィクトール・ボワイヨ氏はワイン造りと並行してヴォルネー村の村長を務めたばかりでなく、当時フランスの生化学、細菌学の権威で酵母がアルコール醗酵を引き起こすことを発見したルイ・パスツール氏とも親交があり、主にワインの健康状態の保持についてのアドバイスを受けていました。また、ヴィクトール氏の甥っ子にあたるポール・マッソン氏はサンフランシスコに移住してワインビジネスを始め、今日でも彼の名前がラベルになっているサンノゼやカリフォルニアワインが販売されています。現在はフランソワ氏の子孫たちがボワイヨ家の名前を冠してブルゴーニュ各地でワイン造りを行っています。
当ドメーヌはジュヴレ=シャンベルタン村の外れに醸造所を構え、6代目当主のピエール・ボワイヨ氏は万人受けするワインよりもテロワールやピノ・ノワールの酸味の旨さを表現できるワイン造りを心掛けています。畑はコート・ド・ニュイのジュヴレ=シャンベルタンからコート・ド・ボーヌのピュリニィ=モンラッシェまで南北に幅広く存在し、様々なテロワールの畑を約7ha所有しています。土壌は基本的に粘土石灰質でどのアペラシオンも古木が多く、最も古いもので樹齢100年を越えるものも多数存在します。樹齢の古い木は1株につき葡萄の房を4つにまで制限し、除草剤は一切使用していません。これらの古木からルビーのような輝きのある、凝縮された味わいのワインが生み出されています。フランス国内ではアラン・デュカスやパリの3つ星レストランであるラセールでも使われています。
収穫は全て手摘みで、葡萄の皮から繊細でしなやかなタンニンを引き出すために100%除梗を行います。また、ピノ・ノワールの色とアロマを出す為に低温マセラシオンを3~5日間行い、自然酵母で18~21日間、最高温度32℃で琺瑯タンクでアルコール醗酵をさせます。櫂入れは1日1~2回行います。熟成は樽で行い、新樽比率は25~30%で18~25ヵ月間寝かせます。そしてノンフィルター、ノンコラージュで瓶詰めされます。
■ 生産者からの新入荷ヴィンテージに対するコメント~
DOMAINE LUCIEN-BOILLOT
2019年は春先に霜が降りる気配もあったが影響がでるような被害はなく、夏はとても気温が上がって暑くなったおかげで素晴らしいクオリティの葡萄が収穫できた。葡萄の収穫は9月6日から開始し、暑く乾燥した影響で収穫量は少なかったものの、葡萄のバランスは良かったので醸造に手は掛からなかった。村名クラスはフレッシュで軽やかな香りと丸く柔らかな口当たり、特に「ジュヴレシャンベルタンレゼヴォセル」はジューシーな果実味ときめ細やかな舌触りで素晴らしいポテンシャルを感じる。1級クラスは完熟果実やジャムのような濃密な香り、リッチな味わいながらも繊細なタンニン、スパイシーな余韻がとても長く続いて柔らかな味わいに仕上がっている。
●
2022 Gevrey-Chambertin
ジュヴレ=シャンベルタン
【2022年ものは何が変わったのか..如実に絵に出ているのがジュヴレ村名・・です。】
 他のキュヴェの写真は今一つ判り辛いと思えるので、このジュヴレの村名をご参考にされると判り易いかと思います。
他のキュヴェの写真は今一つ判り辛いと思えるので、このジュヴレの村名をご参考にされると判り易いかと思います。そもそもルシアン・ボワイヨのワインって・・クラシカルながら完全に近いエキスの味わいで、超エレガントな味わいでした。甘く無く仕上げて・・エキスに昇華させ、そのエキス自体の味わいだった訳です。
それが、おそらく若い人たちが入って来て変わり始めた・・んでしょう。
どう変わったかと言いますと、まず・・栽培を自然なものへと変更して行ったはずです。そしてSo2の使用量をかなり減らし、葡萄の濃度は自然に任せるものの・・畑の仕事が回り始めると、しっかりした密度が出始め、それが中心のやや盛り上がったコア感につながり、そこからなだらかな傾斜を感じさせながら円形のパレットを美しく描けるようになった・・と思っています。
このグラスの写真も、まぁ・・撮った角度も若干影響しているかと思いますが、2021年ものよりもしっかり濃く、しかし2020年ものの凄い濃さには追い付かないものの、最も優れたバランスだと感じさせる出来に落とし込めるようになったと感じています。
そもそもはジュヴレの生産者さんですが、ニュイ=サン=ジョルジュにも、ヴォルネイにも、ピュリニーにも畑を持っていますからかなり広い範囲に渡っています。血族で育んで来て、また一緒になって・・分かれて・・を繰り返し、今は今の形になっているのでしょうが、余りに広い範囲ですと難しい問題も出て来ます。
それが今、だいぶ上手く回り始めたんじゃないか・・そう思わせるのが2022年だったんですね。
 この村名ジュヴレも、2023年は・・とても村名とは思えないような93ポイントまでジャスパーさんが付けています。2022年は普通に90ポイントでは有りますが、
この村名ジュヴレも、2023年は・・とても村名とは思えないような93ポイントまでジャスパーさんが付けています。2022年は普通に90ポイントでは有りますが、「実を言うと、この2022年ものにもその上昇気流をしっかり感じることが出来る」
訳ですね。
コルクを抜いて飲み始めて、
「あ・・美味しい!」
と、すぐに言える出来なんです。
チェリッシュで、ほんのりと鉄っぽさと岩っぽさを感じられ、ジュヴレ的なやや重厚なスパイス感と大きな構造、そしてその構造を・・
「ちゃんと埋め尽くしているのが2022年」
と言うことなんですね。
凄いと予想してしまいますが2023年ものを待つ間、上昇気流に乗った味わいがする2022年ものを是非飲んでみてください。So2の少ない軽やかで優しい飲み口のジュヴレ村名です。お薦めします!
以下は以前のレヴューです。
-----
【この美しいエキスこそがボワイヨの特徴!エレガントでめっちゃ良いです!】
 滅茶美味しいです!・・もう、このような涼やかなヴィンテージに集中しつつもエレガントで、色の淡さをむしろ楽しめる造り手さんは、ホント・・希少かと・・思います。
滅茶美味しいです!・・もう、このような涼やかなヴィンテージに集中しつつもエレガントで、色の淡さをむしろ楽しめる造り手さんは、ホント・・希少かと・・思います。とは言え、noisy 的には2018年まではノーマークでして、むしろ・・見て見ないフリをしていた・・と言いますか、スルーしていたと言うか・・以前は余り良い印象が無かったんですね。
noisy 自身がそんなに急に趣旨変え、好みが激変するはずが無いので、やはりルシアン・ボワイヨが変わった・・と言うことだと思うんですが、やはりフィネスさんのワインのコンディションの良さが有ってこそのこの素晴らしいエキスの味わいだろうと思います。
2021年ものはご存じの通り、非常に悲惨な生産量でして・・このジュヴレ村名2021年もたったの6本だけの入荷です。それを無理やりテイスティングしましたから販売は5本だけで・・
「飲めたらラッキー」
位に思ってください。
2019年ものからの写真が有りますので、ぜひ見比べてみてください。2019年ものは・・まぁ・・レベルな濃さでしょうか。淡くも無いですが、濃くも見えない感じです。2020年ものは濃いですね・・濃いけれど冷ややかさも有り・・果皮の美しい濃度で甘く無く滅茶美味しかったです。
で、やはり2021年は・・もっとも淡い色彩です。寄った写真の液体の色が綺麗でしょう?・・少し離れてグラス全体の写真になりますと、テーブルの明るい茶色がバックになり、調整しないものですから・・少し暖かい色になりますが、今のところの Noisy wineの写真はその傾向が有ると思っていてください。
 非常にエレガントです。エレガントと言うことは、余り強さを感じない・・と言うイメージも有ります。しかしエキスはとてもしっかりしていて・・口内の味蕾を「押してくる」ような迫力も有ります。しかしやはり超絶にエレガントで、膨らみ方もどこか淑女を思わせるようなおしとやかな感じ、余韻にかけてもエキスの美味しさを堪能できます。
非常にエレガントです。エレガントと言うことは、余り強さを感じない・・と言うイメージも有ります。しかしエキスはとてもしっかりしていて・・口内の味蕾を「押してくる」ような迫力も有ります。しかしやはり超絶にエレガントで、膨らみ方もどこか淑女を思わせるようなおしとやかな感じ、余韻にかけてもエキスの美味しさを堪能できます。アロマはブラックなチェリー・・そしてジュヴレらしい鉄っぽさが少し、ビターなニュアンスを伴いながらの良く溶け込んだ粘土や石灰のイメージで、良く香ります。
一緒に同じ村名ですが上級キュヴェのゼヴォセルを飲ませていただきました。やはり上級キュヴェだけあって・・よりチェリーの表現も上質、キュッと締まって行くような様に品格が有って、
「ん~・・最低1点は上・・・」
と感じます。
ですが、シンプルな総体としての美味しさのあるジュヴレ村名も、これはこれで「有り」だと感じます。ぜひ飲んでみてください。
「エレガント系、エキス系のしっとりと押してくる淑女系の味わい」
です・・あ、熟女と言ってしまうとイメージが変わりますのでご注意ください。お薦めします!2021年ものは希少です。
以下は以前のレヴューです。
-----
【受けるには訳が有る!・・ベストなバランス・・濃密さもどこか僅かに感じさせつつ、ドライで精緻で美しく雅なニュアンスをたなびかせてくれるジュヴレ村名です!・・旨い!】
 昔のルシアン・ボワイヨからは考えられないほど精緻で厚みが有りつつ、非常にエレガントなスタイルに仕上がっている2020年の村名ジュヴレです。
昔のルシアン・ボワイヨからは考えられないほど精緻で厚みが有りつつ、非常にエレガントなスタイルに仕上がっている2020年の村名ジュヴレです。まぁ・・この素晴らしい色彩を是非・・舐めるようにご覧ください。
「惚れて・・まうやろ・・」
と・・思わず言葉が唇からこぼれてしまっていませんか?
そうなんですよ・・凄っごい・・美しいですよね・・。素晴らしい葡萄が持つ果皮をしっかり抽出してはいるんですが、
「滅茶上質!」
なんですね。
そしてここが大事・・甘みが無い!・・全くのドライに近いのに、エキスが旨味をちゃんと伝えてくれるんですね。そして「滅茶しっとりしている」んですよ・・濡れた感じです。だからこの果皮の美味しさ、果皮の周りの美味しさをたっぷり楽しめる訳です。
 その上で、ジュヴレ=シャンベルタンが持っている個性・・鉄っぽさや赤っぽさ、血っぽさや獣っぽさを、
その上で、ジュヴレ=シャンベルタンが持っている個性・・鉄っぽさや赤っぽさ、血っぽさや獣っぽさを、「ほんの僅かずつシェアしているかのように内包!」
しているように感じます。
これらは結構に1級畑クラスが1つ~2つだけ持っていて、それらが素晴らしい輝きを見せるからこそ・・テロワールを意識出来るんですが、流石に1級とは行かないのは当然だとしても、それらを結構に欲張りに持っていて、僅かずつ表情に出してくれる感じなので、飲む方としましては・・
「・・おっ?」
と・・構えてからの飲みに入って行く・・そんな感じで美味しくいただけると思います。なので、
「どうしちゃったの・・・?ルシアン・ボワイヨ!」
と思っていただけること、間違い無しかと!
そして感じたのはコンディションの良さです。この濡れた感じですが、コンディションの良さも一役買っているかと思うんですね。昔のルシアン・ボワイヨだと、「乾いた感じ」でしたから・・。
素晴らしいジュヴレ村名かと思います。今飲んでも美味しいです!是非お試しください。お勧めします。
以下は以前のレヴューです。
-----
【2019年のルシアン・ボワイヨのテイスティングの最初で、思わず唸ってしまいました・・調べて見ましたら、なんとジャスパー・モリス氏は91ポイントでした!】
 村名のジュヴレとしますと、相当高いレベルに感じられる優れたポテンシャルを持った味わいでした。
村名のジュヴレとしますと、相当高いレベルに感じられる優れたポテンシャルを持った味わいでした。しかも2019年のルシアン・ボワイヨのテイスティングの最初のアイテムでしたので・・余り気乗りがしないままテイスティングを始めた・・んですね。
しかしながら、いつもですと愚息がコルクを抜くんですがその日は何故か留守でして、noisy が抜栓から行いました。
空けた傍から・・もう、いつものルシアン・ボワイヨじゃぁ無いのが歴然・・柔らかくもほんのりとスパイシーなアロマが漂ってくるでは有りませんか。
そうなってしまいますと、余り乗ってない気持ちなど吹っ飛んでしまいますから、写真を撮るのもそこそこに・・グラスをノーズに近付けると・・甘さの無いドライなアロマが「ぶわっ」と飛び込んで来ました。
一瞬、ルーミエさん風にも思いましたが、むしろルーミエさんの方がもう少し甘やかでラズベリーっぽいかな?・・などと思い返したところに、透明感バッチリのミネラリティが感じられ何が何だかよく判らない・・少なくとも noisy が知っているルシアン・ボワイヨでは無いぞ・・と・・一度感覚をリセットする羽目になってしまいました。
淡いルビーを積層させたかのような比較濃い目の色合いです。充実した色彩です。グラスを振ると零れてくる果実・・。その深い積層した味わい・・。
いや・・どうも自身の中で納得が行かない・・と言いますか、マッチングしない感覚がいつまでも消えませんでした。それはワインが悪いと言う意味では全く無く、noisy 自身の中にある違和感が消えないだけなんですが。
 本気で扱うつもりは無かったので、3本ずつ6アイテムのテイスティング用の仮仕入です。
本気で扱うつもりは無かったので、3本ずつ6アイテムのテイスティング用の仮仕入です。「もしかして・・大失敗?」
と思いつつも、
「いや、明日は2本開けるし・・明後日は上級キュヴェを3本開けてチェックしてから相談しよう」
と思い直しました。翌日のヴォルネイとポマールのテイスティングで、2019年のルシアン・ボワイヨが半端無い仕上がりになっていることを確認しましたが、連休中でフィネスの担当さんに連絡が取れず、結局追加できないことになり諦めました。
エキスが凝縮した素晴らしい村名ジュヴレです。今飲んでも相当旨い!・・です。
ネットを探してみましたら、まぁ・・ちょっとブレは大きい、もしくはアペラシオンで決める感じが目立つものの、乗った時、弾けた時はその目の鋭さが魅力のジャスパー・モリス氏が91ポイント付けていました。
見事なしっとり感、そこからの心地良い穏やかなスパイス、溶け込んだ透明なミネラリティが魅力かと思います。将来的にはそれなりのムンムンした感じが出てくるんじゃないかと思います。
因みは畑は、ブロション側(北)と、マジ=シャンベルタン下部(村の中央)のブレンドのようです。今飲んでも非常に美味しいです!お勧めします。
●
2022 Gevrey-Chambertin les Evocelles
ジュヴレ=シャンベルタン・レ・ゼヴォセル
【準1級的存在のレ・ゼヴォセルも過去最高!・・そして2023年ものは過去最高を更新しています!・・ここの伸び方を是非・・見ていただきたい!】
 こんなことを言うと・・何だか偉そうに言ってるなぁ・・などと引かれてしまうとは思うんですが、それでもワイン屋の視点としては、
こんなことを言うと・・何だか偉そうに言ってるなぁ・・などと引かれてしまうとは思うんですが、それでもワイン屋の視点としては、「グッと伸びて来たと感じた時!」
を大事にしてきて、結構に良い思いもしたし、それを失って脱力感も感じることになったり・・した訳ですね。
まぁ・・フーリエも以前はまったくフリーだったので2009年ものまでは相当な数を販売させていただきましたし、セシルにしても最初から高かったので苦労はしたんですが、気付いたら瞬殺状態・・でも毎年30%ずつ減らされてしまいましたし、ラミーもとんでもない量を販売させていただきましたが、世評が上がると価格も上がってしまって・・「だ~っ!」な状況になりそうですし、あ、そうそう・・これは書いておかないといけないですが、
「ギルベール・ジレは3年目ですが、最新ヴィンテージのNoisy wine の扱い量は1/15に激減」
です。
これは、ギルベール・ジレの意向でレストランさん中心に流通させたい・・とのことで、ワイン屋経由の販売を絞ったことによります。なので、
「とんでもなく痛い・・」
ですし、お客様には多大な迷惑をお掛けすることになってしまいました。ここでお詫びさせていただきます。
まぁ・・ギルベール・ジレは初年度で、
「この造り手は絶対に延びる!」
と感じて、周りではまったく売れていない時に頑張っちゃいましたので、2年目で相当な数をいただけた訳です。でも残念ながら「無い」のと同じほどの数ですから、どうしようかと思案しています。
 ある意味、このルシアン・ボワイヨの2022年ですが・・「伸びの具合」が半端無いと感じています。
ある意味、このルシアン・ボワイヨの2022年ですが・・「伸びの具合」が半端無いと感じています。なので、2023年ものも楽しみではあるんですがその前に、
「この2022年ものが本当に美味しいのか・・どう変わったのか・・」
を判らないと、いきなり2023年ものが飲めたとしても・・楽しさは結構減ると思うんですね。
そしてこの2022~2023年の伸長率が続くかどうか?・・でしょう?
なので、この2022~2023年ものをチェックし、厳しいだろう2024年がどうなるか?・・なんですよね・・。これを確かめるのがワインの楽しさの一つでも有ると思っています。
で、このレ・ゼヴォセルですが、ほとんどの部分がブロションにあり、ほんの僅かが1級レ・シャンポー上部に有ることで、村名とされている畑です。
なので、1級になりそこねたので「準1級」としていますが、冷涼感の漂う・・まさにジュヴレの高地の味わいに、ブロション的な・・フィサン的なと言い換えた方が良いかもしれませんが、その優しさを持った複雑性が何とも心地良い、優しいピノ・ノワールです。
出来は非常に良いです。キュッと締まって滅茶ドライ、ふんわりとジュヴレ的な鉄っぽさを持ちつつも、2022年のボワイヨ共通の、
「ど真ん中のコアの存在」
が感じられ、そこからなだらかにエッジへと向かう美しいテクスチュア、そしてエッジの丸さにほんのり紫が乗る感覚が美味しさを感じさせてくれます。エレガントですが適度な濃度も有り、万人受けしそうな味わいです。ぜひ飲んでみてください。超お薦めです!
以下は以前のレヴューです。
-----
【実質1級の滅茶お買い得なリューディ・ゼヴォセル!・・エキスの美味しさにただよう格上感は、やっぱり半端無い!旨し!】
 メディアの2019年ものの評価を上げさせていただきました。最近のものは見当たりませんで・・
メディアの2019年ものの評価を上げさせていただきました。最近のものは見当たりませんで・・「2021年もののルシアン・ボワイヨの評価、出てないかな?」
と散々探しましたところ、まったく見つからず、代わりに・・
「余りのエキスの出来、美味しさにびっくりした2019年もの」
の評価を掲載したと言う訳です。
これについては以前もコラムに書いており、
「デュガ=ピィに劣らず、しかも価格は半分以下」
としています。
2019年ものと今回の2021年ものを比較してみますと、
「全体のバランスは2019年ものに分が有り、エキスの純粋な美味しさと冷ややかさは2021年ものに分が有る」
と感じます。
色彩も2021年ものの方が淡く、やはりエレガンスが素晴らしいです。
そして、ブラックチェリーやブラックベリーの風味が繊細に感じられますが、やはりディテールの美しさが際立ちます。細やかなんですね・・。
やはりこの「ゼヴォセル」と言う畑は、
「1級レ・シャンポーの上部(西)、東に接し、1級レ・グーロの北に接している村名畑」
でして、そのほとんどが隣村の「ブロション」に有ります。ジュヴレにも有りますが少ないです。
 そんな畑ですから、ロケーションだけ見ますと、
そんな畑ですから、ロケーションだけ見ますと、「ん?・・なんでここが村名畑なの?」
と言いたくなるような位置なんですね。南から偉大なル・クロ・サン=ジャック、レ・カゼティエ、コンブ・オ・モワンヌ、レ・シャンポーと続き、
「全く同様な高度に連続して存在している村名畑」
ですから、言ってみれば・・
「並みのジュヴレ村名畑では無い」
とも言えます。
ですので・・まぁ・・
「準1級?」
と言いたくなるような高質さを持っていまして、それがディテールの美しさに現れていると感じます。めっちゃ美味しいです!・・ビターでエレガントで見事にエキス系です。今飲んでも美味しいですが、2020年もののように濃さで誤魔化される部分は少ないですから、これからも遂次上昇して行くでしょう。5本だけです。お早めにどうぞ!激お薦めします。
以下は以前のレヴューです。
-----
【この美しいエキスこそがボワイヨの特徴!エレガントでめっちゃ良いです!】
 どえりゃ~・・美味しいです!・・むしろディガ=ピィより好き・・(^^;;
どえりゃ~・・美味しいです!・・むしろディガ=ピィより好き・・(^^;;この畑はジュヴレの最上部に在りながら、またそれは1級レ・シャンポーの真上に在りながら・・ほとんどの畑がフィサン寄り・・つまりブロションに有りますので、
「それだけで1級にはなれなかった疑惑?」
も付いて回るほど・・デュガ=ピィのレ・ゼヴォセルは人気です。
ですがどうでしょう・・この2020年もの・・デュガ=ピィは久しく飲めていませんが・・
「・・えっ?・・もしかして・・?」
と思わせるほど、素晴らしい仕上がりをしています。
何せ垂涎のジュヴレ1級畑が並ぶ・・そう、あのクロ・サン=ジャックからの北への並びです・・そこに有りながら、僅かに傾斜が・・・とか、一番高いところだから・・とか、そもそも、
「ジュヴレじゃないし・・」
等と言うイジメも有ったのかもしれません。
 ですが、この2020年のように日照に恵まれ・・過ぎてしまうと、そんな高い場所の涼やかな畑が、
ですが、この2020年のように日照に恵まれ・・過ぎてしまうと、そんな高い場所の涼やかな畑が、「実はもっとも条件が良くなってしまった」
可能性も出てくるんじゃないかと。
村名ジュヴレが滅茶美味しいので、そちらをお勧めしていますが、可能でしたらこのグラスの写真を見比べてみてください。
「これ・・美味しく無い訳が・・無いんじゃん?」
村名ジュヴレも素晴らしいですが、この色彩の持つグラデュエーション、そうは出会えないと思いますよ。言ってしまえば、最近のルーミエさんのクロ・ド・ラ・ビュシエールを思わせるようなグラデュエーションに近いように感じます。
そして飲んだらもう・・甘露です!・・つるん・・と入って来て、複雑で素晴らしい表情を見せてくれます。
村名ジュヴレでは1級並みとは・・ハッキリは言えなかった訳ですが、このレ・ゼヴォセルには・・しっかり書いてしまいました!素晴らしいです!・・でも3本だけ。お早めにご検討くださいませ。
以下は以前のレヴューです。
----
【ジュヴレのレ・ゼヴォセルと言えば・・デュガ=ピィですよね・・このレ・ゼヴォセルも素晴らしい出来です!】
 デュガ=ピィ的な味わいでは有りませんが、やはり同じ畑らしく・・その雰囲気はバリバリに出ています。
デュガ=ピィ的な味わいでは有りませんが、やはり同じ畑らしく・・その雰囲気はバリバリに出ています。このレ・ゼヴォセルと言うジュヴレ=シャンベルタンA.C.の畑ですが、その一部はジュヴレに有るものの、ほとんどが北に接するお隣りのブロションに有るんですね。なので、ジュヴレの地図上だと・・そのジュヴレのレ・ゼヴォセルは、
「1級レ・シャンポーの一部」
に見えるほどなんです。
デュガ=ピィさんのレ・ゼヴォセルが有名ですから、飲まれたことの有る方は多いと思いますが、デュガ=ピィはもっと黒い・・と言うか、少なくとも暗い色合いをしていると思うんですね。
あ、そうそう・・例えば「レ・ゼヴォセル」で検索を掛けて・・グラスの写真が出てくるような時代になる良いなぁ・・なんて思うんですが、全然出て来ないですよね。Noisy wine のサーバーには、
「・・もういい加減にしてくれないかなー!」
と思う位、各社のクローラー(検索エンジンのサイトを巡回して収集してくるロボット)が画像を拾いに活動しています。最近多いのはApple社のボット・・お行儀が悪いと言うか、四十八時連続的にアクセスして持っていきます。Apple でボットで拾いまくって、それを何に使用しているのか?・・noisy は理解していません。
 ちょっと道を外れてしまいましたが、素晴らしい出来の2019年ジュヴレ村名に比較しますと、相当に「緻密」で「複雑性の高い」「冷涼な」味わいとアロマを持っています。
ちょっと道を外れてしまいましたが、素晴らしい出来の2019年ジュヴレ村名に比較しますと、相当に「緻密」で「複雑性の高い」「冷涼な」味わいとアロマを持っています。これはやはり1級レ・シャンポーとも共通な「涼やか感」だと思います。しかしそれだけに終わらず、アロマの伸びが素晴らしい!・・だいぶデュガ=ピィとはニュアンスが異なりますかね。
細やかな赤い果実をたっぷり持ち、高地の風の影響か低い気温の中、やっと熟したような密度の高い味わいです。非常に健康的でエキスたっぷり・・これは素晴らしい!
このレ・ゼヴォセルもジャスパー・モリス氏は評価していまして、なんと92ポイント!・・ん~・・素晴らしい・・ですが、もう少しあげても良いかな・・と思います。
因みにデュガ=ピィの2019年、レ・ゼヴォセルの評価はこんな感じです。
2019 Domaine Dugat-Py Gevrey-Chambertin "Les Evocelles"
91-93+ Points Robert Parker's Wine Advocate
91-93 Points Vinous
90-92 Points Allen Meadows - Burghound
あらら・・ほとんど変わらないですね。価格は1/2から1/2.5でしょうか。
今飲んでも素晴らしさは充分に伝わってくると思いますが、やはりこれは2~3年寝かせるべきでしょう。ご検討くださいませ。
●
2022 Nuits-Saint-Georges 1er Cru les Pruliers
ニュイ=サン=ジョルジュ・プルミエ・クリュ・レ・プリュリエ
【久しぶりに入荷の在った1級プリュリエですが、この2022年ものは上値93ポイント止まりも2023年ものはシェルボード同様に96ポイント!・・ビックリです!】
 まぁ・・無い、入ってないものの話しをしたところで虚しいだけではあるんですが、
まぁ・・無い、入ってないものの話しをしたところで虚しいだけではあるんですが、「ルシアン=ボワイヨの2022年ものはとんでもない出来!」
だと訴えるには非常に良い題材だと思うんですね。
確かに以前のレヴューで、
「2019年ものも93ポイント!」
としていますから、メディアもまったく無視していた訳では無いとしてもですよ・・
「その他のヴィンテージ、2020年、2021年、そして2018年以前の評価はほとんど見つからない」
訳ですから、テイスティングさえ行われていたのかも不明な訳です。
それがいきなり2022年もので評点の復活が有って2019年ものとほぼ同様の評点、そして2023年ものでプラス3点のグラン・クリュ並みの96ポイント・・ですから、まぁ・・メディアも中々に「したたか」だなぁと思ってしまいました。
noisy は、このレ・プリュリエとジュヴレ1級レ・シェルボードを同日にテイスティングしていまして、仮の評点がどちらも同じだったんですね。その意味ではジャスパーさんとまったく同じです。もうちょっと付けると思いますけどね。
 で、2023年もののジャンプアップを想像させるような、
で、2023年もののジャンプアップを想像させるような、「とんでもなく美しい完全に昇華されたエキスからのアロマと表情!」
が感じられる訳ですよ。
アロマはほんのりとスパイシーで軽やかにフワッと・・チェリーを混ぜ込んで来ます。まったくエキスの味わいで贅肉は無く、中心にあるコアから・・やはりなだらかな傾斜を持ってエッジに辿り着き、エッジの断崖絶壁は非常に丸みがあって滑らか、厳しさが無い非常なスムーズさを感じさせてくれます。
余韻に掛けてもほんのりと複雑性をエレガントに醸し出しつつ、美しいクラシカルな味わいの残像を見せつつ、ナチュールな味わいもふんわりと感じさせ消えて行きます。
ボワイヨの2022年のA.C.ブルを3週間ほど逆刺ししたまま置いてあったものを飲んでみたんですが、
「酸化はしているものの・・揮発酸はほぼ出ず、非常に美しくて・・ある意味、とても旨い!」
と思ったんですね。
おそらくですがSo2の生成も添加も少ないと思われますが、質の良い葡萄だけを選別し、相当頑張ったんじゃないかと思っています。
これは是非飲んでみていただきたいですね。そして2023年ものを待ちましょう。96ポイントって・・簡単に出る評点ではありません。どうぞよろしくお願いします。
以下は以前のレヴューです。
-----
【おそらくですが・・若い人の力が発揮されてこの見事な味わいになっていると思います。ジャスパー・モリス氏はレ・シェルボードと同じ評価で93ポイントです!】
 素晴らしいプリュリエでした。しっとりとした全体の印象から、穏やかながらも甘美さを隠し切れずに漏れてくるかのような果実、花、スパイス・・。
素晴らしいプリュリエでした。しっとりとした全体の印象から、穏やかながらも甘美さを隠し切れずに漏れてくるかのような果実、花、スパイス・・。昨今のニュイ=サン=ジョルジュは信じられないほど土っぽくない・・ですよね。まぁ、ニュイ=サン=ジョルジュは難しい・・とおっしゃる方もいらっしゃいますが、
「土むさいだけ」
「テクスチュア最悪」
みたいなニュイ=サン=ジョルジュが当たり前だった、ちょっと前までをお考えいただけましたら・・とんでも無くスキルアップ?したんじゃないかと・・思いませんでしょうか。
あのアンリ・グージュも・・凄いワインになりました・・でもそれは最近です。シュヴィヨン、レシュノー、ラルロは良いけれど・・あと誰が良かったでしたっけ・・この何年かの間に、土むさくテクスチュアのザラザラした力任せ感たっぷりなニュイ=サン=ジョルジュは、大幅に減ったと思うんですね。
勿論それには、気候の変化も影響していると思います。しかし皆、
「マッチョなブルゴーニュを造ろうとはしなくなった」
と言う意識改革と、
「自然派、無農薬への回帰」
が、ニュイ=サン=ジョルジュは進んでいると思うんですね。
 ルシアン・ボワイヨも、息子さんなんでしょうか・・ピエールさんがほぼ継いだ状況のようです。大きく変わった原因としたら・・それが一番なのかもしれませんね。
ルシアン・ボワイヨも、息子さんなんでしょうか・・ピエールさんがほぼ継いだ状況のようです。大きく変わった原因としたら・・それが一番なのかもしれませんね。So2 も多くは無いと感じています。何しろ香りの上りがスムーズで柔らかいです。色合いも美しいでしょう?昔なら、「茶」と言いたい位のニュイ=サン=ジョルジュをいっぱい見たような気がします・・がそれは記憶違いでしょうか。
このレ・プリュリエは、ヴォーヌ=ロマネ側に接した丘では無く、ニュイの町を挟んで南に展開される部分に有ります。昔はこの辺りがむしろヴォーヌ=ロマネっぽいと感じていました。ヴォーヌ=ロマネに接した丘の方はニュイ的だと思っていたんですが、最近はどうでしょう・・真逆に感じています。
おそらくそれは上にも書いた通り、
「脱力して・・リキミ無く」
美しいワインに仕上げる努力が出来るようになったことに由来すると思います。昔は、濃く、強く・・多く樽掛けしてでした。でもそれではブルゴーニュ・ピノ・ノワールの美しさを描き切れなかった・・ニュイ=サン=ジョルジュのエレガンスが出てこなかったと感じています。
なので、このようなレ・プリュリエを見てしまいますと、
「ニュイ=サン=ジョルジュが好き!」
とおっしゃる方が増えると思うんですね。
そして若い方を中心に、どんどん美しくなってきていると思います。ルシアン・ボワイヨ...noisy は乗り遅れてしまいましたが、素晴らしい2019年でした。是非飲んでみていただきたいと思います。お勧めです!
ローラン・パタイユ
ローラン・パタイユ
フランス Laurent Pataille ブルゴーニュ
● 初めての扱いになりますドメーヌ・ローラン・パタイユをご紹介させていただきます。
2025年、アリゴターで兄シルヴァンと共に来日されたローラン・パタイユですが、アリゴターの牽引車である兄の・・ドメーヌでも一緒に働き、成果を上げているのは知っていましたが、正規輸入のインポーターさん大榮産業さんとはお取引が無く、また・・まぁ・・色々ありまして、今まで静観していました。
少しずつ日本でもその存在が知られて来まして流石に黙っていられなくなり、アポイントを取りお取引をさせていただきました。
ワインのコンディションにつきましては noisy が全アイテムをテイスティングすることで問題無いことを確認していますが、以後も出来得る限り様々な観点からチェックを入れさせていただき、問題が有った場合は販売しない方向性で行かせていただきますのでご安心ください。
 ローラン・パタイユの2022年のワインを5アイテム全てテイスティングさせていただきました。
ローラン・パタイユの2022年のワインを5アイテム全てテイスティングさせていただきました。
全体的な印象としましては、兄シルヴァンの緊張感溢れる伸びやかな若々しい酸のあるミネラリティ豊かな味わいとは、むしろ90度ほど方向性が異なるかな?・・もしくは、
「ドメーヌ・シルヴァン・パタイユで出来ない部分を拡大して仕上げている」
ようなニュアンスを受けました。
つまり、兄シルヴァンは・・収穫のタイミングは葡萄が仕上がったと判断したベストな時・・もしくは少しだけフレッシュに仕上げるために前倒しにしている感覚が有りますが、ローランは・・
「より葡萄の熟度を求めている」
と感じます。なので、シルヴァンほど酸が強く無く、よりまろやかです。そして果実感はより熟したものになります。もっともこれは葡萄の樹齢にもよる可能性もあり、さらに樹齢が加わりますと似る方向に行くかもしれません。
そしてシルヴァン同様にシャルドネ・ロゼ(白葡萄)を育てていますが、一瞬・・
「・・えっ?ユベール・ラミーに倣ったの?」
と思えるほどの超密植(1.7万本/ha)を行っています(・・ラミーに倣った訳ではありません)。
またナチュール感は兄シルヴァンも時折揮発酸を感じるヴィンテージも有ったとは言え、また非常に美しい仕上がりであるとは言え、さほどナチュール感を前面に出したものでは無いと感じますが、ローランの場合はよりナチュールな感覚も有りつつ、So2の使用量を大幅に抑え(基本、醸造中は使用しない)ているのも有るのに、表情に浮かぶ揮発酸的なニュアンスはほぼありません。
全体的に良く熟した葡萄を使用するローラン、ややフレッシュに仕上げるシルヴァン・・と言った違いが一番多いかもしれません。
色彩も白ワインは・・実際にどのように仕込んでいるか詳細は不明ですが、非常に濃い目で美しい黄色~黄金色をしています。これは醸造中にSo2を使用していないことにより、またバレルファルメンテーションによるものと思われます。濃密で蜜っぽいニュアンスが感じられる素晴らしい味わいです。
赤ワインについては、将来1級畑になるかもしれないマルサネ・エシェゾーが有るとは言え、現状のトップ・キュヴェが村名畑のフィサンですので、物凄い評価になると言うようなことは考えられませんが、村名フィサンの膨らみのあるナチュール感の乗った美しくふくよかな味わいは、飲む者に多大な心地良さを感じさせてくれるはずです。もちろんマルサネ・エシェゾーも同じ味筋にあります。
価格の方は2022年、シルヴァン・パタイユもローラン・パタイユも大幅にアップされたようで少し残念では有りますが、やはりお客様には何とか飲んでいただき、ブルゴーニュの改革者でもある両者のワインの比較もしていただきたいと言う観点から、出来得る限りのプライスを出しています。ぜひ飲んでみていただきたい素晴らしいドメーヌです。どうぞよろしくお願いします。
■バックグラウンド
ローランはシルヴァンの弟です。彼もシルヴァンと似た髪質で、ワイン造りをしていますが、彼のワインを見つけるのははるかに困難です。彼が所有する畑はわずか1ヘクタールで、造る5つのキュヴェのほとんどは日本に輸出されています。
ローランは1978年生まれ、シルヴァンは1975年生まれです。家族のブドウ畑がほとんどなかったため、二人ともワイン造り家になるというのは少し意外なことでした。父親はバスの運転手で朝勤のため午後は自由時間がありました。彼はその時間を利用して、友人のジャン・フルニエの手伝いをしていました。そして1980年代にわずか半エーカーのブドウ畑を購入しました。
兄弟は幼い頃から、学校が終わるとすぐに父親の畑かフルニエの畑へ駆け寄りました。父方の大叔父はメドックにもっと大きなドメーヌを所有しており、パタイユ兄弟は毎年夏に2週間そこを訪れていました。
ローランはボーヌのブドウ栽培・醸造学校に通い、その後ディジョン大学で醸造学の学位を取得しました。インターンシップ先としては、サン=テミリオンのシャトー・カロンとアルザスのルネ・ミュレがあります。その後ボルドーで経営学修士号を取得し、卒業後はプイィ=フュメのシャトー・ド・トラシーのレジスール(支配人)に就任し、2008年3月まで5年間在籍しました。
しかし2007年に父親が病に倒れ、2008年にはシルヴァンの主要な従業員の一人が退職しました。ローランはブルゴーニュに戻りシルヴァンと共に働く時が来たと決意しました。ローランの友人の多くはシルヴァンの家族と働くのは大変だろうと警告していました。
「確かに大変でした」
とローランは言います。
「それでシルヴァンと話し合ったんです。それで決まったんです。」
ローランはシルヴァンの右腕となり、今もなおそうあり続けています。
2010年、フィサンのドメーヌ・デュランは、雑誌『ブルゴーニュ・オージュールデュイ』から、毎年恒例のテイスティング用のサンプル収集を依頼されました。ローランがシルヴァンのサンプルを届けたとき、デュラン氏に借りたいブドウ畑がいくつかあると伝えました。
シルヴァンは興味があるかと尋ねました。もちろん、興味がありました。それほど多くはありませんでした。フィサンのピノ・ノワール 12アール(0.3エーカー)、マルサネのアリゴテ 5アール(0.12エーカー)です。冬の霜もブドウ畑に大きな被害を与え、ローランは最初のヴィンテージでわずか150本しか生産できませんでした。
2009年の収穫期には、福田智子さんという若い日本人女性がシルヴァンの畑でインターンとして働きました。ローランと智子は2011年に結婚しました。二人はフランスの結婚書類を日本語に翻訳する人を雇いました。しばらくしてその翻訳者はローランを日本の輸入業者である大榮産業に紹介し、同社が彼の代理を務めることになりました。通常のヴィンテージ生産量はわずか700本だったため、ローラン自身は他の輸入市場を探すことはありませんでした。
実際シルヴァンの畑で彼とよく会っていたにもかかわらず、彼は自分でワインを造っているとは一度も口にしませんでした。2017年のヴィンテージで彼の弟からそのことを知りました。
ドメーヌは2010年から成長を続け、2013年にローランがマルサネ・エ・シェゾーの休耕畑を購入し、父親は同じリュディにある畑を彼に貸しました。2015年、ローランは休耕地にシャルドネ・ロゼの選抜品種を1ヘクタールあたり2万本の密度で植えました。この高密度植樹のインスピレーションはオリヴィエ・ラミーから得たものだとすぐに思いがちですが、実際にはシャトー・ド・トラシーから来ています。2001年には1ヘクタールあたり1万7000本のブドウを植え、2004年にローランが初めて醸造を行いました。
2015年にはローランはラ・シャンパーニュ・オートのマルサネ地区にあるアリゴテ畑を15アール(0.37エーカー)借り受け、2019年にはマルサネ・レ・ロンジェロワ地区で30アール(0.74エーカー)を購入しました。
■ブドウ栽培
ローランは創業当初からブドウ畑を有機栽培で育てており、ビオディナミ農法も使用しています。2020年には有機認証の取得プロセスも開始しました。もちろん、彼は有機栽培を強く信じていますが、近隣住民への配慮も欠かせません。マルサネはディジョンに非常に近いため、南部の村々よりもはるかに発展しています。
「私のブドウ畑の隣にはペタンクコートを備えた公共庭園もあります」
とローランは言います。
「農薬散布を見て不快に思う人々に、オーガニックワインであることを安心してもらいたいのです。」
(ペタンク コートは、ペタンクと呼ばれるボールゲームをプレイする場所です。一般的に、4メートル(13フィート)幅で15メートル(49フィート)長の長方形の区域に、土や砂利などの硬い地面が使われます。)
■白ワインの醸造
ローランは祖父から受け継いだ垂直圧搾機のみを使用しているため破砕は必須です。彼は畑の規模に応じてこれを足で、またたは旧式の破砕機で行います。圧搾サイクルは5~6時間と長く、垂直圧搾から得られる澱は非常に質が高いため沈殿させる必要はありません。発酵は自然発酵で、自然酵母を使用し、硫黄は添加していません。
アリゴテは以前はタンクで発酵・熟成されていました。2019年からは、その半分を古い樽で醸造・熟成しています。一部は泥灰土で栽培されているため、還元が促進されます。樽内での酸素化によって還元が抑制されます。アリゴテは1年間熟成させた後、瓶詰めされます。
シャルドネ・ロゼ「ヴァン・ミル」は主に樽で発酵・熟成され、少量はタンクで行われます。2017年は初ヴィンテージであり、ローラン氏は新しい樽を必要としており80%が新樽でした。 2018年は新樽比率が50%でした。2019年と2020年は新樽を使用しませんでした。さらに2020年の樽は300リットルでした。樽はタンクに移され、さらに6ヶ月熟成されます。
バトナージュはテイスティングに基づいて行われます。ワインを肥大化させるのではなく、澱を利用してワインを還元的に保ち保護することです。
ローランによると、これまでのところマロラクティック発酵後に硫黄を添加する必要はなかったとのことです。最初の添加は12ヶ月目の最初の澱引き時(通常10ppm)です。瓶詰め時に硫黄濃度を25~40ppmに調整します。
ローラン氏は毎年清澄試験を実施しており、清澄化に成功しています。ろ過は通常、タンクの底部のみに行われます。
■赤ワインの醸造
2016年まで、フィサンは100%全房発酵で造られていました。しかしローランはこのワインに少々ハーブの香りが強すぎると感じていました。またこのキュヴェの容量が少なかったため発酵の開始に苦労しました。
マルサネ・エ・シェゾーの最初のヴィンテージは2013年でした。厳しい条件のため、100%除梗せざるを得ませんでした。2014年と2015年は50%全房、2016年は収量が極めて少なかったため、100%全房で造らざるを得ませんでした。
2017年と2018年には、両方の赤ワインとも70%全房で醸造しました。その間、彼の弟であるシルヴァンは非常に興味深い比較研究を行っていました。2017年には、マルサネ・アン・クレマンジョの4つのキュヴェを造りました。100%全房、 100%除梗、50%全房、100%全房、一部破砕。
2019年からローランは後者を採用しました。現在、彼の赤ワインは100%全房で醸造され、そのうち30%は破砕されています。この製法の主な利点は、タンク内に果汁があるため、発酵が早く開始することです。しかし、ローラン氏は100%全房であるにもかかわらず、ワインの植物的な特徴が大幅に減少していることも発見しました。
発酵は自然発酵で常温酵母を使用し、硫黄は添加していません。ブドウは少量のドライアイスを加えることで二酸化炭素で保護されています。発酵開始時には毎日ポンプオーバーを行います。ローラン氏は発酵中期、つまり1060気圧でパンチングを行うことを好みます。ポンプオーバーを再開する前に、合計4~5回のパンチダウンを行います。総浸軟時間は短く、約 15 日間です。
ローランは近年、定期的にブドウ畑を借りたり買収したりしているドメーヌであるため、新樽の購入が必要です。フィサンとマルサネはそれぞれ新樽50%と30%で熟成されています。2018年までは、赤ワインは1年後にタンクに移されていました。現在は12ヶ月熟成後に古樽に移し替えられ、さらに6ヶ月熟成されます。
最初の硫黄添加は、セラーが温まる夏に行われます。瓶詰め時に調整され、合計25~40ppmになります。赤ワインは清澄処理を行いません。濾過は通常、樽の底に残った部分のみに行われます。
 ■ マルサネを代表する生産者シルヴァン・パタイユの片腕であり実弟。
■ マルサネを代表する生産者シルヴァン・パタイユの片腕であり実弟。
ブルゴーニュ大学でエノログ国家資格を取得後プイィ=フュメのシャトー・ド・トラシーの責任者として5年間働いた後ブルゴーニュに帰って、兄シルヴァンのドメーヌを手伝いながら近年畑を取得。ファースト・ヴィンテージは2010年とごく最近ながら、地元を中心に即完売。兄シルヴァンのドメーヌでの経験を活かしピュアなワインを造る。畑を購入したばかりの為、以前の所有者の影響が畑にまだ残りますが現在ビオに転換中。通常フィサンは粘土質が多くマルサネに比べて重くなりがちですが、この畑は小石が多く果実味がきれいなワインになります。ドメーヌ・シルヴァン・パタイユでの仕事は今後も継続予定で、収穫などはシルヴァン・パタイユと同じチームが行っています。
2025年、アリゴターで兄シルヴァンと共に来日されたローラン・パタイユですが、アリゴターの牽引車である兄の・・ドメーヌでも一緒に働き、成果を上げているのは知っていましたが、正規輸入のインポーターさん大榮産業さんとはお取引が無く、また・・まぁ・・色々ありまして、今まで静観していました。
少しずつ日本でもその存在が知られて来まして流石に黙っていられなくなり、アポイントを取りお取引をさせていただきました。
ワインのコンディションにつきましては noisy が全アイテムをテイスティングすることで問題無いことを確認していますが、以後も出来得る限り様々な観点からチェックを入れさせていただき、問題が有った場合は販売しない方向性で行かせていただきますのでご安心ください。
 ローラン・パタイユの2022年のワインを5アイテム全てテイスティングさせていただきました。
ローラン・パタイユの2022年のワインを5アイテム全てテイスティングさせていただきました。全体的な印象としましては、兄シルヴァンの緊張感溢れる伸びやかな若々しい酸のあるミネラリティ豊かな味わいとは、むしろ90度ほど方向性が異なるかな?・・もしくは、
「ドメーヌ・シルヴァン・パタイユで出来ない部分を拡大して仕上げている」
ようなニュアンスを受けました。
つまり、兄シルヴァンは・・収穫のタイミングは葡萄が仕上がったと判断したベストな時・・もしくは少しだけフレッシュに仕上げるために前倒しにしている感覚が有りますが、ローランは・・
「より葡萄の熟度を求めている」
と感じます。なので、シルヴァンほど酸が強く無く、よりまろやかです。そして果実感はより熟したものになります。もっともこれは葡萄の樹齢にもよる可能性もあり、さらに樹齢が加わりますと似る方向に行くかもしれません。
そしてシルヴァン同様にシャルドネ・ロゼ(白葡萄)を育てていますが、一瞬・・
「・・えっ?ユベール・ラミーに倣ったの?」
と思えるほどの超密植(1.7万本/ha)を行っています(・・ラミーに倣った訳ではありません)。
またナチュール感は兄シルヴァンも時折揮発酸を感じるヴィンテージも有ったとは言え、また非常に美しい仕上がりであるとは言え、さほどナチュール感を前面に出したものでは無いと感じますが、ローランの場合はよりナチュールな感覚も有りつつ、So2の使用量を大幅に抑え(基本、醸造中は使用しない)ているのも有るのに、表情に浮かぶ揮発酸的なニュアンスはほぼありません。
全体的に良く熟した葡萄を使用するローラン、ややフレッシュに仕上げるシルヴァン・・と言った違いが一番多いかもしれません。
色彩も白ワインは・・実際にどのように仕込んでいるか詳細は不明ですが、非常に濃い目で美しい黄色~黄金色をしています。これは醸造中にSo2を使用していないことにより、またバレルファルメンテーションによるものと思われます。濃密で蜜っぽいニュアンスが感じられる素晴らしい味わいです。
赤ワインについては、将来1級畑になるかもしれないマルサネ・エシェゾーが有るとは言え、現状のトップ・キュヴェが村名畑のフィサンですので、物凄い評価になると言うようなことは考えられませんが、村名フィサンの膨らみのあるナチュール感の乗った美しくふくよかな味わいは、飲む者に多大な心地良さを感じさせてくれるはずです。もちろんマルサネ・エシェゾーも同じ味筋にあります。
価格の方は2022年、シルヴァン・パタイユもローラン・パタイユも大幅にアップされたようで少し残念では有りますが、やはりお客様には何とか飲んでいただき、ブルゴーニュの改革者でもある両者のワインの比較もしていただきたいと言う観点から、出来得る限りのプライスを出しています。ぜひ飲んでみていただきたい素晴らしいドメーヌです。どうぞよろしくお願いします。
■バックグラウンド
ローランはシルヴァンの弟です。彼もシルヴァンと似た髪質で、ワイン造りをしていますが、彼のワインを見つけるのははるかに困難です。彼が所有する畑はわずか1ヘクタールで、造る5つのキュヴェのほとんどは日本に輸出されています。
ローランは1978年生まれ、シルヴァンは1975年生まれです。家族のブドウ畑がほとんどなかったため、二人ともワイン造り家になるというのは少し意外なことでした。父親はバスの運転手で朝勤のため午後は自由時間がありました。彼はその時間を利用して、友人のジャン・フルニエの手伝いをしていました。そして1980年代にわずか半エーカーのブドウ畑を購入しました。
兄弟は幼い頃から、学校が終わるとすぐに父親の畑かフルニエの畑へ駆け寄りました。父方の大叔父はメドックにもっと大きなドメーヌを所有しており、パタイユ兄弟は毎年夏に2週間そこを訪れていました。
ローランはボーヌのブドウ栽培・醸造学校に通い、その後ディジョン大学で醸造学の学位を取得しました。インターンシップ先としては、サン=テミリオンのシャトー・カロンとアルザスのルネ・ミュレがあります。その後ボルドーで経営学修士号を取得し、卒業後はプイィ=フュメのシャトー・ド・トラシーのレジスール(支配人)に就任し、2008年3月まで5年間在籍しました。
しかし2007年に父親が病に倒れ、2008年にはシルヴァンの主要な従業員の一人が退職しました。ローランはブルゴーニュに戻りシルヴァンと共に働く時が来たと決意しました。ローランの友人の多くはシルヴァンの家族と働くのは大変だろうと警告していました。
「確かに大変でした」
とローランは言います。
「それでシルヴァンと話し合ったんです。それで決まったんです。」
ローランはシルヴァンの右腕となり、今もなおそうあり続けています。
2010年、フィサンのドメーヌ・デュランは、雑誌『ブルゴーニュ・オージュールデュイ』から、毎年恒例のテイスティング用のサンプル収集を依頼されました。ローランがシルヴァンのサンプルを届けたとき、デュラン氏に借りたいブドウ畑がいくつかあると伝えました。
シルヴァンは興味があるかと尋ねました。もちろん、興味がありました。それほど多くはありませんでした。フィサンのピノ・ノワール 12アール(0.3エーカー)、マルサネのアリゴテ 5アール(0.12エーカー)です。冬の霜もブドウ畑に大きな被害を与え、ローランは最初のヴィンテージでわずか150本しか生産できませんでした。
2009年の収穫期には、福田智子さんという若い日本人女性がシルヴァンの畑でインターンとして働きました。ローランと智子は2011年に結婚しました。二人はフランスの結婚書類を日本語に翻訳する人を雇いました。しばらくしてその翻訳者はローランを日本の輸入業者である大榮産業に紹介し、同社が彼の代理を務めることになりました。通常のヴィンテージ生産量はわずか700本だったため、ローラン自身は他の輸入市場を探すことはありませんでした。
実際シルヴァンの畑で彼とよく会っていたにもかかわらず、彼は自分でワインを造っているとは一度も口にしませんでした。2017年のヴィンテージで彼の弟からそのことを知りました。
ドメーヌは2010年から成長を続け、2013年にローランがマルサネ・エ・シェゾーの休耕畑を購入し、父親は同じリュディにある畑を彼に貸しました。2015年、ローランは休耕地にシャルドネ・ロゼの選抜品種を1ヘクタールあたり2万本の密度で植えました。この高密度植樹のインスピレーションはオリヴィエ・ラミーから得たものだとすぐに思いがちですが、実際にはシャトー・ド・トラシーから来ています。2001年には1ヘクタールあたり1万7000本のブドウを植え、2004年にローランが初めて醸造を行いました。
2015年にはローランはラ・シャンパーニュ・オートのマルサネ地区にあるアリゴテ畑を15アール(0.37エーカー)借り受け、2019年にはマルサネ・レ・ロンジェロワ地区で30アール(0.74エーカー)を購入しました。
■ブドウ栽培
ローランは創業当初からブドウ畑を有機栽培で育てており、ビオディナミ農法も使用しています。2020年には有機認証の取得プロセスも開始しました。もちろん、彼は有機栽培を強く信じていますが、近隣住民への配慮も欠かせません。マルサネはディジョンに非常に近いため、南部の村々よりもはるかに発展しています。
「私のブドウ畑の隣にはペタンクコートを備えた公共庭園もあります」
とローランは言います。
「農薬散布を見て不快に思う人々に、オーガニックワインであることを安心してもらいたいのです。」
(ペタンク コートは、ペタンクと呼ばれるボールゲームをプレイする場所です。一般的に、4メートル(13フィート)幅で15メートル(49フィート)長の長方形の区域に、土や砂利などの硬い地面が使われます。)
■白ワインの醸造
ローランは祖父から受け継いだ垂直圧搾機のみを使用しているため破砕は必須です。彼は畑の規模に応じてこれを足で、またたは旧式の破砕機で行います。圧搾サイクルは5~6時間と長く、垂直圧搾から得られる澱は非常に質が高いため沈殿させる必要はありません。発酵は自然発酵で、自然酵母を使用し、硫黄は添加していません。
アリゴテは以前はタンクで発酵・熟成されていました。2019年からは、その半分を古い樽で醸造・熟成しています。一部は泥灰土で栽培されているため、還元が促進されます。樽内での酸素化によって還元が抑制されます。アリゴテは1年間熟成させた後、瓶詰めされます。
シャルドネ・ロゼ「ヴァン・ミル」は主に樽で発酵・熟成され、少量はタンクで行われます。2017年は初ヴィンテージであり、ローラン氏は新しい樽を必要としており80%が新樽でした。 2018年は新樽比率が50%でした。2019年と2020年は新樽を使用しませんでした。さらに2020年の樽は300リットルでした。樽はタンクに移され、さらに6ヶ月熟成されます。
バトナージュはテイスティングに基づいて行われます。ワインを肥大化させるのではなく、澱を利用してワインを還元的に保ち保護することです。
ローランによると、これまでのところマロラクティック発酵後に硫黄を添加する必要はなかったとのことです。最初の添加は12ヶ月目の最初の澱引き時(通常10ppm)です。瓶詰め時に硫黄濃度を25~40ppmに調整します。
ローラン氏は毎年清澄試験を実施しており、清澄化に成功しています。ろ過は通常、タンクの底部のみに行われます。
■赤ワインの醸造
2016年まで、フィサンは100%全房発酵で造られていました。しかしローランはこのワインに少々ハーブの香りが強すぎると感じていました。またこのキュヴェの容量が少なかったため発酵の開始に苦労しました。
マルサネ・エ・シェゾーの最初のヴィンテージは2013年でした。厳しい条件のため、100%除梗せざるを得ませんでした。2014年と2015年は50%全房、2016年は収量が極めて少なかったため、100%全房で造らざるを得ませんでした。
2017年と2018年には、両方の赤ワインとも70%全房で醸造しました。その間、彼の弟であるシルヴァンは非常に興味深い比較研究を行っていました。2017年には、マルサネ・アン・クレマンジョの4つのキュヴェを造りました。100%全房、 100%除梗、50%全房、100%全房、一部破砕。
2019年からローランは後者を採用しました。現在、彼の赤ワインは100%全房で醸造され、そのうち30%は破砕されています。この製法の主な利点は、タンク内に果汁があるため、発酵が早く開始することです。しかし、ローラン氏は100%全房であるにもかかわらず、ワインの植物的な特徴が大幅に減少していることも発見しました。
発酵は自然発酵で常温酵母を使用し、硫黄は添加していません。ブドウは少量のドライアイスを加えることで二酸化炭素で保護されています。発酵開始時には毎日ポンプオーバーを行います。ローラン氏は発酵中期、つまり1060気圧でパンチングを行うことを好みます。ポンプオーバーを再開する前に、合計4~5回のパンチダウンを行います。総浸軟時間は短く、約 15 日間です。
ローランは近年、定期的にブドウ畑を借りたり買収したりしているドメーヌであるため、新樽の購入が必要です。フィサンとマルサネはそれぞれ新樽50%と30%で熟成されています。2018年までは、赤ワインは1年後にタンクに移されていました。現在は12ヶ月熟成後に古樽に移し替えられ、さらに6ヶ月熟成されます。
最初の硫黄添加は、セラーが温まる夏に行われます。瓶詰め時に調整され、合計25~40ppmになります。赤ワインは清澄処理を行いません。濾過は通常、樽の底に残った部分のみに行われます。
 ■ マルサネを代表する生産者シルヴァン・パタイユの片腕であり実弟。
■ マルサネを代表する生産者シルヴァン・パタイユの片腕であり実弟。ブルゴーニュ大学でエノログ国家資格を取得後プイィ=フュメのシャトー・ド・トラシーの責任者として5年間働いた後ブルゴーニュに帰って、兄シルヴァンのドメーヌを手伝いながら近年畑を取得。ファースト・ヴィンテージは2010年とごく最近ながら、地元を中心に即完売。兄シルヴァンのドメーヌでの経験を活かしピュアなワインを造る。畑を購入したばかりの為、以前の所有者の影響が畑にまだ残りますが現在ビオに転換中。通常フィサンは粘土質が多くマルサネに比べて重くなりがちですが、この畑は小石が多く果実味がきれいなワインになります。ドメーヌ・シルヴァン・パタイユでの仕事は今後も継続予定で、収穫などはシルヴァン・パタイユと同じチームが行っています。
●
2022 Bourgogne Aligote
ブルゴーニュ・アリゴテ
【樹齢が高目のアリゴテから高い熟度で収穫、パレットの拡がりをしっかり感じる肉厚な見事な味わい!・・最近ちょっと無いタイプの高質アリゴテです!】
 レ・ロンジュロワ直下の2つの古木が植わる畑からのアリゴテです。
レ・ロンジュロワ直下の2つの古木が植わる畑からのアリゴテです。兄シルヴァンのアリゴテは緊張感溢れる・・どちらかと言えば筋肉質で、贅肉の無いボディに酸の美しさ、伸びやかさ、ミネラリティをその筋一本一本に塗り込めたようなニュアンスです。区画名付きの方はそこに何とも心地良く感じられる複雑な味わいと表情が出て来ます。
こちらは2区画、一方は1960年植樹、もう一方は1982年ということで、それぞれ樹齢62年、40年の古木です。
醸造時にSo2を使用せずファルメンタスィョン・エン・バリック、ボトル詰め時に少量加えるスタイルのようですので、酸化由来の色落ち + バリックからの色付きがある・・と言いますか・・黄色~黄金色の凄い色彩が感じられます。そしてさらに、
「遅摘みとまでは言えないとしても、熟度がとても高い!・・と感じさせる」
んですね。
その分、兄シルヴァンの白ワインに感じる「キリっとした酸の伸びやかな味わい」とは言えないんですが、そもそも縦延びしやすいアリゴテの性格を・・
「横方向への膨らみとボディの厚みに長け、やわらかでふんわりとした酸になっている」
と言えます。
 これもまた今では非常に稀有なアリゴテのスタイルと言えますが、熟度の高い葡萄だけに蜜っぽくも有り、甘やかさも有りつつ、フレッシュなニュアンスを抑え、高質なワインとして感じられるんじゃないか・・と思えます。
これもまた今では非常に稀有なアリゴテのスタイルと言えますが、熟度の高い葡萄だけに蜜っぽくも有り、甘やかさも有りつつ、フレッシュなニュアンスを抑え、高質なワインとして感じられるんじゃないか・・と思えます。ここまで蜜っぽくは無く・・もう少し樽のニュアンスで抑圧されたような風味が載って来ると、大昔のコシュ=デュリ(最近のはとても飲めないので・・)のアリゴテに近いスタイルかと感じます。
これ、かなり面白いですね・・もちろん美味しい訳ですが、おそらく誰もが・・
「・・えっ?・・このブ厚いボディの白ワイン・・アリゴテなの?」
と驚かれるんじゃないでしょうか。
流石にアリゴターを牽引するパタイユ兄弟だと感じます。
あ・・ある意味、ドメーヌ・シルヴァン・パタイユのワインも兄シルヴァン、弟ローランの共作で有ると言えますが、それぞれの「出来ること」「得意なこと」を理解し協力し合っているんだと思いますが、
「兄シルヴァンがやらない、できないことを弟ローランがやっている」
んじゃないかとも感じました。
色合いが様々の柑橘、やや熟度の高い柑橘で有り、蜜っぽくも有り、ドライフルーツになって行く乾き始めた柑橘果実、柑橘果実の皮のニュアンスに、
「非常に細やかなミネラリティが溶け込んでいる」
と感じます。
下は2021年もののシルヴァン・パタイユのアリゴテのグラス写真ですが、ミネラリティの見え方、赤っぽさを含む色彩の分布も相当異なると判ります。
そして・・この赤っぽさですが、このアリゴテもまた・・
「ピノ・ノワールであるレ・ロンジュロワと共通のニュアンスを含んでいる!?」
とも感じます・・・ね?・・超面白そうでしょう?
Noisy wine は初の扱いですから余り沢山はいただけず、それに全数テイスティングさせていただいたものの・・利益を得るまではどうも行かなそうなので、ギリギリまで下げています。永遠には出来ませんので初年度と言うことで、お客様にも是非飲んでみていただきたいと思います。お薦めです!

●
2022 Marsannay Blanc es Chezots Vingt Mille
マルサネ・ブラン・エ・シェゾー・ヴァンミル
【美しい黄金色に輝く、ほんのりと赤みが差した色彩から、熟度の高いリッチでふんわりとしたアロマ、真ん丸なパレットを感じる・・将来の1級畑です!】
 まぁ・・1級に認定されるかどうかはINAOの決定待ちなのかもしれませんが、このエ・シェゾーもポテンシャルが有る畑であるとは言え、レ・ロンジュロワも、クロ・デュ・ロワも同様に相応のポテンシャルが有ることは、お客様もシルヴァン・パタイユのワインで確認済じゃないかと思うんですね。
まぁ・・1級に認定されるかどうかはINAOの決定待ちなのかもしれませんが、このエ・シェゾーもポテンシャルが有る畑であるとは言え、レ・ロンジュロワも、クロ・デュ・ロワも同様に相応のポテンシャルが有ることは、お客様もシルヴァン・パタイユのワインで確認済じゃないかと思うんですね。そしてこのエ・シェゾーも・・
「ドメーヌ・バールのとことんリーズナブルな2021年マルサネ・エ・シェゾー・ルージュでご確認済?」
なんじゃないかとも思います。
まぁ・・バールは途轍も無く安い(安かった?)ですから・・6千円台でしたからね・・昨今の、マルサネやフィサンの認知度上昇、アリゴテの地位上昇?で価格も高騰しているとは言え、1級になってしまったらキツイよなぁ・・とは思いますので、
「今の内に赤くて美味しいマルサネの美味しさ」
「結構に沢山あるマルサネA.C.の畑の理解」
をしておくと、
「・・ん・・これは買いだろう!」
とすぐに決められるし、価格が高くても買いか、安いなら買いか・・などの判断も出来ますので・・お薦めです。
こちらの白ですが、ほんのりと厳しい感じの石、岩的なミネラリティを感じられる・・本来はもっとハードさが差し込んで来る感じかと思いますが、
「熟度の高い葡萄故に・・」
 ふんわりとしたニュアンスが有り、横方向へも適度に膨らみ、蜜っぽさや熟度の高い柑橘フレーヴァーがしっかり感じられる素晴らしい出来です。
ふんわりとしたニュアンスが有り、横方向へも適度に膨らみ、蜜っぽさや熟度の高い柑橘フレーヴァーがしっかり感じられる素晴らしい出来です。兄シルヴァンのシャルドネ系ですと・・もっと外殻にハードなミネラリティのコーティングが感じられる場合がほとんどかと思いますが、弟ローランの場合はそうじゃ無いんですね。
ローランのアリゴテもそうでしたが、この色彩をご覧になればお判りのように・・まったくの同類です。
So2 を使用せずに醸造し、バリックも使って・・醸造~エルヴァージュは20カ月間にも及ぶ訳です。ですから、適度な酸化が施されますから・・
「滑らかでふんわり、尖った部分が少ない滑らかな味わい」
になります。
ほんのりと「赤み」さえ感じる色彩ですから、感じられる果実・柑橘にも同様にオレンジとか金柑とか・・そう言った赤み、橙色も入って来ます。
兄シルヴァンの白よりも酸の味わいも柔らかく滑らかで、しかし奥底にはしっかりとしたミネラリティの支えが存在しています。
やはり・・兄シルヴァンとは同じにはならない・・のか、同じように受け取られるようにはしていないのか、何も考えずにこうなっているのかは判りませんが、
「ん・・これは弟ローランのエ・シェゾー白!」
と、見えない「ハンコ」がしっかり押されています。
価格は2022年もの、だいぶ上がった様にも思えますが、かなり頑張って値付けしました。ぜひ飲んでみてください。かなり旨いです!
●
2022 Marsannay es Chezots Rouge
マルサネ・エ・シェゾー・ルージュ
【将来の1級畑候補!・・ローランと智子さんと息子さんの家族の愛に溢れる雰囲気さえ漂って来ているような優しさを感じる見事なピノ・ノワールです!】
 noisy がテイスティングした最も最近のマルサネ・エシェゾーは・・あ、最近は
noisy がテイスティングした最も最近のマルサネ・エシェゾーは・・あ、最近は「エ・シェゾー(エス・シェゾー)」
と「エシェゾー」を分けて表記するようになっていますが、やはりドメーヌ・バールのエ・シェゾーですね。
村名にしておくのは少し可哀そうな・・しかし1級と言うにはほんの少し足りないかも・・とも思えなくもないリューディです。
しかしながら1級畑には1級畑の、村名には村名畑としての制限が有りますから、仮に1級昇格ともなりますとその制限内での収穫量になりますから、
「1級畑になった暁には、確実に1級・・もしくはそれ以上の表現をしてくれるのは間違いないだろう」
と感じさせる優れた畑です。
他には・・これも白のコラムでも書きましたが、やはりレ・ロンジュロワやクロ・デュ・ロワが1級畑となる可能性が有るんじゃないかな?・・と思われますが、同様に1級畑に昇格した際は、今までリリースして来た村名ものよりもよりハッキリとしたポテンシャルを輝かせて見せてくれるものと確信しています。シルヴァン・パタイユのアリゴテ・クロ・デュ・ロワなんぞ・・驚くほどに1級レベルでしたから。
ただし・・標高と言う観点からは、このエ・シェゾーは最も高い位置に有り、傾斜も急なので・・エ・シェゾーだけが1級畑に昇格・・と言うことはあり得ると思っています。
 マルサネ=ラ=コートらしい、赤を基調とし、その赤をしつこいほどに何層にも積み上げているように感じさせる積層された赤は透明感もバッチリです。そこに金属感でしょうか・・ジュヴレのような重さを多分に感じさせる鉄のようなものでは無く、もう少し軽やかな感じがします。
マルサネ=ラ=コートらしい、赤を基調とし、その赤をしつこいほどに何層にも積み上げているように感じさせる積層された赤は透明感もバッチリです。そこに金属感でしょうか・・ジュヴレのような重さを多分に感じさせる鉄のようなものでは無く、もう少し軽やかな感じがします。上品でエレガント、兄シルヴァンのような冷ややかでやや鋭角な酸は無く、より柔らかでふんわりとしたニュアンスです。やはり「熟度の高い葡萄」を得るためにやや収穫時期を遅らせている・・か、もしくは、
「(様々なタイミングは有るとしても)兄シルヴァンの畑から収穫し、のちにローランの畑を収穫する」
しか無い・・と言う理由も有り得ますが、もはや明らかに赤も白も、
「ローラン・パタイユ的と言える熟度が高く酸度がやや低め・・」
がスタイルとして感じられる2022年ものです・・が、noisy もこの2022年ものがローラン・パタイユの初見ですから絶対そうだとは言い切れない部分ではあります。
赤いチェリーにほんのりブラック・チェリーが混じり、ほんのりとノーズにチリチリと・・マグネシウムっぽいスパイスが感じられます。中盤の膨らみは見事で、酸度はやや抑え目、飲み心地が非常に良く・・流れるような瑞々しさを伴う余韻です。
これ・・もう少し収穫を抑え目にしたら・・1級、OKでしょう。So2感が無く心地良いのでいつ飲んでも良いでしょうし、相当良くなると思いますよ。
ドライながらも酸バランスは旨味成分が感じられますから・・相当出来も良いでしょう。リアルワインガイドはポテンシャル 93+ と、村名とは思えないような評点が出ています。素晴らしい出来です。ぜひ飲んでみてください!・・どこか、ローラン・パタイユの朗らかで愛溢れるファミリーと同質のものが漂って来ているかのようで、幸せな感覚にしてくれます。お薦めです!
●
2022 Marsannay les Longeroies
マルサネ・レ・ロンジュロワ
【明らかに兄シルヴァンよりも優しい!・・円に近いパレットを感じます。しかも深い!・・兄弟のワインで比較可能な、将来の1級畑レ・ロンジュロワです!】
 冷ややかさのあるエ・シェゾーと比較しますと、中心に熱と言いますか、エナジーと言うかコアと言うか、旨味の酸の塊のようなものが感じられるレ・ロンジュロワです。
冷ややかさのあるエ・シェゾーと比較しますと、中心に熱と言いますか、エナジーと言うかコアと言うか、旨味の酸の塊のようなものが感じられるレ・ロンジュロワです。ここは・・最上部に有って谷からの風が抜けるエ・シェゾーの下に有ります。傾斜も幾分緩いですから・・比較しますと温かみとして感じられるんですね。
そしてその中心点がよりハッキリとしているのが特徴でもあり、・・まぁ・・有り体に言えば、
「ピン呆けしていない高質のワイン」
なんですね。
まぁ・・エ・シェゾーはより冷ややかですから、レ・ロンジュロワと比較しますとタイトでは有ります。
しかしながらローラン・パタイユのワインは熟度が高いので、尖がってないんですね。ふんわりと柔らかく優しいんです。
その上でビオ系ですから・・まぁ・・これを言うとちょっと勘違いされるかもしれないんですが、言ってみれば・・
「全くアヴァンギャルドでは無い、超キレイなヤン・ドゥリューに近い!?」
と思っていただくと・・そうは遠く無いと・・あぁあ・・書いちゃった・・(^^;; まぁ・・ヤン・ドゥリューの方が濃いっちゃ濃いですけど。
 赤に黒を10%ほど積層させた感じの色彩です。全景を見ますと冷ややかではあるんですが、エナジーのコアがしっかりあり、そこに旨味が詰まっています。
赤に黒を10%ほど積層させた感じの色彩です。全景を見ますと冷ややかではあるんですが、エナジーのコアがしっかりあり、そこに旨味が詰まっています。ジューシーと言うのは安易ですが、非常に飲みやすく、飲み心地が良く、酔い心地が軽いです。チェリーやブラックチェリー、エ・シェゾーの超細かい金属のニュアンスよりはややサイズが大きくなったミネラリティ、しかし重くならずに軽やかです。
細やかで詰まった非常に美しい、赤さのあるやや乾いた粘土が、おそらく多分に土壌に存在するのでしょう。Google Map でロンジュロワ通りを進みますと、畑は乾いて赤みを持っていますが、小さな白い石が沢山転がっているんですよね。
エ・シェゾーはもっと大きな石や岩を感じるんですが、このレ・ロンジュロワの石のニュアンスは・・Google Map で見た小石そのものとほぼ同感覚です。きっと色彩の透明感はこの石由来なのか?・・などとも考えてしまいますが、土壌深くの地層由来だと思いたいです。
スイスイっと入って来ますが軽やかに・・でも確実に心地良いニュアンスが滞留します。これはもう・・ぜひ・・
「ぜひぜひ・・シルヴァン・パタイユと比較して欲しい!」
と思います。きっとnoisy の言っていることが良く判ると思いますよ。
やや先鋭で尖ったところが心地良いシルヴァン、屈託のない柔らかな美味しさと心地良いナチュール感のローラン・・。受け取り方は人それぞれですが、評価できるワイン・・ドメーヌだと思います。ぜひご検討くださいませ。お薦めします!
ルイ・モーラー
ルイ・モーラー
フランス Louis Maurer アルザス
● アルザスから超期待の大型新人をご案内させていただきます。ビオディナミを実践しビオの調剤も自作、So2 も出来る限り控えて、まさに「ナチュール」な出来上がりで有りながら、アヴァンギャルドには陥らない、素晴らしいワインを造っています。
アルザスのビオと言いますと・・大御所ですとマルセル・ダイス、若いところですとジュリアン・メイエのパトリック、それにリエッシュでしょうか。勿論、ジェラール・シュレールもご存じでしょう。
中々に素晴らしい仕上がりで、ちょっとビックリしましたが、
「どの程度?・・誰に似てる感じ?」
と言う部分が皆さんのご興味かと思うんですね。
因みに・・
「So2 の残存量は極端に少ない方!」
です。リースリング・レルシェンベルグ2021で10mg/L と言いますから、検出限界に近い数字です。
マルセル・ダイスはビオですが、昨今は非常に安定していまして、徐々にそのナチュールさに先鋭さを増して来ているものの、
「先進的なビオでは無い」
と言えます。
例えばジェラール・シュレールは、気合の入った時の美しさ、出来は物凄いんですが、時に・・
「・・あれっ?・・」
みたいな・・(^^;; ちょっと理解に苦しむ仕上がりに、ご紹介するかどうかなどを含めて悩むことになる訳です。
ジュリアン・メイエは最近、扱いませんが、最近は安定して来たものの、一時は、
「・・これはすでにお酢だろう!」
と・・当時、J子さんとやり合ったこともある位でして、
「そのレベルで普通にリリースするのね・・」
と言う理解をしたので扱いを止めてしまいました。
このルイ・モーラーですが、ジェラール・シュレールやパトリック・メイエ並みに攻めているんですが、
「ワインとして・・ちゃんとしている!」
と思える素晴らしい仕上がり方をしているんですね。
で、しかも・・
「滅茶苦茶にナチュラルなのに、アヴァンギャルドじゃない!」
んですよ。
勿論ですが揮発酸は出ていたり、ほぼ無かったりするんですが、
「表情のひとつとして存在している」
と認められる仕上がりなんです。
マルセル・ダイスはビオ的にそこまでは攻めていません。ナチュラルですが、先進的なビオでは無く、So2の使用はルイ・モーラーよりも全く緩いです。
「ルイ・モーラーは基本的にSo2を使いたくない人」
であり、
「必要と認めた場合、ごく少量のみの使用で済ませられる状況と環境を作っている!」
と感じました。
初めての扱いですので、言い切ってしまうのは厳しいですが、少なくとも今回の入荷分については上記のことは間違い在りません。
優しくふんわりとしつつ薫り高くナチュール的で、非常にナチュール的に美しいです。是非飲んでみていただきたい素晴らしい生産者さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
 ■ ポスト・ミレニアル世代のナチュラル・アルザス
■ ポスト・ミレニアル世代のナチュラル・アルザス
◇ 20歳でデビューした若さ溢れるナチュール・ヴィニュロン
ルイ・モーラーは今年27 歳になるアルザスで最も若いヴァン・ナチュールの造り手の一人です。彼は醸造学校在学中にマルク・クライデンヴァイスとドメーヌ・セルツで研修し、ビオロジック農法のワインへの影響の重要性を学びました。高校卒業後はカトリーヌ・リスが醸造所を間借りしていたルカ・リーフェルの下で1 年半修行し、ヴァン・ナチュールについて実践で学びました。2016 年から実家のドメーヌに参画し、当時20 歳ながら、家族のワインとは別に、自
身の名前で3 種類のヴァン・ナチュール(2016 ヴィンテージ)を醸造してデビューしました。
◇ カトリーヌ・リスに続く欧米で話題の新星
ルイは、カトリーヌ・リスやリエッシュ、パトリック・メイエと非常に仲が良く、頻繁に会ってワイン造りについて意見交換をしています。2018 ヴィンテージからは複数品種を混醸したヴァン・ド・ソワフやピノ・グリをリースリングの果汁でマセレーションしたキュヴェなど個性的なワインも造り始めました。
彼のワインは欧米のナチュラルワインの愛好家の間で、すくに話題となり、SNS で数多く取り上げられています。ポスト・ミレニアル世代の造る若さ溢れるアルザスのヴァン・ナチュールです。
■ ルイ・モーラーについて
ルイ・モーラーは1996 年生まれ。ポスト・ミレニアル世代のアルザスでも最も若い世代のヴァン・ナチュールの造り手の一人です。ルイはルファックRouffach の醸造学校でBTS(醸造栽培上級技術者のディプロマ)を取得。在学中にマルク・クライデンヴァイスとドメーヌ・セルツで研修し、ビオロジック農法のワインへの影響の重要性を学びました。高校卒業後はルカ・リーフェル(当時カトリーヌ・リスが醸造所を間借りしてたドメーヌ)の下で1 年半修行し、ヴァン・ナチュールについて実践で学びました。
2016 年から実家のドメーヌに参画。当時わずか20 歳ながら、家族のワインとは別に、自身の名で3 種類のヴァン・ナチュール(2016 ヴィンテージ)を醸造しました。実家のドメーヌは⾧年ビオロジックでブドウ栽培を行っており、2009 年からはビオディナミも導入しているため、ルイはさらに先に進みたいと考え、ブドウ以外には何も加えないヴァン・ナチュールの醸造(SO2 も無添加で、必要な場合に限り瓶詰め時に最低限のみ添加する)に挑戦したのです。ルイはドメーヌの三代目になりますが、ドメーヌの創始者である祖父母も両親も彼の挑戦を強く後押ししてくれたそうです。
その後、2018 ヴィンテージからは複数品種を混醸したヴァン・ド・ソワフやピノ・グリをリースリングの果汁でマセレーションしたキュヴェなど個性的なワインも造り始めました。ルイは、カトリーヌ・リスやジャン・ピエール・リエッシュ(二人とも隣村のミッテルベルクハイムに住んでいます)、パトリック・メイエと非常に仲が良く、頻繁に会ってワイン造りについての考えや哲学について意見交換をしています。ラベルデザインは彼のガールフレンドがデザインしたものだそうです。
■ ドメーヌについて
ルイの実家のドメーヌはルイの祖父によって設立。現在はルイの父のフィリップが当主を務めています。ストラスブールとコルマールのほぼ中間のエイコフェン Eichhoffen に本拠を置いています。栽培面積は16ヘクタールで、細分化された40 の区画がエイコフェンと隣村のアンドロー、エプフィグ、イッタースヴィラーに点在しています。
ドメーヌでは昔から除草剤や化学肥料は一切使用しておらず、15 年以上前に完全なビオロジックに転換。2009 年からはビオディナミも導入しました。これによって、ブドウ木の生命力が劇的に向上し、自然に収量が低くなり、ブドウ中のエキスも最上の状態で凝縮されるようになりました。ドメーヌの畑は全て耕耘され、中耕除草も行います。ブドウ畑の畝の間には下草を生やし、ライ麦と野菜を栽培しています。
そして、初夏に下草を抜いて、畝の間に敷き詰めてカバークロップにしています。こうすることによって、草が自然の覆いの役割を果たし、過剰な暑さや雨から土を保護してくれるのです。また、地中の温度が低く保たれることによって微生物の活動と、土中の水の浸透能力が維持されるという効果もあるのです。
ブドウの病害予防には、イラクサ、トクサ、ヤナギなどのハーブや植物の煎じ薬を用いています。また、堆肥や牛糞、ブドウの搾りかすや藁などをベースにしたコンポストを自前で作って畑に撒いています。生命力に満ちたこのコンポストによって土が活性化され、健康で成熟した果実を造るために必要なあらゆるミネラル成分がブドウ木に行き渡ります。ドメーヌでは、生きた土壌とブドウ木から、成熟のピークに達したブドウを低収量で収穫することがテロワールを表現するために必要不可欠な条件であると考えています。
■ 醸造と周辺環境について
醸造に関しては、何よりもブドウを尊重することを大切にしています。ワインがテロワールとその独創性を最大限に表現できるように、人為的介入を最小限にしています。ブドウは野生酵母で自発的に発酵され、スーティラージュも必要な場合にしか行いません。SO2 も必要な最低限のみ添加するだけです。ワインはアルザス伝統のフードルで醸造されます。フードルでは大きな澱が樽の底に沈殿し、細かい澱が通常の樽よりも広がるという利点があります。ド
メーヌのワインは全てエコサートの認証を受けています。
このように、ルイの実家のドメーヌのワインはビオディナミ栽培と人為的介入の少ない醸造で造られていますが、カトリーヌ・リスやリエッシュ、パトリック・メイエなどとの交流で触発されたルイは、家業に参画した2016 年から、それをさらに進めたヴァン・ナチュールの醸造(ブドウ以外に何も加えず醸造。SO2 も無添加。必要な場合に限り瓶詰め時に最低限のみ添加)に挑戦することを決断したのです。祖父母も両親も、ルイの挑戦を後押してくれ、ルイはドメーヌの約3 ヘクタールの区画の栽培の全てを委ねられ、自分の手で栽培したブドウから自分自身の名前でナチュラルワインを2016 ヴィンテージから醸造しています。
ルイのドメーヌは、マルク・クライデンヴァイスの本拠Andlau アンドローや、カトリーヌ・リスやジャン・ピエール・リエッシュが本拠を置くittelbergheim ミッテルベルクハイム、オステルタグの本拠Epfig エプフィグなどの村に隣り合わせています。ルイ・モーラーは、現在のアルザスで最もエキサイティングな場所に生まれた最新世代のヴァン・ナチュールの造り手と言えます。
アルザスのビオと言いますと・・大御所ですとマルセル・ダイス、若いところですとジュリアン・メイエのパトリック、それにリエッシュでしょうか。勿論、ジェラール・シュレールもご存じでしょう。
中々に素晴らしい仕上がりで、ちょっとビックリしましたが、
「どの程度?・・誰に似てる感じ?」
と言う部分が皆さんのご興味かと思うんですね。
因みに・・
「So2 の残存量は極端に少ない方!」
です。リースリング・レルシェンベルグ2021で10mg/L と言いますから、検出限界に近い数字です。
マルセル・ダイスはビオですが、昨今は非常に安定していまして、徐々にそのナチュールさに先鋭さを増して来ているものの、
「先進的なビオでは無い」
と言えます。
例えばジェラール・シュレールは、気合の入った時の美しさ、出来は物凄いんですが、時に・・
「・・あれっ?・・」
みたいな・・(^^;; ちょっと理解に苦しむ仕上がりに、ご紹介するかどうかなどを含めて悩むことになる訳です。
ジュリアン・メイエは最近、扱いませんが、最近は安定して来たものの、一時は、
「・・これはすでにお酢だろう!」
と・・当時、J子さんとやり合ったこともある位でして、
「そのレベルで普通にリリースするのね・・」
と言う理解をしたので扱いを止めてしまいました。
このルイ・モーラーですが、ジェラール・シュレールやパトリック・メイエ並みに攻めているんですが、
「ワインとして・・ちゃんとしている!」
と思える素晴らしい仕上がり方をしているんですね。
で、しかも・・
「滅茶苦茶にナチュラルなのに、アヴァンギャルドじゃない!」
んですよ。
勿論ですが揮発酸は出ていたり、ほぼ無かったりするんですが、
「表情のひとつとして存在している」
と認められる仕上がりなんです。
マルセル・ダイスはビオ的にそこまでは攻めていません。ナチュラルですが、先進的なビオでは無く、So2の使用はルイ・モーラーよりも全く緩いです。
「ルイ・モーラーは基本的にSo2を使いたくない人」
であり、
「必要と認めた場合、ごく少量のみの使用で済ませられる状況と環境を作っている!」
と感じました。
初めての扱いですので、言い切ってしまうのは厳しいですが、少なくとも今回の入荷分については上記のことは間違い在りません。
優しくふんわりとしつつ薫り高くナチュール的で、非常にナチュール的に美しいです。是非飲んでみていただきたい素晴らしい生産者さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
 ■ ポスト・ミレニアル世代のナチュラル・アルザス
■ ポスト・ミレニアル世代のナチュラル・アルザス◇ 20歳でデビューした若さ溢れるナチュール・ヴィニュロン
ルイ・モーラーは今年27 歳になるアルザスで最も若いヴァン・ナチュールの造り手の一人です。彼は醸造学校在学中にマルク・クライデンヴァイスとドメーヌ・セルツで研修し、ビオロジック農法のワインへの影響の重要性を学びました。高校卒業後はカトリーヌ・リスが醸造所を間借りしていたルカ・リーフェルの下で1 年半修行し、ヴァン・ナチュールについて実践で学びました。2016 年から実家のドメーヌに参画し、当時20 歳ながら、家族のワインとは別に、自
身の名前で3 種類のヴァン・ナチュール(2016 ヴィンテージ)を醸造してデビューしました。
◇ カトリーヌ・リスに続く欧米で話題の新星
ルイは、カトリーヌ・リスやリエッシュ、パトリック・メイエと非常に仲が良く、頻繁に会ってワイン造りについて意見交換をしています。2018 ヴィンテージからは複数品種を混醸したヴァン・ド・ソワフやピノ・グリをリースリングの果汁でマセレーションしたキュヴェなど個性的なワインも造り始めました。
彼のワインは欧米のナチュラルワインの愛好家の間で、すくに話題となり、SNS で数多く取り上げられています。ポスト・ミレニアル世代の造る若さ溢れるアルザスのヴァン・ナチュールです。
■ ルイ・モーラーについて
ルイ・モーラーは1996 年生まれ。ポスト・ミレニアル世代のアルザスでも最も若い世代のヴァン・ナチュールの造り手の一人です。ルイはルファックRouffach の醸造学校でBTS(醸造栽培上級技術者のディプロマ)を取得。在学中にマルク・クライデンヴァイスとドメーヌ・セルツで研修し、ビオロジック農法のワインへの影響の重要性を学びました。高校卒業後はルカ・リーフェル(当時カトリーヌ・リスが醸造所を間借りしてたドメーヌ)の下で1 年半修行し、ヴァン・ナチュールについて実践で学びました。
2016 年から実家のドメーヌに参画。当時わずか20 歳ながら、家族のワインとは別に、自身の名で3 種類のヴァン・ナチュール(2016 ヴィンテージ)を醸造しました。実家のドメーヌは⾧年ビオロジックでブドウ栽培を行っており、2009 年からはビオディナミも導入しているため、ルイはさらに先に進みたいと考え、ブドウ以外には何も加えないヴァン・ナチュールの醸造(SO2 も無添加で、必要な場合に限り瓶詰め時に最低限のみ添加する)に挑戦したのです。ルイはドメーヌの三代目になりますが、ドメーヌの創始者である祖父母も両親も彼の挑戦を強く後押ししてくれたそうです。
その後、2018 ヴィンテージからは複数品種を混醸したヴァン・ド・ソワフやピノ・グリをリースリングの果汁でマセレーションしたキュヴェなど個性的なワインも造り始めました。ルイは、カトリーヌ・リスやジャン・ピエール・リエッシュ(二人とも隣村のミッテルベルクハイムに住んでいます)、パトリック・メイエと非常に仲が良く、頻繁に会ってワイン造りについての考えや哲学について意見交換をしています。ラベルデザインは彼のガールフレンドがデザインしたものだそうです。
■ ドメーヌについて
ルイの実家のドメーヌはルイの祖父によって設立。現在はルイの父のフィリップが当主を務めています。ストラスブールとコルマールのほぼ中間のエイコフェン Eichhoffen に本拠を置いています。栽培面積は16ヘクタールで、細分化された40 の区画がエイコフェンと隣村のアンドロー、エプフィグ、イッタースヴィラーに点在しています。
ドメーヌでは昔から除草剤や化学肥料は一切使用しておらず、15 年以上前に完全なビオロジックに転換。2009 年からはビオディナミも導入しました。これによって、ブドウ木の生命力が劇的に向上し、自然に収量が低くなり、ブドウ中のエキスも最上の状態で凝縮されるようになりました。ドメーヌの畑は全て耕耘され、中耕除草も行います。ブドウ畑の畝の間には下草を生やし、ライ麦と野菜を栽培しています。
そして、初夏に下草を抜いて、畝の間に敷き詰めてカバークロップにしています。こうすることによって、草が自然の覆いの役割を果たし、過剰な暑さや雨から土を保護してくれるのです。また、地中の温度が低く保たれることによって微生物の活動と、土中の水の浸透能力が維持されるという効果もあるのです。
ブドウの病害予防には、イラクサ、トクサ、ヤナギなどのハーブや植物の煎じ薬を用いています。また、堆肥や牛糞、ブドウの搾りかすや藁などをベースにしたコンポストを自前で作って畑に撒いています。生命力に満ちたこのコンポストによって土が活性化され、健康で成熟した果実を造るために必要なあらゆるミネラル成分がブドウ木に行き渡ります。ドメーヌでは、生きた土壌とブドウ木から、成熟のピークに達したブドウを低収量で収穫することがテロワールを表現するために必要不可欠な条件であると考えています。
■ 醸造と周辺環境について
醸造に関しては、何よりもブドウを尊重することを大切にしています。ワインがテロワールとその独創性を最大限に表現できるように、人為的介入を最小限にしています。ブドウは野生酵母で自発的に発酵され、スーティラージュも必要な場合にしか行いません。SO2 も必要な最低限のみ添加するだけです。ワインはアルザス伝統のフードルで醸造されます。フードルでは大きな澱が樽の底に沈殿し、細かい澱が通常の樽よりも広がるという利点があります。ド
メーヌのワインは全てエコサートの認証を受けています。
このように、ルイの実家のドメーヌのワインはビオディナミ栽培と人為的介入の少ない醸造で造られていますが、カトリーヌ・リスやリエッシュ、パトリック・メイエなどとの交流で触発されたルイは、家業に参画した2016 年から、それをさらに進めたヴァン・ナチュールの醸造(ブドウ以外に何も加えず醸造。SO2 も無添加。必要な場合に限り瓶詰め時に最低限のみ添加)に挑戦することを決断したのです。祖父母も両親も、ルイの挑戦を後押してくれ、ルイはドメーヌの約3 ヘクタールの区画の栽培の全てを委ねられ、自分の手で栽培したブドウから自分自身の名前でナチュラルワインを2016 ヴィンテージから醸造しています。
ルイのドメーヌは、マルク・クライデンヴァイスの本拠Andlau アンドローや、カトリーヌ・リスやジャン・ピエール・リエッシュが本拠を置くittelbergheim ミッテルベルクハイム、オステルタグの本拠Epfig エプフィグなどの村に隣り合わせています。ルイ・モーラーは、現在のアルザスで最もエキサイティングな場所に生まれた最新世代のヴァン・ナチュールの造り手と言えます。
●
N.V.(2023) au bout du Goulot Blanc
オー・ブー・デュ・グロ・ブラン
【高く高度なナチュールさに加え、美しいピュアさ!葡萄そのものを頬張っている・・そんなイメージのペティアンです!】
 ナチュールですね~・・めちゃナチュールです!比較、癖の少ないリースリングを主体に若いうちは硬質なミュスカを加えてバランスを取ったアルザスのペティアンです。
ナチュールですね~・・めちゃナチュールです!比較、癖の少ないリースリングを主体に若いうちは硬質なミュスカを加えてバランスを取ったアルザスのペティアンです。何せ、澱引きもしていませんから・・結構に澱は有りますが、飲んだ感じでは・・
「邪魔にはならない」
です。
そして、
「その澱が旨味の元?」
になっているようなニュアンスで、意外や意外・・結構に太目の味わいがします。
泡質は強くは無く、しかしペティアンとしますと程良い感じです。ペティアンの場合は結構、「粗い感じの泡」になる場合が多いように感じますが、そこそこにふんわり感が有ります。甘みはほとんど無く、ドライです。
アロマは泡に載って飛び込んできますが、まったく「危険性の無い」美しいもの。ナチュールなニュアンスはバリバリに有りますが、同時に、
「ピュア感」
も半端無く有ります。
 色彩は結構に濁った黄色ですが、
色彩は結構に濁った黄色ですが、「濁った味」
と言うよりは、
「深みのあるピュアな味わいとノーズ」
です。
ん~・・こういうのは良いですね・・。やはりビオ系で半端無いナチュール度だとしても、揮発酸が泡に載って「ツーン」と香るようだと興醒めしてしまいます。大抵の場合、そのような泡になってしまいますと・・
「余韻の風味がみんな同じ・・そしてワインならではの余韻とはかなりかけ離れる」
場合が多いです。
こちらはヴィヴィットさんのセレクションですが、やはりバイヤーさん・・と言いますか、彼らの選択眼は中々に良いと感心しています。決して「変なの」は・・無いと言いますか、余り無い・・です。
余り無いと言うのは・・ヴィヴィットさんがそのつもりでいても、時に生産者さんが暴走することも有り得ますから、そんな時は Noisy wine のようなセレクトショップがちゃんとレヴューすれば良い訳ですよね。
価格も安く、残存So2 も滅茶少なく・・
「たったの18mg/L!」
心地良い飲み口なのもご理解いただけるでしょう・・そしてリーズナブルです。どうぞよろしくお願いいたします。お薦めします!
●
2023 Haute Voltige A.O.C. Alsace
オート・ヴォルティージュ A.O.C.アルザス
【新キュヴェ「遅積みゲヴェルツ」!オレンジ・マーマレードのようなコクのある果実が「ギュッ!」と詰まったピュア・アルザスです!】[ oisy wrote ]
 [ oisy wrote ]
[ oisy wrote ]ルイ・モーラーの新キュヴェです。実はこのワイン、一本開けてテイスティングしているのですが、その前にVivitさんのところで試飲させてもらっていました。
その時に非常に面白いインプットがあって、現状抜栓したてはトロトロなので、デキャンタに移してからシャカシャカ空気を含ませると粘性が取れます、とのこと。乳酸菌の影響で一時的なトロみがついているとのことで、熟成や抜栓からの時間の経過とともに粘性は穏やかになっていくとのことです。
その時は抜栓二日目のテイスティングだったので過剰な粘性は感じられずだったので、改めて抜栓したところ確かに「トロトロ」。
しかしこれがネガティブかと言われればそんなことは無く、さらっとした餡のようで、その粘性が徐々に緩んでいく過程と、味わいや香りが開いていく過程が同時進行していくので、これはこのままでもいいのでは?と思いましたが、粘性がちょっとキツイなと思われた方はシャカシャカやってみてください。
同じゲヴェルツのレトランジェ・オレンジュとなにが違うの?といえば、このオート・ヴォルティージュの方が収穫が遅いようです。アルコール度数も14.5度もあります・・!正確な収穫時期はわかりませんが結構な遅積みではないでしょうか。
遅積みによって増幅した糖分はほぼ気付かない程度のみ残糖として残され、その大部分は発酵に回されています。ですので味スジとしてはドライとセミドライの中間・・ほぼドライと言っていいと思います。裏面ラベルを見ると、2021年からAOCアルザスに義務付けられた残糖度の表記では一番辛口の4g未満のセック(ドライ)に該当していますので、粘性が若干の甘さを演出する部分もあるのだと思います。
そしてよく熟したブドウからの、香り立ちの良さが目立ちます。オレンジ、マーマレード、金柑、枇杷。オレンジ系のフルーツがいくつも重なり、そこに穏やかなハーブが交じり合います。ゲヴェルツらしいライチ感は控えめです。
「ギュッ!」と詰まったオレンジ果実が、じんわ~り口内にいきわたります。
これだけアルコール度数も高く、粘性もあるのに全くしつこくなく、めちゃピュアでナチュラルな果実の充足感と余韻がけを残していく・・・この構成を産み出すバランス感覚は素晴らしいですね!
ちなみにめちゃ安定していますし、澱をしっかりと落として落ち着かせればクリーンなワインです。ただしSO2も少なく、めちゃピュアで、飲む直前まで低温管理を想定した造りですので、温度管理にはご注意ください。一度高温に晒されると一気にバランスを崩すような繊細さも持ち合わせています。
ブドウの熟度が要求されるため、毎年は造られないキュヴェとのこと。2023ヴィンテージは総生産量1700本しかないようです。ぜひルイ・モーラーの新しい挑戦、「遅積みゲヴェルツ」をご堪能ください!
●
2023 l'Etrange Orange A.O.C. Alsace
レトランジュ・オランジュ A.O.C.アルザス
【ベルガモット、ホップ、金木犀、紅茶・・アロマティックな「香りのチーム」と日本人的感覚で引き出される「旨味」の妙が素晴らしい・・!】[ oisy wrote ]
 [ oisy wrote ]
[ oisy wrote ]ルイ・モーラーのゲヴェルツは非常に特徴的で、ライチよりも「オレンジが主体」です。
それもシンプルなオレンジではなく、伊予柑やベルガモットのような、香立ちの良いアロマの含みがあります。そこに金木犀やホップのようなビター感がポンポン加わってくるので、
「意外に賑やか」
です。
しかし南のワインのように一つの香りが、他を押しのけるようにやってくるわけではなく、各香りの要素たちに皆協調性があるので、
「香りのチーム」
として楽しませてくれます。
そしてチームとなり、総合力をアップさせた香りが、とてもアロマティック。ある種とても日本人的なチームワークと言えるかもしれません。
実は日本人的なのは香りだけではなく、味わいも非常に日本人的だな・・と思うんです。そこにこそルイ・モーラーの真骨頂があるような気がしてならないんですが、どのキュヴェからも「旨味」をしっかりと感じるんですよね。
レトランジェ・オレンジュもシュール・リー由来の旨味を感じますし、技法だけではなく、しっかりと「果実の良さ」からやってくる旨味があります。間違いなく、これは畑が良い・・!と言えると思います。
重要なのは「旨味だけ」を残し、「えぐみ」やその他の要素をちゃんと置いてきているという点です。このバランス感覚が絶妙で、旨味をギリギリまで引っ張って持ってきて、えぐみが出る直前で引き上げる。というタイミングのセンスがあるからこそ、ホップのような強目のビター感を感じられるのでしょうし、充実した「擦られたような果実の旨味」、「旨味の伸び」が感じられるのだと思います。
また酸素と触れ合わせているとわずかに紅茶のようなニュアンスが出てきます。「ベルガモット x 紅茶」ですからまさに
「香るアールグレイ・・!
のように進化していくわけですね。
ミネラリティと組み合わさって、オイリーさも感じますが、しっかりと締まりの良さがあります。香りはあまやかですが、味わいはしっかりドライ、とてもバランス感覚に優れたアロマティックでピュアなワインです。きっとこれがルイ・モーラーの世界感か・・と心地よい酔いにどっぷり浸ることができると思います。
かなりクリーンで安定感のあるオレンジワインです。素晴らしいですね!ぜひご堪能くださいませ!
[ noisy wrote ]
以下は以前のレビューです。
--------
【これぞ・・オレンジワイン!!・・じゃない?・・オレンジワインと名乗るフレーヴァーが飛んで存在しないオレンジ色のワインとは、まったく異なる見事な味わいです!】
 「 noisyさんは余りオレンジワインは扱わないですよね?」
「 noisyさんは余りオレンジワインは扱わないですよね?」と稀に聞かれることが有ります。なのでそんな時は、
「・・タイミングかなぁ・・。敢えてオレンジを探すと言うような行動はしないけど、美味しいのが有ればやってるよ。」
と返しています。
中々オレンジワインで美味しいの・・って・・無いですよね。ピノ・グリが本家かなぁ・・と思いますが、なんとこのワインは、
「ゲヴェルツトラミネール100%!」
で造ったオレンジワインなんですね・・。
ですから比較的おとなしいピノ・グリよりも、輪郭やアロマが活き活きしていて、ディテールがしっかり感じられます。
でも一般的なゲヴェが見せるような、
「ちょっと尖がって、スパイスがキツイ」
ようなスタイルにはなっておらず、滑らかでしっとりしつつ、硬軟、強弱をわきまえたかのような素晴らしい表情を持っています。
 ドライで、ほんのり活き活きしたスパイス、フルーティーです。でもそれだけか?・・と言う訳では無く、お茶とか紅茶を香らせたかと思えば、
ドライで、ほんのり活き活きしたスパイス、フルーティーです。でもそれだけか?・・と言う訳では無く、お茶とか紅茶を香らせたかと思えば、「ん?・・杏のドライフルーツまで・・出てくる?」
と言うような瞬間も有り、非常に楽しめます。
何より、酢酸系のドギツイ香りの邪魔が入らず、美しくて味わいそのもの、香りそのものを楽しめるんですね・・。
さらには、身体に優しいと言うのが・・飲み終えて30分~1時間後に感じられると思いますよ。基本、So2は「余り使いたくない人」のようです。
まぁ・・オレンジですから、物凄くポテンシャルが有るか?・・と言われましたら、
「・・いや、そこまではどうでしょ。」
と言わざるを得ませんが、
「アルザスのゲヴェルツトラミネール種としても楽しめる」
性格も有ると感じます。ぜひ飲んでみてください。意外にも骨太です。お薦めします!
以下は以前のレヴューです。
-----
【生きているオレンジワイン!?・・多種多彩な果実のニュアンスがたっぷりで華やか!・・造り手のセンスを感じさせる素晴らしいオレンジです!】
 有りそうで余り見あたら無い・・でしょう?
有りそうで余り見あたら無い・・でしょう?「ナチュラル感が凄く載った美味しいオレンジワイン!」
って・・何か有るでしょうか?
仮に・・この言葉を3つに分けて、
「ナチュラル感が凄く載った」
「美味しい」
「オレンジワイン」
にした場合には、それぞれにそこそこに挙げられるかと思うんですよね。
ですがこの3つを繋げてしまいますと・・
「まず・・当たらない・・見当たらない」
でしょう?
もしくは、もう少し敷居を低くして、
「ナチュラル感のある美味しいオレンジワイン!」
にしたところで・・どうでしょう?・・
 実は、オレンジワインを飲んでナチュラル感を感じる場合に・・は、
実は、オレンジワインを飲んでナチュラル感を感じる場合に・・は、「美味しい!」
が抜けちゃうんですよ。
ナチュラル感は有っても美味しさが・・少ないんですね・・。なんか、枯れてしまったものばかりを集めたような感じだったり、ビオ的に攻めたは良いが、何を飲んでいるのか悩むような感じだったりしないでしょうか?
この「レトランジュ・オランジュ」は、
「まさにオレンジ感がバッチリ!」
です。
オレンジな果実やミント、ハーブが優しくふっくらと・・感じられます。ドライフルーツ的なニュアンスも有りますが、多くのオレンジワインがそうであるように、「お茶・ウーロン茶」的なニュアンスはほんの僅かで・・「その他大勢」です。
もし・・このワインを自身の設計通りに造れたのだとすると・・この方、相当半端無いと思います。色彩も生きています!
揮発酸は僅か・・です。しっかり要素の一つとして溶け込んでおり、揮発酸を意識することは無いに等しいでしょう。美味しいオレンジワイン!?・・です。是非飲んでみてください。お勧めします!
●
2023 Pinot Gris Duttenberg A.O.C. Alsace
ピノ・グリ・デュッテンベルグ A.O.C.アルザス
【青いフルーツに、ドライなのにあまい日本酒のような吟醸香!繊細で日本的な侘寂ミネラリティにじんわり湧き出る果実の旨味感!】[ oisy wrote ]
 [ oisy wrote ]
[ oisy wrote ]レトランジェ・オレンジュの項で「和風!」とか「ルイ・モーラーのワインは日本人的!」と書かせていただきましたが、その最たるものはこのデュッテンベルグのピノ・グリ・・・かもしれません。
ひじょ~に繊細なワインなんですよね。過去のNoisyのレビューを年を追うごとに繊細さに磨きがかかっているのではないか・・と感じます。
香りは控えめなところから、青い柑橘、青りんご、そしてドライなのにあまい、よく磨かれた日本酒のような吟醸香・・!
昨今の日本酒はワインのようにどんどんアロマティックになっていっておりますが、デュッテンベルグのピノ・グリは逆にどんどん日本酒に近づいてる・・?のかもしれません。
モンラッシェ近郊のミネラル爆弾や、シャブリのような分厚さのあるミネラリティではなく、細か~く浸透したような日本的な「侘寂」を感じるミネラリティです。
ルイ・モーラーらしい「じんわりとした果実の旨み」がジワジワと上がってきて、これはフレンチレストランよりも、出汁の効いた煮物や、焼き魚にはじかみみたいのが合いそう・・・そうだ!女将さんのいるあそこの割烹料理屋に持ち込もう・・!なんて気持ちにさせてくれます。
インパクトを求めるとちょっと違いますが、出汁感のシミジミさに舌鼓を打つ・・・なんてときはデュッテンベルグの出番かもしれません!ご検討くださいませ。
[ noisy wrote ]
以下は以前のレビューです。
--------
【ん?・・2021年ものとはだいぶ色調が異なる??・・でも、味わいはかなり似ているし・・でもミネラリティの出方がちょっと違うかも??】
 ・・とても旨いです!・・ピノ・グリなんですが、むしろ2021年ものよりもクリスタルなミネラリティが多分に存在しているような感じがします。
・・とても旨いです!・・ピノ・グリなんですが、むしろ2021年ものよりもクリスタルなミネラリティが多分に存在しているような感じがします。何しろ2021年ものの時は、一瞬これもオレンジか?・・と思った位ですから・・オレンジ的なソフトさと、ちょっとした濁りと、収穫の遅さ??・・みたいなものは感覚的に持っていたと思います。
2022年ものはむしろ若々しく、透明なミネラリティが多分に有り、それこそ・・
「・・あれ?・・これってピノ・グリなの?」
と、品種を疑ってしまうような、素直なスパイスと、やや硬質な果実の風味を感じ、とてもスタイリッシュで完成度が高いと感じました。
アルザスワインって、結構に「熱」を感じるシュチュエーションが多いんですが、このピノ・グリも冷ややかです。ルイ・モーラーのワインは基本、結構にドライで冷ややか、エレガントで・・なので、そのアルザス風の熱風とか蒸し暑さとかは出て来ないんですね。
 やや色落ちして見えるのは、おそらく、
やや色落ちして見えるのは、おそらく、「野生酵母を使用することと、発酵初期にSo2を使用しないこと」
に由来すると想像しています。
まぁ・・現在は野生酵母を使用してボラティル値を上げないためには様々な手法が有って、どのような手法を取っているのかは判りませんが、
「ルイ・モーラーはその辺り、かなり上手い!」
と言えます。
仕上がるワインは美しく、ドライでナチュラルで、でも危険性はほぼ無いんですね・・。ぜひ飲んでみてください。ピノ・グリがこれほどピュアで透明感が有るんだ?・・と驚かれるでしょう。お薦めです!
以下は以前のレヴューです。
-----
【優しくナチュラルな果実感の高い、ほんのりスパイシーなピノ・グリ!これも滅茶旨いです!】
 色彩だけ見れば・・オレンジワインにかなり近いですよね・・(^^;;
色彩だけ見れば・・オレンジワインにかなり近いですよね・・(^^;;ですがこちらは、発酵時に果皮と種子を漬け込まないので、多分・・オレンジワインとは言わないはずです・・知りませんが。オレンジワインの発祥の地と言われているジョージアでは元々、白葡萄もマセラシオンしていたので・・オレンジ色の色素が出てオレンジワインと言われたんだと思いますが、
「こちらはオレンジワインでは無い」
としておきます。
「レトランジュ・オランジュ」の方はステンレスタンクでマセラシオンしますから、果皮と種子から色素やタンニンなどが出て、
「味わいに深みが出ている」
訳ですね。
ですが、非常に・・バランスが良く、果皮と種子からの抽出したものが出しゃばらないので、むしろ・・
「マセラシオンを意識せずに普通に美味しく飲める!」
ほどの味わいなんですね。まぁ・・あちらはゲヴェですが。
 こちらはピノ・グリですから、ゲヴェほどはスパイシーさが無く、優しいスパイスのアロマが有ります。
こちらはピノ・グリですから、ゲヴェほどはスパイシーさが無く、優しいスパイスのアロマが有ります。マセラシオンしていない、普通の白ワインの造りですから・・レトランジュ・オランジュよりはスッキリしているはず・・なんですが、
「・・ん・・そこも余り意識しないで美味しく飲めてしまう!」
のが恐ろしいところです。いや・。・モーラーさん、非常にお上手!
こちらも僅かに揮発酸は出ています。少量So2 も使用したようです。ですが、飲み終えた後の身体の自然な酔い・・と言いますか、酔い自体が非常に軽いです。
残存So2は30mg/L ほどのようで・・これだと、
「ほぼ使用していない!」
に等しいです。
通常は醸造で10~20mg/L ほどは生成されてしまう訳ですね。なので、ボトル詰めの時に「大きなタンク(1000Lほど)に耳かきで一杯」みたいな感じなのでしょう。
丸っとしたリンゴや洋ナシ、花梨、ハーブなスパイス。中域も適度な膨らみでふんわりなミネラリティがノーズに還って来ます。余韻もふんわり・・優しい味わいが長く持続します。美味しいです。是非飲んでみてください。お勧めします!
●
2023 Riesling Lerchenberg A.O.C. Alsace
リースリング・レルシェンベルグ A.O.C.アルザス
【青リンゴ、青い柑橘、吟醸香に穏やかなペトロールが手を繋ぎあったアロマの美しさ!上質で繊細なルイらしいリースリングです!】[ oisy wrote ]
 [ oisy wrote ]
[ oisy wrote ]ルイ・モーラーのリースリングは畑の組成もあるのでしょうが、どちらかと言えばその造りを反映して、「繊細」、「和の風格」を感じる佇まいです。
グランクリュであるメンヒベルグに隣接するらしく、粘性は高く、キラキラ鉱物的なミネラリティを見せながら砂質のさらっとした感覚もあり、非常に上質・・・と感じます。
一方で、THE・リースリングというようなペトロールのくどさが驚くほどなく、砂質のさらっと感がつれてくるようなさらりとした軽いペトロール香に、青リンゴや緑の皮の柑橘があり、フレッシュで活き活きとしたハーブもいます。
ですので香りと味わいが同系統でリンクしておりシームレス、一直線に繋がる感覚です。
さらに吟醸香のような日本酒風なアロマもあり、比較的に穏やか系のアロマが手を繋ぎあった美しさがあります。
酸は冷たくも温かく、ソフトでピュア。非常にバランスが取れていて繊細です。
リースリングというと冷たくも、主張が強く、ベッタリとしがちですが、レルシェンベルグはまさに真逆のキャラクターで、穏やかで主張は強くないものの多様で繊細な風味、低域からしっかりと充足感を持つ中身のしっかりとした、質実剛健なワインです。
やはり和の香味との相性が良さそうで、山椒の葉や、少しだけ生姜が効いた煮物、柚子やすだちなどの和柑橘、出汁を効かせた食材と合わせたくなります。
穏やかでピュアな液体は、まさに上質な出汁が身体に染み込むように浸透し、癒しをもたらしてくれます。
ルイ・モーラーは写真をみると、恰幅のいいお兄ちゃんという雰囲気ですが、ワインは非常に繊細で心地よい、類稀なるセンスの持ち主だと感じます。ご検討くださいませ!
[ noisy wrote ]
以下は以前のレビューです。
--------
【アルザス・リースリングとしますと、結構にスレンダーで縦延び!?少しドイツ風のリースリングがセパージュされているかと思えるほど、ファットでない質感の美味しさです!】
 これは出来も良いです。グラスの淵を粘って落ちる涙の粘性が見て取れます。そして、グラン・クリュ・メンヒベルクに隣接と言うこの畑の素性の良さが、エレガンスに現れています。
これは出来も良いです。グラスの淵を粘って落ちる涙の粘性が見て取れます。そして、グラン・クリュ・メンヒベルクに隣接と言うこの畑の素性の良さが、エレガンスに現れています。アルザスのリースリングと言いますと、そもそもが遅熟ですし、熟させないと言うような造り手の意思も有るのか、結構にグラマラスでファットな味わいかと思います。グラン・クリュになりますとその辺りが少し変わって来て、ドライに仕上げさえしますと・・涼やかでミネラリティがバッチリ感じられる縦延び系になるんですが、そんな資質が出ているのかもしれません。
ドイツのモーゼル辺りの出来の良いものは、もっと酸が立っていて、ミネラリティも金属系のものを感じるんですが、どうでしょう・・少しドイツっぽさも感じられるかもしれませんね。
そしてメンヒベルクもそうですが、「砂」の存在がまた・・そのスタイリッシュさにも影響しているでしょうし、砂の組成がまたミネラリティにも影響するはずです。
砂の中には・・あ、川砂と海砂でも結構異なるかもしれませんし、人為的に崩して砂を作ったりもしているのでしょうが、あの・・
「キラキラとした透明、白色の小さな粒」
もあるはずです。
 そして砂が有ると言うことは、元々は川だったり、海だったり・・と言う地形が多いと思われますが、
そして砂が有ると言うことは、元々は川だったり、海だったり・・と言う地形が多いと思われますが、「その砂がリースリングの味わいをクッキリとしたものにしている」
のが、この「レルシェンベルグ」なのかもしれません。
マルセル・ダイスなら・・「準1級・自称1級」かも・・しれませんね。
先だってのギルベール・ジレのサヴィニー=レ=ボーヌのワインのご紹介には、結構な頻度で「砂質」を書かせていただきました。まぁ・・単純には「さらりとしたニュアンスが加わる」と思っていて良いかとも思います。それに加え、例えば・・あのフェルム36の矢野さんのところの畑もですね・・
「昔は川底!」
と言うことで、勿論・・川の上流とか中流とか・・下流とかでも変わると思いますが、矢野さんのところは「中流?」なのかなと・・比較大きめの角の取れた丸めの石が多くて大変だったとおっしゃっているようですので・・。
で、あの素晴らしいミネラリティですよ。日本のワイン生産者さんの中でも指折りのミネラリティの有るワインを造られると思いますが、砂とか、石とか・・それが地中に有ると言うことが、あの味わいになっているのが面白いなと思っている訳です。
そしてこのリースリングにはおそらく細かな砂・・そして、風化して崩れやすくなっているんじゃないかと思えるミネラリティが有ります。ぜひ飲んでみてください。めちゃお買い得なリースリングだと思います。お薦めです。
以下は以前のレヴューです。
-----
【So2無添加のグラン・クリュに接した畑のリースリング!・・滅茶ナチュールですが、滅茶美味しい!・・リースリングのソリッドさはSo2によるものなのか?と思ってしまいそうな美味しさです!】
 思えば随分とビオ系の生産者さんには悩まされたような気がしています。今はだいぶ・・良くなったと思うんですが、例えばインポーターさんも・・
思えば随分とビオ系の生産者さんには悩まされたような気がしています。今はだいぶ・・良くなったと思うんですが、例えばインポーターさんも・・「臭い」
とは言ってくれなかった訳です。
臭い・・と言うのは色々有りますでしょう?・・自然派ワインの場合。豆っぽかったり・・お酢臭かったり・・。昔は「厩臭(うまやしゅう)」まで有りました。
noisy としましては、その辺がどうしても許せないので・・
「酢酸臭がする場合、許容範囲か範囲外か・・位は自分たちで判断して伝えましょうよ」
と・・散々、言って来た訳です。10数年も言い続けて来ましたが、ようやっとこの何年かで・・インポーターさんも、その辺りを伝えてくれるようになったと感じています。いまだに隠したい方々はいっぱいいらっしゃいますが。黙っていて販売出来てしまうのならその方が良い・・と考えているのかもしれないと、勘繰りたくなってしまいます。
で、このマーラーさんちのリースリングは何と・・
「So2無添加!」
です。それでこの色彩・・です。まっ茶っ茶じゃぁ・・有りません。美しい黄色です。もっとも・・抜栓して時間が経過しますと色は落ちて行きますが。
 で、揮発酸ですが・・ハッキリ言いましょう。
で、揮発酸ですが・・ハッキリ言いましょう。「揮発酸は有ります!」
・・(^^;;
ですが、まったくこれ・・許容範囲内です・・と言いますか、
「このワインの表情にはむしろ必要不可欠で有り、必要な要素だと言えるし、揮発酸だけを取り出してああだこうだと言う必要が無い!」
と言えると感じます。
こんなことが出来るんですね・・いや、ちょっと驚きました!
シュレールにせよメイエにせよ・・「これは勘弁して欲しいなぁ・・」と思ったことは多く有ります。
「ぷんぷんと匂って・・飲んで行くうちに揮発酸値が増大して行く」
なんてことも有る訳です。
ですが・・・非常にノーブルです!尖がったカチコチのリースリングでは無く、ふくよかでふんわり優しく丸い、しかも果実感はしっかり、ミネラリティもしっかり、余韻まで美味しいリースリングです。
これは飲んでみて欲しいですね・・未来を担う味わいになるんじゃないか・・少なくとも、この方向性は間違い無いと思います。是非飲んでみてください。お勧めします!
●
2020 Pinot Gris Grand Cru Moenchberg
ピノ・グリ・グラン・クリュ・メンヒベルグ
【ギラギラしてない、優しくしっとりなG.C.メンヒベルクのピノ・グリ!普通に有るアルザスのちょっと尖った厳しい攻めが無い!・・けれどちゃんと硬質さが存在しています。】-----すみません、こちらは以前のレヴューを使用しています。
 呆れたアルザス・グラン・クリュのピノ・グリです。まぁ・・イタリアだとピノ・グリージョですが、イタリアにはグラン・クリュ格付けはありませんしね。
呆れたアルザス・グラン・クリュのピノ・グリです。まぁ・・イタリアだとピノ・グリージョですが、イタリアにはグラン・クリュ格付けはありませんしね。アルザスではグラン・クリュの畑で、グラン・クリュを名乗れる品種で有れば、申請・官能検査を経て晴れてグラン・クリュを名乗れる訳です。
ですが、フランスでは時に・・検査で落とされる場合も場合も多く有ります。
もし・・30年前に、この色彩で審査に出したら・・通ったのかな?・・とちょっと疑問に思ってしまいました。何せ、色彩がね・・オレンジ系ですから・・。So2 がもう少し多ければ・・と言いますか、自然酵母で無ければ圧搾時にSo2を使用出来ますから、もっと黄色いはずなんですね。
マセラシオンしないまでもゆっくりと時間を掛けてプレスする・・と、どうしても酸化してしまいますから、昨今はその際に色々やったりする訳です。でもその際に失敗すると、せっかくの自然酵母が動いてくれなかったり・・するはずなんですね。
でも、
「わたし・・失敗しないので・・」
みたいに・・見事なグラン・クリュ・ピノ・グリを造っています。エチケットの真ん中の色とほとんど同じですよね・・。
 G.C.リースリングよりもよりふくよかで、ほんのりと蜜、花梨、洋ナシ、各種ピール、ハーブの複雑な構成・・です。暑苦しく無く・・あ、そうそう・・揮発酸もほぼ無いです・・と言いますか、全く気にする必要が無いです。
G.C.リースリングよりもよりふくよかで、ほんのりと蜜、花梨、洋ナシ、各種ピール、ハーブの複雑な構成・・です。暑苦しく無く・・あ、そうそう・・揮発酸もほぼ無いです・・と言いますか、全く気にする必要が無いです。滑らかで柔らか、ミネラリティもふんわり・・奥に潜むニュアンスは優雅なのでむしろブルゴーニュに近いと思いますが、現状の表面はロワール中流でしょうか。これからもっと細かな部分が出てくると思います。とても高質です。
中域は適度な膨らみが有り、余韻も穏やかな酸がたなびき、有機物のアロマや石灰系のミネラリティがノーズに戻って来ます。そして身体に優しく浸透していき、最後に非常に穏やかなスパイスを感じさせます。
いや・・良いですね~・・アルザスワインはもっと、ドギツイ(すみません)感じに攻め立ててくるのがほとんどでしょう?
優しく丸いんですよ・・スパイシーだが全然キツクないんです。だから飲んでいる人自身も自然体でいられる・・そんな感じです。飲んでみてください。ピノ・グリ・メンヒベルグ・・美味しいです!お勧めします。
●
2021 Riesling Grand Cru Moenchberg
リースリング・グラン・クリュ・メンヒベルグ
【2022年11月時点でのSo2残存量はたったの16mg/L!・・すでに半年以上経過していますから・・実質ゼロでしょう!・・裸のGCリースリング!】----すみません、こちらは以前のレヴューを使用しています。
 最近、近所に出来た地元系の野菜を美味しく食べさせてくれるレストランに、定休日にランチに行くのがマイブームになっていたりします。
最近、近所に出来た地元系の野菜を美味しく食べさせてくれるレストランに、定休日にランチに行くのがマイブームになっていたりします。もっとも・・定休日と言っても店のシャッターを開けないだけで、自宅か店かで必ず仕事をしていますから、年間休日は若干増えて7日か8日・・。どうあがいても超ブラックな店です・・と文句を言ってもど~にもならない訳ですが。
それに近所と言いましても車で15分ほど離れたところにそのレストランさんは有りますし、予約をしないと伺っても入れないこと、食材が不足して希望のものが食べられないことも有りますから、何日か前に予約を入れ忘れないようにしないといけません。
予約をネットで入れるんですが、車は乗り合わせでお願いしますと出ますし、20人も入ると一杯のお店ですからさほどは大きくは無い・・でも、いつも一杯で、女子率90パーセント超え・・間違い無し。先日も男性は2人だけでした。
このお店に伺ってみて、久しぶりに美味しい野菜を美味しく食べさせていただけたのに驚き、何度か通っている訳ですが・・やはり素材が良いだけでは無く、それをどう料理するか?・・みたいな部分がちゃんとしていないと、美味しくは食べられないですよね。ここのお店は、
「野菜の味がちゃんとする」
んですよ。歯ごたえも良い・・香りも良い・・五味もちゃんとするし、でも基本、味付けは優しい・・(^^;; まぁ、時に異なることも有るかもしれませんが。
 で、このリースリング・グラン・クリュのメンヒベルクもまた・・
で、このリースリング・グラン・クリュのメンヒベルクもまた・・「葡萄の味がちゃんとする!」
んですね~・・。
それも・・尖がってもおらず、葡萄をちゃんと感じさせてくれる・・気付けばそれはリースリングだった!・・と言う感じです。
アルザスに良くある・・僅かに甘いリースリングでは無く、基本・・全くのドライです。ですが、余計なものは全く感じず・・柔らかでしっかり香りが立つのに嫌味が無い・・訳です。
ドギツい果実が有る訳では無く、やさしく丸い・・でも繊細で・・フレッシュな素材だと感じるんですね。美味しいです。
飲んだ後に、
「・・あぁ・・飲んじゃった・・」
みたいな罪悪感が全然浮かんでこないんですね・・あ、あのお店と同じだなぁ・・と思った次第です。
因みにモーラーさんちは、以前からワインを造っていたようです。ですが、評価が余り高く無かった・・(^^;;
親父さんたちや、お爺さんたちの時代とは全然違うスタンスでルイさんが継いだ・・もしくは分けて貰ってドメーヌを興した?のでしょう。
「野菜の味がちゃんとする美味しい料理」--->「葡萄の味がちゃんとする美味しいワイン」
です。揮発酸もほとんど感じません。全く無い・・もしくは存在しなかった・・とは言いませんけど!・・それよりまず飲んでみてください。そしてこのグラン・クリュの高質さを楽しんでみてください。お勧めです・・リーズナブルです!
●
2022 Pinot Noir
ピノ・ノワール
【ドライで美しい!・・めちゃ端正なピノ・ノワールです!・・So2も少なく貴重な存在です!ポスト・ジェラール・シュレールはルイ・モーラー!?】
 ジェラール・シュレールを初めて飲んだ時は驚きました・・余りの綺麗さ、美しさに・・そして、So2 を使いたく無い人なんだなと・・INAOとも常に揉めているのがラインナップを見ても伝わって来ました。
ジェラール・シュレールを初めて飲んだ時は驚きました・・余りの綺麗さ、美しさに・・そして、So2 を使いたく無い人なんだなと・・INAOとも常に揉めているのがラインナップを見ても伝わって来ました。ただし、時折見せる・・
「・・これ、大丈夫かぁ?」
みたいにしか判断しようのない味わいが、noisy をずいぶんと迷わせてくれたんですね。
なのでそのようなキュヴェに出くわすと、
「・・これはたぶん、3~5年置けば大丈夫かな」
などと判断し、そのまましばらくお蔵入りにしてしまうとか・・でも、
「・・これ、古いのに何であるの?」
と忘れてしまうことも度々・・、ビオの難しさを実感していました。
 そんな中で時折少しだけいただけたシュレールのシャン・デ・ゾワゾーの美しい味わいには・・驚きましたね・・
そんな中で時折少しだけいただけたシュレールのシャン・デ・ゾワゾーの美しい味わいには・・驚きましたね・・あそこは白葡萄の畑のようで、石灰が強く淡い色調になっており・・華やかな美しいアロマでした。このピノ・ノワールも、
「とんでもなくドライ!」
ですが、旨味をちゃんと感じる酸バランスに仕上がっていて、しかもグラスの写真をご覧いただけば判ると思いますが、
「何となく白っぽい!?」
ですよね・・。
華やかな石灰由来のアロマも、シャン・デ・ゾワゾーには適わないとしても、しっかり感じます。
素晴らしい出来だと思います・・・ルイ・モーラー...ぜひ覚えておいてください。超お薦めします!
以下は以前のレヴューです。
-----
【このSo2無添加のピノ・ノワールのアロマは正にピノ・ファン的!・・薬品無しのピノ・ノワールは、シュレールのシャン・デ・ゾワゾーにも重なります。ピノ・ノワール裸の姿に驚いてください!】
 素晴らしいアロマです!・・スピードも速くノーズにふんわり・・しかしスムーズにピノの美しい香りを運んでくれます。
素晴らしいアロマです!・・スピードも速くノーズにふんわり・・しかしスムーズにピノの美しい香りを運んでくれます。フラワリーでもあり果実的でもあり香水的でもあり、しっとりしたスパイスがエレガントに香ります。
アルザスは夏場、そこそこに暑いので・・もっと真っ黒で粘土のニュアンスが全面を覆っているような、
「どちらかと言うと暑苦しい感じがするピノ・ノワール」
が多いでしょう?
ジェラール・シュレールのピノのトップ・キュヴェ、グラン・クリュなのに名乗れないシャン・デ・ゾワゾーも、淡い色彩に多分な石灰のニュアンスを持った味わいで滅茶エレガント・・でもエキスはそれなりに濃密ですが、このピノ・ノワールも・・かなり似たニュアンスを持っていると感じました。
まぁ・・シャン・デ・ゾワゾーの方が繊細さが際立っているかと思いますが、このピノ・ノワールはなんせ、
「So2無添加!」
です。
 残存量もかなり少ないですから・・言ってみれば、
残存量もかなり少ないですから・・言ってみれば、「素っ裸のピノ・ノワール!」
なんですね。
初めてシュレールのシャン・デ・ゾワゾーを飲んだ時はおったまげましたが、惜しくも届かないまでも・・
「かなり近いんじゃない?」
と言えるんじゃないでしょうか。
白ワインよりは無添加で造りやすい赤ワインだとは言え、このレベルでワインを仕上げられることに驚きを感じます。しかもこちらは酢酸的ニュアンスはほぼ無いんですよね・・。
複雑性は届かないにせよ、シャンボールの・・ミュジニーにも近い部分にも似た素晴らしいワインでした。是非飲んでみてください。超お勧めします!
マリー・ロシェ
マリー・ロシェ
フランス Marie Rocher ロワール
● 古くよりの noisy のお客様は..ご存じなんじゃないかと思います。今回の初入荷のマリー・ロシェですが、何とあの「クロ・ロッシュ・ブランシュ」の醸造所と畑を借りて・・ナチュラルなワインを造っています。
そう・・あの新井順子さんが畑を譲っていただいたのがクロ・ロッシュ・ブランシュ。その残りの部分をクロ・ロッシュ・ブランシュが耕作してワインを販売していました。今は高齢になってしまったので、畑や醸造所を貸しているようで、あのノエラ・モランタンもそうでしたよね。このマリー・ロシェも同じです。
そしてnoisy と言えば、仲間と一緒に「クロ・ロッシュ・ブランシュ」のタンク別のキュヴェを数種飲ませてもらい良いものを選択、オリジナルのエチケットで販売もさせていただいてました。
noisy もお初ですから..じっくり向き合っています。今のところロゼの2アイテムのテイスティングで、どちらも好印象。これは飲んでいただいても「ノー」の言葉を聞かずに済む美しい味わいですので、ぜひご検討くださいませ。

マリー・ロシェは、クロ・ロッシュ・ブランシュの醸造所を借りて、2018年にナチュラルワインのミクロネゴスを立ち上げました。彼女は高校卒業後、マルセル・ラピエールで5年間ブドウ収穫を経験。その後は別の分野で働いていましたが、ナチュラルワイン造りに惹かれロワールに移住。レ・カプリアード、エルヴェ・ヴイルマード、ミカエル・ブージュ、ブリュノ・アリオンでの研鑽を経て、ミクロネゴスを立ち上げました。ワインをアール・ド・ラ・ターブル(食卓の芸術)と考えるマリーのワインは、味わいだけでなくプレゼンテーションもポエジー(詩情)に溢れています。このため初VTからパリや欧米で大ブレイク。1年以上待って日本への割り当てを確保することができました。
■ クロ・ロッシュ・ブランシュのセラーから誕生
ロワールの数多くの造り手に大きな影響を与えてきたクロ・ロッシュ・ブランシュ。その畑を引き継いで、ボワ・ルカ、ノエラ・モランタン、ローラン・サイヤール、ジュリアン・ピノーなどのドメーヌが誕生しました。また、当初ノエラとサイヤールはクロ・ロッシュ・ブランシュの醸造所を借りていました。そしてまた一人、ディディエ・バルイエとカトリーヌ・ルッソルの手助けを受けて、クロ・ロッシュ・ブランシュの醸造所でナチュラルワイン造りを始めた女性がいます。2018 ヴィンテージがデビューとなるパリ生まれのニューフェイス、マリー・ロシェです。
■ 初ヴィンテージからパリや欧米で大ブレイク
マリーは高校卒業後、マルセル・ラピエールで5 年間ブドウ収穫を経験。その後は別の分野で働いていましたが、ナチュラルワイン造りに惹かれロワールに移住。レ・カプリアード、エルヴェ・ヴイルマード、ミカエル・ブージュ、ブリュノ・アリオンでの研鑽を経て、ミクロネゴスを立ち上げました。ワインをアール・ド・ラ・ターブル(食卓の芸術)と考えるマリーのワインは、味わいだけでなくプレゼンテーションもポエジー(詩情)に溢れています。このため初VT からパリや欧米で大ブレイク。1 年待ってやっと一昨年から日本への輸入を始めることができました。
マリー・ロシェは、自分が美味しいと思うワインを造りたいと考えています。それは畑とブドウに由来する自然なアロマを備えた、味覚を心地良く刺激してくるワイン。そして、美食的
なマティエールと柔らかさを備え、味覚の喜びと詩的な趣きが溢れるアール・ド・ラ・ターブル(食卓の芸術)なワインです。そのようなワインを造るためには、彼女自身がそのテロワー
ルと畑仕事のクオリティを知っているビオやビオディナミで栽培された造り手のブドウを収穫して醸造する必要があります。マリーは以下のような哲学を大切にしながらナチュラルワイン造りをしています。
・ブドウの質と野生酵母、醸造での入念な仕事に立脚し、可能な限りナチュラルに醸造を行う小規模な生産量のミクロネゴスであり続ける。
・自然なアロマを備えた食材と、アール・ド・ラ・ターブル(食卓の芸術)の喜びに対する情熱を持った女性としての経験によるインスピレーションを大切にする。
・自身が出版した、ジュール・ショーヴェや、人間と環境に敬意を払いながら仕事をしているアルティザン(職人)の知識やノウハウを扱った本の内容と調和が取れたワインを醸造する。
・ワインと詩情(ポエジー)を結び付ける。文筆や出版の仕事によってワインを育む時間とともに、ワインに詩情を与えること。
現在、マリー・ロシェのワインは、スウェーデン、ベルギー、アメリカ、韓国などに輸出されています。イタリアやオーストリア、カナダにも輸出される見通しです。マリーの母はテレビ朝日のパリ支局でジャーナリストとして働いていたそうです。このため、マリーも日本文化に強い関心をもっていて、自身のワインを日本に輸出できるようになったことをとても喜んでいます。
そう・・あの新井順子さんが畑を譲っていただいたのがクロ・ロッシュ・ブランシュ。その残りの部分をクロ・ロッシュ・ブランシュが耕作してワインを販売していました。今は高齢になってしまったので、畑や醸造所を貸しているようで、あのノエラ・モランタンもそうでしたよね。このマリー・ロシェも同じです。
そしてnoisy と言えば、仲間と一緒に「クロ・ロッシュ・ブランシュ」のタンク別のキュヴェを数種飲ませてもらい良いものを選択、オリジナルのエチケットで販売もさせていただいてました。
noisy もお初ですから..じっくり向き合っています。今のところロゼの2アイテムのテイスティングで、どちらも好印象。これは飲んでいただいても「ノー」の言葉を聞かずに済む美しい味わいですので、ぜひご検討くださいませ。

マリー・ロシェは、クロ・ロッシュ・ブランシュの醸造所を借りて、2018年にナチュラルワインのミクロネゴスを立ち上げました。彼女は高校卒業後、マルセル・ラピエールで5年間ブドウ収穫を経験。その後は別の分野で働いていましたが、ナチュラルワイン造りに惹かれロワールに移住。レ・カプリアード、エルヴェ・ヴイルマード、ミカエル・ブージュ、ブリュノ・アリオンでの研鑽を経て、ミクロネゴスを立ち上げました。ワインをアール・ド・ラ・ターブル(食卓の芸術)と考えるマリーのワインは、味わいだけでなくプレゼンテーションもポエジー(詩情)に溢れています。このため初VTからパリや欧米で大ブレイク。1年以上待って日本への割り当てを確保することができました。
■ クロ・ロッシュ・ブランシュのセラーから誕生
ロワールの数多くの造り手に大きな影響を与えてきたクロ・ロッシュ・ブランシュ。その畑を引き継いで、ボワ・ルカ、ノエラ・モランタン、ローラン・サイヤール、ジュリアン・ピノーなどのドメーヌが誕生しました。また、当初ノエラとサイヤールはクロ・ロッシュ・ブランシュの醸造所を借りていました。そしてまた一人、ディディエ・バルイエとカトリーヌ・ルッソルの手助けを受けて、クロ・ロッシュ・ブランシュの醸造所でナチュラルワイン造りを始めた女性がいます。2018 ヴィンテージがデビューとなるパリ生まれのニューフェイス、マリー・ロシェです。
■ 初ヴィンテージからパリや欧米で大ブレイク
マリーは高校卒業後、マルセル・ラピエールで5 年間ブドウ収穫を経験。その後は別の分野で働いていましたが、ナチュラルワイン造りに惹かれロワールに移住。レ・カプリアード、エルヴェ・ヴイルマード、ミカエル・ブージュ、ブリュノ・アリオンでの研鑽を経て、ミクロネゴスを立ち上げました。ワインをアール・ド・ラ・ターブル(食卓の芸術)と考えるマリーのワインは、味わいだけでなくプレゼンテーションもポエジー(詩情)に溢れています。このため初VT からパリや欧米で大ブレイク。1 年待ってやっと一昨年から日本への輸入を始めることができました。
マリー・ロシェは、自分が美味しいと思うワインを造りたいと考えています。それは畑とブドウに由来する自然なアロマを備えた、味覚を心地良く刺激してくるワイン。そして、美食的
なマティエールと柔らかさを備え、味覚の喜びと詩的な趣きが溢れるアール・ド・ラ・ターブル(食卓の芸術)なワインです。そのようなワインを造るためには、彼女自身がそのテロワー
ルと畑仕事のクオリティを知っているビオやビオディナミで栽培された造り手のブドウを収穫して醸造する必要があります。マリーは以下のような哲学を大切にしながらナチュラルワイン造りをしています。
・ブドウの質と野生酵母、醸造での入念な仕事に立脚し、可能な限りナチュラルに醸造を行う小規模な生産量のミクロネゴスであり続ける。
・自然なアロマを備えた食材と、アール・ド・ラ・ターブル(食卓の芸術)の喜びに対する情熱を持った女性としての経験によるインスピレーションを大切にする。
・自身が出版した、ジュール・ショーヴェや、人間と環境に敬意を払いながら仕事をしているアルティザン(職人)の知識やノウハウを扱った本の内容と調和が取れたワインを醸造する。
・ワインと詩情(ポエジー)を結び付ける。文筆や出版の仕事によってワインを育む時間とともに、ワインに詩情を与えること。
現在、マリー・ロシェのワインは、スウェーデン、ベルギー、アメリカ、韓国などに輸出されています。イタリアやオーストリア、カナダにも輸出される見通しです。マリーの母はテレビ朝日のパリ支局でジャーナリストとして働いていたそうです。このため、マリーも日本文化に強い関心をもっていて、自身のワインを日本に輸出できるようになったことをとても喜んでいます。
●
N.V.(2023) les Passantes Rouge V.d.F.
レ・パサント・ルージュ V.d.F.
【思わず一目惚れをしてしまうような、蒸れ感のある赤果実が魅惑的なガメイです!】[ oisy wrote ]
 [ oisy wrote ]
[ oisy wrote ]蒸れ感のあるガメイです・・!
しんなりと、蒸れた赤い果実が、香水感を伴って上がってきます。「蒸れ」というのは人によってポジティブか、ネガティブか受け取り方が違うかもしれませんが、oisyはかなりポジティブな要素として使っています。
そしてこの蒸れというのは、妖艶さを助長する要素でもある・・と感じています。
このワインにもフレッシュなエレガンスが備わっています。そこに蒸れがあることで、ちょっと妖艶な感じが強まっているように感じるんですね。まるで「一目惚れ」をしてしまうかのような・・・
もしかしたらマリーはこの香りに「レ・パサント(一目惚れしてしまった通りすがりの女性達)」と名づけたのかな・・・と想像してしまいます。
味わいは柔らかく、ピュア。ジューシーさもありながら奥行きを感じさせる深みがあります。若々しくも魅力的なワインです。
赤い果実の中にはほんのり緑を感じるスパイシーさがあり、そのギャップも「萌え」要素かと思います。
抜栓仕立てはフレッシュ感が支配気味です。しかし液量が残った状態で2〜3日放置するとかなりエレガンスが立ってきます。
価格帯的にも割と早めに飲まれる方が多いと思われるので、よかったらちょっと我慢して試してみてください。酸素を含ませるとしても、グラスで頑張ってスワリングしたり、デキャンタージュで一気に含ませるよりも、前日抜栓で緩やかに、穏やかに接触させた方がエレガンスが出てくるように思います。
以前はカベフラとのミックスだったようですが、2023はガメイ単体です。ご検討くださいませ!
[ noisy wrote ]
以下は以前のレビューです。
--------
【新井順子さん・・対マリー・ロシェ..と言う構図も有りなんじゃないでしょうか?・・ガメを2に対しフランを1と言う、まさにロワールの黒葡萄をバランス良く表現したワインです!】
 重厚さが有りながらスパイシーさも有るフランを1/3に、軽快ながらもジューシーなガメを2/3とセパージュしたのがこれ、レ・パサント・ルージュです。
重厚さが有りながらスパイシーさも有るフランを1/3に、軽快ながらもジューシーなガメを2/3とセパージュしたのがこれ、レ・パサント・ルージュです。到着は2023年の1月頃だったか・・若い感じがまだあるなぁ・・と思いつつも、何故か店頭で売れてしまい、半端な本数しかなくなってしまたったので、レ・ヴァルスーズやヴォワラ・レテと言うロゼ・コンビはご案内させていただきましたがご紹介が遅れてしまっていました。
なので、その頃の価格ですから・・安いと思います。次回はいつになるか判りませんが、今はユーロは175円と30円ほどユーロは上がっていますから・・お財布にはちょっと厳しくなりますよね。
やはり noisy としましては、「クロ・ロッシュ・ブランシュ」と言うと思い入れが有る・・と言いますか、良くも悪くも色々と思い出す訳ですね。
新井順子さんがドメーヌ・デ・ボワ・ルカとして始めた時にクロ・ロッシュ・ブランシュから畑を分けていただいた訳ですが、その話しを聞いた時には、
「・・え~~っ!」
と、喉から心臓が飛び出すアニメよろしく、ビックリしたものです。あのクロ・ロッシュからか~・・と。
で、順子さんも美味しいガメを何種類か、ソーヴィニヨン・ブランも、カベルネ・フランもリリースしていました。
noisy には、クロ・ロッシュ・ブランシュ時代のガメの味わいも身体に染み込んでいますし、順子さんのガメもまた、毎年のようにテイスティングしていましたから良く判ります。もちろん、
「トゥーレーヌ・カベルネ・フラン」
としてリリースしていたボワ・ルカの味わいも・・です。
 ロワールのカベルネ・フランは単独だと・・普通に仕上げた場合は・・やや渋く、タンニンや酸が少々暴れ気味・・と言うじゃじゃ馬的な性格も有ります。
ロワールのカベルネ・フランは単独だと・・普通に仕上げた場合は・・やや渋く、タンニンや酸が少々暴れ気味・・と言うじゃじゃ馬的な性格も有ります。順子さんはその辺、かなり上手く手懐けながらフランをリリースしていたと思います。ガメも良く熟していて滑らかで美味しかったですよね。
まさにそんな感じのガメとフランを2/3、1/3と言うセパージュでブレンドし、さらに表情の起伏を滑らかにしたかのような感じなのが・・このマリー・ロシェのレ・パサントなんですね。
フランの暴れん坊ぶりをガメが鎮める感じ・・と言うよりは、
「ガメの滑らかでジューシーな美味しさを生かしながら、フランの複雑なアロマと重厚な部分をコアに置いた」
かのような仕上がりです。
昨年9月にテイスティングしたところ、かなり美味しくなっていたので・・店にいらした方にお勧めしている内にこんな数になってしまいました。
「レ・パサント」とは通りすがりの女・・と言う意味らしいですが、まさに!・・順子さんもマリーも・・いや、これは絶対内緒にしてくださいね・・(^^;;
色彩も濃い目にみえますが味わい的に濃くて暴れが有る感じでは無く、ちょうど良い濃度に仕上がっている感じで、滑らかでしなやかに身体に浸透してくる感覚が有ります。飲んでみてください。お薦めです。
●
N.V.(2023) la Tendresse Rouge V.d.F.
ラ・タンドレス・ルージュ V.d.F.
【ピノ・ノワール&ドニスの赤い果実のエキスを、重ねて、奥行きが産み出されています・・!】[ oisy wrote ]
 [ oisy wrote ]
[ oisy wrote ]最近はシャトー・カズボンヌや、ラロック・ダンタンのように「濃い色合いなのに、重くない」というワインにはよく出会ってきましたが、このワインは「淡く見えるのに、薄くない」ワインです。
湿り気のある赤果実、淡い赤が連想させるのはハリのある「チェリー」。
ライトな質感ながら、エキス的な重なりがあり、液体は隙間なく、絶え間なく連続して次から次へと薄いエキスの層を流し込んできます。
そしてエキスの重なりが産み出す奥行きがあり・・・重なり由来の、しっかりと探っていける深みがあります。
深みを感知すると、このワインはどこまで伸びていくのだろうか・・・と考えてしまうのはワインラヴァーの性でしょうか。一見キャッチーな香りから、デイリーな軽いワインかと思ってしまうのですが、時間をかけて飲み込んでいくうちにこのワインの持つ深みに虜になっていきます。
質感としてはドライなワインですが、エキスが産み出す果実の甘やかさがあり、それが優しく口内をタッチしていきます。
遺伝的な関係はありませんが、同じ松かさが由来のピノがつく2品種を使用しています。マリーはその特徴をよく把握し、造りを変えている・・と感じます。
70%を占めるピノ・ノワールは10%全房で、30%を占めるピノ・ドニスは完全徐梗です。ですので、あくまでピノが主体の味わいに、ピノ・ドニスのスパイシーさが出過ぎないように、しかしスパイシーさはほんのり感じられるような具合で、仕上げられています。
色合いの薄さと反比例するような深みを感じるのもロワールのピノ・ドニスのキャラクターかと思います。
このワインにおいては、キャッチーなチェリー感を担当するのはピノ・ノワール。ドニスだけだとドライになりすぎてしまうところに潤いを与えているのもまたピノ・ノワールの要素かと思います。
ドニスの足りないところを、ピノ・ノワールが補い、ピノ・ノワールに不足しがちな部分をドニスがサポートする、そうしてこの淡いながらも充実したワインはバランスしています。
ロワールの赤にありがちな硬さはなく、まさに、優しく、染み入る味わいです。聞いたことはありませんが、なんとなくラ・タンドレスの曲が想像できるような気がします。ご検討くださいませ!
●
N.V.(2023) Dansez Blanc V.d.F. Mousseux Brut Nature
ダンセ・ブラン V.d.F. ムスー・ブリュット・ナチュール
【ビターな柑橘が強炭酸に乗って、喉奥目掛けて一直線に向かってきます!】[ oisy wrote ]
 [ oisy wrote ]
[ oisy wrote ]正直「またかよ・・・」と思ってしまいました。
だってまたロワールの、シュナン・ブランの、めちゃくちゃ旨いペット・ナットに出会ってしまったんですから・・・!
その代表格であるレ・ゴーシェの、蜂蜜のようにあまやかな香りで、ふくよかなスタイルとはまた違ってきます。(レ・ゴーシェもご好評いただきありがとうございます!)
まず泡がですね・・・めちゃくちゃ旺盛なんです!
瓶差はあるかもしれませんが、ハイボールでいったら強炭酸のレベルです。そして泡の粒子も結構細かい。写真のボトルに浮かぶ泡が分かりますでしょうか?抜栓仕立てはまるで鮭の遡上のように、瓶の中でかなりの勢いで泡が上がっていくのが観察できます。
ですから、抜栓時は気をつけてください。T字型のシャンパーニュ・コルクですが、普通に開けたら抑えきれないかもしれません。オイジーの慢性腱鞘炎の手では抑えられませんでした。シンクで瓶の頭にタオルを被せ、左手でタオルごと瓶の首を持ち最悪吹き飛んでもコルクが飛んでいかないようにし、右手でタオルの上から抜栓することをお勧めします。
主体は「ビターな柑橘」です。イメージ的にはグレープフルーツが近いです。
で、「充実度」がめちゃくちゃ高い。「ビターな果実が液体にいっぱい」なんです。
その充実した果実が強炭酸に乗って一直線に「喉奥」に向かってくるんです。
え〜つまりですね・・・
「喉越しがめちゃくちゃ良い!」
んです。
まるで某大手メーカーのビールを思い起こす表現ですよね・・チープな印象になりそうであまり使いたくはなかったんですが、このダンセを表すにはかなり適しているのかな、と。ですので誤解を恐れずに使用させていただきました。
最近暖かくなってきて、汗をかく日も増えてきませんか・・? そういう日にこれを飲んだら、もう止まりません。oisyはたまたま梱包が激・忙しい日にこのワインをテイスティングしたのでグラスに注ぐ手がもう止まりませんでした・・・笑
それで、ゴクゴクと飲んでいるとふと気づくんですよ。この還ってくる旨みと充実感はなんだ・・?と。
徐々に泡が抜けてくるとその正体に見えてきます。泡に隠されていましたが、液体自体はかなり密度があってオイリー。この充実感の正体は果実の密度とロワールらしい岩っぽい厚みのあるミネラリティが充足していることにあります。
汚れのない、密度あるピュア果実をこのミネラリティが膜を張るようにコーティングしています。泡が通り過ぎた舌の上を、オイリーな液体が通過していくので、口内が常に充実しています。
だから「グビッ」と飲んで旨いし、喉が喜ぶ。その上で舌が満たされているから充実度が高い。さらに言えば本領は泡が抜けた後でしょう。スティルワインになってしまってもうまいんです。
最近のロワールのペットナットはこんなにもクオリティ高いものばっかりでどうなっちゃってるんでしょうか・・? シュナン・ブランとペットナットの相性の良さを感じずにはいられません。
パートナーと一緒にこれを飲んで「シャル・ウィ・ダンス?」なんてできる日本人はごく少数でしょうが、このダンセは思わず踊りだしたくなるような、気持ちを上げてくれる泡でございます。ご検討くださいませ。
●
N.V.(2021) Emmenez moi Blanc
アムネ・モワ・ブラン
【酸っぱく無い梅?な感じがする締まったムニュ・ピノ!・・目が詰まっていて、シトラス、黄色い柑橘のニュアンスが素晴らしいです!】
 ル・クロ・デュ・テュエ=ブッフのティエリー・ピュズラやパスカル・ポテールなど、多くのロワールのナチュール生産者もリリースするムニュ・ピノです。
ル・クロ・デュ・テュエ=ブッフのティエリー・ピュズラやパスカル・ポテールなど、多くのロワールのナチュール生産者もリリースするムニュ・ピノです。しかし・・高くなりましたね~・・テュエ=ブッフのル・ブラン・ド・シェーヴルにしても5千円って・・ちょっと信じられません・・昔を知っていると・・まぁ、ユーロは何故に高値になって行くのか、経済音痴の noisy にはどうも理解できません。有事の円として円が買われるようにならないことも期待はしていますが、新旧軍備の輸出でユーロもドルも高値安定なんでしょうか・・なんだかなぁと・・非常に残念では有ります。
ムニュ・ピノって時折聞かれる品種ですが、シュナン・ブランから分かれた亜種のようですね。noisy 的には・・飲んだ時にちょっと「ムニュっ」とする感じ・・と言う風に覚えています。ほぼダジャレですが、ちょっとキュッと締まった酸・・それもパレット一杯に拡がるようなものでは無く、小さな球のようなニュアンスで・・だから「すっぱくない梅」などと思っていますが、シュナンのように豪放な味わいになることは無く、ドライに仕上がってキュッと丸い酸のある
「愛らしい味わい」
を持った、ちょっと・・
「ソーヴィニヨンも・・入ってる?」
みたいな感覚です。あ、あの・・
「アルザスのミュスカをロワールで造ったような感じ」
なんても思ったりすることも有ります。
 それに・・そうそう、白カビ系のチーズ的な感じもします・・カマンベールとかブリとか。
それに・・そうそう、白カビ系のチーズ的な感じもします・・カマンベールとかブリとか。味わいは甘く無くドライで、かなり白っぽい、そして少々粉っぽいほどに細やかな石灰っぽくもあり、黄色い柑橘と洋梨系の果実、中域もド太くはならずに平均的な太さで美しい曲線を滑らかに描きながら、また愛らしい余韻をたなびかせてくれる感じです。
このマリー・ロシェさん、決してアヴァンギャルドには陥らず、美しい表情を可憐にも、精緻にも見せてくれるので・・素晴らしいですね。
そして硬質さは余り感じられませんが、結構に細やかな部分で硬さ、ソリッドさと言いますか、締まりが有ると言う感じです。グラスを斜めに走る涙は結構に粘性を感じますが、「粘る」と言う感じは無く、さらっとしつつ、それなりに長居してくれる感覚です。
素晴らしい出来だと思います。価格も安いです・・この位の価格なら良いでしょう?・・飲んでみてください。きっとマリー・ロシェさんのファンになってしまうでしょう。お薦めします!
ドメーヌ・マルク・ロワ
マルク・ロワ
フランス Domaine Marc Roy ブルゴーニュ
● ドメーヌ・マルク・ロワの2022年です。noisy も本気では気付かないうちにマルク・ロワの評価も爆上がりしていたようです。看板のキュヴェ・アレクサンドリーヌ2022年はラ・ルヴェ・デュ・ヴァン・ド・フランス誌で何と・・95ポイント、ヴィエイユ・ヴィーニュ2022年も93ポイントと、
「まるでグラン・クリュとプルミエ・クリュの評価を思わせるような評価」
が出ていたんですね。
・・一方でヴィノスのニール・マーティンさんの評価も何とか見つけ出したんですが、こちらは10年以上前からまるで変わらずで、掲載するのも憚られるほど(アレクサンドリーヌで上値91ポイントほど)だったので、静かにその画面を閉じました。
まぁ・・どちらが正しいのか、もしくはどちらも正しく無いのかは判りませんが、少なくとも2022年のA.C.ブルを飲んだ限りでは、
「マルク・ロワはかなり向上しているのは間違い無い」
と思えるんですね。
なお、価格は順調に上がっています。流石に2021年の価格が限度だろうと・・思っていたので、2022年ものの扱いをどうしようかと長く思案していまして、結局のところ、数量を抑えてご案内することにした・・ところ、上記の評価を見つけてバタバタしてしまったと言うタイミングでした。
なので、とりあえず、
「昨年の2021年ものの価格と全く同じ価格で2022年ものをご案内!」
することにし、上昇分は Noisy wine 持ちとさせていただきました。
因みに各コラムでも記載させていただきましたが、村名畑で95ポイントと言うのはまずあり得ない評価です。テイスターの立場で言うなれば、
「・・そんな怖いこと・・ようでけん・・」
と言うことなんですね。
それでもその評価をすると言うことは、評価者に冒険をさせるほどに、よほどそのワインに大きな魅力が有った・・と言うことだと思います。毎年ご購入いただいているお客様もいらっしゃいます。ぜひマルク・ロワの凄い成長、お確かめください。どうぞよろしくお願いします。
-----
マルク・ロワの、「花ぶるい」のみの「キュヴェ・アレクサンドリーヌ」、珠玉のジュヴレ=シャンベルタンです。
noisy も2009、2010、2011、2012年と飲み、2013年は少なすぎて飲めず、2014年は飲めましたよ。
性格的には、いつだかのCFの・・・
「・・・苦手なものはございますか・・?」
「ん・・・気の強い女性が・・ちょっと・・」
みたいな感じの、少し勝気な部分も持ちつつの超絶美女です。いや、やられました!是非ゲットしてください。
・・と書いていたんですが、2013年は収量激減・・。毎年5ケースほどいただいていたところ、何とたったの「12本」・・
ど~も昨今は、キュヴェ・アレクサンドリーヌの知名度が上がってしまったようで・・、検索上位で引っかかるらしく、
「マルク・ロワのキュヴェ・アレクサンドリーヌ・・何年のものでも良いので、お持ちでは有りませんか?」
とお問い合わせをいただくことが増えました。
とは言え、すぐに売切れてしまうので無いものは無い・・残念ですが、2013年は本当にどうしようもない・・。今回は飲めずにご案内のみとなります。気の強そうな女性のファンの方も多そうですので、お早めにどうぞ。
なお、下記はエージェントさんの資料より転載です。事実のみをお読み取りください。

コート・ドールでは,90年代後半から世代交代の波が急速に進んでいる。それは,アルマン・ルソー,ベルナール・デュガ=ピィ,ドゥニ・モルテといった頂 点を極めた造り手たちが凌ぎを削るジュヴレィ・シャンベルタンも例外ではない。
ジュヴレィ・シャンベルタンのコミューンで4世代続くドメーヌ・マルク・ロワは,栽培面積4ヘクタールのブドウ畑からわずか3種類(総生産量1万5千本)のキュヴェしか造ら ない(ACブルゴーニュでさえ造らない)ミクロ・ドメーヌ。このため,これまでフランス国外ではその存在がまったく知られていなかった。 しかし,数年前に 一人娘であるアレクサンドリーヌがドメーヌを引き継いでから,世界市場を目指すドメーヌへと大変貌を遂げた。『フルールス・ワインガイド/2002年版』 で,ドメーヌのジュヴレィ・シャンベルタンがドゥニ・モルテを凌ぎ,ベルナール・デュガ=ピィと同等の評価を受けたのを皮切りに,『デュセール・ジェルベ /2005年版』,『アシェット/2006年版』に初登場と,一躍桧舞台に躍り出た。しかも,『ラ・ルヴュ・デュ・ヴァン・ド・フランス/2006年 7-8月号』で行われたブルゴーニュ2005年物の水平テイスティングにおいては,ドゥニ・モルテや若手のヴィルジル・リニエ,ジェローム・ガレランをお さえ,見事ジュヴレィの2005年物No. 1の称号を獲得。もはや世界的な名声確立は時間の問題。タンザーもパーカーも,スペクテーターさえも知らない,《未来のドゥニ・モルテ,第二のアルマン・ ルソー》と呼べるジュヴレィの超新鋭ドメーヌといっても過言ではない。
【補足】:マルク・ロワ家のブドウ栽培の歴史は4世代前に遡るが,ワインはすべてバルクでネゴシアンに売却していた。元詰めを開始したのは現当主アレクサンドリーヌ/Alexandrineの父,マルク/Marcの時代から。一人娘のアレクサンドリーヌはボーヌ醸造学校を卒業後,オーストラリア,ニュージーランド,南仏,ブルゴーニュでの修行を経て,2003年にドメーヌを引き継いだ。現在,両親と3人でクシェイとジュヴレィ・シャンベルタンにある所有畑2.77ヘクタールのほか,分益耕作畑0.51ヘクタール,小作畑0.72ヘクタールを合わせ,トータル4ヘクタールの畑でブドウを栽培している。ドメーヌが手がけるワインは,ジュヴレィ・シャンベルタン“ヴィエイユ・ヴィーニュ”,ジュヴレィ・シャンベルタン“クロ・プリウール”,マルサネー“レ・シャン・ペルドリ”の3種類のみ。ACブルゴーニュやアリゴテなどはまったく生産していない。 ブドウ栽培はリュット・レゾネに則って可能な限り自然な方法で行われている。肥料は一切使用せず,有機堆肥のみ使用。ドメーヌのすべての畑で,秋と春の 2回耕耘を行う。これは,
◆畝の間の雑草を取り除き,雑草が吸収してしまう地中の養分やミネラルをブドウ樹が吸収しやすくなるようにすること
◆地表近くに伸びてしまうブドウ樹の根を切断することによってブドウの根が地中深く伸びるように誘引し,ブドウ樹がより深土の養分やミネラルを吸収して,ワインに最大限のテロワールが表れるようにする
・・・という目的がある。
ただし,マルサネー“レ・シャン・ペルドリ”の区画は標高が高く,急勾配の斜面に位置するため,耕耘を行うと,雨侵と土壌流出の危険性が高いため,耕耘は行っていない。
ドメーヌでは,ブドウの収量を低く抑えることを栽培の最も重要なことと位置付けている。すべてのブドウ樹は冬の剪定でシングル・ギュイヨ(8つ芽を残した長梢1本と2つ芽を残した短梢1本)に仕立てられるが,グリーン・ハーヴェストを行い,収穫時には1株あたり5-6房のブドウのみが残される。最近は,収量は低ければ低いほど良いというような風潮があるが,過剰な房落としは逆効果で,ブドウにストレスがかかることによってタンニンが多いブドウとなり,結果としてバランスを欠いた固すぎるワインが生まれてしまう。
このため,ドメーヌでは収穫時に残す房の数は5-6房以下にはしないようにしている。ブドウの収穫・選別に関してはさらに厳格で,熟していないブドウや病気に冒されたブドウはすべて取り除かれる。ドメーヌの収穫は20年以上一緒に仕事をしている収穫人のみで行われる。毎年の天候に応じて,どのようなブドウを収穫し,どのようなブドウを取り除くかが,各収穫人たちに明確に説明されるため,収穫されるブドウはその場で各収穫人によって選別される。
また,収穫日の直前段階で,真南向きの畝に多い焼けたブドウは,当主アレクサンドリーヌと父マルクの手で取り除かれるため,収穫ブドウに混入することは決してない。各収穫人が小さなカゴで集めたブドウは,ブドウ同士が重さで潰れないように底の浅いケースに移されるが,その際,必ず収穫した人間とは別の人間(アレクサンドリーヌやマルク,あるいは収穫人の責任者)が再度ブドウを選別し,絶対に質の良くないブドウが混入しないように細心の注意を払っている。
この結果,収穫ブドウがセラーに到着してから,選別台に広げてブドウが潰れたり,傷んだり,あるいは酸化してしまう危険性はまったくない。
収穫したブドウは100%除梗,16度の温度で約3日間低温マセレーションを行う。その後,温度を上げてアルコール発酵が自然に起こるように誘引する。
アルコール発酵は32-34度の温度で自然酵母のみでステンレス・タンクで実施。発酵中はルモンタージュと足によるピジャージュを毎日1回交互に実施(朝,ルモンタージュを実施したら,夕方ピジャージュを実施)する。
発酵が終了に近づいたらピジャージュは行わず,ルモンタージュのみ1日1-2回実施。アルコール発酵を含めたキュヴェゾン(果皮浸漬)の期間は14-15日。圧搾後バリックに移し,マロラクティック発酵と熟成。マロラクティック発酵終了後に澱引きしてアッサンブラージュを行う。熟成期間は12ヶ月。清澄は行わず,ごく軽い濾過の後,瓶詰め。瓶詰め後,さらにドメーヌで6ヶ月寝かせてからリリースされる。
収穫したブドウは100%除梗,16度の温度で約3日間低温マセレーションを行う。その後,温度を上げてアルコール発酵が自然に起こるように誘引する。アルコール発酵は32-34度の温度で自然酵母のみでステンレス・タンクで実施。発酵中はルモンタージュと足によるピジャージュを毎日1回交互に実施(朝,ルモンタージュを実施したら,夕方ピジャージュを実施)する。
発酵が終了に近づいたらピジャージュは行わず,ルモンタージュのみ1日1-2回実施。アルコール発酵を含めたキュヴェゾン(果皮浸漬)の期間は14-15日。圧搾後バリックに移し,マロラクティック発酵と熟成。マロラクティック発酵終了後に澱引きしてアッサンブラージュを行う。熟成期間は12ヶ月。清澄は行わず,ごく軽い濾過の後,瓶詰め。瓶詰め後,さらにドメーヌで6ヶ月寝かせてからリリースされる。
■コメント:1990年以来15年ぶりの超当たり年となった2005ヴィンテージに初めて造られた奇跡のキュヴェ。なんと,ドメーヌが所有するジュヴレィ・シャンベルタン域内の畑で栽培されるピノ・ノワールのなかで,ミルランダージュ(=結実不良)のブドウのみを選りすぐって醸造したキュヴェ。
故アンリ・ジャイエがミルランダージュのピノ・ノワールをこよなく愛していたことは良く知られているが,ミルランダージュのブドウだけでキュヴェを造ったのは,長いブルゴーニュの歴史でも,これが史上初のことでしょう。至上最高のピノ・ノワールとされるミルランダージュ。神様アンリ・ジャイエの片鱗を感じさせるキュヴェです。 平均収量30ヘクトリットル。総生産量1200本。新樽比率50%。使用する樽は,カデュス/Cadus社製のアリエ産とニエーヴル産のバリック。樽の焼きはアリエがミディアム,ニエーヴルがウェルダン。
ジャッキー・リゴーは,自著『アンリ・ジャイエのワイン造り』のなかで,ミルランダージュについてこう述べている:
・・・ミルランダージュは面白い現象であり,これが発生した果粒は,種のある普通の粒とは生理機能が大きく異なっている。ミルランダージュの粒は果肉が発達せず,その代わりに果皮に蓄えられる香り成分(ポリフェノール)が多くなる。ミルランダージュの年はいつも色が濃く,香りの赤いワインができるのであり,1978年,1988年,1995年などがそれにあたるだろう。ミルランダージュは,安定した濃い色,果実味,重厚なタンニンや複雑なボディをもたらしてくれるのである。ミルランダージュのもうひとつの利点とは,同じ房についている正常な果粒と比べてカリウム含有量が少ないことである。というのもカリウムは,ワインの酸味を保つ上でマイナスとなるからだ。ミルランダージュの比率が高くなると,ワインのpHを下げることができ,つまりは長期熟成が可能な卓越したワインになるというわけである。さらに,ミルランダージュはブドウの房内に間隔をつくり,空気の循環をよくしてくれもする。灰色カビ病の繁殖を防ぐことによって,こうしたカビに由来する悪い風味からワインを守り,間接的にワインの質を高めてくれる。
また,アンリ・ジャイエも同じ本のなかでこう述べている:
「最良のブドウとはミルランダージュが起きたものであり,そこからは色の濃い濃縮されたワインが生まれてくる」
「ブルゴーニュではミルランダージュが歓迎されているのだが,それはこの現象が起きると果肉がわずかしか発達せずに皮の部分が厚くなり,アロマ(ポリフェノール)が豊かになるからだ。ミルランダージュが起きたと誌には,色が深く,タンニンがしっかりしていて香りの高いワインが生まれる。」
「まるでグラン・クリュとプルミエ・クリュの評価を思わせるような評価」
が出ていたんですね。
・・一方でヴィノスのニール・マーティンさんの評価も何とか見つけ出したんですが、こちらは10年以上前からまるで変わらずで、掲載するのも憚られるほど(アレクサンドリーヌで上値91ポイントほど)だったので、静かにその画面を閉じました。
まぁ・・どちらが正しいのか、もしくはどちらも正しく無いのかは判りませんが、少なくとも2022年のA.C.ブルを飲んだ限りでは、
「マルク・ロワはかなり向上しているのは間違い無い」
と思えるんですね。
なお、価格は順調に上がっています。流石に2021年の価格が限度だろうと・・思っていたので、2022年ものの扱いをどうしようかと長く思案していまして、結局のところ、数量を抑えてご案内することにした・・ところ、上記の評価を見つけてバタバタしてしまったと言うタイミングでした。
なので、とりあえず、
「昨年の2021年ものの価格と全く同じ価格で2022年ものをご案内!」
することにし、上昇分は Noisy wine 持ちとさせていただきました。
因みに各コラムでも記載させていただきましたが、村名畑で95ポイントと言うのはまずあり得ない評価です。テイスターの立場で言うなれば、
「・・そんな怖いこと・・ようでけん・・」
と言うことなんですね。
それでもその評価をすると言うことは、評価者に冒険をさせるほどに、よほどそのワインに大きな魅力が有った・・と言うことだと思います。毎年ご購入いただいているお客様もいらっしゃいます。ぜひマルク・ロワの凄い成長、お確かめください。どうぞよろしくお願いします。
-----
マルク・ロワの、「花ぶるい」のみの「キュヴェ・アレクサンドリーヌ」、珠玉のジュヴレ=シャンベルタンです。
noisy も2009、2010、2011、2012年と飲み、2013年は少なすぎて飲めず、2014年は飲めましたよ。
性格的には、いつだかのCFの・・・
「・・・苦手なものはございますか・・?」
「ん・・・気の強い女性が・・ちょっと・・」
みたいな感じの、少し勝気な部分も持ちつつの超絶美女です。いや、やられました!是非ゲットしてください。
・・と書いていたんですが、2013年は収量激減・・。毎年5ケースほどいただいていたところ、何とたったの「12本」・・
ど~も昨今は、キュヴェ・アレクサンドリーヌの知名度が上がってしまったようで・・、検索上位で引っかかるらしく、
「マルク・ロワのキュヴェ・アレクサンドリーヌ・・何年のものでも良いので、お持ちでは有りませんか?」
とお問い合わせをいただくことが増えました。
とは言え、すぐに売切れてしまうので無いものは無い・・残念ですが、2013年は本当にどうしようもない・・。今回は飲めずにご案内のみとなります。気の強そうな女性のファンの方も多そうですので、お早めにどうぞ。
なお、下記はエージェントさんの資料より転載です。事実のみをお読み取りください。

コート・ドールでは,90年代後半から世代交代の波が急速に進んでいる。それは,アルマン・ルソー,ベルナール・デュガ=ピィ,ドゥニ・モルテといった頂 点を極めた造り手たちが凌ぎを削るジュヴレィ・シャンベルタンも例外ではない。
ジュヴレィ・シャンベルタンのコミューンで4世代続くドメーヌ・マルク・ロワは,栽培面積4ヘクタールのブドウ畑からわずか3種類(総生産量1万5千本)のキュヴェしか造ら ない(ACブルゴーニュでさえ造らない)ミクロ・ドメーヌ。このため,これまでフランス国外ではその存在がまったく知られていなかった。 しかし,数年前に 一人娘であるアレクサンドリーヌがドメーヌを引き継いでから,世界市場を目指すドメーヌへと大変貌を遂げた。『フルールス・ワインガイド/2002年版』 で,ドメーヌのジュヴレィ・シャンベルタンがドゥニ・モルテを凌ぎ,ベルナール・デュガ=ピィと同等の評価を受けたのを皮切りに,『デュセール・ジェルベ /2005年版』,『アシェット/2006年版』に初登場と,一躍桧舞台に躍り出た。しかも,『ラ・ルヴュ・デュ・ヴァン・ド・フランス/2006年 7-8月号』で行われたブルゴーニュ2005年物の水平テイスティングにおいては,ドゥニ・モルテや若手のヴィルジル・リニエ,ジェローム・ガレランをお さえ,見事ジュヴレィの2005年物No. 1の称号を獲得。もはや世界的な名声確立は時間の問題。タンザーもパーカーも,スペクテーターさえも知らない,《未来のドゥニ・モルテ,第二のアルマン・ ルソー》と呼べるジュヴレィの超新鋭ドメーヌといっても過言ではない。
【補足】:マルク・ロワ家のブドウ栽培の歴史は4世代前に遡るが,ワインはすべてバルクでネゴシアンに売却していた。元詰めを開始したのは現当主アレクサンドリーヌ/Alexandrineの父,マルク/Marcの時代から。一人娘のアレクサンドリーヌはボーヌ醸造学校を卒業後,オーストラリア,ニュージーランド,南仏,ブルゴーニュでの修行を経て,2003年にドメーヌを引き継いだ。現在,両親と3人でクシェイとジュヴレィ・シャンベルタンにある所有畑2.77ヘクタールのほか,分益耕作畑0.51ヘクタール,小作畑0.72ヘクタールを合わせ,トータル4ヘクタールの畑でブドウを栽培している。ドメーヌが手がけるワインは,ジュヴレィ・シャンベルタン“ヴィエイユ・ヴィーニュ”,ジュヴレィ・シャンベルタン“クロ・プリウール”,マルサネー“レ・シャン・ペルドリ”の3種類のみ。ACブルゴーニュやアリゴテなどはまったく生産していない。 ブドウ栽培はリュット・レゾネに則って可能な限り自然な方法で行われている。肥料は一切使用せず,有機堆肥のみ使用。ドメーヌのすべての畑で,秋と春の 2回耕耘を行う。これは,
◆畝の間の雑草を取り除き,雑草が吸収してしまう地中の養分やミネラルをブドウ樹が吸収しやすくなるようにすること
◆地表近くに伸びてしまうブドウ樹の根を切断することによってブドウの根が地中深く伸びるように誘引し,ブドウ樹がより深土の養分やミネラルを吸収して,ワインに最大限のテロワールが表れるようにする
・・・という目的がある。
ただし,マルサネー“レ・シャン・ペルドリ”の区画は標高が高く,急勾配の斜面に位置するため,耕耘を行うと,雨侵と土壌流出の危険性が高いため,耕耘は行っていない。
ドメーヌでは,ブドウの収量を低く抑えることを栽培の最も重要なことと位置付けている。すべてのブドウ樹は冬の剪定でシングル・ギュイヨ(8つ芽を残した長梢1本と2つ芽を残した短梢1本)に仕立てられるが,グリーン・ハーヴェストを行い,収穫時には1株あたり5-6房のブドウのみが残される。最近は,収量は低ければ低いほど良いというような風潮があるが,過剰な房落としは逆効果で,ブドウにストレスがかかることによってタンニンが多いブドウとなり,結果としてバランスを欠いた固すぎるワインが生まれてしまう。
このため,ドメーヌでは収穫時に残す房の数は5-6房以下にはしないようにしている。ブドウの収穫・選別に関してはさらに厳格で,熟していないブドウや病気に冒されたブドウはすべて取り除かれる。ドメーヌの収穫は20年以上一緒に仕事をしている収穫人のみで行われる。毎年の天候に応じて,どのようなブドウを収穫し,どのようなブドウを取り除くかが,各収穫人たちに明確に説明されるため,収穫されるブドウはその場で各収穫人によって選別される。
また,収穫日の直前段階で,真南向きの畝に多い焼けたブドウは,当主アレクサンドリーヌと父マルクの手で取り除かれるため,収穫ブドウに混入することは決してない。各収穫人が小さなカゴで集めたブドウは,ブドウ同士が重さで潰れないように底の浅いケースに移されるが,その際,必ず収穫した人間とは別の人間(アレクサンドリーヌやマルク,あるいは収穫人の責任者)が再度ブドウを選別し,絶対に質の良くないブドウが混入しないように細心の注意を払っている。
この結果,収穫ブドウがセラーに到着してから,選別台に広げてブドウが潰れたり,傷んだり,あるいは酸化してしまう危険性はまったくない。
収穫したブドウは100%除梗,16度の温度で約3日間低温マセレーションを行う。その後,温度を上げてアルコール発酵が自然に起こるように誘引する。
アルコール発酵は32-34度の温度で自然酵母のみでステンレス・タンクで実施。発酵中はルモンタージュと足によるピジャージュを毎日1回交互に実施(朝,ルモンタージュを実施したら,夕方ピジャージュを実施)する。
発酵が終了に近づいたらピジャージュは行わず,ルモンタージュのみ1日1-2回実施。アルコール発酵を含めたキュヴェゾン(果皮浸漬)の期間は14-15日。圧搾後バリックに移し,マロラクティック発酵と熟成。マロラクティック発酵終了後に澱引きしてアッサンブラージュを行う。熟成期間は12ヶ月。清澄は行わず,ごく軽い濾過の後,瓶詰め。瓶詰め後,さらにドメーヌで6ヶ月寝かせてからリリースされる。
収穫したブドウは100%除梗,16度の温度で約3日間低温マセレーションを行う。その後,温度を上げてアルコール発酵が自然に起こるように誘引する。アルコール発酵は32-34度の温度で自然酵母のみでステンレス・タンクで実施。発酵中はルモンタージュと足によるピジャージュを毎日1回交互に実施(朝,ルモンタージュを実施したら,夕方ピジャージュを実施)する。
発酵が終了に近づいたらピジャージュは行わず,ルモンタージュのみ1日1-2回実施。アルコール発酵を含めたキュヴェゾン(果皮浸漬)の期間は14-15日。圧搾後バリックに移し,マロラクティック発酵と熟成。マロラクティック発酵終了後に澱引きしてアッサンブラージュを行う。熟成期間は12ヶ月。清澄は行わず,ごく軽い濾過の後,瓶詰め。瓶詰め後,さらにドメーヌで6ヶ月寝かせてからリリースされる。
■コメント:1990年以来15年ぶりの超当たり年となった2005ヴィンテージに初めて造られた奇跡のキュヴェ。なんと,ドメーヌが所有するジュヴレィ・シャンベルタン域内の畑で栽培されるピノ・ノワールのなかで,ミルランダージュ(=結実不良)のブドウのみを選りすぐって醸造したキュヴェ。
故アンリ・ジャイエがミルランダージュのピノ・ノワールをこよなく愛していたことは良く知られているが,ミルランダージュのブドウだけでキュヴェを造ったのは,長いブルゴーニュの歴史でも,これが史上初のことでしょう。至上最高のピノ・ノワールとされるミルランダージュ。神様アンリ・ジャイエの片鱗を感じさせるキュヴェです。 平均収量30ヘクトリットル。総生産量1200本。新樽比率50%。使用する樽は,カデュス/Cadus社製のアリエ産とニエーヴル産のバリック。樽の焼きはアリエがミディアム,ニエーヴルがウェルダン。
ジャッキー・リゴーは,自著『アンリ・ジャイエのワイン造り』のなかで,ミルランダージュについてこう述べている:
・・・ミルランダージュは面白い現象であり,これが発生した果粒は,種のある普通の粒とは生理機能が大きく異なっている。ミルランダージュの粒は果肉が発達せず,その代わりに果皮に蓄えられる香り成分(ポリフェノール)が多くなる。ミルランダージュの年はいつも色が濃く,香りの赤いワインができるのであり,1978年,1988年,1995年などがそれにあたるだろう。ミルランダージュは,安定した濃い色,果実味,重厚なタンニンや複雑なボディをもたらしてくれるのである。ミルランダージュのもうひとつの利点とは,同じ房についている正常な果粒と比べてカリウム含有量が少ないことである。というのもカリウムは,ワインの酸味を保つ上でマイナスとなるからだ。ミルランダージュの比率が高くなると,ワインのpHを下げることができ,つまりは長期熟成が可能な卓越したワインになるというわけである。さらに,ミルランダージュはブドウの房内に間隔をつくり,空気の循環をよくしてくれもする。灰色カビ病の繁殖を防ぐことによって,こうしたカビに由来する悪い風味からワインを守り,間接的にワインの質を高めてくれる。
また,アンリ・ジャイエも同じ本のなかでこう述べている:
「最良のブドウとはミルランダージュが起きたものであり,そこからは色の濃い濃縮されたワインが生まれてくる」
「ブルゴーニュではミルランダージュが歓迎されているのだが,それはこの現象が起きると果肉がわずかしか発達せずに皮の部分が厚くなり,アロマ(ポリフェノール)が豊かになるからだ。ミルランダージュが起きたと誌には,色が深く,タンニンがしっかりしていて香りの高いワインが生まれる。」
●
2022 Gevrey-Chambertin Vieille Vigne
ジュヴレ=シャンベルタン・ヴィエイユ・ヴィーニュ
【RVF誌は何と93ポイント!・・これもまた凄いです!デュガ=ピィも真っ青!?・・頑張って昨年の2021年ものと同じ価格を出しています。】
キュヴェ・アレクサンドリーヌはジュヴレの畑に拡がる持ち畑から、ミルランダージュの粒のブドウだけを選んで収穫していますから、当然ながらこのV.V.の畑からもミルランダージュだけを先に抜かれている訳です。
そうなりますと・・何となくですが、
「じゃぁ抜かれた部分が無い訳だから、だいぶ落ちるのでは?」
と考えがちですよね。
noisy も大昔にマルク・ロワを扱い始めた時に飲んで以来、V.V.は飲めていませんから判りませんでしたが、
「なんとRVF誌はこのV.V.にも93ポイント!」
と大盤振る舞いしているんですね。
因みにRVF誌では無いんですが、デュガ=ピィの2022年ジュヴレ=シャンベルタン・クー・ド・ロワ・トレV.V.の評価が、
「デカンター 94 ポイント、バーガウンド 90~92 ポイント、アドヴォケイト 90~92 ポイント」
ですから、
「キュヴェ・アレクサンドリーヌはデュガ=ピィ超え!?」
「ヴィエイユ・ヴィーニュはほぼデュガ=ピィ並み!?」
と言えそうで、デュガ=ピィは上代37000円ですから・・1級畑並みの評点だと考えてみますと、
「マルク・ロワって・・この価格でもまだ安いのか?」
などと思ってしまいます。
この評価も最近になってようやっと見つけたので、このV.V.は余り仕入れて無いんですよね・・やはりいずれしっかり飲んでみないといけないかと思っています。ご検討くださいませ。
以下は以前のレヴューです。
-----
【テイスティング予定でしたが・・持ち帰るのを忘れてしまいました・・】
すみません・・飲もうと思っていたんですが、忘れて他のアイテムを持って帰ってしまい、間に合わなくなってしまいました。
もっとも6本しか入荷が無かったので、とても手を出せる状況には無いんですが、このV.V.は余り飲んだことが無いんですね。なので、敢えて滅茶評価が高くなって、それに連れて価格も上がったキュヴェ・アレクサンドリーヌ2021の数を減らすよりはと考えていた訳です。
因みにですが、このヴィエイユ・ヴィーニュ2021年のメディアの評点は探せませんでしたが、例年の評点を見てみますと、2019年で92ポイント、ラ・ルヴェ・デュ・ヴァン・ド・フランスやセラートラッカーが付けていますし、2018年ものにはベタンヌで換算93ポイントまで付いています。
もし間に合うようで時間が出来ましたら、再度書き直してアップさせていただきます・・が2024年の3月後半は入荷ラッシュになりそうで怖いです。どうぞよろしくお願いいたします。
そうなりますと・・何となくですが、
「じゃぁ抜かれた部分が無い訳だから、だいぶ落ちるのでは?」
と考えがちですよね。
noisy も大昔にマルク・ロワを扱い始めた時に飲んで以来、V.V.は飲めていませんから判りませんでしたが、
「なんとRVF誌はこのV.V.にも93ポイント!」
と大盤振る舞いしているんですね。
因みにRVF誌では無いんですが、デュガ=ピィの2022年ジュヴレ=シャンベルタン・クー・ド・ロワ・トレV.V.の評価が、
「デカンター 94 ポイント、バーガウンド 90~92 ポイント、アドヴォケイト 90~92 ポイント」
ですから、
「キュヴェ・アレクサンドリーヌはデュガ=ピィ超え!?」
「ヴィエイユ・ヴィーニュはほぼデュガ=ピィ並み!?」
と言えそうで、デュガ=ピィは上代37000円ですから・・1級畑並みの評点だと考えてみますと、
「マルク・ロワって・・この価格でもまだ安いのか?」
などと思ってしまいます。
この評価も最近になってようやっと見つけたので、このV.V.は余り仕入れて無いんですよね・・やはりいずれしっかり飲んでみないといけないかと思っています。ご検討くださいませ。
以下は以前のレヴューです。
-----
【テイスティング予定でしたが・・持ち帰るのを忘れてしまいました・・】
すみません・・飲もうと思っていたんですが、忘れて他のアイテムを持って帰ってしまい、間に合わなくなってしまいました。
もっとも6本しか入荷が無かったので、とても手を出せる状況には無いんですが、このV.V.は余り飲んだことが無いんですね。なので、敢えて滅茶評価が高くなって、それに連れて価格も上がったキュヴェ・アレクサンドリーヌ2021の数を減らすよりはと考えていた訳です。
因みにですが、このヴィエイユ・ヴィーニュ2021年のメディアの評点は探せませんでしたが、例年の評点を見てみますと、2019年で92ポイント、ラ・ルヴェ・デュ・ヴァン・ド・フランスやセラートラッカーが付けていますし、2018年ものにはベタンヌで換算93ポイントまで付いています。
もし間に合うようで時間が出来ましたら、再度書き直してアップさせていただきます・・が2024年の3月後半は入荷ラッシュになりそうで怖いです。どうぞよろしくお願いいたします。
ドメーヌ・ラロック・ダンタン
ラロック・ダンタン
フランス Domaine Laroque d’Antan カオール
 [ oisy wrote ]
[ oisy wrote ]南西地方、カオールから凄いワインを造る、新規生産者のご紹介です。
今の時代、ドメーヌを始めるとなったら畑を買ったり、譲り受けたり、それなりにベースのあるところから始める造り手が多いと思います。
しかしなんとこのラロック・ダンタン、「森を開墾」するところから始めています。
・2002年・・・荒地の森を購入
・2002〜2008年・・・開墾、整地、植樹。
・2017年・・・白ワイン、ネフェールをリリース
・2018年・・・赤ワイン、ニグリンヌをリリース
なんと土地を購入してから「16年」もかけて入念に準備してきています。一定の樹齢に達するまではリリースしないと硬く決めてきたのでしょう。
それもそのはずで、当主のブルギニョン夫妻はあのDRCやルロワ、ルフレーヴ、ジャック・セロスなどの錚々たる造り手の土壌研究をしてきた方です。そんな方が選んだ土地ですから、畑のポテンシャルを大事にするのは当たり前なのだと思います。
そして面白いのはブルギニョン夫妻の挑戦を「ほぼファーストヴィンテージ」から追いかけられるという点です。
恐らくブルギニョン夫妻の慧眼で選ばれた畑の本当のポテンシャルを引き出すには樹齢が必要だと思います。しかし現段階でもそのポテンシャルの高さはしっかりと感じられ、素晴らしいワインに仕上がっています。そしてこれが樹齢が高くなったらどうなってしまうんだろうか・・・と考えずにはいられません。そんな成長を最初から楽しめるのは今だけかもしれません。
品種も多品種、色もブルゴーニュと全く違うのに、不思議とちらつくのはブルゴーニュの畑・・・そんなワインを造るブルギニョン夫妻の活躍に目が離せません!!ご検討くださいませ!
■エージェント情報
ラロック・ダンタンは、地質学の世界的権威リディア&クロード・ブルギニョン夫妻が南西地方のカオールに創設したドメーヌです。90年代から、DRC、ルロワ、ルフレーブ、ジャック・セロスなど世界の超一流ドメーヌの畑の土壌分析をしてきたブルギニョン夫妻は、いつか引退した後に自分自身でワイン造りをしたいという夢を抱いていました。
二人は、農薬が一切使われたことのない、汚れていないピュアな畑を求めて、2002年に荒れ地の森を購入し、その荒れ地を6年掛けて開墾・整地し、理想的な品種を植樹。 場所はブルゴーニュでもボルドーでもシャンパーニュでもなく、なんと南西地方。「テロワールは品種よりも強い」という信念を持つブルギニョン夫妻が、ワイン造りの夢を心に抱いてから実に四半世紀。そして、2017ヴィンテージで白ワインを、続く2018ヴィンテージで赤ワインのキュヴェを醸造し、造り手としてデビュー。世界的な資質学者の名に恥じない『グラン・ヴァン』のフィネスを備えた南西ワインが誕生しました 。
●
2018 Nephele Blanc I.G.P. Cotes du Lot
ネフェール・ブラン I.G.P. コート・デュ・ロット
【2018はクラシック感が強め!ブルギニョン夫妻の慧眼にかなった土壌の持つミネラリティと熟度と瑞々しさの両立したコアのある液体!】[ oisy wrote ]
 [ oisy wrote ]
[ oisy wrote ]2018はネフェルの2年目のヴィンテージです。ですので、もしかしたらまだ手探りの部分はあるのかもしれません。しかしとても2年目とは思えない完成度のワインです・・・
2002年に森を購入し、6年かけて開墾、聖地、植樹ということですから植えたのは2008年ということでしょうか。そこから10年、恐らく根が一定の深さに到達するまでワインを造らなかったということなのでしょう。
もちろん10年あれば十分というわけではないと思いますが、このワインから感じるミネラリティは非常にポテンシャルを感じます。
ボーヌのような、厚さのある鉱物感のあるミネラリティ、そこにごく僅かに南の黄色い果実の風味。グレープフルーツのようなビター感。「熟しているが、余分に熟してはおらず」、冷涼さに富んでいて充実しています。
樽もそこそこ効いていると思います。スモーキーさとバニラの風味。しかし樽使いはヴィンテージによって結構違いがありますね。詳しくは2021ヴィンテージのコラムにて書こうと思っています。
しかしこの樽に負けないミネラリティがあり、「不思議と瑞々しさとも同居」しています。そしてしっかりとした「コア」を感じます。
2018ヴィンテージには少しクラシックなブルゴーニュ的なスタイルを感じます。それが、為せるのも長年の土壌分析のデータを蓄積しているブルギニョン夫妻だからこその土地選びにあるのかもしれません。品種は全く違うのに・・・です。
品種選びも相当考え抜かれたものであるように感じます。ソーヴィニヨン・ブランが50%を占めますが、ハーブ香が強いかというとそんなことはなく、多品種のブレンドというよりは
「複雑性をもった単一品種」
のように感じられるほどまとまりがあります。
ここまで「格」を感じる南西地方のワインには初めて出会いました・・!自然派ではありますが、「ワインとしての完成度」が高いです。
ようやく飲み頃に入ってきたというタイミングかと思います。ピークはまだ数年先かと思います。樹齢10年で「これ」ですからこれからが楽しみですね!ご検討くださいませ!
●
2021 Nephele Blanc V.d.F.
ネフェール・ブラン V.d.F.
【むむむ・・?ピュア感が増し、果実とミネラルの輪郭がクッキリとしてきたぞ・・!!】[ oisy wrote ]
 [ oisy wrote ]
[ oisy wrote ]あれ・・・?2018とスタイルはだいぶ違うぞ・・・
ピュア感がかなり増している・・・樽のニュアンスはほぼ感じないレベルまで下がり、果実の輪郭がはっきりしているぞ・・!
こうなるとよりこの土地のテロワールが見えてきます・・リンゴやグレープフルーツなどの黄色いドライな果実。金属的なミネラリティとそれに由来するエレガンスを放ちます。フルーツとミネラリティのあいまった、あまやかな香り・・・こりゃあたまらない!!
熟度とミネラリティ由来のオイリーさを纏っていて高い密度と充実感です。ラロック・ダンタンのワインは「よく熟しているが、余分には熟していない」という絶妙な塩梅が特徴的で、「熟度は感じるのに、瑞々しい」という、まるで塩分は控えめなのに風味は強い上質な出汁のような相反する要素を持ち合わせています。
これ今レビューを書いてて閃いたんですが、もしかしたらこの畑が森を開墾して造られた農薬を一切使っていない、「激ピュアな畑」だから・・・なのではないかと思いました。だとすると「ここ」にこそブルギニョン夫妻が人生をかけてまで表現したかったものが現れているんじゃないかな・・・と想像してみたりします。
樽使いが大きく変わったのは、様々な試行錯誤を繰り返しているから・・・あれ、あれれ?このコラムを添削しているときに気づきました。テクニカルにシレッと
「70%はジャック・セロスから譲り受けた古樽(容量228Lと400L)で発酵と熟成」
と追記されているではありませんか・・!このスタイルの変化の理由を見た気がします。古樽になったのは間違いないだろうな・・と思っていましたが、ただの古樽ではなかったようですね。ミネラルがツヤツヤと磨かれて、表に出てくるには樽の質や樽使いが重要なのかもしれない・・そんな新たな気づきを得ました・・!
それとやはり樹齢・・ですかね。ラロック・ダンタンのワインは樹齢とともに間違いなく旨くなっています。DRCやルフレーヴで土壌研究をしてきたブルギニョン博士、そのお眼鏡に適った畑でありますから、そのポテンシャルを十分に引き出すには樹齢が必要なのは間違いないでしょう。
そして樹齢や樽の進化によってこれからさらに進化していくと考えるとワクワクが止まりませんね・・!ラロック・ダンタンのワインは追いかける楽しさがあります!ほぼファーストの2018から追いかけられるというタイミングも今しかありません!ぜひご検討くださいませ!
●
2018 Nigrine Rouge I.G.P. Cotes du Lot
ニグリンヌ・ルージュ I.G.P. コート・デュ・ロット
【なんと森を開墾するところからスタート・・!伝説の始まりとなるのか・・10年以上の下準備を経てようやくファーストビンテージとなったブルギニョン夫妻のチャレンジの始まりです!】[ oisy wrote ]
 [ oisy wrote ]
[ oisy wrote ]注目のラロック・ダンタン、赤のファーストヴィンテージです・・!
むわっとくる芳香・・!黒の入った赤果実の、これはエレガンスと言って良いレベルでしょう。スピード感があります。
ブラン同様、「熟しているのに余分には熟しておらず」、果実の深みがありながらも酸も適度にハリがあります。
柔らかさのある果実、石灰と鉄分を感じるミネラリティ、余韻は色味のイメージよりもだいぶ伸びやか。果実のコクと深みはあるのに、瑞々しさも同居しているのが不思議な感覚です。
タンニンはしなやかで粒度は非常に細かいです。うっすらと樽の感じはありますね。若干ですがスモーキー&スパイシー。ヴィンテージ的にも全体的に柔らかくなってきた頃合いだと思います。まとまりが出てきて飲み頃に入ってきましたね。
しかしDRCやルロワ、ルフレーブの土壌分析してきた方が行き着くのが南西地方のカオールというのは興味深いですね。「テロワールは品種よりも強い」というのは、最近oisyがよく感じているところでもあります。
2018年ヴィンテージはニグリンヌのファーストヴィンテージということですが、10年以上の計画を立て、なんと「森を開墾」するところから始めているブルギニョン夫妻のチャレンジはまだ始まったばかりです。なんとなくですが・・・樹齢とともに化けていきそうな気配がしています。
これからどのように進化していくのか・・・伝説の始まりとなるのか・・・非常に楽しみです!ドメーヌの成長を追いかけていくにはやはりこれを飲まないと始まらないでしょう。ご検討くださいませ!
●
2021 Nigrine Rouge V.d.F.
ニグリンヌ・ルージュ I.G.P. コート・デュ・ロット
【ピュア感が増し、テロワールの輪郭がよりハッキリとしてきました!不思議と見えてくるのはブルゴーニュのあの村・・・なぜなんだ!?】[ oisy wrote ]
 [ oisy wrote ]
[ oisy wrote ]やはりニグリンヌも2018ヴィンテージとはスタイルが違い・・・ピュア感は増し、素材であるブドウをよりダイレクトに感じられるような造りになってきています!
ジューシーさとバター感が混在したようなエレガンス・・!これに近い香りを嗅いだのは、最近ではビッビアーノのグラン・セレツィオーネでしょうか。まるで質の良いメルローのようではありますが、主体はカベルネ・フラン。ここまで青さの無いカベフラもなかなか無い・・と思います。
ピュア感に磨きがかかったことで、より「酸の輪郭」がハッキリとしてきました。ディティールがより明確になったことで隙間があれば見つかりやすくなってしまうものですが、エキスの積層感が高くなったことにより、そのあたりもカバーされています。樹齢が上がってきたのが大きそうです。
不思議な感覚ですね。恐らく、地理的条件や品種などを鑑みるにボルドー的な味わいであるかと思うんですが、スタイルがブルゴーニュ的なので、飲み心地が軽く、エキスに富んでいます。ボルドー的でもあり、ブルゴーニュ的でもある・・・脳がバグるような感覚です。ただその方向性は間違いなく、ブルゴーニュの生産者が目指しているスタイルと同じなんだろうなと感じます。
肌触りも良く、タンニンもシルキーで、気にするレベルにすらありません。最近だとシャトー・カズボンヌのスタイルに似ているかもしれません。ブドウに自信がないと、できないスタイルです
温度が上がるとよりこのエキスの柔らかさとピュア感は増してきます。うっすらとヴォーヌ・ロマネのカゲロウが見えてくるような赤い果実感が膨らんできます。この地理的条件と品種で・・?と思われるかもしれませんが、不思議なことに結構な頻度でチラついてくるんです・・・
一度も農薬が使われていないピュアな畑を求め、わざわざ山を開墾し、10年かけて作った畑。それがこれほど「純」なワインを産んでいるのかもしれません。
地質学の権威が人生をかけて造るワイン、最終的な形はまだこれからなのしれませんが、私たち単なるワインラヴァーの見えている景色とは全く違うものが見えているんだろうな・・・と実感します。そしてブルギニョン夫妻の見ているもの知るには追いかけ続けるしかないのだとも。このワインを飲んで、追いかけ続けていきたいと強く思いました。
樽使いが大きく変わったのは、様々な試行錯誤を繰り返しているからということもあるでしょうが、「下手な古樽を使いたくない」というのもあるのかもしれません。ここまで丹精込めて造り上げた大事な大事な畑です。古樽をどこかから調達してきたら以前に使われていたブドウの成分が樽に染み込んでいるわけです。そこに染み込んでいるワインが農薬を使われていたものだとしたら・・・それは今までの努力をパーにしてしまうものと考えても不思議ではありません。
だとすると古樽も自身のワインで使用したものを使いたいと考えるのも自然な流れです。なのでファーストやセカンドヴィンテージは新樽をどうしても使わなければなりません。初年度の樽が古樽として使えるのは3~4年目くらいからでしょうか・・・それまでは例え自身の理想とするスタイルと違ったとしても待たなければなりません。(あくまでoisyの勝手な推察ですが) もしこの考察が正しければ2021ヴィンテージはようやくブルギニョン夫妻の求めるワインができるようになった・・・ということなのかもしれません。白はジャック・セロスの古樽を使用しているそうですが、赤は特に記載がないので、自身の古樽を使用していると思われます。
素晴らしいワインです。年々確実に良くなっていますし、樹齢が増してくると恐らくもっと良くなるのでしょう。2021はラロック・ダンタンのワインにとっても大きな変化があった年だと感じます!ご検討くださいませ。
レ・ゴーシェ
レ・ゴーシェ
フランス les Gauchers ロワール
 [ oisy wrote]
[ oisy wrote]ロワールより自然派の新規生産者をご紹介します。その名も「ル・ゴーシェ」です。
コトー・デュ・ヴァンドモワというアペラシオンをご存知でしょうか・・?僅か125haの小さなアペラシオンです。ロワール川中流に位置し、ヴーヴレから少し離れた上の方に「離れ小島」のように存在しています。
小さいアペラシオンながら情熱を持った生産者がいる地域らしく、ル・ゴーシェもその一つです。
白は主にペットナット(瓶内一次発酵の自然派ペティヤン)で、ブラン・ド・ノワールのピノ・ドニスやシュナン・ブランから実に素晴らしいペットナットを造ります。価格も安いし、正直なところ、絶対下手なシャンパーニュより良いよな~・・・と思ってしまいました。またシュナン・ブランとペット・ナットの相性の良さ・・・についても言及していますので、ぜひコラムをご確認ください。
赤はコトー・デゥ・ヴァンドモワではメインの品種の「ピノ・ドニス」と「カベルネ・フラン」です。淡いピノ・ドニスはしっかりうまいエキス系、癒し系のやわらかカベルネ・フランには心を奪われてしまいました・・・
ナチュラルで、非常に安定した造り手です!よろしくお願いします!
■ エージェント情報
パリのランジュヴァンでナチュールに開眼したロワールの新星
・国際NGO から転身してナチュラルワイン造りに
レ・ゴーシェは、2017 年にロワールのコトー・デュ・ヴァンドモワに設立されたナチュラルワインのドメーヌです。造り手であるセドリック・フルーリーはロワールのヴァンドーム出身。1990 年代のパリでの学生時代に、ジャン・ピエール・ロビノのパリのレストラン「ランジュヴァン」で彼の叔父がシェフをしていたため頻繁に通ってナチュラルワイン好きになりました。その後、経済学を修めたセドリックは、国際NGO の仕事でマリやイエメン、アフガニスタンなどで15 年間働いていました。
しかし、この間にも、休暇やヴァカンスなどにはフランスに戻り、ロワールのクロ・テュ・ブッフのティエリー・ピュズラの下で収穫、ラ・グラップリのルノー・ゲティエの下で醸造などを経験しました。
2013 年に、本格的にナチュラルワイン造りに携わりたいと考え、NGO の仕事を辞めてフランスに戻り、アンボワーズの醸造学校に入学。ドメーヌ・ド・モントリューのエミール・エレディアの下で2 年間働いた後、2017 年に地元で2.6 ヘクタールの畑を購入して、ヴァンドーム近郊のトレ・ラ・ロシェットに自身のドメーヌ『Les Gauchers レ・ゴーシェ』を立ち上げて独立しました。レ・ゴーシュとはフランス語で『左利きの人達』という意味です。セドリックも彼の娘も左利きのため、このように命名したのだそうです。初ヴィンテージは2017年で、僅か1 樽の生産量からスタートしました。ビオディナミの手法を取り入れたセドリックのワインはとても活力があり、明るくさわやかで、同時に正確さを備えた味わいです。フランス各地のナチュラルワインショップやパリのナチュラルワインのレストランで販売されている他、デンマーク、オランダ、スイスなどにも輸出されています。
・ 畑と栽培について
ドメーヌの畑は、前オーナーが植樹をした約20 年前からビオロジックで栽培されていてエコサートの認証を受けています。畑はコトー・デュ・ヴァンドモワ域内の標高115 メートルの真南向きのコート(斜面)に位置しています。大きく以下の2 つの区画に分かれていて、土壌は表土がシレックス混じりの粘土。母岩が石灰(テュフォー)となっています。
・ Montrieux モントリュー: 栽培面積1ha(ピノ・ドニス0.5ha、ピノ・ノワール0.25ha、カベルネ・フラン0.25ha)。平均樹齢19 年。
・ La Pente des Coutis ラ・ポント・デ・クティ 栽培面積1.6ha(シュナン・ブラン)平均樹齢18 年。
ドメーヌではビオディナミの認証は受けていませんが、ビオディナミで使われる、スギナ、イラクサ、ノコギリ草などの調剤を効果的に使って栽培を行っています。畑は年に2回耕耘し、畝の間にはカバークロップを生やしています。また、収穫後には羊を放牧して自然な雑草駆除(羊が雑草を食む)を行っています。ブドウ木は剪定と芽かきを行った後は、除葉もグリーン・ハーヴェストも行いません。生物多様性の促進のために、知人の養蜂家とコラボレーションして区画の横に養蜂箱を設置するなどの試みをしています。
・ 醸造とワインについて
収穫は手摘みでその場で厳格に選果されます。その後、トレ・ラ・ロシェットにある洞窟を改装したドメーヌの醸造所に運ばれて醸造が行われます。ワインは野生酵母で自発的に発酵させ、醸造添加物やSO2 は一切加えずに醸造されます。温度管理を行いません。熟成後、無清澄、ノンフィルター、SO2 も無添加で、重力を利用して自然に瓶詰めされます。
セドリックは、今でもラ・グラップリのルノー・ゲティエと、元ドメーヌ・ド・モントリューのエミール・エレディアと非常に仲が良く、頻繁に会ってワイン造りについての考えや哲学について意見交換をしています。ちなみに現在、エミール・エレディアはドメーヌ・ド・モントリューを離れ、ラングドックでドメーヌを経営。夫のクリスチャン・ショサールを亡くしたドメーヌ・ル・ブリゾーのナタリー・ゴビシェールと再婚し、ナタリーが営むネゴス、ナナ・ヴァンにブドウを提供しています。
エチケットデザインはセドリックの友人のアーティスト、Morgane Bader モルガン・バデがデザインしたものです。
●
2021 le Club Blanc V.d.F.
ル・クラブ・ブラン V.d.F.
【柑橘とホップのビター感がまるで、上質なペールエールのクラフトビールのようなバランス!充実感も素晴らしい・・!】[ oisy wrote ]
 [ oisy wrote ]
[ oisy wrote ]王冠のペットナットです。泡は一般的なペットナットレベルにあり、持続性も高いです。
ドライな味スジなんですが香りは豊かで、オレンジ、蜂蜜、金柑などのアロマティックといって差し支えない香り・・・ラン・ドノワールらしい充実した果実感と
「ホップのようなビター感」。
この泡、香り、味わいは・・・まるで「上質なペールエールのクラフトビール」を飲んでいるかのよう・・!ビターな果実感がグリップよく締めてくれるので、無駄にもたれることなく香りの余韻だけが延びていく・・気持ちが良いです。
そして再びグラスに近づくと柑橘のアロマが迎えてくれる・・・これ無限に繰り返せます・・
うまいですね・・・ 価格に見合わない密度と充実感です・・・もちろん良い意味で。
ピノ・ドニスというブドウをご存知でしょうか?オイジーは詳しく知らなかったので、調べてみました。
黒ぶどう品種です。ピノ・ノワールのPinotではなくpineauと書きます。フランス語のピンに由来し、松かさのような形を指すようです。ピノ・ノワールの「ピノ」もスペルは違いますが、同義のようです。
両者とも赤ワイン用の品種として使われたり、このル・クラブのようにブラン・ド・ノワールで使われたりで似たような使われ方をしますが、この二つの品種に遺伝的な直接の関係性は無いらしいです。
またシュナン・ノワールとも呼ばれるようですが、シュナン・ブランとの関係性も特にないようです・・・(無いんかい!笑)かつてはロワール全域で広く栽培されていたようですが、フィロキセラの流行で大幅に栽培面積を減少させたとのこと。
まあ今では出会うことの少なくなった品種なのかと思いますが・・・結構にうまいじゃないですか!もちろんセドリックのセンスが良いのはあるんでしょうが、この価格にして密度感と骨格がしっかりある!この充実感は寒い冬に飲んでも十分に満たしてくれますね・・・
サポートや励ましをくれる隣人たちの集まりをクラブと称しているためこのキュヴェの名前にしたそうです。きっと収穫の時にはわいわいクラブの人たちで作業するんでしょうね。そんな疲れた体にこのル・クラブ・・・絶対染み入りますね!
ワインとしてのマリアージュも色々考えられますが、ペールエールのビールに合うものならだいたい合いそうです。フライドポテトとかチキンとか、タルタルで食べるフィッシュフライとか!
フォーマルからカジュアルまで幅広く対応できるクオリティだと思います。コスパ素晴らしい味わいです。ぜひご検討くださいませ!!
●
2018 l'Herbe Tendre
レルブ・タンドル・ブラン(ドゥ・ピエ)
【飲み頃真っ只中・・!蜜、柑橘、酵母感とほのかに甘い熟したジュースがクセになるペットナットです!】[ oisy wrote ]
 [ oisy wrote ]
[ oisy wrote ]酵母感、熟成感、蜜、熟したレモン、みかんのフレーバー。ハリのある酸の角が取れてきて、ほのかに甘く、熟してまろやか。
こりゃうまい・・・!声を大にして言いたいと思います・・・
「飲み頃、真っ只中で~~~~す!!!」
ところでシュナン・ブランのペティヤンってもっとあっても良いんじゃない・・?って思います。
オイジー的感覚ですが、発泡性ワインになると通常のワインでは味が乗らない・・・のではないのかなと思います。舌先に最初に当たるのは泡なので、アタックが泡にごまかされて、味がしっかり感じるには泡の後にも負けない、それなりに強い味や酸が必要なのかなと。
それでロワールのシュナン・ブランは酸と強めの果実味が備わっているのでペティヤンに最適なのではないかと・・・セドリックのシュナンのペティヤンを飲んで感じます。セドリックはペティヤンの扱い、相当上手いです。
で、この2018のレルブ・タンドル・ドゥ・ピエは2年ほど店内で放置されていました。恐らくNoisyが忙しくてレビューできずに忘れ去られていたものかと。放置されていた間、静かに時を重ね、今まさに飲み頃となっています。
泡のレベルのそこまで強くはないですが、微発泡まではいかず、ちゃんとした泡が感じられます。しかしこちらは通常コルクの発泡性ワインということもあってか、泡は若干弱めです。形状的に王冠やシャンパンコルクのものより泡の抜けは早いと思われます。しかし泡の角も取れてきていると言いますか、泡がしなやかになっていて、その加減が「今」ちょうど良く、身体に染み込みます。この寒い時期でも美味しく飲めますね〜。
ドュ・ピエは100%古樽のバリックで熟成です。ふくよかさ、風味の豊かさはサンク・ピエより高いと感じます。現時点で香りも味わいも飽和しています。超おすすめです!ご検討くださいませ!
●
2022 Gueules Pressee Rouge V.d.F.
グール・プレッセ・ルージュ V.d.F.
【柔らかく、ジューシーで、「満たされ感」のあるカベフラに癒されちゃってください!】[ oisy wrote ]
 [ oisy wrote ]
[ oisy wrote ]いいですねー!
やわらかく、しっとりとしていて、丸みのあるカベフラです。未熟なカベフラにありがちな青さはなく、「熟した美味しいグリーン」です。
ロワールらしく酸はあるんだけれども、それがごわつくことなく、緻密でジューシー。そう、ジューシーなんです!
ジューシーというと軽いイメージがまとわりついてしまうので迂闊に使えない表現の一つなんですが、このワインを表現するために、あえて使っていきたいと思います。
ジューシーとは一般的にはみずみずしく、フレッシュという印象かと思いますが、オイジーが伝えたいジューシー感とは「果実のジュースがたっぷり」という意味合いです。
どういうことかと言いますと、ダメージを受けていない緻密な酸、まずこれがジューシー感を表現する上で重要なベースにあり、加えて適度に熟した、でも熟しすぎていない果実が必要です。
最後に柔らかいプレス、これによりエグ味や渋みなどの余計なものを抽出せずに「置いてきた」エキス的な液体。
これらが揃って初めてオイジー的「ジューシー」は表現されるわけです。つまりジューシーとは「バランス」と言い換えても良いかもしれません。
しかしなぜ「潰れた唇」なんでしょうか・・?気になります・・・どなたか名前の由来にピンときた方はぜひ教えてください。
よくある、酸の刺々しい荒いロワールのカベルネ・フランとは一線を画す味わいです!「ジューシー」なカベフラは「満たされ感」と「癒し」を連れてきてくれます!ご検討くださいませ。
●
2021 l’Appel du Large Rouge V.d.F.
ラペル・デュ・ラルジュ・ルージュ V.d.F.
【イチゴ、サクランボに綺麗な野のニュアンスが混じった淡いエキス系!酸の角は取れ、落ち着いて飲み頃になってきています!】[ oisy wrote ]
 [ oisy wrote ]
[ oisy wrote ]淡い赤果実エキスにスパイス&ハーブ。ただし、スパイスハーブはトッピングみたいなもので、スワリングとともに奥から赤果実のエキス由来の香りが出てきます・・・!
酸の角は取れ、落ち着きあり、飲み頃に差し掛かってきてると言っていいと思います・・・うまいです!
ピノ・ドニスのキャラクターはまだ計りかねているんですが、このラペル・デュ・ラルジュに関して言えば、ジュラのピノやサンソーのような淡い赤果実系に似ているなと思います。
酸にハリがあり、シャープさもありながらしっとりもしている・・・この辺は品種特性というよりセドリックの腕前かな・・・ イチゴ、サクランボなどの瑞々しい赤果実に、綺麗な野のニュアンスが混じります。もしかしたらこのニュアンスと色の淡さは全房発酵に由来するものかもしれません。全房発酵だと色素が梗に吸着してワインが淡くなるらしいです。
濃くはないですが、しっとりとした果実エキスの抽出感があり
「飲み心地が良い」
ワインに仕上がっています。
このスタイルでの並のワインは、香りの発露はあってもすぐに落ちていくのが常ですが、ラペル・デュ・ラルジュの香りはグラスに居座り続けて、グラスを口に運ぶ度に「こんにちは」してくれます。まあ飽きませんね!
キャッチーで、ライトなエキス系ですが、セドリックのワインは「しっかりうまい」のが共通しています。美味しいです!ご検討くださいませ。
●
2021 l’Albatros Rouge V.d.F.
ラルバトロス・ルージュ V.d.F.
【軽やかで酸がしっかりうまい、ライトエキス系!ブレンドの妙が冴えています!】[ oisy wrote ]
 [ oisy wrote ]
[ oisy wrote ]コー、ピノ・ドニス、ガメイ、カベルネ・フランのブレンドの赤ワインです。
ところでコーという品種をご存知でしょうか?別名をマルベックといい、こちらの方が聞き馴染みの多い方も多いかもしれません。
「黒ワイン」と呼ばれる濃い色素を持った品種です。片親がメルローと同じで、腹違いの兄弟らしいです。味わいとしてはしっかりとした酸味が出るのが特徴のようなので、メルローとは少し違った特徴を持つのかな・・
このワインにはしっかりとコーの存在感を感じます。メリハリのある酸があって心地よい軽さを演出しています。それでいてしっかりエキス的で、この酸と相まってハリのあるエキスを形成しています。実にピュア・・・
面白いのが香りで、ピノ・ドニスのペッパー感、ガメイのフルーティさ、カベルネ・フランのハーブ感のどれもが感じられます。これらがちょうど良い塩梅で、どれかが突出することなく、調和しています。
色合いを見てもコーの黒さは感じられず、淡い透明感のある液体で、コーのイメージよりも色合いのイメージの方が味わいに近い液体です。余韻にはコーの酸味がキュッと締めてくれるんだけれども、赤い果実の収束感があり、余韻は伸びていきます。
うまいですねー!軽やかに楽しめるんだけど、しっかりうまいです。ブレンドの妙も冴え渡っています。様々な品種が入り混じっていますが、全体的な印象としてはライトなエキス系のワインです。でも軽いだけではなく、「しっかりうまい」ところがポイントです。ご検討くださいませ!
レ・ゴーシェ
レ・ゴーシェ
フランス Les Gauchers ロワール
 [ oisy wrote]
[ oisy wrote]ロワールより自然派の新規生産者をご紹介します。その名も「ル・ゴーシェ」です。
コトー・デュ・ヴァンドモワというアペラシオンをご存知でしょうか・・?僅か125haの小さなアペラシオンです。ロワール川中流に位置し、ヴーヴレから少し離れた上の方に「離れ小島」のように存在しています。
小さいアペラシオンながら情熱を持った生産者がいる地域らしく、ル・ゴーシェもその一つです。
白は主にペットナット(瓶内一次発酵の自然派ペティヤン)で、ブラン・ド・ノワールのピノ・ドニスやシュナン・ブランから実に素晴らしいペットナットを造ります。価格も安いし、正直なところ、絶対下手なシャンパーニュより良いよな~・・・と思ってしまいました。またシュナン・ブランとペット・ナットの相性の良さ・・・についても言及していますので、ぜひコラムをご確認ください。
赤はコトー・デゥ・ヴァンドモワではメインの品種の「ピノ・ドニス」と「カベルネ・フラン」です。淡いピノ・ドニスはしっかりうまいエキス系、癒し系のやわらかカベルネ・フランには心を奪われてしまいました・・・
ナチュラルで、非常に安定した造り手です!よろしくお願いします!
■ エージェント情報
パリのランジュヴァンでナチュールに開眼したロワールの新星
・国際NGO から転身してナチュラルワイン造りに
レ・ゴーシェは、2017 年にロワールのコトー・デュ・ヴァンドモワに設立されたナチュラルワインのドメーヌです。造り手であるセドリック・フルーリーはロワールのヴァンドーム出身。1990 年代のパリでの学生時代に、ジャン・ピエール・ロビノのパリのレストラン「ランジュヴァン」で彼の叔父がシェフをしていたため頻繁に通ってナチュラルワイン好きになりました。その後、経済学を修めたセドリックは、国際NGO の仕事でマリやイエメン、アフガニスタンなどで15 年間働いていました。
しかし、この間にも、休暇やヴァカンスなどにはフランスに戻り、ロワールのクロ・テュ・ブッフのティエリー・ピュズラの下で収穫、ラ・グラップリのルノー・ゲティエの下で醸造などを経験しました。
2013 年に、本格的にナチュラルワイン造りに携わりたいと考え、NGO の仕事を辞めてフランスに戻り、アンボワーズの醸造学校に入学。ドメーヌ・ド・モントリューのエミール・エレディアの下で2 年間働いた後、2017 年に地元で2.6 ヘクタールの畑を購入して、ヴァンドーム近郊のトレ・ラ・ロシェットに自身のドメーヌ『Les Gauchers レ・ゴーシェ』を立ち上げて独立しました。レ・ゴーシュとはフランス語で『左利きの人達』という意味です。セドリックも彼の娘も左利きのため、このように命名したのだそうです。初ヴィンテージは2017年で、僅か1 樽の生産量からスタートしました。ビオディナミの手法を取り入れたセドリックのワインはとても活力があり、明るくさわやかで、同時に正確さを備えた味わいです。フランス各地のナチュラルワインショップやパリのナチュラルワインのレストランで販売されている他、デンマーク、オランダ、スイスなどにも輸出されています。
・ 畑と栽培について
ドメーヌの畑は、前オーナーが植樹をした約20 年前からビオロジックで栽培されていてエコサートの認証を受けています。畑はコトー・デュ・ヴァンドモワ域内の標高115 メートルの真南向きのコート(斜面)に位置しています。大きく以下の2 つの区画に分かれていて、土壌は表土がシレックス混じりの粘土。母岩が石灰(テュフォー)となっています。
・ Montrieux モントリュー: 栽培面積1ha(ピノ・ドニス0.5ha、ピノ・ノワール0.25ha、カベルネ・フラン0.25ha)。平均樹齢19 年。
・ La Pente des Coutis ラ・ポント・デ・クティ 栽培面積1.6ha(シュナン・ブラン)平均樹齢18 年。
ドメーヌではビオディナミの認証は受けていませんが、ビオディナミで使われる、スギナ、イラクサ、ノコギリ草などの調剤を効果的に使って栽培を行っています。畑は年に2回耕耘し、畝の間にはカバークロップを生やしています。また、収穫後には羊を放牧して自然な雑草駆除(羊が雑草を食む)を行っています。ブドウ木は剪定と芽かきを行った後は、除葉もグリーン・ハーヴェストも行いません。生物多様性の促進のために、知人の養蜂家とコラボレーションして区画の横に養蜂箱を設置するなどの試みをしています。
・ 醸造とワインについて
収穫は手摘みでその場で厳格に選果されます。その後、トレ・ラ・ロシェットにある洞窟を改装したドメーヌの醸造所に運ばれて醸造が行われます。ワインは野生酵母で自発的に発酵させ、醸造添加物やSO2 は一切加えずに醸造されます。温度管理を行いません。熟成後、無清澄、ノンフィルター、SO2 も無添加で、重力を利用して自然に瓶詰めされます。
セドリックは、今でもラ・グラップリのルノー・ゲティエと、元ドメーヌ・ド・モントリューのエミール・エレディアと非常に仲が良く、頻繁に会ってワイン造りについての考えや哲学について意見交換をしています。ちなみに現在、エミール・エレディアはドメーヌ・ド・モントリューを離れ、ラングドックでドメーヌを経営。夫のクリスチャン・ショサールを亡くしたドメーヌ・ル・ブリゾーのナタリー・ゴビシェールと再婚し、ナタリーが営むネゴス、ナナ・ヴァンにブドウを提供しています。
エチケットデザインはセドリックの友人のアーティスト、Morgane Bader モルガン・バデがデザインしたものです。
●
2020 l'Herbe Tendre(Cinq Pieds) V.d.F.
レルブ・タンドル・ブラン(サンク・ピエ) V.d.F.
【フルーツを超えた蜜のような香りと味わい!熟成感、ブリオッシュも備え、ムニエ主体のシャンパーニュのような味スジ・・!?既にこなれてうまいです・・・!】[ oisy wrote ]
 [ oisy wrote ]
[ oisy wrote ]うま〜い!!!
ちょっとしたシャンパーニュ感もありますね。泡の細かさやボリュームはそこまでではないですが、香り!熟成感を伴いブリオッシュ感もあるかな・・・フルーツを超えた蜜のような香りと味わい。
シュナン・ブランの果実の充実感が高い!ムニエ主体のシャンパーニュにキャラクターは似ています。
ミネラリティはやはりシャンパーニュのそれとは違います。少し丸みを帯びていて、しかしよく満たされています。充実していますね〜。これはこれで良いキャラクターです。シャンパーニュほどの鋭さはいらないけど、冷涼で充実感のある泡が飲みたい・・・というニーズに十分答えてくれるのはないでしょうか。そしてシャンパーニュにはなかなか無いピュア感を感じられます。
ロワールのシュナンらしく、酸もハリがあってボリュームがありますが、既にこなれてきて、うまいです。最近下手なシャンパーニュを凌駕するペットナットが散見されますが、これもその一角かと思います。個人的にペットナットは要注目のカテゴリーだと思っています。
商品名には(サンク・ピエ)と記載がありますが、これは5本の足という意味で、ラベルデザインにもなっています。タンクと樽熟成のブレンドということのようです。
同じレルブ・タンドルでもドゥ・ピエ(二本足)は古樽のバリック100%。2018はドゥ・ピエです。こちらとはキャラクターは結構違い、飲み比べも楽しいはず・・!ドゥ・ピエの方がふくよかで、サンク・ピエの方がハリやキレがありますね。2020で2年ほど若いというのもありますが・・・
こちらは王冠のペット・ナットなので、抜栓時は念の為シンクの上で、斜めで栓抜きし、斜めの状態をキープしたまま一杯注いでください。一杯注いだら立てて大丈夫です。
熟成感があって、酸が柔らかくなってきて、ピュアで密度がある・・・泡としておよそこれで満足できない要素はないのではないのでしょうか・・・?レ・ゴーシェの泡は美味いですよ!オススメです!ご検討くださいませ!
ドメーヌ・クロード・デュガ
クロード・デュガ
フランス Domaine Claude Dugat ブルゴーニュ
● 「憑き物が完全に落ちた!」
とテイスティングでまず感じた2022年のドメーヌ・クロード・デュガをご紹介させていただきます。
「新樽100%と濃密な葡萄」と言うような呪縛に捕われていた?・・何とか脱出しようともがいていた・・noisy はずっとそう感じていました。
しかしながら2022年もので、完全に脱出成功・・純粋で純度が高く、とんでもないほどにエキスが美味しい・・結果として、テロワールを美しく表現しえるワインになった・・と言えます。
これは是非飲んでいただきたい、半端無いブルゴーニュワインだと思います。A.C.ブル、めっちゃ旨いです!・・ラ・マリーも半端無く美味しかったですが、割り当てが無かった・・残念!・・その代わり、村名ジュヴレも海外メディアはラ・マリー並みと評価しています(noisy はそうは思いませんが)ので、
「2022年以降のデュガさんは、美しいエキスが描くディテールが美しく浮き上がって来る見事なジュヴレワイン!」
と思って間違い無いでしょう。ぜひ飲んでみてください。お薦めします!
-----
2021年もののクロード・デュガです。余りに少なくて・・村名ジュヴレしかテイスティングできませんでした。
ですが・・このところのデュガさんのスタイルを継承し、膨らませていることを確認しました。村名ジュヴレ・・今飲んでも非常に美味しいです・・幾分、仕上がり切ってはいないんですが、飲み進めるにしたがってどんどん良くなって来ます。そして、気付いたらいつの間にか無くなっている・・そんな感じの仕上がり具合です。
もはや以前の黒くて濃くて強い、新樽バリバリの味わいでは無く、美しい伸びやかなエキスと酸からの・・美しいディテール・・エレガント系です。ぜひご検討くださいませ。
-----
2020年のクロード・デュガです。順調に値上がっていますが、周りの生産者のワインの余りの高騰に、余り高くなったようには見えません・・(^^;;
この何年かのクロード・デュガのワインを飲めば、1990~2000年代の黒くて濃い、若い時分は果実が主体のワインだったものが、エキス系の美しさ、エレガンス主体の優雅に香るワインに大きく変わっていることに気付きます。
そして徐々に自然派ワインのようなナチュラルなニュアンスがし始めているのにも気付かれるでしょう。ですので現在は、エレガント系、ちょっと自然派系のピュアなエキス系の見事な味わいです。
2019年ものには、それまでやや迷っていた感が有ったものが消えうせ、高温発酵系の不作為な・・いや、ワインが自由になりたいようになることを許容したかのような、伸び伸びとした作風へと変化し、2020年ものはその延長上・・さらに高いポテンシャルのワインを目指しているのが判ります。
上級キュヴェはいつものように飲めなかったんですが、いや・・A.C.ブルで充分に素晴らしいです。A.C.ブルと言うよりも優れた村名ジュヴレと言いたくなる見事な出来栄えで、例えば、
「赤い果実中心の誰が飲んでも納得するような素晴らしい出来栄え!」
であったフーリエのA.C.ブルとは、余りに見事に異なります。フーリエはおそらく、2020年もののA.C.ブルの葡萄を得て果実主体のワインに持って行ったはずですが、ベルトランはしっかりエキス系の村名ジュヴレ的な方向へ誘導したのでしょう。これは今でも滅茶苦茶旨いです。
村名ジュヴレは柔らかな酸を持ち丸いパレットを美しく描きますが、まだ完全にはこなれておらず、少しの生育が必要です。
この2つのことからも2020年と言うヴィンテージが、
「いつもと異なる」
ことが判るでしょう。2019年以前は、明らかに村名ジュヴレが早く仕上がっていて、
「A.C.ブルは村名ジュヴレのセカンド」
と言った印象を与えていました。
しかし2020年ものは明らかにA.C.ブルの仕上がりがより早く、しかも高いポテンシャルを持ち発揮し始めています。村名ジュヴレは仕上がりはまだで、少し時間が必要・・と言うことは、上級キュヴェはこれから時間を得て仕上がって行くものと思われます(想像です)。
2020年もののクロード・デュガのワインは、下のクラスから順に飲まれることをお勧めします。ですが、
「A.C.ブルの余りの美しさと出来の良さを知ってしまうとすぐに上級キュヴェに手を出したくなる!」
そんな気持ちになってしまう可能性がありますので、そこはグッと堪えて・・少なくとも来春までは手を出さないよう・・お願いします。
ドメーヌ・クロード・デュガも世代交代時期です。今は息子さんのベルトランが頑張っているのでしょう。伸びて来ているのが判ります。海外メディアの2020年A.C.ブルの評価は低すぎると思ってください。お勧めします。
■ドメーヌによる2020年ヴィンテージの感想
2020年は冬から温暖で湿度も高く、春も暑くて日照量が多かった。葡萄の成長はとても早く、冬に降った雨による地中の水分量が適度にあり、畑のコンディションは非常に良かった。開花期もあっという間に過ぎ、一部で花ぶるいやミルランダージュはあったものの、全体的に見れば葡萄の状態は素晴らしい。夏はとても暑く、時々雨は降るものの空気は乾燥していて葡萄の健康状態も良好。収穫は2003年と同じ8月29日から始めるほど早熟だった。しかし酷暑の影響はやはり大きく、葡萄のクオリティは素晴らしいが葡萄の粒も小さいので収穫量はとても少ない。
-----
2019年のクロード・デュガをご紹介させていただきます。2000年以降、道を迷いに迷って迷走を続けているかのようなクロ・ド・デュガですが、出口が見えた2018年に続き、2019年は、
「エキス系のピノ・ノワール本来のしなやかな味わい」
を目指し、邁進している姿を見ることが出来、世代交代と共に、一時代を気付き上げたクロード・デュガの大変革が、今の世界の状況を含んだものだと感じさせてくれました。
この、新型コロナウイルスが世界に蔓延している状況も、温暖化によると思われる異常気象も、薬漬けだった世代からの教訓を受け、ナチュラルで滑らかでエレガントなピノ・ノワールへの回帰を感じさせてくれます。
2019年もののクロード・デュガは、
「もう迷わない!」
と言っているように感じます。事実、A.C.ブルもA.C.ジュヴレもエキス系で、非常に良い出来です。
特にすぐに飲まれるのであれば、2019年ジュヴレ=シャンベルタンをお薦めします。A.C.ブルは3年経ってから。勿論、上級キュヴェは5年ほどでしょうか。是非ご検討くださいませ。
-----
あれだけ「濃密なブルゴーニュワイン」の代名詞的存在だったクロード・デュガですが・・とんでもない!・・エレガント系への華麗な転身は間違い無い・・と感じる、しかも相当に出来が良いと言える2018年ものをご紹介させていただきます。
この数年、
「どうしちゃったの?・・大丈夫?」
と声を掛けたくなってしまうほど、迷走を続けていたように思えるクロード・デュガですが、次世代へのバトンタッチで・・やはりナチュラルな方向へのシフトが待った無しだと言う気持ちの表れでは無いかな?・・と感じます。
親や祖父母、親類、友人たちが病気で倒れる、農薬でふらふらになるのを見て来た若い世代にとっては、全く他人事では無いと思います。
そして2018年もののリリースで、ドメーヌ・クロード・デュガが目指している方向性が確認出来る程に成熟してきたのをまざまざと見せつけられました。滅茶美味しいA.C.ブル、そしてその延長上で滅茶複雑性豊かな村名ジュヴレをテイスティングさせていただきました。是非ご検討ください。
-----
クロード・デュガです。こちらは正規の「フィネスさん」ものです。ようやくチェック・・テイスティング終了しました。・・いや~・・村名ジュヴレの2017年がかなり旨いです!
濃厚な黒系ピノとして、長く愛されてきたクロード・デュガですが、昨今の「綺麗系」「エキス系」への転身は、目に見えて成就してきました。
明らかに美しいエキスがほとばしるドライな液体の村名ジュヴレ=シャンベルタンを基本として、村名のセカンドワイン的存在のA.C.ブルゴーニュ、そして繊細で緻密な1級、精妙なグラン・クリュと言うラインナップになっています。
流石にテイスティングで上級キュヴェまでは手が出せない状況ですが、「綺麗系」「エキス系」ブルゴーニュワインとして、年々成長しているのが手に取るように判ります。
2017年はまず村名が滅茶美味しいので、早めに手をつけるならこれです。A.C.ブルゴーニュは3~5年は寝かせてください。要素の複雑性、美しさから言えば村名には及ばないとしても、大きさはジュヴレに勝るかもしれません。
1級以上は流石の評価が出ています。ご検討くださいませ。
 2017年は2016年同様、霜のリスクがあったが結果的には大きな被害はなく、夏は暑くて雨も降って欲しいときに降ってくれたので、近年では安定したヴィンテージと言える。収穫量も十分でチャーミングな果実味と適度な酸味のある飲みやすいヴィンテージ。凝縮感はあるが重い印象はなく、とてもエレガントなのでボトル1本飲めてしまえるような味わいになっている。2016年よりも早くから楽しむことができるが10~15年くらいの熟成もできるだろう。
2017年は2016年同様、霜のリスクがあったが結果的には大きな被害はなく、夏は暑くて雨も降って欲しいときに降ってくれたので、近年では安定したヴィンテージと言える。収穫量も十分でチャーミングな果実味と適度な酸味のある飲みやすいヴィンテージ。凝縮感はあるが重い印象はなく、とてもエレガントなのでボトル1本飲めてしまえるような味わいになっている。2016年よりも早くから楽しむことができるが10~15年くらいの熟成もできるだろう。
13世紀に建てられた教会をそのままカーヴとしている当家は現在約6haの葡萄畑を所有しています。物腰静かで高貴な印象の現当主クロードデュガ氏は、良いワインができる条件は葡萄の品質の良さという考えに基づき、畑の手入れを入念に行い、化学肥料は使わずに健康な葡萄を育てています。
また、庭でJonquille(ジョンキーユ:黄水仙の花という意味)という名前の牝馬を飼っていて、小さな区画や古木の区画を耕させています。特に古木の畑は葡萄の根が地中に広く張り巡らされていてトラクターで根を傷つけたり、トラクターの重みで土を固くしてしまったりするのでこの牝馬が活躍しています。収穫された葡萄は温度調節の容易な、酒石がびっしり付着しているコンクリートタンクに運ばれ、アルコール発酵が行われます。新樽がズラリと並んだ地上のカーヴでは最新のヴィンテージのワインのマロラクティック醗酵が行われ、地下水が壁から染み出ている、砂利が敷き詰められた地下のカーヴではその前年のワインが熟成されています。瓶詰めの際にはフィルターもコラージュも行いませんが、ワインは非常に透明感があります。
とテイスティングでまず感じた2022年のドメーヌ・クロード・デュガをご紹介させていただきます。
「新樽100%と濃密な葡萄」と言うような呪縛に捕われていた?・・何とか脱出しようともがいていた・・noisy はずっとそう感じていました。
しかしながら2022年もので、完全に脱出成功・・純粋で純度が高く、とんでもないほどにエキスが美味しい・・結果として、テロワールを美しく表現しえるワインになった・・と言えます。
これは是非飲んでいただきたい、半端無いブルゴーニュワインだと思います。A.C.ブル、めっちゃ旨いです!・・ラ・マリーも半端無く美味しかったですが、割り当てが無かった・・残念!・・その代わり、村名ジュヴレも海外メディアはラ・マリー並みと評価しています(noisy はそうは思いませんが)ので、
「2022年以降のデュガさんは、美しいエキスが描くディテールが美しく浮き上がって来る見事なジュヴレワイン!」
と思って間違い無いでしょう。ぜひ飲んでみてください。お薦めします!
-----
2021年もののクロード・デュガです。余りに少なくて・・村名ジュヴレしかテイスティングできませんでした。
ですが・・このところのデュガさんのスタイルを継承し、膨らませていることを確認しました。村名ジュヴレ・・今飲んでも非常に美味しいです・・幾分、仕上がり切ってはいないんですが、飲み進めるにしたがってどんどん良くなって来ます。そして、気付いたらいつの間にか無くなっている・・そんな感じの仕上がり具合です。
もはや以前の黒くて濃くて強い、新樽バリバリの味わいでは無く、美しい伸びやかなエキスと酸からの・・美しいディテール・・エレガント系です。ぜひご検討くださいませ。
-----
2020年のクロード・デュガです。順調に値上がっていますが、周りの生産者のワインの余りの高騰に、余り高くなったようには見えません・・(^^;;
この何年かのクロード・デュガのワインを飲めば、1990~2000年代の黒くて濃い、若い時分は果実が主体のワインだったものが、エキス系の美しさ、エレガンス主体の優雅に香るワインに大きく変わっていることに気付きます。
そして徐々に自然派ワインのようなナチュラルなニュアンスがし始めているのにも気付かれるでしょう。ですので現在は、エレガント系、ちょっと自然派系のピュアなエキス系の見事な味わいです。
2019年ものには、それまでやや迷っていた感が有ったものが消えうせ、高温発酵系の不作為な・・いや、ワインが自由になりたいようになることを許容したかのような、伸び伸びとした作風へと変化し、2020年ものはその延長上・・さらに高いポテンシャルのワインを目指しているのが判ります。
上級キュヴェはいつものように飲めなかったんですが、いや・・A.C.ブルで充分に素晴らしいです。A.C.ブルと言うよりも優れた村名ジュヴレと言いたくなる見事な出来栄えで、例えば、
「赤い果実中心の誰が飲んでも納得するような素晴らしい出来栄え!」
であったフーリエのA.C.ブルとは、余りに見事に異なります。フーリエはおそらく、2020年もののA.C.ブルの葡萄を得て果実主体のワインに持って行ったはずですが、ベルトランはしっかりエキス系の村名ジュヴレ的な方向へ誘導したのでしょう。これは今でも滅茶苦茶旨いです。
村名ジュヴレは柔らかな酸を持ち丸いパレットを美しく描きますが、まだ完全にはこなれておらず、少しの生育が必要です。
この2つのことからも2020年と言うヴィンテージが、
「いつもと異なる」
ことが判るでしょう。2019年以前は、明らかに村名ジュヴレが早く仕上がっていて、
「A.C.ブルは村名ジュヴレのセカンド」
と言った印象を与えていました。
しかし2020年ものは明らかにA.C.ブルの仕上がりがより早く、しかも高いポテンシャルを持ち発揮し始めています。村名ジュヴレは仕上がりはまだで、少し時間が必要・・と言うことは、上級キュヴェはこれから時間を得て仕上がって行くものと思われます(想像です)。
2020年もののクロード・デュガのワインは、下のクラスから順に飲まれることをお勧めします。ですが、
「A.C.ブルの余りの美しさと出来の良さを知ってしまうとすぐに上級キュヴェに手を出したくなる!」
そんな気持ちになってしまう可能性がありますので、そこはグッと堪えて・・少なくとも来春までは手を出さないよう・・お願いします。
ドメーヌ・クロード・デュガも世代交代時期です。今は息子さんのベルトランが頑張っているのでしょう。伸びて来ているのが判ります。海外メディアの2020年A.C.ブルの評価は低すぎると思ってください。お勧めします。
■ドメーヌによる2020年ヴィンテージの感想
2020年は冬から温暖で湿度も高く、春も暑くて日照量が多かった。葡萄の成長はとても早く、冬に降った雨による地中の水分量が適度にあり、畑のコンディションは非常に良かった。開花期もあっという間に過ぎ、一部で花ぶるいやミルランダージュはあったものの、全体的に見れば葡萄の状態は素晴らしい。夏はとても暑く、時々雨は降るものの空気は乾燥していて葡萄の健康状態も良好。収穫は2003年と同じ8月29日から始めるほど早熟だった。しかし酷暑の影響はやはり大きく、葡萄のクオリティは素晴らしいが葡萄の粒も小さいので収穫量はとても少ない。
-----
2019年のクロード・デュガをご紹介させていただきます。2000年以降、道を迷いに迷って迷走を続けているかのようなクロ・ド・デュガですが、出口が見えた2018年に続き、2019年は、
「エキス系のピノ・ノワール本来のしなやかな味わい」
を目指し、邁進している姿を見ることが出来、世代交代と共に、一時代を気付き上げたクロード・デュガの大変革が、今の世界の状況を含んだものだと感じさせてくれました。
この、新型コロナウイルスが世界に蔓延している状況も、温暖化によると思われる異常気象も、薬漬けだった世代からの教訓を受け、ナチュラルで滑らかでエレガントなピノ・ノワールへの回帰を感じさせてくれます。
2019年もののクロード・デュガは、
「もう迷わない!」
と言っているように感じます。事実、A.C.ブルもA.C.ジュヴレもエキス系で、非常に良い出来です。
特にすぐに飲まれるのであれば、2019年ジュヴレ=シャンベルタンをお薦めします。A.C.ブルは3年経ってから。勿論、上級キュヴェは5年ほどでしょうか。是非ご検討くださいませ。
-----
あれだけ「濃密なブルゴーニュワイン」の代名詞的存在だったクロード・デュガですが・・とんでもない!・・エレガント系への華麗な転身は間違い無い・・と感じる、しかも相当に出来が良いと言える2018年ものをご紹介させていただきます。
この数年、
「どうしちゃったの?・・大丈夫?」
と声を掛けたくなってしまうほど、迷走を続けていたように思えるクロード・デュガですが、次世代へのバトンタッチで・・やはりナチュラルな方向へのシフトが待った無しだと言う気持ちの表れでは無いかな?・・と感じます。
親や祖父母、親類、友人たちが病気で倒れる、農薬でふらふらになるのを見て来た若い世代にとっては、全く他人事では無いと思います。
そして2018年もののリリースで、ドメーヌ・クロード・デュガが目指している方向性が確認出来る程に成熟してきたのをまざまざと見せつけられました。滅茶美味しいA.C.ブル、そしてその延長上で滅茶複雑性豊かな村名ジュヴレをテイスティングさせていただきました。是非ご検討ください。
-----
クロード・デュガです。こちらは正規の「フィネスさん」ものです。ようやくチェック・・テイスティング終了しました。・・いや~・・村名ジュヴレの2017年がかなり旨いです!
濃厚な黒系ピノとして、長く愛されてきたクロード・デュガですが、昨今の「綺麗系」「エキス系」への転身は、目に見えて成就してきました。
明らかに美しいエキスがほとばしるドライな液体の村名ジュヴレ=シャンベルタンを基本として、村名のセカンドワイン的存在のA.C.ブルゴーニュ、そして繊細で緻密な1級、精妙なグラン・クリュと言うラインナップになっています。
流石にテイスティングで上級キュヴェまでは手が出せない状況ですが、「綺麗系」「エキス系」ブルゴーニュワインとして、年々成長しているのが手に取るように判ります。
2017年はまず村名が滅茶美味しいので、早めに手をつけるならこれです。A.C.ブルゴーニュは3~5年は寝かせてください。要素の複雑性、美しさから言えば村名には及ばないとしても、大きさはジュヴレに勝るかもしれません。
1級以上は流石の評価が出ています。ご検討くださいませ。
 2017年は2016年同様、霜のリスクがあったが結果的には大きな被害はなく、夏は暑くて雨も降って欲しいときに降ってくれたので、近年では安定したヴィンテージと言える。収穫量も十分でチャーミングな果実味と適度な酸味のある飲みやすいヴィンテージ。凝縮感はあるが重い印象はなく、とてもエレガントなのでボトル1本飲めてしまえるような味わいになっている。2016年よりも早くから楽しむことができるが10~15年くらいの熟成もできるだろう。
2017年は2016年同様、霜のリスクがあったが結果的には大きな被害はなく、夏は暑くて雨も降って欲しいときに降ってくれたので、近年では安定したヴィンテージと言える。収穫量も十分でチャーミングな果実味と適度な酸味のある飲みやすいヴィンテージ。凝縮感はあるが重い印象はなく、とてもエレガントなのでボトル1本飲めてしまえるような味わいになっている。2016年よりも早くから楽しむことができるが10~15年くらいの熟成もできるだろう。13世紀に建てられた教会をそのままカーヴとしている当家は現在約6haの葡萄畑を所有しています。物腰静かで高貴な印象の現当主クロードデュガ氏は、良いワインができる条件は葡萄の品質の良さという考えに基づき、畑の手入れを入念に行い、化学肥料は使わずに健康な葡萄を育てています。
また、庭でJonquille(ジョンキーユ:黄水仙の花という意味)という名前の牝馬を飼っていて、小さな区画や古木の区画を耕させています。特に古木の畑は葡萄の根が地中に広く張り巡らされていてトラクターで根を傷つけたり、トラクターの重みで土を固くしてしまったりするのでこの牝馬が活躍しています。収穫された葡萄は温度調節の容易な、酒石がびっしり付着しているコンクリートタンクに運ばれ、アルコール発酵が行われます。新樽がズラリと並んだ地上のカーヴでは最新のヴィンテージのワインのマロラクティック醗酵が行われ、地下水が壁から染み出ている、砂利が敷き詰められた地下のカーヴではその前年のワインが熟成されています。瓶詰めの際にはフィルターもコラージュも行いませんが、ワインは非常に透明感があります。
●
2022 Gevrey-Chambertin
ジュヴレ=シャンベルタン
【純度が爆上がりした2022年のクロード・デュガ!・・まさに憑き物落ちをしっかり感じる、美しくも複雑なジュヴレが持つ表情を見事に映し出しています!】
 長年に渡って同じ生産者さんのワインをテイスティングし続けていると、その変遷が手に取るように理解できる・・ような気がします。
長年に渡って同じ生産者さんのワインをテイスティングし続けていると、その変遷が手に取るように理解できる・・ような気がします。1990年台のクロード・デュガさんは、もう・・物凄い勢いで市場を席捲していまして、noisy 的には、
「デュガと言ったらベルナール・デュガ」
と言う気持ちだったので、
「クロード・デュガ?・・知らんなぁ・・」
と言うのが知った時の印象で、間もなく飲んでみると・・
「こりゃぁ・・ウケるわ!」
と感じたのを覚えています。
デュガ=ピィとドメーヌ名を変更する前のベルナール・デュガは、ある程度をルロワに渡して残りをドメーヌで出していました。余り知られていないドメーヌだったので、noisy が「ベルナール・デュガ」と言っても・・余り反応は有りませんでした。今や大ドメーヌですが。
やはりPKさんが「新樽!・・とにかく新樽だ!」とうるさく言い始めた時代だったので、猫も杓子も熟度を高めた葡萄を収穫して新樽に詰める・・と言う作風が席巻したんですね。濃くてやや甘い、果実の強いワインで、デュガさんのワインもどんどん黒くなって行ったように記憶しています。
ですがそんな時代も自然派の広まりもあってか2000年を境に去り、以前の美しいエキスのピノ・ノワールの時代へ、
「葡萄を適度に完熟させる技術を持ったまま」
引き継がれて行ったのだろうと思っています。
 そんな新しい時代になり、彼のグリオットやシャルムと言ったワインはそのままウケ続けましたが、それ以外のアイテムはどうでしょう・・今一つだったんじゃないかと思うんですね。
そんな新しい時代になり、彼のグリオットやシャルムと言ったワインはそのままウケ続けましたが、それ以外のアイテムはどうでしょう・・今一つだったんじゃないかと思うんですね。で、この10年はずいぶんと変わったと感じていたんですが、2021年もののこのジュヴレ村名は美味しかったです。おそらく、
「一皮剝けた」
みたいな言い方をしていたと思います。
しかし!
2022年ものは・・「憑き物が完全に落ちた!」と申し上げておきましょう。
純粋で香しいアロマは膨らみとスピードを持ち、ジュヴレならではの・・
「様々な表情が交錯して現れる複雑なアロマ!」
も、物の見事に感じられます。
エキス系の味わいで果実の甘みだけに頼らず、ドライながらも美しいディテールを描き出す、ポテンシャルの高いジュヴレ村名です。
可能なら1年ほど瓶熟させますとさらに良くなることでしょう。
あ、そうそう・・販売は・・割り当てが無かったので出来ませんが、「ラ・マリー」と言うアイテムはテイスティングだけ、させていただいたんですね。これがま~・・A.C.ブル同様に今飲んでもとんでもなく美味しくてビックリしました!
 色彩は村名と比較しますと若干濃い目で暗めですが、とんでもなく美しく・・
色彩は村名と比較しますと若干濃い目で暗めですが、とんでもなく美しく・・「美しい系のデュガさんの新作ラ・マリー2022、とんでもなくお薦め!」
と言ってご案内出来れば良かったんですが・・残念では有ります。
面白いのは・・メディアはこの2022ラ・マリーに対し、ヴィノスが村名ジュヴレと同点の評価、アドヴォケイトは上値だけを1ポイント上げ・・と言う評価に終わっていることです。まぁ・・面白いかどうかはお客様によるかとは思いますが、
「エレガントで微細なところで高いバランスを持っているワインへの評価が著しく低い」
のが、今の海外メディアの欠点かなと思ってもいます。
その昔はブルゴーニュワイン全体の評価が余り良く無かったものが、日本から飛び火して東南アジアでバカウケし、さらには転売系が買い占め・・ようやく自分たちの間違いに気付いたものの、黙ったままポイントを上げて行った・・と残念ながら noisy にはそのようにしか見えませんが・・。
ようやっと円安に歯止めが掛かりそうな時代にはなってきたように思いますが、まだ何かの出来事で元の木阿弥になってしまわないかと懸念しています。ぜひともこの、
「憑き物が落ちた純度の高いデュガさんの村名!」
ご検討いただけましたら幸いです。どうぞよろしくお願いします。
以下は以前のレヴューです。
-----
【2021年もののクロード・デュガは、自身のワインの姿をきっちり定めたと言えるでしょう!エレガント系+エキス系の非常に好ましい味わいです!】
 2021年もののジュヴレ=シャンベルタンをずいぶんとテイスティングさせていただいていますが、何でしょう・・すべからく素晴らしい出来なんですよね。どうしても「ウィークな弱い出来」とか、「ネガティヴさ」みたいなイメージが付きまとうと思うんですが・・まったくそんなことが無いんです。
2021年もののジュヴレ=シャンベルタンをずいぶんとテイスティングさせていただいていますが、何でしょう・・すべからく素晴らしい出来なんですよね。どうしても「ウィークな弱い出来」とか、「ネガティヴさ」みたいなイメージが付きまとうと思うんですが・・まったくそんなことが無いんです。半面、例えばジュヴレ=シャンベルタンではあるけれどブロションにある畑・・とかと言うことになると、比較して幾分の弱さ、言わばエレガントさがより際立っている感じには思えますが・・。
で、ここだけの話し・・エマニュエル・ルジェさんちのネゴスの「2021年 ジュヴレ=シャンベルタン」を飲んじゃったんですね~・・いや、それだけじゃなくて、「2020年もののジュヴレ=シャンベルタン」も、「2021年 ラドワ・ブラン」も、「2021年 ラドワ1級レ・グレション・ブラン」も・・(^^;
ルジェさんのジュヴレ=シャンベルタンは、2021年ものは・・ま~~~・・
「しっかりとジュヴレ=シャンベルタンしてる!」
し、
「しっかりとエマニュエル・ルジェしてる!」
んですよ。
そしてですね・・2020年もののジュヴレ=シャンベルタンとボトルを横並びにして、グラスも2個用意して・・交互に比較試飲したんですね~・・・。
そうしますと・・2020年ものの濃いこと!・・未だにコナレてはおらず、濃密だがめちゃドライな味筋で、そのルジェさんらしさも、ジュヴレ=シャンベルタンらしさも・・しっかりとマスキングしているんですね・・。
一方ですよ・・2021年ったら前述のように、エマニュエル・ルジェ的な官能を揺さぶるエロい香りで・・誘われているような感じが素晴らしくて、
「良い年と言うことで選ぶのなら間違い無く2020年だが、劣るとは判っていながら・・きっと飲みたいのは2021年を選択するなぁ・・」
と言うことなんですね。
あ・・じゃぁ2021年ものの写真を。
 どうでしょう?・・なんか、ゾクゾクっとして来ないですか?・・美しいですよね・・照りがありますよね・・グラデュエーションが凄いですよね~・・。めっちゃ美味しかったです!・・すみません・・。
どうでしょう?・・なんか、ゾクゾクっとして来ないですか?・・美しいですよね・・照りがありますよね・・グラデュエーションが凄いですよね~・・。めっちゃ美味しかったです!・・すみません・・。で、この2021年もののデュガさんのジュヴレ=シャンベルタン村名なんですが・・まだルジェさんのジュヴレ=シャンベルタン村名ほどは仕上がって無いんですね・・。
ただし、芯の強さ、しっかり感はデュガさんのジュヴレに分が有ります。単に時間の問題だけです。
非常にエキスなワインを感じさせる見事な出来です。しかしまだ仕上がってない・・。
でも、飲み始めて10分もして来ますと・・断然、良くなって来るんですね。やや硬めだったニュアンスに柔らかさが見え始めますと、その堅い殻を破るかのように優しくふわっとしたやや官能的なアロマと細やかな味わいの襞を感じられるようになって来ます。
まぁ・・ここ最近、3年ほどのデュガさんのワインを飲んでいれば、もう・・昔のような・・
「黒くて濃い・・ボルドー右岸と間違えるような味わい」
ではあり得ないことは充分に承知している訳です。
おそらく新樽の使い方の違いと、葡萄の凝縮度の違いでしょうか・・。もちろん、色合いを比較していただけましたら判るかと思いますが、
「葡萄自体が充実しているのはデュガさんの方」
です。しかし仕上がるタイミングは、しっかりしている分、若干遅くなるんでしょう・・そう感じます。
 まぁ・・昨今のエマニュエル・ルジェさんのワインはもはや「化け物」と言って良いレベルですから、比較して条件が悪いはずのネゴスとしてのジュヴレでも、
まぁ・・昨今のエマニュエル・ルジェさんのワインはもはや「化け物」と言って良いレベルですから、比較して条件が悪いはずのネゴスとしてのジュヴレでも、「エマニュエル・ルジェも、ジュヴレ=シャンベルタンも、どちらも滅茶美味しく訴えかけてくる!」
と言えます。
じゃぁ・・ポイントを付けるとしたらどうか?・・としますとですね・・今飲んでのポイントは確実にルジェさんが上です。ポテンシャルはどうか?・・と言いますとですね・・これは、ほぼ同じか・・わずかにデュガさんに軍配が上がるか・・と思います。
質感の素晴らしさ、精緻さはデュガさん、色っぽい目線はルジェさん・・ですね。
で、デュガさんのジュヴレ=シャンベルタン村名ですが、今から飲み始めて大丈夫です。飲み進めていく内にどんどん美味しくなって行きます。
「気づいたら・・あれ?・・もう無い・・」
と言うようなシュチュエーションに追い込まれるんじゃないかと思うんですね。
2021年のデュガさんのワイン、滅茶少ないので・・この村名しか飲めませんでした。フィネスさんものはさらに少ないでしょうから・・まぁ、やや高いですが・・
あ、これはですね・・いくつかあるインポーターさんの間での「闘い」でも有るはずです。noisy が知っているだけでも日本では3社有ります。
フィネスさんは・・そんな「闘い」には無縁で、ただひたすら・・ドメーヌとのお付き合いを大事に長くお取引を継続し、良いコンディションでワイン屋さんに渡す努力を惜しみません。
ですが多くのインポーターさんの間では、価格で何とか乗り切り、可能なら独占契約に持ち込みたいと・・考える訳ですね。なので、むしろフィネスさんの方が普通の値付けであって、他社さんは何かしらの思惑が入った値付けになっていると思います。
コンディションが良く美味しいワインの方が・・良いですよね。どうぞご検討よろしくお願いいたします。お勧めします。
以下は以前のレヴューです。
-----
【「・・・これがクロード・デュガ・・か!?」と・・是非驚いてください!・・でも飲むのは少し先です!】
 デカンター誌はシャルル・カーティス MW が93ポイント、飲み頃予想2023~2040 と評価していまして・・流石だな・・と思ってしまいましたね。どこかの誰かと違って 2022~2028 なんて有り得ない評価にはしないし、飲み始めを2023年としています。
デカンター誌はシャルル・カーティス MW が93ポイント、飲み頃予想2023~2040 と評価していまして・・流石だな・・と思ってしまいましたね。どこかの誰かと違って 2022~2028 なんて有り得ない評価にはしないし、飲み始めを2023年としています。noisy も・・ほぼそう判断します。来春までは生育しなければいけません。もっとも、流石だな・・と言うのは noisy の意見と同じだから・・では無く、評価者の意思が伝わってくるポイント付けをされていらしたからですね。全く伝わってこない方もいらっしゃいますから・・はい。
今、ほぼ仕上がった(仕上がりつつ・・ですが)2020年A.C.ブルの美しく集中した味わいから見ると、その深い赤を何層にも積層させたかのような美しい色彩では有っても、
「まだ抜けて来ていない色彩」
でもあるように見えます。
実際飲んでみると、A.C.ブルの冷ややかで美しい酸バランスとはやや異なり、柔らかで幾分の温かさを含んだ味わいが、腰高感を思わせるんですね。
「・・あぁ・・まだ仕上がって無いなぁ・・」
と思わざるを得ない訳です。
しかしながら1枚目の写真の美しい色彩には、
「もう少し・・待ってね・・」
と言ってるかのようなニュアンスが有りますが、今までこのような美しさをデュガさんのワインが見せたことが有るでしょうか。
 残念ながらこのコラムでも2013年ものの写真までしか遡れませんが、
残念ながらこのコラムでも2013年ものの写真までしか遡れませんが、「・・この2013年からの一連の8枚の写真って同じ人の同じアイテムのワイン・・なんだね・・」
と、認識すべきなんですね。
余りに違うことに驚かれるかもしれませんが、・・そうなんですよ・・本当に全然違ってきているんですね。
2020年もの村名ジュヴレ、非常に集中しています。ベルヴェッティな触感・・その表面は非常にソフトで小さな起伏に富んでいます。良い感じのしなやかなアロマが飛び出してくるんですが、しかしやや「こもり気味」です。
中域もほんのりと膨らみが有りますが、アロマを強く放出して来ないのと、時間での変化の具合がまだ大人しいんですね。質感の高さを感じさせつつ長めの余韻を楽しめます。
ですので、今早めに飲まれるならA.C.ブルです。村名ジュヴレは少なくとも来春まで我慢しましょう。クロードの息子さん、ベルトランや兄妹たちも何かを掴んだと感じます。
「滅茶面白くなって来たクロード・デュガ!」
です。是非飲んでみてください!お勧めします。
以下は以前のレヴューです。
-----
【2019年と言うグレートイヤーに、「復活した!」とまではnoisy は言い切れませんが、少なくともこのジュヴレ=シャンベルタンは超旨いです!】
 その昔・・90年代のデュガのジュヴレをワイン会にブラインドで持ち込んだ友人がいて、noisy は他のワイン会から・・何と「掛け持ち」でお伺いをしたため、そこそこに酔っぱらっていたんじゃないかとは思いますが、モノの見事に外しました。
その昔・・90年代のデュガのジュヴレをワイン会にブラインドで持ち込んだ友人がいて、noisy は他のワイン会から・・何と「掛け持ち」でお伺いをしたため、そこそこに酔っぱらっていたんじゃないかとは思いますが、モノの見事に外しました。でも・・誰も「ブルゴーニュ」とすら・・言いませんでした。1995年ものだったんじゃないかと思い出しますが、そのワイン会も何度も同じ場所でやっていたので、幾つかの記憶が混じってしまっているかもしれませんが、noisy は、「ポムロル・・メルロ」と言ったんじゃないかと。それほどにその頃のデュガは濃かったし黒かった?・・と思います。
最もその後は、もっと濃い方が色々出ていらっしゃいましたから、その「濃度の高さ」も、デュガさんの専売特許じゃなくなってしまったんですね。日本での人気も1999年頃がピークだったように思います。
で、現在のデュガさんは、しなやかでエキスの美しい・・外側が濃いんじゃなくて、芯側がしっかりしている・・と言う感じで、男っぽいドライな味わいと、そのしなやかで伸びの良い味わいが特徴になっています。
なので、2017年以前とは相当に違うと思いますが、2014~2017年のワインは、熟すと結果的に似てくるとも思います。
味わい的には相当に評価すべきだと思っていて、アドヴォケイトの92点は過小評価でしょう。93+まではポテンシャル点として窺うべきだと思います。とても美味しいですよ・・これは超お勧めです。しかも価格も相当・・頑張っています。これ以下は無理・・!他のインポーターさんなら別ですけどね。どうぞご検討よろしくお願いいたします。
以下は以前のレヴューです。
-----
【・・げげっ!?・・そう来たか?・・デュガよ・・お前もか!?】
 素晴らしい仕上がりでした!・・今までの村名ジュヴレの味わいは・・A.C.ブルでほぼほぼ近い形で味わえます。2018年の村名ジュヴレは今まで以上のポテンシャルを持っていることは間違い無いと踏みました。
素晴らしい仕上がりでした!・・今までの村名ジュヴレの味わいは・・A.C.ブルでほぼほぼ近い形で味わえます。2018年の村名ジュヴレは今まで以上のポテンシャルを持っていることは間違い無いと踏みました。しかもですね・・これ、もしかしたら間違っている可能性もあるんですが・・
クロード・デュガと言えば、アンリ・ジャイエのワインとは相当にかけ離れたところにある醸造だった訳です。ジャイエは収穫した葡萄を低温で漬け込んでおき、長い発酵期間(つまり低温での発酵)を取ると言う手法・・。デュガさんは低温でなんぞ漬け込まないし、さほど長い発酵期間は取りませんでした(・・そのはず・・)。
ところが、2018年もののアロマを嗅いだ瞬間、そして一口すすった時に・・
「・・あれ?」
アロマは柔らかく、まるで自然派のごとくの拡がり方をして来ます。そして・・低温で漬け込んだ時に良く出るアロマが・・有ったんですね。
まぁ、低温浸漬時由来で良く出るとは言え、それ以外では出ないとは言い切れないので・・断言はしかねますが・・2018年もののワインの色合い・・とてもしっかりしていますよね?
以前の写真と比較すれば、もう一目瞭然です。
ですが、決して濃密で・・濃い訳じゃ無いんですよ。エキスは濃いですよ・・しかし、濃厚な味わいと言えるような、以前のデュガさんのジュヴレの味わいとは、相当に異なるんですね。
いや~・・これは美味しい。しかも相当に複雑性が高いです。黒み掛った紫~紅の小果実の群生、細やかなミネラリティはフローラルにノーズに飛び込んで来ます。中域は適度な膨らみですが、将来はこんなものじゃ済まないでしょう。中盤以降の超複雑な味わいは、今までのデュガさんのジュヴレでは感じなかったもので・・1級クラスの複雑性を感じます。
因みに・・ティム・アトキンさんは92ポイント、ヴィノスは91ポイントで2022~2033と言う飲み頃です。アドヴォケイトは正確には確認できませんが、ウィリアム・ケリーさんが90~92ポイントのようです。まぁ、noisy 的にはリアルワインガイド的評価で、今飲んで91 ポテンシャル93 飲み頃2023~2043です。
これはちょっと面白くなって来たんじゃないでしょうか?・・今までのやり方を改め、低温でのアプローチをし始めたか?・・ホント?・・・いや、まだわからないぞ・・個体差かもしれないし・・などと思っていますが、確実に旨くなって来たのは間違い無く、将来へのさらなる期待も出来るんじゃないかと思っています。
クロード・デュガと言ったらグリオットだけだと思われている方も多いかと思います。noisy は、
「グリオットは・・いらない」
とフィネスさんに言って有りますので、これから先も来ないでしょう。誰でもそれだけは売れるワインを貰っても嬉しくないし面白くない・・でも、
「2018年ものグリオット=シャンベルタンはアドヴォケイト98ポイント、ティム・アトキン氏96ポイント、ヴィノス95ポイント」
のようですので、ティム・アトキンさんが98点以上も付けるようなら・・欲しいな・・前言撤回・・(^^;;
その時はフィネスさんにお願いするかもしれません。それまで、下のクラスで修行していきたいと思います。コンディションの良いワインは本当に美味しいです。ご検討くださいませ。
-----
【これは滅茶苦茶美味しいです!絶対に飲むべきジュヴレ!・・グリオットとシャペルとシャルムに接するオー・エトロワ主体!】
 2016年の村名ジュヴレも「神品!」と書くぐらい美味しかった訳です。
2016年の村名ジュヴレも「神品!」と書くぐらい美味しかった訳です。ですが2017年ものは・・
「完全に吹っ切れた感!」
が目にも判るんじゃないかと。
ある種の「迷い」が「くぐもった感」を生むと仮定するなら、写真を見比べていただければ、2017年ものにその感じは無いと思うんですね。
2017年ものは完全にエキスの味わい。それも非常に上質です。濃さから言えば2016年ものなのかもしれませんが、そこには僅かに吹っ切れない感、詰まった感が有るかもしれません。まぁ、その辺の細かな比較になってしまいますと、「思い込み」も関与してくるとは思いますが、
「何年も続けてテイスティングしていると判ることが有る」
と確信しています。
ある意味、プルミエ・クリュ並みの出来なので・・そのように題名を付けても良いんですが・・何せ「オー・エトロワ」は、グリオットとシャペルとシャルムに接している畑なんですね~。
そしてフィネスさんの輸入で、noisy も出来うる限り良い状態でお渡ししたいと頑張っていますので・・美味しくない訳が無いと・・思いません?
これなら決して高く無いと思います。なんせ、X 級並みですから・・(^^;; 是非ご堪能くださいませ!
以下は以前のレヴューです。
-----
【「神品!」・・ついに・・来たか!長い迷走の終わりを感じさせる凄い出来!!】
 いや~・・圧巻でした。この十数年の間のクロード・デュガさんのワインに感じたことの無い凄み・・繊細な表現を「デュガ味」として認識したのは初めてです。そもそもは90年台のデュガさんの、
いや~・・圧巻でした。この十数年の間のクロード・デュガさんのワインに感じたことの無い凄み・・繊細な表現を「デュガ味」として認識したのは初めてです。そもそもは90年台のデュガさんの、「・・まるでポムロルかサンテミリオンか?」
と思わせるような、また「全く別の印象の凄み」は感じていましたが、
「エキスの集中感から来る密度の高い黒果実、存在感の凄み」
は、このジュヴレの前にテイスティングしたA.C.ブルゴーニュからは全く感じ取れないものでした。
ただし・・昨年、2015年ものの時に、すでにその予感は有った訳です。「いつか来る・・きっと来る・・♪♪」みたいな感じを持っていたんですね。
で、さっそく担当のK君と相談です。
「デュガさんの村名、もっと無いかなぁ?」
「・・すみません・・もう無いんですよ・・」
「(・・あちゃ~・・やっちまったな~~・・)」
そうなんです。ハッキリ言って・・他のエージェントさんの価格を見てしまえば、割高であるのは間違い無いんです。他のエージェントさんからの2016年ジュヴレを飲んでいないので確かなことは言えませんが、「おそらく大分違うんじゃないか?」と言う気がするんですね。
だって・・ここまで凄い村名を全てのボトル、とことんまで造れたとは思えないんですよ。
大抵の場合、いや、ブルゴーニュの小規模生産者の場合、ある程度の量を造ることが出来る村名やA.C.ブルクラスを、平均的な味わいで仕上げることはほぼ不可能なんですね。それをするには「樽寄せ」と言う作業をしなくてはならないからです。一度仕上がったすべてのキュヴェを一緒にしてからボトリングすることが求められますんで、あのD.R.C.も1980年台になってからようやく手を付けたぐらいですから。
この仕上がりなら、もう全然高く無いです。でも、noisyも飲んでしまいましたのであと5本しかない・・どうしよう・・と言う訳です。
リアルワインガイド第63号は、「今飲んで 91 ポテンシャル 93 飲み頃予想 2020~2048」と言う、近年に無いほどの?高い評価だと思います。また、「メチャクチャ美味しい味になること必至」と表現しています。
noisy 的には今飲んでも・・
「すげ~!」
と感じてしまいました!あの、べらぼうな出来だったフーリエの2006年を飲んだ時と同様の印象です。・・いや、フーリエとは全く仕上がりは異なりますけど・・フーリエは「赤果実主体」、デュガは「黒果実」です。
この滅茶凄い村名ジュヴレ、是非とも飲んでいただきたい!・・と強く思います。ドメーヌ・クロード・デュガさんちのワインへの印象は大きく変わることでしょう!・・写真をご覧いただいても、「存在感」は映り込んでいると思います。お勧めです!
以下は以前のレヴューです。
-------
【このエキシーな味わいがクロード・デュガのスタイル!・・と言って良いのでしょう!安定の美味しさです。】
 クロード・デュガさんのワインの正規品の扱いを再開して3年、自分自身、そろそろ結論を出さないといけない頃なんだろうと思っていましたが、この2015年ものジュヴレを飲んで、
クロード・デュガさんのワインの正規品の扱いを再開して3年、自分自身、そろそろ結論を出さないといけない頃なんだろうと思っていましたが、この2015年ものジュヴレを飲んで、「ん~・・おそらくデュガさんはさほど変わってはいないのでは?」
と思えるようになりました。1990年代に大受けしたのは、彼にその時代そのものが乗っかったからなんじゃないかと。
確かに1990年代のデュガさんのワインは、濃密で有り余るパワーを持て余し気味でした。10年ほど置いたものを飲むと、きっちり仕上がっていて、まるで高質なポムロールのメルロに生き生きとしたスパイスをトッピングしたかのようなニュアンスが有りました。凄いなぁ・・と思ったものです。
2000年頃に価格は暴騰し、ネットのショップの価格競争、目玉商品になった頃から、ブルゴーニュワインに求められていたものが変わり始めたのでしょう。時代そのものが彼に乗るのを止めた頃です。
2015年のジュヴレ=シャンベルタンはとても良い出来だと思います。2014年ものも非常に美しく、通好みのドライでエキシーな味わいでした。2015年ものもしっかりそのラインを踏襲しています。
評価も2014年とほぼ同様、アドヴォケイトが90~92Points、バーガウンドが88~91Pointsと安定しています。
この、90~92Points、88~91Points と言う黄色文字の部分に全てが現わされていまして、要約すると、
「美味しいしポテンシャル高いが、そこに到達するのに少し時間が掛かる、もしくは現在は内向的である」
と言うことなのでしょう。
そうなんですよ。通好み・・と言ってしまえば簡単ですが、非常に良く出来ています。しかし内向的なんですね。余り愛想が良く無い・・んです。
物凄い人気だった頃は、有り余るフレーヴァーで若い時にも取り合えず飲めてしまった訳です。パワーを凄く感じる。
しかし現在は以前のような、横方向に拡がるベクトルは抑えられています。縦方向には非常に伸びて行く訳ですが、判りやすい横へのベクトルのパワーが少ない分、判り辛いと言えるのかもしれません。
非常にピュアですし、先行きも明るいし、今飲んでもけっこうに美味しいです。しかし高いポテンシャルを今感じさせてくれるか・・と言うと少し時間が掛かるだろうと言う訳です。
今飲んだら90Points の大台は超えている・・と言うのがnoisy の評価です。後は飲まれるタイミングですね。2014年と2015年の差はさして有りませんが、noisy 的にはむしろ2015年の方がポテンシャル点が高く、今飲んで点は低い・・でもその差は僅かだと評します。
この、ちょっと「むっつりスケベ」的ジュヴレは好きですね。ご検討くださいませ。
以下は以前のレヴューです。
-----
【贅肉を捨て脂肪の無い筋肉質なボディ・・エレガントなジュヴレにスタイル変更!凝縮感たっぷりながら、ツヤツヤと輝き、まるっと滑らかです!】
 これは旨いですね。この艶っぽい色合いからもそれは伝わってくるでしょう。2013年ものもそうでしたが、村名はリリース直後からかなり美味しく飲めます。ACブルは1~2年置いた方が良いでしょう。それにしても美しく伸びやかです
これは旨いですね。この艶っぽい色合いからもそれは伝わってくるでしょう。2013年ものもそうでしたが、村名はリリース直後からかなり美味しく飲めます。ACブルは1~2年置いた方が良いでしょう。それにしても美しく伸びやかですプライスも、2013年は1万5千円を超えていましたが、2014年は何とか1万3千円代を頑張って付けました。この仕上がりなら是非飲んで欲しいですね。
デュガさんらしい、残糖感が全く無いドライな味わいです。果皮の濃度、ジュヴレの鉄や妖艶さの在るミネラリティが深い構造から漂っているのが感じられます。赤と黒・・その中間色は出て来て無い感じですが、それで味蕾や鼻の感覚器官は飽和します。たっぷり在るミネラリティから要素が少しずつ出ているような感じですから、やや柔らかさを感じるでしょう。ガチガチになってないです。
相対的に、やはり美しさを感じます。2013年もそうですし、その前も・・2010年位から感じていたクロード・デュガさんのスタイル変更は、やはりこんな感じにしたい・・と言うデュガさんの意思表示なのでしょう。
享楽的な味わいになるまでには、かなりに年数を必要とするでしょう・・おそらく10年とか・・ですが、昔のデュガさんのワインのように、2~3年は濃さで美味しく飲めるが、その後しばらく黙り込む期間が長い・・と言うスタイルでは無く、一旦閉じることは有っても、全く出て来なくなることは無いでしょう。
贅肉を捨て、筋肉を手に入れたかのような、スタイリッシュなジュヴレでした。かなり美味しいと思います。ティム・アトキン氏は93Pointsでした。是非飲んでみてください!お勧めします!
以下は2013年のコメントです。
-----
【悩んでいたか?・・のクロード・デュガ復活の年!この凄い味わいは確認しておくべきではないでしょうか!】
 え~・・ACブルの写真が見当たらないので掲載していませんが、2013年はもう2度ほど飲んでますんで・・はい・・ほぼ完璧に理解したつもりです。
え~・・ACブルの写真が見当たらないので掲載していませんが、2013年はもう2度ほど飲んでますんで・・はい・・ほぼ完璧に理解したつもりです。で、価格の安いACブルをお奨めしたいところなんですが、残念ながら「今飲んで」の評価を無理して上げることなど出来ませんで、残念ながら3年後を目処にとさせていただきました。
しかし村名ジュヴレの素晴らしさにはビックリです。フィネスさんの扱いの良さを感じることも出来るかと思います。
上記では、「クロード・デュガはしばらく扱って無かった」と書きましたが、定期的では無いにせよ、ちょくちょく飲んでいましたので、彼のワインの変化も気付いていました。
昨年も2000年のグリオットを開けたりして・・良かったですよ。
そして2008年もの位から、ブローカーものを中心に時折ご紹介させていただいています。現在もブローカーものの2011年村名ジュヴレを新着に掲載しています。・・まぁ、価格差は見ないでくださいね・・別に「ボッてる」訳じゃぁ無いんです。本当に仕入れの価格がね・・違うんですよ。
で、2008年ものの記事の時にはしっかり書いた記憶が有るんですが、
「もしかしたらデュガは迷っている?・・悩んでいる?」
みたいな記事です。
それまで、まるでメルロかと思えるような重厚さのある味筋だったものが、エキス系の綺麗なものに変化していたんですね。ただし、受け取る側の印象が予定調和で終わらなかった性も有るとは言え、余りの変化、そして何となくの「中途半端感」が有ったのは事実です。
綺麗なのは綺麗なんだが、何か途中で途切れてしまうような・・例えば余韻ですね・・。続いていて、長くない・・とは言わないものの、何となく途中で途切れ・・弱弱しく復活・・で途切れ・・みたいな感じでしょうか。中域も何となく「イビツ」な形状で、素直に丸みがあるとも言えないような・・です。
ところがですね・・この2013年の村名ジュヴレ・・エライ美しいじゃないですか!・・エキスがたっぷりで、しかも美しいパレットを描きます。いつものデュガさんのように、やや遅い収穫を思わせる「黒味」を持ち、「赤味」も当然ながら有るんですが、黒味から赤味に向かう部分に途切れは無く、何層にも自然なグラデュエーションが有るんですよ。滑らかで深く、非常にドライです。
それに加え、ジュヴレらしい質のミネラリティもしっかり持ち、濡れたような質感、アロマの上がりのスピードはまるで自然派並みでしかも美しいです。「す~っ」と入って来ておだやかに質感を見せ、中盤以降から消えるまでの間に様々な表現をしてくれます。
例えばフーリエはもっと赤く、若々しい部分の高い周波数領域の表現がちゃんとしていますが、デュガさんはその部分はやや黒味で覆われ、より低い周波数領域での表現になります。
しかし、この厳冬期のように品温が下がりやすい時期には、フーリエのような全域にバランスの良い、赤い味わい中心のブルゴーニュは、中域と低域のパフォーマンスをやや落とします。デュガさんは高い周波数領域は黒で置換していますから、フレッシュな部分を持たず、中高域、中域、低域をしっかり持ち、品温度が下がってもバランスを崩さないんですね。
なので、13度~14度で飲み始めても・・重厚で香りも上がり、全体のバランスも素晴らしいんです。調子に乗って随分と飲んでしまいました。
反面、ACブルは、確かに村名ジュヴレにそっくりなんですが・・残念ながら村名ほどのポテンシャルが不足しています。美味しく飲めますが15度ほどまでに上げないと厳しいですし、その表情はやや硬く、内向的です。しかし3年ほど置きますと持っているポテンシャルを発揮しはじめ、村名と同様なパフォーマンスを見せるでしょう。
つまりよりタイトに薄く仕上がって居るわけですね。なので熟成に時間が掛かっちゃう訳です。
それにしても村名ジュヴレはビックリするほど旨かった!・・質も素晴らしいです。このプライスはこの質なら仕方が無いと確認できるでしょう!コンディションも素晴らしいです。是非飲んで欲しい・・です!ご検討くださいませ。
●
2022 Gevrey-Chambertin 1er Cru
ジュヴレ=シャンベルタン・プルミエ・クリュ
【すみません・・1本だけです・.・】----以前のレヴューを掲載しています。
あまりに少ない2021年のジュヴレ1級です。ヴィノスは上値94ポイントと・・余り以前とも評価は変わりません。
「2021年ものは・・しなやかでエレガントで美味しいヴィンテージ!」
と言いたいですね・・その昔は2000年とか、2002年とかをそう言ってましたら・・白い目で斜めに見られてるような気分になりました。ご検討くださいませ。
以下は以前のレヴューです。
-----
【アドヴォケイトは上値94ポイントでした!】
まぁ・・海外メディアは2019年ものと、そうは変わらない評価をしているようです。コラムの数字をいじらなくて良いのは楽ですが、反面・・混乱してしまいます。
2020年ものはやはり複雑性の高い味わいをどのように判断するか?・・と言う点で、評価者それぞれの意見が異なる場合がある様に思います。下げに掛かっている方、現状維持の方が多く、上げていらっしゃる方は多く有りません。2020年ものの性格から、バレルテイスティングは相当難しかったと思われます。
このジュヴレ1級のワインですが、クロ・サン=ジャック下(ほんの少し離れる)のクレピヨと、マジ=シャンベルタン直下に接したラ・ペリエールのブレンドです。クレピヨは多くの生産者さんがリリースしている訳では在りませんが、クロ・サン=ジャックのポテンシャルをほんのり持っている・・そんな感覚が有りますし、ラ・ペリエールはマジっぽいスパイシーさとある種の硬さ・・(^^;; が有るように思います。
ですので良い1級なんじゃないかなぁ・・と思うしかないですね。入庫、1本でした!・・ので、飲んじゃうと無くなっちゃうんですね・・すみません。
以下は以前のレヴューです。
-----
【アドヴォケイトは92~94 ポイント、アレン・メドゥズは90~93ポイントと上々の評価です。】
A.C.ブルや村名ジュヴレを飲めば、もう90年代の濃厚なデュガのスタイルでは無いことは判っていますが、さすがにこのプルミエ・クリュ、飲めるところまでは行っておりません。
飲みたいのは山々なんですが、飲まなきゃならないア
「2021年ものは・・しなやかでエレガントで美味しいヴィンテージ!」
と言いたいですね・・その昔は2000年とか、2002年とかをそう言ってましたら・・白い目で斜めに見られてるような気分になりました。ご検討くださいませ。
以下は以前のレヴューです。
-----
【アドヴォケイトは上値94ポイントでした!】
まぁ・・海外メディアは2019年ものと、そうは変わらない評価をしているようです。コラムの数字をいじらなくて良いのは楽ですが、反面・・混乱してしまいます。
2020年ものはやはり複雑性の高い味わいをどのように判断するか?・・と言う点で、評価者それぞれの意見が異なる場合がある様に思います。下げに掛かっている方、現状維持の方が多く、上げていらっしゃる方は多く有りません。2020年ものの性格から、バレルテイスティングは相当難しかったと思われます。
このジュヴレ1級のワインですが、クロ・サン=ジャック下(ほんの少し離れる)のクレピヨと、マジ=シャンベルタン直下に接したラ・ペリエールのブレンドです。クレピヨは多くの生産者さんがリリースしている訳では在りませんが、クロ・サン=ジャックのポテンシャルをほんのり持っている・・そんな感覚が有りますし、ラ・ペリエールはマジっぽいスパイシーさとある種の硬さ・・(^^;; が有るように思います。
ですので良い1級なんじゃないかなぁ・・と思うしかないですね。入庫、1本でした!・・ので、飲んじゃうと無くなっちゃうんですね・・すみません。
以下は以前のレヴューです。
-----
【アドヴォケイトは92~94 ポイント、アレン・メドゥズは90~93ポイントと上々の評価です。】
A.C.ブルや村名ジュヴレを飲めば、もう90年代の濃厚なデュガのスタイルでは無いことは判っていますが、さすがにこのプルミエ・クリュ、飲めるところまでは行っておりません。
飲みたいのは山々なんですが、飲まなきゃならないア
●
2022 Charmes-Chambertin Grand Cru
シャルム=シャンベルタン・グラン・クリュ
【憑き物が落ちたんじゃないか!?と思えるほどに素晴らしい2022年のデュガさんのシャルム=シャンベルタンです!】
2022年のデュガさんのA.C.ブルが余りに素晴らしく、びっくりして・・村名ジュヴレも開けたんですが、2020年頃までに感じていた「悩み事」みたいなものが全て無くなり、ブルゴーニュ・ピノ・ノワールらしい・・あっけらかんとした美しさを表現してくれました。
noisy 的には、濃厚さ故の新樽の強い使い方がドメーヌ・クロード・デュガの味わいの特徴だったものを・・それじゃいかんと・・この10年ほどの間に様々なトライをして来たのだろうと思っていますし、息子さんが入ったことも、それまでの造りを変えるキッカケになったのでしょう。
海外メディアの評点からは、余りその変化を感じるようなものには見えず、バーガウンドは2021年から1ポイント上げているに留まります。
しかしながら、この均整の取れた美しさこそは単一品種で仕上げるブルゴーニュワインの特徴でも有りますから、これが完全に出来たと思える2022年の仕上がりを見れば、
「長年の悩みが消え去ったのは事実だろう」
と推測しています。ぜひ・・2010年以前とは全く・・大きく変わったクロード・デュガさんの美しい味わい、お確かめください。
以下は以前のレヴューです。
-----
【アドヴォケイトは上値96ポイントでした!】
まぁ・・デュガさんは3枚のグラン・クリュをリリースしています。言わずと知られたグリオット=シャンベルタン、シャペル=シャンベルタン、シャルム=シャンベルタンです。どの畑も非常に狭く、3枚合わせても1ヘクタールにも満たないので、入手が難しいワインです。
アドヴォケイトはデュガさんに優しいので、いつも比較的に高めの評価が出ていました。今はまぁ・・ちょっとだけ?・・
因みに2020年のグリオットには、アドヴォケイト 96~98 Points、ティム・アトキン氏 96 Points。シャペル=シャンベルタンにはアドヴォケイト 95~96+ Points、ティム・アトキン氏 96 Points。
シャルムにはアドヴォケイト94~96 Points、ティム・アトキン氏 95 Points ですから、グリオットとシャペルはほぼ変わらず、シャルムはほんのわずか劣るかな・・と言う感じでしょう。
貴重なワインです。是非ご検討くださいませ。
以下は以前のレヴューです。
-----
【デュガさんの2枚目の看板ワインです!】
デュガのグリオット=シャンベルタンの持つ圧倒的な存在感から言えば、僅かに劣るかもしれない・・にせよ、やはりシャルム=シャンベルタンは素晴らしいと・・思います。最近では2000年を飲みましたが、十数年経過して大分飲みやすくなっていました。その頃のデュガさんはまだ濃密系でした。
1990年代のデュガさんは、村名でさえ・・
「・・右岸・・すか?」
と言いたくなるような・・と言うか、ブラインドだと悩みに悩んで最終的にソコにたどり着くしかない・・と言う結論に達し、オープンで・・
「・・デュガか~・・」
と・・(^^;; 経験ある方、多いんじゃないかと思いますが・・
しかし、それはそれでとても美味しかったし、他のワインを圧倒していたと思います。
2017年のシャルム=シャンベルタンは、リアルワインガイドでポテンシャル97ポイントと言う凄い評価です。
一方アドヴォケイトは・・・上値で94ポイント、飲み頃予想も2023~2040 と、ちょっと過小評価気味で意味不明な感じです。濃厚なスタイルから脱しようとし、脱したとは思っていないのかもしれませんね。
現在のデュガさんのスタイルは、日本人にはとても受けると確信しています。ご検討くださいませ。
以下は以前のレヴューです。
━━━━━
【2016年・・迷走の末辿り着いた先には・・?】
フィネスさん扱いのドメーヌ・クロード・デュガの看板の一つ、シャルム=シャンベルタンです。まぁ・・皆さんが欲しいのはグリオット=シャンベルタンなのかもしれませんが・・(^^;;
noisy 的には、フィネスさんとお取引が再開できることになった時、
「デュガさんのワインは別に分けてくれなくていいから、欲しい人に上げてください。」
と、担当のK君に伝えていました。
まぁ、大抵は飲めば色々ワインが教えてくれるんですが、最近のデュガさんのワインは良く判らなかったし、欲しい人がいるならグリオットもシャルムもいらない・・と思っていたからなんですね。
気が変わったのは2016年のジュヴレを飲んでから・・です。これはやはり素晴らしい・・物凄いジュヴレでした。圧巻でしたね。
で、気付けば noisy 宛ての予約表にはシャルムとプルミエ・クリュが掲載されていた・・と言う訳です。
フィネスさんのワインはやはり一味違う・・と言うのは、全てのワインにおいて「その通り」とは言わないものの、結構な確率で「その違い」に気付くことが有ります。その辺り、ブルゴーニュ・ファンの中には「フィネス・ファン」が多いと言うのも頷けます。
ただし、価格は他のエージェントさんに比較すると結構に高めですよね。2016年のジュヴレなどは、noisy の仕入れより安く販売しているショップが結構に有りますからね。
なので、さすがに数の無いシャルムとかプルミエ・クリュ・クラスの比較はできないまでも、村名クラスで「エージェント対決」をやってみたいなぁ・・などと考えています。
この希少なシャルム=シャンベルタン2016年はリアルワインガイド第63号でついに・・ポテンシャル97+ まで来ました。グリオットは98 ポイントでしたので、ほぼ同格?ですかね。
「すげ~です」
だそうです。
個人的には、代替わりを始めたドメーヌ・クロード・デュガの迷走が終わった年・・それが2016年かと感じています。ご検討くださいませ。
noisy 的には、濃厚さ故の新樽の強い使い方がドメーヌ・クロード・デュガの味わいの特徴だったものを・・それじゃいかんと・・この10年ほどの間に様々なトライをして来たのだろうと思っていますし、息子さんが入ったことも、それまでの造りを変えるキッカケになったのでしょう。
海外メディアの評点からは、余りその変化を感じるようなものには見えず、バーガウンドは2021年から1ポイント上げているに留まります。
しかしながら、この均整の取れた美しさこそは単一品種で仕上げるブルゴーニュワインの特徴でも有りますから、これが完全に出来たと思える2022年の仕上がりを見れば、
「長年の悩みが消え去ったのは事実だろう」
と推測しています。ぜひ・・2010年以前とは全く・・大きく変わったクロード・デュガさんの美しい味わい、お確かめください。
以下は以前のレヴューです。
-----
【アドヴォケイトは上値96ポイントでした!】
まぁ・・デュガさんは3枚のグラン・クリュをリリースしています。言わずと知られたグリオット=シャンベルタン、シャペル=シャンベルタン、シャルム=シャンベルタンです。どの畑も非常に狭く、3枚合わせても1ヘクタールにも満たないので、入手が難しいワインです。
アドヴォケイトはデュガさんに優しいので、いつも比較的に高めの評価が出ていました。今はまぁ・・ちょっとだけ?・・
因みに2020年のグリオットには、アドヴォケイト 96~98 Points、ティム・アトキン氏 96 Points。シャペル=シャンベルタンにはアドヴォケイト 95~96+ Points、ティム・アトキン氏 96 Points。
シャルムにはアドヴォケイト94~96 Points、ティム・アトキン氏 95 Points ですから、グリオットとシャペルはほぼ変わらず、シャルムはほんのわずか劣るかな・・と言う感じでしょう。
貴重なワインです。是非ご検討くださいませ。
以下は以前のレヴューです。
-----
【デュガさんの2枚目の看板ワインです!】
デュガのグリオット=シャンベルタンの持つ圧倒的な存在感から言えば、僅かに劣るかもしれない・・にせよ、やはりシャルム=シャンベルタンは素晴らしいと・・思います。最近では2000年を飲みましたが、十数年経過して大分飲みやすくなっていました。その頃のデュガさんはまだ濃密系でした。
1990年代のデュガさんは、村名でさえ・・
「・・右岸・・すか?」
と言いたくなるような・・と言うか、ブラインドだと悩みに悩んで最終的にソコにたどり着くしかない・・と言う結論に達し、オープンで・・
「・・デュガか~・・」
と・・(^^;; 経験ある方、多いんじゃないかと思いますが・・
しかし、それはそれでとても美味しかったし、他のワインを圧倒していたと思います。
2017年のシャルム=シャンベルタンは、リアルワインガイドでポテンシャル97ポイントと言う凄い評価です。
一方アドヴォケイトは・・・上値で94ポイント、飲み頃予想も2023~2040 と、ちょっと過小評価気味で意味不明な感じです。濃厚なスタイルから脱しようとし、脱したとは思っていないのかもしれませんね。
現在のデュガさんのスタイルは、日本人にはとても受けると確信しています。ご検討くださいませ。
以下は以前のレヴューです。
━━━━━
【2016年・・迷走の末辿り着いた先には・・?】
フィネスさん扱いのドメーヌ・クロード・デュガの看板の一つ、シャルム=シャンベルタンです。まぁ・・皆さんが欲しいのはグリオット=シャンベルタンなのかもしれませんが・・(^^;;
noisy 的には、フィネスさんとお取引が再開できることになった時、
「デュガさんのワインは別に分けてくれなくていいから、欲しい人に上げてください。」
と、担当のK君に伝えていました。
まぁ、大抵は飲めば色々ワインが教えてくれるんですが、最近のデュガさんのワインは良く判らなかったし、欲しい人がいるならグリオットもシャルムもいらない・・と思っていたからなんですね。
気が変わったのは2016年のジュヴレを飲んでから・・です。これはやはり素晴らしい・・物凄いジュヴレでした。圧巻でしたね。
で、気付けば noisy 宛ての予約表にはシャルムとプルミエ・クリュが掲載されていた・・と言う訳です。
フィネスさんのワインはやはり一味違う・・と言うのは、全てのワインにおいて「その通り」とは言わないものの、結構な確率で「その違い」に気付くことが有ります。その辺り、ブルゴーニュ・ファンの中には「フィネス・ファン」が多いと言うのも頷けます。
ただし、価格は他のエージェントさんに比較すると結構に高めですよね。2016年のジュヴレなどは、noisy の仕入れより安く販売しているショップが結構に有りますからね。
なので、さすがに数の無いシャルムとかプルミエ・クリュ・クラスの比較はできないまでも、村名クラスで「エージェント対決」をやってみたいなぁ・・などと考えています。
この希少なシャルム=シャンベルタン2016年はリアルワインガイド第63号でついに・・ポテンシャル97+ まで来ました。グリオットは98 ポイントでしたので、ほぼ同格?ですかね。
「すげ~です」
だそうです。
個人的には、代替わりを始めたドメーヌ・クロード・デュガの迷走が終わった年・・それが2016年かと感じています。ご検討くださいませ。
バティスト・ナイラン
バティスト・ナイラン
フランス Baptiste Nayrand ブルゴーニュ
[ oisy wrote ]
ブルゴーニュはコトー・デュ・リヨネより、ナチュール界の新星バティスト・ナイランをご紹介いたします。
コトー・デュ・リヨネというアペラシオンはご存知ない方もいらっしゃるかと多いかと思います。調べてみると、ソムリエ教本にはブルゴーニュのページの最後に一行記載されているのみでした。ボジョレーから南、リヨン西側の丘陵地帯で、ガメイが主体の地域です。
バティストのスタイルは「ナチュール系」です。しかも結構「攻め攻め」です。この1年私もNoisy Wineに入荷するワインを毎日テイスティングしてきましたが、その中でも「最もアヴァンギャルド」かもしれません。
揮発酸もあります。ですので「揮発酸のニュアンスが全くダメ」という方はお手に取らないようご注意ください。
赤はそれほどもないですが、白のゼニスは「ギリギリまで攻めて」います。ナチュール好き、という方もゼニスに関しては特にコラムをよくご確認の上、ご購入ください。
しかしこの攻めたスタイルだからこそ辿りつける、「激ピュアな世界」があることを知りました。アヴァンギャルドレベルがトップクラスなら、ピュア感もトップレベルです。エキスの抽出が驚くほど上手いです。
お好きな方の手に届くことを祈っております。各コラムに詳細を記載しております。キュヴェによってアヴァンギャルドさは大きく異なりますので、よくよくご確認の上ご購入いただけますよう、よろしくお願い申し上げます。
 ■エージェント情報
■エージェント情報
世界的な食のライト&ヘルシー化によって、今ではピノ・ノワールに並ぶ人気品種となったガメィ。そんなガメィの新たな可能性を表現する造り手が現れました。2015ヴィンテージからナチュラルワイン造りを始めたバティスト・ナイランです。バティストは、ピエール・オヴェルノワやマルセル・ラピエールのワインに強い感銘を受け、30歳の時にそれまでの仕事を辞めて、ジュリアン・ギィヨとミシェル・ギニエの下で研鑽。生まれ故郷であるリヨン近隣のコトー・デュ・リヨネ南部のミルリーで1ヘクタールの古木のガメィの畑を引き継いで、ドメーヌを設立しました。
2015年が初ヴィンテージですが、欧米のガメラーのナチュラルワイン愛好家の間では大人気で、既にドメーヌからの割り当て数量しか購入することができません。北の品種が好きなバチストはピノ・ノワールやアリゴテ、シャルドネなどのワインも手掛けています。
ブルゴーニュはコトー・デュ・リヨネより、ナチュール界の新星バティスト・ナイランをご紹介いたします。
コトー・デュ・リヨネというアペラシオンはご存知ない方もいらっしゃるかと多いかと思います。調べてみると、ソムリエ教本にはブルゴーニュのページの最後に一行記載されているのみでした。ボジョレーから南、リヨン西側の丘陵地帯で、ガメイが主体の地域です。
バティストのスタイルは「ナチュール系」です。しかも結構「攻め攻め」です。この1年私もNoisy Wineに入荷するワインを毎日テイスティングしてきましたが、その中でも「最もアヴァンギャルド」かもしれません。
揮発酸もあります。ですので「揮発酸のニュアンスが全くダメ」という方はお手に取らないようご注意ください。
赤はそれほどもないですが、白のゼニスは「ギリギリまで攻めて」います。ナチュール好き、という方もゼニスに関しては特にコラムをよくご確認の上、ご購入ください。
しかしこの攻めたスタイルだからこそ辿りつける、「激ピュアな世界」があることを知りました。アヴァンギャルドレベルがトップクラスなら、ピュア感もトップレベルです。エキスの抽出が驚くほど上手いです。
お好きな方の手に届くことを祈っております。各コラムに詳細を記載しております。キュヴェによってアヴァンギャルドさは大きく異なりますので、よくよくご確認の上ご購入いただけますよう、よろしくお願い申し上げます。
 ■エージェント情報
■エージェント情報世界的な食のライト&ヘルシー化によって、今ではピノ・ノワールに並ぶ人気品種となったガメィ。そんなガメィの新たな可能性を表現する造り手が現れました。2015ヴィンテージからナチュラルワイン造りを始めたバティスト・ナイランです。バティストは、ピエール・オヴェルノワやマルセル・ラピエールのワインに強い感銘を受け、30歳の時にそれまでの仕事を辞めて、ジュリアン・ギィヨとミシェル・ギニエの下で研鑽。生まれ故郷であるリヨン近隣のコトー・デュ・リヨネ南部のミルリーで1ヘクタールの古木のガメィの畑を引き継いで、ドメーヌを設立しました。
2015年が初ヴィンテージですが、欧米のガメラーのナチュラルワイン愛好家の間では大人気で、既にドメーヌからの割り当て数量しか購入することができません。北の品種が好きなバチストはピノ・ノワールやアリゴテ、シャルドネなどのワインも手掛けています。
●
2022 Nadir Blanc V.d.F.
ナディール・ブラン V.d.F.
【ちょいアヴァンギャルドだけど激ピュア!甘みのあるオレンジ系果実に台湾ウーロン茶のアロマが堪まりません!】[ oisy wrote ]
 [ oisy wrote ]
[ oisy wrote ]こちらもアヴァンギャルド的ではありますが、ゼニスほどの攻めた造りではありません。ただし揮発酸のニュアンスはあります。酢酸は極々わずかで感じないレベルです。苦手な方は、くれぐれもご注意ください。
このナディール、オイジーは勘違いしていたかもしれません。というよりまだまだ経験不足だったと痛感いたしました。
というのも抜栓仕立てでは揮発酸が強めで、これはアウトかもしれないと思ったんですね。しかしその後ほぼボトルに残った状態で、冷暗所に1週間ほど置いていたら揮発酸が穏やかになり、他の要素が上がってきて、かなり美味しく・・・なってきたんですね。いやびっくりしました。
アンズ、オレンジマーマレードのような、甘みのあるオレンジ系果実。そこに紅茶や台湾ウーロン茶のようなアロマティックな茶葉のニュアンス。タオピオで有名なゴンチャの阿里山ウーロン茶を彷彿とさせます。これらが合わさって複雑な香りです。しかしエスニックにいくことなく、あくまで主体は果実のピュア感です。
残糖はごく僅かにはあると思うんですが、糖分由来ではなく、ピュアな果実が黒糖やドライフルーツのような詰まった柔らかい甘みを形成しています。果実の旨みもあり、凝縮感も高いのに全く重くない。味わいの充実感に対しての液体のエアリーさが高く、普通なら矛盾するような要素が両立しているのは、やはりこの極限のピュアさからの表現だと思います。これだけマセレーションしてエグ味や枯れ感がまったく無いというのもちょっとすごい・・・です。
意外だったのはマリアージュがなんでもいけそうだ、ということ。魚系の前菜や、肉料理はもちろん、クリーム系や和食にもいけそうな雰囲気があります。ワインからもどことなく「和」の雰囲気を感じるんですよね。
「生きたワイン」ですから飲むタイミング、抜栓からの経過時間、酸素との触れ合い度合いによって表情が目まぐるしく変わると思います。少し違うな、と思ったら一旦おいて、翌日、または一週間後に飲んでみると驚くほど味わいが纏っているかもしれません。ただし今は活動が停止している酢酸菌が活性化すると一気に酢へと向かってしまう危険性も含有していますので、保管はくれぐれも14度付近、高くても20度以下の環境でしていただけますようお願いいたします。飲む際は逆に温度を上げていくと、変化も大きく、丸さや香り、このワインが持つ複雑性がグッと出てくると思います。赤ワイン的な温度帯で飲まれることをお勧めいたします。
アヴァンギャルドなオレンジ果実と台湾ウーロン茶の茶葉のニュアンスがたまらない激ピュアワインです!ナチュールファンの方にお勧めです。ご検討くださいませ。
●
2023 Toit du Monde
トワ・デュ・モンド V.d.F.
【とろけるような果実の質感と、濡れ感のあるガメイの奥深さを感じ取れる、激ピュアな一本!】[ oisy wine ]
 [ oisy wine ]
[ oisy wine ]激ウマです。ただし要注意事項もありますので、よくよくレビューをご確認の上、ご検討いただけますようお願いいたします。
抜栓仕立ては、無いとは言えない揮発酸のニュアンスと還元で、私も見誤っていました。ボトルに9割以上残っている状態で1週間冷暗所保管、要素が上がってきて・・・このワインの素晴らしさに気づきました。毎日毎日テイスティングに励んでいますが、まだまだ未熟であることを痛感しました。精進あるのみですね。
バティストのワインに共通する驚くようなピュア感はさることながら、「柔らかさ」に痺れました。「果実が柔らかい」と表現したらいいのでしょうか。ぶどうの質もあるのでしょうが、アンフュージョンという「煎じるのみ」のマセレーションが大きいのかもしれません。一切のエグ味のない、果実オンリーの柔らかい深みの抽出です。
煎じるというと煮出すようなイメージですが、ワイン造りの文脈では、「浸漬するだけ」ということのようです。ピジャージュなどをせず、ただ浸漬するだけでこれだけ果実の豊かな風味とポテンシャルを引き出せるというのは、かなりブドウの質も良いな、ということが伺えます。
バティスト本人がマルセル・ラピエールに強い感銘を受けたと言っている通り、かなりマルセル・ラピエールのモルゴンのキャラクターに似ていると感じます。「果実のあたかかさ」があり、そのあたかたかさが「果実のコク」を連れてきています。違うのは、やはりバティストの方がギリギリまで攻めているのと、「酸の冷ややかさ」が高いという点です。
温かいの冷ややかってどういうこと?という感じですが、「果実は温かい」のに「酸は冷たい」ということです。これには畑の標高が高いことも影響していると思われ、「冷涼な高い標高で、ブドウがよく熟した」ということだと思います。そして「過熟に至っていない」ということなのかと思います。収穫タイミングの良さも伺えます。
トリュフチョコレートのようなとろけるような果実の質感があるのはそのせいかもしれません。深く温かい果実エキスと鉄と石灰が混じりあったようなミネラリティ、素直に美味しいと感じます。
やはり「生きたワイン」であることを実感します。体に染み込む、体が喜ぶような感覚になるのはそのせいかもしれません。ですがその分温度変化には気をつけなければなりません。14度付近での保管が推奨です。20度を超えるとワインが劣化(酢酸菌が再度動き出し、酢へと向かう)する可能性があります。温度管理さえしっかりしていれば熟成も可能なポテンシャルがあり、結構ポテンシャルも高いと感じます。ご検討のほど、どうぞよろしくお願いいたします。
●
2021 L’Astrale Rouge V.d.F.
ラストラル・ルージュ V.d.F.
【アヴァンギャルドなのにエレガント系!? ここまでエキスがクリアーなガメイは見たことがありません!】[ oisy wine ]
 [ oisy wrote ]
[ oisy wrote ]トワ・デュ・モンドと比べるとよりクリアーで艶やか、石灰系のミネラリティを感じる造りです。極限のピュア感も健在で、ごく僅かに揮発酸と還元のニュアンスがあります。
還元のニュアンスは現在の時点で抜栓後数日で取れます。半年から一年待てば消えると思います。揮発酸はレベル的には僅か、ナチュールワインとしては問題なく、むしろこのワインには必要な要素であると感じます。現時点では目立ちますが、こちらも時間が経てば他の要素が上がってきて、ほぼ感じず、香水的な妖艶さを含む香りの立ち上がりをサポートする一要素として馴染むと思います。
特にこのワインはバティストの「エキスの抽出の上手さ」が際立っており、エグ味や青みが出やすいガメイにおいて、そのようなニュアンスが一切なく、ピュアでクリアーなエキスが澱みなく抽出されています。アヴァンギャルドさはありますが、スタイルとしては「エレガント系」です。そういえばこのワインもガメイなんですよね。ガメイでここまでクリアーなエキス的ワインってあまり見ないな・・・
それでいて抽出が不十分というわけではなく、果実の旨みや深み、積層感がしっかりと抽出されきっていて、深みや複雑性がありありと表現されているんですよね。赤い果実に紫蘇、出汁的な旨み、めちゃうまな果実酸が一体となって体に染み込んでいきます。
テイスティングしてると、飲まずに口内で確認している段階で誤って飲み込んでしまいそうになります。それぐらい自然に体が吸収してしまう、してしまいたくなる、まるで経口補水液のような側面を持つワインです。
こちらのワインも温度管理は特に重要です。14度前後での保管をお願いいたします。20度を超える保管は活動停止中の酢酸菌が動き出し、劣化(酢化)が進む可能性があります。また揮発酸のニュアンスが若干量含まれますので苦手な方はお手に取らないようお願い申し上げます。その分ピュア感は満載です。ご検討のほど、よろしくお願いいたします。
●
2022 Sauvage Rouge V.d.F.
ソヴァージュ・ルージュ V.d.F.
【果実酸の旨み、あまみが激ウマ!激ピュア!ガメイの亜種が主体の20品種のフィールド・ブレンドです!】[ oisy wrote ]
 [ oisy wrote ]
[ oisy wrote ]赤白約20品種混植のフィールド・ブレンドとのことですが、製法、色味的に赤ワイン寄りだと思っていただいた方がいいかと思います。ただしその色味はかなりクリアーで透明感を持ち、白ブドウがブレンドされていることは見た目からもわかります。
最近、マルセルダイスのラルシュやクロヴァロンのレ・ザンディジェーヌなどのワインを飲ませていただき、「フィールド・ブレンドのワインにしかない良さ」があると感じております。
それは色んなブドウ品種由来の味がする、ということではなく、「様々な特徴を持ったブドウ品種が一体となった時の美しさ」が素晴らしいということです。単一品種がピアノの独奏とするならば、さながらオーケストラのような感じです。お、ちょっとうまいこと言えたかもしれません。
とにかくピュアな、赤い果実です。そこに探せば、アンズ、オレンジ、枇杷、アメリカンチェリー、金木犀、バラ、ラベンダーなど様々な要素が入り乱れています。
しかし不思議と一体感があり、じゃあ誰がこれを指揮しているのかといえば、この土地のミネラリティ、すなわちテロワールだと思います。
バティストの他のワインを飲むと、全体的にツヤ感のあるミネラリティを感じます。このワインも白ブドウ由来の透明感かな、と思っていましたがそれだけではなく、石灰系のミネラリティ由来の透明感もあるような気がします。ですのでどのワインもはっきりと「赤い果実」が主体に来ます。
またこのワインを飲んでイメージしたのはヴァーゼン・ハウスの激うまグラン・ドルディネールです。「弾けるような赤い果実の旨みとピュア感」がよく似ていて、テクニカルを見るとセミ・マセラシオンカルボニックを用いているところから手法的にも近しい感性で作られているのかなと思いますが、ヴァーゼンハウスは親しみやすいワインを造るという目的で導入しているかと思いますが、バティストはこの区画のブドウには「この手法が良い」ということで採用しているように感じます。というのもこのワインが他のバティストのワインと比べて飛び抜けてエレガンスを持っているからなんですね。
そしてほぼ気づかない程度の甘さがあります。果実のあまやかさと僅かな残糖、そして果実酸の旨みがワイン全体をまとめ上げています。この「あまみが激うま」です。(ワインとしてはドライ・・・いや中口というのが適切かと思います。)
そしてこのワインも揮発酸は僅かにありますが、問題ないです。むしろこのワインに関しては他のワインよりも揮発酸以外の要素が先んじて上がってきているので(セミ・マセラシオン・カルボニックの影響かな・・・)今時点で最も安定してきています!
ただし激ピュアですので、温度管理にはお気をつけくださいませ。14度前後での保管が推奨です。20度を超えると劣化の恐れがあります。昨今スーパーなどで色んな理屈をつけて「生ワイン」と謳っているものを散見しますが、こういうワインこそ「生ワイン」と言いたくなりますね!ご検討くださいませ。
セバスチャン・フェザス
セバスチャン・フェザス
フランス Sebastien Fezas ガスコーニュ
 [ oisy wrote ]
[ oisy wrote ]ボルドーの南東からスペインにかけての間に位置する、フランス・ガスコーニュ地方よりナチュールの新星をご紹介いたします。ビオディナミの充実したぶどうで、SO2無添加ながら、安定感のある素晴らしいワインを産み出します。
テイスティングして感じたのは、非常に酸の表現が綺麗です。どのキュヴェもハリのある美しい酸を持っています。そして、ボルドーより南なのに・・・非常に冷やかなんですよね。特に彼の綺麗な酸から生み出される泡には感激してしまいました・・・
本人としては「カジュアルに楽しめるワインを造りたい」という趣旨が強いようですが、センスなんでしょうね・・・アロマやエレガンスもあるワインに仕上がっております。しかもそれでいて非常に手に取りやすい価格帯です。一押しです!ぜひお試しくださいませ!
■エージェント情報
2010年代に入りガスコーニュ地方でもワインの潮流は大きく進化しています。セバスチャン・フェザスは2012年に家業のドメーヌを引き継ぎ、ビオディナミを導入し2017年からナチュラルワイン造りを始めたガスコーニュ地方のナチュールの新星です。フランツ・ソーモンやベルトラン・ジュセ、レ・シェ・デュ・ポール・ドゥ・ラ・リュンヌなどのナチュラルワインの造り手達が大きな信頼を寄せており、毎年彼からブドウを購入しているネオ・ヴィニュロンでもあります。
世界中でワイン造りを学んだセバスチャンは、今までにない南西地方のワインを手掛けています。産膜酵母で熟成させた南西版ヴァン・ジョーヌや海をイメージしたペットナット、プティ・マンサンのオレンジワインなど個性的なナチュラルワインが揃っており、エチケットデザインも毎年変えるなど新時代の感性も備えています。ナチュラルに敏感な北欧のデンマークやスウェーデン、英国、ベルギーなどのインポーターは既に彼のワインの輸入を始めています。
●
N.V.(2022) Franche Lippee Rouge V.d.F.
フランシュ・リッペ・ルージュ V.d.F.
【しっとり果実のエキスと、ピュアフルーツのフィネスを含んだアロマが素晴らしいです!】[ oisy wrote]
 [ oisy wrote]
[ oisy wrote]ピュアなフルーツが発するアロマ・・・これはやはりSO2によって削られてしまうのかな・・・当たりのナチュールの赤ワインに出会うとよく思ってしまいます。
このピュアフルーツアロマ。クラシカルなワインのエレガンスとはちょっと違うんですよね。エレガンスの一部としては感じることはあるんですが、主体にならないというか・・・
しかし得てしてナチュールの良い生産者には主体的に感じられることが多々あります。
紫を含んだ透明感もある赤です。チェリー、ブルーベリー、ぶどうそのもの。ここに冒頭のフルーツアロマが上がってきます。すみません、今レビューを書きながらふと気が付きました。このアロマの立ち上がりには・・・極少量の揮発酸が必要なんですね!揮発酸といえば、通常はネガティブな要素だけれども使い方次第では・・・ポジティブに働きますね。ナチュールの良い作り手は知ってか知らずか、揮発酸をコントロールしてこのアロマを創出している・・・のかもしれません。
例えばブルゴーニュ的エレガンスはミネラルの組成と熟成によって得られる・・と思っています。そのためにはあの素晴らしい土壌が必要。しかしどの産地にもそう素晴らしい土壌ばかりではない・・・ではどうするか。
できるだけ良いぶどうを育てて、丁寧に醸す、そうすると土壌由来のエレガンスではなく、果実のピュアさ由来のアロマが生成される。そしてこのアロマの立ち上がりには極微量のポジティブな揮発酸のサポートが必要になる。SO2を入れるとこの揮発酸を抑えてしまうので、感じなくなってしまう、みたいな感じではないかと感じたわけです。しかし非常に微妙な調整が要求されるんでしょうね。フランシェ・リッペはまさにそんな感じでフルーツのアロマの表現に成功したワインだと思います。芳しい香水的なフルーツのアロマをプンプンさせています。
エキス的な質感とシラーの綺麗な果実感、ピチッと酸があります。白と泡を飲んで思いましたが、セバスチャンのワインは酸の表現が本当にキレイです。そしてしなやかな果実感がありながら酸には冷やかさも
ニコラ・ルナール
ニコラ・ルナール
フランス Nicolas Renard ラングドック
● もう・・30年近く、彼のゴタゴタに付き合っているような気がしていますが、珍しくラシーヌさんのリストに出ていたので仕入れてみました。物凄く久しぶりのニコラ・ルナールです。
■ Nicolas Renard(Chateau de Gaure)ニコラ・ルナール(シャトー・ド・ゴール)
●Alderica Syrah - Monrodon 2021アルデリカ シラー・モンロドン 2021
◆シャトー・ド・ゴールでのワイン造りについてニコラ・ルナールから
「リムーで僕がコンサルタントをするワインがあるのだけれど、興味ある?」
と、またしても突然話が降ってきたのが2021年の夏。シャトー・ド・ゴールという生産者のコンサルタントをすることになり、2021年VTの醸造からリムーでのワイン造りを手伝うことになったという。
シャトー・ド・ゴールは50ha以上の畑をワイナリーなので、オーナーのピエール・ファーブルと話し合いながら、少量ずつニコラの考えるワイン造りをしていくことになるだろう、という話だった。大きく不安に思いながらも、ニコラの手掛けるグルナッシュ、シラー、シュナン、シャルドネ、ペット・ナットなどなど、期待せずにはいられないフレコミで、ラシーヌからNOという返事をすることはありえなかった。ピエールもラシーヌにニコラの関わったワインの紹介については積極的で、まだ出来上がっていないワインの購入が決まった。
2022年春に試飲した、熟成中のワインは、生産地が違ったとしても、ニコラ作のワインだと納得のいくものだった。しかしその頃からお互いに意思疎通が難しくなってきている、とニコラとピエールのやり取りをラシーヌが介することが多くなった。片や50haの畑を所有するワイナリーのオーナーと、片や年産10000本に満たないワインを洞窟で生産する風来坊。わかり切っていたことなのかもしれないが、2022年の夏に二人の共同プロジェクトは解消してしまう。
「ワインにおいてブドウ栽培が何よりも大事で、醸造で出来ることは何もない」
とワインの造り手はしばしば口にする。とはいえ誰がどのように、どこまでワイン醸造に関わってきたかも同様に重要な要素であることには疑いが無い。共同プロジェクト解消の2022年夏時点で、ラシーヌが購入を約束していたワインは全てシャトー・ド・ゴールにて熟成中で、それらのワインの原料となるブドウの栽培にニコラは関わっていない。
ラシーヌとしてはワインの醸造から瓶詰までだけでも、ニコラに完結してもらわなければならない。ピエールとニコラを根気よく説得し、2022年11月にニコラの監督の元、赤ワイン(グルナッシュ1種とシラー2種)の瓶詰めをしてもらうことが出来た。
白ワインとペット・ナットについては、ニコラの手による瓶詰をすることが不可能だったため、購入を断念。プロジェクトの立ち消えは残念でならないが、もしまた同じような話があったら何度でも乗ってしまいたくなるような夢のあるプロジェクトだった。赤ワインすら到着しなかったらと思うと気が気でなかったが、ワインは無事入港し日本市場に紹介できる運びとなった。
上記のような理由から100%ニコラのワインとは言えないかもしれないが、収穫から瓶詰までニコラの監督の元で行われた。
「収穫のタイミングは出来上がるワインの方向性を決定づける重要な事項だ。ロワールと醸造所のあるリムーを行き来するのは大変だったけれど、瓶詰まで責任をもって行うことが出来たし、素敵な人たちに出会うことが出来た。最終的にはド・ゴール側とのやり取りが難しくなってしまったが、最後まで僕を信じて指示通りにワインの管理を行ってくれたマチューと、ド・ゴール敷地内で民宿を営むブノワとテレーズには感謝してもしきれない。」
とニコラ。
※キュヴェ名はどれもアルデリカ(シャトー・ド・ゴールの地域に伝わる伝説に登場する王女の名に由来)で、それぞれ品種名が記載されている。シラーの2種の畑名は裏ラベルに記載。
以下は大昔のコラムの内容です。
-----
極少量の入荷です。
伝説か、それとも懐古的な噂話に過ぎないのか・・いや、
「・・ニコラ・ルナール?・・誰?・・それ?」
と言われかねない状況を作ってしまったのは、やはりニコラ・ルナール本人なのでしょう。知らない人にはどのように説明すれば良いのかと、非常に面倒なことになってしまいます。
その辺の昔話しは追々・・コラム中で書ければと思いますが、やはり・・これだけは言っておきたい・・
「本当に素晴らしいワインです!」
天才としてその名を馳せたニコラ・ルナールでは有りますが、やはりワインの中身で勝負するのは、その名が有ろうが無かろうが同じことです。
「私ももう50歳。最後に良い仕事をしたいからね。」
とロワールに購入した洞窟セラーが、そんな彼のワインを育むのに一役どころか何役も影響していると思われます。
今回はネゴス・・買い葡萄で仕込んだ・・非常にリーズナブルなソーヴィニヨンのジャンヌ2014年と、彼のお得意、珠玉のシュナン・ブランはドメーヌもののトゥーレーヌ・ルル2014年、そしてローヌのティエリー・アルマンの元での「サン=ペレ2011年&2012年」は、
「おったまげ~!!もの凄いです!!」
な品質でした!
■ Nicolas Renard(Chateau de Gaure)ニコラ・ルナール(シャトー・ド・ゴール)
●Alderica Syrah - Monrodon 2021アルデリカ シラー・モンロドン 2021
◆シャトー・ド・ゴールでのワイン造りについてニコラ・ルナールから
「リムーで僕がコンサルタントをするワインがあるのだけれど、興味ある?」
と、またしても突然話が降ってきたのが2021年の夏。シャトー・ド・ゴールという生産者のコンサルタントをすることになり、2021年VTの醸造からリムーでのワイン造りを手伝うことになったという。
シャトー・ド・ゴールは50ha以上の畑をワイナリーなので、オーナーのピエール・ファーブルと話し合いながら、少量ずつニコラの考えるワイン造りをしていくことになるだろう、という話だった。大きく不安に思いながらも、ニコラの手掛けるグルナッシュ、シラー、シュナン、シャルドネ、ペット・ナットなどなど、期待せずにはいられないフレコミで、ラシーヌからNOという返事をすることはありえなかった。ピエールもラシーヌにニコラの関わったワインの紹介については積極的で、まだ出来上がっていないワインの購入が決まった。
2022年春に試飲した、熟成中のワインは、生産地が違ったとしても、ニコラ作のワインだと納得のいくものだった。しかしその頃からお互いに意思疎通が難しくなってきている、とニコラとピエールのやり取りをラシーヌが介することが多くなった。片や50haの畑を所有するワイナリーのオーナーと、片や年産10000本に満たないワインを洞窟で生産する風来坊。わかり切っていたことなのかもしれないが、2022年の夏に二人の共同プロジェクトは解消してしまう。
「ワインにおいてブドウ栽培が何よりも大事で、醸造で出来ることは何もない」
とワインの造り手はしばしば口にする。とはいえ誰がどのように、どこまでワイン醸造に関わってきたかも同様に重要な要素であることには疑いが無い。共同プロジェクト解消の2022年夏時点で、ラシーヌが購入を約束していたワインは全てシャトー・ド・ゴールにて熟成中で、それらのワインの原料となるブドウの栽培にニコラは関わっていない。
ラシーヌとしてはワインの醸造から瓶詰までだけでも、ニコラに完結してもらわなければならない。ピエールとニコラを根気よく説得し、2022年11月にニコラの監督の元、赤ワイン(グルナッシュ1種とシラー2種)の瓶詰めをしてもらうことが出来た。
白ワインとペット・ナットについては、ニコラの手による瓶詰をすることが不可能だったため、購入を断念。プロジェクトの立ち消えは残念でならないが、もしまた同じような話があったら何度でも乗ってしまいたくなるような夢のあるプロジェクトだった。赤ワインすら到着しなかったらと思うと気が気でなかったが、ワインは無事入港し日本市場に紹介できる運びとなった。
上記のような理由から100%ニコラのワインとは言えないかもしれないが、収穫から瓶詰までニコラの監督の元で行われた。
「収穫のタイミングは出来上がるワインの方向性を決定づける重要な事項だ。ロワールと醸造所のあるリムーを行き来するのは大変だったけれど、瓶詰まで責任をもって行うことが出来たし、素敵な人たちに出会うことが出来た。最終的にはド・ゴール側とのやり取りが難しくなってしまったが、最後まで僕を信じて指示通りにワインの管理を行ってくれたマチューと、ド・ゴール敷地内で民宿を営むブノワとテレーズには感謝してもしきれない。」
とニコラ。
※キュヴェ名はどれもアルデリカ(シャトー・ド・ゴールの地域に伝わる伝説に登場する王女の名に由来)で、それぞれ品種名が記載されている。シラーの2種の畑名は裏ラベルに記載。
以下は大昔のコラムの内容です。
-----
極少量の入荷です。
伝説か、それとも懐古的な噂話に過ぎないのか・・いや、
「・・ニコラ・ルナール?・・誰?・・それ?」
と言われかねない状況を作ってしまったのは、やはりニコラ・ルナール本人なのでしょう。知らない人にはどのように説明すれば良いのかと、非常に面倒なことになってしまいます。
その辺の昔話しは追々・・コラム中で書ければと思いますが、やはり・・これだけは言っておきたい・・
「本当に素晴らしいワインです!」
天才としてその名を馳せたニコラ・ルナールでは有りますが、やはりワインの中身で勝負するのは、その名が有ろうが無かろうが同じことです。
「私ももう50歳。最後に良い仕事をしたいからね。」
とロワールに購入した洞窟セラーが、そんな彼のワインを育むのに一役どころか何役も影響していると思われます。
今回はネゴス・・買い葡萄で仕込んだ・・非常にリーズナブルなソーヴィニヨンのジャンヌ2014年と、彼のお得意、珠玉のシュナン・ブランはドメーヌもののトゥーレーヌ・ルル2014年、そしてローヌのティエリー・アルマンの元での「サン=ペレ2011年&2012年」は、
「おったまげ~!!もの凄いです!!」
な品質でした!
 | Nicolas Renard ニコラ・ルナール 地域: Loire 地区/村:アンボワーズ 造り手: Nicolas Renard ニコラ・ルナール 醸造・栽培責任者: Nicolas Renard ニコラ・ルナール 創業年:2013年 ドメ ーヌ解説:2011年がファーストヴィンテッジ。借りた畑で栽培を行い、自身のワインを造っています。同じエリアで3haの畑を別途購入。今後ルーサンヌを中心に樹根し、一部グルナッシュグリ(ペティヤンを造る予定)を植える予定だったが売却、現在はトゥーレーヌはAmboise(アンボワーズ)周辺で3haの畑をレンタルしワイン造りを行っている。 畑面積:3ha 主要品種:シュナン・ブラン、シャルドネ、ソーヴィニョン 平均年間生産量:6000本 |
 ■2013年1樽だけのシュナン・ブラン | 『ラシーヌ便り』no.108 《合田泰子のワイン便り》より、 2014年10月寄稿 《ニコラ・ルナールの本気》 トリノからパリ、続いてロワールへ。ニコラ・ルナールの新たな出発を確認のため訪問。思えば長いつきあいとなるニコラは、他に真似できない飛びぬけたワインを造る点にかけては、疑いなく天才です。が、天才には気まぐれがつきもの。いつも内心、ワインが商品となって出てくるまで、ハラハラしどうしです。なのに、このたびは大きな嬉しい驚きでした。なんと、理想的な洞窟のカーヴを入手していたらしいのです。 今年の1月、「ワインを造ったので、よかったら会いにきてください」と、たった一行のSMSメールを受け取り、すぐさまニコラのもとに飛んでいったことはご存知の通り。2014年からアンボワーズで、シュナン・ブラン、シャルドネ、ソーヴィニョンを造ることになっており、畑の旧持ち主からセラーの一部を借りると聞いていました。 |
 | がニコラは、実際に作業をするにつれて不便を感じ、自分のセラーを持とうと思い立ち、つい最近インターネットで探し始めたところ、なんとアンボワーズの駅から10分ほどの川沿いにある、洞窟つきの廃業したネゴシアンの小さなカーヴが売りに出ていました。洞窟は一つ、奥行きは10mほどでしょうか。 そうこうするうちに、隣人の洞窟も購入することになりましたが、何と奥行きは100mもあり、中で元の洞窟とつながっていました。 「私も50歳、最後にいい仕事をしたいからね」 とのこと。値段を聞いて高くないのに驚きましたが、幸運な物件に出会えてニコラはとても満足げ。これで長期エルヴァージュ計画も、準備は万端。 |
 | 昨年、一樽だけ造ったロワール・シェールのシュナン・ブランは、さらに一年間樽で熟成するという。 「やっぱり、私のドライなシュナンの原点は、ニコラにあった!」 と叫ばずにいられない、素晴らしいシュナン・ブランでした。八月は好天に恵まれ、このまま行けば、2014年は良いとしになりそうです。 2011年からニコラが3ヴィンテッジ造ったサン・ペルレは、2012年と13年はまだ樽に入っています。この春リリースされた2011年は、ビン詰めから一年間たって味わいが落ちつき、美しいまとまりが出てきていました。骨格・奥行きとも姿を現し、大変おいしくなっています。今後、サン・ペルレがどうなるかわかりませんが、ラシーヌとしてはロワールに専念してもらいたいと願っています。 数年間過ごしたアルデッシュでのワイン作りも、ひとまず一段落。これからはアンボワーズの理想的な洞窟カーヴで、思い切り醸造できるようになったわけです。ニコラの前途明るい再出発を、心から喜んでおります。 |
 | 『ラシーヌ便り』no.122 《合田泰子のワイン便り》より、2015年12月寄稿 新年おめでとうございます。新年を明るい話題で出発したいと思っていたところ、待望のワインの船積みが暮れぎりぎりに確定したという連絡が届きました。一つは、我らがニコラ・ルナール。やっと。リリースです。 ラシーヌ便り108号でお知らせしましたように、「ニコラ・ルナールの本気」が姿を現します。 「ヤスコ、僕を覚えてますか? ワインを作ったので見に来てください」 と、携帯からショートメールが届いたのが、2014年1月。早速アンボワーズを訪ねて、ー樽に満たないシュナン・ブラン2013年をテイスティングし、ニコラの復活を感激のうちに祝いました。当時われらのニコラはまだローヌに住んでいて、サン・ペルレの2011年、2012年と2013年が醸造中。と同時にニコラは、ロワールでのワイン作りに向けて準備を始めていました。 ところが、2011年のサン・ペルレが無事届いた後、2012年と2013年産が予定の時期が来ても音沙汰がありません。連絡がプッツリと途切れたまま、梨のつぶてです。「また、どこかに消えちゃったのかしら?」と半ば諦めかけていました。 風来坊のニコラは、周辺の作り手とも交流がない様子。誰に聞いても、「最後に見かけたのは2003年頃のディーヴかな」という始末。フランスでも、いまや忘れられた存在も同然でした。1995年と1996年に、あのすさまじいジャニエールを作っていたことを知っている人も、もうほとんどいません。 2015年4月には、アンボワーズのセラーに様子を見にラシーヌのスタッフが行くという連絡を、期待せずに送りました。いざ訪問してみたら、ネット環境も整っていない作業場で、ニコラは寝泊まりしながらワインを作っていたのです。それで少し安心したのでしたが、2013年と2014年のシュナン・ブラン、ソーヴィニョン2014年がいつ出てくるか、待てど暮らせど連絡がありません。 |
 | 「私も50歳、最後にいい仕事をしたいからね」 というニコラの言葉に歓喜していたのに、まさかのぬか喜びだったのか、と歎きながら時間が過ぎて行きました。 ところが2015年も押し詰まった12月2日になって突然、「12月7日、集荷に来てください。ラベルと印刷代用のお金が足りない」と、いきなり入金催促メールです。ニコラもワインも無事というわけで、一同、安堵の胸をなでおろしました。 さて、2016年2月にはサン・ペルレ、シュナン・ブラン、ソーヴィニョン、が一挙に届きます。ニコラの復活を祝してロワール地方のお料理と、細身で繊細なシュナン・ブランを楽しむ会を開かなくては、と大きく期待がふくらみます。 |
●
2021 Alderica Grenache
アルデリカ・グルナッシュ
【・・そもそもあなたは赤ワイン、造ってたんだっけか?・・(^^;;】
 最初に言っておきたいと思います。ワイン自体はめちゃ素晴らしいです!ですが、少し還元的で、抜栓直後はちょっと気になるかもしれません。でもそれを差し引いても・・素晴らしい味わいです。
最初に言っておきたいと思います。ワイン自体はめちゃ素晴らしいです!ですが、少し還元的で、抜栓直後はちょっと気になるかもしれません。でもそれを差し引いても・・素晴らしい味わいです。ニコラ・ルナールです。彼のワインとは・・どうだろう、四半世紀は過ぎているでしょう。ティエリー・ピュズラ名でキュヴェ・ニコラ・ルナールを扱って以来、
「長く持って3年・・」
と言う、その働き場所でのゴタゴタを起こしてしまう悪い癖・・?・・が、アチコチに影響を与えてしまったんですね。
しかしながら・・彼のワインは素晴らしく美味しい・・。彼が抜けた後のワインは、例え彼が少し携わっていたとしても・・どこか「腑抜け」になって感じられます。一体何度、そんなことを繰り返したのか・・noisy も間接的にかなり力をお貸ししたと・・思ってはいます。
そもそもあなた・・
「そんなに赤ワイン、リリースしてましたっけ?」
まぁ・・ローヌのティエリー・アルマンにもいましたから・・当然ながら黒葡萄も手にしていたでしょう。ですが noisy 的には二コラは、
「白ワインの人」
でした。なので、シャトー・ド・ゴールの赤ワインを造ると言うのもどこか・・
「ん?」
と思ってしまうんですね。
 ですが、この特売のグルナッシュ、非常に良く出来ています。
ですが、この特売のグルナッシュ、非常に良く出来ています。まぁ・・抜栓したてはやや匂います。「還元臭」と言うやつです。なので、これに弱い方は、
「飲むより30分早く抜栓しておく」
か、
「購入を思い留まる」
のをお薦めします。
充分に凝縮した赤黒果実・・味わい的には僅かな部分は無視するとして甘くないが、アロマは甘やかさを含みます。決してスパイスが乾いた感じで横に拡がって行く・・なんてことは有りません。しっとりと落ち着いたスパイスが、健全な葡萄をアピールして来ます。
おそらくほんのりと残糖は有るのでしょう・・が、甘くは感じないんですね・・。ここは、
「さすがニコラ・ルナール!」
と言いたくなる絶妙のバランスです。
この、ほんの僅かな残糖が生む細やかな味わいこそが、彼の持ち味であるとも・・思っています。彼の僅かな甘みを残したロワールワイン・・滅茶美味しかったです!・・絶品でした。遅摘みの甘いワインも素晴らしく・・めちゃ美味しかったですが、甘いのでそんなには飲めないんですね。でもこの、
「有るかどうかわからない位の残糖」
が・・素晴らしいんです。リアリティのある果実、花を感じさせてくれます。
そして・・そこには・・
「僅かなガス」
が有り、舌先に感じるその「ピチピチ」がまた・・素晴らしい訳です。飲めば判りますよ。
そして、締まりを持ちながらも良い感じで美しい酸のピュアさを感じさせながら膨らみます。これがまた果実感をリアルに引きだたせているとも言えるかと。
そして余韻もピュアでナチュラル・・と言うより自然な感じ。マロラクティックも物凄く自然で・・なんとも心地良い滑らかさです。
濃度はあるものの、アルコール分は14度・・でもそんな風には感じさせない・・エレガンスも感じるワインで、
「微細微妙なバランス」
を感じます。
ん~・・やっぱりあなた、天才なのかなぁ・・余り褒めたくないなぁ・・と思いつつ、自分のことは思いっきり棚に上げて、
「周りの人と上手くやって行かないといかんよ・・」
などとブツブツ言ってしまいました・・。ぜひ飲んでみてください。面白い・・いや、めちゃ美味しいと思います!
以下はもっとも最近にご紹介させていただいたニコラ・ルナールのワインのレヴューです。
-----
【申し訳ありません、テイスティングできるような数が来ておりませんので、テイスティングコメントはありません。】
極少量の入荷です。テイスティングコメントも出せず誠に申し訳ございませんが、お一人様1本+条件の無いワイン1本にてお願いいたします。
1995年もののテュエブッフ・ネゴスワインとしての初登場から、全てテイスティングを行い、お客様にはご理解をいただいてご購入いただいて来ましたニコラ・ルナールの素晴らしいワインですが、時代の流れでしょうか・・非常に残念ですが、このような状態になってしまいました。
テイスティングを行い、流通数を減らしてしまうよりも、お客様に実際に飲んでいただこうと考えています。
以下は以前のコラムより、買い葡萄の「ジャンヌ2014」のレヴューです。
━━━━━
【レンタルの畑?の葡萄で仕込んだトゥーレーヌ・ソーヴィニヨン!!ニコラ・ルナール復活の狼煙となった1本は実にリーズナブル!!】
 素晴らしいソーヴィニヨン・ブランです!トゥーレーヌはロワール中流域にあたるアペラシオンですが、白の品種はシュナン・ブランが多いです。昨今はソーヴィニヨン・ブランやシャルドネも増えてきていますが、下流域よりは膨らみのあるワインに仕上がるとしても、やや軽薄な味わいになりがちかと思います。
素晴らしいソーヴィニヨン・ブランです!トゥーレーヌはロワール中流域にあたるアペラシオンですが、白の品種はシュナン・ブランが多いです。昨今はソーヴィニヨン・ブランやシャルドネも増えてきていますが、下流域よりは膨らみのあるワインに仕上がるとしても、やや軽薄な味わいになりがちかと思います。しかしながら、ソーヴィニヨンの華やかさ、エレガンスはそのままに、しっかりと中域と低域をバランス良く表現、見事な味わいに仕上げているのは、さすがニコラ・ルナールと唸ってしまいました。
天才たる所以・・それは当然ながら畑仕事にもよるかと思います。しかしながら noisy 的には、
「醸造とワインのエルヴァージュのマジジャン」
だと・・思うんですね。
思い起こせば2004年もののルメール・フルニエです。ニコラ・ルナールはこれを完全に仕上げる前に・・ドメーヌをトンズラしてしまいました。言い訳は聞いていないので判りませんが、やはりオーナーとの軋轢でしょう。まぁ・・どっちにしても女性問題かと・・思いますが・・。
で、この2004年ものを待ちわびて・・ようやく届いたワインをテイスティングしたnoisy はビックリしてしまいました。
そして、2004年ものはそこでエンド。売りには出したか出さなかったか・・忘れましたが、出したとするなら、
「不味い」
と書いたはずです。実際、とてもニコラ・ルナールが仕上げたキュヴェとは思えなかったんです。なので2ケースほど入れたアイテムをほとんど売らなかったと思います。
ニコラ・ルナールが2004年ものを仕上げずに出奔したと聞いたのはその後です。ラシーヌさんでも状況は良く判らなかったようでした。後で、仕上げていない・・つまり、瓶詰めしていないキュヴェを、別の人を雇ってコルクを打ち、販売に出したと言うことでした。
このことから、ワインの瓶詰め前のエルヴァージュが完全に終わった段階で、即、瓶詰めをしなければならないのに、温度管理はしていたとしてもタンクの中に置いておかずにはいられなかった状況が、2004年のルメール・フルニエのワインの味わいをおかしなものにしたと判断した訳です。
その後、ラシーヌさんもニコラのいないルメール・フルニエから手を引いてしまいました。ドメーヌに残った2003年もの、2004年ものの処分をあるエージェントさんから協力依頼が有り、美味しい2003年ものはかなり販売させていただきましたが、2004年ものは一切手を付けませんでした。
あれから10年・・ですね。今、このソーヴィニヨン・ジャンヌ2014を飲んで、とても面白かった2000年頃からのニコラ・ルナールのワインとのお付き合いを思い返しています。
やはりこの人は葡萄を見る天才で有り、葡萄をワインに昇華する天才であると思います。こんなソーヴィニヨン・・を造れちゃうんですから・・。ロワール中流で、これほどの重量感の有るソーヴィニヨンを、重さを全く感じさせずに、スパイシーなアロマを消さずに、全体をエレガンスに満ちたものに仕上げるなんぞ、天才でなければ無理でしょう。
重みは下手をすれば「鈍重」に直結してしまいます。ほとんどがそうです。ボルドーのソーヴィニヨンもそうです。リーズナブルかもしれないが、その重みは甘みに頼っているのみだからです。ニコラはちゃんとドライにしつつ、葡萄がワインにどんな道のりで成りたいのかを常に見ていると思います。その上で、例え何年掛かろうとも、発酵が終わらないものはそのまま発酵を続けさせます。終わったと判断した段階で、スピーディに瓶に詰め、瓶熟成をさせ、出荷するんです。こんな簡単なように思えることが、実は一番難しいんです。
今飲んでも素晴らしいです。ソーヴィニヨンの緑のニュアンス、スパイシーさ、フラワリーなアロマ、軽やかなミネラリティが有り、中域も美しく拡がり、実は底もかなり深い・・です。美味しいですね・・。本領発揮には2~3年掛かるかと思いますが、このバランスでも素晴らしいです。本数は有る程度いただきましたが、このソーヴィニヨンによるジャンヌはレンタルの畑ものだか買い葡萄だか判りませんが、今回一度っきりだそうです。なので今回限りです。是非・・天才が天才たる所以をお試しいただければと思います。お勧めです!
ドメーヌ・ディディエ・ダグノー
ディディエ・ダグノー
フランス Domaine Didier Dagueneau シュド・ウェスト
● ドメーヌ・ディディエ・ダグノーの2021年ものをご紹介させていただきます。と言いましても2021年ものとしては・・
「1アイテムのみ」
です。天候が悪く、畑毎に仕込むことが不可能になり、プイィ=フュメの全てを合わせて「XXI(ヴァン・テ・アン)」をリリースすることにされたんですね。しかも量は超絶に少ないです。
メディアもまた・・全くと言って良いほど、このヴァン・テ・アンの評価を出していませんので、noisy としましても・・まぁ・・どこか、ディディエ・ダグノーとの繋がりをずっと感じていたので、開けさせていただきました。
そうしましたら・・何と十数年ぶりに、
「ディディエに出会った!」
と・・感じました。詳細はコラムをお読みください。
メディアも評価を出していないと書きましたが、Vivino と言うSNS的要素を持ったサイトに書込みが有り、総合的には、
「5ポイント満点で4.3ポイント」
と高い評価が出ています。
また、書かれたコメントも・・面白いのでちょっと訳してみました。
「4.5/5.0。バンジャマン・ダグノーのキュヴェXXI。岩水のように透明な色、信じられないほど複雑な香り、最初はレモン、その後洋梨や白桃、しかしその背景には香水のように、非常にわずかにスモーキーな側面、アーモンド、そして何か塩分、ミネラル。口に含むと非常にストレートで、非常にコントロールされた酸味、余韻の驚くべきミネラル感、そしてクレイジーな長さ!魚のウォーターゾイは、脂ののった料理とバランスのとれた組み合わせです。」
「3.8/5.0.魅力的なワイン。ロワールでは不作だったので、ルイ・バンジャマンはすべての区画をこの区画に結合することで対応しました。フリント、サラブレッドなどなど。純粋な灰と塩、わずかな煙。生理食塩水、牡蠣の殻。奇妙?」
また日本人の方もフィネスさんの試飲会で飲まれて「美味しい」とされ、4.4/5.0 の評価でした。
ですが、飲むタイミングで評価は相当変わると思われますので、ぜひコラムをご確認いただき、どうされるかお考えください。
また、バックヴィンテージのシレックスやピュル=サンなどをいただきましたので、そちらもどうぞよろしくお願いいたします。
-----
ダグノーの2020年をご紹介させていただきます。入荷数は今までの1/2~1/3です。フィネスさんもその辺りを慮って、2019年ものを少し分けてくれましたので一緒にご案内させていただきます。
非常に少ないので飲めたのは「2021エトセトラ」だけでした。ですが・・飲んでおいて良かった・・ベンジャマンが何を考えているのか・・少し理解出来たと思います。因みに本人は以下のように言っていますので・・まずご覧ください。
///
2020年は日照量がとても多く年間通して気温が高く乾燥したので、2018年、2019年に続いて3年連続で暑さに悩まされるヴィンテージとなった。春から早熟傾向で暑い夏は水不足に悩まされたが葡萄はよく耐えてくれて元気に成長した。収穫は9月初めに行ったが、フレッシュさを残すのか、もしくは完熟させるのか、葡萄をどの段階で収穫するかで近所の生産者の間でも収穫日がかなり異なるので各生産者ごとにワインの特性がだいぶ変わるヴィンテージになっている。当家では比較的早めに収穫したので豊かでたっぷりとした味わいながらもフレッシュさは損なわれておらず、口当たりはゆったりとしており素晴らしく長い余韻がある。
///
エトセトラ2020 を飲む限りにおいて、やはりベンジャマンは・・非常なほどに多く内包しているミネラリティの存在での・・ある種の「若い時期における閉じこもりがち」な表情を何とかしよう・・としていて、それを実現して来ていると感じられます。
それは・・「卵型の樽を試験的に使用している」と言うテクニカルからも感じられますが、新型コロナウイルスの蔓延で情報が少ないので、実際にはどのようなことをやっているのかは判りませんが、
「飲んでみればフカフカとしか畑と火打石、石の存在」
を若いうちから感じられるんですね。2020年ものは2019年ものよりも、その傾向は強いんじゃないかと感じました。
また海外メディアでは・・特にヴィノスですが、最近はシレックスよりもピュル・サンの方を高く評価しているんですね・・平気で・・(^^;; まぁ、これが正しいかどうかはかなり微妙では有りますが、ピュル・サンって・・昔から相当美味しいのに何故か皆シレックスに流れてしまう傾向が有りますから、
「ピュル・サンを数週間放置して楽しむ」
そんな飲み方も以前に提案していますので、もし可能でしたらやってみてください。
2020年の太陽の恵みを最大限に活かした造りになっていると思います。是非ご検討くださいませ。
-----
ディディエ・ダグノーの2019年です。いや~・・このところのダグノーは、ミネラリティのマンモス度は以前のままに、柔らかさを毎年、増して来ています。
ですので以前のように、
「・・飲んだけど・・硬くて酸っぱくて・・どこが美味しいの?」
などとガッカリすることは無い・・そのように言えるでしょう。もっとも、
「ちゃんと飲めばその凄さは誰にでも判る」
のも、以前と全く変わりませんが。
しかし、シレックスもピュル・サンもエトセトラも・・これほどまでに外向的に、どんどんにこやかになって来たのには驚かされます。そもそも自然派ですから、畑の柔らかさが感じられるのが普通のはずで・・やっとディテールが出て来た・・のには、
「ベクトル変換」
が出来ている・・んだと思います。
卵型や横長の樽などを使い、ミネラリティをやや内側に配置、表情をやや外側に持って行くことに成功しているんだろうと思います。
その上で、ディディエ・ダグノーらしいスタイルは以前のまま・・ですから、
「毎年、より美味しさを感じやすくなって来ている!」
と言えます。
あ、バビロン・セック2017年だけは・・いまちょっと硬いです・・。これは様子を見ながら・・果実感の成長を待ちましょう!・・素晴らしいブラン・フュメ・ド・プイィです。すみません、2019年のサン=セールは数が少な過ぎて割り当てが有りませんでした。
-----
2018年ものを中心に入って来ましたディディエ・ダグノーです。このところベンジャマンが造り出すワインは、以前のような「クリスタルの殻」に閉じこめられたかのような、テッカテカで滑らかなテクスチュアは本当に素晴らしいけれど、熟すのに時間が相当掛かる・・と嘆くようなものから脱出、やはりベクトル変換をしたかのような・・それでもミネラリティの総量は以前と全く変わらない・・各要素を外向きに、得やすくなったような「柔らかさ」も身に着けています。
2018年もののブラン・フュメ各種の出来は見事なものでした。ただミネラリティだけが目立つのではなく、おそらく2015年頃までのものが見せたクリスタルの塊が持つような硬さを、かなり細かく砕いたようなイメージで、様々な表情が出現しやすくなっています。
例えばあの「シレックス2018」は、それこそ抜栓直後は硬さを見せるものの、3~4日で官能的な柑橘フルーツのアロマをポンポンと振りまき、味わいも膨らみも、
「美味しく飲める!」
と感動するようなタイミングが有ります。そして、また数週間掛けて収縮と膨張を繰り返しながら徐々に全開放に向かってくれます。
これはもうとても感動的です。タイミング良くNoisy wine にご来店された方は、ドライバーの方は除き、テイスティング出来ましたので・・もうグラスをいつまでも離せないような状況になってしまいました。それほどまでに感動的なアロマが店内の空気を彩っていました。申し訳なかったのはドライバーさんで・・香りは嗅げどその本体には触れられない・・と言うお預けを喰ってしまった訳です。
今回はバックヴィンテージ、サンセールを除き全アイテムのテイスティングをさせていただきました。上記のシレックスの振る舞いは、他のロワールのキュヴェも同様です。
また、バビロンのセック、モワルー2016も飲ませていただきました。いや・・
「激旨!」
です。セックの美味しさもさることながら、モワルーの美味しさには感動しました。
まぁ、ワインファンは迂闊にも甘さの有るワインへの恐怖?畏怖?みたいなものを持っているようですが、これ、飲んだらそんなものはすっ飛んでしまう事、請け合いです。
また、ダグノーのシレックスは、海外メディアは良いところ、94ポイント止まりです。アドヴォケイトは2018年ものシレックスを93ポイントと評価しているようです。
しかし、以下の評価を見ていただければお判りになるかと思いますが、残念ながら彼らはダグノーのワインをちゃんと理解は出来ていないと思います。
2015 Blanc Fume de Pouilly Silex Domaine Didier Dagueneau
94 Points 2018-2025 / Andrew Jefford Decanter.com January 2018
17.5/20 Points 2017-2027 / Richard Hemming MW JancisRobinson.com July 2017
デカンター誌は94ポイントとまぁまぁ・・では有りますが、飲み頃を2018年から2025年としていますし、ジャンシス・ロビンソン・コムでは17.5ポイントで2017~2027年と、直近の10年間の飲み頃予想です。
言わずともお判りいただけるかと思いますが、この期間に美味しく飲める幸せな時間を得られる人が、本当にいるとしたら・・それは奇跡でしか有りません。特に2015年ものはまだ今のようにはリリース直後の柔らかさを身に付けていなかった時期でもありますから。
本当のことを知ったら、もしくは経験されたら彼らもビックリすることになるかと思っています。少なくとも、この10年しかないとした寿命の間は、一気に飲むのではなく、長い時間を掛けて楽しむか、思いっきり開かせる努力をし、ワインのご機嫌が良い時に飲む・・みたいな、ワイン主体の飲み方をされると良いかと思います。
本来はやはり(リリースから)10年経過してから・・ようやく開いてくるワインたちです。勿論ですが、まだ硬い時期にマリアージュで美味しく飲むことは可能です。
この素晴らしいワインを是非、ご堪能いただきたいと思います。
-----
フィネスさんもののディディエ・ダグノーです。(造り手別ページには、違うエージェントさん輸入のダグノーも一緒に掲載されます。ご注意ください。)
2017年のダグノーは、今のところは定番の「ブラン・フュメ」のみのテイスティングですが・・いや~・・ぶっ飛びました!・・近年稀に見る出来栄えです!
と言うよりも、ドメーヌ・ディディエ・ダグノの先代の時代から、始まって以来かもしれないと感じています。
何せ、あの滅茶滑らかなクリスタル風テクスチュアと膨大なミネラリティはそのままに、
「果肉を思わせるかのような柔らかさと起伏」
まで、感じさせてくれるんですね。
そして、超高質なソーヴィニヨン・ブランのアロマティックなアロマに・・ノックアウトされてしまいます。
ところが皆さん・・事件です。ディディエ・ダグノーならではの昔風のA.O.C.(A.O.P.)表記、「ブラン・フュメ・ド・プイィ」が無くなりました。その理由は・・まぁ、裏に貼られているエチケットにも何やら書いてあるようですが・・エージェントさんの資料はこんなようになっています。
2017年は春から日照量が多く暖かかったが、4月末に降りた霜で大きな被害が出てしまった。夏は暑く乾燥したので葡萄の出来自体は素晴らしかったが、霜害の影響で収穫量は約60%減となり、特に被害が甚大だったビュイソンルナールはワイン自体が造れなかった。
ワインの出来は素晴らしく分析上も完璧に近かったが、アペラシオン認証を得るための試飲で揮発酸が多いという指摘を受けた。もちろん分析上はリミットを超えてはおらず問題のない数値だったがそれでも認証が得られなかったので、サンセール以外はAOPを放棄してVindeFrance(ヴァンドフランス)としてリリースすることにした。馬鹿げたルールと固定観念に囚われた一部の人間の偏見はプイィフュメのアペラシオンのレベルを下げると感じ、このような制度に縛られていてはドメーヌのオリジナリティや信念、哲学を表現する本物のワインを造ることは難しいのでAOPから離れる決意をした。
「はぁ?・・揮発酸?・・そんなもん、検出限界でしょ!」
ブラン・フュメからは全くそんなニュアンスは判りませんでした。仲間に揮発酸検知器とまで揶揄される noisy が言うのですから、それを嗅ぎ取ろうと思っても無駄な努力かと思います。
原因は・・
「So2 の量を相当少ない限界まで減らした!」
ことに有ると思っています。
心地良い幅のあるリアルなアロマが「すっ」と立ち昇り、そしてこの肉感的な柔らかさを硬質なミネラリティが物凄い量存在する中から感じさせてくれる訳です。
これは正にSo2の少なさから感じさせる「全くネガティヴな要素の無い」表情です。
2017年のダグノーの、他のキュヴェのテイスティングが非常な楽しみになっています。これは皆さん、ビックリすると思いますよ。リアルで柔らかな表情のダグノー2017年に乾杯!・・恐ろしいほど深い表情を是非ご堪能くださいませ。
 2008年に飛行機事故で早世した故ディディエ氏の跡を継いだ息子のベンジャマン氏は、葡萄の成熟を重視しながらヴィンテージごとの個性やテロワールをしっかり表現するワイン造りを行っています。畑の広さは約12haで土壌と環境を尊重し、父の故ディディエ氏が1989年から続けてきたビオディナミを引き継いでいます。畑の区画によっては馬で耕作を行い、出来る限り機械は使わないような栽培方法が採られています。
2008年に飛行機事故で早世した故ディディエ氏の跡を継いだ息子のベンジャマン氏は、葡萄の成熟を重視しながらヴィンテージごとの個性やテロワールをしっかり表現するワイン造りを行っています。畑の広さは約12haで土壌と環境を尊重し、父の故ディディエ氏が1989年から続けてきたビオディナミを引き継いでいます。畑の区画によっては馬で耕作を行い、出来る限り機械は使わないような栽培方法が採られています。
葡萄は畑で選別作業を行いながら手摘みで収穫されます。醸造所の2階にある除梗機で100%除梗され、1階にある空圧式圧搾機でプレスし、地下のタンクへ葡萄果汁が運ばれます。この間の葡萄の移送はすべて重力によって行われます。そして醗酵前に果汁を冷やし、不純物を取り除くための澱引きを密に行います。樽でのアルコール醗酵には純正培養酵母が使われ、新樽と1~3年樽をそれぞれ25%ずつ使用。樽の種類も特注のシガールと呼ばれる300Lの樽とドゥミムイと呼ばれる600Lの樽を主に使用し、澱に触れる面積の違いによって味わいにも違いが出るようにしています。12ヵ月の醗酵、熟成後にステンレスタンクでアサンブラージュをしてさらに8ヵ月熟成させます。プイィフュメのすべてのワインにおいて同様の醸造が行われているので、各アイテムの違いはテロワールのみになります。





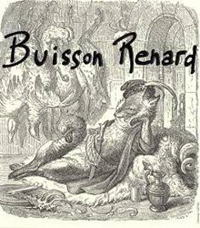




「1アイテムのみ」
です。天候が悪く、畑毎に仕込むことが不可能になり、プイィ=フュメの全てを合わせて「XXI(ヴァン・テ・アン)」をリリースすることにされたんですね。しかも量は超絶に少ないです。
メディアもまた・・全くと言って良いほど、このヴァン・テ・アンの評価を出していませんので、noisy としましても・・まぁ・・どこか、ディディエ・ダグノーとの繋がりをずっと感じていたので、開けさせていただきました。
そうしましたら・・何と十数年ぶりに、
「ディディエに出会った!」
と・・感じました。詳細はコラムをお読みください。
メディアも評価を出していないと書きましたが、Vivino と言うSNS的要素を持ったサイトに書込みが有り、総合的には、
「5ポイント満点で4.3ポイント」
と高い評価が出ています。
また、書かれたコメントも・・面白いのでちょっと訳してみました。
「4.5/5.0。バンジャマン・ダグノーのキュヴェXXI。岩水のように透明な色、信じられないほど複雑な香り、最初はレモン、その後洋梨や白桃、しかしその背景には香水のように、非常にわずかにスモーキーな側面、アーモンド、そして何か塩分、ミネラル。口に含むと非常にストレートで、非常にコントロールされた酸味、余韻の驚くべきミネラル感、そしてクレイジーな長さ!魚のウォーターゾイは、脂ののった料理とバランスのとれた組み合わせです。」
「3.8/5.0.魅力的なワイン。ロワールでは不作だったので、ルイ・バンジャマンはすべての区画をこの区画に結合することで対応しました。フリント、サラブレッドなどなど。純粋な灰と塩、わずかな煙。生理食塩水、牡蠣の殻。奇妙?」
また日本人の方もフィネスさんの試飲会で飲まれて「美味しい」とされ、4.4/5.0 の評価でした。
ですが、飲むタイミングで評価は相当変わると思われますので、ぜひコラムをご確認いただき、どうされるかお考えください。
また、バックヴィンテージのシレックスやピュル=サンなどをいただきましたので、そちらもどうぞよろしくお願いいたします。
-----
ダグノーの2020年をご紹介させていただきます。入荷数は今までの1/2~1/3です。フィネスさんもその辺りを慮って、2019年ものを少し分けてくれましたので一緒にご案内させていただきます。
非常に少ないので飲めたのは「2021エトセトラ」だけでした。ですが・・飲んでおいて良かった・・ベンジャマンが何を考えているのか・・少し理解出来たと思います。因みに本人は以下のように言っていますので・・まずご覧ください。
///
2020年は日照量がとても多く年間通して気温が高く乾燥したので、2018年、2019年に続いて3年連続で暑さに悩まされるヴィンテージとなった。春から早熟傾向で暑い夏は水不足に悩まされたが葡萄はよく耐えてくれて元気に成長した。収穫は9月初めに行ったが、フレッシュさを残すのか、もしくは完熟させるのか、葡萄をどの段階で収穫するかで近所の生産者の間でも収穫日がかなり異なるので各生産者ごとにワインの特性がだいぶ変わるヴィンテージになっている。当家では比較的早めに収穫したので豊かでたっぷりとした味わいながらもフレッシュさは損なわれておらず、口当たりはゆったりとしており素晴らしく長い余韻がある。
///
エトセトラ2020 を飲む限りにおいて、やはりベンジャマンは・・非常なほどに多く内包しているミネラリティの存在での・・ある種の「若い時期における閉じこもりがち」な表情を何とかしよう・・としていて、それを実現して来ていると感じられます。
それは・・「卵型の樽を試験的に使用している」と言うテクニカルからも感じられますが、新型コロナウイルスの蔓延で情報が少ないので、実際にはどのようなことをやっているのかは判りませんが、
「飲んでみればフカフカとしか畑と火打石、石の存在」
を若いうちから感じられるんですね。2020年ものは2019年ものよりも、その傾向は強いんじゃないかと感じました。
また海外メディアでは・・特にヴィノスですが、最近はシレックスよりもピュル・サンの方を高く評価しているんですね・・平気で・・(^^;; まぁ、これが正しいかどうかはかなり微妙では有りますが、ピュル・サンって・・昔から相当美味しいのに何故か皆シレックスに流れてしまう傾向が有りますから、
「ピュル・サンを数週間放置して楽しむ」
そんな飲み方も以前に提案していますので、もし可能でしたらやってみてください。
2020年の太陽の恵みを最大限に活かした造りになっていると思います。是非ご検討くださいませ。
-----
ディディエ・ダグノーの2019年です。いや~・・このところのダグノーは、ミネラリティのマンモス度は以前のままに、柔らかさを毎年、増して来ています。
ですので以前のように、
「・・飲んだけど・・硬くて酸っぱくて・・どこが美味しいの?」
などとガッカリすることは無い・・そのように言えるでしょう。もっとも、
「ちゃんと飲めばその凄さは誰にでも判る」
のも、以前と全く変わりませんが。
しかし、シレックスもピュル・サンもエトセトラも・・これほどまでに外向的に、どんどんにこやかになって来たのには驚かされます。そもそも自然派ですから、畑の柔らかさが感じられるのが普通のはずで・・やっとディテールが出て来た・・のには、
「ベクトル変換」
が出来ている・・んだと思います。
卵型や横長の樽などを使い、ミネラリティをやや内側に配置、表情をやや外側に持って行くことに成功しているんだろうと思います。
その上で、ディディエ・ダグノーらしいスタイルは以前のまま・・ですから、
「毎年、より美味しさを感じやすくなって来ている!」
と言えます。
あ、バビロン・セック2017年だけは・・いまちょっと硬いです・・。これは様子を見ながら・・果実感の成長を待ちましょう!・・素晴らしいブラン・フュメ・ド・プイィです。すみません、2019年のサン=セールは数が少な過ぎて割り当てが有りませんでした。
-----
2018年ものを中心に入って来ましたディディエ・ダグノーです。このところベンジャマンが造り出すワインは、以前のような「クリスタルの殻」に閉じこめられたかのような、テッカテカで滑らかなテクスチュアは本当に素晴らしいけれど、熟すのに時間が相当掛かる・・と嘆くようなものから脱出、やはりベクトル変換をしたかのような・・それでもミネラリティの総量は以前と全く変わらない・・各要素を外向きに、得やすくなったような「柔らかさ」も身に着けています。
2018年もののブラン・フュメ各種の出来は見事なものでした。ただミネラリティだけが目立つのではなく、おそらく2015年頃までのものが見せたクリスタルの塊が持つような硬さを、かなり細かく砕いたようなイメージで、様々な表情が出現しやすくなっています。
例えばあの「シレックス2018」は、それこそ抜栓直後は硬さを見せるものの、3~4日で官能的な柑橘フルーツのアロマをポンポンと振りまき、味わいも膨らみも、
「美味しく飲める!」
と感動するようなタイミングが有ります。そして、また数週間掛けて収縮と膨張を繰り返しながら徐々に全開放に向かってくれます。
これはもうとても感動的です。タイミング良くNoisy wine にご来店された方は、ドライバーの方は除き、テイスティング出来ましたので・・もうグラスをいつまでも離せないような状況になってしまいました。それほどまでに感動的なアロマが店内の空気を彩っていました。申し訳なかったのはドライバーさんで・・香りは嗅げどその本体には触れられない・・と言うお預けを喰ってしまった訳です。
今回はバックヴィンテージ、サンセールを除き全アイテムのテイスティングをさせていただきました。上記のシレックスの振る舞いは、他のロワールのキュヴェも同様です。
また、バビロンのセック、モワルー2016も飲ませていただきました。いや・・
「激旨!」
です。セックの美味しさもさることながら、モワルーの美味しさには感動しました。
まぁ、ワインファンは迂闊にも甘さの有るワインへの恐怖?畏怖?みたいなものを持っているようですが、これ、飲んだらそんなものはすっ飛んでしまう事、請け合いです。
また、ダグノーのシレックスは、海外メディアは良いところ、94ポイント止まりです。アドヴォケイトは2018年ものシレックスを93ポイントと評価しているようです。
しかし、以下の評価を見ていただければお判りになるかと思いますが、残念ながら彼らはダグノーのワインをちゃんと理解は出来ていないと思います。
2015 Blanc Fume de Pouilly Silex Domaine Didier Dagueneau
94 Points 2018-2025 / Andrew Jefford Decanter.com January 2018
17.5/20 Points 2017-2027 / Richard Hemming MW JancisRobinson.com July 2017
デカンター誌は94ポイントとまぁまぁ・・では有りますが、飲み頃を2018年から2025年としていますし、ジャンシス・ロビンソン・コムでは17.5ポイントで2017~2027年と、直近の10年間の飲み頃予想です。
言わずともお判りいただけるかと思いますが、この期間に美味しく飲める幸せな時間を得られる人が、本当にいるとしたら・・それは奇跡でしか有りません。特に2015年ものはまだ今のようにはリリース直後の柔らかさを身に付けていなかった時期でもありますから。
本当のことを知ったら、もしくは経験されたら彼らもビックリすることになるかと思っています。少なくとも、この10年しかないとした寿命の間は、一気に飲むのではなく、長い時間を掛けて楽しむか、思いっきり開かせる努力をし、ワインのご機嫌が良い時に飲む・・みたいな、ワイン主体の飲み方をされると良いかと思います。
本来はやはり(リリースから)10年経過してから・・ようやく開いてくるワインたちです。勿論ですが、まだ硬い時期にマリアージュで美味しく飲むことは可能です。
この素晴らしいワインを是非、ご堪能いただきたいと思います。
-----
フィネスさんもののディディエ・ダグノーです。(造り手別ページには、違うエージェントさん輸入のダグノーも一緒に掲載されます。ご注意ください。)
2017年のダグノーは、今のところは定番の「ブラン・フュメ」のみのテイスティングですが・・いや~・・ぶっ飛びました!・・近年稀に見る出来栄えです!
と言うよりも、ドメーヌ・ディディエ・ダグノの先代の時代から、始まって以来かもしれないと感じています。
何せ、あの滅茶滑らかなクリスタル風テクスチュアと膨大なミネラリティはそのままに、
「果肉を思わせるかのような柔らかさと起伏」
まで、感じさせてくれるんですね。
そして、超高質なソーヴィニヨン・ブランのアロマティックなアロマに・・ノックアウトされてしまいます。
ところが皆さん・・事件です。ディディエ・ダグノーならではの昔風のA.O.C.(A.O.P.)表記、「ブラン・フュメ・ド・プイィ」が無くなりました。その理由は・・まぁ、裏に貼られているエチケットにも何やら書いてあるようですが・・エージェントさんの資料はこんなようになっています。
2017年は春から日照量が多く暖かかったが、4月末に降りた霜で大きな被害が出てしまった。夏は暑く乾燥したので葡萄の出来自体は素晴らしかったが、霜害の影響で収穫量は約60%減となり、特に被害が甚大だったビュイソンルナールはワイン自体が造れなかった。
ワインの出来は素晴らしく分析上も完璧に近かったが、アペラシオン認証を得るための試飲で揮発酸が多いという指摘を受けた。もちろん分析上はリミットを超えてはおらず問題のない数値だったがそれでも認証が得られなかったので、サンセール以外はAOPを放棄してVindeFrance(ヴァンドフランス)としてリリースすることにした。馬鹿げたルールと固定観念に囚われた一部の人間の偏見はプイィフュメのアペラシオンのレベルを下げると感じ、このような制度に縛られていてはドメーヌのオリジナリティや信念、哲学を表現する本物のワインを造ることは難しいのでAOPから離れる決意をした。
「はぁ?・・揮発酸?・・そんなもん、検出限界でしょ!」
ブラン・フュメからは全くそんなニュアンスは判りませんでした。仲間に揮発酸検知器とまで揶揄される noisy が言うのですから、それを嗅ぎ取ろうと思っても無駄な努力かと思います。
原因は・・
「So2 の量を相当少ない限界まで減らした!」
ことに有ると思っています。
心地良い幅のあるリアルなアロマが「すっ」と立ち昇り、そしてこの肉感的な柔らかさを硬質なミネラリティが物凄い量存在する中から感じさせてくれる訳です。
これは正にSo2の少なさから感じさせる「全くネガティヴな要素の無い」表情です。
2017年のダグノーの、他のキュヴェのテイスティングが非常な楽しみになっています。これは皆さん、ビックリすると思いますよ。リアルで柔らかな表情のダグノー2017年に乾杯!・・恐ろしいほど深い表情を是非ご堪能くださいませ。
 2008年に飛行機事故で早世した故ディディエ氏の跡を継いだ息子のベンジャマン氏は、葡萄の成熟を重視しながらヴィンテージごとの個性やテロワールをしっかり表現するワイン造りを行っています。畑の広さは約12haで土壌と環境を尊重し、父の故ディディエ氏が1989年から続けてきたビオディナミを引き継いでいます。畑の区画によっては馬で耕作を行い、出来る限り機械は使わないような栽培方法が採られています。
2008年に飛行機事故で早世した故ディディエ氏の跡を継いだ息子のベンジャマン氏は、葡萄の成熟を重視しながらヴィンテージごとの個性やテロワールをしっかり表現するワイン造りを行っています。畑の広さは約12haで土壌と環境を尊重し、父の故ディディエ氏が1989年から続けてきたビオディナミを引き継いでいます。畑の区画によっては馬で耕作を行い、出来る限り機械は使わないような栽培方法が採られています。葡萄は畑で選別作業を行いながら手摘みで収穫されます。醸造所の2階にある除梗機で100%除梗され、1階にある空圧式圧搾機でプレスし、地下のタンクへ葡萄果汁が運ばれます。この間の葡萄の移送はすべて重力によって行われます。そして醗酵前に果汁を冷やし、不純物を取り除くための澱引きを密に行います。樽でのアルコール醗酵には純正培養酵母が使われ、新樽と1~3年樽をそれぞれ25%ずつ使用。樽の種類も特注のシガールと呼ばれる300Lの樽とドゥミムイと呼ばれる600Lの樽を主に使用し、澱に触れる面積の違いによって味わいにも違いが出るようにしています。12ヵ月の醗酵、熟成後にステンレスタンクでアサンブラージュをしてさらに8ヵ月熟成させます。プイィフュメのすべてのワインにおいて同様の醸造が行われているので、各アイテムの違いはテロワールのみになります。





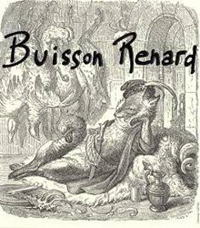




●
2019 Jurancon les Jardins de Babylone Sec
ジュランソン・レ・ジャルダン・ド・バビロン・セック
【これは・・柑橘を「これでもか!」と凝縮させて詰め込みつつ・・それが全く外に出て来ていない、ある意味本当に化け物状態。今開けてはいけません。】-----以前のレヴューを掲載しています。
 凄いですね~・・そう、ある意味・・ディディエ・ダグノーは・・こうでした。勿論その頃は「セック」は造って無かったと思いますが、
凄いですね~・・そう、ある意味・・ディディエ・ダグノーは・・こうでした。勿論その頃は「セック」は造って無かったと思いますが、「要素をこれでもか!と詰め込んで、でもほとんど何も外には放出しないワイン」
それがディディエ・ダグノーのワインだった・・そう理解していました。初めての出会いは1990年代でしたが、
「ディディエ・ダギュノー...って知ってますか?」
と、あるエージェントさんからご紹介いただいたのがファーストコンタクトでした。
そう・・ダギュノーって言ってたと思いますが、noisy は勝手に「ダグノー」と読んでいましたら、そのうち世の中がダグノーと呼ぶようになっていました。ルジェもそうでしたよ。昔は結構に、
「エマニエル・ルージュ」
なんて呼ばれていました。それはなんか違う・・と思って、「エマニュエル・ルジェ」と書いてネットで販売していましたら、いつの間にか・・そう呼ばれるようになっていました。最近はそのようなことは余り無くなって・・noisy的な読み方がされることもなく、ただnoisy のところだけがそう呼んでいる・・たとえば、「オーセ=デュレッス」とか・・(^^;;
で、この2017年のバビロン・セックですが・・これはもう・・
「・・絶対に勘違いされる状態!」
だと・・・思います。
 もう・・ドライフルーツを滅茶苦茶一杯にガラス器に詰め込んであるものの・・
もう・・ドライフルーツを滅茶苦茶一杯にガラス器に詰め込んであるものの・・「そのフタを開けた時の凄い匂いのする状態!」
に近いんじゃないか・・と思います。
そしてその状態から、ちょっとやそっとじゃ変わって行かない・・(^^;;
ですから、これは2~3年・・そのままにしておくべきだと思います。どうしても飲むなら、飲む2~3日前に平底デキャンタに落としておくとか、相当工夫をしないと本性にはたどり着けないかと思います。
ですが、ポテンシャルは呆れるほど高いと思いました・・ので、この相当な匂いのドライフルーツが、やがて柑橘+ドライフルーツに変化して行くまで、なんとかそだて上げて欲しいと思います。
しかもこのセック...何故か価格がリーズナブルになっているんですよ・・。間違ってないのか、ちょっと心配になりますが・・まぁ大丈夫でしょう。是非ご検討くださいませ。
以下は以前のレヴューです。
-----
【激旨!分厚いボディから漏れ出る柑橘のピュアさ!感動的です!】
 ようやく飲めました!・・そもそも何本も入荷しないので、テイスティングするのは難しいワインなんですね・・ダグノーのキュヴェで未だに飲めていないのは「サンセール」です・・。比較的最近リリースしたのがサンセールですので、まだ皆さんも飲めていない=人気が高いと言うことで、引く手が非常に多いです。
ようやく飲めました!・・そもそも何本も入荷しないので、テイスティングするのは難しいワインなんですね・・ダグノーのキュヴェで未だに飲めていないのは「サンセール」です・・。比較的最近リリースしたのがサンセールですので、まだ皆さんも飲めていない=人気が高いと言うことで、引く手が非常に多いです。こちらはジュランソンの古代品種を用いて造られた「ドライな方」です。少し前までは「ドゥミ・セック」だったように思いますが、最近は・・こんな感じだと思いますよ。
「ジュランソン・モワルー」
昔:やや甘口
今:僅かな甘口
「ジュランソン・セック & ドゥミ・セック」
昔:僅かな甘口
今:辛口
なので、ほぼ残糖を感じないのがこちらです。
しかしながら・・滅茶苦茶複雑な味わいです。中域のボディも結構に分厚いです。そして余韻も滅茶長い・・。
そもそもここジュランソンはピレネー山脈の丘に有りまして、そもそも・・ピレネー山脈は、
「アルプス山脈よりも地層が古い!」
と言われています。
WIKIペディアによりますと、
古生代から中生代にかけて海底の比較的浅い場所に堆積してできた地層が、特に古第三紀始新世頃の大陸移動に伴う圧力の影響を受けて隆起や褶曲を起こしたことによって、ピレネー山脈の原型が形成されたと考えられている。その後、降雨や流水などによる侵食などの影響などを受けて、現在のピレネー山脈の形状になったとされる。こうしてできた現在のピレネー山脈の山体を構成する主な岩石は花崗岩であるものの、山脈の西部の周辺部には石灰岩なども見られる。
と言うことになってますので、
「古生代から・・と言うことになれば、ブルゴーニュ等が中生代とするなら、もっと以前に隆起してできた?」
とも言える訳ですね。
それに加え・・「アルプス・ヒマラヤ造山帯」に属していますので、西は大西洋からジュランソンを通り、ヒマラヤを通り抜けマレー半島まで・・と言う、地球を半周してしまうような大きな造山帯に存在している訳です。
ですが、プティ・クルブ種、グロ・クルブ種、グロ・マンサン種、カラマレ種、ローゼ種 と言われましても・・まぁ、「マンサン種」位は何とか知っているとしても、
「その特徴は?」
などとはまるで言葉にできない・・むしろ、昔からの「安ワイン」でしかイメージが沸かず、結局は、
「ダグノーのジュランソンは別物!」
と言うしかない訳です。
しかしながら、それでも仕上がったバビロンは一般的なシャルドネよりも構造が大きく、重心は低く、超高域の伸びやかさまではシャルドネに及ばない・・みたいなイメージですが、ブルゴーニュのシャルドネとは比較するのが難しいほど複雑性に富んでいるのも事実だと感じます。そして、ダグノーのワインに共通された「洗練性」が有りますので、
「うわ~・・凄い・・」
と思ってしまうのでしょう。
モワルーも美味しいんですが、流石に価格がね・・ヤバイです。太い柑橘のアロマと重心の低い味わい、是非お楽しみくださいませ!
以下は以前のレヴューです。
-----
【コンディションは非常に重要です!】--以前のレヴューを使用しています。
時折友人たちと集まってワイン会・・と言うよりは完全な飲み会ですが、ワインを持ち寄って「あ~でもない、こ~でもない、そ~に決まっている」とぎゃぁぎゃぁ・・うるさくやったりしているnoisyです。
この間・・結構前では有りますが、「とってもコンディションの良いディディエ・ダグノー」と、「とってもコンディションの良く無いディディエ・ダグノー」をお持ちになってくださった方がいらっしゃいました。彼女も、おそらく「とってもコンディションの良く無いディディエ・ダグノー」が見るからに・・いや、液体の色を見るにつけ、
「これはコンディションが悪いんじゃないかな~・・」
と感じていたようで、
「2本とも駄目だったらどうしよう・・」
と、ワイン会参加者ならではの恐怖にもにた切迫感みたいなものに囚われていたように思います。
まぁ、色合いを見つつエチケットのヴィンテージや輸入者シールを確認すると、
「あぁ・・輸入がxxxxxxか・・。問題はここかな」
とか、
「輸入がxxxxで販売店がeeeeeか・・。店の管理が悪いな・・」
とかがある程度判ってしまうわけですね。
その上で飲んでみると、まぁ、酔っ払っていない限りは、物流の問題なのか、管理の問題なのか、店かエージェントか造り手か・・などは、ほぼ完全に理解できる訳です。もちろんですがワイン屋ですから、皆さんの知らない情報・・特に余り外にはおおっぴらに出来ないような情報も知っていたりしますから、その総合判断は有る程度の確実性を持っているかなと思うんですね。
勿論、皆さんの中にはプロ顔負けの実力をお持ちの方も大勢いらっしゃいますし、我々よりも情報網も行動力もお持ちの方もいらっしゃいますから、決してプロじゃないから・・などと偉そうなことは申しません・・。まして、ワインを楽しむということは、その人が楽しければ良いわけですから、その楽しみの中には修行にも似た辛い時間も含まれるわけで、先の彼女も、
「2本とも駄目だったら・・」
等と言うような圧迫感でさえ、ある種の楽しみに切り替えることが出来るのがワインを飲むことによって生まれますからね。
で、思ったとおり、少々「重い・・暗い・・鉛のような色合いを含むとってもコンディションの良く無いディディエ・ダグノー」はやっぱり全然駄目で、しかし一方の「突き抜けたような照りを含むとってもコンディションの良いディディエ・ダグノー」の、全てを許容してくれるような感動的な味わいが、駄目なダグノーをも、「コンディションの大切さ」とか、「どこがどうゆう風に駄目だと駄目なのか」とかを教えてくれる良い教材としてくれちゃう訳ですね。
案の定、「とっても状態の良く無いディディエ・ダグノー」は、全く温度管理など出来ない悪名高きコンビニエンス・ストアの造りのショップで購入された棚曝しの熱劣化ワインだった訳で、自然派ワインを平気で温度管理の無い場所におくことができるショップの姿勢がそうさせたということなのでしょう。
今回のディディエ・ダグノーは、フィネスさんから分けていただいた貴重なアイテムです。コンディションは非常に良いように見えます。ただし、サン=セールのエチケットは手で貼る時に少し失敗したようです。ご了承ください。
ダグノーの看板ワインである「シレックス」ですが、2013年を送ると連絡が有ったものの来たのは2012年でした。なので、2012年は以前にご案内していますのでご注意くださいね。「同じものを仕入れてコンディション比較」・・なんて言うシビアな企画のワイン会・・も良いかもしれません・・(^^;;まぁ、飲み頃は凄い先になるかと思いますが、1カ月間、2~3日置きに30mlずつ楽しむ・・なんていうことが平気で出来ちゃうのがディディエ・ダグノーのマンモス・ミネラリティの魅力でも有ります。30日経ったって、全然崩れないですからね・・香りも凄いです。どんどん柑橘が出て来ますよ。是非ビックリしていただきたいものです。
ピュル・サン の畑はシレックスより小粒の火打石に覆われていますので、より判りやすいかと思いますが・・これで充分旨いんですよね~・・noisyは大好きです。こちらは2011年です。
普通のブラン・フュメはずっと以前「アン・シャイユー」の名でリリースされていたブレンドものです。これでも・・普通に・・最高に旨いです。しかしながら、直近の状態しか見えない方々には、
「・・・すっぱいだけ」
などとブログに書かれてしまうでしょう。ワインを味わうには想像力が不可欠です。結果だけを見て、今までの経験を繋ぎ合わせる努力をしないと想像力はたくましくなりません。もし飲まれるならやはり4週間掛けて少しずつ飲みましょう。・・もしくはデキャンタに落として2週間、毎晩栓を抜いてグルグル回して・・また栓をしてください。2週間後には少し開いてくるかと思います。
サンセール・ル・モン・ダネ・シャヴィニョール はディディエが開墾したサンセールの銘醸畑です。まだ樹齢が若いそうですが評判は高いようです。実はnoisyは飲んだことが無いです。非常にレアです。担当のK君は余り気に入ってないようです。エチケットにはヨレが有ります。ご了承願います。
ジュランソン・レ・ジャルダン・ド・バビロン は、これも最近出し始めたセックで辛口(・・余り甘く無い・・と言う意味)です。モワルーでは無いのでご注意くださいね・・辛口の方です。これもまだレアです。
そんな訳でフィネスさんもののディディエ・ダグノーです。いろんな意味で・・面白いアイテムかと思います。決して今までご紹介させていただいたディディエ・ダグノー(一応正規です)もコンディションは良いですが、さて・・どんなことになりますか、楽しみでも有ります。ご検討くださいませ。
以下は以前のコメントを使用しています。
━━━━━
【2009年からはベンジャマンの仕上げたヴィンテージ!!見事にディディエ・ダグノーを継承しました!素晴らしいブラン・フュメ・ド・プイィ!】
元々はディディエの補佐をしていましたので、ベンジャマンになったからと言って大きく変わることは無いだろうと・・は思っていましたが、それでも一応のチェックをしなくては・・と云う気持ちを抑えられずに、ベースのブラン・フュメ・ド・プイィを飲んでみました。そして・・安心しました。・・そう、何も変っていないと。あの、ガラスのような、石英のような厚みのある透明なミネラルの風味に、奥底から徐々に沸いてくる白、黄色の果実。酸度のレベルの高さとグリップの強さ、余韻の長さなど、いつものディディエ・ダグノーの味わいです。
どこかのコラムに書かせていただいたはずですが、人間は脳の5~10%しか使用しておらず、記憶は一体どこに仕舞って有るんだろう・・・noisyは、ちょっとその辺に置いておき、時折取りに行っているように思う・・と。大体、年間途轍もない本数を20年もテイスティングしておいて、そんな記憶を・・忘れてしまっている部分が有るにせよ、自分の内部に留めておけるはずが、いや、自信が無い・・みたいなことでした。
先だって斜め読みしたある本には、衝撃的な内容が書かれていました。ケンブリッジ大学の2年生だか3年生のとても数学が優秀で運動も得意な方が、ラグビーの試合中、頭を蹴られて脳震盪を起こし、病院に搬送されたそうです。そこで彼はビックリするような事実を知ります。何とCTスキャンの結果、彼には脳がほぼ無いことが判明したんです・・実際には5~10%ほど、隅っこに脳組織と思われるものが有ったんですが、その他の部分には骨髄液が満たされた状態だったそうです!彼は、自分が脳を持たないことにショックを受けていたそうですが、トップクラスの優秀な学生であり、しかもスポーツも万能だそうで、普通以上に普通に生活している・・・そんな内容でした。
noisy のお客様にはお医者様も多くいらっしゃいますし、学者の方も沢山・・いらっしゃいます。上記は本に書かれていた事実では有りますが、内容が事実かどうかは確かめようが有りません。でも、現代の常識が、全て正しいとは思えませんし、
「そんなバカな話しにつきあってられね~・・」
と思われる方もいらっしゃるでしょう。でも、脳が一部、場合に寄っては半分以上欠損していても、普通に生活してらっしゃる方も多く存在するようですし、少なくともそれは事実です。脳が損傷を受けると、脳内の出血がその人の生命に大きな危機をもたらすかもしれませんが、それらを含めて脳が記憶の全てを担っていることの証明にはなっていないように思います。
だからと言って、noisy が思いついたように、
「記憶は中空の・・その辺りに置いてあって・・」
とは、とても言えないかもしれませんが、考える以上に突飛過ぎてはいないかもしれないとも・・感じています。
良く、仲間や連れ合い、子供さんを亡くされても、
「何故かいつもそばにいるような気がする」
とか、
「彼の声が聞こえるんだよ」
等に始まり、
「自分の知らない記憶が突然現れてきた」
なんてことも有るようです。
だから、もしかすると、脳は記憶を実際に持っているんじゃなくて、記憶にアクセスする方法を知っているだけなんじゃないかと・・思っちゃったんですね。でももしそうだとするなら、ベンジャミンもディディエの記憶にアクセスできない訳では無いとも考えられます。受け取る気持ちが強く有る人と渡したい気持ちが強く有った人同士なのでしょう。
まあ、確かにトンデモ話では有りますが、限りのある脳細胞の10%で覚えられる情報はたかが知れているんです。それは間違い無いでしょう。そして仲の良かった父、ディディエと、ディディエの記憶と一緒に、ベンジャミンも素晴らしいブラン・フュメ・ド・プイィを造っているのかもしれません。でもまあ、御伽噺として聞いてくださいね。
「・・・証明しろ!」
などとは決して迫ってこないように・・お願いします・・(^^
2009年のブラン・フュメ・ド・プイィはアドヴォケイト(91~92+)です。noisyもほぼ同様に思いますが、飲み頃予測の2010~2018には・・とてもじゃないが賛同できませんね。早くて2015からです。それでも飲めないことは無いですが、何日も何週間も掛けて楽しんだほうが良いでしょう。2015年から2030年頃まで持つワインです。
その他のワインは飲んでいませんが、2009年のピュル・サンはアドヴォケイト(92~93+)とぶっ飛びの評価、飲み頃予測2010~2020とこれまた間違った評価です。ポイントは信頼できますが飲み頃予測はでたらめです。ビュイッソン・ルナールも(92~93+)でマチュリティは書いてないです。かのシレックス2009年はさすがに(93~94+)・・・。飲み頃は2010~2022だそうです・・・これも無いです。ダヴィッドさんはよっぽど硬くて若いワインがお好きなんでしょう。
そして、昨今造りはじめた実に秀逸、且つ希少なサンセールは・・・すみません・・・1本だけしか入らなかったので、申し訳ないけれどセットを組ませていただきました。売れなければnoisy用です!・・・だって、noisyだって飲んだ事無いんですよ・・!畑名も入ったし、デザインも変ったし・・。
そんな訳で、ディディエの後継者は、彼の遺志をしっかりと受け継いだようです。是非・・ご検討くださいね。お奨めします!
以前のコラムより転載です。
━━━━━
【すぐに飲むなら実験的に!】
はっきり言って、物凄いワインです。ボーヌの偉大なシャルドネと同列に語られるべき・・・です。しかし、購入してすぐそれを確かめようとしても、ほとんどの方が理解出来ないと思います。最低10年は置くべきワインですので、もし飲まれるのであれば・・・2週間掛けて毎日一口ずつお楽しみください。そして、
「美味しくなってきたかな?」
と思ったら少し多めに飲み、
「・・・・何か、全く何も出てこない・・・」
と思われたら、その日は諦めましょう。抜栓してもコルクを逆ざししたまま1カ月は平気で持ちます。(もちろんセラーに入れてくださいね)半端なポテンシャルじゃあ無いことを肝に銘じておきましょう。有名なワインですので時折、ブログでも取り上げているようで、中には否定的な見方の方もいらっしゃいますが、それはそれ、本当はどうなのかは、自身で確かめると良くわかると思います。
なお、正規の取り扱いなのかそうでないのか良く判りませんので、一応非正規、とさせていただきますが、状態は万全だと思います。少なくて飲めませんので、以下に以前のレヴューを掲載しておきます。よろしくお願いいたします。是非ご検討ください!
ここから2004年の時の文章です━━━━━
【何というアロマ!何というべき長熟さ!絶句です!】
ロワール上流のサンセール対岸、プイィ・フュメに凄い奴がいました。その名も「ディディエ・ダグノー」。 皆さんもおそらくご存知でしょう。
今回は正規品のご案内ですが、さすがにこの世界情勢の中でやや値上がりしてしまいました。トップ・キュヴェのシレックスは大台を超えてしまいましたね。
で、早速飲んでみました。結果2004年のディディエ・ダグノーは...
「べらぼうな出来!」
と、安易に断言してしまいましょう。
飲んだのはシャイユーの後継と目される「音符のエチケット」のブラン・フュメ・ド・プイィとピュール・サンです。細かな部分は後に掲載しますが、溢れんばかりの軽量なマンモス・ミネラルと素晴らしいバランスを持った巨大な酸。まるで眠りから目覚めるように、まどろみながら、のんびりのんびり巨大化してゆきます。何メーターか離れていても、メロンやレモンのアロマが飛び込んできます。さらには「酸っぱい」とさえ感じられる酸ですが、まことに美しい輪郭を持っていますので、長熟さをアピールしています。
もっとも、勘違いして欲しくないんですが、今の状態で、
「美味しい!」
と感じられる方は少数派でしょう。3~5年ほど置いた状態からでしたら、その数は過半数ほどに達すると思いますし、10年置けば大多数になるでしょう。
もし、ディディエの2004年を早い段階で抜栓されるのであれば、そのアロマの複雑さと量、酸と構成の巨大さを確認していただき、もし、好みではないな、とか、美味しいと感じられないとしても、
「ん?これから先が楽しみなワインだ、と考えるべきなのかな?」
と、理解して欲しいと思います。本当の姿が現れるのは..10年くらい掛かりそうです..
● 2004 ブラン・フュメ・ド・プイィ
音符のエチケットだったので、ミュージシャン崩れの noisy としましては、しっかり頭の中で音符の音を鳴らして見ました..。そしたらまあ、なんと..音楽をかじった方なら判ると思いますが、重なるほとんどの音が半音違いで「不協和音」なんですね~♪♪..で、ほんの何箇所かが3度か5度違いの和音という音符..で、結局最後の1度と5度の和音で丸く収めるという曲でした。音楽的には、
「何もない..」
という結論です。(そんなところはどうでも良い、という声が聞こえてきますが..)
味わいは、ピュール・サンに比較すれば、珪藻土系のミネラルに石灰が混じり、やや黄緑のイメージが拡がって行きます。飲み頃はやっぱり先で2~4年後からでしょう。飲み方は、最初1杯だけ味見をして、その後はデキャンタすることをお奨めします。栓をしたまま2週間置いても全く落ちないと思いますよ。
● 2004 ピュール・サン
ものすごいミネラルと酸、エキスの塊りでした。2週間近く経っても、アロマは生き生きとしています。酸の美しさは、やはりセロスやコシュ=デュリを思い出します。酸の性格が似ているのはコシュ=デュリでしょうか..素晴らしいソーヴィニヨン・ブランだと思いますが、今の状態で美味しいと言える人..それはプロですね。飲み頃は3~5年経ってからでしょう。
● 2004 シレックス
飲んでいないので判りませんが、ピュール・サンの出来から想像するに、トップ・キュヴェのシレックスは最低でも5年以上置いたほうが良いでしょう。量は少ないです。
● 2004 ビュイッソン・ルナール
実を言うと、このビュイッソン・ルナールは一番少ないです。裏ラベルには名前の由来が書いてありますので、お暇でしたら読んでみてください。ノー・テイスティングです。
●
2020 Buisson Renard Vin Blanc
ビュイッソン・ルナール・ヴァン・ブラン
【非常に細やかな、肌理の細かいシレックスと軽い粘土・・超繊細系です。2018年は滅茶ドライ!】---以前のヴィンテージのレヴューを掲載しています!
 シレックスのシレックスが塊なら、ビュイソン・ルナールはその塊は粉々になっている・・もしくはシレックスはクラスターでビュイソン・ルナールは「さざれ石」的なイメージです。
シレックスのシレックスが塊なら、ビュイソン・ルナールはその塊は粉々になっている・・もしくはシレックスはクラスターでビュイソン・ルナールは「さざれ石」的なイメージです。そしてピュル・サンの粘土は湿って少し重量感が有り、ビュイソン・ルナールはやや乾いていて軽めです。まぁ・・あくまでもイメージですが、2018年ものを飲んでようやくnoisy も、ビュイソン・ルナールのイメージを自分なりに確定できたかな?・・と思っています。
どちらかと言うと僅かな甘みを感じることの多かったビュイソン・ルナールですが、2018年ものは超ドライでピュアです。勿論、ミネラリティはマンモス級、テクスチュアは「てっかてか・つっやつや」と言うよりも「やや起伏の有るもの」で、これまた「さざれ石」を舐めているような?・・イメージですね。
そして思った以上に「白っぽい」感じです。実際の色合いは結構に黄色・・と言うか、土壌の色合いを拾っているのかな?・・と言うようなイメージです。
柑橘系のフレーヴァーには、北で採れる冷ややか系のものが主ですが、飲み進めるにつれ、やや南の方のこってりした柑橘も出て来ます。ややビターな余韻がまた・・リアルフルーツを感じさせてくれますし、徐々に「甘み」を連想?・・脳内で合成されてしまうのか、実際には「超ドライ」なのに「甘み」までも感じさせてくれます。
ハードなシレックス、繊細なビュイソン・ルナール・・・と覚えてください。美味しいです!是非飲んでみて下さいね。飲み方は・・
「硬かったらそのまま栓を逆刺しして翌日以降に回し、後日開いて来たと思ったらボトルアップまで飲む!」
で宜しいんじゃないでしょうか。ご検討くださいませ。
以下は以前のレヴューです。
-----
【写真が見当たりませんで・・すみません・・2015年ものを開けたんですが・・2016年ものは、なんとマグナムも有ります!】
甘みもへったくれも無い、超絶にドライなシレックスとピュル・サン、そしてベースのブラン・フュメに比較すれば、僅かに残糖感のある甘みをも感じさせてくれる、やや官能さをリリース時から持っているのがこの「ビュイッソン・ルナール」です。写真が無いのが残念ですが、2016年ものもまったく2015年に劣らない仕上がりかと思います。
海外的な評価は、以前のレヴューにも出ていますが、1.シレックス、2.ビュイッソン・ルナール、3.ピュル・サン と言う、価格通りのものですが、どうなんでしょう・・・このビュイッソン・ルナールは、単純にそう言う列で言ってしまうと、それしか経験の無い方には勘違いさせてしまうかと思います。
シャンパーニュで言えば、エクストラ・ブリュットがシレックスやその他で有って、ビュイッソン・ルナールはブリュットで有ると・・言うような理解で良いかもしれません。
ほんのりとした葡萄由来の心地良い甘みがベースに残った味わいですから、若くして飲んでも美味しいですよ。熟成させると物凄く変わると思います。是非飲んでみてください。お勧めです!
以下は以前のレヴューです。
━━━━━
【入荷数量の少ないビュイッソン・ルナールです!】
すみませんが、こちらは飲めていません。シレックスと言うのはご存知かと思いますが「火打ち石」のことですね。ダグノーのシレックスは、まさにシレックスだらけですが、他のキュヴェもかなりなシレックスは存在しています。でも、プイィ=フュメ イコール シレックス土壌 と言う図式は当てはまりませんのでご注意くださいね。
このビュイッソン・ルナールは粘土土壌に大き目のシレックスが散らばるような畑だそうです。大き目のシレックスが日中の熱量を夜間の粘土土壌に加えているような感じなのかな?と想像しますが、ピュル・サンやシレックスに比較すると良く熟した葡萄が供給されるようで、ほんのりとした甘味を感じる場合が多いようです。ピュル・サンやシレックスは完全にドライですけど。
ダグノーの2014年ものは3アイテムの試飲から非常に良い仕上がりだと思います。現地の評価機関の評価を見てみると、シレックスが19/20、ビュイッソン・ルナールが18/20~18.5/20、ピュル・サン17/20~18/20位のようですね。まぁ、ラ・ルヴェ・デュ・ヴァンにしてもベタンヌにしても結構ばらつきますが、ほぼ当たっていると思います。でもポテンシャル点を付けるとするとどうなんでしょうね・・もう少し上値を見た方が良いかな・・と言う気もします。
今回は2本のみです。是非ご検討くださいませ。
●
2020 Buisson Renard Vin Blanc Magnum
ビュイッソン・ルナール・ヴァン・ブラン・マグナム
【非常に細やかな、肌理の細かいシレックスと軽い粘土・・超繊細系です。2018年は滅茶ドライ!】---以前のヴィンテージのレヴューを掲載しています!
 シレックスのシレックスが塊なら、ビュイソン・ルナールはその塊は粉々になっている・・もしくはシレックスはクラスターでビュイソン・ルナールは「さざれ石」的なイメージです。
シレックスのシレックスが塊なら、ビュイソン・ルナールはその塊は粉々になっている・・もしくはシレックスはクラスターでビュイソン・ルナールは「さざれ石」的なイメージです。そしてピュル・サンの粘土は湿って少し重量感が有り、ビュイソン・ルナールはやや乾いていて軽めです。まぁ・・あくまでもイメージですが、2018年ものを飲んでようやくnoisy も、ビュイソン・ルナールのイメージを自分なりに確定できたかな?・・と思っています。
どちらかと言うと僅かな甘みを感じることの多かったビュイソン・ルナールですが、2018年ものは超ドライでピュアです。勿論、ミネラリティはマンモス級、テクスチュアは「てっかてか・つっやつや」と言うよりも「やや起伏の有るもの」で、これまた「さざれ石」を舐めているような?・・イメージですね。
そして思った以上に「白っぽい」感じです。実際の色合いは結構に黄色・・と言うか、土壌の色合いを拾っているのかな?・・と言うようなイメージです。
柑橘系のフレーヴァーには、北で採れる冷ややか系のものが主ですが、飲み進めるにつれ、やや南の方のこってりした柑橘も出て来ます。ややビターな余韻がまた・・リアルフルーツを感じさせてくれますし、徐々に「甘み」を連想?・・脳内で合成されてしまうのか、実際には「超ドライ」なのに「甘み」までも感じさせてくれます。
ハードなシレックス、繊細なビュイソン・ルナール・・・と覚えてください。美味しいです!是非飲んでみて下さいね。飲み方は・・
「硬かったらそのまま栓を逆刺しして翌日以降に回し、後日開いて来たと思ったらボトルアップまで飲む!」
で宜しいんじゃないでしょうか。ご検討くださいませ。
以下は以前のレヴューです。
-----
【写真が見当たりませんで・・すみません・・2015年ものを開けたんですが・・2016年ものは、なんとマグナムも有ります!】
甘みもへったくれも無い、超絶にドライなシレックスとピュル・サン、そしてベースのブラン・フュメに比較すれば、僅かに残糖感のある甘みをも感じさせてくれる、やや官能さをリリース時から持っているのがこの「ビュイッソン・ルナール」です。写真が無いのが残念ですが、2016年ものもまったく2015年に劣らない仕上がりかと思います。
海外的な評価は、以前のレヴューにも出ていますが、1.シレックス、2.ビュイッソン・ルナール、3.ピュル・サン と言う、価格通りのものですが、どうなんでしょう・・・このビュイッソン・ルナールは、単純にそう言う列で言ってしまうと、それしか経験の無い方には勘違いさせてしまうかと思います。
シャンパーニュで言えば、エクストラ・ブリュットがシレックスやその他で有って、ビュイッソン・ルナールはブリュットで有ると・・言うような理解で良いかもしれません。
ほんのりとした葡萄由来の心地良い甘みがベースに残った味わいですから、若くして飲んでも美味しいですよ。熟成させると物凄く変わると思います。是非飲んでみてください。お勧めです!
以下は以前のレヴューです。
━━━━━
【入荷数量の少ないビュイッソン・ルナールです!】
すみませんが、こちらは飲めていません。シレックスと言うのはご存知かと思いますが「火打ち石」のことですね。ダグノーのシレックスは、まさにシレックスだらけですが、他のキュヴェもかなりなシレックスは存在しています。でも、プイィ=フュメ イコール シレックス土壌 と言う図式は当てはまりませんのでご注意くださいね。
このビュイッソン・ルナールは粘土土壌に大き目のシレックスが散らばるような畑だそうです。大き目のシレックスが日中の熱量を夜間の粘土土壌に加えているような感じなのかな?と想像しますが、ピュル・サンやシレックスに比較すると良く熟した葡萄が供給されるようで、ほんのりとした甘味を感じる場合が多いようです。ピュル・サンやシレックスは完全にドライですけど。
ダグノーの2014年ものは3アイテムの試飲から非常に良い仕上がりだと思います。現地の評価機関の評価を見てみると、シレックスが19/20、ビュイッソン・ルナールが18/20~18.5/20、ピュル・サン17/20~18/20位のようですね。まぁ、ラ・ルヴェ・デュ・ヴァンにしてもベタンヌにしても結構ばらつきますが、ほぼ当たっていると思います。でもポテンシャル点を付けるとするとどうなんでしょうね・・もう少し上値を見た方が良いかな・・と言う気もします。
今回は2本のみです。是非ご検討くださいませ。
ラ・ボンヌ・ピヨッシュ
ラ・ボンヌ・ピヨッシュ
フランス La Bonne Pioche シュド=ウエスト
● アメリカでソムリエさんをしていたと言う、ラ・ボンヌ・ピヨッシュをご紹介させていただきます。

■ アメリカでのソムリエ経験から転身したネオ・ヴィニュロン
ラ・ボンヌ・ピヨッシュはフランス南西のアンディヤックにあるドメーヌです。造り手のヨアン・ルジエは、妻がアメリカ人であったため、当初アメリカでソムリエをしていました。そこで、世界中のありとあらゆるワインを試飲したヨハンは、ナチュラルワインに強く引き付けられていきました。土地とそこに根差した食、そして自然を愛する二人は、フランスに戻ってドメーヌを設立。ナチュラルワイン造りに乗り出したのです。
◇ 標準化にはうんざり。ユニークな個性を目指したワイン
ヨアンは標準化されたワインにうんざりしていました。クラシックなものや、居心地の良い場所から抜け出して、ちょっと変わったワインを消費者に提供したいと考えていました。そこで、自身の感性のおもむくまま、そしてブドウが自発的にどうなりたいかに寄り添ってワイン造りをしています。彼が手掛けているのは、ガイヤックの地場品種主体にしたペット・ナットやオレンジ、軽やかな赤など、これまで南西ワインにはないユニークな個性を備えたワインばかりです。
◇ドメーヌとその哲学について
La Bonne Pioche ラ・ボンヌ・ピヨッシュはフランスのシュッド・ウエストのAndillac アンディヤックにYohann Rougier ヨアン・ルジエによって2019 年に設立されたドメーヌです。1986 年生まれのヨアンは、妻のAmy エイミーがアメリカ人だったこともあり、当初はアメリカに住んでいました。アメリカのワインショップでソムリエとして働いていたヨアンは、その間に、フランス、アメリカ、そして世界各国のワイン、あらゆる品種のワイン、工業的ワインからアーティザナルなワイン、ナチュラルワインに至るまで様々なワインを試飲して、発見する機会に恵まれました。
その時に、知人を通して、ブルゴーニュでナチュラルワインを造っているクリストフ・サンティニと知り合いました。彼からフランスで何が起こっているのかを教えてもらったといいます。テロワールに誇りを持ちながら、AOC を必ずしも崇拝しないヴィニュロン達、化学物質を一切使わないワイン造りは不可能だと言われてきたにもかかわらず、驚くべき方法で遂にそれをやってのけたヴィニュロン達。多くのヴィニュロンが様々なアプローチでナチュラルワイン造りをし、人々はそこで歴史を作っているということを知ったのです。そのことを妻に話すと、エイミーは
「わかった。フランスでワインを造ってみよう!」
と言ってくれたそうです。そして、その数カ月後には二人はフランスに引っ越しをしていました。フランスに戻ったヨアンは、ブドウ畑を探して、ロワールやラングドックなどのワイン産地を回りました。
しかし、最終的に自分の育った地方であるガイヤックに住むことに決めました。10 代の頃のヨハンはガイヤックという産地がどんなものか知らず、イメージも良くありませんでした。しかし、ガイヤックでは、辛口の白ワインから甘口まで、プリムールワインから熟成用の赤ワイン、酸化的ワインまで、ほとんど全てのスタイルのワインが造られています。
また、今は世界中でペット・ナットがもてはやされていいますが、ガイヤックでは昔からペット・ナットが造られていました。さらに、ヨアンはガイヤックの地場品種がどれも個性的であることにも強く引き付けられました。例えば、デュラスはシラーよりも芳醇なペッパーのアロマを備え、モーザックにはリンゴや洋梨の味わいがはっきりと感じ取れます。ヨアンにとってガイヤックは「隠れた宝石」だったのです。こうして、2019 年にガイヤック近郊の村アンディヤックに定住したヨアンは、耕作放棄地だった1ha のブドウ畑を譲り受け、モーザックとBraucol ブロコル(マルシアックではフェル・セルヴァドゥと呼ばれる赤ブドウ品種)を栽培。ナチュラルワイン造りを始めたのです。
最初の3年間は、ドメーヌの仕事と並行して、同じガイヤックのナチュラルワインのドメーヌ、カンタローズで働いていました。カンタローズとは現在も親交があり、ワイン造りについての意見交換を頻繁にしています。また、ミネルヴォワのル・プティ・ドメーヌ・ド・ジミオとも家族ぐるみで交流があり、一緒に食事しながらワイン造りについての見解を語り合う仲だそうです。
ヨアンもエイミーも、ヴィニュロンの家系の出身ではありません。しかし、二人とも生活を楽しむ家族の出身でした。人が食べるものが土地と密接に
関係していることは明らかです。忘れてしまいがちですが、ワインは何よりも農産物です。そして、ワインも「生きているもの」でなければなりません。
ワインは畑で造られます。そのためにはブドウ木と一緒に仕事をすることが何よりも大切です。また、ヨアンはヴィニュロンの役割は、土壌を枯渇させないこと、そして生物多様性を活性化することであると考えています。なぜなら、そうすることで畝の間に沢山の花や昆虫が集まってきます。ブドウ木の代わりに花やハーブ、果物、生け垣、木を茂らせることは収量の点からはバカバカしいことですが、そのおかげで、多種多様な花が咲き、様々な虫が集まり、豊かな自然の香りが感じられます。多様性は至るところに存在しています。ブドウに付着する酵母も生きています。それは私達にとっても美しいことですし、心を和ませてくれます。
二人はビオロジックで殆ど全ての農作業を手作業で行っています。ブドウ畑での作業は難しく、時間がかかります。農薬を使わないということは、畑作業に多くの時間を費やすことになります。反復的で、近道をしたくなる状況が沢山あります。しかし、ブドウ木のバランスを保つためには、1 枚の葉が他の全ての葉よりも優先されるということを受け入れることはできません。
実際、病害を制御するのは非常に困難です。化学殺虫剤を使用して、生命を破壊するという簡単で楽な方法を取りたくなるかもしれません。しかし、土壌を生かす唯一の解決策「つるはし」です。ヨハンは、この「つるはし」との親密な関係がとても気に入っています。
シンプルな道具ですが、多くのことを象徴しています。ハードですが公正な仕事との関係。そして、農薬を使うような近道をすることは解決策ではないことを毎日自分に言い聞かせていたいのだそうです。そのようなことから、ドメーヌの名前を『La Bonne Pioche ラ・ボンヌ・ピヨッシュ』と名付けました。
ピヨッシュとはフランス語で「つるはし」のことです。ラ・ボンヌ・ピヨッシュと言うと「正しい選択、賢明な選択」を意味する慣用句になります。ヨアンは、このような小規模な家族経営の農場こそが持続可能な農業であると考えています。性別に関係なく全ての人にとって持続可能であること。私達が尊厳と節度を持って仕事から生計を立てることができるように、そして、これからもワインが全ての人の飲み物であり続けるために、可能な限り介入を少なくするように努めています。
ヨアンは標準化されたワインにうんざりしていました。クラシックなものや、居心地の良い場所から抜け出して、ちょっと変わったワインを消費者に提供したいと考えていました。そこで、自身の感性のおもむくまま、そしてブドウが自発的にどうなりたいかに寄り添ってワイン造りをしています。ヨアンはワインを自分の子供のようなものと感じています。学校では子供に全てを管理し、修正することを教えます。しかし、ヨハンは父親の役割は、子供(ブドウ)がどうなりたいかを教えるのではなく、子供(ブドウ)が自発的にどうなりたいかに寄り添っていくことであると考えているのです。彼の目標は透明性、そして何も加えない純粋なジューズからナチュラルワインを造ることです。土着酵母で醸造し、無清澄・無濾過、そして可能な限り亜硫酸をゼロに近づけること。添加する場合には、必要最低限の量であり、その他の醸造添加物は一切使いません。

■ アメリカでのソムリエ経験から転身したネオ・ヴィニュロン
ラ・ボンヌ・ピヨッシュはフランス南西のアンディヤックにあるドメーヌです。造り手のヨアン・ルジエは、妻がアメリカ人であったため、当初アメリカでソムリエをしていました。そこで、世界中のありとあらゆるワインを試飲したヨハンは、ナチュラルワインに強く引き付けられていきました。土地とそこに根差した食、そして自然を愛する二人は、フランスに戻ってドメーヌを設立。ナチュラルワイン造りに乗り出したのです。
◇ 標準化にはうんざり。ユニークな個性を目指したワイン
ヨアンは標準化されたワインにうんざりしていました。クラシックなものや、居心地の良い場所から抜け出して、ちょっと変わったワインを消費者に提供したいと考えていました。そこで、自身の感性のおもむくまま、そしてブドウが自発的にどうなりたいかに寄り添ってワイン造りをしています。彼が手掛けているのは、ガイヤックの地場品種主体にしたペット・ナットやオレンジ、軽やかな赤など、これまで南西ワインにはないユニークな個性を備えたワインばかりです。
◇ドメーヌとその哲学について
La Bonne Pioche ラ・ボンヌ・ピヨッシュはフランスのシュッド・ウエストのAndillac アンディヤックにYohann Rougier ヨアン・ルジエによって2019 年に設立されたドメーヌです。1986 年生まれのヨアンは、妻のAmy エイミーがアメリカ人だったこともあり、当初はアメリカに住んでいました。アメリカのワインショップでソムリエとして働いていたヨアンは、その間に、フランス、アメリカ、そして世界各国のワイン、あらゆる品種のワイン、工業的ワインからアーティザナルなワイン、ナチュラルワインに至るまで様々なワインを試飲して、発見する機会に恵まれました。
その時に、知人を通して、ブルゴーニュでナチュラルワインを造っているクリストフ・サンティニと知り合いました。彼からフランスで何が起こっているのかを教えてもらったといいます。テロワールに誇りを持ちながら、AOC を必ずしも崇拝しないヴィニュロン達、化学物質を一切使わないワイン造りは不可能だと言われてきたにもかかわらず、驚くべき方法で遂にそれをやってのけたヴィニュロン達。多くのヴィニュロンが様々なアプローチでナチュラルワイン造りをし、人々はそこで歴史を作っているということを知ったのです。そのことを妻に話すと、エイミーは
「わかった。フランスでワインを造ってみよう!」
と言ってくれたそうです。そして、その数カ月後には二人はフランスに引っ越しをしていました。フランスに戻ったヨアンは、ブドウ畑を探して、ロワールやラングドックなどのワイン産地を回りました。
しかし、最終的に自分の育った地方であるガイヤックに住むことに決めました。10 代の頃のヨハンはガイヤックという産地がどんなものか知らず、イメージも良くありませんでした。しかし、ガイヤックでは、辛口の白ワインから甘口まで、プリムールワインから熟成用の赤ワイン、酸化的ワインまで、ほとんど全てのスタイルのワインが造られています。
また、今は世界中でペット・ナットがもてはやされていいますが、ガイヤックでは昔からペット・ナットが造られていました。さらに、ヨアンはガイヤックの地場品種がどれも個性的であることにも強く引き付けられました。例えば、デュラスはシラーよりも芳醇なペッパーのアロマを備え、モーザックにはリンゴや洋梨の味わいがはっきりと感じ取れます。ヨアンにとってガイヤックは「隠れた宝石」だったのです。こうして、2019 年にガイヤック近郊の村アンディヤックに定住したヨアンは、耕作放棄地だった1ha のブドウ畑を譲り受け、モーザックとBraucol ブロコル(マルシアックではフェル・セルヴァドゥと呼ばれる赤ブドウ品種)を栽培。ナチュラルワイン造りを始めたのです。
最初の3年間は、ドメーヌの仕事と並行して、同じガイヤックのナチュラルワインのドメーヌ、カンタローズで働いていました。カンタローズとは現在も親交があり、ワイン造りについての意見交換を頻繁にしています。また、ミネルヴォワのル・プティ・ドメーヌ・ド・ジミオとも家族ぐるみで交流があり、一緒に食事しながらワイン造りについての見解を語り合う仲だそうです。
ヨアンもエイミーも、ヴィニュロンの家系の出身ではありません。しかし、二人とも生活を楽しむ家族の出身でした。人が食べるものが土地と密接に
関係していることは明らかです。忘れてしまいがちですが、ワインは何よりも農産物です。そして、ワインも「生きているもの」でなければなりません。
ワインは畑で造られます。そのためにはブドウ木と一緒に仕事をすることが何よりも大切です。また、ヨアンはヴィニュロンの役割は、土壌を枯渇させないこと、そして生物多様性を活性化することであると考えています。なぜなら、そうすることで畝の間に沢山の花や昆虫が集まってきます。ブドウ木の代わりに花やハーブ、果物、生け垣、木を茂らせることは収量の点からはバカバカしいことですが、そのおかげで、多種多様な花が咲き、様々な虫が集まり、豊かな自然の香りが感じられます。多様性は至るところに存在しています。ブドウに付着する酵母も生きています。それは私達にとっても美しいことですし、心を和ませてくれます。
二人はビオロジックで殆ど全ての農作業を手作業で行っています。ブドウ畑での作業は難しく、時間がかかります。農薬を使わないということは、畑作業に多くの時間を費やすことになります。反復的で、近道をしたくなる状況が沢山あります。しかし、ブドウ木のバランスを保つためには、1 枚の葉が他の全ての葉よりも優先されるということを受け入れることはできません。
実際、病害を制御するのは非常に困難です。化学殺虫剤を使用して、生命を破壊するという簡単で楽な方法を取りたくなるかもしれません。しかし、土壌を生かす唯一の解決策「つるはし」です。ヨハンは、この「つるはし」との親密な関係がとても気に入っています。
シンプルな道具ですが、多くのことを象徴しています。ハードですが公正な仕事との関係。そして、農薬を使うような近道をすることは解決策ではないことを毎日自分に言い聞かせていたいのだそうです。そのようなことから、ドメーヌの名前を『La Bonne Pioche ラ・ボンヌ・ピヨッシュ』と名付けました。
ピヨッシュとはフランス語で「つるはし」のことです。ラ・ボンヌ・ピヨッシュと言うと「正しい選択、賢明な選択」を意味する慣用句になります。ヨアンは、このような小規模な家族経営の農場こそが持続可能な農業であると考えています。性別に関係なく全ての人にとって持続可能であること。私達が尊厳と節度を持って仕事から生計を立てることができるように、そして、これからもワインが全ての人の飲み物であり続けるために、可能な限り介入を少なくするように努めています。
ヨアンは標準化されたワインにうんざりしていました。クラシックなものや、居心地の良い場所から抜け出して、ちょっと変わったワインを消費者に提供したいと考えていました。そこで、自身の感性のおもむくまま、そしてブドウが自発的にどうなりたいかに寄り添ってワイン造りをしています。ヨアンはワインを自分の子供のようなものと感じています。学校では子供に全てを管理し、修正することを教えます。しかし、ヨハンは父親の役割は、子供(ブドウ)がどうなりたいかを教えるのではなく、子供(ブドウ)が自発的にどうなりたいかに寄り添っていくことであると考えているのです。彼の目標は透明性、そして何も加えない純粋なジューズからナチュラルワインを造ることです。土着酵母で醸造し、無清澄・無濾過、そして可能な限り亜硫酸をゼロに近づけること。添加する場合には、必要最低限の量であり、その他の醸造添加物は一切使いません。
●
N.V.(2022) Rage Against the Bomboche V.d.F. Rouge
レイジ・アゲンスト・ザ・ボンボッシュ V.d.F.ルージュ
【Rage Against the Machine は良く知りませんが、首振り縦ノリ系?・・でも、Rage Against the Bomboche は、首が疲れるような激しさは無く、美しく伸びやかな「濃いスル」!・・これは美味しいです!】
 レイジ・アゲンスト・ザ・マシーンと言うバンドは良く知らないので、Youtube で探して聞いてみました。
レイジ・アゲンスト・ザ・マシーンと言うバンドは良く知らないので、Youtube で探して聞いてみました。まぁ、ヘヴィーなサウンド・・メタリックでも有るのかな?・・メッセージ色の強い歌詞を低音中心のリズムで・・縦の首振り系のようで・・いや、余り知らないのでそんなことも無いのかもしれませんが・・。
で、それをモジってのレイジ・アゲンスト・ザ・ボンボッシュと言うことなんですね。
ご覧のようにとても濃いですが、むしろオナタンドン・ラ・プリュイほど果皮果皮しておらず、やや淡いでしょうか。適度が集中が有り美しい味わいです。
このラ・ボンヌ・ピヨッシュのヨアン・ルジエさん、アメリカでソムリエをしていたそうですが、中々の感性の持ち主と思われ、
「濃度は有るものの濃過ぎと言うことも無いほど、つり合いの取れた美しい酸が有り、ドライで甘く無くナチュラルでピュアな自然派ワイン」
と言えます。
ジューシーと直に言うほどの甘みが無く、しかし渋みやビターとのバランスも取れていて、アルコール度も14度でこの手のワインとしてはちょうど良く、
「誰も文句の無いスタイリッシュな味わいバランス」
だと思います。
 果実は見事なブリッブリのブラックチェリー、チェリー、ほんのりブルーベリー、カカオが入るでしょうか。オナタンドン・ラ・プリュイよりも中心点がハッキリしているのはカベルネ・ソーヴィニヨンの存在かな?・・と想像していますが、たまにはこのようなとても美しいスタイルの南西地方のワインも良いと思いますよ。
果実は見事なブリッブリのブラックチェリー、チェリー、ほんのりブルーベリー、カカオが入るでしょうか。オナタンドン・ラ・プリュイよりも中心点がハッキリしているのはカベルネ・ソーヴィニヨンの存在かな?・・と想像していますが、たまにはこのようなとても美しいスタイルの南西地方のワインも良いと思いますよ。南西地方のワインにしては、
「茶や黒のイメージがとても少ない」
のが特徴で、しかも、
「So2 の存在をまったく意識しないで飲めるレベル」
と言うのも、このラ・ボンヌ・ピヨッシュの特徴でしょう。ぜひ飲んでみて下さい。気に入っていただけると思います。お薦めです!
ドメーヌ・バール
バール
フランス Domaine Bart ブルゴーニュ
● 昨年の2020年ものから本格的に扱わせていただくことになったドメーヌ・バールの2021年ものをご紹介させていただきます。
「そもそもなんで noisyさんがバールを?」
と・・きっと思われているんじゃないかと勝手に想像しています。
だって・・余り見るべきところが無く、クラシカルでやや硬くて、なかなか安定しない内向きな味わい・・だったでしょう?・・そうでしたよね。
noisy も折に触れてはバールのワインをテイスティングしていました。だって・・
「サンプルをいただけるから・・」
(^^;;
貰うだけ貰い、飲むだけ飲んで、しっかり「いらない!」と断り続けたこの数年・・悪い奴ですね~・・。
ですが!
 昨年の2020年ものを飲んで・・
昨年の2020年ものを飲んで・・
「・・おや?」
と・・思った訳です。いや・・良くなったなぁ・・と。こりゃぁ行けそうだと・・(^^;;・・と言うか、
「今の内・・ラストチャンス?」
と・・ワイン屋の嫌らしい?感が働いた訳です。それで扱わせていただくことになりました。
2021年ものはその noisy 的野生の感が当たったか的外れなのか、結果が出るヴィンテージとなった訳ですから、そりゃぁ・・noisy も真剣にテイスティングさせていただきました。
申し上げておきたいのは、
「2021年のドメーヌ・バール..すこぶる旨い!・・まったく外れ無し!・・しかもめちゃリーズナブル!」
です。
まぁ・・言っちゃなんですが、セシルもフーリエもラミーもヴァーゼンハウスも・・そうやって掘り出した訳ですから・・少しは信用は有るかと思っています・・ん?・・信用なんかしてない?・・(T.T
noisy 的にはこの・・息子さんのピエールさんが入ってからのバールが、今のバールを生み出しているかな・・と感じます。そしてピエールさんは、
「天才肌と言うよりは地道に努力を重ねて伸びて行く職人タイプ」
かと・・。
ですから、タイプで言ったらクリストフ・ルーミエでしょうか。彼もまた・・まぁ・・美味しかったけれど90年代は普通っちゃ普通・・でした。アンリ・ジャイエもご存命でしたし・・凄い造り手さんがいっぱいいた中で、彼も伸びて来た訳です。
なので noisy も、このバールさんちには物凄く期待しています。そして、2021年もの・・途轍もなく美しく、ミネラリティがビシっと通った素晴らしい味わいで、
「マルサネの各畑の個性に光を当てているのが良く判る!」
んですね。
マルサネと言いますと・・noisyもずっと頑張って来たシルヴァン・パタイユがありますが、ま~・・ラシーヌさんから入って来ない・・まいっちゃいます。
ですが、
「2021年もののドメーヌ・バールは、まるでシルヴァン・パタイユの美しく光り収束まで延々と感じさせるようなミネラリティを持ち、ルジェさん的なエロスなアロマをも感じさせてくれる!」
と言う・・余り有り得ない、おそらく今まで飲んだことが無いようなタイプだと・・確信しています。
想像してみてください・・パタイユ的なハードな美しいミネラリティにルジェ的な官能のアロマ・・そしてマルサネと言う未開の個性!
素晴らしいです。A.C.ブルで良いので、ぜひ飲んでみてください。安くて滅茶美味しい!・・将来性も滅茶感じると思います。激お薦めです!
-----
初めての取り扱いになりました、マルサネ・ラ・コートのドメーヌ・バールをご紹介させていただきます。「いにしえ」の大ドメーヌ、クレール=ダユを継承したのはブリュノ・クレールだけでは無いんですね・・このドメーヌ・バールもまた、クレール=ダユの姻族の血統です。
長らくテイスティングだけに留めていたんですが、やや硬くてゴワゴワっとしたテクスチュアの少し飲みにくさが有ったワインが・・、
「・・あれ?」
と・・(^^;;
それに、かの偉大なクレール=ダユから受け継いだボンヌ=マールとクロ・ド・ベーズの評価だけは爆上がりしていましたので、時々下のクラスしかチェックが出来なかったものですから気付かず・・ですが、
「グラン・クリュの質に下のクラスも追いついて来た」
と判断したんですね。
ボンヌ=マールは戦時中に植えたとのことですから80年以上のヴィエイユ・ヴィーニュで、海外サイトによりますと「ミルランダージュが付く素晴らしい畑」とのことですし、クロ・ド・ベーズはボンヌ=マールほどでは無いにせよ65年以上の古木だそうで、
「ん~・・今の内かな~・・何とか飲んでみたいなぁ・・」
と思っています。
2007年から従兄弟のピエールさんが栽培・醸造責任者となっていまして、徐々にその能力を高めて来たと考えています。今回は、2020年ものを含め、そろそろ美味しくなってきた2018年もの、2019年ものをご紹介させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
■ エージェント情報
シルヴァン・パタイユやジャン・フルニエといった新星ヴィニュロンが割拠するマルサネ村。マルサネ村にAOC呼称が与えられたのは比較的新しい1987年です。その礎を築いたのが、ドメーヌ・クレール=ダユです。
日常消費用のガメイ主体のワイン産地にピノ・ノワールの可能性を見出し、世間に知らしめてきた功績は非常に大きいものでした。クレール家の畑は現在、ブルノ・クレール、ルイ・ジャド、そしてこのドメーヌ・バールに引き継がれています。
2009年、当主マルタン・バールの甥にあたるピエール・バールが参画。その若き才能は2013年、そして昨年2018年とブルゴーニュのヴィニュロンの登竜門となっている Le Groupe des jeunes Professionnels de la Vigne (GJPV) で選出されたことからも測り知れます。
非常に落ち着きがあり、聡明なピエール・バールの造るワインは華やかな香りや、エレガントな時流に乗ったスタイルではなく極めて素直に、葡萄の良さをミレジムの個性に乗せて表現してきます。ドミニク・ローランら著名生産者がこぞって彼のワインを買い付ける点が彼の実力を証明しております。
 コート・ド・ニュイ最北端に位置するマルサネは、バジョシアン階とバトニアン階の石灰岩が混ざる土壌の多様性、 そしてブルゴーニュで唯一、赤・白・ロゼのワインを生みだすことが出来る、一躍注目を浴びているアペラシオンである。
コート・ド・ニュイ最北端に位置するマルサネは、バジョシアン階とバトニアン階の石灰岩が混ざる土壌の多様性、 そしてブルゴーニュで唯一、赤・白・ロゼのワインを生みだすことが出来る、一躍注目を浴びているアペラシオンである。
歴史:マルサネ近代化の礎を築いたドメーヌ・クレール=ダユ、その血統を継ぐのが、ブリュノ・クレールと、このドメーヌ・バールなのです。
1982年、バール家の二人の子供達であるオディールとマルタン・バールによって 自分たちのドメーヌを立ち上げ元詰めを始めました。1987年にはGAEC(農業経営集合体)に加盟。姉であるオディールが指揮を執り、経営、マルタンがブドウ栽培から醸造を担当しています。7年前よりオディールの息子ピエールもドメーヌに参画しました。
ドメーヌはコート・ドールの北端マルサネを中心に21ヘクタールを所有しています。収穫したワインの60%は自社で瓶詰めし、そこからおよそ3分の1を輸出します。残りの40%はネゴシアンに売却します。
葡萄栽培は自然環境を尊重し、除草剤、化学肥料は施しません。葡萄樹の衛生状態に対しては天気予報やウドンコ病の情報といった有効な情報ツール、そして畑を定期的に観察するおかげで、最適なレベルを保つことが出来るのです。
例えば季節の初めの葉の量に応じて、生産量を調整することで殺虫剤も減らすことが出来ます。6月の下旬まで畑を耕作し、その後、夏の間は有機農法で葡萄樹同士の生存競争をさせます。このおかげで葡萄は最高の成熟度を得ることが出来ます。
7月初旬には全ての区画で除葉します。最後に手で収穫し、必要に応じてその場で選果します。
 ワイン造り:ヴィンテージによって異なりますが、5~9日間の低温マセラシオンを施します。これによって私たちのワインに果実味が備わります。
ワイン造り:ヴィンテージによって異なりますが、5~9日間の低温マセラシオンを施します。これによって私たちのワインに果実味が備わります。
アルコール発酵は葡萄自体が持つ天然酵母で行われます。圧搾後、樽に入れる前に2週間、タンクへ移しデカンタージュします。これは熟成の際に、ワインに有益な純粋な澱だけを保護することです。
新樽比率はキュヴェによって異なり5~50%です。残りは1~4年の古樽です。マロラクティック発酵は自然な順序を経て施されます。12カ月の樽熟成後、ワインをグラスファイバータンクに移し3カ月間均一化させ、瓶詰めします。この過程で、樽香が完全にワインに馴染むのです。
私たちは基本的に濾過・清澄を施しません。私たちは赤ワインにおいては、ピノ・ノワールの持つ精妙なフィネスを拠り所にしているのです。新樽を100%使わないのもそのためです。私たちのワインは伝統的であり、テロワールを最上に体現した結果、美しい緊張感とミネラル感を備えています。
私たちは常に同じ印象を受ける様な均一化されたワインではなく、ワインに各ミレジムの個性を反映させます。

「そもそもなんで noisyさんがバールを?」
と・・きっと思われているんじゃないかと勝手に想像しています。
だって・・余り見るべきところが無く、クラシカルでやや硬くて、なかなか安定しない内向きな味わい・・だったでしょう?・・そうでしたよね。
noisy も折に触れてはバールのワインをテイスティングしていました。だって・・
「サンプルをいただけるから・・」
(^^;;
貰うだけ貰い、飲むだけ飲んで、しっかり「いらない!」と断り続けたこの数年・・悪い奴ですね~・・。
ですが!
 昨年の2020年ものを飲んで・・
昨年の2020年ものを飲んで・・「・・おや?」
と・・思った訳です。いや・・良くなったなぁ・・と。こりゃぁ行けそうだと・・(^^;;・・と言うか、
「今の内・・ラストチャンス?」
と・・ワイン屋の嫌らしい?感が働いた訳です。それで扱わせていただくことになりました。
2021年ものはその noisy 的野生の感が当たったか的外れなのか、結果が出るヴィンテージとなった訳ですから、そりゃぁ・・noisy も真剣にテイスティングさせていただきました。
申し上げておきたいのは、
「2021年のドメーヌ・バール..すこぶる旨い!・・まったく外れ無し!・・しかもめちゃリーズナブル!」
です。
まぁ・・言っちゃなんですが、セシルもフーリエもラミーもヴァーゼンハウスも・・そうやって掘り出した訳ですから・・少しは信用は有るかと思っています・・ん?・・信用なんかしてない?・・(T.T
noisy 的にはこの・・息子さんのピエールさんが入ってからのバールが、今のバールを生み出しているかな・・と感じます。そしてピエールさんは、
「天才肌と言うよりは地道に努力を重ねて伸びて行く職人タイプ」
かと・・。
ですから、タイプで言ったらクリストフ・ルーミエでしょうか。彼もまた・・まぁ・・美味しかったけれど90年代は普通っちゃ普通・・でした。アンリ・ジャイエもご存命でしたし・・凄い造り手さんがいっぱいいた中で、彼も伸びて来た訳です。
なので noisy も、このバールさんちには物凄く期待しています。そして、2021年もの・・途轍もなく美しく、ミネラリティがビシっと通った素晴らしい味わいで、
「マルサネの各畑の個性に光を当てているのが良く判る!」
んですね。
マルサネと言いますと・・noisyもずっと頑張って来たシルヴァン・パタイユがありますが、ま~・・ラシーヌさんから入って来ない・・まいっちゃいます。
ですが、
「2021年もののドメーヌ・バールは、まるでシルヴァン・パタイユの美しく光り収束まで延々と感じさせるようなミネラリティを持ち、ルジェさん的なエロスなアロマをも感じさせてくれる!」
と言う・・余り有り得ない、おそらく今まで飲んだことが無いようなタイプだと・・確信しています。
想像してみてください・・パタイユ的なハードな美しいミネラリティにルジェ的な官能のアロマ・・そしてマルサネと言う未開の個性!
素晴らしいです。A.C.ブルで良いので、ぜひ飲んでみてください。安くて滅茶美味しい!・・将来性も滅茶感じると思います。激お薦めです!
-----
初めての取り扱いになりました、マルサネ・ラ・コートのドメーヌ・バールをご紹介させていただきます。「いにしえ」の大ドメーヌ、クレール=ダユを継承したのはブリュノ・クレールだけでは無いんですね・・このドメーヌ・バールもまた、クレール=ダユの姻族の血統です。
長らくテイスティングだけに留めていたんですが、やや硬くてゴワゴワっとしたテクスチュアの少し飲みにくさが有ったワインが・・、
「・・あれ?」
と・・(^^;;
それに、かの偉大なクレール=ダユから受け継いだボンヌ=マールとクロ・ド・ベーズの評価だけは爆上がりしていましたので、時々下のクラスしかチェックが出来なかったものですから気付かず・・ですが、
「グラン・クリュの質に下のクラスも追いついて来た」
と判断したんですね。
ボンヌ=マールは戦時中に植えたとのことですから80年以上のヴィエイユ・ヴィーニュで、海外サイトによりますと「ミルランダージュが付く素晴らしい畑」とのことですし、クロ・ド・ベーズはボンヌ=マールほどでは無いにせよ65年以上の古木だそうで、
「ん~・・今の内かな~・・何とか飲んでみたいなぁ・・」
と思っています。
2007年から従兄弟のピエールさんが栽培・醸造責任者となっていまして、徐々にその能力を高めて来たと考えています。今回は、2020年ものを含め、そろそろ美味しくなってきた2018年もの、2019年ものをご紹介させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
■ エージェント情報
シルヴァン・パタイユやジャン・フルニエといった新星ヴィニュロンが割拠するマルサネ村。マルサネ村にAOC呼称が与えられたのは比較的新しい1987年です。その礎を築いたのが、ドメーヌ・クレール=ダユです。
日常消費用のガメイ主体のワイン産地にピノ・ノワールの可能性を見出し、世間に知らしめてきた功績は非常に大きいものでした。クレール家の畑は現在、ブルノ・クレール、ルイ・ジャド、そしてこのドメーヌ・バールに引き継がれています。
2009年、当主マルタン・バールの甥にあたるピエール・バールが参画。その若き才能は2013年、そして昨年2018年とブルゴーニュのヴィニュロンの登竜門となっている Le Groupe des jeunes Professionnels de la Vigne (GJPV) で選出されたことからも測り知れます。
非常に落ち着きがあり、聡明なピエール・バールの造るワインは華やかな香りや、エレガントな時流に乗ったスタイルではなく極めて素直に、葡萄の良さをミレジムの個性に乗せて表現してきます。ドミニク・ローランら著名生産者がこぞって彼のワインを買い付ける点が彼の実力を証明しております。
 コート・ド・ニュイ最北端に位置するマルサネは、バジョシアン階とバトニアン階の石灰岩が混ざる土壌の多様性、 そしてブルゴーニュで唯一、赤・白・ロゼのワインを生みだすことが出来る、一躍注目を浴びているアペラシオンである。
コート・ド・ニュイ最北端に位置するマルサネは、バジョシアン階とバトニアン階の石灰岩が混ざる土壌の多様性、 そしてブルゴーニュで唯一、赤・白・ロゼのワインを生みだすことが出来る、一躍注目を浴びているアペラシオンである。歴史:マルサネ近代化の礎を築いたドメーヌ・クレール=ダユ、その血統を継ぐのが、ブリュノ・クレールと、このドメーヌ・バールなのです。
1982年、バール家の二人の子供達であるオディールとマルタン・バールによって 自分たちのドメーヌを立ち上げ元詰めを始めました。1987年にはGAEC(農業経営集合体)に加盟。姉であるオディールが指揮を執り、経営、マルタンがブドウ栽培から醸造を担当しています。7年前よりオディールの息子ピエールもドメーヌに参画しました。
ドメーヌはコート・ドールの北端マルサネを中心に21ヘクタールを所有しています。収穫したワインの60%は自社で瓶詰めし、そこからおよそ3分の1を輸出します。残りの40%はネゴシアンに売却します。
葡萄栽培は自然環境を尊重し、除草剤、化学肥料は施しません。葡萄樹の衛生状態に対しては天気予報やウドンコ病の情報といった有効な情報ツール、そして畑を定期的に観察するおかげで、最適なレベルを保つことが出来るのです。
例えば季節の初めの葉の量に応じて、生産量を調整することで殺虫剤も減らすことが出来ます。6月の下旬まで畑を耕作し、その後、夏の間は有機農法で葡萄樹同士の生存競争をさせます。このおかげで葡萄は最高の成熟度を得ることが出来ます。
7月初旬には全ての区画で除葉します。最後に手で収穫し、必要に応じてその場で選果します。
 ワイン造り:ヴィンテージによって異なりますが、5~9日間の低温マセラシオンを施します。これによって私たちのワインに果実味が備わります。
ワイン造り:ヴィンテージによって異なりますが、5~9日間の低温マセラシオンを施します。これによって私たちのワインに果実味が備わります。アルコール発酵は葡萄自体が持つ天然酵母で行われます。圧搾後、樽に入れる前に2週間、タンクへ移しデカンタージュします。これは熟成の際に、ワインに有益な純粋な澱だけを保護することです。
新樽比率はキュヴェによって異なり5~50%です。残りは1~4年の古樽です。マロラクティック発酵は自然な順序を経て施されます。12カ月の樽熟成後、ワインをグラスファイバータンクに移し3カ月間均一化させ、瓶詰めします。この過程で、樽香が完全にワインに馴染むのです。
私たちは基本的に濾過・清澄を施しません。私たちは赤ワインにおいては、ピノ・ノワールの持つ精妙なフィネスを拠り所にしているのです。新樽を100%使わないのもそのためです。私たちのワインは伝統的であり、テロワールを最上に体現した結果、美しい緊張感とミネラル感を備えています。
私たちは常に同じ印象を受ける様な均一化されたワインではなく、ワインに各ミレジムの個性を反映させます。

●
2021 Marsannay Rouge les Longeroies
マルサネ・ルージュ・レ・ロンジュロワ
【激エレガントなレ・フィノットと首一つ差!・・やっぱりレ・ロンジュロワ・・めちゃお美味しいです!】
 レ・ロンジュロワと言えば・・この10年弱ほどは、noisyも
レ・ロンジュロワと言えば・・この10年弱ほどは、noisyも「シルヴァン・パタイユ」
でした。
ま~・・中々パタイユも売れなくてね・・結構に苦労したんですね。それがいつの間にか・・いや、リアルワインガイドが後押しになったような感も有って、決して noisy が持ち上げた訳では無いと理解しています。
ですがこの3年ほどは入荷が変でして・・明らかにおかしい・・。まぁ・・入って来ると思っていたものが入って来ないと売り様がない訳で、本当に困った訳です。
そんなところにこのバールのボトルをいただきまして・・いや、今までも何度もいただいているんですけどね・・気に入らないと買わないもので・・すみません。
ですが2020年ものを飲んだ時に、
「あ、・・こりゃ・・きっと・・来るなぁ・・」
と・・思ったんですね。
それ以前とはもう、大きく変わっていたんですよ。そしてこの2021年、勝負のヴィンテージだと思っていました。
このレ・ロンジュロワはあのシルヴァン・パタイユも造っています。パタイユのレ・ロンジュロワよりも幾分柔らかく、そしてその分・・
「色っぽい!」
です。
 何とも艶っぽいアロマが有って、またレ・ロンジュロワの複雑なニュアンス、わずかな鉄っぽさ、ちょっと別の金属・・マンガンとか・・そんな感じのミネラリティがふんだんにあるように感じます。そしてフラワリーな・・軽やかな花のニュアンスと赤い新鮮なチェリーと少し熟したチェリーが混じる感じです。
何とも艶っぽいアロマが有って、またレ・ロンジュロワの複雑なニュアンス、わずかな鉄っぽさ、ちょっと別の金属・・マンガンとか・・そんな感じのミネラリティがふんだんにあるように感じます。そしてフラワリーな・・軽やかな花のニュアンスと赤い新鮮なチェリーと少し熟したチェリーが混じる感じです。あ、テクニカルにあるエージェントさん情報の「カシス」は余り感じませんでした。
それよりも色は淡く、劇的にエレガントで・・今はまだ・・例の・・他のキュヴェではそれなりに顕著な・・
「シルヴァン・パタイユとエマニュエル・ルジェのコラボ」
的な部分は成長途中かと感じますが、いずれ出てくると思います。面白いのは、
「このレ・ロンジュロワとエ・シェゾーのその部分は有るものの、今のところやや穏やか」
で、下級キュヴェの方がより強く感じます。この2つに限っては、
「ポテンシャルの高さゆえに今のところ見えて来ていない」
と判断しました。
まぁ・・90点は低すぎて無いかな・・と思います。ぜひ飲んでみてください。リーズナブルで、テロワール違いもしっかり感じられる素晴らしい激エレガントなピノ・ノワールです!超お薦めします!
以下は以前のレヴューです。
-----
【これは買いでしょう!マルサネの深い赤果実の美味しさをたっぷり持った、これからもたっぷり美味しい期間が長い、飲み頃を迎えつつあるレ・グランド・ヴィーニュです!】
 Noisy wine でマルサネと言えば「シルヴァン・パタイユ」ですが、この造り手もちょっと苦労はしたものの、ようやっと売れるようになった・・と思ったら、何だかスムーズに入って来ないんですよね・・未だに2020はご案内はいただけず、一体どうなっちゃっているのか・・一番多い時は20ケース以上は販売していたはずなんですが、これが販売出来ないとなると相当な痛手です。
Noisy wine でマルサネと言えば「シルヴァン・パタイユ」ですが、この造り手もちょっと苦労はしたものの、ようやっと売れるようになった・・と思ったら、何だかスムーズに入って来ないんですよね・・未だに2020はご案内はいただけず、一体どうなっちゃっているのか・・一番多い時は20ケース以上は販売していたはずなんですが、これが販売出来ないとなると相当な痛手です。そもそもマルサネには将来性を感じていましたから、その昔は結構にアレコレやってみたんですね・・。フィリップ・シャルロパン(・パリゾ)にも注目していたんですが・・ん~・・今ひとつでボツになってしまったし・・でも、パタイユのル・シャピトルには驚かされました・・あれ、当初はかなり安かったんですね・・A.C.ブルとしては高かったですが。
ル・シャピトルはマルサネ・クロ・デュ・ロワのさらに北にある、何故か村名になっていなかった秀逸は畑でしたので、価格はクロ・デュ・ロワと同じでした。ル・シャピトルはマルサネ・ラ・コートの村の北のお隣、シュノーヴ村に有ります。マルサネのアペラシオンは相当に広範にわたっていまして、南から、(フィサンの北の・・)
クーシェ村 -- マルサネ・ラ・コート村 -- シュノーヴ村
と3カ村に渡っています。今回ご紹介のレ・グランド・ヴィーニュはマルサネ・ラ・コートの上部南端です。同時にご案内させていただいている「シャン・サロモン」はクーシェ村ですが、このレ・グランド・ヴィーニュと向かい合って接しているんですね。
ですがこのレ・グランド・ヴィーニュとシャン・サロモン、バールに言わせますと、
「濃度が全然違うので仕上げも違う」
と言っています。・・その辺りの違いは「シャン・サロモン」のコラムに書かせていただきました。
 エージェント情報には記載は有りませんが、調べてみるとこのキュヴェは、
エージェント情報には記載は有りませんが、調べてみるとこのキュヴェは、「新樽は少々、他は600Lのデミ・ミッドを使用」
としているようです。冷ややかな畑のようで、非常にフレッシュさが感じられます・・活き活きとしている感じです。
アルコール分は13度でベストと言える度数です。エレガントさと濃密さのバランスが良い度数と言えます。
濃密だが滅茶ドライで赤黒果実が深いです。ほんのりと煙、グリオット、ハーブ、少し鉄、ほんのりとしなやかに粘り、口内に拠点を造る感じです。重心は低いですがマルサネらしく重くなり過ぎず、スレンダーな縦延び系です。
近いのはパタイユですとグラス・テートですが、あれは透明なミネラル感が非常に強く前に出るので、その部分は少し弱く、もう少し品の良い赤い粘土を増やした感じです。
もしくはやや重心を少し上げて、重い部分を飛ばし、透明なミネラリティを増やしたジュヴレでしょうか・・。赤いニュアンスがしっかり有りますが、ジュヴレのような重い鉄は無い・・でも縦に良く伸びてくれます。
熟し始めていて、今飲んでも非常に美味しいです。2年先にはもっとずっと開いてくると思いますが、今飲んで良いものは是非・・しかもリーズナブルですので飲んでみてください。超お勧めします!
●
2021 Bonnes-Mares Grand Cru
ボンヌ=マール・グラン・クリュ
【クレール=ダユの偉大なボンヌ=マールを相続!・・長く硬いクラシカルな製法をしていましたが、1/3が全房、1/3が新樽、1/3の古樽で大復活!!】---以前のレヴューを掲載しています。
1970年以前には、ブルゴーニュらしい荘厳なワインを造る大ドメーヌとして鳴らしたドメーヌ・クレール=ダユでした。相続が上手く行かず・・評判も落ちていたクレール=ダユは、その虎の子の畑を切り売りせざるを得なくなり、1985年に消滅しています。
その際、ブリュノ・クレールがモレ=サン=ドニのボンヌ=マールを継承し、バールがそれ以外のシャンボール側にあるボンヌ=マールを・・結果的にいただいた訳ですね。
ブリュノ・クレールのボンヌ=マールは承継後、色々有ってフォジュレイ・ド・ボークレールが借りて造っていました。こちらはモレに有りますから・・シャンボール側に有る大半のボンヌ=マールとはだいぶ味わいが違ったと・・言われています。noisy もそのボークレールのボンヌ=マールを販売したことが有り、飲んでもいますが・・これも硬かったですね~。
・・そもそもボンヌ=マールと言うワインは、
「ミュジニー並みの長命なワインで飲むタイミングが難しい。ミュジニーが若くして素晴らしい芳香を放出していてもボンヌ=マールはほぼ閉じたまま。しかしミュジニーが開く前にボンヌ=マールは飲み頃を迎えて長く持続する。」
と言われていたと思いますし、noisy もそれをほぼ確認しています。
ですが昨今の濃密な味わいに仕上げたボンヌ=マールは決してそんなことは無く、早い段階からそこそこに美味しく飲めてしまいます。近代的な技術の進歩も有り、温暖化の影響もあり・・と言うことなのかもしれません。
しかし・・しかしですよ・・本当にボンヌ=マールがその本性を見せるとするなら・・やはり長い月日を忍耐強く待たなければならないのかな・・とは思っています。
因みにバールのボンヌ=マールは、シャンボールの南側(ヴォギュエとの地所の真上の上部、ルーミエさんの地所のうち最も南側にある部分の上部、ジャック=フレデリック・ミュニエの地所の南側)に大きな区画が1箇所と、ボンヌ=マールの中央に小さな区画が1箇所で、合わせて1ヘクタール以上有る様です。(0.5ヘクタールと言う話も有ります。)
で、La Revue du Vin de France誌が長くこのボンヌ=マールを評価していますので・・とりあえずご覧ください。
2018 17.5/20
2017 18.0/20
2016 19.0/20
2015 19.0/20
2014.18.5/20
2013 18.5/20
2012 18.5/20
2011 17.5/20
2010 18.0/20
2009 ----
2008 17.5/20
2007 16.5/20
2006 15.5/20
2004 16.5/20
2003 16.0/20
2002 17.0/20
2001 15.0/20
どうでしょう?・・20点満点ですが、この20年弱ほどの間に相当評点が上昇しています。
また、ジャスパー・モリスさんに至っては・・2020年ものは上値97ポイント、2019年ものは上値98ポイント、2018年ものは上値97ポイントと・・大変にご執心のようです。ルーミエさんは96~98 Points と言う評価ですからそれに次ぐ高い評価です。
残念ながら2本だけの入荷ですので飲む訳にも行かなくて残念ですが・・まだまだリーズナブルなのかな・・と思います。ご検討いただけましたら幸いです。
その際、ブリュノ・クレールがモレ=サン=ドニのボンヌ=マールを継承し、バールがそれ以外のシャンボール側にあるボンヌ=マールを・・結果的にいただいた訳ですね。
ブリュノ・クレールのボンヌ=マールは承継後、色々有ってフォジュレイ・ド・ボークレールが借りて造っていました。こちらはモレに有りますから・・シャンボール側に有る大半のボンヌ=マールとはだいぶ味わいが違ったと・・言われています。noisy もそのボークレールのボンヌ=マールを販売したことが有り、飲んでもいますが・・これも硬かったですね~。
・・そもそもボンヌ=マールと言うワインは、
「ミュジニー並みの長命なワインで飲むタイミングが難しい。ミュジニーが若くして素晴らしい芳香を放出していてもボンヌ=マールはほぼ閉じたまま。しかしミュジニーが開く前にボンヌ=マールは飲み頃を迎えて長く持続する。」
と言われていたと思いますし、noisy もそれをほぼ確認しています。
ですが昨今の濃密な味わいに仕上げたボンヌ=マールは決してそんなことは無く、早い段階からそこそこに美味しく飲めてしまいます。近代的な技術の進歩も有り、温暖化の影響もあり・・と言うことなのかもしれません。
しかし・・しかしですよ・・本当にボンヌ=マールがその本性を見せるとするなら・・やはり長い月日を忍耐強く待たなければならないのかな・・とは思っています。
因みにバールのボンヌ=マールは、シャンボールの南側(ヴォギュエとの地所の真上の上部、ルーミエさんの地所のうち最も南側にある部分の上部、ジャック=フレデリック・ミュニエの地所の南側)に大きな区画が1箇所と、ボンヌ=マールの中央に小さな区画が1箇所で、合わせて1ヘクタール以上有る様です。(0.5ヘクタールと言う話も有ります。)
で、La Revue du Vin de France誌が長くこのボンヌ=マールを評価していますので・・とりあえずご覧ください。
2018 17.5/20
2017 18.0/20
2016 19.0/20
2015 19.0/20
2014.18.5/20
2013 18.5/20
2012 18.5/20
2011 17.5/20
2010 18.0/20
2009 ----
2008 17.5/20
2007 16.5/20
2006 15.5/20
2004 16.5/20
2003 16.0/20
2002 17.0/20
2001 15.0/20
どうでしょう?・・20点満点ですが、この20年弱ほどの間に相当評点が上昇しています。
また、ジャスパー・モリスさんに至っては・・2020年ものは上値97ポイント、2019年ものは上値98ポイント、2018年ものは上値97ポイントと・・大変にご執心のようです。ルーミエさんは96~98 Points と言う評価ですからそれに次ぐ高い評価です。
残念ながら2本だけの入荷ですので飲む訳にも行かなくて残念ですが・・まだまだリーズナブルなのかな・・と思います。ご検討いただけましたら幸いです。
ドメーヌ・シュヴィニー=ルソー
シュヴィニー=ルソー
フランス Domaine Chevigny-Rousseau ブルゴーニュ
● いや~・・ビックリしました!・・2022年もののシュヴィニー=ルソーですよ・・。思わずフィネスさんの担当さんに電話してしまった位ですから・・はい。
シュヴィニー=ルソーってピュアで一途、ナチュール感もふんわり感も有って美味しいんですが、何と言いますか・・
「どこか漂っている愛想の少なさ」
が、飲むタイミングにより感じられるのがね・・と思っていた訳です。
 ところがですね・・これもフィネスマジックなんでしょうかね。いや、フィネスさんのワイン、新入荷で入って来て何年かで大化けすることが結構にして有るんですが、それを noisy は勝手にそう呼んでいるんですね。
ところがですね・・これもフィネスマジックなんでしょうかね。いや、フィネスさんのワイン、新入荷で入って来て何年かで大化けすることが結構にして有るんですが、それを noisy は勝手にそう呼んでいるんですね。
「美味しくなってからリリースする主義のシュヴィニー=ルソーが仕上げてすぐの2022年ものを数アイテムリリースしてきた!」
ので飲んでみると、
「レ・シャン・ペルドリ2022年の、信じられないようなパフォーマンス!」
に・・驚かされたんですね。左の写真をご覧ください。この色彩!・・村名の訳が無い・・そう見えませんか?・・ルーミエさんの1級をややタイトにドライに・・もしくはシルヴァン・パタイユが乗り移ったか?・・(^^;;
まぁ・・本来は、1級オ・レイニョとラ・ターシュに接した畑です・・ラ・ロマネもロマネ=コンティもすぐそこですから、村名格がオカシイ位の畑な訳です。でも、一向に凄いレ・シャン・ペルドリに出会わない・・一番うまいのはシュヴィニー・ルソーでしたが・・
で、その村名レ・シャン・ペルドリはとんでもなく旨いし、村名ヴォーヌ=ロマネも素晴らしいので、今回リリースになった2022年ものの1級も飲みたかったんですがすべて2本ほどの入荷・・・実際には確かめきれませんでした。
ですが、
「2022年のシュヴィニ=ルソーは絶対に買い!」
と言う気持ちを萎えさせる証拠はどこにも無く、ほぼ同時期に飲ませていただいた2018年もの、2019年ものも・・今までの「愛想の少なさ」が感じられず、
「・・あれ?・・これって・・ドメーヌが変わったか、フィネスマジックか?」
と・・完全には結論が出せずにいます。
今回は2019年もののレ・ルージュ・デュ・バのエシェゾーも開けさせていただきました。お楽しみいただけましたら幸いです。
■ ドメーヌより
2022年は太陽の年と言っても過言ではないヴィンテージで、春から暑く乾燥し、夏はさらに暑く日照量が多かった。ただ、暑さの影響でいくつかの区画では日焼けなどの被害もあったが、我々の畑では葡萄の根が深くまで伸びているので夏の水不足のストレスを受けることがなく、成熟は素晴らしいものになった。色調は濃く深いガーネット色、良く熟した赤い果実のアロマと新樽由来のバニラ香、口当たりは力強いが丸みがありスパイシーな果実味、飲みやすくて食欲をそそるような味わいでとてもバランスが取れている。早くから飲めるが長く熟成することもできるだろう。
-----
シュヴィニー・ルソーです。noisy も20年ぶりに再会したドメーヌです。なので、
「どんな造り手さんだったか?」
が今ひとつピンと来ておらず、お客様も少しどうして良いか・・どんなワインなのか今ひとつ判らずに狼狽?しているかのような感じに思えていました。
ですので、ここは気合を入れて・・何とエシェゾー2018年まで開けて・・確信を持ってご紹介させていただきます。
脱線の上、超昔の話しで恐縮ですが、たまたま昔のデータをみつけて見ていて・・大昔にル・テロワールさんが輸入し、最後に会社を整理する時の処分ものだったかと思いますが、・・なんとヴォーヌ=ロマネ・シャン・ペルドリ2000年を、3060円で販売していました・・いや~・・今なら「是非とも売ってくれ!」と言いたいほどとんでもない価格です。
白はリュリー、ムルソー、赤は数種類飲ませていただきました。兎に角入荷してきているヴィンテージがバラバラで、テイスティングも相当に「リキ」を入れないと正確な判断がし辛かったシュヴィニー・ルソーですが、ここへ来てヴィンテージも揃いはじめまして、ようやくnoisy的にも理解が深まった・・その上での判断が出来たと思っています。
独断的に・・言い切ってしまうとこんな印象になります。
「古き良き時代のブルゴーニュワインを現代によみがえらせたような、ピュアで繊細・・新樽の強い効果に重きを置かない煌びやかで美しい果実酸の美味しいエキス系の味わいでリリースしているドメーヌ」
と言えるかと思います。まぁ、そうは言っても新樽を使用していない訳では無く、90年代のように、全てのキュヴェに新樽を用いるようなスタイルでは無い・・と言うことですね。
そしてそもそも自然派ですから、アロマが素晴らしい・・スピードも速く繊細で伸びやかです。クラシカルな味わいですが、自然派のアプローチで非常に美しいです。
例えば、エマニュエル・ルジェは御大の教えを守っていますから、醸造前の低温の漬け込みと「新樽」由来の効果をバッチリ・・最大限に利用した、「リリース時からも官能的なあじわい」を持っていますが、シュヴィニー・ルソーは全くの真逆です。
どこまでも純な果実の美しさを基調とした、ブルゴーニュの葡萄の美しい表現に手を加えることなく、その上で自然に任せた醸造をしていると言えます。
そう・・そんな造り手が、今のブルゴーニュにどれだけいるでしょうか?・・ほとんどいないと言っても過言では有りません。
「エシェゾーはどこまでも純粋で、汚れ無き美しさを持っている!」
と書くつもりでいますが、それを信じられますか?・・中々難しいでしょう?・・そう、どこまでも美しくたなびく味わいなんですね・・。ルジェとは真逆のスタイルですが、「時間と言う魔術師」の作用で、最終的にはかなり似てくるのも間違いないでしょう。
「どのタイミングで飲むか?」
で、大きく印象が変わってくるはずです。
面白いのはマリアージュにおいてです・・どうしても新樽の大きな影響を得たブルゴーニュワインに慣れている我々は、
「すでにその新樽系の味わい、香りをイメージした上でのマリアージュを考えてしまっている。」
「新樽系の影響の少ない、美しい果実を表現した昔のブルゴーニュワインは、そのイメージとは全く別のマリアージュをする。」
と言えるのが、このシュヴィニー・ルソーを飲みながら食事をすると伝わって来ます。
ですので、合わないと単純に考えてしまうような、例えば「魚とピノ・ノワール」でも、見事なマリアージュをする場面にも出くわします。
それに、飲み進めるにしたがい、食べ進めるにしたがって・・
「シュヴィニー・ルソーのワインも滅茶苦茶美味しくなってくる」
ことがお判りになるかと思うんですね。
ワイン単体での素晴らしさは、抜栓直後はルジェのワインには全く適わないでしょう。ですが、食事と一緒に飲み進めて行くと・・「・・あれっ?」と・・気付くはずです。
「・・このワイン、もしかしたら・・もの凄いワインじゃないだろうか・・」
と。
素の姿はおそらくエマニュエル・ルジェと大差ないと思います。しかし、抜栓してグラスに注いだシュヴィニー・ルソーのワインの姿は、エマニュエル・ルジェとは全く違う振る舞いを見せます。
グラン=ゼシェゾーまでは開けられませんでしたが、
「心底ピュアで純な、クラシカルだが今でも美味しさを理解できる見事な味わい!」
と言いたいと思います。
現在のワインの志向を見ると、いつかこんなピュア・ブルゴーニュが世界を席巻することになるやもしれません。言ってみれば、ヴァーゼンハウスをさらに凝縮・集中させたようなスタイルです。美しさは全く同様・・でしょう。
是非一度、この美しさ、ピュアさ、クラシカルな美味しさに触れてみて下さい。お勧めします。
フィネスさんが初めて輸入された期待のヴォーヌ=ロマネ本拠のドメーヌ、「ドメーヌ・シュヴィニー=ルソー」をご紹介させていただきます。すでにネットの世界では評判になっているようで、どこのサイトを見ても「完売」か、カートに商品の数を入れられないと言う、凄い状態です。
まぁ、このような場合は大抵、Noisy wine は「ネットのワイン屋の中でドンケツ」のご紹介になってしまうのが常でして・・何せ、ただでさえテイスティング・アイテムの大行列の交通整理をしなければならない状況の中に、「新しい扱いの生産者さん」のワインがその行列を伸ばしてくれますので、そうなってしまうんですね。いや、むしろ、それで「完売」のオンパレードに出来てしまう・・と言うワイン屋さんの底力に驚いています。
Noisy wine もこの「シュヴィニー=ルソー」は初めての扱いになりますが・・いや・・ホントかぁ?・・(^^;;
実はかれこれ四半世紀前ほど遡りますが、今はラシーヌを経営されていらっしゃる合田泰子さん、塚原正章さんが、その前にやられていた伝説のインポーターさん、「ル・テロワール」さんの時代に、noisy も扱わせていただいていました。
最も・・ドメーヌ名が少し変わっておりまして、その頃は「ドメーヌ・パスカル・シュヴィニー」と名乗っていらしたんですね。なので、昨年の晩夏位に担当の K君から「シュヴィニー=ルソー」の話しを聞かせて貰った時には、しばらくの間、思い出せなかったんですね。遠い記憶を探って、
「・・・シュヴィニ―?・・ルソー・・?・・シュヴィニ―・・。・・あ、パスカル・シュヴィニー!!」
と、やっとの思いで記憶の蓋をこじ開けることが出来ました。
酒質は、その頃のパスカル・シュヴィニーをハッキリとは思い出せませんでしたが、
「濃厚・濃密・新樽100%」
の時代に迎合することなく、エレガント系・エキス系のドライなヴォーヌ=ロマネ等をリリースしていた・・と思います。
久しぶりに飲んだパスカル・シュヴィニーは、やはり昔扱った頃のイメージと似たニュアンスが有ったのでしょう・・
「決して濃い系では無い・・果実味たっぷり型でも無い。集中しているが、決して意図的に濃くしようとはしない。エレガンス重視の重さを感じさせない味わい」
でした。
また、ナチュラルさはその頃には無かった、もしくはnoisy にまだ感じ取る能力が無かった・・のかもしれませんが、1990年代の比では無いほどに有機的でナチュラル感も有ります。そして決して「アヴァンギャルドな攻めたナチュール」では有り得ず、ピュアさをたっぷり感じるものです。
その上で、古き良きブルゴーニュワインのニュアンスも感じます。「葡萄に無理強いしない」「無理に抽出しない」「化粧を濃くしない」を見事に守っていると感じました。
それでいて、アイテムのリリースは順番では無く、「リリースして良いと思ったら出荷する」そうでして、今回のラインナップをご覧いただきましても、見事にバラバラですよね。
今回は全9アイテム中、トップ・キュヴェのグラン=ゼシェゾーのみテイスティングできませんでした。8アイテムのテイスティングをさせていただき、その、
「超エレガントなヴォーヌ=ロマネの世界」
を感じさせていただきました。是非ご検討いただけましたら幸いです。
なお、非常にエレガントな味わいですので、
「ワインのサービス時の品温」
にご注意くださいませ。
決して冷えて冷たい状態で飲み始めないように・・特にバックヴィンテージは、15度以上まで品温を上げてから、もしくはこの冬の時期には、温めた室温に馴染ませてから飲み始めてください。どうぞよろしくお願いいたします。
■造り手情報

第2次世界大戦後の1947年にルシアン・シュヴィニーがヴォーヌ=ロマネの「Aux Champs Perdrix(オー・シャン・ペルドゥリ)」の区画に葡萄を植えたのがこのドメーヌの始まりで、3代目となる現当主のパスカル・シュヴィニーは父ミッシェルから1984年にドメーヌを引き継ぎました。
ドメーヌ名はパスカルの父方の苗字「Chevigny(シュヴィニー)」と母方の苗字「Rousseau(ルソー)」を掛け合わせたもので、現在はコート・ド・ニュイを中心に約4haの葡萄畑を所持しています。リュットレゾネで栽培を行っていますが、HVE 認証という葡萄栽培から瓶詰に至るまで、より厳しく環境のことを考えて活動している生産者に与えられる認証を得ており、高い品質のワイン造りを目指しています。
ワインの販売については、ドメーヌで瓶熟させながら飲み始めても良いなと思ったヴィンテージをリリースできるように努めています。
 葡萄の収穫は手摘みで除梗100%、アルコール醗酵は自然酵母で櫂入れと液循環を行いながら最高30℃で10~15日間行います。熟成は樫樽でブルゴーニュ・クラスは12ヵ月、それ以外は約18ヵ月間行います。新樽比率はヴィンテージにもよりますが、ブルゴーニュで約25%、それ以外は約80%ほど、グラン・エシェゾーのみ100%にすることもあります。瓶詰前にコラージュのみを行い、ノンフィルターで瓶詰されています。
葡萄の収穫は手摘みで除梗100%、アルコール醗酵は自然酵母で櫂入れと液循環を行いながら最高30℃で10~15日間行います。熟成は樫樽でブルゴーニュ・クラスは12ヵ月、それ以外は約18ヵ月間行います。新樽比率はヴィンテージにもよりますが、ブルゴーニュで約25%、それ以外は約80%ほど、グラン・エシェゾーのみ100%にすることもあります。瓶詰前にコラージュのみを行い、ノンフィルターで瓶詰されています。
シュヴィニー=ルソーってピュアで一途、ナチュール感もふんわり感も有って美味しいんですが、何と言いますか・・
「どこか漂っている愛想の少なさ」
が、飲むタイミングにより感じられるのがね・・と思っていた訳です。
 ところがですね・・これもフィネスマジックなんでしょうかね。いや、フィネスさんのワイン、新入荷で入って来て何年かで大化けすることが結構にして有るんですが、それを noisy は勝手にそう呼んでいるんですね。
ところがですね・・これもフィネスマジックなんでしょうかね。いや、フィネスさんのワイン、新入荷で入って来て何年かで大化けすることが結構にして有るんですが、それを noisy は勝手にそう呼んでいるんですね。「美味しくなってからリリースする主義のシュヴィニー=ルソーが仕上げてすぐの2022年ものを数アイテムリリースしてきた!」
ので飲んでみると、
「レ・シャン・ペルドリ2022年の、信じられないようなパフォーマンス!」
に・・驚かされたんですね。左の写真をご覧ください。この色彩!・・村名の訳が無い・・そう見えませんか?・・ルーミエさんの1級をややタイトにドライに・・もしくはシルヴァン・パタイユが乗り移ったか?・・(^^;;
まぁ・・本来は、1級オ・レイニョとラ・ターシュに接した畑です・・ラ・ロマネもロマネ=コンティもすぐそこですから、村名格がオカシイ位の畑な訳です。でも、一向に凄いレ・シャン・ペルドリに出会わない・・一番うまいのはシュヴィニー・ルソーでしたが・・
で、その村名レ・シャン・ペルドリはとんでもなく旨いし、村名ヴォーヌ=ロマネも素晴らしいので、今回リリースになった2022年ものの1級も飲みたかったんですがすべて2本ほどの入荷・・・実際には確かめきれませんでした。
ですが、
「2022年のシュヴィニ=ルソーは絶対に買い!」
と言う気持ちを萎えさせる証拠はどこにも無く、ほぼ同時期に飲ませていただいた2018年もの、2019年ものも・・今までの「愛想の少なさ」が感じられず、
「・・あれ?・・これって・・ドメーヌが変わったか、フィネスマジックか?」
と・・完全には結論が出せずにいます。
今回は2019年もののレ・ルージュ・デュ・バのエシェゾーも開けさせていただきました。お楽しみいただけましたら幸いです。
■ ドメーヌより
2022年は太陽の年と言っても過言ではないヴィンテージで、春から暑く乾燥し、夏はさらに暑く日照量が多かった。ただ、暑さの影響でいくつかの区画では日焼けなどの被害もあったが、我々の畑では葡萄の根が深くまで伸びているので夏の水不足のストレスを受けることがなく、成熟は素晴らしいものになった。色調は濃く深いガーネット色、良く熟した赤い果実のアロマと新樽由来のバニラ香、口当たりは力強いが丸みがありスパイシーな果実味、飲みやすくて食欲をそそるような味わいでとてもバランスが取れている。早くから飲めるが長く熟成することもできるだろう。
-----
シュヴィニー・ルソーです。noisy も20年ぶりに再会したドメーヌです。なので、
「どんな造り手さんだったか?」
が今ひとつピンと来ておらず、お客様も少しどうして良いか・・どんなワインなのか今ひとつ判らずに狼狽?しているかのような感じに思えていました。
ですので、ここは気合を入れて・・何とエシェゾー2018年まで開けて・・確信を持ってご紹介させていただきます。
脱線の上、超昔の話しで恐縮ですが、たまたま昔のデータをみつけて見ていて・・大昔にル・テロワールさんが輸入し、最後に会社を整理する時の処分ものだったかと思いますが、・・なんとヴォーヌ=ロマネ・シャン・ペルドリ2000年を、3060円で販売していました・・いや~・・今なら「是非とも売ってくれ!」と言いたいほどとんでもない価格です。
白はリュリー、ムルソー、赤は数種類飲ませていただきました。兎に角入荷してきているヴィンテージがバラバラで、テイスティングも相当に「リキ」を入れないと正確な判断がし辛かったシュヴィニー・ルソーですが、ここへ来てヴィンテージも揃いはじめまして、ようやくnoisy的にも理解が深まった・・その上での判断が出来たと思っています。
独断的に・・言い切ってしまうとこんな印象になります。
「古き良き時代のブルゴーニュワインを現代によみがえらせたような、ピュアで繊細・・新樽の強い効果に重きを置かない煌びやかで美しい果実酸の美味しいエキス系の味わいでリリースしているドメーヌ」
と言えるかと思います。まぁ、そうは言っても新樽を使用していない訳では無く、90年代のように、全てのキュヴェに新樽を用いるようなスタイルでは無い・・と言うことですね。
そしてそもそも自然派ですから、アロマが素晴らしい・・スピードも速く繊細で伸びやかです。クラシカルな味わいですが、自然派のアプローチで非常に美しいです。
例えば、エマニュエル・ルジェは御大の教えを守っていますから、醸造前の低温の漬け込みと「新樽」由来の効果をバッチリ・・最大限に利用した、「リリース時からも官能的なあじわい」を持っていますが、シュヴィニー・ルソーは全くの真逆です。
どこまでも純な果実の美しさを基調とした、ブルゴーニュの葡萄の美しい表現に手を加えることなく、その上で自然に任せた醸造をしていると言えます。
そう・・そんな造り手が、今のブルゴーニュにどれだけいるでしょうか?・・ほとんどいないと言っても過言では有りません。
「エシェゾーはどこまでも純粋で、汚れ無き美しさを持っている!」
と書くつもりでいますが、それを信じられますか?・・中々難しいでしょう?・・そう、どこまでも美しくたなびく味わいなんですね・・。ルジェとは真逆のスタイルですが、「時間と言う魔術師」の作用で、最終的にはかなり似てくるのも間違いないでしょう。
「どのタイミングで飲むか?」
で、大きく印象が変わってくるはずです。
面白いのはマリアージュにおいてです・・どうしても新樽の大きな影響を得たブルゴーニュワインに慣れている我々は、
「すでにその新樽系の味わい、香りをイメージした上でのマリアージュを考えてしまっている。」
「新樽系の影響の少ない、美しい果実を表現した昔のブルゴーニュワインは、そのイメージとは全く別のマリアージュをする。」
と言えるのが、このシュヴィニー・ルソーを飲みながら食事をすると伝わって来ます。
ですので、合わないと単純に考えてしまうような、例えば「魚とピノ・ノワール」でも、見事なマリアージュをする場面にも出くわします。
それに、飲み進めるにしたがい、食べ進めるにしたがって・・
「シュヴィニー・ルソーのワインも滅茶苦茶美味しくなってくる」
ことがお判りになるかと思うんですね。
ワイン単体での素晴らしさは、抜栓直後はルジェのワインには全く適わないでしょう。ですが、食事と一緒に飲み進めて行くと・・「・・あれっ?」と・・気付くはずです。
「・・このワイン、もしかしたら・・もの凄いワインじゃないだろうか・・」
と。
素の姿はおそらくエマニュエル・ルジェと大差ないと思います。しかし、抜栓してグラスに注いだシュヴィニー・ルソーのワインの姿は、エマニュエル・ルジェとは全く違う振る舞いを見せます。
グラン=ゼシェゾーまでは開けられませんでしたが、
「心底ピュアで純な、クラシカルだが今でも美味しさを理解できる見事な味わい!」
と言いたいと思います。
現在のワインの志向を見ると、いつかこんなピュア・ブルゴーニュが世界を席巻することになるやもしれません。言ってみれば、ヴァーゼンハウスをさらに凝縮・集中させたようなスタイルです。美しさは全く同様・・でしょう。
是非一度、この美しさ、ピュアさ、クラシカルな美味しさに触れてみて下さい。お勧めします。
フィネスさんが初めて輸入された期待のヴォーヌ=ロマネ本拠のドメーヌ、「ドメーヌ・シュヴィニー=ルソー」をご紹介させていただきます。すでにネットの世界では評判になっているようで、どこのサイトを見ても「完売」か、カートに商品の数を入れられないと言う、凄い状態です。
まぁ、このような場合は大抵、Noisy wine は「ネットのワイン屋の中でドンケツ」のご紹介になってしまうのが常でして・・何せ、ただでさえテイスティング・アイテムの大行列の交通整理をしなければならない状況の中に、「新しい扱いの生産者さん」のワインがその行列を伸ばしてくれますので、そうなってしまうんですね。いや、むしろ、それで「完売」のオンパレードに出来てしまう・・と言うワイン屋さんの底力に驚いています。
Noisy wine もこの「シュヴィニー=ルソー」は初めての扱いになりますが・・いや・・ホントかぁ?・・(^^;;
実はかれこれ四半世紀前ほど遡りますが、今はラシーヌを経営されていらっしゃる合田泰子さん、塚原正章さんが、その前にやられていた伝説のインポーターさん、「ル・テロワール」さんの時代に、noisy も扱わせていただいていました。
最も・・ドメーヌ名が少し変わっておりまして、その頃は「ドメーヌ・パスカル・シュヴィニー」と名乗っていらしたんですね。なので、昨年の晩夏位に担当の K君から「シュヴィニー=ルソー」の話しを聞かせて貰った時には、しばらくの間、思い出せなかったんですね。遠い記憶を探って、
「・・・シュヴィニ―?・・ルソー・・?・・シュヴィニ―・・。・・あ、パスカル・シュヴィニー!!」
と、やっとの思いで記憶の蓋をこじ開けることが出来ました。
酒質は、その頃のパスカル・シュヴィニーをハッキリとは思い出せませんでしたが、
「濃厚・濃密・新樽100%」
の時代に迎合することなく、エレガント系・エキス系のドライなヴォーヌ=ロマネ等をリリースしていた・・と思います。
久しぶりに飲んだパスカル・シュヴィニーは、やはり昔扱った頃のイメージと似たニュアンスが有ったのでしょう・・
「決して濃い系では無い・・果実味たっぷり型でも無い。集中しているが、決して意図的に濃くしようとはしない。エレガンス重視の重さを感じさせない味わい」
でした。
また、ナチュラルさはその頃には無かった、もしくはnoisy にまだ感じ取る能力が無かった・・のかもしれませんが、1990年代の比では無いほどに有機的でナチュラル感も有ります。そして決して「アヴァンギャルドな攻めたナチュール」では有り得ず、ピュアさをたっぷり感じるものです。
その上で、古き良きブルゴーニュワインのニュアンスも感じます。「葡萄に無理強いしない」「無理に抽出しない」「化粧を濃くしない」を見事に守っていると感じました。
それでいて、アイテムのリリースは順番では無く、「リリースして良いと思ったら出荷する」そうでして、今回のラインナップをご覧いただきましても、見事にバラバラですよね。
今回は全9アイテム中、トップ・キュヴェのグラン=ゼシェゾーのみテイスティングできませんでした。8アイテムのテイスティングをさせていただき、その、
「超エレガントなヴォーヌ=ロマネの世界」
を感じさせていただきました。是非ご検討いただけましたら幸いです。
なお、非常にエレガントな味わいですので、
「ワインのサービス時の品温」
にご注意くださいませ。
決して冷えて冷たい状態で飲み始めないように・・特にバックヴィンテージは、15度以上まで品温を上げてから、もしくはこの冬の時期には、温めた室温に馴染ませてから飲み始めてください。どうぞよろしくお願いいたします。
■造り手情報

第2次世界大戦後の1947年にルシアン・シュヴィニーがヴォーヌ=ロマネの「Aux Champs Perdrix(オー・シャン・ペルドゥリ)」の区画に葡萄を植えたのがこのドメーヌの始まりで、3代目となる現当主のパスカル・シュヴィニーは父ミッシェルから1984年にドメーヌを引き継ぎました。
ドメーヌ名はパスカルの父方の苗字「Chevigny(シュヴィニー)」と母方の苗字「Rousseau(ルソー)」を掛け合わせたもので、現在はコート・ド・ニュイを中心に約4haの葡萄畑を所持しています。リュットレゾネで栽培を行っていますが、HVE 認証という葡萄栽培から瓶詰に至るまで、より厳しく環境のことを考えて活動している生産者に与えられる認証を得ており、高い品質のワイン造りを目指しています。
ワインの販売については、ドメーヌで瓶熟させながら飲み始めても良いなと思ったヴィンテージをリリースできるように努めています。
 葡萄の収穫は手摘みで除梗100%、アルコール醗酵は自然酵母で櫂入れと液循環を行いながら最高30℃で10~15日間行います。熟成は樫樽でブルゴーニュ・クラスは12ヵ月、それ以外は約18ヵ月間行います。新樽比率はヴィンテージにもよりますが、ブルゴーニュで約25%、それ以外は約80%ほど、グラン・エシェゾーのみ100%にすることもあります。瓶詰前にコラージュのみを行い、ノンフィルターで瓶詰されています。
葡萄の収穫は手摘みで除梗100%、アルコール醗酵は自然酵母で櫂入れと液循環を行いながら最高30℃で10~15日間行います。熟成は樫樽でブルゴーニュ・クラスは12ヵ月、それ以外は約18ヵ月間行います。新樽比率はヴィンテージにもよりますが、ブルゴーニュで約25%、それ以外は約80%ほど、グラン・エシェゾーのみ100%にすることもあります。瓶詰前にコラージュのみを行い、ノンフィルターで瓶詰されています。
●
2021 Bourgogne Rouge
ブルゴーニュ・ルージュ
【とことんまでピュア!で繊細なエキスを感じさせてくれるブルゴーニュ唯一のドメーヌのA.C.ブル!静かに燃える水のようなワインです。】
 水は燃えません・・と言われてしまいそうですが・・(^^;; 水素も酸素も燃えますからご容赦ください。
水は燃えません・・と言われてしまいそうですが・・(^^;; 水素も酸素も燃えますからご容赦ください。と言いますか、そもそもがこのシュヴィニー=ルソーのワインは滅茶瑞々しく、でもエキスが凄く濃い・・なんては感じないですよね。とことんまでピュアで滑らか、そして他に有り得ないほどのドライさです。
昨年は2019年ものをご案内しているので2020年ものが届くかと思いきや、
「おそらく2020年はドメーヌ側ではまだ仕上がっていないと言う判断」
だと思うんですね。
2021年ものを出して来た理由としては、
「そろそろ飲み始めて良いと言う判断」
と言うことなんでしょう。
ノーズは柔らかさを感じつつもミネラリティのツヤツヤとした薄いカバーがあるようなニュアンスと、赤黒なベリー、チェリーのピュアなニュアンス。
口に含むとドライなチェリー感、膨らみ切らないものの、やがて僅かに解れだします。
 そこからはまぁ・・例えば何かお料理を口にしますと、その料理の塩分やミネラリティと、何とも表現のし辛い・・マッチングを見せて来ます。
そこからはまぁ・・例えば何かお料理を口にしますと、その料理の塩分やミネラリティと、何とも表現のし辛い・・マッチングを見せて来ます。するとどうでしょう。エキスの旨味が浮かび上がって来て、ピュアで繊細な果実の風味と旨味、ブルゴーニュ・ピノ・ノワールらしいエレガンスが劇的に増大して来て、その料理の味わいをグッと盛り上げてくれるんですね。
そして面白いのは、赤ワインだから・・と言うことで肉料理に合うだけでなく、魚系の料理にも非常に相性が良く、料理に効かせた適度な塩分、その料理の味わいと反応して、さらにワインも料理も輝きを増して行く感じに思います。
これはおそらく、シュヴィニー=ルソーのワインが非常にピュアで余り酸化をさせていないこと、マロラクティックも深くは無く、適度に明るい色彩の酸が残存している性では無いかな・・と思っています。
2021年のシュヴィニー=ルソーのワインは、他のコラムでも書きましたがまったくネガティヴさを感じないワインで、ピノ・ノワールらしいハツラツとした部分と滑らかさ、高貴さとエレガンスに長けたワインです。強い力は感じないが、不足感の全く無い見事な味わいです。是非飲んでみてください。水が・・静かに燃えているようなイメージです・・(^^;;
以下は以前のレヴューです。
-----
【2019年と言うヴィンテージの素晴らしさをそのままに、シュヴィニー=ルソー特有のエレガンスも具現化した見事な味わいです!】
 (2度目の入荷です。以前の入荷分よりも明らかに素晴らしい出来で・・ビックリしました。価格は一気に上がりました・・ですが、それだけの価値はあると思います。)
(2度目の入荷です。以前の入荷分よりも明らかに素晴らしい出来で・・ビックリしました。価格は一気に上がりました・・ですが、それだけの価値はあると思います。)このA.C.ブルは本当に素晴らしいです!・・今、最高に美味しい!・・勿論、これからも熟した美味しさを徐々に増して来るとは思いますが、
「シュヴィニー=ルソーのスタイルを知る!」
には最高のアイテムかと思います。
この色・・そこそこに濃密にさえ、見えるんじゃないかと思いますが・・どうでしょう?
でも決して濃くなど無いんですよ。張りのある・・徐々に膨張して行こうとする意志のようなものさえ感じるほどですが、さらりとしていて、非常にドライ・・しかもピュアだけに留まらず、そこはかと無く漂うナチュラルさがまた素晴らしいんですね・・。
これはやはり、シュヴィニー=ルソーのスタイルと、2019年の「健康的で優良な作柄」が生み出したマジックなのかもしれません。
そして面白いのは、昨夏、フィネスさんでテイスティングした時には、2018年ものが滅茶苦茶美味しく、この2019年のようだったと・・言う事と、2019年ものはまだやや酸っぱく、仕上がり切っていなかったそうなんですね。まぁ、2019年のミレジメで2020年の夏のサンプル・テイスティングですから、そのように感じられるのも間違いない事象だったでしょう。約半年の時間を経て、ちょうど仕上がったタイミングだと思います。
また、「エレガンス」と言う点でもそこは面白いですね。マロラクティックをキツクし無い・・と想像出来ますが、この点は何年か見ないとハッキリは言えませんので、今後の課題とさせてください。
兎に角、今飲んでとてもシュヴィニー=ルソーに対する理解が得られるのはA.C.ブル2019年・・そして2018年です。2018年ものについてはそちらのコラムに記載しますのでよろしくお願いいたします。是非飲んでみて下さい!超お勧めです!
●
2018 Nuits-Saint-Georges
ニュイ=サン=ジョルジュ
【ほぼほぼ完熟!?・・あと少し??・・シュヴィニー=ルソーのワインの熟し始めの美味しさを堪能できる、シュヴィニー=ルソーらしいピュアで繊細な表情です!】
 いや~・・良いですね・・旨いです。ちょうど良い熟・・と思うか、あと少し待った方が良かったか・・その辺りは飲まれる方によって、好みにより判断は変わるかと思えるタイミングです。
いや~・・良いですね・・旨いです。ちょうど良い熟・・と思うか、あと少し待った方が良かったか・・その辺りは飲まれる方によって、好みにより判断は変わるかと思えるタイミングです。今回は同時にご案内の2010年ものも有りますので、ピノ・ノワールの、ニュイ=サン=ジョルジュの熟成を理解するのにも良い教材になるかな・・と思います。noisy はさすがに2010年もののニュイ=サン=ジョルジュ村名までは開けられませんでした。
まぁ・・2019年のエシェゾーまで開けちゃいましたので鼻血が止まらない状態ですのでご容赦くださいませ。
ニュイ=サン=ジョルジュ的な温かさと土のニュアンス、その割にはハードなミネラリティも奥に持っている感じのニュイ=サン=ジョルジュ村名です。しかし、
「土むさく無い」
です。美しい土です。やや茶色掛かった明るい感じの土です。フラワリーさが無くなり、赤い果実がしっかり、そこにおだやかなスパイスが載り、コーヒーっぽい感じや土、そしてその粘性も感じます。
1級までは行かない感じですがピュアで「はんなり」と上品で、ニュイ=サン=ジョルジュ村名には余り感じることの無い繊細な上品さが有ります。
 2018年ものですから収穫から6年目ですので、
2018年ものですから収穫から6年目ですので、「そろそろ良いだろう」
とは思えるものの、実際に手にしてみると・・
「やっぱりもう少し・・待つか?」
と悩むタイミングですよね・・6年は。
実際に開けてみると、
「まさにそのような感じ!」
のタイミングでして、
「若目のピノがお好きな方はほぼドンピシャリ!」
じゃないでしょうか。
熟し気味の方がお好みの方は、あと1年位でしょうか。完熟してトロットロまで待ちたいならあと3~4年、ピーク過ぎのとんでもなく透明感が出てパキーンとしたニュイ=サン=ジョルジュが飲みたいようでしたら・・14~15年・・(^^;; まぁ、思っているよりワインの寿命は長いです。10年でダメになると思っている海外メディアは信用しないでください。お薦めです!
以下は2009年もののレヴューです。
-----
【良い感じに熟した2009年!是非、品温を上げて、この熟してから見せるエレガンスを楽しんでください!】
 2009年ものです。もう・・何とも言えない見事な熟です。ニュイらしい土っぽさと、むしろ優しさの有る温かみ、ふんわり感さえあるミネラリティが一緒になって口内に入り、まるでそこで分解されるように味蕾を刺激してくれます。
2009年ものです。もう・・何とも言えない見事な熟です。ニュイらしい土っぽさと、むしろ優しさの有る温かみ、ふんわり感さえあるミネラリティが一緒になって口内に入り、まるでそこで分解されるように味蕾を刺激してくれます。最も・・これは冷えてたら判り辛いかもしれないと思います。12~13度の品温では、何せ「超ドライ」ですし、「超エレガント」ですから台無しになってしまいます。
「2009年ものだから・・甘さも有るでしょう?」
と思われるかもしれませんが、熟して酸がさらに丸くなって、落ち着いて来ての「エキスの甘さ」だけですから、それに、ニュイの北側の「サン=ジュリアン」と言う畑もまた・・非常にエレガントで美しい味わいを見せるんですが、派手さはまず出てこない畑です。そして、レ・シャルモワもどちらかと言いますと「温かみのある優しい味わい」で、土むさい感じは出にくい・・そう感じています。なので是非とも15~16度まで品温を上げる努力をしてくださいね。
そしてまた、このワインも13度と言うアルコール分です。超エレガントなニュイ=サン=ジョルジュ・・・飲んでみたいと思いませんか?・・ご検討くださいませ。
●
2010 Nuits-Saint-Georges Vieilles Vignes
ニュイ=サン=ジョルジュ・ヴィエイユ・ヴィーニュ
【良い感じに熟した2009年!是非、品温を上げて、この熟してから見せるエレガンスを楽しんでください!】-----2009年もののレヴューです。
 2009年ものです。もう・・何とも言えない見事な熟です。ニュイらしい土っぽさと、むしろ優しさの有る温かみ、ふんわり感さえあるミネラリティが一緒になって口内に入り、まるでそこで分解されるように味蕾を刺激してくれます。
2009年ものです。もう・・何とも言えない見事な熟です。ニュイらしい土っぽさと、むしろ優しさの有る温かみ、ふんわり感さえあるミネラリティが一緒になって口内に入り、まるでそこで分解されるように味蕾を刺激してくれます。最も・・これは冷えてたら判り辛いかもしれないと思います。12~13度の品温では、何せ「超ドライ」ですし、「超エレガント」ですから台無しになってしまいます。
「2009年ものだから・・甘さも有るでしょう?」
と思われるかもしれませんが、熟して酸がさらに丸くなって、落ち着いて来ての「エキスの甘さ」だけですから、それに、ニュイの北側の「サン=ジュリアン」と言う畑もまた・・非常にエレガントで美しい味わいを見せるんですが、派手さはまず出てこない畑です。そして、レ・シャルモワもどちらかと言いますと「温かみのある優しい味わい」で、土むさい感じは出にくい・・そう感じています。なので是非とも15~16度まで品温を上げる努力をしてくださいね。
そしてまた、このワインも13度と言うアルコール分です。超エレガントなニュイ=サン=ジョルジュ・・・飲んでみたいと思いませんか?・・ご検討くださいませ。
●
2022 Vosne-Romanee
ヴォーヌ=ロマネ
【ようやっと飲めた村名ヴォーヌ=ロマネ!!・・2022年ものは半端無いです!】
 余りに2022年のレ・シャン・ペリドリが凄いので、やや霞んだトーンでのご案内になるかもしれませんが、いや・・村名でも滅茶美味しいですよ。ただ、まるでヴォーヌ=ロマネ1級格は有るだろう・・と思えるようなレ・シャン・ペルドリの気高さまでには届かないかと・・しかし素晴らしいです。
余りに2022年のレ・シャン・ペリドリが凄いので、やや霞んだトーンでのご案内になるかもしれませんが、いや・・村名でも滅茶美味しいですよ。ただ、まるでヴォーヌ=ロマネ1級格は有るだろう・・と思えるようなレ・シャン・ペルドリの気高さまでには届かないかと・・しかし素晴らしいです。で、2枚目の写真に・・向かって左がレ・シャン・ペルドリ、右がヴォーヌ=ロマネ村名を並べてみました。ちょっと小さいかと思いまして、「大きい写真」の文字をクリックしますと大きめの写真になりますが、
「スマホでアクセスの方は引き延ばした時の画質が良くなるだけ」
だと思いますのでご注意ください。PCでご覧の方は横が800pxのデカい写真になります。
やはりレ・シャン・ペルドリの方がやや涼やかで、透明なミネラル感がビシっと通った感じに見えると思います。村名の方は全体のトーンはヴォーヌ=ロマネ風の暖かさが見えるような色彩でやや赤く、やや淡い?・・同じくらい?でしょうか。
繊細なヴォーヌ=ロマネの表情で、しなやかなテクスチュアから美しい土、ほんのり皮革、スパイス、チェリーのノーズ。良い年を思わせる非常にバランスに優れた味わいで、パレットも美しい円形を見せます。
 大きい写真
大きい写真豊かさやリッチなニュアンスはむしろ村名ヴォーヌ=ロマネに分が有りますが、繊細で冷ややか、質感はやはり・・
「周りの畑の凄さ」
なんでしょうかね・・やはりレ・シャン・ペルドリが真骨頂を発揮します。
まぁ・・こんなに美しいヴォーヌ=ロマネ村名と言うのは、中々に無いと思うんですね。
例えば、あのプティDRCとして思い切り旨いので買ってください・・と言っても売れなかった、ミュヌレ=ジブールのヴォーヌ=ロマネ村名は、
「旨味をしっかり出し、適正な甘みと酸のバランス、全体のバランスに優れた素晴らしいヴォーヌ=ロマネ」
です。
どこが違うか?・・と言いますと・・
「残糖分の少なさ」
でしょう。シュヴィニー=ルソーのブルゴーニュ・ピノ・ノワールは、シャンパーニュ風に言えば「エクストラ・ブリュット」です。
 ですので、通常のヴィンテージですと・・旨味、甘みの点でやや物足りなさを感じるはずなんですね。シュヴィニー=ルソーのワインは、熟しつつ、その旨味を形成して行く、非常にピュアなピノ・ノワールだと言えます。
ですので、通常のヴィンテージですと・・旨味、甘みの点でやや物足りなさを感じるはずなんですね。シュヴィニー=ルソーのワインは、熟しつつ、その旨味を形成して行く、非常にピュアなピノ・ノワールだと言えます。なので、グラスを振りつつ、その酸化を助長しつつ飲みたくなるワインですが、2022年ものは・・そこまで行かず、何もしなくても旨いチェリーが有り、有機物の表情が多彩で美味しく飲めると思います。
2022年のシュヴィニー=ルソー、超お薦めです!ぜひ飲んでみてください。超お薦めします!
●
2019 Grands Echezeaux Grand Cru
グラン=ゼシェゾー・グラン・クリュ
【すみません、今のところ飲めてはいません!・・が、2019年エシェゾーの旨さを見ますと、今飲んでもOKでしょう!】
シュヴィニー=ルソーと言うドメーヌは、ブルゴーニュの中でもキラリと光る独自性を持っていると思うんですね。それが中々評価に繋がらなかったと・・言うことなのかなと思っています。
ですが、2022年もののレ・シャン・ペルドリや村名ヴォーヌ=ロマネを飲みますと、
「・・・これはもう・・時間の問題だけ・・で高く評価されるに違いない!」
と感じます。
はっきり言って、あんなに旨いレ・シャン・ペルドリを飲んだのは初めてです。ラ・タージュ(レ・ゴーディショ)の真上に有りながらも村名に貶められたまま、中々浮上出来ないのも・・
「無理して濃くしようとして失敗している?」
みたいなワインが多いように感じていました。
ですがシュヴィニー=ルソーは、濃くしようとか、淡くしたいとか・・はおそらく考えておらず、自身が思うブルゴーニュのエレガンスを生み出すことだけに集中していると思います。
グラン=ゼシェゾーと言うワインは、綺羅星のようなヴォーヌ=ロマネのアペラシオンの中でも上から5番目ほどです。ぜひご検討いただけましたら幸いです。
以下は以前のレヴューです。
-----
【シュヴィニー=ルソーのトップ・キュヴェです!】
実はまぁ・・コラムには書かないまでも、シュヴィニー=ルソーのテイスティングは結構進めています。例えば・・飲んでいないのでと書いて有る「2019年シャンボール1級レ・コンボット」は飲んでいたりします。でも、正確な分析が出来なかった・・つまり、抜栓して時間が経過してしまったものをテイスティングしたので、他の飲んだアイテムと同列で書いてしまうと齟齬が生じるかと言うことで・・あ、また時間も無いし・・(^^;; ですみません・・ご容赦ください。
ただし、2019年のシャンボール・コンボット!・・旨かったです!・・が、残っていたのが少な過ぎでした。
このグラン=ゼシェゾー2018年は、自身で開けられもせず、開いたボトルを飲むことも出来ず・・でした。でも、
「激ピュアなグラン=ゼシェゾー!」
であることは間違い無いと想像しています。2018年のエシェゾーは、自身で開けたもの(抜栓も自分、持出も・・)と、開けて残った、時間が経過したものの両方をテイスティングしています。
「・・ほんと、noisy さんは良くそんな時間が有りますね・・」
「・・はい、しょっちゅう言われます。」
なので、エシェゾー2018年のポテンシャル判断には自信も有りますよ。・・で、おそらくですが、このグラン=ゼシェゾー2018年も同様のラインながら、グラン=ゼシェゾーらしい「ある種の黒さ」も有るんじゃないかと推測しています。ご検討くださいませ。
-----
【すみません・・これだけは飲めませんでした!非常に希少な2013年ものグラン=ゼシェゾーは2本のみの入荷です。】
昨今はグラン=ゼシェゾーともなりますと凄い価格になってしまうのが常ですが、この位だと・・「安いじゃん・・」と思えてしまう自分がちょっと怖いですね。
シュヴィニー=ルソーは、まず・・海外メディアには掲載されない・・品物を渡さないのか、渡せないのか判りませんが、良くあるパターンは、1990年代に酷い目に遭ったことで懲りている・・みたいな感じですね。
なので、現在は知る人ぞ知るドメーヌです。noisy も今のところは飲めていませんので何とも言いようが無いんですが、今回ご紹介させていただいた「2017 エシェゾー」が滅茶美味しかったので、この2013年グラン=ゼシェゾーも期待しています。是非ご検討くださいませ。
ですが、2022年もののレ・シャン・ペルドリや村名ヴォーヌ=ロマネを飲みますと、
「・・・これはもう・・時間の問題だけ・・で高く評価されるに違いない!」
と感じます。
はっきり言って、あんなに旨いレ・シャン・ペルドリを飲んだのは初めてです。ラ・タージュ(レ・ゴーディショ)の真上に有りながらも村名に貶められたまま、中々浮上出来ないのも・・
「無理して濃くしようとして失敗している?」
みたいなワインが多いように感じていました。
ですがシュヴィニー=ルソーは、濃くしようとか、淡くしたいとか・・はおそらく考えておらず、自身が思うブルゴーニュのエレガンスを生み出すことだけに集中していると思います。
グラン=ゼシェゾーと言うワインは、綺羅星のようなヴォーヌ=ロマネのアペラシオンの中でも上から5番目ほどです。ぜひご検討いただけましたら幸いです。
以下は以前のレヴューです。
-----
【シュヴィニー=ルソーのトップ・キュヴェです!】
実はまぁ・・コラムには書かないまでも、シュヴィニー=ルソーのテイスティングは結構進めています。例えば・・飲んでいないのでと書いて有る「2019年シャンボール1級レ・コンボット」は飲んでいたりします。でも、正確な分析が出来なかった・・つまり、抜栓して時間が経過してしまったものをテイスティングしたので、他の飲んだアイテムと同列で書いてしまうと齟齬が生じるかと言うことで・・あ、また時間も無いし・・(^^;; ですみません・・ご容赦ください。
ただし、2019年のシャンボール・コンボット!・・旨かったです!・・が、残っていたのが少な過ぎでした。
このグラン=ゼシェゾー2018年は、自身で開けられもせず、開いたボトルを飲むことも出来ず・・でした。でも、
「激ピュアなグラン=ゼシェゾー!」
であることは間違い無いと想像しています。2018年のエシェゾーは、自身で開けたもの(抜栓も自分、持出も・・)と、開けて残った、時間が経過したものの両方をテイスティングしています。
「・・ほんと、noisy さんは良くそんな時間が有りますね・・」
「・・はい、しょっちゅう言われます。」
なので、エシェゾー2018年のポテンシャル判断には自信も有りますよ。・・で、おそらくですが、このグラン=ゼシェゾー2018年も同様のラインながら、グラン=ゼシェゾーらしい「ある種の黒さ」も有るんじゃないかと推測しています。ご検討くださいませ。
-----
【すみません・・これだけは飲めませんでした!非常に希少な2013年ものグラン=ゼシェゾーは2本のみの入荷です。】
昨今はグラン=ゼシェゾーともなりますと凄い価格になってしまうのが常ですが、この位だと・・「安いじゃん・・」と思えてしまう自分がちょっと怖いですね。
シュヴィニー=ルソーは、まず・・海外メディアには掲載されない・・品物を渡さないのか、渡せないのか判りませんが、良くあるパターンは、1990年代に酷い目に遭ったことで懲りている・・みたいな感じですね。
なので、現在は知る人ぞ知るドメーヌです。noisy も今のところは飲めていませんので何とも言いようが無いんですが、今回ご紹介させていただいた「2017 エシェゾー」が滅茶美味しかったので、この2013年グラン=ゼシェゾーも期待しています。是非ご検討くださいませ。
ラ・スール・カデット
ラ・スール・カデット
フランス la Soeur Cadette ブルゴーニュ
● 久しぶりのラ・スール・カデットです。ヴェズレのジャン・モンタネの・・ネゴス部門ですね。ご存じの方は良~~く知っておられるはず。凄く平たく言いますと、ヴェズレの協同組合の組合長だったジャン・モンタネさんが、組合の方針が変わって・・ナチュラルな造りが出来なくなり、
「そんなの、やってられるかい!」
と止めてしまい、自分自身のドメーヌを始め、その中で出来たネゴス部門です。
ドメーヌものも美味しいですがネゴスものも引けを取らず、しかも・・本拠のヴェズレの葡萄では無い南部の葡萄を買い付けていたりしまして、それがまた何とも不思議な味わいを醸し出します。
現在は息子さんがやられているのかな?・・noisy も含め、「自然派ワイン」と言う言葉が出始めた頃には大いにお世話になった造り手さんです。リーズナブルなので・・どうぞよろしくお願いいたします。
 ■ ラ・スール・カデットについて
■ ラ・スール・カデットについて
醸造所はヴェズレイにあり同地のドメーヌ・ド・ラ・カデットにて、父ジャン・モンタネと働きつつ、母親カトリーヌのドメーヌ・モンタネ・トダンでは醸造責任者として腕を振るう、ヴァランタン・モンタネのネゴシアン。醸造される買いブドウは、ヴェズレイ周辺のブドウだけでなく、ヴァランタンの醸造学校時代や、彼と志を同じくする友人の多い、ボジョレーやマコンのブドウの仕込みもしている。ドメーヌ・ド・ラ・カデット同様、ヴァランタンの父ジャンの設立したネゴシアンだが、2014年ころからは、醸造学校や海外での経験を経て帰ってきたヴァランタンに次第に運営を任せるようになり、近年ではヴァランタンが責任者としてワイナリーを経営している。2019年現在の生産ワインはヴェズレイ、マコン、ボジョレーを主軸にしているが、様々な地域でのワイン造りを経験し、好奇心の強いヴァランタンは、また新たな可能性を探しているようだ。
◆ グラン・オーセロワについて
シャブリの周縁、数カ所の小規模な栽培地の総称。主な構成地域は4つで、シャブリから南西約15kmのイランシー村などで知られるオーセロワ地区、シャブリの南約40km、ディジョンからほぼ真西に約100kmの位置にあるヴェズレイ村などで知られるヴェズリアン地区、シャブリ東側のトネロワ地区、同西北西ジョワニー地区である。いずれも石灰岩豊富な土壌で、ブルゴーニュに典型的な葡萄が栽培されるが、黒葡萄のセザール(Cesar).白葡萄のサシー(Sacy)などの固有品種も極わずかに栽培されている。1999年に村名AOCに昇格したイランシー(以前はAOCブルゴーニュ・イランシー)はピノ・ノワール主体の赤ワインのアペラシオン。2003年に村名AOCとなったサン・ブリはブルゴーニュ唯一のソービニヨン・ブラン主体の白ワインのAOC。ミネラル豊富な辛口のシャルドネを生むトネロワ地区も、2006年にブルゴーニュ・トネールというAOCが認定された。
◆ ブルゴーニュについて
北端のシャブリとその周縁、偉大なグランクリュの数々を含むコート・ドール、その南に続くコート・シャロネーズ、マコネ、ボジョレまでを含む地域の総称。大規模農園が多いボルドーと異なり、ここでは農園は相続を繰り返すごとに細分化され、農家の畑の平均は約6ha。通常一つのアペラシオン名を有する区画が多くの生産者に分割所有され、その最たる例のクロ・ヴージョは約50haが90の農家に分割所有される。ラ・ターシュなどのように一つのクリュの一生産者単独所有(モノポール)は稀有な例外である。それゆえ同じアペラシオンのワインでさえ、生産者によって「悲惨な代物から、素晴らしい逸品まで」と言われるほど品質のバラツキ、不確実性が顕著。ワインの生産形態も三つに大分され、1.ネゴシアン(買いブドウ/ワイン)を集めてブレンド。2.ネゴシアン自社畑栽培・自社醸造。3.ドメーヌ(農家の自社栽培・醸造がある)。なかには、まさに魂をゆさぶる、人知を越えた名品があるとさえ思わされるが、それにたどり着くのは至難である。
■ SARL La Soeur Cadette(ラ・スール・カデット)
地域 Bourgogne
地区、村 Vezelay ヴェズレ
オーナー:Valentin Montanet
醸造責任者、栽培責任者:Valentin Montanet
Homepage :なし
ドメーヌ創業年:2010 年
醸造所は ヴェズレイ にあ り 、同地のドメーヌ・ド・ラ・カデットで、父ジャン・モンタネと働きつつ、母親カトリーヌのドメーヌ・モンタネ・トーデンでは醸造責任者として腕を振るう、ヴァランタン・モンタネのネゴシアン部門 。醸造される買いブドウは、ヴェズレイ周辺のブドウだけでなく、ヴァランタンの醸造学校時代や、彼と志を同じくする友人の多い、ボジョレーやマコンのブドウの仕込みもしている。
ドメーヌ・ド・ラ・カデット同様、ヴァランタンの父ジャンの設立した ネゴシアンだが、 2014年頃からは、醸造学校や海外での経験を経て帰ってきたヴァランタンに次第に、運営を任せるようになり、近年ではヴァランタンが責任者としてワイナリーを経営している。
2019年現在の生産ワインはヴェズレイ、マコン、ボジョレーを主軸にしているが 、様々な地域でのワイン造りを経験し、好奇心の強いヴァ ランタンは、 また新たな可能性を探しているようだ。
【畑について】
自社ブドウ畑面積: 0ha
契約ブドウ畑面積: 21ha
ブドウ品種: シャルドネ、ピノ・ノワール、ムロン・ド・ブルゴーニュ、ガメ
栽培:ビオロジック(1999年より、2002年認証取得)
認証機関:アグリカルチャー・ビオロジック、カリテ・フランス※2002年認証取得
栽培方法の将来的な展望: ビオディナミへの転向等は予定なし、化学薬品は一切使用しないが型にははまらずブドウ樹に付き添い常に進化し続けていく
土壌:粘土石灰質、赤粘土、青粘土
【醸造について】
酵母のタイプ:
野生酵母
圧搾方式:水平式Vaslin二台と空気圧式一台
醗酵容器の素材と容量(L):白は27hlと50hlのステンレスタンク、赤は228l、400l、500lの樽、琺瑯を一台のみデブルバージュ用に所有
熟成容器の素材:キュヴェにより異なる。ステンレスか樽、新樽は一切使用しない。
セラー環境: 自宅地下一階が樽用のカーヴ、ステンレスタンクは併設された建物の2階に設置、収穫用の選果台やプレス機などは数百メートル離れた場所にあり、収穫後は主にそちらで作業する。畑はCuverieを中心として全区画4km圏内
年間生産ボトル本数:約110000本(うち、ブルゴーニュ・ヴェズレイとムロン・ド・ブルゴーニュを30~50hl/ha外部から購入)
「そんなの、やってられるかい!」
と止めてしまい、自分自身のドメーヌを始め、その中で出来たネゴス部門です。
ドメーヌものも美味しいですがネゴスものも引けを取らず、しかも・・本拠のヴェズレの葡萄では無い南部の葡萄を買い付けていたりしまして、それがまた何とも不思議な味わいを醸し出します。
現在は息子さんがやられているのかな?・・noisy も含め、「自然派ワイン」と言う言葉が出始めた頃には大いにお世話になった造り手さんです。リーズナブルなので・・どうぞよろしくお願いいたします。
 ■ ラ・スール・カデットについて
■ ラ・スール・カデットについて醸造所はヴェズレイにあり同地のドメーヌ・ド・ラ・カデットにて、父ジャン・モンタネと働きつつ、母親カトリーヌのドメーヌ・モンタネ・トダンでは醸造責任者として腕を振るう、ヴァランタン・モンタネのネゴシアン。醸造される買いブドウは、ヴェズレイ周辺のブドウだけでなく、ヴァランタンの醸造学校時代や、彼と志を同じくする友人の多い、ボジョレーやマコンのブドウの仕込みもしている。ドメーヌ・ド・ラ・カデット同様、ヴァランタンの父ジャンの設立したネゴシアンだが、2014年ころからは、醸造学校や海外での経験を経て帰ってきたヴァランタンに次第に運営を任せるようになり、近年ではヴァランタンが責任者としてワイナリーを経営している。2019年現在の生産ワインはヴェズレイ、マコン、ボジョレーを主軸にしているが、様々な地域でのワイン造りを経験し、好奇心の強いヴァランタンは、また新たな可能性を探しているようだ。
◆ グラン・オーセロワについて
シャブリの周縁、数カ所の小規模な栽培地の総称。主な構成地域は4つで、シャブリから南西約15kmのイランシー村などで知られるオーセロワ地区、シャブリの南約40km、ディジョンからほぼ真西に約100kmの位置にあるヴェズレイ村などで知られるヴェズリアン地区、シャブリ東側のトネロワ地区、同西北西ジョワニー地区である。いずれも石灰岩豊富な土壌で、ブルゴーニュに典型的な葡萄が栽培されるが、黒葡萄のセザール(Cesar).白葡萄のサシー(Sacy)などの固有品種も極わずかに栽培されている。1999年に村名AOCに昇格したイランシー(以前はAOCブルゴーニュ・イランシー)はピノ・ノワール主体の赤ワインのアペラシオン。2003年に村名AOCとなったサン・ブリはブルゴーニュ唯一のソービニヨン・ブラン主体の白ワインのAOC。ミネラル豊富な辛口のシャルドネを生むトネロワ地区も、2006年にブルゴーニュ・トネールというAOCが認定された。
◆ ブルゴーニュについて
北端のシャブリとその周縁、偉大なグランクリュの数々を含むコート・ドール、その南に続くコート・シャロネーズ、マコネ、ボジョレまでを含む地域の総称。大規模農園が多いボルドーと異なり、ここでは農園は相続を繰り返すごとに細分化され、農家の畑の平均は約6ha。通常一つのアペラシオン名を有する区画が多くの生産者に分割所有され、その最たる例のクロ・ヴージョは約50haが90の農家に分割所有される。ラ・ターシュなどのように一つのクリュの一生産者単独所有(モノポール)は稀有な例外である。それゆえ同じアペラシオンのワインでさえ、生産者によって「悲惨な代物から、素晴らしい逸品まで」と言われるほど品質のバラツキ、不確実性が顕著。ワインの生産形態も三つに大分され、1.ネゴシアン(買いブドウ/ワイン)を集めてブレンド。2.ネゴシアン自社畑栽培・自社醸造。3.ドメーヌ(農家の自社栽培・醸造がある)。なかには、まさに魂をゆさぶる、人知を越えた名品があるとさえ思わされるが、それにたどり着くのは至難である。
■ SARL La Soeur Cadette(ラ・スール・カデット)
地域 Bourgogne
地区、村 Vezelay ヴェズレ
オーナー:Valentin Montanet
醸造責任者、栽培責任者:Valentin Montanet
Homepage :なし
ドメーヌ創業年:2010 年
醸造所は ヴェズレイ にあ り 、同地のドメーヌ・ド・ラ・カデットで、父ジャン・モンタネと働きつつ、母親カトリーヌのドメーヌ・モンタネ・トーデンでは醸造責任者として腕を振るう、ヴァランタン・モンタネのネゴシアン部門 。醸造される買いブドウは、ヴェズレイ周辺のブドウだけでなく、ヴァランタンの醸造学校時代や、彼と志を同じくする友人の多い、ボジョレーやマコンのブドウの仕込みもしている。
ドメーヌ・ド・ラ・カデット同様、ヴァランタンの父ジャンの設立した ネゴシアンだが、 2014年頃からは、醸造学校や海外での経験を経て帰ってきたヴァランタンに次第に、運営を任せるようになり、近年ではヴァランタンが責任者としてワイナリーを経営している。
2019年現在の生産ワインはヴェズレイ、マコン、ボジョレーを主軸にしているが 、様々な地域でのワイン造りを経験し、好奇心の強いヴァ ランタンは、 また新たな可能性を探しているようだ。
【畑について】
自社ブドウ畑面積: 0ha
契約ブドウ畑面積: 21ha
ブドウ品種: シャルドネ、ピノ・ノワール、ムロン・ド・ブルゴーニュ、ガメ
栽培:ビオロジック(1999年より、2002年認証取得)
認証機関:アグリカルチャー・ビオロジック、カリテ・フランス※2002年認証取得
栽培方法の将来的な展望: ビオディナミへの転向等は予定なし、化学薬品は一切使用しないが型にははまらずブドウ樹に付き添い常に進化し続けていく
土壌:粘土石灰質、赤粘土、青粘土
【醸造について】
酵母のタイプ:
野生酵母
圧搾方式:水平式Vaslin二台と空気圧式一台
醗酵容器の素材と容量(L):白は27hlと50hlのステンレスタンク、赤は228l、400l、500lの樽、琺瑯を一台のみデブルバージュ用に所有
熟成容器の素材:キュヴェにより異なる。ステンレスか樽、新樽は一切使用しない。
セラー環境: 自宅地下一階が樽用のカーヴ、ステンレスタンクは併設された建物の2階に設置、収穫用の選果台やプレス機などは数百メートル離れた場所にあり、収穫後は主にそちらで作業する。畑はCuverieを中心として全区画4km圏内
年間生産ボトル本数:約110000本(うち、ブルゴーニュ・ヴェズレイとムロン・ド・ブルゴーニュを30~50hl/ha外部から購入)
●
2022 Bourgogne Rouge
ブルゴーニュ・ルージュ
【今の・・行き過ぎたようなナチュールとは一線を画す、ある意味・・本物のナチュールかもしれません。決して凄さは無いのに・・とても美味しいと感じる不思議な感じも有ります!】
 え~・・テクニカルにはマコンから買い付けた有機の葡萄で仕込んだと書かれていますので、一応そのように受け止めています。
え~・・テクニカルにはマコンから買い付けた有機の葡萄で仕込んだと書かれていますので、一応そのように受け止めています。ですが・・
「本当にマコンの葡萄?」
と思えるようなノーズのトッピング・・も有り、やや眉に唾を付けながらのご紹介です。
濃度は適度に在って、まったく甘く無く、ナチュールな・・いや、これが本当じゃないかと思うんですが・・自然な抑揚と膨らみを持ったアロマが立ち昇ります。
もう・・いきなり揮発酸が「ぷーん」と来ますとですね・・少し身構えてしまう「クセ」が付いてしまいましたので、自由なスタイルで、どこまで酢酸的でも造り手自身が良いと思えば・・
「テーブルワインでリリースできる」
訳でして、そりゃぁご自身は良いかもしれませんが・・売り手は大変です。半年も置けば纏まるものもあれば、数年置いてようやく仕上がるもの、そして、どうやっても無理なもの・・ほぼお酢と言えるような仕上がりの物も有ります。
そもそもナチュールは、So2 を使うか使わないか・・では有り得ず、有機の栽培のことを言った訳ですが、いつの間にか、
「So2 を使わない醸造」
とすり替わってしまっているような気さえします。
ですがこのカデットは全くそんな部分を見せない、ある意味、「真のナチュール」と感じますが・・まったく危険性を感じないのにナチュール感を感じます。
 適度に熟したベリーとプラム、そして中間的な色のチェリーに、ん・・これを言って良いのか・・やはりブルゴーニュの北の大地のややフリンティなニュアンスのトッピングも受け取れるような感覚です。
適度に熟したベリーとプラム、そして中間的な色のチェリーに、ん・・これを言って良いのか・・やはりブルゴーニュの北の大地のややフリンティなニュアンスのトッピングも受け取れるような感覚です。重く無く、むしろ「ふわっ」とやや軽量で、柔らかなノーズと柔らかなフィルムのようなミネラリティに包まれたようなノーズが交錯します。
中域は締まりつつも徐々に膨らみを見せ、綺麗な余韻を適度に感じさせてくれます。非常にバランスが良く、何も不足せず、何も過剰では無く、やや北の土地の冷ややかさと、ほんのりと葡萄の持つ温度感を感じます。
ついでで申し訳ないのですが、ウェブをサーフしておりましたら・・どこかのサイトで・・
「葡萄の実には土壌由来のミネラルは蓄積しない」
と・・わざわざ書いてありました。他にもそんなことを言っているMWの方も知っていますが、何でそんな挑戦的にも感じることを言いたいのか・・
ただ noisy 的には、じゃぁ・・飲んだ時に感じるミネラル感は何なんだ?・・とも思いますし、「日本食品標準成分表」と言うのが公表されていまして、そこにも、
「ぶどう/皮なし」
「ぶどう/皮あり」
に、それぞれリン、鉄、亜鉛、マンガン、カリウム、カルシウム、マグネシウムなどの標準とされる含有量が記載されています。
まぁ・・日本の葡萄にはミネラルは有るが、海外の葡萄には無いのか・・それとも、葡萄の実・果皮にミネラルは有るが、土壌由来では無い??・・ということを言いたいのか、noisyにはまるで理解できませんが、敢えて突っ込まないようにしておきましょう。
しかしこのラ・スール・カデットのブルゴーニュ・ルージュ2022には、構造はしっかりあるものの全てを埋め尽くすようなものでは無く、比較軽やかに感じられる心地良いミネラリティがたっぷりあると感じます。ぜひ飲んでみてください。非常にバランスが良くナチュール感が有って適度に充実した心地良いA.C.ブルです。お薦めします。
ドメーヌ・セバスチャン・リフォー
セバスチャン・リフォー
フランス Sebastien Riffault ロワール
● ドメーヌ・セバスチャン・リフォーをご紹介させていただきます。順子さんもご自身のサンセール・ブランを造らせて貰っているビオ系のドメーヌです。
Sebastian Riffault
サンセールの常識を変えた男
日本には何度も来日しているセバスチャン・リファー氏、今更説明も要らないと思います。セバスチャンは 1981年12月5日生まれ最初彼のワインを輸入した時は31歳でしたが、今は45歳と一番仕事ののっている年齢です。あれだけの畑を全て無農薬で管理し、上のクラスの畑は今も馬で耕しております。先日訪問した時は丁度馬の装幀と言って、足の金具を取り換えている時でした。毎日毎日の餌の管理から始まり、あんなに大きな動物を維持するのは大変な作業です。しかし自然環境に対する彼のフィロソフィー、ワインをこよなく愛する姿勢、妥協しないワイン作り、本当に尊敬に値する醸造家です。ソーヴィニヨン・ブランと言う品種は実は収量が管理によっては増やす事が可能な品種です。ボルドーが良い例です。それをあのSB らしい香りを出すためには収量をぐっと抑えます。そして厚みを出すために、葡萄を濃くしっかりとした味わいを出すためです。あのセバスチャンの味わいは、そういう管理下の中、収穫を可能な限り遅らせて彼の表現したいワインを作っているのです。その宝物を扱える我々は、感謝しながら飲みたいと思っております。
新井順子
Sebastian Riffault
サンセールの常識を変えた男
日本には何度も来日しているセバスチャン・リファー氏、今更説明も要らないと思います。セバスチャンは 1981年12月5日生まれ最初彼のワインを輸入した時は31歳でしたが、今は45歳と一番仕事ののっている年齢です。あれだけの畑を全て無農薬で管理し、上のクラスの畑は今も馬で耕しております。先日訪問した時は丁度馬の装幀と言って、足の金具を取り換えている時でした。毎日毎日の餌の管理から始まり、あんなに大きな動物を維持するのは大変な作業です。しかし自然環境に対する彼のフィロソフィー、ワインをこよなく愛する姿勢、妥協しないワイン作り、本当に尊敬に値する醸造家です。ソーヴィニヨン・ブランと言う品種は実は収量が管理によっては増やす事が可能な品種です。ボルドーが良い例です。それをあのSB らしい香りを出すためには収量をぐっと抑えます。そして厚みを出すために、葡萄を濃くしっかりとした味わいを出すためです。あのセバスチャンの味わいは、そういう管理下の中、収穫を可能な限り遅らせて彼の表現したいワインを作っているのです。その宝物を扱える我々は、感謝しながら飲みたいと思っております。
新井順子
●
2020 Sancerre Raudonas Rouge Doamine Sebastien Riffault
サンセール・ラウドナス・ルージュ ドメーヌ・セバスチャン・リフォー
【So2生成量、添加量も少ない、濃密系・・ほんのりアヴァンギャルド系が入った・・でも許容範囲のピノ・ノワール!・・揮発酸がダメな方はスルーで、でもお若い方はお好きだと思います!】
 セバスチャン・リフォーの・・ナチュールなサンセールです。
セバスチャン・リフォーの・・ナチュールなサンセールです。まぁ、「ナチュールな」と言う定義は中々に面倒臭いんですが、一般的に言うところのナチュール度は高め・・と言うことになります。
ただし時折言ってますが、ワインに携わる方々でも、思いっきり勘違いしておられるか、もしくは判っていても「ナチュールだから」と言いたいのか・・は判りませんが、どうもですね・・
「So2の少なさを言いたい」
「揮発酸の生成、その影響を余り大きな声で言いたくない」
が・・ための「ナチュール」で有る場合が非常に多いです。
まぁ・・ナチュールと酸化防止剤無添加は結びつき易いものではありますが、
「絶対にイコールでは無い」
訳ですね。インポーターさんの中にはその辺りを何とかグレーにしたいと思っているんじゃないか?・・と疑われる方もいらっしゃいます。
そんなことを言ってますが、セバスチャン・リフォーの栽培はビオディナミで葡萄を良く熟させたい、そして基本、So2を使いたくない人です・・ので、揮発酸は有ります。
ですので、ブルゴーニュの一部・・とも思えなくもないロワール上流のロケーションのピノ・ノワールで有りながらも、揮発酸が動いた形跡のある味わいになっています・・から、
「揮発酸が有ったらワインはダメ!」
と思っていらっしゃる多くのブルゴーニュ・ピノ・ノワールファンの方には・・
「まったく向かない!・・のでスルーしましょう!」
と申し上げておきたいと思います。
ただし、おそらくそんなピノ・ノワール・ファンの方々の約半分は、飲まれてもその存在に気付かないかもしれない・・です。
 なので、自然派大好きな方、そしてお若い方には、めちゃファンになってしまうような魅力のあるナチュールで有ると・・言えます。
なので、自然派大好きな方、そしてお若い方には、めちゃファンになってしまうような魅力のあるナチュールで有ると・・言えます。色彩も濃密で果実の味わいが深いです。グラスの写真の色彩もそれなりに濃いと思うんですね。ですがまったく重ったるくはなっていませんで、エキスがしっかり出た、充実したパレットを描きます。
あ、ちょっと脱線しますが・・このグラスの写真を見て・・揮発酸の影響が見えると思える方・・流石です・・そう・・見えるようになるんですね・・長年やってますと・・。抜栓しますともう・・てき面に判ってしまいますが・・。
その揮発酸の影響は少ないですが確実に有ります。しかし、後口を全て「サワー」のようにしてしまうほどには・・当然なっておらず、言ってみれば・・
「ヤン・ドゥリューよりも少ないくらい」
です。
非常に複雑性に富んだエキスの味わいで、非常にドライですが旨味がたっぷりです。
あ・・前にも少し書きましたが、最近は多くの外人さんに、
「ウマミ」
「ダシ」
は・・そのまま通るようになって来ました。何かちょっと嬉しい感じがします。
ドライですがジューシーでも有り、当初は揮発酸の中に隠れていた複雑で細やかなニュアンスが、5~10分ほど経過しますと拡がり始めます。スイスイも飲めますが、徐々にその複雑性が膨らんで来ますので、
「いつの間にか・・その複雑性と対峙するため、飲むスピードがゆっくりになって行く」
そんな感じです。このセバスチャン・リフォーさん・・貴腐の付いた葡萄が好きなようで、特に白では顕著なのでしょうが、この2020年は特段にその影響を受けているとは感じませんが、結構に複雑な印象です。
2020年ものですから、それらが全て混然一体となるまで1~2年と言ったところだと思います。今飲んでも美味しく、この先7~8年は上昇して行くものと思います。飲んでみてください。
あ・・因みに・・新井順子さんセレクツのボワ・ルカ輸入です。2019年ものは有っても2020年ものは余り扱いは無いんじゃないかなと思いますのでどうぞよろしくお願いいたします。
ドメーヌ・ド・ヴェルニュス
ド・ヴェルニュス
フランス Domaine de Vernus ブルゴーニュ
● 3年目の・・ギョーム・ルジェが指揮するドメーヌ・ド・ヴェルニュスをご紹介させていただきます。まさに、
「!!・・そう来たか~!」
と思えるような2021年ものの仕上がりでした。
「・・ん?・・どう来たの?」
と思っておられるかと思うんですが・・
前年の2020年ものには、まさにドメーヌ・エマニュエル・ルジェ張りの・・
「新樽マジック!」
を見せ、さらに前年のファーストヴィンテージもの、2019年ものとは・・
「まったく異なる出来!」
に驚かされた訳です。2019年ものにはギョーム・ルジェはほぼ関与していないだろう・・もしくは醸造からだろうと言うのが noisy的な見立てです。
2020年ものはエマニュエル・ルジェ張りの「官能的なブルゴーニュワイン」であり、余りの官能さにクラクラ来てしまうと言う・・そんな出来でした。
そして3年目の2021年ものですが、・・おっとその前に、ドメーヌからの2021年ものの評価文をご覧ください。
「2021年は春の霜や雹による被害に続き、夏は雨が多く、8月後半以降は天気は回復したものの、にわか雨も降って最後まで警戒を怠ることが出来なかったヴィンテージ。2021年最初の3カ月は過去の平均よりも気温が0.4℃高く、降雨量は18mm多く、日照量は56時間多い南国のような温暖な気候だった。そのため、葡萄はどちらかというと早熟傾向で4月5日には芽吹きが始まり、非常に早熟だった2020年と比べれば約1週間遅いものの、1993年以降の平均からは2日早かった。4月5~8日は歴史的な霜が畑に襲い掛かり、2021年の4月は4月としては2001年以降最も冷涼だった。5月も同じような傾向で平均よりも日照量も多かったが雨も多く、月間降水量が1959年以降最も多かった。
開花期は6月9日頃で2020年からは20日も遅く、7月に入っても雨が多く、月間降水量は1964年以降では1977年に次ぐ2番目に多い記録だった。8月に入ると多少にわか雨は降ったもののたいした降水量ではなく、全体的に乾燥していて葡萄の色付きは8月5日頃から見られ、平均からは7日遅かった。8月後半から9月の天候が良かったおかげで葡萄は成熟してはくれたが収穫量は平均よりも少なくなっており、ボージョレの生産者にとっては複雑で難しい年となった。酸味のある赤い果実旨味、アルコールとタンニンは軽やかでデリケートな味わい。2020年も力強く素晴らしいヴィンテージだったが、2021年は洗練されて飲みやすい見事な出来栄えとなっている。」
そう言うことなんですが、noisy はその場面は見ていないので、なるほどとしか言えません。しかしながら・・テイスティングでこのように感じています。
「2021年ものはめちゃピュア!・・新樽の使用は抑え気味にし、その分、前年もので感じた官能さも控え気味で2~3年後から出始めるはず。非常に伸びやかで健全、ナチュール&ピュア、ほんのり官能的で素晴らしい出来!」
だと感じました。
2021年の葡萄の出来具合から、新樽使用による緩やかな酸化を抑え気味にしたのだろう・・と予想していますが、いや・・ギョーム・ルジェ、恐るべき感性の持ち主なのかもしれない・・と思い始めています。
今回、一番価格の安い・・本拠の「2021 ルニエ・レ・ヴェルジェ」ですが、ま~・・今、とんでもなく旨いです!・・もちそんモルゴンもフルーリーも、そしてトップのムーラン・ナ・ヴァンも素晴らしいですが、少し早い・・です。
なので、とにかくレ・ヴェルジェ!・・飲んでみてください。とてもガメだとは思わないはず・・(^^;;??・・です。やはり今やブルゴーニュの将来を担うルジェ家なのでしょう。どうぞよろしくお願いいたします。
-----
2022年の夏に一度入ってきました時にご案内させていただいてましたド・ヴェルニュスの上級キュヴェの残りがようやく到着です。すでに以前のド・ヴェルニュスを飲まれたお客様からは多くのお問い合わせをいただいていますが、少ない2020~2021年ものに関しましては何のお約束も出来ず、忸怩たる思いをしていました。
「2020年のド・ヴェルニュスは、アンリ・ジャイエの正当な継承者エマニュエル・ルジェの持つアイデンティティをボージョレで開花させたドメーヌ」
です。
まぁ・・ガメやボージョレには興味無し・・の方々には、まず動いていただけないアイテムかとは思いますが、
「まずはグラスの写真を見てから!」
と申し上げたいですね。見ても何も思わなければ仕方が無い・・(^^;; どうぞよろしくお願いいたします。素晴らしいです!
以下は以前のレヴューです。
-----
もうこれは・・半端無いです!・・エマニュエル・ルジェと言う造り手の凄さを改めて感じさせられた気持ちになっています。
もはや、
「ボージョレで最高のエレガンスを発揮している!」
と言うべきではないでしょうか。
もし昨年ご案内させていただいた、このドメーヌ・ド・ヴェルニュスの2019年ものを飲まれていたとしても、この2020年ものを一緒だとは思わないでください。勿論ですが、この2020年ものを飲めば、noisy がこんなに舞い上がっていることの全てを理解できる・・と思います。
圧巻なテイスティングでした。今回ご案内できず、今秋以降に届くアイテムもテイスティングしていますが、それらはさらに上級キュヴェで・・物凄い味わいです。
そして、フレデリック・ジェムトンさんのドメーヌでは有りますが、
「ドメーヌ・エマニュエル・ルジェの哲学を反映させている」
と言う言葉に嘘は無い・・つまり、
「ドメーヌ・エマニュエル・ルジェがボージョレを造ると・・こうなる」
その姿をご覧いただける訳です。そしてきっと、
「さらなる成長が楽しみになる!」
ことに必ず繋がると感じます。是非ともこの見事な波に乗ってみることをお薦めします!・・そして価格は滅茶安い!・・ご検討くださいませ。
ブルゴーニュワインファンの皆さんも固唾を飲んで見守っていると思われる、期待の新人をご紹介させていただきます。フレデリック・ジェムトン氏とおっしゃるブルゴーニュ出身の・・おそらく noisy とさしては年齢も変わらないに違いない・・?白髪のナイスミドル・・??・・です。
30年務めた保険業界をリタイヤし、さすがにコート=ドール近辺に畑を買うことは出来なかったか、それとも自然豊かなボージョレのレーニエが気に入られたのか判りませんが、クリュ・ボージョレの畑、もしくは葡萄を入手し2019年より醸造することになったんですね。
そして・・何と、あのエマニュエル・ルジェさんの次男、「ギョーム・ルジェ」氏をコンサルタントに迎え、ドメーヌ・エマニュエル・ルジェの作風を大いに生かしたボージョレにしようと頑張っているそうなんです。
エマニュエル・ルジェのパスグラも当然ガメが使用されていますが、今やその・・
「パスグラでさえ、エマニュエル・ルジェを主張している!」
のは、皆さんもご存じかと思います。官能的で柔らかく、非常に良く香る素晴らしいワインになっていますよね?・・noisy も、90年代から・・だったか、ルジェのパスグラは飲んでいますが、その頃はまだ・・いや、美味しかったですが、今のようなリリース時からの「官能さ」は有りませんでした。勿論価格も滅茶安く、2千円ほどだったと記憶しています。
今やエマニュエル・ルジェさんも、いつ引退しても不思議ではない年齢になり、長男のニコラ君、次男のギョーム君が頑張ったことで、あの名作ともいうべき2017年のドメーヌ・エマニュエル・ルジェのワインが生まれた訳です。
そんなギョーム君がコンサルされたフレデリック・ジェムトン氏のドメーヌが、この「ドメーヌ・ド・ヴェルニュス」なんですね。なのでnoisyもたっぷり期待して待ってましたとばかりにテイスティングさせていただきました。
 初ヴィンテージの2019年もののNoisy wine への到着は今年2021年5月末~6月始め頃でした。アイテムは今回ご紹介の4アイテムです。・・あ、因みに左の写真はサンプル入手の2020年もの・・未発表のものです・・10アイテムほど有りますが、これがまぁ・・滅茶苦茶美味しいんですよ!・・あ、すみません、今回は2019年もののお話しでしたね。
初ヴィンテージの2019年もののNoisy wine への到着は今年2021年5月末~6月始め頃でした。アイテムは今回ご紹介の4アイテムです。・・あ、因みに左の写真はサンプル入手の2020年もの・・未発表のものです・・10アイテムほど有りますが、これがまぁ・・滅茶苦茶美味しいんですよ!・・あ、すみません、今回は2019年もののお話しでしたね。
で、6月に入って2019年ものを徐々にテイスティングを始めたんです。非常にピュアで軽やかなアロマが心地良い、凄く健康的な美味しいクリュ・ボージョレでした。・・ただし、タイミングが良く無かったのか、
「ちょっと硬い・・なぁ・・余りルジェさん風にも感じないし・・」
そうなんですよ・・当初、フィネスのK君に聞いていたのとは印象が結構に異なっていました。
ですが、良く良く・・嗅ぎまわってみると、確かにルジェ風の官能さが表面に出ている白く軽やかなミネラリティの奥の奥に在ることが判ったんですね。
なので・・残念でしたが・・
「ん~・・フィネスさんには2カ月前に入荷だから・・合計で半年弱ほど・・待つかぁ・・」
と言うことで、ようやく今回ご紹介させていただくことになった訳です。
話しは飛びまして、上記写真の2020年ものですが、圧巻と言えるほど素晴らしいです。ルジェ風の「濡れたテクスチュア」がバッチリ、そして「官能さ」も出始めています。そもそもこのボトルたちはサンプルとしてフィネスさんに届いたもので、その残りを頂戴させていただいた・・と言う、ちょっとした「役得」みたいな感じですね。
なので、noisy がテイスティングしたのは、フィネスさんがテイスティングされた何日か後・・と言うことになります。
noisy 的には、2019年ものは自宅でボトルを開けて、すぐのタイミングで・・素晴らしいけれどちょっと硬かった・・それが今年の6月です。
2020年ものは今年の10月、フィネスさんで抜栓後の数日後と言うタイミングで滅茶苦茶柔らかく、濃度も出ていて美味しかった・・んです。
ですが2020年ものは、担当のK君の話しによりますと、
「到着直後と言うこともあってか、酸が少し硬かった・・」
そうなんですね。
で、同時期に飲んだ2019年もの(フルーリー、レーニエ・レ・ヴェルジェ等の今回ご紹介のアイテムたち)はとても開いていて、同時テイスティングのエマニュエル・ルジェさんのパスグラに勝るとも劣らない・・同じようなニュアンスを持った見事な味わいで、ヴェルニュスのワインがガメだけだとはとても思えなかった・・と言うのが、大方の出席者さんたちの感想
だったそうです。
そうかぁ・・と、まぁ、ある意味では noisy の想像通りでは有った訳で、流石に12本ずつしか存在しないファーストヴィンテージのワインたちを2本も消費してしまう訳にもいかないため、
「・・(良かった!)」
と、胸を撫で下ろしたところです。
ですので、ワインはやはり、
「どうやって飲むか?」
が非常に重要で、これをおろそかにしてしまうと、本来そのワインが持っている味わいを台無しにしてしまう場合も有ります。
さほど高いワインではないから・・と気を抜かず、しっかり休めて、タイミングと品温に気を付けながら飲んでいただけましたら、このクリュ・ボージョレの素晴らしさ、アンリ・ジャイエ直系、エマニュエル・ルジェ直系の素晴らしい味わいに出会うことが出来るかと・・思っています。
また、もし開けてしまったのに硬かったらどうしたら良いか?・・そんな時には、そのままコルク栓を逆刺しにして、3~5日ほど冷暗所で保存し、再び飲んでみて下さい。
次から次へと大きな話題をくれるエマニュエル・ルジェ・ファミリーです。・・が、このファミリーのボージョレへの進出は、この地区のワインを・・単に、
「ヌーヴォー専用」
と言う看板を大きく塗り替えて行くものと思っています。是非ご検討くださいませ。
 ドメーヌ ド ヴェルニュス
ドメーヌ ド ヴェルニュス
DOMAINE DE VERNUS
地所:ブルゴーニュ地方 ボージョレ地区
2019年に誕生した当ドメーヌはボージョレ地区のほぼ中央に位置する「Regnie-Durette(レニエ・デュレット)」という集落に所在しています。ブルゴーニュ生まれの当主フレデリック・ジェムトン氏は保険業界で30年間働いた後、ワイン好きが高じてワイン造りを始める決意をしました。どこでワインを造るかはいくつかの候補がありましたが、最終的には美しい風景が広がり、類まれなる可能性があるボージョレに腰を据えることにしました。
ボージョレの山々に広がる畑の様々な標高や方角、土壌構成、葡萄の木の健康状態などを考え、ドメーヌ設立時には綿密に選定された合計7haの葡萄畑を購入し、その大多数は古木になっています。畑作業や醸造などのワイン造りに関しては、ブルゴーニュの試飲会で知り合ってから数年来の友人であるギョーム・ルジェ氏(エマニュエルルジェ氏の次男)にコンサルタントを依頼しています。ヴォーヌ=ロマネで家族経営のドメーヌを支えている彼の手腕や技量、哲学に感嘆したフレデリック氏は葡萄の植樹から瓶詰の日程に至るまですべての工程において指示を仰ぎ、ギョーム氏はそれに応えて「Domaine Emmanuel Rouget」の哲学をワイン造りに反映させています。
 選別しながら手摘みで収穫された葡萄は醸造所に運ばれ、テーブルの上でさらに念入りに選別された健康な粒だけを使用。除梗は区画ごとのキャラクターによって比率を変えています。
選別しながら手摘みで収穫された葡萄は醸造所に運ばれ、テーブルの上でさらに念入りに選別された健康な粒だけを使用。除梗は区画ごとのキャラクターによって比率を変えています。
低温浸漬でアロマと色調をゆっくりと抽出させ、ステンレスタンクでアルコール醗酵を行ってから10ヵ月間タンクもしくは樫樽で静かに熟成させます。フレデリック氏はアペラシオンや区画が持つ個々のキャラクターを尊重してテロワールの違いを楽しめる様々なキュヴェを敢えてボージョレで造ることを目指しています。
「!!・・そう来たか~!」
と思えるような2021年ものの仕上がりでした。
「・・ん?・・どう来たの?」
と思っておられるかと思うんですが・・
前年の2020年ものには、まさにドメーヌ・エマニュエル・ルジェ張りの・・
「新樽マジック!」
を見せ、さらに前年のファーストヴィンテージもの、2019年ものとは・・
「まったく異なる出来!」
に驚かされた訳です。2019年ものにはギョーム・ルジェはほぼ関与していないだろう・・もしくは醸造からだろうと言うのが noisy的な見立てです。
2020年ものはエマニュエル・ルジェ張りの「官能的なブルゴーニュワイン」であり、余りの官能さにクラクラ来てしまうと言う・・そんな出来でした。
そして3年目の2021年ものですが、・・おっとその前に、ドメーヌからの2021年ものの評価文をご覧ください。
「2021年は春の霜や雹による被害に続き、夏は雨が多く、8月後半以降は天気は回復したものの、にわか雨も降って最後まで警戒を怠ることが出来なかったヴィンテージ。2021年最初の3カ月は過去の平均よりも気温が0.4℃高く、降雨量は18mm多く、日照量は56時間多い南国のような温暖な気候だった。そのため、葡萄はどちらかというと早熟傾向で4月5日には芽吹きが始まり、非常に早熟だった2020年と比べれば約1週間遅いものの、1993年以降の平均からは2日早かった。4月5~8日は歴史的な霜が畑に襲い掛かり、2021年の4月は4月としては2001年以降最も冷涼だった。5月も同じような傾向で平均よりも日照量も多かったが雨も多く、月間降水量が1959年以降最も多かった。
開花期は6月9日頃で2020年からは20日も遅く、7月に入っても雨が多く、月間降水量は1964年以降では1977年に次ぐ2番目に多い記録だった。8月に入ると多少にわか雨は降ったもののたいした降水量ではなく、全体的に乾燥していて葡萄の色付きは8月5日頃から見られ、平均からは7日遅かった。8月後半から9月の天候が良かったおかげで葡萄は成熟してはくれたが収穫量は平均よりも少なくなっており、ボージョレの生産者にとっては複雑で難しい年となった。酸味のある赤い果実旨味、アルコールとタンニンは軽やかでデリケートな味わい。2020年も力強く素晴らしいヴィンテージだったが、2021年は洗練されて飲みやすい見事な出来栄えとなっている。」
そう言うことなんですが、noisy はその場面は見ていないので、なるほどとしか言えません。しかしながら・・テイスティングでこのように感じています。
「2021年ものはめちゃピュア!・・新樽の使用は抑え気味にし、その分、前年もので感じた官能さも控え気味で2~3年後から出始めるはず。非常に伸びやかで健全、ナチュール&ピュア、ほんのり官能的で素晴らしい出来!」
だと感じました。
2021年の葡萄の出来具合から、新樽使用による緩やかな酸化を抑え気味にしたのだろう・・と予想していますが、いや・・ギョーム・ルジェ、恐るべき感性の持ち主なのかもしれない・・と思い始めています。
今回、一番価格の安い・・本拠の「2021 ルニエ・レ・ヴェルジェ」ですが、ま~・・今、とんでもなく旨いです!・・もちそんモルゴンもフルーリーも、そしてトップのムーラン・ナ・ヴァンも素晴らしいですが、少し早い・・です。
なので、とにかくレ・ヴェルジェ!・・飲んでみてください。とてもガメだとは思わないはず・・(^^;;??・・です。やはり今やブルゴーニュの将来を担うルジェ家なのでしょう。どうぞよろしくお願いいたします。
-----
2022年の夏に一度入ってきました時にご案内させていただいてましたド・ヴェルニュスの上級キュヴェの残りがようやく到着です。すでに以前のド・ヴェルニュスを飲まれたお客様からは多くのお問い合わせをいただいていますが、少ない2020~2021年ものに関しましては何のお約束も出来ず、忸怩たる思いをしていました。
「2020年のド・ヴェルニュスは、アンリ・ジャイエの正当な継承者エマニュエル・ルジェの持つアイデンティティをボージョレで開花させたドメーヌ」
です。
まぁ・・ガメやボージョレには興味無し・・の方々には、まず動いていただけないアイテムかとは思いますが、
「まずはグラスの写真を見てから!」
と申し上げたいですね。見ても何も思わなければ仕方が無い・・(^^;; どうぞよろしくお願いいたします。素晴らしいです!
以下は以前のレヴューです。
-----
もうこれは・・半端無いです!・・エマニュエル・ルジェと言う造り手の凄さを改めて感じさせられた気持ちになっています。
もはや、
「ボージョレで最高のエレガンスを発揮している!」
と言うべきではないでしょうか。
もし昨年ご案内させていただいた、このドメーヌ・ド・ヴェルニュスの2019年ものを飲まれていたとしても、この2020年ものを一緒だとは思わないでください。勿論ですが、この2020年ものを飲めば、noisy がこんなに舞い上がっていることの全てを理解できる・・と思います。
圧巻なテイスティングでした。今回ご案内できず、今秋以降に届くアイテムもテイスティングしていますが、それらはさらに上級キュヴェで・・物凄い味わいです。
そして、フレデリック・ジェムトンさんのドメーヌでは有りますが、
「ドメーヌ・エマニュエル・ルジェの哲学を反映させている」
と言う言葉に嘘は無い・・つまり、
「ドメーヌ・エマニュエル・ルジェがボージョレを造ると・・こうなる」
その姿をご覧いただける訳です。そしてきっと、
「さらなる成長が楽しみになる!」
ことに必ず繋がると感じます。是非ともこの見事な波に乗ってみることをお薦めします!・・そして価格は滅茶安い!・・ご検討くださいませ。
ブルゴーニュワインファンの皆さんも固唾を飲んで見守っていると思われる、期待の新人をご紹介させていただきます。フレデリック・ジェムトン氏とおっしゃるブルゴーニュ出身の・・おそらく noisy とさしては年齢も変わらないに違いない・・?白髪のナイスミドル・・??・・です。
30年務めた保険業界をリタイヤし、さすがにコート=ドール近辺に畑を買うことは出来なかったか、それとも自然豊かなボージョレのレーニエが気に入られたのか判りませんが、クリュ・ボージョレの畑、もしくは葡萄を入手し2019年より醸造することになったんですね。
そして・・何と、あのエマニュエル・ルジェさんの次男、「ギョーム・ルジェ」氏をコンサルタントに迎え、ドメーヌ・エマニュエル・ルジェの作風を大いに生かしたボージョレにしようと頑張っているそうなんです。
エマニュエル・ルジェのパスグラも当然ガメが使用されていますが、今やその・・
「パスグラでさえ、エマニュエル・ルジェを主張している!」
のは、皆さんもご存じかと思います。官能的で柔らかく、非常に良く香る素晴らしいワインになっていますよね?・・noisy も、90年代から・・だったか、ルジェのパスグラは飲んでいますが、その頃はまだ・・いや、美味しかったですが、今のようなリリース時からの「官能さ」は有りませんでした。勿論価格も滅茶安く、2千円ほどだったと記憶しています。
今やエマニュエル・ルジェさんも、いつ引退しても不思議ではない年齢になり、長男のニコラ君、次男のギョーム君が頑張ったことで、あの名作ともいうべき2017年のドメーヌ・エマニュエル・ルジェのワインが生まれた訳です。
そんなギョーム君がコンサルされたフレデリック・ジェムトン氏のドメーヌが、この「ドメーヌ・ド・ヴェルニュス」なんですね。なのでnoisyもたっぷり期待して待ってましたとばかりにテイスティングさせていただきました。
 初ヴィンテージの2019年もののNoisy wine への到着は今年2021年5月末~6月始め頃でした。アイテムは今回ご紹介の4アイテムです。・・あ、因みに左の写真はサンプル入手の2020年もの・・未発表のものです・・10アイテムほど有りますが、これがまぁ・・滅茶苦茶美味しいんですよ!・・あ、すみません、今回は2019年もののお話しでしたね。
初ヴィンテージの2019年もののNoisy wine への到着は今年2021年5月末~6月始め頃でした。アイテムは今回ご紹介の4アイテムです。・・あ、因みに左の写真はサンプル入手の2020年もの・・未発表のものです・・10アイテムほど有りますが、これがまぁ・・滅茶苦茶美味しいんですよ!・・あ、すみません、今回は2019年もののお話しでしたね。で、6月に入って2019年ものを徐々にテイスティングを始めたんです。非常にピュアで軽やかなアロマが心地良い、凄く健康的な美味しいクリュ・ボージョレでした。・・ただし、タイミングが良く無かったのか、
「ちょっと硬い・・なぁ・・余りルジェさん風にも感じないし・・」
そうなんですよ・・当初、フィネスのK君に聞いていたのとは印象が結構に異なっていました。
ですが、良く良く・・嗅ぎまわってみると、確かにルジェ風の官能さが表面に出ている白く軽やかなミネラリティの奥の奥に在ることが判ったんですね。
なので・・残念でしたが・・
「ん~・・フィネスさんには2カ月前に入荷だから・・合計で半年弱ほど・・待つかぁ・・」
と言うことで、ようやく今回ご紹介させていただくことになった訳です。
話しは飛びまして、上記写真の2020年ものですが、圧巻と言えるほど素晴らしいです。ルジェ風の「濡れたテクスチュア」がバッチリ、そして「官能さ」も出始めています。そもそもこのボトルたちはサンプルとしてフィネスさんに届いたもので、その残りを頂戴させていただいた・・と言う、ちょっとした「役得」みたいな感じですね。
なので、noisy がテイスティングしたのは、フィネスさんがテイスティングされた何日か後・・と言うことになります。
noisy 的には、2019年ものは自宅でボトルを開けて、すぐのタイミングで・・素晴らしいけれどちょっと硬かった・・それが今年の6月です。
2020年ものは今年の10月、フィネスさんで抜栓後の数日後と言うタイミングで滅茶苦茶柔らかく、濃度も出ていて美味しかった・・んです。
ですが2020年ものは、担当のK君の話しによりますと、
「到着直後と言うこともあってか、酸が少し硬かった・・」
そうなんですね。
で、同時期に飲んだ2019年もの(フルーリー、レーニエ・レ・ヴェルジェ等の今回ご紹介のアイテムたち)はとても開いていて、同時テイスティングのエマニュエル・ルジェさんのパスグラに勝るとも劣らない・・同じようなニュアンスを持った見事な味わいで、ヴェルニュスのワインがガメだけだとはとても思えなかった・・と言うのが、大方の出席者さんたちの感想
だったそうです。
そうかぁ・・と、まぁ、ある意味では noisy の想像通りでは有った訳で、流石に12本ずつしか存在しないファーストヴィンテージのワインたちを2本も消費してしまう訳にもいかないため、
「・・(良かった!)」
と、胸を撫で下ろしたところです。
ですので、ワインはやはり、
「どうやって飲むか?」
が非常に重要で、これをおろそかにしてしまうと、本来そのワインが持っている味わいを台無しにしてしまう場合も有ります。
さほど高いワインではないから・・と気を抜かず、しっかり休めて、タイミングと品温に気を付けながら飲んでいただけましたら、このクリュ・ボージョレの素晴らしさ、アンリ・ジャイエ直系、エマニュエル・ルジェ直系の素晴らしい味わいに出会うことが出来るかと・・思っています。
また、もし開けてしまったのに硬かったらどうしたら良いか?・・そんな時には、そのままコルク栓を逆刺しにして、3~5日ほど冷暗所で保存し、再び飲んでみて下さい。
次から次へと大きな話題をくれるエマニュエル・ルジェ・ファミリーです。・・が、このファミリーのボージョレへの進出は、この地区のワインを・・単に、
「ヌーヴォー専用」
と言う看板を大きく塗り替えて行くものと思っています。是非ご検討くださいませ。
 ドメーヌ ド ヴェルニュス
ドメーヌ ド ヴェルニュスDOMAINE DE VERNUS
地所:ブルゴーニュ地方 ボージョレ地区
2019年に誕生した当ドメーヌはボージョレ地区のほぼ中央に位置する「Regnie-Durette(レニエ・デュレット)」という集落に所在しています。ブルゴーニュ生まれの当主フレデリック・ジェムトン氏は保険業界で30年間働いた後、ワイン好きが高じてワイン造りを始める決意をしました。どこでワインを造るかはいくつかの候補がありましたが、最終的には美しい風景が広がり、類まれなる可能性があるボージョレに腰を据えることにしました。
ボージョレの山々に広がる畑の様々な標高や方角、土壌構成、葡萄の木の健康状態などを考え、ドメーヌ設立時には綿密に選定された合計7haの葡萄畑を購入し、その大多数は古木になっています。畑作業や醸造などのワイン造りに関しては、ブルゴーニュの試飲会で知り合ってから数年来の友人であるギョーム・ルジェ氏(エマニュエルルジェ氏の次男)にコンサルタントを依頼しています。ヴォーヌ=ロマネで家族経営のドメーヌを支えている彼の手腕や技量、哲学に感嘆したフレデリック氏は葡萄の植樹から瓶詰の日程に至るまですべての工程において指示を仰ぎ、ギョーム氏はそれに応えて「Domaine Emmanuel Rouget」の哲学をワイン造りに反映させています。
 選別しながら手摘みで収穫された葡萄は醸造所に運ばれ、テーブルの上でさらに念入りに選別された健康な粒だけを使用。除梗は区画ごとのキャラクターによって比率を変えています。
選別しながら手摘みで収穫された葡萄は醸造所に運ばれ、テーブルの上でさらに念入りに選別された健康な粒だけを使用。除梗は区画ごとのキャラクターによって比率を変えています。低温浸漬でアロマと色調をゆっくりと抽出させ、ステンレスタンクでアルコール醗酵を行ってから10ヵ月間タンクもしくは樫樽で静かに熟成させます。フレデリック氏はアペラシオンや区画が持つ個々のキャラクターを尊重してテロワールの違いを楽しめる様々なキュヴェを敢えてボージョレで造ることを目指しています。
●
2021 Morgon Grand Cras
モルゴン・グラン・クラ
【2020年ものの濃密なエロスか、2021年ものの清純な色っぽさか、どっちがタイプ?・・高いポテンシャルを減らさずに仕上げたモルゴン・グラン・クラです!】
 2019年もののド・ヴェルニュスは、美味しかったけれど・・どこにもルジェは居なかったと・・(^^;; そう思わざるを得なかった訳です。いや・・noisy だって言えないことは有りますよ。なんでもかんでも好き勝手にほざいている訳では無く、
2019年もののド・ヴェルニュスは、美味しかったけれど・・どこにもルジェは居なかったと・・(^^;; そう思わざるを得なかった訳です。いや・・noisy だって言えないことは有りますよ。なんでもかんでも好き勝手にほざいている訳では無く、「これを言ったら怒られるだろうなぁ・・」
とか、
「ここは一応、話しを通しておくべきかなぁ・・」
などと、人並みに気を使ってはいるつもりですが、そうは言っても・・ですね・・嘘はつかないので・・言えないこともある・・そういう感じです。
で、このギョーム・ルジェさんの2021年ものですが、そりゃぁ・・
「2020年もの同様にめっちゃ美味しいです~~!」
と言えば、数は無いし、ご購入いただけるのは間違い無いでしょう。でも、
「・・2020年ものとはだいぶ違うじゃん・・」
と感じてしまった以上、そこはしっかりとお伝えしなくてはと思っている訳です。
なので、
「2021年ものは新樽由来の表情は控えめ!」
です。
新樽をしっかり使えば、まぁ・・ルジェマジックなので、どのように使うか・・が一番の問題だとしても、官能さバリバリの早くから美味しいワインに仕上がるのは間違い無い訳です。
 しかし、その新樽を抑えた・・と言うことは、
しかし、その新樽を抑えた・・と言うことは、「2020年ものの化け物的な葡萄のポテンシャルには少し足りなかった」
と判断したのかな?・・と思うんですね。もしくは、ある意味においての「保険を掛けた」か、「美しいディテールを生かしたいと思った」かの、どちらかでしょう。
ですから、まるでナチュールのトップレベルの生産者さんのモルゴンのスペシャル・キュヴェを飲んでいるかのように・・いや、結果的にですが、
「モルゴンの大御所とバチバチの勝負を挑んでいる??」
そんな凄いモルゴンに仕上がっているんですね。
細やかな赤い金属のミネラリティがふんだんにあり、鉄よりもやや軽く伸びやかです。チリチリっと・・ノーズに火花が散るようなニュアンス・・でしょうか。そこに赤いベリーとラズベリーがドライに、でもしっかり感じられます。中域もたっぷりしていますがしっかり締まっています。余韻もまた、例のチリチリっとノーズへの還りを感じつつ、ノーズへは還らない、やや重量感のある濃い赤のニュアンスが残像として感じられます。
いや・・凄いですね・・しっとりもしていますが、ノーズへの訴えも非常に心地よいです。
今から飲まれても大丈夫では有りますが、色っぽさが出てくるまで待って欲しいなぁ・・とも思います。寿命はしっかり長いですが、10年という短いスパンでは終わらないポテンシャルです。飲んでみてください!超お薦めです!
以下は以前のレヴューです。
-----
【凄みさえ感じる魅力たっぷりのモルゴン・グラン・クラ!パワフルですが精緻でピュア!・・樽使いの魔術?・・素晴らしいです!】
 飲み頃だとかそうじゃないとか・・言ってる場合じゃないかもしれない・・そんな感覚に陥るド・ヴェルニュスが造る半端無いクリュ・ボージョレです。
飲み頃だとかそうじゃないとか・・言ってる場合じゃないかもしれない・・そんな感覚に陥るド・ヴェルニュスが造る半端無いクリュ・ボージョレです。2019年の初登場時は、まだまだ・・エレガントさがとても魅力的だが、そこから離れるともう何も・・と言うようなイメージでした。もっとも熟してきますと妖艶さも加わり、魅力あふれるワインであったことも間違いありません。
ところがです・・2020年ものがリリースされまして、そのサンプルをいただいた訳ですが・・いや~・・もうびっくりですよ。どちらかと言いますと、エマニュエルの息子さん、「ギョームさんの影」など微塵も感じることが無かった2019年ものからは考えられないほどの、
「まったくの別物!」
と言える豊かでピュア、繊細さを兼ね備えた見事な味わいに大変革されていたんですね・・。
「・・お~い・・2019年ものとは全く違うじゃないか~!」
と、地球の裏側の人に言いたくなってしまうほどでした。
 おそらくですが醸造的にはエマニュエル・ルジェの樽使いをド・ヴェルニュス風にアレンジしたのが大成功したのでしょうし、アンリ・ジャイエ直伝の畑の作法・・と言いますか、強制ミルランダージュ製造法??・・のような・・(^^; そんな異常なほど密度の高い葡萄に仕立てる魔法のような作業がなされたんじゃないか・・と疑いたくなるほどの凄い味わいになっています。このグラン・クラだけじゃなく、2020年のすべてのキュヴェでそれが感じられる訳です。
おそらくですが醸造的にはエマニュエル・ルジェの樽使いをド・ヴェルニュス風にアレンジしたのが大成功したのでしょうし、アンリ・ジャイエ直伝の畑の作法・・と言いますか、強制ミルランダージュ製造法??・・のような・・(^^; そんな異常なほど密度の高い葡萄に仕立てる魔法のような作業がなされたんじゃないか・・と疑いたくなるほどの凄い味わいになっています。このグラン・クラだけじゃなく、2020年のすべてのキュヴェでそれが感じられる訳です。それに加えて・・モルゴンですから・・はい。ちょっと酸化した鉄とか、マンガンとか・・そんなニュアンスがしっかりあって、やがて官能さが出てくると予想される味わいなんですが、ジャン・フォワイヤールやマルセル・ラピエールの「赤さ」と言うよりは、そこにはより熟した葡萄の「黒さ」が混じっている感じがします。ただ、例えばラピエールのキュヴェ・マルセル・ラピエールなどの上級キュヴェとは幾分、共通する部分も有るかと思います。何より、
「ピノ・ノワール的」
とさえ感じさせる見事さが有ります。
ミネラリティの要素の膨大さも2019年ものとはかけ離れていて、しかし鈍重さなどのネガティヴなニュアンスには結びつかないと言う・・なんとも「完璧!」と言ってしまいたくなる味わいでした。
因みにnoisy は、昨年の11月と今年の夏に、このワインを2度テイスティングさせていただきました。サンプルをいただけたんですね・・
ここへ来て気温がずいぶん下がっていますので、ワインの味わいも大きく変化していることと思います。もし少し硬くなっているようでしたら、様子を見ながらゆっくり飲むか、さらに締まってくるようでしたら、いったんコルクを差して翌日、翌々日などに再度飲むようにしていただくと良いと思います。
エマニュエル・ルジェ・・恐るべし!・・ギョーム・ルジェの若い感覚も半端無い!・・そう感じさせてくれること、間違い無いでしょう。超お勧めします!飲まなきゃ損、損!だと思います。
以下は以前のレヴューです。
-----
【満を持しての初登場!?・・クリュ・ボージョレ看板のひとつ、モルゴン!低域からのバランスの良さと伸びの良さ、官能さ!是非味わってみて下さい!】
 noisy も、このコラムを書くにあたって初めて見たテクニカルに・・
noisy も、このコラムを書くにあたって初めて見たテクニカルに・・「・・あ、そういうことか・・!」
と頷ずいてしまいました。
そう・・完全除梗じゃ無かったんですね・・。それなら納得です。
例えば、ルロワのボージョレ=ヴィラージュ・プリムールを飲まれたことの有る方ならお判りかと思うんですが・・
「余りヌーボーっぽくない。そもそもボージョレっぽくない。」
でしょう?
こちらのド・ヴェルニュスの2020年モルゴンもそうだったんですよ。そもそも全房っぽさが薄く、構成が大きく深く、しかし重さは無くエレガントで・・しかもモルゴンらしい鉱物のニュアンスが有って、ちょっと「チリチリ」としていて肉が有り、そこからの押し寄せるようなエキスの美味しさが素晴らしいんですね。
 結局、除梗は90%と言うことですから・・MCをしたとしても10%・・なんですね。
結局、除梗は90%と言うことですから・・MCをしたとしても10%・・なんですね。まぁ・・先に飲んじゃってますから「自身の想像が先」であって、それから答え合わせをすることになるので、
「・・あれ?・・」
と言う疑問を引きずっていた訳です。
モルゴンは古くより素晴らしい産地として認められていました。やはりその大きな構造・・独特の・・他のクリュ・ボージョレとは異なる独自性でしょうか。見た目で他のワインよりもやや「黒み」が感じられるかな?・・と思いますが、それはきっと独特の土壌組成によるものだと思います。
今回ご紹介させていただくワインの中には、「ムーラン=ナ=ヴァン」も有りますから、
「どっちが白眉か?」
と言われてしまいますと・・
「今回ご紹介の中ではムーラン=ナ=ヴァンが上!」
と言うことになってしまうんですね。その次に・・少しだけ届かなかったこのモルゴンが来ます。
しかしながら・・これも今年の秋口以降の話しになってしまいますが、
「単一畑もののモルゴン・グラン・クラ2020」
が届きます。
noisy はこれも飲んでおりまして・・すっごいモルゴンです。あの、コート・ド・ピィを凌ぐんじゃないかと・・思います。何より、
「ブルゴーニュっぽい・・と言うか、ピノっぽい!」
んですよね・・。
で、この単一畑物じゃないモルゴン2020年は、さすがにそこには届かないものの、
「いや~・・これで充分でしょう!」
と思えるほどの仕上がりです。
リーズナブルです。しかもギョーム・ルジェです。2020年ものは、
「ルジェの影が見える味わい!」
かと思います。是非飲んでみて下さい。お勧めします。
ドメーヌ・ヴァンサン・レディ
ヴァンサン・レディ
フランス Domaine Vincent Ledy ブルゴーニュ
● 昨年初めて2019年ものをご紹介させていただいたヴァンサン・レディの2020年ものをご紹介させていただきます。
当然ながら濃密なヴィンテージなんですが、やはり感じた通り、ヴァンサン・レディさん・・凄いです・・
「もしかして四半世紀早くデビューしていたら、ルーミエさん、ルジェさんクラスになっていたかも・・」
とさえ感じる・・感性の素晴らしさを感じます。
結構に様々な手法を駆使して、ワインそれぞれに個性を感じさせます。そしてもちろん、テロワールの具現も素晴らしいです・・。
2020年ものは濃く見えるが、けっしてダルい味わいでは無く、流れるような美しさを見せてくれます。そして・・まぁ・・余り言いたくないんですが、
「皆さんがおそらく眼中に無い、ショレ=レ=ボーヌやサヴィニー=レ=ボーヌがとんでも無く旨い!」
です。
A.C.ブルも実はクロ=ヴージョの国道の反対側と言うロケーションで、完全除梗してしなやかさを出していますし、看板の「レ・ポレ」は半端無い出来・・凄いです。アルコール度15パーセントもある化け物ですが・・それを感じさせないんですよ・・。
そしてどうやら、2021年ものはジャスパー・モリスさんにロックオンされたんじゃないかと・・見ていますので、もしかしたら世に認められて大化けする可能性も・・などと思っています。
しなやかで瑞々しく美しい味わい・・の下級キュヴェと、とんでもないポテンシャルを感じるトップ・キュヴェです。お勧めします。ぜひご検討くださいませ!
-----
今やブルゴーニュワインは高価な飲み物になりつつ有ります。気候の変化が植生をいじり始め、世界情勢が対立構造を深めた性で為替も変動を大きくし食料問題をも引き起こしています。そしてまた新型コロナウイルスと言う厄介ものを背負ったまま、日本はバブル崩壊後の金融機関保護、大企業保護に動いたまま身動きが出来ない状況で、サラリーも全く増えて行かない・・海外からは完全に置いて行かれたとみるべきでしょう。
そんな中ででも、
「やっぱり美味しいブルゴーニュワインを飲みたい!」
「心や身体にスッと入って来て輝きを見せながら美しく収束する・・ピノ・ノワールが大好き!」
「・・でももはや有名ドメーヌの高いワインには手が出せなくなってきた・・」
みたいな・・気持ちが生まれて来ていると思うんですね。
 まぁ・・そうは言いつつも、ルーミエやルソーやルジェのワインの案内を見てしまうと、ついつい「ポチっ」とやってしまって、後になって・・
まぁ・・そうは言いつつも、ルーミエやルソーやルジェのワインの案内を見てしまうと、ついつい「ポチっ」とやってしまって、後になって・・
「・・どうやってカミさんを誤魔化すか・・」
と嬉しいやら何やら困惑の自分に、何やってるんだろう・・なんて思ってしまう訳です。
でもヨクヨク考えてみれば、ルーミエさんだってワインを飲み始めた頃はまるで知らず、たまたま飲んでみたら凄く美味しくてハマった・・んですよね。
だから noisy も頑張って、どんどん素敵な造り手さんを探して、飲んで、ご紹介して・・を延々繰り返して来ました。今や・・それらの造り手さんたちは大人気になってしまい、いつの間にか Noisy wine から姿を消した・・つまり、Noisy にも分けていただけないような状況になってしまった・・ほど、売れるドメーヌになったとも言えます。
で、そんな時にはテイスティングを繰り返して、
「これは行ける・・かも!」
「・・将来性が・・ある!」
と見込んだ生産者さんをご紹介している訳でして・・・そんな中で久しぶりに「ニュイ」の新しいドメーヌをご紹介出来ることになりました。
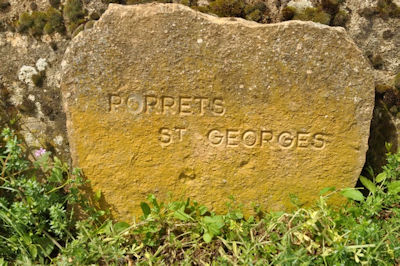 その名は「ドメーヌ・ヴァンサン・レディ」です。ニュイ=サン=ジョルジュ村のドメーヌで、2007年スタートと言うことです。日本には今までも一度、ちらっと入ったことは有ったようですが、傷跡さえ残せずにいたようです。
その名は「ドメーヌ・ヴァンサン・レディ」です。ニュイ=サン=ジョルジュ村のドメーヌで、2007年スタートと言うことです。日本には今までも一度、ちらっと入ったことは有ったようですが、傷跡さえ残せずにいたようです。
ですが、ニュイの大御所の一人、アラン・ミシュロを叔父に持っているそうでして、ニュイ=サン=ジョルジュの素晴らしい「1級レ・ポレ・サン=ジョルジュ」を所有しています。まぁ・・叔父さんに何とかしてもらったのかなぁ・・などと邪推していますが・・。
で、その「1級レ・ポレ2019」が相当・・旨いんですよ。ここは、ニュイ=サン=ジョルジュ村の南のドンケツに有る最高の区画「1級レ・サン=ジョルジュ」の北に有り、南から、
「レ・サン=ジョルジュ」-->「レ・カイユレ」-->「レ・ポレ」
と連なっている・・最高のロケーションで有ると言えます。
あ、ちょっと脱線しますが、あのアンリ・グージュの「クロ・デ・ポレ・サン=ジョルジュ」は「レ・ポレ・サン=ジョルジュ」の北に接していて、実はこの2つを合わせて、
「レ・ポワレ」
と言う区画名になっているんですね。ちょっと複雑では有りますが、そこを判っていないとニュイ=サン=ジョルジュ村の地図をいくら探しても、クロ・デ・ポレもレ・ポレも見つけられないと言う・・寂しい結果になってしまいます。
で、このレ・ポレは最高に旨いです!・・そして、そのV.V.が造られていて、そのキュヴェがこのドメーヌのトップ・キュヴェと言うことになります。
また、オート=コートの赤白、ショレ=レ=ボーヌ、サヴィニー=レ=ボーヌもそれぞれに個性を発揮していて、合格です。リーズナブルですし・・他のドメーヌとの違いも結構有って、
「これからのニュイの群雄割拠な状況に割り込んでゆく可能性が有り!」
と見ています。
また今回は入って来ていませんが、どうやらクロ=ヴージョの低地にA.C.ブルの畑も持っているようで、これも楽しみにしています。
スタイル的にはちょっと面白くて、
「新樽嫌い」
だそうです。「樽からのタンニンをワインにまとわせるのが怖い・・」みたいな言い方をしています。なので、
「ピノ・ノワールには新樽を使わない・・すべて古樽を使用」
のようです。
ですが、「新樽嫌い」のクセにオート=コートの白にはビッチリ・・樽の影響が見られるんですね。それでも決して樽に負けない見事な味わいでは有るんですが、
「ブルゴーニュの古くからの技法で、先に新樽を一度白ワインに使い、その後ピノ・ノワールに使用する」
みたいなことをやっているはずです。
まぁ・・現状、インポーターさんも初めての輸入で余り資料を提示できないようで、仕方が無いのでアチコチのネットを探りまくって、そんなことだろうと当たりを付けました。
味わい的にはエレガント系で綺麗系でエキス系・・酸が出っ張らない穏やかな膨らみが見事ですから、飲んでみていただけましたら、「好きかも!」と言っていただけるんじゃないかと思います。
そんな訳で初のお目見えです。まだ誰も目を付けていないので・・あ、日本でも・・そして海外も・・です。フーリエやセシル・トランブレイが大ブレークしたようになってくれたらなぁ・・と思いますが、そうなってしまうと・・
「また毎年30%ずつ減らされる」
ことになりかねないので痛し痒し・・。でも今のところはリーズナブルですし、知られていないドメーヌと言うことで、
「ブルゴーニュワインフリークたちの心をくすぐることが出来るかもしれない」
造り手だと思います。是非ご検討くださいませ。
■ エージェント情報
◇ゼロからスタート、センスが光るナチュラル志向の若きヴィニュロン
ニュイ・サン・ジョルジュの名手として知られるドメーヌ・アラン・ミシュロの立役者、アラン氏を叔父に持つヴァンサン・レディが2007年にゼロから立ち上げた新しいドメーヌで本拠地はニュイ・サン・ジョルジュ。家系より相続したレ・ポレ・サン・ジョルジュ以外は少しづつ畑を買い足し、現在は合計4.1haを所有し、細部まで目を向けて栽培から醸造まで全ての作業を基本1人で行う。購入した畑はAOPブルゴーニュ、オート・コート・ド・ニュイ、ショレ・レ・ボーヌ、サヴィニー・レ・ボーヌと著名なアペラシオンではないが、知名度や格付けよりも樹齢や土壌、方角といった畑の区画そのもののポテンシャルに着目している。
ボーヌの醸造学校で学んだ後に同じニュイ・サン・ジョルジュ村のスター生産者であるドメーヌ・レシュノーの下で修業を積む。その縁で現在でも使用する樽は全てレシュノーで数年使用した樽を譲り受けている。平均樹齢は40年以上の畑では2013年より有機栽培を実践し(※2021年産より認証取得)、自然と収量を制限する事に注力。全房発酵を積極的に実践し抽出は優しく行う。伝統手法を重んじながらも自然な造りを基本とし、テロワールを最大限に引き出すには新樽からのタンニンは不要という考えから古樽のみを使用し、滓引きは行わずに18ヶ月のシュール・リー熟成。清澄・ろ過も行わずにSO2の添加を極力抑えた状態で瓶詰めされる。
仕上がりワインはテロワールとヴィンテージの特徴を反映させたピュアかつ完熟した果実感があり、キュヴェによってはナチュラルワイン特有の揮発酸が若干感じられるがネガティブな要素ではなく、活力に溢れ絶妙なバランスを保っている。その個性豊かなスタイルは「ベタンヌ・ドゥソーヴ」2019年版にて年間最優秀発見生産者として掲載されており、年々フランス国内での人気が高まっている。まだまだ発展途上ではあるが将来がとても楽しみな生産者。
当然ながら濃密なヴィンテージなんですが、やはり感じた通り、ヴァンサン・レディさん・・凄いです・・
「もしかして四半世紀早くデビューしていたら、ルーミエさん、ルジェさんクラスになっていたかも・・」
とさえ感じる・・感性の素晴らしさを感じます。
結構に様々な手法を駆使して、ワインそれぞれに個性を感じさせます。そしてもちろん、テロワールの具現も素晴らしいです・・。
2020年ものは濃く見えるが、けっしてダルい味わいでは無く、流れるような美しさを見せてくれます。そして・・まぁ・・余り言いたくないんですが、
「皆さんがおそらく眼中に無い、ショレ=レ=ボーヌやサヴィニー=レ=ボーヌがとんでも無く旨い!」
です。
A.C.ブルも実はクロ=ヴージョの国道の反対側と言うロケーションで、完全除梗してしなやかさを出していますし、看板の「レ・ポレ」は半端無い出来・・凄いです。アルコール度15パーセントもある化け物ですが・・それを感じさせないんですよ・・。
そしてどうやら、2021年ものはジャスパー・モリスさんにロックオンされたんじゃないかと・・見ていますので、もしかしたら世に認められて大化けする可能性も・・などと思っています。
しなやかで瑞々しく美しい味わい・・の下級キュヴェと、とんでもないポテンシャルを感じるトップ・キュヴェです。お勧めします。ぜひご検討くださいませ!
-----
今やブルゴーニュワインは高価な飲み物になりつつ有ります。気候の変化が植生をいじり始め、世界情勢が対立構造を深めた性で為替も変動を大きくし食料問題をも引き起こしています。そしてまた新型コロナウイルスと言う厄介ものを背負ったまま、日本はバブル崩壊後の金融機関保護、大企業保護に動いたまま身動きが出来ない状況で、サラリーも全く増えて行かない・・海外からは完全に置いて行かれたとみるべきでしょう。
そんな中ででも、
「やっぱり美味しいブルゴーニュワインを飲みたい!」
「心や身体にスッと入って来て輝きを見せながら美しく収束する・・ピノ・ノワールが大好き!」
「・・でももはや有名ドメーヌの高いワインには手が出せなくなってきた・・」
みたいな・・気持ちが生まれて来ていると思うんですね。
 まぁ・・そうは言いつつも、ルーミエやルソーやルジェのワインの案内を見てしまうと、ついつい「ポチっ」とやってしまって、後になって・・
まぁ・・そうは言いつつも、ルーミエやルソーやルジェのワインの案内を見てしまうと、ついつい「ポチっ」とやってしまって、後になって・・「・・どうやってカミさんを誤魔化すか・・」
と嬉しいやら何やら困惑の自分に、何やってるんだろう・・なんて思ってしまう訳です。
でもヨクヨク考えてみれば、ルーミエさんだってワインを飲み始めた頃はまるで知らず、たまたま飲んでみたら凄く美味しくてハマった・・んですよね。
だから noisy も頑張って、どんどん素敵な造り手さんを探して、飲んで、ご紹介して・・を延々繰り返して来ました。今や・・それらの造り手さんたちは大人気になってしまい、いつの間にか Noisy wine から姿を消した・・つまり、Noisy にも分けていただけないような状況になってしまった・・ほど、売れるドメーヌになったとも言えます。
で、そんな時にはテイスティングを繰り返して、
「これは行ける・・かも!」
「・・将来性が・・ある!」
と見込んだ生産者さんをご紹介している訳でして・・・そんな中で久しぶりに「ニュイ」の新しいドメーヌをご紹介出来ることになりました。
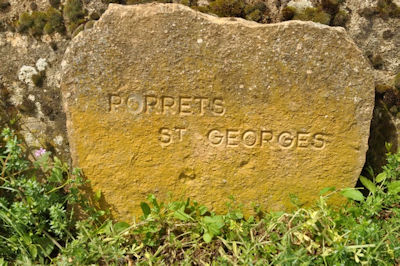 その名は「ドメーヌ・ヴァンサン・レディ」です。ニュイ=サン=ジョルジュ村のドメーヌで、2007年スタートと言うことです。日本には今までも一度、ちらっと入ったことは有ったようですが、傷跡さえ残せずにいたようです。
その名は「ドメーヌ・ヴァンサン・レディ」です。ニュイ=サン=ジョルジュ村のドメーヌで、2007年スタートと言うことです。日本には今までも一度、ちらっと入ったことは有ったようですが、傷跡さえ残せずにいたようです。ですが、ニュイの大御所の一人、アラン・ミシュロを叔父に持っているそうでして、ニュイ=サン=ジョルジュの素晴らしい「1級レ・ポレ・サン=ジョルジュ」を所有しています。まぁ・・叔父さんに何とかしてもらったのかなぁ・・などと邪推していますが・・。
で、その「1級レ・ポレ2019」が相当・・旨いんですよ。ここは、ニュイ=サン=ジョルジュ村の南のドンケツに有る最高の区画「1級レ・サン=ジョルジュ」の北に有り、南から、
「レ・サン=ジョルジュ」-->「レ・カイユレ」-->「レ・ポレ」
と連なっている・・最高のロケーションで有ると言えます。
あ、ちょっと脱線しますが、あのアンリ・グージュの「クロ・デ・ポレ・サン=ジョルジュ」は「レ・ポレ・サン=ジョルジュ」の北に接していて、実はこの2つを合わせて、
「レ・ポワレ」
と言う区画名になっているんですね。ちょっと複雑では有りますが、そこを判っていないとニュイ=サン=ジョルジュ村の地図をいくら探しても、クロ・デ・ポレもレ・ポレも見つけられないと言う・・寂しい結果になってしまいます。
で、このレ・ポレは最高に旨いです!・・そして、そのV.V.が造られていて、そのキュヴェがこのドメーヌのトップ・キュヴェと言うことになります。
また、オート=コートの赤白、ショレ=レ=ボーヌ、サヴィニー=レ=ボーヌもそれぞれに個性を発揮していて、合格です。リーズナブルですし・・他のドメーヌとの違いも結構有って、
「これからのニュイの群雄割拠な状況に割り込んでゆく可能性が有り!」
と見ています。
また今回は入って来ていませんが、どうやらクロ=ヴージョの低地にA.C.ブルの畑も持っているようで、これも楽しみにしています。
スタイル的にはちょっと面白くて、
「新樽嫌い」
だそうです。「樽からのタンニンをワインにまとわせるのが怖い・・」みたいな言い方をしています。なので、
「ピノ・ノワールには新樽を使わない・・すべて古樽を使用」
のようです。
ですが、「新樽嫌い」のクセにオート=コートの白にはビッチリ・・樽の影響が見られるんですね。それでも決して樽に負けない見事な味わいでは有るんですが、
「ブルゴーニュの古くからの技法で、先に新樽を一度白ワインに使い、その後ピノ・ノワールに使用する」
みたいなことをやっているはずです。
まぁ・・現状、インポーターさんも初めての輸入で余り資料を提示できないようで、仕方が無いのでアチコチのネットを探りまくって、そんなことだろうと当たりを付けました。
味わい的にはエレガント系で綺麗系でエキス系・・酸が出っ張らない穏やかな膨らみが見事ですから、飲んでみていただけましたら、「好きかも!」と言っていただけるんじゃないかと思います。
そんな訳で初のお目見えです。まだ誰も目を付けていないので・・あ、日本でも・・そして海外も・・です。フーリエやセシル・トランブレイが大ブレークしたようになってくれたらなぁ・・と思いますが、そうなってしまうと・・
「また毎年30%ずつ減らされる」
ことになりかねないので痛し痒し・・。でも今のところはリーズナブルですし、知られていないドメーヌと言うことで、
「ブルゴーニュワインフリークたちの心をくすぐることが出来るかもしれない」
造り手だと思います。是非ご検討くださいませ。
■ エージェント情報
◇ゼロからスタート、センスが光るナチュラル志向の若きヴィニュロン
ニュイ・サン・ジョルジュの名手として知られるドメーヌ・アラン・ミシュロの立役者、アラン氏を叔父に持つヴァンサン・レディが2007年にゼロから立ち上げた新しいドメーヌで本拠地はニュイ・サン・ジョルジュ。家系より相続したレ・ポレ・サン・ジョルジュ以外は少しづつ畑を買い足し、現在は合計4.1haを所有し、細部まで目を向けて栽培から醸造まで全ての作業を基本1人で行う。購入した畑はAOPブルゴーニュ、オート・コート・ド・ニュイ、ショレ・レ・ボーヌ、サヴィニー・レ・ボーヌと著名なアペラシオンではないが、知名度や格付けよりも樹齢や土壌、方角といった畑の区画そのもののポテンシャルに着目している。
ボーヌの醸造学校で学んだ後に同じニュイ・サン・ジョルジュ村のスター生産者であるドメーヌ・レシュノーの下で修業を積む。その縁で現在でも使用する樽は全てレシュノーで数年使用した樽を譲り受けている。平均樹齢は40年以上の畑では2013年より有機栽培を実践し(※2021年産より認証取得)、自然と収量を制限する事に注力。全房発酵を積極的に実践し抽出は優しく行う。伝統手法を重んじながらも自然な造りを基本とし、テロワールを最大限に引き出すには新樽からのタンニンは不要という考えから古樽のみを使用し、滓引きは行わずに18ヶ月のシュール・リー熟成。清澄・ろ過も行わずにSO2の添加を極力抑えた状態で瓶詰めされる。
仕上がりワインはテロワールとヴィンテージの特徴を反映させたピュアかつ完熟した果実感があり、キュヴェによってはナチュラルワイン特有の揮発酸が若干感じられるがネガティブな要素ではなく、活力に溢れ絶妙なバランスを保っている。その個性豊かなスタイルは「ベタンヌ・ドゥソーヴ」2019年版にて年間最優秀発見生産者として掲載されており、年々フランス国内での人気が高まっている。まだまだ発展途上ではあるが将来がとても楽しみな生産者。
●
2020 Bourgogne Rouge les Combes
ブルゴーニュ・ルージュ・レ・コンブ
【これは・・樽の影響がめちゃ少ないクロ=ヴージョ的・・濡れて柔らかで果実がしっかり・・何が似てるかって言ったら・・困ってしまいますね。】
 なるほど・・高目の値付けだし、人気のあるのも頷ける仕上がりです。
なるほど・・高目の値付けだし、人気のあるのも頷ける仕上がりです。昨年の2019年ものの時には、noisy も出遅れたのも有って・・入手できなかった経緯が有ります。それに、上級キュヴェのオート=コートとの価格差が余り無いのも・・有りますよね。
ですがオート=コートは準村名ですがニュイ=サン=ジョルジュのさらに南側です。こちらはA.C.ブルとは言え、ヴージョの国道の東に接する畑です。
「言ってしまえば、畑の反対側はグラン・クリュのクロ=ヴージョ!」
ですから、その辺の事情も有ってか・・余りオート=コートとの差が無いのかもしれません。
で、このキュヴェは完全除梗したキュヴェのようです。ふんわりと柔らかなチェリーな果実がピュアに、しっかり存在しています。
2020年的な果実の濃さも有りますが、
「ヴァンサン・レディ的なスッキリと綺麗に収束する感じ」
が有って、全体のバランスは非常に良いです。
 「ん・・これで新樽とか、やや焦げた樽由来の表情が有ったら?」
「ん・・これで新樽とか、やや焦げた樽由来の表情が有ったら?」と考えますと、道を挟んだ反対側にあるあのグラン・クリュを考えてしまいますよね。
その昔、クロ=ヴージョの最下部で、素晴らしいクロ=ヴージョをリリースする生産者さんがいました。ジャン・ラフェさんです。
彼はまぁ・・確かに弱いヴィンテージも有りましたが、ご機嫌にエレガントで超ふんわりしたクロ・ヴージョを、
「・・えっ?・・こんなところから?・・A.C.ブルと変わらないじゃん・・」
みたいな低地で造っていました。
そのことを考えますと・・彼の少し弱いヴィンテージは、
「下手すればこのA.C.ブルの方が・・(^^;;」
と・・考えてしまいます。
でもまぁ・・ヨクヨク考えてみましたら、その頃のジャン・ラフェさんの3種類ほど異なるエチケットが有ったクロ=ヴージョは6~8千円でしたから、
「今も価格は・・変わらない?」
かもしれません。
なんでジャン・ラフェを思い出したかと言いますと、国道の反対側が・・と言うことも有りますが、
「滑らかですっきり、でも微細な抑揚がある素晴らしいクロ=ヴージョ」
と言うことも有ったと思います。飲んでみてください。ヴァンサン・レディ...只者では無いと思っていただけるでしょう。お薦めです!
●
2020 Chorey-les-Beaune les Beaumonts
ショレ=レ=ボーヌ・レ・ボーモン
【少なくとも・・少なくともですよ、「こんなに素晴らしいショレ=レ=ボーヌ、飲んだことない!」と言っていただけると思います!激推し!】
 まぁ・・サヴィニーのコラムでも書かせていただいたんですが、ショレ=レ=ボーヌやサヴィニー=レ=ボーヌのワインは、なんでしょうね・・飲まず嫌いと言うよりは、
まぁ・・サヴィニーのコラムでも書かせていただいたんですが、ショレ=レ=ボーヌやサヴィニー=レ=ボーヌのワインは、なんでしょうね・・飲まず嫌いと言うよりは、「・・ん~~・・酸っぱい・・(薄い・・)」
などとご経験から思われていると思うんですね。フレデリック・コサールでさえ・・サヴィニーは売れないですからね。あれは結構、濃い目なんですね。
ショレと言えばご存じなのはきっと「トロ=ボー」さんでしょう。あのドメーヌこそ、昔は淡くて薄くて硬くて酸っぱかった・・(^^;
でも今はどうです?・・飲まれて無いかもしれませんが、相当美味しくなって来ました。でも、このヴァンサン・レディのショレ=レ=ボーヌ2020はきっと、
「もっと美味しい!」
です。
桜と言うかさくらんぼ・・と言うレベルはアロマにはわずかに有りますが、やはり品の良いチェリーかな・・実にリアリティが高いです。
そして濃い目には出ているんですが瑞々しく、ミネラリティがしっかり支えてくれています。
で・・このショレのレ・ボーモンは、
「ショレ=レ=ボーヌと言っても、ほとんどサヴィニー=レ=ボーヌ!」
でして、
「・・なんでここがショレなの?」
と・・(^^;; そんなロケーションです・・ここは深くは追いませんが・・。
 甘みはほとんどなく、ドライなのに・・
甘みはほとんどなく、ドライなのに・・「酸バランスが途轍もなく素晴らしい!」
ので、
「うまみ成分も嫌味無くしなやかに流れるような感じ」
に感じます。
そして余韻・・静かなのに燃えているようなエナジーを感じます・・この人、ヴァンサン・レディさん・・いや、末恐ろしいと思ってます。こんなワインが造れるのなら、
「ブルゴーニュのトップ10に入れる能力を持っている!」
と言わざるを得ないんじゃないか?・・とさえ思っています。
この先、どんなワインを造ってくれるのか、そしていつか海外メディアの目に触れ、持ち上げられる日が来るのか来ないのか?・・判りませんが、
「価格もあるが、noisyも見守っていきたいと思っているドメーヌの一人」
です。
まぁ・・今回のヴァンサン・レディの2020年ものも、noisy の予想をはるかに超える値上げになっていましたので、
「せっかく2019年ものである程度良いスタートが切れたのに、ここで普通の値付けをしたのでは上手く行かないのでは?」
と言うような心配も有って、下限ギリギリの値付けになっています。
言ってみれば、
「この価格でも滅茶安い」
ですし、
「価格に見合った・・もしくは価格以上のポテンシャルを持っている!」
と判断した訳です。ぜひこのショレ=レ=ボーヌ・レ・ボーモン
以下は以前のレヴューです。
-----
【実はこのショレ=レ=ボーヌ・レ・ボーモンは、あの、目ちゃんこ美味しいマリウス・ドラルシェのペルナン=ヴェルジュレス・レ・ブティエールに接する畑・・なんです(^^;;】
 ドラルシェの2017年、ペルナン=ヴェルジュレス・レ・ブティエール..美味しいでしょう?・・何とも色っぽく熟した超エレガントなピノ・ノワール。全く濃く無く、しかし官能に直結して訴えてくる見事な味わいに仕上がっていました。
ドラルシェの2017年、ペルナン=ヴェルジュレス・レ・ブティエール..美味しいでしょう?・・何とも色っぽく熟した超エレガントなピノ・ノワール。全く濃く無く、しかし官能に直結して訴えてくる見事な味わいに仕上がっていました。言ってみれば、「濃度(濃さ)」は、本来持っている様々な表情をマスキングします。その奥にあるものを見つけようとしないなら、全く見当たらないんですね。
ですが若い時の「濃さ」と「若さ(フレッシュさ)」は、マスキングと未生成になりますし、適度に熟してきてもその「濃さ」は中々・・奥に行ってはくれないものです。
なので、2017年と言うヴィンテージで熟し始めて来たエレガントなレ・ブティエールは、素晴らしい味わいになっていた訳です。
で、今回のヴァンサン・レディのショレ=レ=ボーヌ・レ・ボーモン2019ですが、実は・・
「レ・ブティエールと言う区画とすると、隣同士!」
なんですよ。村の名前も違いますから気付かないかもしれませんが、区画同士がお隣です。もう少し細かく言いますと、
「レ・ブティエールと言う区画はアロース=コルトンとペルナン=ヴェルジュレスにあり、そしてサヴィニー=レ=ボーヌにはレ・ブティエールに接したオー・ブティエールが存在する」
んです。なので、このショレのレ・ボーモンのお隣が3つの村に有るレ・ブティエール(+ オ・ブティエール)と接しているんですね。
で、言ってみれば、
「ドラルシェのペルナン=ヴェルジュレス・レ・ブティエールはショレ=レ=ボーヌ的な繊細で軽妙なワイン」
でもあり、ドラルシェのアロース=コルトンとも地続きでしたよね?ですが、アロース=コルトンとペルナン=ヴェルジュレス・レ・ブティエールは隣に有るとは思えないほど違います。より豊かなんですね。
ですが、こちらのショレ=レ=ボーヌ・レ・ブティエールは・・エレガントで優しく、レ・ブティエールの持つエレガントさを2/3ほど、アロース=コルトンの豊かさを1/6ほど持っている・・そう思っていただけますと近い味筋じゃないかと思います。
そもそもショレ=レ=ボーヌって、ホントに売れなかったんですね・・。トロ=ボーも熟すと美味しいんですが、ショレ=レ=ボーヌ..売れないので、シャルドネばかりを探して販売させていただいてました。トロ=ボーのA.C.ブルのシャルドネ、ホント、名品です。そう言い続けていたら、最近は全く買えなくなってしまっています。
 このレ・ボーモン、ヴァンサン・レディの手によりますと、
このレ・ボーモン、ヴァンサン・レディの手によりますと、「ショレ=レ=ボーヌらしからぬ酸の柔らかさ」
を感じられると思います。
「ショレ=レ=ボーヌって、もっとずっと軽くてスレンダー・・だよね?」
と思われるかもしれませんが、ヴァンサン・レディのピノ・ノワールって、酸の当たりがマイルドでふんわり優しいんですね。これはすべてのキュヴェに言えます。
その上で、さくらんぼ的な果実..チェリーとは言いたくないかなぁ・・とベリーが少し、中域はややスレンダーながら非常にバランスが良く、ミネラリティも充分に感じられます。
「ちょうどアロース=コルトン、ペルナン=ヴェルジュレス、ショレ=レ=ボーヌのそれぞれの特徴を併せ持った味わいがする」
微妙な表情のワインなんですね。
まぁ、ショレ=レ=ボーヌ自体は複雑性はやや乏し目では有りますが軽妙な美味しさが有り、しかも「早く熟し始める」ことが、直近の美味しさを生んでくれる訳です。
今飲んでも満足できますし、2~3年でピークに近い形になりますから、実に有難い・・んです。
なんでも複雑で濃くて要素が凄いワインばかりじゃ・・開けた時にこっちを向いてくれるかどうかが「賭け」になってしまいます。早熟さも魅力の内です。是非飲んでみてください。お勧めします!
ル・プレ・ヴェール
ル・プレ・ヴェール
フランス Le Pre Vert シュド=ウエスト
● 魅力的なフランス南西地方のビオロジックのワイン生産者を紹介させていただきます。ギョーム・ジャックマンさんと言う若い生産者さんのようです。奥様は日本人のようで、どんどん世界はボーダーレスになって行く現代を感じさせてくれます。
基本的には「酸化防止剤を使用したくない人」だけれど、「必要な時は少量使用する」方のようです。アイテムによっては揮発酸が元気なものもあるようですが、Noisy wine ではテイスティングでOK出来るものをご紹介していますのでご安心下さい。
今回の白は、「ハーフオレンジワイン??」・・皮ごとマセラシオンしつつ、アンフュージョンで葡萄を加えて行くスタイルのようで、出来は・・
「滅茶美味しい!」
です。アヴァンギャルドではないです。
赤は・・と言いますか、赤白(メルロ80%、ソーヴィニヨン20%)と言う・・「逆ロゼ」とも言いたくなるようなワインですが、
「飲んだら普通にめちゃ美味しい赤ワイン!」
です!・・しかもSo2無添加で、現状は検出限界・・凄いですね・・。
どちらも王冠で止まっていますが、ガスはほとんど無いので開ける時は心配しないで大丈夫です。
もっとも管理が悪いとどうなってしまうか判りませんのでご注意くださいね。
どちらも素晴らしいです!ぜひ飲んでみてください。将来が楽しみな生産者さんです!
 ■ みずみずしくフレッシュな南西のナチュラルワイン
■ みずみずしくフレッシュな南西のナチュラルワイン
◇ ベルジュラックの新星ドメーヌ
ル・プレ・ヴェ-ルは、ギョーム・ジャックマンが妻のYasuko ヤスコと共に2017 年にフランスの南西地方に創設したドメーヌです。ボルドーの様々なシャトーでワインを造り、オーストラリアやアメリカでの醸造経験もあるギヨームは、自身でチュラルワインを造りたいという想いにかられ、妻のヤスコとともに理想の場所を探していましたが、2017 年、ベルジュラックの丘の上に森に囲まれた素晴らしいブドウ畑を見つけて移住。ワイン造りを始めたのです。
◇ 緑が溢れる生き生きとした地で生まれるナチュール
自然とワインを愛する二人は、すぐに畑をビオとビオディナミ農法に転換。無耕起、無肥料で栽培を行っています。畑の周りには池や林があり、カエルや魚が泳ぎ、鴨などの野鳥が飛来します。そして、野生のプルーンやサクランボ、栗など様々な木々の茂る林には猪や鹿、キツネやウサギが現れます。二人は、緑が溢れる生き生きとしたこの地で、その年のブドウの出来に合わせたワインを造っています。
◇ ドメーヌについて
Le Pré Vert ル・プレ・ヴェ-ルは、Guillaume Jacquemin ギョーム・ジャックマンが妻のYasuko ヤスコと共に2017年に南西地方に創設したドメーヌです。ボルドーの様々なシャトーでワインを造り、オーストラリアやアメリカでの醸造経験もあるギヨームは、自身でワイン造りをしたいという想いにかられ、妻のヤスコとともに、丘の上で、家とセラーとブドウ畑が森に囲まれていると言う条件を満たす場所を探していました。2017 年、二人はベルジュラックの Razac de Saussignac ラーザック・ド・ソシニャックのコミューンに、その理想に叶う素晴らしい場所を見つけて移住。ワイン造りを始めたのです。
 自然とワインを愛する二人は、すぐに畑をビオとビオディナミ農法に転換。無耕起、無肥料で栽培を行っています。ビオディナミの調剤の他に、空豆やクローバー、セレアルなどを緑肥として畑に撒いています。また、畑と周辺の生物と植物の調和、そして気候変動に対応するため、畑の周辺に生け垣を作り、果樹を植えています。ブドウ畑の周りには池や林があり、魚が泳ぎ、蛙、イモリ、オケラ、アメンボなどが生息しています。鴨などの野鳥も飛来します。また野生のプルーンやサクランボ、栗など様々な木々の茂る林には猪や鹿、キツネやウサギがいて、時々畑にも現れます。
自然とワインを愛する二人は、すぐに畑をビオとビオディナミ農法に転換。無耕起、無肥料で栽培を行っています。ビオディナミの調剤の他に、空豆やクローバー、セレアルなどを緑肥として畑に撒いています。また、畑と周辺の生物と植物の調和、そして気候変動に対応するため、畑の周辺に生け垣を作り、果樹を植えています。ブドウ畑の周りには池や林があり、魚が泳ぎ、蛙、イモリ、オケラ、アメンボなどが生息しています。鴨などの野鳥も飛来します。また野生のプルーンやサクランボ、栗など様々な木々の茂る林には猪や鹿、キツネやウサギがいて、時々畑にも現れます。
Le Pré Vert ル・プレ・ヴェ-ルとはフランス語で緑の草原と言う意味です。二人は、緑が溢れる生き生きとしたこの地で、その年のブドウの出来に合わせたワインを造りたいとの想いから、ドメーヌ名をル・プレ・ヴェ-ルとしたとのことです。
栽培面積は6 ヘクタールで、ブドウ畑はドルドーニュ河を見下ろす丘陵の斜面に位置しています。土壌は、石灰岩の母岩で、表土はシレックスと泥灰土。栽培品種はメルロー、カベルネ・フラン、マルベック、セミヨン、ソーヴィニョン・ブラン、マンサン・ノワール、マルセラン、フェル・ザルバドゥ、ユニ・ブラン、コロンバール、シュナン・ブランなど11 品種を栽培しています。温暖化対策と病害対策のため、特に病害に弱いメルローを、糖度が上がりにくい古代来種のブドウに、少しずつ植え替えをしています。秋には羊を放牧して雑草の駆除を行います。羊の糞はそのまま畑の肥料になります。
手摘みしブドウは、野生酵母のみで自発的に発酵され、醸造添加物は一切加えずに醸造されます。発酵はステンレスタンクもしくはファイバータンクで行われ、熟成後、無清澄、ノンフィルターで瓶詰めされます。
亜硫酸は無添加、もしくは必要な場合に限り、瓶詰め時に最小限添加するのみです。ドメーヌでは、辛口の白ワインから軽い赤、ロゼ、しっかりとした赤、マセラシオンの白、甘口ワインまで、バラエティーに富んだキュヴェを手掛けています。ル・プレ・ヴェ-ルのワインは、どれもみずみずしくフレッシュで、美しくしなやか味わいが特徴です。
基本的には「酸化防止剤を使用したくない人」だけれど、「必要な時は少量使用する」方のようです。アイテムによっては揮発酸が元気なものもあるようですが、Noisy wine ではテイスティングでOK出来るものをご紹介していますのでご安心下さい。
今回の白は、「ハーフオレンジワイン??」・・皮ごとマセラシオンしつつ、アンフュージョンで葡萄を加えて行くスタイルのようで、出来は・・
「滅茶美味しい!」
です。アヴァンギャルドではないです。
赤は・・と言いますか、赤白(メルロ80%、ソーヴィニヨン20%)と言う・・「逆ロゼ」とも言いたくなるようなワインですが、
「飲んだら普通にめちゃ美味しい赤ワイン!」
です!・・しかもSo2無添加で、現状は検出限界・・凄いですね・・。
どちらも王冠で止まっていますが、ガスはほとんど無いので開ける時は心配しないで大丈夫です。
もっとも管理が悪いとどうなってしまうか判りませんのでご注意くださいね。
どちらも素晴らしいです!ぜひ飲んでみてください。将来が楽しみな生産者さんです!
 ■ みずみずしくフレッシュな南西のナチュラルワイン
■ みずみずしくフレッシュな南西のナチュラルワイン◇ ベルジュラックの新星ドメーヌ
ル・プレ・ヴェ-ルは、ギョーム・ジャックマンが妻のYasuko ヤスコと共に2017 年にフランスの南西地方に創設したドメーヌです。ボルドーの様々なシャトーでワインを造り、オーストラリアやアメリカでの醸造経験もあるギヨームは、自身でチュラルワインを造りたいという想いにかられ、妻のヤスコとともに理想の場所を探していましたが、2017 年、ベルジュラックの丘の上に森に囲まれた素晴らしいブドウ畑を見つけて移住。ワイン造りを始めたのです。
◇ 緑が溢れる生き生きとした地で生まれるナチュール
自然とワインを愛する二人は、すぐに畑をビオとビオディナミ農法に転換。無耕起、無肥料で栽培を行っています。畑の周りには池や林があり、カエルや魚が泳ぎ、鴨などの野鳥が飛来します。そして、野生のプルーンやサクランボ、栗など様々な木々の茂る林には猪や鹿、キツネやウサギが現れます。二人は、緑が溢れる生き生きとしたこの地で、その年のブドウの出来に合わせたワインを造っています。
◇ ドメーヌについて
Le Pré Vert ル・プレ・ヴェ-ルは、Guillaume Jacquemin ギョーム・ジャックマンが妻のYasuko ヤスコと共に2017年に南西地方に創設したドメーヌです。ボルドーの様々なシャトーでワインを造り、オーストラリアやアメリカでの醸造経験もあるギヨームは、自身でワイン造りをしたいという想いにかられ、妻のヤスコとともに、丘の上で、家とセラーとブドウ畑が森に囲まれていると言う条件を満たす場所を探していました。2017 年、二人はベルジュラックの Razac de Saussignac ラーザック・ド・ソシニャックのコミューンに、その理想に叶う素晴らしい場所を見つけて移住。ワイン造りを始めたのです。
 自然とワインを愛する二人は、すぐに畑をビオとビオディナミ農法に転換。無耕起、無肥料で栽培を行っています。ビオディナミの調剤の他に、空豆やクローバー、セレアルなどを緑肥として畑に撒いています。また、畑と周辺の生物と植物の調和、そして気候変動に対応するため、畑の周辺に生け垣を作り、果樹を植えています。ブドウ畑の周りには池や林があり、魚が泳ぎ、蛙、イモリ、オケラ、アメンボなどが生息しています。鴨などの野鳥も飛来します。また野生のプルーンやサクランボ、栗など様々な木々の茂る林には猪や鹿、キツネやウサギがいて、時々畑にも現れます。
自然とワインを愛する二人は、すぐに畑をビオとビオディナミ農法に転換。無耕起、無肥料で栽培を行っています。ビオディナミの調剤の他に、空豆やクローバー、セレアルなどを緑肥として畑に撒いています。また、畑と周辺の生物と植物の調和、そして気候変動に対応するため、畑の周辺に生け垣を作り、果樹を植えています。ブドウ畑の周りには池や林があり、魚が泳ぎ、蛙、イモリ、オケラ、アメンボなどが生息しています。鴨などの野鳥も飛来します。また野生のプルーンやサクランボ、栗など様々な木々の茂る林には猪や鹿、キツネやウサギがいて、時々畑にも現れます。Le Pré Vert ル・プレ・ヴェ-ルとはフランス語で緑の草原と言う意味です。二人は、緑が溢れる生き生きとしたこの地で、その年のブドウの出来に合わせたワインを造りたいとの想いから、ドメーヌ名をル・プレ・ヴェ-ルとしたとのことです。
栽培面積は6 ヘクタールで、ブドウ畑はドルドーニュ河を見下ろす丘陵の斜面に位置しています。土壌は、石灰岩の母岩で、表土はシレックスと泥灰土。栽培品種はメルロー、カベルネ・フラン、マルベック、セミヨン、ソーヴィニョン・ブラン、マンサン・ノワール、マルセラン、フェル・ザルバドゥ、ユニ・ブラン、コロンバール、シュナン・ブランなど11 品種を栽培しています。温暖化対策と病害対策のため、特に病害に弱いメルローを、糖度が上がりにくい古代来種のブドウに、少しずつ植え替えをしています。秋には羊を放牧して雑草の駆除を行います。羊の糞はそのまま畑の肥料になります。
手摘みしブドウは、野生酵母のみで自発的に発酵され、醸造添加物は一切加えずに醸造されます。発酵はステンレスタンクもしくはファイバータンクで行われ、熟成後、無清澄、ノンフィルターで瓶詰めされます。
亜硫酸は無添加、もしくは必要な場合に限り、瓶詰め時に最小限添加するのみです。ドメーヌでは、辛口の白ワインから軽い赤、ロゼ、しっかりとした赤、マセラシオンの白、甘口ワインまで、バラエティーに富んだキュヴェを手掛けています。ル・プレ・ヴェ-ルのワインは、どれもみずみずしくフレッシュで、美しくしなやか味わいが特徴です。
●
2022 Couci-Couca V.d.F.
クゥシ=クゥサ V.d.F.
【いわゆるところオレンジワインなのかもしれませんが、ソーヴィニヨン・ブランをアンフュージョンした・・「先進的ボルドー・ブラン!」のように感じられるかもしれません!・・美味しいです!】
 巷では自然はワインがウケていると・・言われ始めてからもう十数年が経過していると感じます。自然派ワインが「自然派ワインとして」・・輸入されてからは四半世紀ほどです。それ以前にももちろん、自然派的アプローチで造られたワインは・・
巷では自然はワインがウケていると・・言われ始めてからもう十数年が経過していると感じます。自然派ワインが「自然派ワインとして」・・輸入されてからは四半世紀ほどです。それ以前にももちろん、自然派的アプローチで造られたワインは・・「日本には普通のワインとして輸入されていた」
訳です。
言ってみれば、ポンソもデュジャックも・・そうでした。ですが彼らは栽培はビオディナミ、ビオロジックだったとしても、醸造では少量でしょうがSo2を使っていました。
つまり、自然派とSo2不使用もしくは必要な場合にごく少量のみ添加・・と言うのは切り離せないように感じられますが、別にビオだからと言ってSo2を使用することはビオの名乗りには全く関係が無い・・訳ですね。仮にたっぷりSo2を使用していたとしてもビオディナミはビオディナミ、ビオロジックも同様です。
日本ではまるで流行りの移り変わりが激しいファッションのように扱われている面も・・あるようにも感じます。もちろん、お客様は価格にも敏感です。
日本に初めて入って来た頃は、自然派ワインはリーズナブルでした・・いや、高いものも有りましたが・・そのようなものは徐々に時間を掛けて入って来たように感じます。
日本で長く自然派ワインが受け入れられてからは、徐々にアジアやその他の地域でも拡がっているようで、人気のワインはさらに価格も上がっていますし、入手も難しくなって来ているのはご存じの通りです。
難しいのは・・価格が上がりますと、今までと同じようには手を出せなくなってしまう・・と言う点でしょう。それでも noisy は比較楽観的で、いずれ「円」は買われ、日本人のサラリーも上がって・・結果的には為替の異常なほどの円の相場は修正されると思っています。
 で、ル・プレ・ヴェールです。南勢地方ですからボルドーの南です。
で、ル・プレ・ヴェールです。南勢地方ですからボルドーの南です。畑に羊を飼って、循環型の農業をされているようです。奥様は日本人なのかな?・・「ヤスコさん」とだけご紹介されています・・ん?・・あ、違うヤスコさんですよ。
このソーヴィニヨン・ブランをアンフュージョンして長いマセラシオンに持ち込んで造る「クゥシ・クゥサ」・・(口xでは無いです・・すみません・・)は、一見して・・
「オレンジワイン」
に感じられます。アンフュージョンと言うのは、発酵中のワインに袋に入れた葡萄を「煎じるように」入れる手法です。なので、その分・・酸化も抑えられるような気がします。
ナチュラルでソーヴィニヨンらしい、「柑橘っぽいニュアンス」が残った、美味しいオレンジ?・・です。フルーツのオレンジの感じも有ります。
お茶や紅茶、ウーロン茶のようなニュアンスは非常に少なく、途轍もなくドライでもない・・非常にバランスに優れた仕上がりをしています。
ですから、
「果実の風味を失ってお茶系のニュアンスしかない・・」
と言うような、マセラシオン系に良く有り勝ちなタイプでは有りません。
敢えて言うならば・・
「ボルドーの白をビオディナミ的に追い求めてみた!・・それでとても美味しく出来た!」
みたいな・・感じがします。
だって・・如何にオレンジワインでも、藁とかお茶とかの風味しかしない・・と、食中酒としてならまだ判るが・・余り面白く無いですよね。
膨らみも有って果実もちゃんとしっかり、そして何より・・
「深い味わいが長く持続する!」
んですね。
ナチュラルで、身体への進入角度がなだらかで、とても美味しくて・・酔い覚めも軽い・・です。飲んでみてください。お勧めします!
ドメーヌ・エレオノール・モロー
エレオノール・モロー
フランス Domaine Eleonore Moreau ブルゴーニュ
● シャブリの期待の星・・のご紹介です。少し気にはなっていたんですが中々手を出せなかったところ、ようやくちょっかいを出せたと言う・・(^^;; なんのこっちゃい・・。
別嬪さんのエネオノールさんが、ビオ的(ビオロジック&ビオディナミ)なアプローチで素晴らしいシャブリを造っています。
意外にも有りそうで無いタイプでして、
「結構にナチュール感も有りつつ、でも全く危なくないと思えるライン・・そのギリギリを攻めている感じ!」
が実に良い!
だって・・別にね・・ラヴノーもドーヴィサも・・ナチュール感はそれなりに有りつつもそんなに攻めてる感じはしないでしょう?・・アリス・エ・オリヴィエも、凄い昔はね・・面白いキュヴェを出してくれていました。So2無添加と自筆で書いて貼ってあったりね・・でも別に・・そんなにナチュール感は無いでしょう?・・キッシキシに硬いのはなんでなんだろうと思っちゃう位でしょう?
言ってしまえば、あの鬼才、「ヤン・ドゥリュー」的な要素も感じる訳ですよ。・・いや、彼女のワインは全然アヴァンギャルドでは無いですよ。でもその下地が無い訳では無いし、これから・・
「・・ど~する?・・どっちに行きたいの?」
と・・。見守りたいなぁと思うんですね。それだけ、彼女のワインに魅力を感じている noisyです。ご検討よろしくお願いいたします。
■ エージェント情報
 シャブリ地区南東部、ポワリー・シュル・スラン村に長く続く農業家の家系で、1982年にローラン・モローがぶどう畑を拓きました。2011年に娘のエレオノールが参画。5年後の2016年にドメーヌを継承し、本格的に自社ビン詰めを開始しました。もともと環境に対して高い意識を持っていた彼女は、2011年の参画と同時に、お父さんの時代のリュット・レゾネ栽培から、完全ビオロジック栽培に切り替えました。
シャブリ地区南東部、ポワリー・シュル・スラン村に長く続く農業家の家系で、1982年にローラン・モローがぶどう畑を拓きました。2011年に娘のエレオノールが参画。5年後の2016年にドメーヌを継承し、本格的に自社ビン詰めを開始しました。もともと環境に対して高い意識を持っていた彼女は、2011年の参画と同時に、お父さんの時代のリュット・レゾネ栽培から、完全ビオロジック栽培に切り替えました。
「化学肥料や農薬を使わないことで、ぶどう樹、土壌、土中の生態系、そして畑で働く私たちすべてにとって、持続可能なぶどう栽培が可能になります。根は地下深く伸び、チトニアン(ポルトランディアン)、キンメッリジアンといったシャブリ地区が誇る石灰質土壌から、ミネラルをたっぷりと吸い上げてくれます。シャブリ地区は早霜や雹害も多く、ビオロジック栽培を実践する生産者は他の産地と比べて少ないのですが、私はいつまでもその一人であり続けたいと思います。」
醸造設備の刷新や、彼女自身が気に入るまで時間をかけて創り上げた新しいパッケージの完成を経て、2020年からようやく輸出にも目を向けられるようになりました。2021年にはプルミエ・クリュの初リリースも予定しております。大地の深き恵みに溢れる彼女の作品には、他のシャブリとは一線を画すようなみずみずしさがあり、体の細胞のひとつひとつに染み入るような「癒し」を感じることができます。
別嬪さんのエネオノールさんが、ビオ的(ビオロジック&ビオディナミ)なアプローチで素晴らしいシャブリを造っています。
意外にも有りそうで無いタイプでして、
「結構にナチュール感も有りつつ、でも全く危なくないと思えるライン・・そのギリギリを攻めている感じ!」
が実に良い!
だって・・別にね・・ラヴノーもドーヴィサも・・ナチュール感はそれなりに有りつつもそんなに攻めてる感じはしないでしょう?・・アリス・エ・オリヴィエも、凄い昔はね・・面白いキュヴェを出してくれていました。So2無添加と自筆で書いて貼ってあったりね・・でも別に・・そんなにナチュール感は無いでしょう?・・キッシキシに硬いのはなんでなんだろうと思っちゃう位でしょう?
言ってしまえば、あの鬼才、「ヤン・ドゥリュー」的な要素も感じる訳ですよ。・・いや、彼女のワインは全然アヴァンギャルドでは無いですよ。でもその下地が無い訳では無いし、これから・・
「・・ど~する?・・どっちに行きたいの?」
と・・。見守りたいなぁと思うんですね。それだけ、彼女のワインに魅力を感じている noisyです。ご検討よろしくお願いいたします。
■ エージェント情報
 シャブリ地区南東部、ポワリー・シュル・スラン村に長く続く農業家の家系で、1982年にローラン・モローがぶどう畑を拓きました。2011年に娘のエレオノールが参画。5年後の2016年にドメーヌを継承し、本格的に自社ビン詰めを開始しました。もともと環境に対して高い意識を持っていた彼女は、2011年の参画と同時に、お父さんの時代のリュット・レゾネ栽培から、完全ビオロジック栽培に切り替えました。
シャブリ地区南東部、ポワリー・シュル・スラン村に長く続く農業家の家系で、1982年にローラン・モローがぶどう畑を拓きました。2011年に娘のエレオノールが参画。5年後の2016年にドメーヌを継承し、本格的に自社ビン詰めを開始しました。もともと環境に対して高い意識を持っていた彼女は、2011年の参画と同時に、お父さんの時代のリュット・レゾネ栽培から、完全ビオロジック栽培に切り替えました。「化学肥料や農薬を使わないことで、ぶどう樹、土壌、土中の生態系、そして畑で働く私たちすべてにとって、持続可能なぶどう栽培が可能になります。根は地下深く伸び、チトニアン(ポルトランディアン)、キンメッリジアンといったシャブリ地区が誇る石灰質土壌から、ミネラルをたっぷりと吸い上げてくれます。シャブリ地区は早霜や雹害も多く、ビオロジック栽培を実践する生産者は他の産地と比べて少ないのですが、私はいつまでもその一人であり続けたいと思います。」
醸造設備の刷新や、彼女自身が気に入るまで時間をかけて創り上げた新しいパッケージの完成を経て、2020年からようやく輸出にも目を向けられるようになりました。2021年にはプルミエ・クリュの初リリースも予定しております。大地の深き恵みに溢れる彼女の作品には、他のシャブリとは一線を画すようなみずみずしさがあり、体の細胞のひとつひとつに染み入るような「癒し」を感じることができます。
●
2021 Petit Chablis
プティ・シャブリ
【チトニアン階の石灰的なニュアンスを「まるっ」と感じさせてくれる、むしろブルゴーニュ・シャルドネ的なプティ・シャブリ!・・出来は非常に良いです!】
 まぁ・・「キンメリジャンのシャブリ」と言う観点からのみ物を言うのであれば、プティ・シャブリは鬼っ子です。
まぁ・・「キンメリジャンのシャブリ」と言う観点からのみ物を言うのであれば、プティ・シャブリは鬼っ子です。「全然シャブリっぽく無い!」
みたいな感じが、シャブリを知れば知るほど・・強くなってくる訳です。
そしてその時代背景と言いますか、
「・・なんでそんなこと、したのよ・・」
と言いたくなる事件が有った訳ですね。
そう・・時代は、
「白ワインの代名詞となったシャブリ!」
そのものが・・ですね・・いや、全世界で、白ワインには「シャブリ」と名付けるようなことになってしまったことで、本来はキンメリッジでは無い場所を拡張して「プティ・シャブリ」と言うアペラシオンを設定したんですね。
まぁ・・キンメリッジの畑も増やしたんですが、すでにもう増やせないほどに拡張済。なので、その周りのチトニアン階の畑も「何とかシャブリ」にしたかった訳です。・・まぁ・・経済の発展も必要ですから・・。
ですが、むしろシャブリの周りのプティ・シャブリよりも、違う村のシャルドネの方がシャブリに似通っている事例が出て来てしまいましたので、却ってシャブリの斜陽を招くことになった・・そんな感じでしょうか。プティ・シャブリが出来た背景を駆け足で何となく説明させていただきました。
ですので、プティ・シャブリと(本物の)シャブリはめっちゃ・・違います。本物のと書いたのは、シャブリを名乗っていても・・
「ど~なのかな~・・これってキンメリジャン?」
みたいな感じのシャブリもそれなりに有るからです。ドーヴィサのシャブリなんぞ飲んだ後にネゴスのシャブリを飲むと・・
「・・水か・・?」
みたいな・・いや、それは大袈裟だとしても、シャリっともせず、粘土石灰っぽかったりするとちょっとテンション、下がっちゃいますよね。
 ですが、村名シャブリでもキンメリ感の無いものが結構に有ります。まぁ・・腕が追い付かないとかも有るかと思いますが、
ですが、村名シャブリでもキンメリ感の無いものが結構に有ります。まぁ・・腕が追い付かないとかも有るかと思いますが、「そもそもキンメリジャンでは無い部分にまでシャブリは拡張された!」
ことが、シャブリの低迷に拍車をかけてしまったと思います。
でも、プティ・シャブリならまぁ・・それも許されるかな・・とも思いますので・・このチトニアンの粘土石灰土壌のプティ・シャブリになりますと、言ってみれば緯度の高い部分の粘土石灰土壌のシャルドネと同様ですから、
「ちゃんと造れれば美味しいシャルドネになる」
のは当然でしょう。
ビオ的アプローチで香りは柔らか、スピードも有ります。ちょっと「クレイ」と言いたくなるようなノーズに石灰感が混じり、丸みを帯びた柑橘果実が心地良いです。
さすがに村名シャブリのような外向的・・と言いますか、八方美人的な・・誰にでも微笑みかけてくれるような感じでは有りませんが、
「むしろフリンティでは無いアロマが、慣れ親しんだシャルドネのニュアンスに近い」
と感じられます。
まぁ・・こちらは2021年ものですから熟成期間も村名シャブリに比較して短いので、4~5日では残念ながら開かず、抜栓直後の華やかなニュアンスがむしろ閉じたまま・・で飲み切ってしまいました。ですので、これをもっと開かそうとするのは結構に大変ですから、
「プティ・シャブリは1日で飲み切りましょう!」
と言うことにしておきます。
どうしても・・と言う方には、もう平底デキャンタに落として(ラップして)5日ほど・・15~16度ほどで置いてみると良いかもしれません。ただしこの方法は実践していませんので確証無しです。
また、村名シャブリのキンメリジャンと、プティ・シャブリのチトニアンを比較するのは、土壌の違いがどれほどに異なるワインの表情になるのかを「有り体に」教えてくれます。しかもどちらもポテンシャルは高いです。是非飲んでみてください。お勧めします!
ドメーヌ・ブッツォ・ボニファシオ
ブッツォ・ボニファシオ
フランス Domaine Buzzo Bunifazziu コルス
● 何とコルスのワインをご紹介することになりました。地中海に浮かぶコルス島、もしくはコルシカ島です。ナポレオンが生まれた島としても有名ですし、何も知らない日本人が地図を見て判断するなら、
「・・サルディーニャの、ほんとすぐの北の島だから・・イタリア領かな・・」
などと言ってしまいそうになるロケーションです。
「コルス」と言うのはフランス語、「コルシカ」と言うのはイタリア語です。またコルシカ語では「コルシガ」と最後が濁ります。ケルト人系?の民族が住んでいましたが、イタリアにちょっかいを出され、また続いてフランスにも攻め込まれ、結局フランス領になっていますが、現在はフランス領では有るものの特別な裁量権を持った「コルス地方公共団体」となっています。
noisy もワインの勉強を始めた頃に、何度かコルスのワインを飲ませていただきましたが、まぁ・・その頃の輸入の状態も有ったのでしょうが・・妙に甘さのある薄っぺらい・・香りの良く無いワインで、早々に興味を失ってしまった記憶が有ります。それに、どんなワイン関係の情報誌を読んでも、まともに取り合って貰えていない状況だったと思います。
(注)Domaine Buzzo Bunifazziu のFacebook より写真を頂戴しました。
 そんな noisy が今更どんな了見でコルスワインをご紹介することになったのか・・皆さんもご興味のある方はその辺りを知りたいと思っていらっしゃると思うんですね。
そんな noisy が今更どんな了見でコルスワインをご紹介することになったのか・・皆さんもご興味のある方はその辺りを知りたいと思っていらっしゃると思うんですね。
いや・・単純な理由ですよ・・凄く。・・それは・・
「美味しいから!」
です・・(^^;;
サルディーニャに近いですから、イタリアワイン風かと思いきや・・
「イタリア風ではない」
と感じるんですね。フレンチワイン風のエレガンスを持った出来映えです。
しかも、
「ポテンシャルが高い!」
ことと、重要なのは・・
「日本人が飲んでも美味しいと思える繊細さに加え、妙な甘さや暑苦しさが無い!」
のが挙げられます。
いくら美味しくても、ちょっと暑苦しいとか・・濃すぎるとか・・酸がキツイとか無いとか・・すぐにダメ出ししたくなるようなワイン、わざわざ買って飲みたくは無いですよね?
それに、
「・・おっ!?」
と思わせてくれるような、高質なニュアンスをアチコチに見ることが出来るんですよ・・。
どうでしょう・・いつもブルゴーニュに浸ってばかりいないで、たまには地中海を散策してみると言うのは?・・きっと、
「・・あらま・・結構・・いや、相当旨いじゃん!」
と言ってくれるはずの完成度の高さを見せてくれます。
また、地理とか歴史とかが絡んで来ますからね・・その辺にご興味のある方もいかがでしょうか。ちょっと「クルーザーに乗ってる気分で」・・
「この全く暑苦しくない美しい果実酸を愛でることが出来る高質なコルスワインを楽しんでみる!」
と言うのも「アリ」だと思います。ご検討くださいませ!
■エージェント情報
コルシカ島最南端、2000年前のボニファシオ石灰岩台地に居を構えるブッツォ・ボニファシオは粘土石灰質土壌、有機栽培で12ヘクタールの畑を所有しています。ブッツォ家において、ワイン造りは家族の物語でもあります。
2010年、ヴァンサン・ブッツォの息子ティエリーは Cala Longa と Sant‘Amanza にほど近い Ciafara と呼ばれる場所で仕事を立ち上げました。12ヘクタールという決して大きくない畑から有機栽培でスタートさせ拡張させています。葡萄栽培、セラーでの仕事は最新の注意を持って丹念に行います。コルシカ島のブドウ品種の個性、土壌の表現こそが私たちの求める感情を表現した味わいと香りを持つワインとなるのです。島という特異な環境の中で外部からの干渉を受けない独自のワイン。葡萄栽培、セラーでの仕事は最新の注意を持って丹念に行います。コルス島のブドウ品種の個性、土壌の表現こそが私たちの求める感情を表現した味わいと香りを持つワインとなるのです。
コルス島はアントワーヌ・アレナのようなトップ生産者が牽引しています。花崗岩質が主となるコルスにおいて非常に少ない隆起した石灰質土壌は、アントワーヌ・アレナのパトリモニオを銘醸畑たらしめています。
◆コルス島最南端ボニファシオ。
この小さな畑もまたコルスでパトリモニオ同様に石灰質土壌の畑でした。ブルゴーニュ、ブルーノ・クラヴリエで研鑽を積んだティエリー・ブッツォ。伝統的な地葡萄、極めて端正なワイン造りで、この土地に多く感じられる大らかさ、悠大さのみならず繊細で緻密な構成美、フィネスとも言える均整のとれた着地の美しさに驚きました。
知らずに試飲した時に感じたブルゴーニュを彷彿とさせるバランスは、造り手の経歴を見て納得です。
コルスというマイナーな土地、地葡萄でありながら決して安易に凝縮度を求めるでもなく愚直なまでに高い熟度と美しい酸のバランスを求めた極めて王道の味わいです。生産本数が少ないためご案内出来る本数に限りがございますがご興味を持っていただければ幸いです。
◆地中海に浮かぶ美しい島(イル・ド・ボーテ)コルス島。
この島に葡萄をもたらしたのは紀元前565年、小アジアから来たギリシャの航海者たちであったと伝えられています。葡萄の植樹と栽培を発展させてきたコルスは1572年、ジェノヴァ共和国はすべての農地保有者に、多額の報酬と引き換えに所有地の中に葡萄を植えることを義務づけました。
1729年に始まるコルシカ独立戦争を経てジェノヴァ共和国はフランスに統治権を譲渡。1768年、ポンテノーヴォの戦いを経てフランス統治下となりました。
1880年、暗黒の時代が始まりました。フィロキセラ禍が島を蹂躙し始めたのです。1888年にはボニファシオにもフィロキセラ禍が到達しました。葡萄の樹を植え替えた土地の所有者たちは特別措置により4年間固定資産税を免除されたにも関わらず、資本の小さな生産者たちは困窮に瀕しました。
コルス島の西側から大半を覆う花崗岩土壌、東側白亜紀のシスト土壌がこの島のテロワールとして名高いですが、コルス最上の葡萄畑と称されるパトリモニオは石灰岩土壌です。そしてコルス最南端、フィガリ湾に面したこのボニファシオもまた石灰岩土壌を有する屈指の銘醸畑なのです。
「・・サルディーニャの、ほんとすぐの北の島だから・・イタリア領かな・・」
などと言ってしまいそうになるロケーションです。
「コルス」と言うのはフランス語、「コルシカ」と言うのはイタリア語です。またコルシカ語では「コルシガ」と最後が濁ります。ケルト人系?の民族が住んでいましたが、イタリアにちょっかいを出され、また続いてフランスにも攻め込まれ、結局フランス領になっていますが、現在はフランス領では有るものの特別な裁量権を持った「コルス地方公共団体」となっています。
noisy もワインの勉強を始めた頃に、何度かコルスのワインを飲ませていただきましたが、まぁ・・その頃の輸入の状態も有ったのでしょうが・・妙に甘さのある薄っぺらい・・香りの良く無いワインで、早々に興味を失ってしまった記憶が有ります。それに、どんなワイン関係の情報誌を読んでも、まともに取り合って貰えていない状況だったと思います。
(注)Domaine Buzzo Bunifazziu のFacebook より写真を頂戴しました。
 そんな noisy が今更どんな了見でコルスワインをご紹介することになったのか・・皆さんもご興味のある方はその辺りを知りたいと思っていらっしゃると思うんですね。
そんな noisy が今更どんな了見でコルスワインをご紹介することになったのか・・皆さんもご興味のある方はその辺りを知りたいと思っていらっしゃると思うんですね。いや・・単純な理由ですよ・・凄く。・・それは・・
「美味しいから!」
です・・(^^;;
サルディーニャに近いですから、イタリアワイン風かと思いきや・・
「イタリア風ではない」
と感じるんですね。フレンチワイン風のエレガンスを持った出来映えです。
しかも、
「ポテンシャルが高い!」
ことと、重要なのは・・
「日本人が飲んでも美味しいと思える繊細さに加え、妙な甘さや暑苦しさが無い!」
のが挙げられます。
いくら美味しくても、ちょっと暑苦しいとか・・濃すぎるとか・・酸がキツイとか無いとか・・すぐにダメ出ししたくなるようなワイン、わざわざ買って飲みたくは無いですよね?
それに、
「・・おっ!?」
と思わせてくれるような、高質なニュアンスをアチコチに見ることが出来るんですよ・・。
どうでしょう・・いつもブルゴーニュに浸ってばかりいないで、たまには地中海を散策してみると言うのは?・・きっと、
「・・あらま・・結構・・いや、相当旨いじゃん!」
と言ってくれるはずの完成度の高さを見せてくれます。
また、地理とか歴史とかが絡んで来ますからね・・その辺にご興味のある方もいかがでしょうか。ちょっと「クルーザーに乗ってる気分で」・・
「この全く暑苦しくない美しい果実酸を愛でることが出来る高質なコルスワインを楽しんでみる!」
と言うのも「アリ」だと思います。ご検討くださいませ!
■エージェント情報
コルシカ島最南端、2000年前のボニファシオ石灰岩台地に居を構えるブッツォ・ボニファシオは粘土石灰質土壌、有機栽培で12ヘクタールの畑を所有しています。ブッツォ家において、ワイン造りは家族の物語でもあります。
2010年、ヴァンサン・ブッツォの息子ティエリーは Cala Longa と Sant‘Amanza にほど近い Ciafara と呼ばれる場所で仕事を立ち上げました。12ヘクタールという決して大きくない畑から有機栽培でスタートさせ拡張させています。葡萄栽培、セラーでの仕事は最新の注意を持って丹念に行います。コルシカ島のブドウ品種の個性、土壌の表現こそが私たちの求める感情を表現した味わいと香りを持つワインとなるのです。島という特異な環境の中で外部からの干渉を受けない独自のワイン。葡萄栽培、セラーでの仕事は最新の注意を持って丹念に行います。コルス島のブドウ品種の個性、土壌の表現こそが私たちの求める感情を表現した味わいと香りを持つワインとなるのです。
コルス島はアントワーヌ・アレナのようなトップ生産者が牽引しています。花崗岩質が主となるコルスにおいて非常に少ない隆起した石灰質土壌は、アントワーヌ・アレナのパトリモニオを銘醸畑たらしめています。
◆コルス島最南端ボニファシオ。
この小さな畑もまたコルスでパトリモニオ同様に石灰質土壌の畑でした。ブルゴーニュ、ブルーノ・クラヴリエで研鑽を積んだティエリー・ブッツォ。伝統的な地葡萄、極めて端正なワイン造りで、この土地に多く感じられる大らかさ、悠大さのみならず繊細で緻密な構成美、フィネスとも言える均整のとれた着地の美しさに驚きました。
知らずに試飲した時に感じたブルゴーニュを彷彿とさせるバランスは、造り手の経歴を見て納得です。
コルスというマイナーな土地、地葡萄でありながら決して安易に凝縮度を求めるでもなく愚直なまでに高い熟度と美しい酸のバランスを求めた極めて王道の味わいです。生産本数が少ないためご案内出来る本数に限りがございますがご興味を持っていただければ幸いです。
◆地中海に浮かぶ美しい島(イル・ド・ボーテ)コルス島。
この島に葡萄をもたらしたのは紀元前565年、小アジアから来たギリシャの航海者たちであったと伝えられています。葡萄の植樹と栽培を発展させてきたコルスは1572年、ジェノヴァ共和国はすべての農地保有者に、多額の報酬と引き換えに所有地の中に葡萄を植えることを義務づけました。
1729年に始まるコルシカ独立戦争を経てジェノヴァ共和国はフランスに統治権を譲渡。1768年、ポンテノーヴォの戦いを経てフランス統治下となりました。
1880年、暗黒の時代が始まりました。フィロキセラ禍が島を蹂躙し始めたのです。1888年にはボニファシオにもフィロキセラ禍が到達しました。葡萄の樹を植え替えた土地の所有者たちは特別措置により4年間固定資産税を免除されたにも関わらず、資本の小さな生産者たちは困窮に瀕しました。
コルス島の西側から大半を覆う花崗岩土壌、東側白亜紀のシスト土壌がこの島のテロワールとして名高いですが、コルス最上の葡萄畑と称されるパトリモニオは石灰岩土壌です。そしてコルス最南端、フィガリ湾に面したこのボニファシオもまた石灰岩土壌を有する屈指の銘醸畑なのです。
●
2018 Biginti Ile de Beaute I.G.P.Blanc
ビギンティ・イル・ド・ボーテ I.G.P.ブラン
【滅茶複雑なシャルドネ?・・ディテールの表情が繊細でアロマティック!・・ちょっと図抜けた感じがします!】
 何せ初めてなので・・しかもエージェントさんも良くは判っていないようですのでハッキリしたことは言い辛いんですが、通常はバルバロッサと言いますと黒か白か、どちらに分類されるかな?・・もしかすると「ブラン・ド・ノワール」なのかもしれません。ただし黒葡萄だとしても色は淡いはずだし・・ですが、
何せ初めてなので・・しかもエージェントさんも良くは判っていないようですのでハッキリしたことは言い辛いんですが、通常はバルバロッサと言いますと黒か白か、どちらに分類されるかな?・・もしかすると「ブラン・ド・ノワール」なのかもしれません。ただし黒葡萄だとしても色は淡いはずだし・・ですが、「単にバルバロッサと言っても近い品種や遠い品種が有る」
はずなので・・迂闊にどっちだと言えないのがつらいところです。
ですが色を見てみると・・どうも・・赤い色素が潜んでいるように見えませんか?・・色合いも結構濃い目ですしね・・まぁ、最初と言うことでご容赦ください。飲んで旨ければ・・何とかなるもんです。
樹齢6年だそうです。・・
「マジすか!?」
と・・思ってしまいました・。これはV.V.だろうと・・テイスティング中には思っていたんですね。何せ、テイスティング時にはエージェントさんにも資料が届いて無いし、有ったとしてもnoisy はテイスティング前には読まないので意味が有りません。
ですから、
「結構に複雑に深い味わいがある」
と思ってくださって結構です。
 ほんのりとトースティなニュアンスが立ち昇り、柔らかさを感じさせつつも硬質さも含んだアロマ。凄く上質なシャルドネ・・と言った印象で、密度の高いエキスを感じさせます。樽の要素をかき分けると、葡萄の蔓の先までを感じさせるような「薄目の緑」の残像が感じられます。質の良いスパイス・・繊細なハーブと言ったグリーンなイメージが有り、
ほんのりとトースティなニュアンスが立ち昇り、柔らかさを感じさせつつも硬質さも含んだアロマ。凄く上質なシャルドネ・・と言った印象で、密度の高いエキスを感じさせます。樽の要素をかき分けると、葡萄の蔓の先までを感じさせるような「薄目の緑」の残像が感じられます。質の良いスパイス・・繊細なハーブと言ったグリーンなイメージが有り、「・・ただものでは無いなぁ・・」
といった印象。
中域は適度に膨らみつつも締まりを失わない感じ・・まったりとしたオイリーさをほんのり感じさせながら長めの余韻が持続します。実に良い感じです。
むしろ、ここまでの高域の表情・・スパイスやハーブなどはブルゴーニュワインでは消されているのが普通ですから、その意味ではブルゴーニュ・シャルドネと区別も可能です。ですが、何ともイントネーションがブルゴーニュっぽいんですね。丸いパレットやオイリーさのニュアンス・・
おそらくですが、このブッツォさんが・・こういうのが好きなんでしょうね。少しだけ樽を感じさせつつ、オイリーで滑らかなシャルドネっぽいクセの少ない味わい・・ブルーノ・クラヴリエで修行されたと言うことなので、
「きっとブルゴーニュワインが大好きなんでしょ?」
と思ってしまいました。
いや・・・これ、樹齢6年って・・ホントですかね~・・出来るのかなぁ・・うちのピノ・ノワールもその位の樹齢ですが、手を掛けない性か・・この頃は「ひねくれて」ばっかり
です。是非飲んでみてください。ゆっくりじっくりと楽しめるコルス旅行です!
アラン・ベルナール
アラン・ベルナール
フランス Alain Bernard シャンパーニュ
● 大変に評判をいただいているピノ・ノワールによるブラン・ド・ノワールです。質感高いシャンパーニュでした!
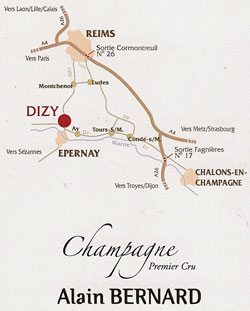 アラン・ベルナールは1912年に設立されたディジーを本拠地とするレコルタン・マニピュラン(ブドウ栽培農家兼醸造業者)の生産者です。現在では、父アランが指揮をとり、息子のブノワが営業を担う家族経営の会社です。彼らは元々はドン・ペリニヨンのような大手メゾンにブドウを供給していました。
アラン・ベルナールは1912年に設立されたディジーを本拠地とするレコルタン・マニピュラン(ブドウ栽培農家兼醸造業者)の生産者です。現在では、父アランが指揮をとり、息子のブノワが営業を担う家族経営の会社です。彼らは元々はドン・ペリニヨンのような大手メゾンにブドウを供給していました。
メゾンの偉大な創設者であるアランの父アーサーは同じディジーにあるメゾン、ガストン・シケで働いていました。彼はシケ氏にカーヴの一角を借りうけて、自分のワイン造っていました。連休となったある週末、彼は息子アランとともに、すべて手作業で、エレベーターなどを使うこともなく手押し車で何度も土砂を掘り運んだ末、地下に自分のカーヴを掘って造りあげたのです。
ワインへの情熱、それはメゾンでのサーヴィスや試飲の才能を身につけることはもちろん、ブドウの樹に対して徹底して世話をやくことです。すなわちそれが、素晴らしいワインを造ることなのです。醸造やカーヴでの仕事はもちろん重要です。しかし畑での仕事がもっとも大きな部分を占めると考えています。アラン・ベルナールでは、科学的な除草剤を一切使いません。そのため畑には雑草が生い茂っていますが、すべて畑を耕して除草剤を使わずに雑草を刈り取っています。近い将来、祖父アーサーがやっていたように、馬を用いた畑耕作に着手する予定です。
 栽培:
栽培:
1月から3月の終わりまで剪定を施します。4月には若木を誘引するリアージュと呼ばれる作業を行います。
5~6月にはその若木を結び付けるパリサージュ、7月には枝の先端を切り落とす芯止め、ログナージュを施していきます。
そして9月の下旬から10月の初頭にかけて葡萄の収穫を行うのです。
ブドウの収穫は機械ではなくすべて手作業で行います。彼らはこれが義務だと考えています。(もちろん土壌の丹念な手入れ、耕作、土寄せ、除草などの多くの畑仕事は12月の終わりから夏場まで続きます。)
醸造:
収穫してからの仕事は細心の注意を払って行います。シャプタリゼーション(アルコール補強のための糖分添加)は一切施しません。収穫の際に、その必要がない程にまで完熟して糖度があがっているからです。自然に流れ出るフリーランジュースの他、プレスしてキュヴェとプルミエ・タイユを搾汁します。その後、果汁にデブルバージュ(前清澄)1回、スーティラージュ(沈殿物を取り除く作業)を2回行います。
アルコール発酵は18℃で12~13日、そして1月にアッサンブラージュして、ティラージュを2月に施します。すべてのワインは最低でも3年間熟成させます。ルミアージュ(動瓶:瓶内二次発酵によって生成された澱を瓶口に集めるために瓶を少しづつ傾ける作業)は、ピュピトルと呼ばれるこの地方伝統の穴の空いた板を使ってすべて手作業でこの行程の度に10000~12000本行われます。
デゴルジュマン(澱引き)はすべてアラン一人で手作業で行います。デゴルジュマン後、最低でも3~6カ月間、リキュールがワインに馴染むのを待って出荷されます。このデゴルジュマンの際に添加するリキュール・デクスペディション(門出のリキュール)にはMCR(MoutConcentre Rectifile)と呼ばれる濃縮果汁を用います。多くの生産者がこの際に砂糖を添加するのに対しMCRは砂糖を一切加えずに果汁のみから生成される物質です。当然、砂糖よりも高額ですが、天然の物質のため酵母による分解が早く、よりワインに馴染みやすいのです。
植密度:8000本/1ヘクタール
所有畑:8ヘクタール(うちディジーに22区画、キュミエールに1区画、アイに4区画、オーヴィレールに1区画所有)プルミエ・クリュとグラン・クリュの畑を丁寧に耕すためにそれ以外の区画はすべて手放しました。
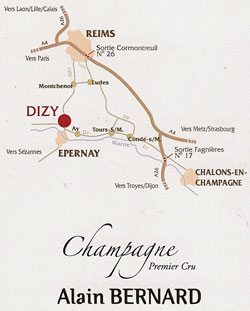 アラン・ベルナールは1912年に設立されたディジーを本拠地とするレコルタン・マニピュラン(ブドウ栽培農家兼醸造業者)の生産者です。現在では、父アランが指揮をとり、息子のブノワが営業を担う家族経営の会社です。彼らは元々はドン・ペリニヨンのような大手メゾンにブドウを供給していました。
アラン・ベルナールは1912年に設立されたディジーを本拠地とするレコルタン・マニピュラン(ブドウ栽培農家兼醸造業者)の生産者です。現在では、父アランが指揮をとり、息子のブノワが営業を担う家族経営の会社です。彼らは元々はドン・ペリニヨンのような大手メゾンにブドウを供給していました。メゾンの偉大な創設者であるアランの父アーサーは同じディジーにあるメゾン、ガストン・シケで働いていました。彼はシケ氏にカーヴの一角を借りうけて、自分のワイン造っていました。連休となったある週末、彼は息子アランとともに、すべて手作業で、エレベーターなどを使うこともなく手押し車で何度も土砂を掘り運んだ末、地下に自分のカーヴを掘って造りあげたのです。
ワインへの情熱、それはメゾンでのサーヴィスや試飲の才能を身につけることはもちろん、ブドウの樹に対して徹底して世話をやくことです。すなわちそれが、素晴らしいワインを造ることなのです。醸造やカーヴでの仕事はもちろん重要です。しかし畑での仕事がもっとも大きな部分を占めると考えています。アラン・ベルナールでは、科学的な除草剤を一切使いません。そのため畑には雑草が生い茂っていますが、すべて畑を耕して除草剤を使わずに雑草を刈り取っています。近い将来、祖父アーサーがやっていたように、馬を用いた畑耕作に着手する予定です。
 栽培:
栽培:1月から3月の終わりまで剪定を施します。4月には若木を誘引するリアージュと呼ばれる作業を行います。
5~6月にはその若木を結び付けるパリサージュ、7月には枝の先端を切り落とす芯止め、ログナージュを施していきます。
そして9月の下旬から10月の初頭にかけて葡萄の収穫を行うのです。
ブドウの収穫は機械ではなくすべて手作業で行います。彼らはこれが義務だと考えています。(もちろん土壌の丹念な手入れ、耕作、土寄せ、除草などの多くの畑仕事は12月の終わりから夏場まで続きます。)
醸造:
収穫してからの仕事は細心の注意を払って行います。シャプタリゼーション(アルコール補強のための糖分添加)は一切施しません。収穫の際に、その必要がない程にまで完熟して糖度があがっているからです。自然に流れ出るフリーランジュースの他、プレスしてキュヴェとプルミエ・タイユを搾汁します。その後、果汁にデブルバージュ(前清澄)1回、スーティラージュ(沈殿物を取り除く作業)を2回行います。
アルコール発酵は18℃で12~13日、そして1月にアッサンブラージュして、ティラージュを2月に施します。すべてのワインは最低でも3年間熟成させます。ルミアージュ(動瓶:瓶内二次発酵によって生成された澱を瓶口に集めるために瓶を少しづつ傾ける作業)は、ピュピトルと呼ばれるこの地方伝統の穴の空いた板を使ってすべて手作業でこの行程の度に10000~12000本行われます。
デゴルジュマン(澱引き)はすべてアラン一人で手作業で行います。デゴルジュマン後、最低でも3~6カ月間、リキュールがワインに馴染むのを待って出荷されます。このデゴルジュマンの際に添加するリキュール・デクスペディション(門出のリキュール)にはMCR(MoutConcentre Rectifile)と呼ばれる濃縮果汁を用います。多くの生産者がこの際に砂糖を添加するのに対しMCRは砂糖を一切加えずに果汁のみから生成される物質です。当然、砂糖よりも高額ですが、天然の物質のため酵母による分解が早く、よりワインに馴染みやすいのです。
植密度:8000本/1ヘクタール
所有畑:8ヘクタール(うちディジーに22区画、キュミエールに1区画、アイに4区画、オーヴィレールに1区画所有)プルミエ・クリュとグラン・クリュの畑を丁寧に耕すためにそれ以外の区画はすべて手放しました。
●
2018 Coteaux Champenois Rouge
コトー・シャンプノワ・ルージュ
【温暖なブルゴーニュへの憧れ?・・厳しい酸を持つシャンパーニュのピノ・ノワールを完熟させた滑らかで柔らかな熟度の高いピノ・ノワールのルージュです!】
 1級格のディジーのピノ・ノワールです。アラン・ベルナールらしいなぁ・・と感じますね。
1級格のディジーのピノ・ノワールです。アラン・ベルナールらしいなぁ・・と感じますね。そもそもシャンパーニュは冷涼な土地ですから、黒葡萄は中々熟さなかった・・昔は・・です。でも今は結構良い感じに熟しますので、こんなピノ・ノワールによるコトー・シャンプノワが生まれるようになっているんですね。
アラン・ベルナールのシャンパーニュを飲むと、「とても厳しくとがった酸」は全く無く、「厳しい酸」も出来うる限り柔らかに、その酸の棘を丸めてふんわり柔らかなテクスチュアになっていますが、このピノ・ノワールのスティル・ワインも同様です。
見た感じはヴォーヌ=ロマネじゃありませんか・・アロマも僅かに動物的な感じも在りつつ、カカオリキュールのような黒っぽさとベリーを煮詰めたようなニュアンスが交差、赤黒果実の良い感じを見せてくれます。
良く熟している感じがしますが甘く無く、「ざらっ」と舌をなでるような・・木綿で腕をこするような感じでは無く、上質な絹・・とまではいかなくても、それに近い感じのスベスベな感じで口内を通り過ぎて行きます。
 noisy 的な感覚では、このように滑らかなタイプのコトー・シャンプノワ・ルージュに出会ったことが少なく・・と言うより、「無い」かもしれません。
noisy 的な感覚では、このように滑らかなタイプのコトー・シャンプノワ・ルージュに出会ったことが少なく・・と言うより、「無い」かもしれません。そもそもコトー・シャンプノワ・ルージュは、ロゼを仕込むために造った訳でして、かのジャック・セロスでさえ当初は原酒のピノ・ノワールを用意できず・・コート・デ・ブランの生産者でしたから優れたピノ・ノワールを入手出来なかったんですね・・なので、アンボネイのエグリ=ウーリエに頼んで調達させてもらっていた訳です。
noisy もまたその頃はエグリ=ウーリエの存在は希薄でして、
「コート・デ・ブランに凄いレコルタンがいるぞ!」
と言う噂を聞きつけ、ブローカーに頼んでフランスのショップから取り寄せていただいていた訳です。・・それがあのジャック・セロス・ロゼ・・。到着してそのロゼを飲んだら・・
「・・こんなに旨いロゼ・シャンパーニュ、初めて飲んだ!」
とビックリした訳です。今だから言っちゃいますが、仕入れは6千円くらいだったと記憶しています。なので販売は1万円はしなかったんですね・・。それからあれよあれよと言う間に・・仕入れるたびに価格は上がり続けましたが、販売価格が1万円を超えるころには、ジャック・セロスも自前でピノ・ノワールを調達できるようになっていました。
それからも何度かセロスのロゼを楽しませていただきましたが・・確かに超旨いんですが、エグリ=ウーリエのピノ・ノワールが入ったセロスのロゼほどの感動が味わえない感じだったんですね・・。
そんなエグリ=ウーリエ的なピノ・ノワールとはまた全然異なる、ある意味・・現時点で完成された味わい・・を見せてくれるのが・・このアラン・ベルナールのコトー・シャンプノワ・ルージュです。エグリのピノを飲むと・・「可能性」みたいなものを感じます。アラン・ベルナールは「完成」かな?・・(^^;; 美味しいと思います。是非飲んでみて下さい。お勧めです。・・実は希少品だったりします。
■アラン・ベルナールのシャンパーニュはこちら
N.V. シャンパーニュ・プルミエ・クリュ・ブラン・ド・ブラン・ブリュット アラン・ベルナール 750ML(16481) ¥4.690
2013 シャンパーニュ・プルミエ・クリュ・ヴィンテージ・ブリュット アラン・ベルナール 750ML(16483) ¥6.580
Copyright(C) 1998-2023 Noisy Wine [ Noisy's Wine Selects ] Reserved