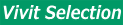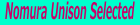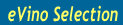頻繁なリロード禁止のお願い
大変お世話になっております。切実なお願いです。
ページのリロードが必要以上に行われるようになっています。サーバーへの過大な負荷でページ更新が滞る状況になっていますので、頻繁なリロードはお止めくださるようお願いいたします。
また、「503 Server is busy」のエラードギュメントページが表示され、一定時間アクセスが制限される場合がございます。いずれ元に戻りますが、そのようなことにならないようお願いいたします。
詳細ページ
ページのリロードが必要以上に行われるようになっています。サーバーへの過大な負荷でページ更新が滞る状況になっていますので、頻繁なリロードはお止めくださるようお願いいたします。
また、「503 Server is busy」のエラードギュメントページが表示され、一定時間アクセスが制限される場合がございます。いずれ元に戻りますが、そのようなことにならないようお願いいたします。
詳細ページ
■新着情報メールサービスのご登録
Noisy wine の新着情報メールサービスにご登録いただきますと、ご登録いただきましたメールアドレスに「タイムリーに」更新情報をお届けいたします。希少性のあるワインをご希望でしたら登録必須のサービスです。
■お届け情報他
現在以下の宛先に対し新着情報メールをお届けするすることが出来ません。世界情勢を反映してか、各社様メールのフィルターを厳しくしています。申し訳ありませんが gmail.com や yahoo.co.jp (yahoo.comは厳しいです) などのフリーアドレスに変更をご検討の上、再登録をお願いいたします。不明な方は最下段中央の「e-mail to noisy」よりお問い合わせください。
■新着情報メール不達の宛先(新規登録も出来ません)
icloud.com nifty.com me.com mac.com hi-ho.ne.jp tiki.ne.jp enjoy.ne.jp docomo.ne.jp plala.or.jp rim.or.jp suisui.ne.jp teabreak.jp outlook.com outlook.jp hotmail.co.jp hotmail.com msn.com infoseek.jp live.jp live.com
etc.
■お届け情報他
現在以下の宛先に対し新着情報メールをお届けするすることが出来ません。世界情勢を反映してか、各社様メールのフィルターを厳しくしています。申し訳ありませんが gmail.com や yahoo.co.jp (yahoo.comは厳しいです) などのフリーアドレスに変更をご検討の上、再登録をお願いいたします。不明な方は最下段中央の「e-mail to noisy」よりお問い合わせください。
■新着情報メール不達の宛先(新規登録も出来ません)
icloud.com nifty.com me.com mac.com hi-ho.ne.jp tiki.ne.jp enjoy.ne.jp docomo.ne.jp plala.or.jp rim.or.jp suisui.ne.jp teabreak.jp outlook.com outlook.jp hotmail.co.jp hotmail.com msn.com infoseek.jp live.jp live.com
etc.
noisy のお奨め

Spiegelau Grand Palais Exquisit
シュピゲラウ・グランパレ・エクスクイジット・レッドワイン 424ML
軽くて薄くて香り立ちの良い赤ワイン用グラスです。使い勝手良し!
Comming soon!

Spiegelau Grand Palais Exquisit
シュピゲラウ・グランパレ・エクスクイジット・ホワイト 340ML
軽くて薄くて香り立ちの良い白ワイン用グラスです。使い勝手良し!
Comming soon!
有 る と 便 利 な グ ッ ズ !
WEBの情報書込みもSSLで安心!


Noisy Wine [NOISY'S WINE SELECTS] のサイトでは、全ての通信をSSL/TLS 情報暗号化通信し、情報漏洩から保護しています。
◆◆Twitter 開始のご案内

時折、Twitter でつぶやき始めました。もう・・どうしようもなくしょうもない、手の施しようの無い内容が多いですが、気が向いたらフォローしてやってくださいね。RWGの徳さん、アルXXロのせんむとか・・結構性格が出るもんです。
https://twitter.com/noisywine
■□新着情報MS 2025年第40弾 Ver.1.0 page6□■
次号発行まで有効です。2025年05月23日(金) より発送を開始いたします。 最短翌日到着地域2025年05月24日(土)! になります。翌々日到着地域で2025年05月25日(日) が最短です。
発送が集中した際はご希望に添えない場合もございます。
◆新着商品は通常の送料サービスと異なります。「ここ」 で確認
◆在庫表示はページ読込時数です。既に完売もございます。
次号発行まで有効です。2025年05月23日(金) より発送を開始いたします。 最短翌日到着地域2025年05月24日(土)! になります。翌々日到着地域で2025年05月25日(日) が最短です。
発送が集中した際はご希望に添えない場合もございます。
◆新着商品は通常の送料サービスと異なります。「ここ」 で確認
◆在庫表示はページ読込時数です。既に完売もございます。
ボッカディガッビア
ボッカディガッビア
イタリア Boccadigabbia マルケ
● ロッソ・ピチェーノです。何故かnoisy の新着では今ひとつの人気なんですが、
「濃いだけじゃない・・・というよりも、決して濃すぎない」
素晴らしい果実味を持っています。
それよりも、マルケのワインに耐性を持たれていないのでしょうか?トスカーナのワインとニュアンスはそうそう変りませんので・・・やや、黒味が強いかな?と言う程度。エレガントで充実した味わいですので、是非ご検討くださいね。

どこからどう見ても極小のワイナリー、ボッカディガッビアは、様々な意味でマルケ州でもっとも興味深いワイナリーのひとつである。
1950年までワイナリーを所有していたのは、かのナポレオン直系の子孫、ルイージ・ジローラモ・ナポレオン・ボナパルト公だった。実際19世紀初頭から、ナポレオン家による経営のもと、ボッカディガッビアにはフランス品種が植えられていたのである。土地の人々が「ボルドー」、「フランチェージ」などと呼んでいた諸品種がそれだ。こうした遺産は、不幸にも競売にかけられ終焉するに至った皇帝領崩壊の際に、完全に失われてしまった。
こんなわけで、現在のオウナー、エルヴィディオ・アレッサンドリが、ピノ・ブラン、シャルドネ、ピノ・グリ、カベルネ・ソーヴィニョンを、伝統的なサンジョヴェーゼとトレッビアーノと一緒に植えたのも、まったく道理にかなったことだ。クオリティの面だけでなく、歴史的にみても意味のある選択なのだ。
ボッカディガッビアが造るワインは、以下の通り。卓越した複雑さを持つカベルネ・ソーヴィニョンのアクロンを約800ケース、柔らかくフレッシュで早飲み型のロッソ・ピチェーノ DOCを5000ケース、ピノ・グリ、ピノ・ブラン、そしてピノ・ノワールをブレンドした、深みのある独特の味わいのラ・カステッレッタ350ケース、そしてイタリアでもベストに数えられる樽発酵のシャルドネ、モンタルペルティを250ケース。そして最後に、ガルビと呼ばれる、シャルドネとトレッビアーノをブレンドした素晴らしく新鮮なワイン。
エルヴィディオの手になるボッカディガッビアの再生は、ごく最近の出来事であるが、とても情熱的な取り組みである。ただクオリティのみを追求した証ともいえる、ブドウ畑とセラーでの彼の業績を、賞賛しないわけにはいかない。畑とセラー、そしてすべてのワインのなかに味わうことのできる卓越性と興奮に関しては、オウナーと献身的なワインメーカー、ファブリツィオ・チュッフォリに敬意を表すべきだろう
「濃いだけじゃない・・・というよりも、決して濃すぎない」
素晴らしい果実味を持っています。
それよりも、マルケのワインに耐性を持たれていないのでしょうか?トスカーナのワインとニュアンスはそうそう変りませんので・・・やや、黒味が強いかな?と言う程度。エレガントで充実した味わいですので、是非ご検討くださいね。

どこからどう見ても極小のワイナリー、ボッカディガッビアは、様々な意味でマルケ州でもっとも興味深いワイナリーのひとつである。
1950年までワイナリーを所有していたのは、かのナポレオン直系の子孫、ルイージ・ジローラモ・ナポレオン・ボナパルト公だった。実際19世紀初頭から、ナポレオン家による経営のもと、ボッカディガッビアにはフランス品種が植えられていたのである。土地の人々が「ボルドー」、「フランチェージ」などと呼んでいた諸品種がそれだ。こうした遺産は、不幸にも競売にかけられ終焉するに至った皇帝領崩壊の際に、完全に失われてしまった。
こんなわけで、現在のオウナー、エルヴィディオ・アレッサンドリが、ピノ・ブラン、シャルドネ、ピノ・グリ、カベルネ・ソーヴィニョンを、伝統的なサンジョヴェーゼとトレッビアーノと一緒に植えたのも、まったく道理にかなったことだ。クオリティの面だけでなく、歴史的にみても意味のある選択なのだ。
ボッカディガッビアが造るワインは、以下の通り。卓越した複雑さを持つカベルネ・ソーヴィニョンのアクロンを約800ケース、柔らかくフレッシュで早飲み型のロッソ・ピチェーノ DOCを5000ケース、ピノ・グリ、ピノ・ブラン、そしてピノ・ノワールをブレンドした、深みのある独特の味わいのラ・カステッレッタ350ケース、そしてイタリアでもベストに数えられる樽発酵のシャルドネ、モンタルペルティを250ケース。そして最後に、ガルビと呼ばれる、シャルドネとトレッビアーノをブレンドした素晴らしく新鮮なワイン。
エルヴィディオの手になるボッカディガッビアの再生は、ごく最近の出来事であるが、とても情熱的な取り組みである。ただクオリティのみを追求した証ともいえる、ブドウ畑とセラーでの彼の業績を、賞賛しないわけにはいかない。畑とセラー、そしてすべてのワインのなかに味わうことのできる卓越性と興奮に関しては、オウナーと献身的なワインメーカー、ファブリツィオ・チュッフォリに敬意を表すべきだろう
●
2020 Rosso Piceno
ロッソ・ピチェーノ
【とても綺麗!いや、要素をしっかり持っていながら・・・美しい!】
 ボッカディガッビアって、もっとコテっとしていたと思うんですが、ミネラリティがとても前面に出ていて、果実味がやや裏側に鎮座していて、とても綺麗なお姿だと思うんですが・・。
ボッカディガッビアって、もっとコテっとしていたと思うんですが、ミネラリティがとても前面に出ていて、果実味がやや裏側に鎮座していて、とても綺麗なお姿だと思うんですが・・。まあ、これが本来の姿なのかもしれません。コンディションは抜群!是非飲んでみてくださいね。
カジュアルな価格帯のポテンシャル高いロッソです。黒中心の小果実に、僅かに赤が混じります。品種はサンジョヴェーゼにモンテプルチアーノです。この地域のロッソ・ピチェーノは比較的軽い物も多く有りますが、これは驚くほどしっかりしています。ですので、極端に安い同名のロッソ・ピチェーノとは全く違う物ですのでお間違いなく..。
太陽の恩恵を充分に受けた黒みがかった紫の液体は、色合いと同じ果実がいっぱい詰まった爆弾娘です。スパ イシーで見事に骨格が大きく、良質なタンニンを多く含んでいますが、それを凌駕するに充分な果実味が有ります。多くあるタンニンもほのかな甘みに支えら れ、厳しさを印象させません。これはとても判りやすい味わいですから、「今ひとつだな」と感じる方はいないでしょう。noisy的には90点付けて良いかな・・と思えるような味わいです..。
また特筆すべきは、全体の印象として「甘くない」ということです。これは結構難しい部分です。料理と合わせていて、トスカーナやマルケの「甘みの強いのが余分だな..」と思うことが有るはずです。特にワインを毎日のように飲まれる方は(noisyもそうです が..)その思いが強いはずです。そこで、名付けて、
「ワイン狂の為のデイリーワイン!」
ね、良い名前でしょ?それだけのポテンシャルを持っています。
で、ほとんど印象は同じなんですが、表面に出ていた果実味が縦構造の真ん中ぐらいに鎮座していますので、「奥ゆかしい」味わいになっているんですね。フ ランスワインに慣れた方でも、この奥ゆかしいエレガントさにはノックアウトされるんじゃないかなと思います。飲んでみてください。お薦めです!
●
2022 Marche Bianco Garbi I.G.T.
マルケ・ビアンコ・ガルビ I.G.T.
【味幅はあるのにシツコク無い!さっぱりしているのにシャバく無い!だから夏にもピッタリ!】
シャルドネ40%、ソーヴィニョン40%、ヴェルディッキオ20% というセパージュだそうです。ある種の黄金比・・・なのかもしれないぞ・・・とまで思わせるような、バランスの良さを感じさせてくれます。
冷ややかな柑橘系のフルーツが、ドライな味わいに映えます。そして、フレッシュでフルーティーなんですが・・・全くシャバく無いんですね。酸のバランスが絶妙に良いのでしょう。焦点がボケず、凛とした風情が感じられます。
どこかのコラムで書いたかもしれませんが、糖分で甘いだけ、糖分が無く辛いだけ・・・ではワインの味わいは成り立ちません。甘みもファクターでは有りますが、甘い、辛いは置いても、酸が重要なんですね。そして、五味を構成するバランスの良い酸が有るからこそ、ワインが美味しく感じられるんです。フルーツをほお張った時のことを考えてみてください。熟していて・・・でも、甘いだけですか?苦味も有りますよね。渋みももしかしたら有るかもしれません。酸っぱみも・・・有るでしょ?
ある種、慣れ親しんだフルーツを口にすると、食べる前からある程度想像してしまっていますので、その想像の範疇の味わいで有れば、そんなに気にすることなく(分析することなく?)食べてしまうんですね。甘いミカンだって甘いだけじゃ無いですよね。色々な味覚が組み合わさって、ミカンと認識している・・とも言えます。
ですので、アフターには僅かなビターやほんの僅かなエグミみたいなものが存在すると、よりリアルになって感じられる訳・・だと思います。もっとも、苦すぎたり、エグミが強すぎたり・・・ではバランスが悪くて駄目ですが!
という訳で、それなりに暑い地域では有りますが、とても冷涼な味わいを持った、美味しいビアンコです。夏にはピッタリ!旨いです。お奨めします!
冷ややかな柑橘系のフルーツが、ドライな味わいに映えます。そして、フレッシュでフルーティーなんですが・・・全くシャバく無いんですね。酸のバランスが絶妙に良いのでしょう。焦点がボケず、凛とした風情が感じられます。
どこかのコラムで書いたかもしれませんが、糖分で甘いだけ、糖分が無く辛いだけ・・・ではワインの味わいは成り立ちません。甘みもファクターでは有りますが、甘い、辛いは置いても、酸が重要なんですね。そして、五味を構成するバランスの良い酸が有るからこそ、ワインが美味しく感じられるんです。フルーツをほお張った時のことを考えてみてください。熟していて・・・でも、甘いだけですか?苦味も有りますよね。渋みももしかしたら有るかもしれません。酸っぱみも・・・有るでしょ?
ある種、慣れ親しんだフルーツを口にすると、食べる前からある程度想像してしまっていますので、その想像の範疇の味わいで有れば、そんなに気にすることなく(分析することなく?)食べてしまうんですね。甘いミカンだって甘いだけじゃ無いですよね。色々な味覚が組み合わさって、ミカンと認識している・・とも言えます。
ですので、アフターには僅かなビターやほんの僅かなエグミみたいなものが存在すると、よりリアルになって感じられる訳・・だと思います。もっとも、苦すぎたり、エグミが強すぎたり・・・ではバランスが悪くて駄目ですが!
という訳で、それなりに暑い地域では有りますが、とても冷涼な味わいを持った、美味しいビアンコです。夏にはピッタリ!旨いです。お奨めします!
ミケーレ・ロレンツェッティ / テッレ・ディ・ジオット
ミケーレ・ロレンツェッティ / テッレ・ディ・ジオット
イタリア Michele Lorenzetti / Terre di Giotto トスカーナ
● イタリアはトスカーナの自然派をご紹介します。なんと、あのヨスコ・グラヴネール(グラヴナー)もコンサルタントしていると言う凄腕、ミケーレ・ロレンツェッティです。
グラヴネールと言えば・・自称では有りますが、日本で最初にご紹介させていただいたのはnoisy だと思っています。勿論、「ネットで・・」ですけど・・ね。
そもそもはフリウーリの凄い生産者がいる・・と言うのを聞きつけ、色々と無い情報を集めていたところ、
「高いのに酷いシャルドネだ。木っ端を入れたマコンの方がマシだ!」
と、某Pxさんが言っているのを聞き、ブローカーから何とか入手して飲んでみると、滅茶苦茶旨いじゃ無いですか・・!それが、ヨスコ・グラヴネールの「ブレグ」と言うワインだったんですね・・。
で、ま~・・もともとがひねくれていますから、彼のような凄い評論家さんの言うことは話半分に聞くような性格がさらに進んでしまった訳です。
グラヴネールは1995年にそれまでの造りを止め、ビオディナミコに走っています。また、品種も地場品種のみにしましたんで、あの物凄いシャルドネはもう「幻」になってしまいました。noisy もマグナムを数本残していましたが、今はもう有りません。
グラヴネールさん・・あ、ミケーレさんと一緒に写っていますね・・も、そこから自然派の大家になられましたが、今だに模索中・・のようにも感じられます。
ですから・・興味あるでしょう?・・醸造家でもあり、生物学者でも有るミケーレさんが、グラヴネールさんのコンサルをやっているんですから。勿論、グラヴネールさんが1997年から始めたビオの造りに最初から参加している訳ではない・・としてもです。
なので、ものに寄っては非常に少ない数しか入手できなかったんですが、今回は仕入れられたキュヴェを全てテイスティングし、その方向性を見定めさせていただきました。いや・・想像以上に面白かったですよ。
なにせ、グラヴネールは地場品種のみ・・ですよ。それも北部のフリウーリです。なのにミケーレは中部のトスカーナ高地。そしてフランス品種なんですよ。
で、気になる「揮発酸由来のアロマ」ですが・・
「全く無し!」
です。・・面白いでしょう?・・グラヴネールも無いですけどね。
で、マセラシオンのキュヴェは僅かにですが・・色落ちはしています。・・でも、
「ほんの僅かな酸化のニュアンスから湧き出すフルーツ香!」
と言う、嘘みたいなフレーズが、全くの現実となって感じられたんですね。・・面白いでしょう?
栽培・醸造コンサルタントが造るピュアなワイン・・・イタリア北部に多く存在するビオディナミコの造り手のワインと比較することで大きな指標であることが判ります。
意外なほど・・綺麗なんですね~・・しかも価格も非常にリーズナブルです。
ガッタイアシリーズは上級キュヴェ・・と言う理解で良いです。しかもマセラシオンしている方だと思ってください。テッレ・ディ・ジオットは下級キュヴェでデイリー感覚の、さらにピュアに仕上げたシリーズと言う理解で・・今のところは良いと思います。是非とも飲んでいただきたい、興味深いワインです。
■エージェント情報

ミケーレ・ロレンツェッティは醸造家で生物学者です。1971年にローマ近郊のフラスカーティで生まれたミケーレは、ローマの大学で生物学を修めた後、さらに醸造学の学士号を取得しました。
しかし、その間に慣行農法のブドウ栽培ではいかに多くの化学薬品が使われているか、そして土壌が単なる根に栄養分を与えるための人工的媒体にしか見なされていないことに強い衝撃を受けたのです。
やがて、彼は土壌は生態系の一つであり、植物が健康に成長していくためには土壌が健康であれば十分であるという確信を持ち、そして、この考えを実践に移すための方法を探す中で、カルロ・ノロと出会い、ビオディナミを学びました。そして、2004年からビオディナミのブドウ栽培と醸造のコンサルタントとして活動を始め、現在ではグラヴネルやイル・マッキオーネ、ラ・ヴィショラなどイタリア全土の数多くのワイナリーでコンサルタントを行っています。ミケーレのビオディナミの師であるカルロ・ノロは、ローマの南にあるLabico ラビーコで農場を経営し、30年以上前からビオディナミのプレパラシオン(調剤)の販売とビオディナミの講座を開催している、フランスのピエール・マッソンのような、イタリアにおけるビオディナミの重鎮的存在です。
ミケーレ・ロレンツェッティはコンサルタント業とは別に、カルロ・ノロの協力者として、ビオディナミ調剤の生産やビオディナミの基礎講座などにも携わっています。
 ミケーレはコンサルタントという職業の経験的背景を完成するためには実践的な仕事が不可欠と考え、自身でもワイン造りをしたいという想いを持っていました。
ミケーレはコンサルタントという職業の経験的背景を完成するためには実践的な仕事が不可欠と考え、自身でもワイン造りをしたいという想いを持っていました。
ある時、仕事でフィレンツェ北部のMugello ムジェッロ地区を訪れた彼は、その地のミクロクリマに強い感銘を受けたのです。ムジェッロは15 世紀にメディチ家がトスカーナ地方修めていた時代から、ワイン造りのために選ばれたテロワールでした。古文書によれば当時は29 ものドメーヌがあり、数多くの果物、そして特にブドウが栽培されていたと記述されています。
1867 年にブルゴーニュ出身の醸造家ヴィットリオ・デリ・アルビジが父から広大な土地を相続します。その土地にはブドウ畑がありましたが、当時はトレッビアーノが栽培されていました。彼はこのトスカーナの高貴なテロワールを表現する個性豊かなワインを造るために、トレッビアーノをピノ・ノワールなどのフランスの高貴品種に植え替えていったのです。しかし、それはフランスの模倣ではなく、高貴品種によってムジェッロのテロワールの個性を表現するための試みで、大きな成功を収めたのです。
しかし、フィロキセラによってブドウ畑は全滅してしまいました。過去のこの貴重な経験を現代に蘇らせるため、ミケーレは2006 年にMugello ムジェッロ地方のVicchio ヴィッキオのコミューンに土地を購入して、自身のワイナリーTerre di Giottoテッレ・ディ・ジオットを設立したのです。
 ムジェッロ地区はフィレンツェの北東約25km、アペニン山脈の麓にある渓谷です。アペニン山脈からの冷たい風の通り道となっているため、トスカーナでも極めて冷涼な気候に恵まれています。加えて、昼夜の寒暖差が大きく風通しが良いため、湿気が畑にたまらないという好条件が備わっています。
ムジェッロ地区はフィレンツェの北東約25km、アペニン山脈の麓にある渓谷です。アペニン山脈からの冷たい風の通り道となっているため、トスカーナでも極めて冷涼な気候に恵まれています。加えて、昼夜の寒暖差が大きく風通しが良いため、湿気が畑にたまらないという好条件が備わっています。
また、霧が眼下に立ち込めるほど標高が高いため、霜の被害を受けることもありません。この独特のミクロクリマと、19 世紀にフランス系品種が栽培されていたという歴史から、ロレンツェッティはこの地には冷涼気候の品種が向くと考えました。そこで、Gattaia ガッタイアと呼ばれる標高500~600 メートルの斜面に位置する1.5ha の区画にピノ・ノワール、シュナン・ブラン、ソーヴィニョン・ブラン、リースリングといった品種を2006 年から2007 年にかけて植樹しました。
このうちシュナン・ブランは、2004 年に友人であるマルク・アンジェリの所に滞在した際に、マルクからフェルム・デ・サンソニエールでマッサル・セレクションした苗木、2000 本を譲り受けて植樹したものです。
また、2015 年には同じヴィッキオのコミューンにあるPesciola ペシオラと呼ばれる1.2ha の畑を購入しました。こちらは標高200 メートルの南向きの斜面の区画で、1972 年に植樹されたサンジョヴェーゼ、トレッビアーノ、マルヴァジアといった地場品種が栽培されています。ドメーヌの所有畑ですが、地元の小さなブドウ栽培家3 人と共同で栽培を行っていて、収穫ブドウを4 人で分配するため、ドメーヌの受け取り分は20%のみです。このため、1 つのワインの生産量は多くても1.000 本にしかなりません。どちらの畑もビオディナミで栽培を行っていますが、ペシオラの畑は認証は受けていません。
ミケーレ・ロレンツェッティのビオディナミへのアプローチは、現実的かつ合理的で、理論的・哲学的推測ではなく、直接の経験と科学的研究に焦点を当てています。彼はビオディナミについて以下のように述べています。
「ビオディナミはブドウ栽培家にとって大きなチャンスです。ビオディナミを実践することは、技術や方法を習得することだけでなく、専門的かつ人間的に豊かな感受性を発達させてくれます。ビオディナミは化学物質を除去し、土壌とブドウの健康を強化してくれます。ビオディナミは予防であり介入ではありません。慣行農法においては、植物の成?に有利な土壌中の窒素やリン、カリウムをベースとする肥料を用いることに慣れてしまっています。しかし、ビオロジックやビオディナミにおいては野菜や動物に由来する有機物質に限って使用をしています。有機物質とビオディナミ調剤によってもたらされるメカニズムにより、土中の腐植土が修復され、ブドウ木はより強くより表現力豊かになります。さらに、醸造添加物なして自発的に発酵できるブドウを収穫することが可能になります。その結果、テロワールの強い個性とアイデンティティーを備えた健康で消化しやすい真のナチュラルワインが生まれるのです。私は単なるワインメーカーになることには興味がありません。造り手の背後にある私の役目は、農業の最高のツールであるビオディナミを提供することです。まず何よりも大切なのはブドウです。10 年以上の醸造経験を通して、自発的な発酵だけが確実な結果を与えてくれるということが分かりました。外的な介入のないワインは、純粋にブドウが育ったテロワールと、そのヴィンテージの作柄の結晶であるのです。」
醸造について

ドメーヌでは、収穫したブドウを野生酵?のみで自発的に発酵させ、培養酵?や酵素、その他のいかなる醸造添加物も加えず、温度管理も一切行わず、清澄も濾過も行わない、可能な限り外的介入のない醸造を行っています。マロ発酵もブドウ自身の力で自発的に自然発生的に行われています。白ワインの場合も100%のケースで行われています。SO2はマロ発酵の後、もしくは瓶詰め時にごく少量添加しています。
またドメーヌでは複数の品種のブレンドによるワインを醸造する場合、全ての品種を発酵前にブレンドして、一緒に発酵を行います。ブドウ果汁がワインへと変換する過程は、非常に繊細な工程であり、単なる糖分のアルコールへの変化でありません。この過程において、酵?は多くの生化学的側面で働き、最善の方法でワインを形成するからです。
ミケーレ・ロレンツェッティは、発酵の後に異なる品種をブレンドすることは、既に出来上がったワインを混ぜることであり、ワインとして統一感を得るには実践面で限界があると考えています。最も統一感のあるワインを得るためには、最初から全ての品種をブレンドして同時に発酵させることが理想であるということです。発酵後にブレンドをするという試みも行ってみましたが、収穫の段階から異なる品種をブレンドする方法と比べた場合、出来上がったワインは複雑性に欠けるとの治験を得たそうです。
このため、複数品種をブレンドするキュヴェに関しては、ブレンドする全ての品種を同じ日に同時に収穫して、同じ発酵層で一緒にアルコール発酵を行っています。これは、かってブドウの品種が特定されていなかった時代に普通に行われていたField Blend フィールド・ブレンドの手法と同じです。フィールド・ブレンドから生まれるワインには、現代的な計算してブレンドするワインにはない複雑な味わいや香りが備わると言われています。いずれにしてもミケーレ・ロレンツェッティは、ワインの発酵の成否はブドウの品質に完全に依存していると考えています。その意味で、ビオディナミでブドウ栽培をすることが何よりも重要であると考えています。
グラヴネールと言えば・・自称では有りますが、日本で最初にご紹介させていただいたのはnoisy だと思っています。勿論、「ネットで・・」ですけど・・ね。
そもそもはフリウーリの凄い生産者がいる・・と言うのを聞きつけ、色々と無い情報を集めていたところ、
「高いのに酷いシャルドネだ。木っ端を入れたマコンの方がマシだ!」
と、某Pxさんが言っているのを聞き、ブローカーから何とか入手して飲んでみると、滅茶苦茶旨いじゃ無いですか・・!それが、ヨスコ・グラヴネールの「ブレグ」と言うワインだったんですね・・。
で、ま~・・もともとがひねくれていますから、彼のような凄い評論家さんの言うことは話半分に聞くような性格がさらに進んでしまった訳です。
グラヴネールは1995年にそれまでの造りを止め、ビオディナミコに走っています。また、品種も地場品種のみにしましたんで、あの物凄いシャルドネはもう「幻」になってしまいました。noisy もマグナムを数本残していましたが、今はもう有りません。
グラヴネールさん・・あ、ミケーレさんと一緒に写っていますね・・も、そこから自然派の大家になられましたが、今だに模索中・・のようにも感じられます。
ですから・・興味あるでしょう?・・醸造家でもあり、生物学者でも有るミケーレさんが、グラヴネールさんのコンサルをやっているんですから。勿論、グラヴネールさんが1997年から始めたビオの造りに最初から参加している訳ではない・・としてもです。
なので、ものに寄っては非常に少ない数しか入手できなかったんですが、今回は仕入れられたキュヴェを全てテイスティングし、その方向性を見定めさせていただきました。いや・・想像以上に面白かったですよ。
なにせ、グラヴネールは地場品種のみ・・ですよ。それも北部のフリウーリです。なのにミケーレは中部のトスカーナ高地。そしてフランス品種なんですよ。
で、気になる「揮発酸由来のアロマ」ですが・・
「全く無し!」
です。・・面白いでしょう?・・グラヴネールも無いですけどね。
で、マセラシオンのキュヴェは僅かにですが・・色落ちはしています。・・でも、
「ほんの僅かな酸化のニュアンスから湧き出すフルーツ香!」
と言う、嘘みたいなフレーズが、全くの現実となって感じられたんですね。・・面白いでしょう?
栽培・醸造コンサルタントが造るピュアなワイン・・・イタリア北部に多く存在するビオディナミコの造り手のワインと比較することで大きな指標であることが判ります。
意外なほど・・綺麗なんですね~・・しかも価格も非常にリーズナブルです。
ガッタイアシリーズは上級キュヴェ・・と言う理解で良いです。しかもマセラシオンしている方だと思ってください。テッレ・ディ・ジオットは下級キュヴェでデイリー感覚の、さらにピュアに仕上げたシリーズと言う理解で・・今のところは良いと思います。是非とも飲んでいただきたい、興味深いワインです。
■エージェント情報

ミケーレ・ロレンツェッティは醸造家で生物学者です。1971年にローマ近郊のフラスカーティで生まれたミケーレは、ローマの大学で生物学を修めた後、さらに醸造学の学士号を取得しました。
しかし、その間に慣行農法のブドウ栽培ではいかに多くの化学薬品が使われているか、そして土壌が単なる根に栄養分を与えるための人工的媒体にしか見なされていないことに強い衝撃を受けたのです。
やがて、彼は土壌は生態系の一つであり、植物が健康に成長していくためには土壌が健康であれば十分であるという確信を持ち、そして、この考えを実践に移すための方法を探す中で、カルロ・ノロと出会い、ビオディナミを学びました。そして、2004年からビオディナミのブドウ栽培と醸造のコンサルタントとして活動を始め、現在ではグラヴネルやイル・マッキオーネ、ラ・ヴィショラなどイタリア全土の数多くのワイナリーでコンサルタントを行っています。ミケーレのビオディナミの師であるカルロ・ノロは、ローマの南にあるLabico ラビーコで農場を経営し、30年以上前からビオディナミのプレパラシオン(調剤)の販売とビオディナミの講座を開催している、フランスのピエール・マッソンのような、イタリアにおけるビオディナミの重鎮的存在です。
ミケーレ・ロレンツェッティはコンサルタント業とは別に、カルロ・ノロの協力者として、ビオディナミ調剤の生産やビオディナミの基礎講座などにも携わっています。
 ミケーレはコンサルタントという職業の経験的背景を完成するためには実践的な仕事が不可欠と考え、自身でもワイン造りをしたいという想いを持っていました。
ミケーレはコンサルタントという職業の経験的背景を完成するためには実践的な仕事が不可欠と考え、自身でもワイン造りをしたいという想いを持っていました。ある時、仕事でフィレンツェ北部のMugello ムジェッロ地区を訪れた彼は、その地のミクロクリマに強い感銘を受けたのです。ムジェッロは15 世紀にメディチ家がトスカーナ地方修めていた時代から、ワイン造りのために選ばれたテロワールでした。古文書によれば当時は29 ものドメーヌがあり、数多くの果物、そして特にブドウが栽培されていたと記述されています。
1867 年にブルゴーニュ出身の醸造家ヴィットリオ・デリ・アルビジが父から広大な土地を相続します。その土地にはブドウ畑がありましたが、当時はトレッビアーノが栽培されていました。彼はこのトスカーナの高貴なテロワールを表現する個性豊かなワインを造るために、トレッビアーノをピノ・ノワールなどのフランスの高貴品種に植え替えていったのです。しかし、それはフランスの模倣ではなく、高貴品種によってムジェッロのテロワールの個性を表現するための試みで、大きな成功を収めたのです。
しかし、フィロキセラによってブドウ畑は全滅してしまいました。過去のこの貴重な経験を現代に蘇らせるため、ミケーレは2006 年にMugello ムジェッロ地方のVicchio ヴィッキオのコミューンに土地を購入して、自身のワイナリーTerre di Giottoテッレ・ディ・ジオットを設立したのです。
 ムジェッロ地区はフィレンツェの北東約25km、アペニン山脈の麓にある渓谷です。アペニン山脈からの冷たい風の通り道となっているため、トスカーナでも極めて冷涼な気候に恵まれています。加えて、昼夜の寒暖差が大きく風通しが良いため、湿気が畑にたまらないという好条件が備わっています。
ムジェッロ地区はフィレンツェの北東約25km、アペニン山脈の麓にある渓谷です。アペニン山脈からの冷たい風の通り道となっているため、トスカーナでも極めて冷涼な気候に恵まれています。加えて、昼夜の寒暖差が大きく風通しが良いため、湿気が畑にたまらないという好条件が備わっています。また、霧が眼下に立ち込めるほど標高が高いため、霜の被害を受けることもありません。この独特のミクロクリマと、19 世紀にフランス系品種が栽培されていたという歴史から、ロレンツェッティはこの地には冷涼気候の品種が向くと考えました。そこで、Gattaia ガッタイアと呼ばれる標高500~600 メートルの斜面に位置する1.5ha の区画にピノ・ノワール、シュナン・ブラン、ソーヴィニョン・ブラン、リースリングといった品種を2006 年から2007 年にかけて植樹しました。
このうちシュナン・ブランは、2004 年に友人であるマルク・アンジェリの所に滞在した際に、マルクからフェルム・デ・サンソニエールでマッサル・セレクションした苗木、2000 本を譲り受けて植樹したものです。
また、2015 年には同じヴィッキオのコミューンにあるPesciola ペシオラと呼ばれる1.2ha の畑を購入しました。こちらは標高200 メートルの南向きの斜面の区画で、1972 年に植樹されたサンジョヴェーゼ、トレッビアーノ、マルヴァジアといった地場品種が栽培されています。ドメーヌの所有畑ですが、地元の小さなブドウ栽培家3 人と共同で栽培を行っていて、収穫ブドウを4 人で分配するため、ドメーヌの受け取り分は20%のみです。このため、1 つのワインの生産量は多くても1.000 本にしかなりません。どちらの畑もビオディナミで栽培を行っていますが、ペシオラの畑は認証は受けていません。
ミケーレ・ロレンツェッティのビオディナミへのアプローチは、現実的かつ合理的で、理論的・哲学的推測ではなく、直接の経験と科学的研究に焦点を当てています。彼はビオディナミについて以下のように述べています。
「ビオディナミはブドウ栽培家にとって大きなチャンスです。ビオディナミを実践することは、技術や方法を習得することだけでなく、専門的かつ人間的に豊かな感受性を発達させてくれます。ビオディナミは化学物質を除去し、土壌とブドウの健康を強化してくれます。ビオディナミは予防であり介入ではありません。慣行農法においては、植物の成?に有利な土壌中の窒素やリン、カリウムをベースとする肥料を用いることに慣れてしまっています。しかし、ビオロジックやビオディナミにおいては野菜や動物に由来する有機物質に限って使用をしています。有機物質とビオディナミ調剤によってもたらされるメカニズムにより、土中の腐植土が修復され、ブドウ木はより強くより表現力豊かになります。さらに、醸造添加物なして自発的に発酵できるブドウを収穫することが可能になります。その結果、テロワールの強い個性とアイデンティティーを備えた健康で消化しやすい真のナチュラルワインが生まれるのです。私は単なるワインメーカーになることには興味がありません。造り手の背後にある私の役目は、農業の最高のツールであるビオディナミを提供することです。まず何よりも大切なのはブドウです。10 年以上の醸造経験を通して、自発的な発酵だけが確実な結果を与えてくれるということが分かりました。外的な介入のないワインは、純粋にブドウが育ったテロワールと、そのヴィンテージの作柄の結晶であるのです。」
醸造について

ドメーヌでは、収穫したブドウを野生酵?のみで自発的に発酵させ、培養酵?や酵素、その他のいかなる醸造添加物も加えず、温度管理も一切行わず、清澄も濾過も行わない、可能な限り外的介入のない醸造を行っています。マロ発酵もブドウ自身の力で自発的に自然発生的に行われています。白ワインの場合も100%のケースで行われています。SO2はマロ発酵の後、もしくは瓶詰め時にごく少量添加しています。
またドメーヌでは複数の品種のブレンドによるワインを醸造する場合、全ての品種を発酵前にブレンドして、一緒に発酵を行います。ブドウ果汁がワインへと変換する過程は、非常に繊細な工程であり、単なる糖分のアルコールへの変化でありません。この過程において、酵?は多くの生化学的側面で働き、最善の方法でワインを形成するからです。
ミケーレ・ロレンツェッティは、発酵の後に異なる品種をブレンドすることは、既に出来上がったワインを混ぜることであり、ワインとして統一感を得るには実践面で限界があると考えています。最も統一感のあるワインを得るためには、最初から全ての品種をブレンドして同時に発酵させることが理想であるということです。発酵後にブレンドをするという試みも行ってみましたが、収穫の段階から異なる品種をブレンドする方法と比べた場合、出来上がったワインは複雑性に欠けるとの治験を得たそうです。
このため、複数品種をブレンドするキュヴェに関しては、ブレンドする全ての品種を同じ日に同時に収穫して、同じ発酵層で一緒にアルコール発酵を行っています。これは、かってブドウの品種が特定されていなかった時代に普通に行われていたField Blend フィールド・ブレンドの手法と同じです。フィールド・ブレンドから生まれるワインには、現代的な計算してブレンドするワインにはない複雑な味わいや香りが備わると言われています。いずれにしてもミケーレ・ロレンツェッティは、ワインの発酵の成否はブドウの品質に完全に依存していると考えています。その意味で、ビオディナミでブドウ栽培をすることが何よりも重要であると考えています。
●
2022 Pam Bianco I.G.T. Toscana
パム・ビアンコ I.G.T. トスカーナ
【ロレンツェッティの天才ぶりが発揮された・・チープなはずのトスカーナのトレッビアーノで、「滅茶旨」な泡です!!】-----以前のレヴューを掲載しています。
 いや、半端無いです・・このお方・・(^^;;
いや、半端無いです・・このお方・・(^^;;流石、あのヨスコ・グラヴネールも認めた・・エノロゴです。ヨスコ自身でも造れるはずですが、わざわざエノロゴとして招いてビオの造りを指導してもらったのかと思いますが、それだけのことは有ると言うことなのでしょう。
トスカーナのトレッビアーノと言いますと、もはや・・安ワインの代名詞だった訳です。暖かいだけに酸も少ない・・それで、
「瓶内二次発酵の泡を造る」
と言うことが、どれだけ大変かと・・思うんですが、
「激エレガントで凄い酸バランスを持った、見事なペティアン風!」
なクレマン?・・いや、フリッツァンテです。
黄色いフルーツが見事です。この手はもっと・・二次発酵タイプだとしてもキャンディっぽいのが多いです。そのエレガントなバランスをぜひご確認いただきたく・・深いですね~・・。
 でも、どうなんでしょうね・・グラヴネール的では無いんですね。このフリッツィアンテにしても・・色落ちは有りません。
でも、どうなんでしょうね・・グラヴネール的では無いんですね。このフリッツィアンテにしても・・色落ちは有りません。そして色落ちのあったソーヴィニヨンは、やや茶色が入って来ているのに・・めちゃ「照り」が有って美しいんです。そして味わいも見事!・・
「茶が活き活きとしている!」
んですね。
グラヴネールも1995年で通常の造りを止めてしまいまして、新樽も使わない・・ビオに転向しました。そしてこのロレンツェッティも参画したんだと思います。
グラヴネールの初期の白ワインは・・中々に noisy も理解できずにいましたが、ロレンツェッティ自身のビオワインは・・良い部分ばかりが感じられ、ネガティヴな部分が無いんですね・・。
このフリッツィアンテも出来は同様です・・相当素晴らしいです!・・ドライで果実も、そして複雑性も高い・・どうやって造ったのか!・・と全く分かりませんが・・是非驚きのフリッツァンテ、飲んでみてください!・・旨いです!
●
2022 Nostrale Bianco I.G.T.Toscana Terre di Giotto
ノストラル・ビアンコ I.G.T. トスカーナ
【クヴェグリ使用の外交的で美しくナチュラルなビアンコです!・・しかも、めちゃ安いです!】----少な過ぎて飲めませんでした。以前のレヴューを掲載しています。
 クヴェグリ使用の白です。それでいて・・色がこれほどまに自然なゴールド!・・美しいです。
クヴェグリ使用の白です。それでいて・・色がこれほどまに自然なゴールド!・・美しいです。やはり2017年ものとは相当に異なります。2018年ものとの比較で言ってしまえば2017年ものは「普通」に思えてしまいます。
So2 も2020年5月で27m/lですから、普通、So2を添加しなくても30m/l程度は出てしまうことを考えれば、入れていないのとさして変わらないと言えます。
で、それでいて、このハツラツとした色合いですよ。
2017年ものはもう少し硬めに感じられたはずですが、2018年ものは中心をしっかり感じさせたまま、柔らかですし、香りの上りも非常にスピード感のあるものに仕上がっています。
揮発酸は、検出できるかできないか・・と言うレベルですので、判らない方が多いでしょう。So2 を出来るだけ使用しないと言う意思でのクヴェグリ使用で、ここまで少ないのは特記すべきことでしょうし、クヴェグリ使用により相当な複雑なニュアンスを、良いベクトルの向きで得ていると感じます。
とてもナチュラルですし、果実もピュア果実に乾燥させたもの、煮詰めたようなニュアンスが出て来ています。
そうそう・・何しろ、
「クヴェグリ使用で2000円台!」
って・・フランスワインじゃ考えられないでしょう?
手間もコストも相当に掛かるやり方です。でも、それをやった結果は・・
「2017年ものはクヴェグリを使っていない」
訳ですから、2017年ものを飲んだ時のことを思い出していただけますと、モロに比較可能なんですね。
複雑で、より外交的で、より包容力のある、より自然な味わいの白です。
しかも、異なる品種を同日に収穫して醸造しています。なので、「混植」とはまた違った「一体感」のある味わいになっていると思いますが・・そこまで見つけることも、もしかしたら可能かもしれません。
多くの情報を含んだとてもリーズナブルなビオの白です。是非飲んでみましょう!超お勧めします!
以下は以前のレヴューです。
━━━━━
【余りにピュアなビオディナミコのブラン!美しいディテールでアヴァンギャルドさはゼロ!・・・ん~・・やっぱりこうじゃないのは失敗なんじゃない?】
 非常にピュアでナチュラルな、デイリー的白ワインです。トスカーナの比較的高くない高度の畑で造っているようです。
非常にピュアでナチュラルな、デイリー的白ワインです。トスカーナの比較的高くない高度の畑で造っているようです。グラヴネールの深遠さや、ミケーレの上級キュヴェのような深みは有りませんが、
「ビオの白はこうやって造るの・・かな?」
みたいなニュアンスがビシビシ伝わって来ます。
柑橘系の果実が穏やかさ、柔らかさを持って感じられます。和田少し若いにしても適度な膨らみを持った中域が有り、何のバリアも感じさせずにアロマが漂ってきます。それこそが自然でストレスフリーです。
余りに呆気ないほど・・ピュアです。アヴァンギャルドなワインがお好きな方は物足りないに違い無いですが、お酢臭いワインが嫌いなビオファンには持ってこいでしょう。
今回は余りに少なく・・ワイン屋の皆さんも期待している性かとは思いますが、合計数ではそこそこいただけました。色々と飲んでみてください。
●
2022 Sauvignon Gattaia I.G.T. Toscana
ソーヴィニョン・ガッタイア I.G.T.トスカーナ
【どうです!?・・この・・美しいゴールド!・・何と、So2無添加で・・これです!・・滅茶美味しい!!激少ですが、激賞しかないです!圧巻!】-----以前のレヴューを掲載しています。
 多くのイタリアの生産者さんが、
多くのイタリアの生産者さんが、「So2 を使用せずに白ワインをマセレーションして仕上げている」
と思います。
ですが、
「まるで干からびてしまっていて、まさに焙じたお茶」
としか思えないような・・まぁ、確かに長く置いておきますと、
「少しずつ若々しいフレーヴァーも出てくる」
ことも有るんですが、それにしても・・
「それじゃぁ・・そこに意味は余り無いんじゃ?」
と言いたくなってしまいます。
ですが!・・
流石、ビオの先生が造る、このクヴェグリで仕上げたソーヴィニヨンは・・まったく違います。
 まぁ・・この辺りを深く掘っていらっしゃる方向けでは有るんですが、いや、こんなのが出来るんなら・・
まぁ・・この辺りを深く掘っていらっしゃる方向けでは有るんですが、いや、こんなのが出来るんなら・・「クヴェグリ、しかもマセラシオンの白も大歓迎!」
と誰もが思うんじゃないでしょうか。
活き活きとした柑橘果実・・少し熟し気味ですが、レモンまで・・有ります。オレンジの風味さえ・・感じるんですね。
まぁ・・中域もしっかりと在りつつ、勿論余韻も長く、美しいんです。
「・・そんなビオのクヴェグリ、So2無添加のイタリアワイン、有ります?」
飲んでみてください。少ないのを無理やり開けてしまいましたが、
「開けて良かった!」
と思えた素晴らしいソーヴィニヨンでした!・・ビオの白を掘り下げていらっしゃる方向け・・とは書きましたが、
「多分、誰が飲んでもOKを出す出来」
です。お薦めします!
●
2021 Gattaia Bianco I.G.T. Toscana
ガッタイア・ビアンコ I.G.T. トスカーナ
【「面」で上がってくる芳香!濃密さと軽快さの両立。移り変わる表情の豊かさにビオディナミの表現力を感じます・・!】[ oisy wrote ]
 [ oisy wrote ]
[ oisy wrote ]I.G.T.トスカーナと言えばかなり柔軟な規定なため、トスカーナで革新的なワイン作りを可能にしている一因・・・なのかもしれませんが、いやまさかシュナン・ブラン主体、ロワールブレンドのワインがあるとは思いもしませんでした。
マルク・アンジェリからマッサル・セレクションで譲り受けた、シュナン・ブランだから・・・だけではないと思います。
この丸く、白い果実の豊かな香り、「面」で押上げてくる芳香は。
香りにも現れるほどの密度。白い果実に少しだけ黄色が混じるのはトスカーナのシュナン・ブランだからでしょうか。白いスパイスと穏やかなハーブが、ソーヴィニヨンの存在を感じさせます。
時間をかけて飲んでいくと、徐々にバターのように変化していき・・・風格を感じさせてくれます。
特に様々な香りの混じり合い方、上部だけで組み合わさってるのではなく、
「複雑な一つの香り」
として昇華されているのは明らかにミケーレのフィールドブランド的な哲学によるものが大きいと感じます。
オイリーでとろみがありながらも、ピュアで冷涼な酸があり、濃密さと軽快さが両立しています。
シュナン・ブランのミネラルの溜め込み方というのはもしかしたら共通してるのかもしれません。ガラスのような厚い膜を貼ったミネラリティは非常にロワール的だなと感じます。
・・・いやもしかしたらミケーレは土壌の特性を見抜いて品種を選択しているのか・・・土壌特性の把握に自信があるからこそこれだけ大胆な品種選択ができるのかもしれません。
表情が豊かで、繊細に移り変わっていく様はまさにミケーレの言うビオディナミによる表現力を感じさせますし、ミネラリティにも複雑性があるように感じるのは樹齢が上がってきているのかもしれません。
かなり熟成に耐えられるポテンシャルを感じます。そのポテンシャルはこの価格帯を凌駕していると思います。しかし、もし早めに抜栓され、一日で飲みきる場合には(多くがこのパターンだと思いますが)、ぜひデキャンタージュもご検討ください。恐らく瓶のままでは酸素供給量が足りず、変化し切る前に飲み切ってしまう可能性が高いです。
それほど酸素との絡みによって変化していきますし、なかなか底を見せないポテンシャルがあります。
そして全く不安定感のないナチュラルなワインです。きっとクラシックのワインがお好きと言う方にも受け入れていただけるほど、ネガティブさが皆無です。
トスカーナのロワールブレンドと言うオリジナリティですが、「土着のブレンドですよ?」と言われても全く疑問を抱かないほどの完成度でした。めちゃくちゃうまいです。ぜひご検討ください!
[ noisy wrote ]
以下は以前のレビューです。
--------
【是非、ビオ嫌いなワインファンにも挑戦してみて欲しいキュヴェです!滅茶深く優しい味わい!】----少な過ぎて飲めませんでした。以前のレヴューを掲載しています。
 美しい白ワインだと思います。優しいし、滋味深いし、非常にピュアで・・後からナチュラルさをジワジワ感じてくる・・そんなタイプです。
美しい白ワインだと思います。優しいし、滋味深いし、非常にピュアで・・後からナチュラルさをジワジワ感じてくる・・そんなタイプです。マルク・アンジェリもそうですが、まぁ・・滅多に揮発酸が乗ることは無いですよね・・いや、マルクのワインに全く無いとは言いませんけどね。でもミケーレのワインは「ゼロ」もしくは限りなく「ゼロに近い」です。noisyも検出限界です。
マルク・アンジェリから分けてもらったクローンのシュナンを主体にしているようです。確かにマルク・アンジェリっぽい柔らかさなのかもしれませんが、非常に良く熟れたシュナンを想像してしまう性でしょうか、余りロワールの・・特にマルク・アンジェリのシュナンだとは感じませんでした。
でも、トスカーナの風土に有った品種なんじゃないか?・・と思えるような、複雑さと深みを得ているように感じます。植樹が2006年頃だとするなら、トスカーナでもまだ若い樹のうちに入ると思います。(南部のイタリアでは、単純にフランスと樹齢を比較できないですが・・)
ある意味、ほとんどビオを感じさせないビオです・・(^^;; 綺麗でピュアです・・僅かに酸化を感じさせる部分がビオだとは言えるかもしれません。むしろ、アンフォラ仕込みのソーヴィニヨンの方がすでに重量感も得ていて、大きな感じさえします。
しかし・・これ、時間が経ってくると充分に立て構造と重量感が出てくるんですよね。マセラシオンにより僅かな渋みが有り、当初はさして気付かないんですが、どんどん巨大化して来ます。
「ん?・・どういうこと?」
と考えてしまいます。
まぁ、言ってしまえば・・安易では有りますが、
「やっぱりセンスが・・」
と言うことなのかもしれません。
今飲んでも美味しいですが、少し寝かせてみても良いと思います。是非飲んでみてください。お勧めします!
●
2021 Massimo Riesling I.G.T.Toscana
マッシモ・リースリング I.G.T. トスカーナ
【金属とペトロールが織りなす「金」の果実・・!オイリーさと瑞々しさの共存は、激烈ピュアの証と見ました!】[ oisy wrote ]
 [ oisy wrote ]
[ oisy wrote ]ラベルを見たとき、何かの間違いかと思ってしまいました。だって・・・
「I.G.T.トスカーナのリースリング」なんですから・・!
一体どんなワインなんだ?
ちゃんとレビューできるのか?
多少なりとも不安はありました。
まるで「北海道で育ったマンゴー」とか「長野で取れたカツオ」のような違和感です。
ただ口に含めば、
「あ・・・」
と誰しもが気づいてしまうことでしょう。
ミケーレはきっと、「このテロワールにはリースリングを合わせてみたい!」と思ったのかもしれない・・・と。
マッシモのテロワールは・・・非常に鉱物的なんです。
しかもかなり「金属的」。
その金属感がペトロールと出会うことによって、清涼感を伴う複雑で個性的な独自のエレガンスを生み出していると感じます。
おそらくこのワインが持つ果実のタイプは、もともとは「黄色」だったと思うんですよ。
標高が高いとは言えトスカーナなので、冷涼感はありながらも(トスカーナの中では最高レベルに高いです!)、果実のニュアンスはそこまで緯度感が高くないんです。
ですが、その「黄色の果実」が「金属感&ペトロール」と合わせることによって、
「金の果実」
に昇華していきます。
さらに密度高く、しっかりと果実の積層感はありますが、同時に「めちゃくちゃ瑞々しい」ので飲み心地はものすごく良いんです。
オイリーで涙がゆっくりとつたう様子からは、グリセリンの存在も感じ取れますが、なぜここまで瑞々しいのかと考えると、やはり・・・
「激烈にピュア」
であるからという結論に行き着きます。
そして激烈にピュアなワインというのは、どうしても醸造上の不安がつきまといますがマッシモ・・・というかミケーレのワインには、その一抹の不安さえも見つからないんです・・!
そしてこのワインはペアリングの腕を問われます。
まず、トスカーナとリースリングと言うほぼ前例のない組み合わせなので、歴史からはヒントをもらえません。
このワインの味わい的に考えると、トスカーナワインと合わせると考えるよりは、「リースリング」と合わせるという切り口から考えた方がいいと思います。
例えば、スモークしたホタテやサーモンなど、魚介は魚介でもマスキングされ、少し乾いた、生臭さを感じづらいものがいいと思います。oisyはたまたま鯖を合わせてしまったんですが、青魚との相性は・・・避けたほうがいいと思います。
なんにしてもこの金属感がポイントになってきます。なので酸の強いものもあまり合わないかもしれませんね。チキンやチーズなどの白っぽい食材の方が相性が良いと思います。
アスパラのようなえぐみを含む野菜は、もしかしたら掛け算のマリアージュになるかもしれません。
そういった意味では、飲み手の力量を試されるワインかもしれませんが、ワイン自体の品質もめちゃくちゃ良いので、ネガティブな組み合わせにならないことだけ気をつけて、ワインに身を委ねてみるのも良いと思います。
イタリアでここまでのリースリングはおよそ経験したことがありません。心の底から素晴らしいと思いました。ぜひご検討下さいませ。
[ noisy wrote ]
以下は以前のレビューです。
--------
【すみません・・!飲めていません。】 このキュヴェのテイスティングをどうしようかと悩んでいたら・・半年も経過していました。このままだと価格が合わなくなってしまうので、
「その時のレートのまま」
一旦ご案内させていただくことにしました。
何せ3~6本しか無いキュヴェが多く、これを全て開けるとロレンツェッティの入荷分、全て販売してもトントンにならないと言う・・厳しい状況で悩んじゃった訳ですね。
そこへブルゴーニュワインが「どかん」と続けて入って来たので、テイスティングすることもままならなくなってしまった訳です。
しかしながら、例えば「パム」を飲んでも・・とんでもなく美味しいですし、ソーヴィニヨン・ガッタイアもまた、
「・・なんで落ちた茶系の色に照りが有るの?」
「・・落ちた色彩から想像できるのが茶色では無いのは何故?」
と思わせるほどに、ロレンツェッティの天才ぶりを感じさせてくれました。
飲まないとほぼ売れないので・・いずれ飲ませていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
●
2017 Angeli Bianco I.G.T. Toscana
アンジェリ・ビアンコ I.G.T. トスカーナ
【ロレンツェッティ・ワールド全開のスーパー濃密&スーパードライな「マルク・アンジェリ由来のシュナン・ブラン」!「・・こんなの・・飲んだこと無い!!」と驚かれるでしょう!・・ロレンツェッティの頭の中が透けて見えるような気配が!!】
 何でしょう・・・もう、頭の中がバグってしまいそうな、とんでもない「シュナン・ブラン」です。因みにこのワインはロワールで造られた訳では有りませんで・・トスカーナです。
何でしょう・・・もう、頭の中がバグってしまいそうな、とんでもない「シュナン・ブラン」です。因みにこのワインはロワールで造られた訳では有りませんで・・トスカーナです。このシュナン・ブランの樹は・・あの・・シュナン・ブランの天才ファーマー、
「ラ・フェルム・ド・ラ・サンソニエールのマルク・アンジェリの葡萄の樹を分けてもらったもの」
です。友人同士だそうですよ・・。
そもそもロレンツェッティは、
「ビオディナミコの大御所のコンサルタント」
として活動しつつ、この「テッレ・ディ・ジオット」で自身のカンティーナをやっていますが、フランスはロワールのマルク・アンジェリで分けてもらったシュナン・ブランを、
「トスカーナの標高500メートルと言う、かなり高い畑に植えて・・やっとリリースしたワインがこの・・アンジェリ!」
なんですね・・これはもう・・サンソニエールファンなら、とても興味を惹かれるワインに違いありません。
・・・がしかし!・・ちょっと待った・・
マルク・アンジェリの・・あのふんわりとした・・まるで仕上がったばかりの食パン(表現がぶっ飛んでてすみません・・)のようなシュナン・ブランを想像されると、
「とてもじゃないが重なる部分が全く無い!」
 と感じられると思いますので注意が必要です。
と感じられると思いますので注意が必要です。しかしだからこそ、
「このアンジェリを飲むと、同じビオディナミを志しつつ目指す方向性の違いや、本人の頭の中が透けて見えて来るものが有る!」
んじゃないかと・・実際、
「(・・なんじゃこりゃ~~!!)」
と、ナチュールな感性に支配されたバージョンの noisy の脳さえ、バグらせるほどの衝撃でした。
劇的に美しい光を反射する琥珀の色彩はアルコール分14度のシュナン・ブランです。まったく甘く無く、エキセントリックなアロマは柔らかさの中にソリッドなニュアンスを含み、高い芳香を持っています。
当初は穏やかな紅茶とハーブに優しいドライフルーツなニュアンスですが、徐々に温まって来ると・・こりゃぁもう・・化け物級の有機物オン・パレードです。果実はもちろん、フラワリーでも有り、先端が尖っていないスパイス。完全にエキス化された液体感から、優しいがエッジ感がしっかりあるパレットを描きつつ、その空間をのんびりと埋め尽くして来る表情・・エンディングは非常に長くたなびき、その有機物がさらに昇華されたような高貴なニュアンスが高域に伸びて行くイメージです。
なんだろう・・これはワインなんだろうか・・と一瞬思いつつも、・・あ、そうか・・ロッレンツェッティの理想像は・・ここなんだ!・・と理解したような気になりました。
まぁ・・アルコール分は14度ですから、さほどは高く無いんですが、どこか上質なフィーヌやマールが織りなす表情も感じられ、それがまた一般的なワインが発することのできる範囲を大きく超えている・・んだと思うんですね。
そしてこの・・ある意味、ワインとしての経験値を超えた味わいは、超絶にドライで有りながら、しなやかさや優しさ、そして懐の深さを物凄く感じさせるんです。
飲んだことの無い凄い白ワイン・・それでも良いですが、
「マルク・アンジェリからのホダギで造られたシュナン・ブランと言うことで、サンソニエールとの比較した場合の、余りにもかけ離れた感が有りながらの超絶な味わい!」
がまた・・ワインファン、ナチュールワインファンの心をくすぐってくれると感じます。言っちゃうと怒られるかもしれませんが、
「大成功したグラヴナー!」
がイメージ的に近いかも・・!少ないですが・・是非飲んでみてください。お薦めします!
●
2022 Nostrale Rosso I.G.T. Toscana
ノストラル・ロッソ I.G.T. トスカーナ
【2018年ものはついに本領発揮!?ビオの先生ならではの、「ビオワインはこれが正当なスタイル」的教えを美味しくリーズナブルに伝えてくれます!】----少な過ぎて飲めませんでした。以前のレヴューを掲載しています。
 ベーシックなクラスのノストラル・ロッソですが、このノストラル・シリーズが凄く良いです。特にこの2018年ものになって、
ベーシックなクラスのノストラル・ロッソですが、このノストラル・シリーズが凄く良いです。特にこの2018年ものになって、「ビオ系コンサルタント」
としての素顔をさらけ出してくれました。
まぁ、正直なところを言ってしまえば、
「2017年ものは少し綺麗過ぎた?」
と・・。
ビオ系としては勿論、自然派系としても、安全パイ的な仕上がりを目指したのが2017年ものだったと感じます・・この2018年ものを飲めば。
2018年もののノストラル・ロッソは、開放的で充実、エレガントさを多分に感じさせつつ、「ビオ」と言う部分もしっかり感じさせつつ、とても安全で美しいディテールをも持っている・・・ある意味、
「ビオワインの鏡」
的な完成度を持っています。
そこには、「クヴェグリの使用」が大きく影響していると思われます。ですので、ベクトルの向きが外向きになり、開放感あふれる表現になっています。ほんの僅かに揮発酸が動いた形跡を香りの中に見つけることは、きっと可能だと・・思える程度の僅かなアヴァンギャルドレベルに収まっています。ですので、ここを一生懸命に探ったとしても、多くの方は見つけられず、複雑な味わいの中のワンポイントになっているだけです。
果実のニュアンスも実にナチュラル、リアルなもので、ふんわりと感じられるアロマに、きっと心地良さだけを感じさせてくれるでしょう。
美味しいデイリー?・・しかもビオです。その栽培由来のビオと、醸造に使用されるSo2の極端な少なさ・・必要最低限の量のみの添加・・サンズ・ナチュールに近い要素(5月で10mgは残存しているにしても)もしっかり感じさせてくれます。是非飲んでみて下さい。お勧めです!
以下は以前のレヴューです。
━━━━━
【トスカーナの個性を持った滅茶精緻でピュアな赤は、どこかフレンチさえ感じさせる?・・そう、時に煩わしい陽気さを隠しているのかもしれません!】
 こんなサンジョ、飲んだこと無い・・です・・(^^;; 滅茶苦茶繊細です。精緻さもかなり有ります。・・まぁ、サンジョだけじゃないですけど・・でも、トスカーナブレンドですから・・はい・・。
こんなサンジョ、飲んだこと無い・・です・・(^^;; 滅茶苦茶繊細です。精緻さもかなり有ります。・・まぁ、サンジョだけじゃないですけど・・でも、トスカーナブレンドですから・・はい・・。それをミケーレは、
「フィールド・ブレンドにより複雑な味わいや香りが備わる」
と言ってるんですから・・実に面白いです。
フィールド・ブレンドは究極に持って行くと「混植」になるでしょう。そう、マルセル・ダイスや、ユッタ・アンブロジッチのゲミシュターサッツです。北の大地では、混植は避けられない方法でしょう。より寒いですから収穫時期もかなりのズレが生じます。
南のトスカーナでは、そこまで「必須にはならない」と言うことなのかもしれません。
マルセル・ダイスの超複雑性+一体感、アンブロジッチのシームレス感と似たものが、ここに存在するんです。そう、立て構造の深さと言うか、高さ?・・と言うか・・です。
なので、滅茶「スッキリ」しています。なのに複雑性も感じ、滅茶ピュアなんですね。ナチュラル感はむしろ「遅れて気付く」と言って良いかもしれません。
これ、面白いです!・・まぁ、そのまんまクイクイのんで、
「・・あ~・・美味しかった!」
で済ませても良い・・と言うか、それこそが造り手の狙いだと思います。
しかし気付けば、・・気づいてみて気付くこと?は、
「これ、トスカーナ・ブレンドだよね?・・しかもデイリーだし・・」
ビオの終着点はもしかしたら・・この辺に有るんじゃないか・・などと思い始めました。是非飲んでみてください。お勧めです!
●
2021 Gattaia Pino Nero I.G.T. Toscana
ガッタイア・ピノ・ネーロ I.G.T. トスカーナ
【赤く、石灰質のエレガンス!繊細で上質、「旨み」の乗った、まるでブルゴーニュの延長線上のテロワールを感じさせるピノネロ・ ・いや、ピノ・ノワールです!】[ oisy wrote ]
 [ oisy wrote ]
[ oisy wrote ]あんまりこういうレビューはしたくないんですが、過去のノイジーと全く同じ感想を持ってしまいました。それは・・・
「ピノ・ネロではなく、ピノ・ノワールだ・・!」
ということです。
大体のイタリアのピノ・ネロは、果実はより黒く、若干粗野であるが旨味を伴ったもの・・・ものによっては、そこにスパイシーさが加わってきたりもする。そんなイメージでした。
ですがこのガッタイアは香りが「完全にピノ・ノワール」なんです・・・
赤く、石灰質のミネラルと組み合わさったフラワリーなエレガンス。香りに関して言えば、かなりブルゴーニュ的。しかもシャンボールに相当近いものがあると見ています。
味わいは石灰系の赤い果実をベースに、若干黒い果実がジワリ行き渡っており、「旨味の乗り」ががあるので、キャラクターはまた違ってくるんですが、しかし実に繊細でたおやか、エキス的です。
これはシュナンブランのアンジェリやリースリングのマッシモを飲んだ時にも思ったんですが、ミケーレは土壌を見極めて品種を変えてるんじゃないかな・・・と思います。
その土壌がどういった構成で、その品種だったら、最もポテンシャルを開花させられるのか、そういった視点を非常に大事にされているように感じます。だからこそ一見大胆に見える品種選択をできるんじゃないかと。
ワインを飲む限り、その試みは非常に成功していると断言できます。
それほどにどれも品質が素晴らしいし、オールドワールドでの長年の試行錯誤に裏打ちされた土壌と品種の組み合わせのルールさえ守れば、どんな土地でも素晴らしいワインができるという好例を見せつけられているかのようです。
というかこれだけ多様な品種に呼応できるって・・・ムジェッロ地区のテロワールの多彩さには驚かされるばっかりです。
ポテンシャルも素晴らしいです。香りの仕上がりに対して、味わいのまとまりはまだ進行途中といった具合なので、できればあと1 〜2年待ちたいところではあります。
ノイジーが言うように、確かに最終形が想像しきれない部分があります。
おそらくこれは、ブルゴーニュのピノにはない類の「旨味」があり、それがポテンシャルを取りに行った際、普段測りに行く層を覆っている感じになっていて、どうにもそこを超えてミネラルの質とボリュームをキャッチしづらいんですよね・・・
しかし、抜栓から時間をかけて、酸素を含ませていくと、香りだけでなく、味わいも粗野感が取れ、どんどんブルゴーニュ的な美しさが出てきます。
そうなってくると、このワインには確かに村名以上のものがある・・!と感じます。そしてここまではっきり理解できて初めて、「コスパめっちゃいいじゃん・・・」と言えるようになってくるわけです。
トスカーナのピノ・ネーロですが、スタイル的にはブルゴーニュの延長線上のテロワールを感じる素晴らしい「ピノ・ノワール」です!ご検討くださいませ!
[ noisy wrote ]
以下は以前のレビューです。
--------
【ビオも何も忘れてください。イタリアで最上の見事なピノ・ノワールです!】----少な過ぎて飲めませんでした。以前のレヴューを掲載しています。
 素晴らしいピノ・ノワールでした。あえてピノ・ネーロとは言いません。そう言ってしまうと、
素晴らしいピノ・ノワールでした。あえてピノ・ネーロとは言いません。そう言ってしまうと、「・・ちょっと違うか?・・ピノ・ネロじゃ伝わらないかも・・」
と感じました。いや、見事なピノ・ノワールでした。
皆さんは素晴らしいピノ・ノワールを沢山お楽しみですから・・それはピノ・ネロでは無かったはずなんですね。クレジットは「ピノ・ネーロ」ですが、それだとどうしても、
「濃くて力強くてどこか鈍重さの有るワイン」
を想像させてしまうんじゃないか・・と危惧してしまった訳です。
この美しい赤紫の色合いを是非ご覧ください。一瞬、
「あれ?・・フランスワイン?」
と見えてしまうことも有るんじゃないかと・・(^^;;
そうなんですよ。今まで飲まれてきた「ピノ・ネーロ」は忘れてください。そしてついでに「ビオディナミコ」も忘れちゃってください。熱で熟れ切ったフランス南部のピノ・ノワールも、どこかに置いて来てください。敢えて言うなら、フランス南部の極上のピノ・ノワール・・・でしょうか?・・でもそれでもこのワインを正確には言い表せていないと思います。
非常に繊細です。しかし、ブルゴーニュのピノ・ノワールには近い感覚ですが、同じでは有りません。言ってしまえばもっと複雑です。色合い、色彩をもっと豊かにした繊細なピノです。粘土が主体ですが、どこかにサラリとした砂地も感じます。その性でしょうか、黒い果実も実にサラリと感じさせてくれます。
今まで飲んだイタリアンのピノ・ノワールの中ではトップ・クラスです。価格も実にリーズナブルです。ブルゴーニュの村名クラスのポテンシャルは充分に有ります。濃くて重いピノ・ノワール・・・ん~・・ちょっと違うかな~・・と感じてしまうのが常ですが、冷やかさにワンポイント、集中した熱量を受けた果実が有り、それを繊細に表現できていると思います。
また、これはある程度の熟を与えても非常に面白いと言えます。どうなって行くのか・・いや、ブルゴーニュだと想像できるんですけどね。もしくはもっと鈍重なピノ・ネロだと判りやすいですが、ここまでの出来だと・・
「最終形が想像しきれない・・」
と感じてしまいました。
まぁ、あのグラヴネールさんがコンサルタントに迎えるくらいですから・・やはり凄いセンスの方なのでしょう。是非トライしてみてください。新たなピノの世界を覗いてください。お勧めです!
ラルコ(フェドリゴ・ルーカ)
ラルコ(フェドリゴ・ルーカ)
イタリア l'Arco ( Fedrigo Luca) ヴェネト
● 鳴り物入りでラシーヌさんに登場したラルコのご案内です。この造り手さんは、クインタレッリで長年働いてきた方だそうですが、何せ、あの偉大なクインタレッリも、ジュゼッペ翁引退後に売られてしまいました。ル・テロワールさん時代に、かなり販売させていただいており、その頃からカンティーナ売却の噂は流れ、心を痛めていました。その恐れが現実となってしまった訳です。
でも、新しい造り手が生まれました。それがこのラルコです。日本での本格デビューもう少し先になります。noisyも、今回ご紹介のアイテム以外のものを1本飲めただけ・・という状況ですが、
「キレイ系のシミジミ旨みが染みてくるタイプ」
の味わいに心がトキメキました!
■エージェント情報(ラシーヌさんのサイトより)
才能溢れる若干32歳のルーカ・フェドリーゴのドメーヌです。これまで幾度となく予告してきた≪ラルコ≫のワイン。造り手のルーカ・フェドリーゴは、14歳からジュゼッペ・クインタレッリの元で従事してきた人物。そこで学んだことベースに、誠心誠意、彼自身の世界観をラルコのワインに表現しています。

お披露目用として、ラインアップのごく一部が、3月16日に出荷開始 となり、ようやくラシーヌに届きました。ワインが無事に到着した安堵感と、到着したてで落ち着いていないであろうその味わいに少し心配しながら、試飲開 始。しかし、その心配などよそに、ラルコのワインは、毅然とした態度で大きな存在感を放ち、思わず感嘆のため息をもらしてしまうほどの驚きを与えてくれました。このワイナリーの名前は、『ユピテルの拱門』と呼ばれる石でできたアーチに由来する。『ユピテルの拱門』は、ネグラールへ向かう道からよく見える。数年前まで、フェドリーゴ一家はその拱門の近所に住んでいた。『ユピテルの拱門』は、その起源を16~17世紀にまでさかのぼり、サン・ヴィート・ディ・ネグラールにある丘陵に沿ってそびえる7つの拱門のひとつである。ルーカ・フェドリーゴにとってこの拱門は、過去の記憶を呼び起こさせるものであり、その記憶こそ、ルーカがワインの中に表現したいと願うものだ。
ルーカは、ヴァルポリチェッラの高名なワイナリー(クインタレッリ)で何年も働いており、多大な経験を得た。アズィエンダはまだ設立から数年ではあるが、過去を尊重した、積極的かつ礎のしっかりとしたワイナリーである。ヴァルポリチェッラのワインが受け継いできた伝統を、そのままに継承しながら、ヴァルポリチェッラらしいワインを生み出すことに細心の注意を払っている。
ルーカ・フェドリーゴは、ブラジル、アルゼンチンおよびトスカーナでワインをつくるルイーズ・アルベルト・バリケッロとの信頼関係を築き上げ、設立当初からワイナリーをともに運営するにいたった。ふたりは2001年に、2種類の重要なIGTワインを生み出した。それが、ヨーロッパ圏内だけでなく北米や南米でも非常に評価の高い、《ルベオ》と《パリオ》である。この2つのワインには、「アマローネのブドウ」と呼ばれるロンディネッラ、コルヴィーナ、モリナーラとは異なった品種も用い、個性的な品種構成をとる。
でも、新しい造り手が生まれました。それがこのラルコです。日本での本格デビューもう少し先になります。noisyも、今回ご紹介のアイテム以外のものを1本飲めただけ・・という状況ですが、
「キレイ系のシミジミ旨みが染みてくるタイプ」
の味わいに心がトキメキました!
■エージェント情報(ラシーヌさんのサイトより)
才能溢れる若干32歳のルーカ・フェドリーゴのドメーヌです。これまで幾度となく予告してきた≪ラルコ≫のワイン。造り手のルーカ・フェドリーゴは、14歳からジュゼッペ・クインタレッリの元で従事してきた人物。そこで学んだことベースに、誠心誠意、彼自身の世界観をラルコのワインに表現しています。

お披露目用として、ラインアップのごく一部が、3月16日に出荷開始 となり、ようやくラシーヌに届きました。ワインが無事に到着した安堵感と、到着したてで落ち着いていないであろうその味わいに少し心配しながら、試飲開 始。しかし、その心配などよそに、ラルコのワインは、毅然とした態度で大きな存在感を放ち、思わず感嘆のため息をもらしてしまうほどの驚きを与えてくれました。このワイナリーの名前は、『ユピテルの拱門』と呼ばれる石でできたアーチに由来する。『ユピテルの拱門』は、ネグラールへ向かう道からよく見える。数年前まで、フェドリーゴ一家はその拱門の近所に住んでいた。『ユピテルの拱門』は、その起源を16~17世紀にまでさかのぼり、サン・ヴィート・ディ・ネグラールにある丘陵に沿ってそびえる7つの拱門のひとつである。ルーカ・フェドリーゴにとってこの拱門は、過去の記憶を呼び起こさせるものであり、その記憶こそ、ルーカがワインの中に表現したいと願うものだ。
ルーカは、ヴァルポリチェッラの高名なワイナリー(クインタレッリ)で何年も働いており、多大な経験を得た。アズィエンダはまだ設立から数年ではあるが、過去を尊重した、積極的かつ礎のしっかりとしたワイナリーである。ヴァルポリチェッラのワインが受け継いできた伝統を、そのままに継承しながら、ヴァルポリチェッラらしいワインを生み出すことに細心の注意を払っている。
ルーカ・フェドリーゴは、ブラジル、アルゼンチンおよびトスカーナでワインをつくるルイーズ・アルベルト・バリケッロとの信頼関係を築き上げ、設立当初からワイナリーをともに運営するにいたった。ふたりは2001年に、2種類の重要なIGTワインを生み出した。それが、ヨーロッパ圏内だけでなく北米や南米でも非常に評価の高い、《ルベオ》と《パリオ》である。この2つのワインには、「アマローネのブドウ」と呼ばれるロンディネッラ、コルヴィーナ、モリナーラとは異なった品種も用い、個性的な品種構成をとる。
●
2021 Rosso del Veronese
ロッソ・デル・ヴェロネーゼ
【最高の出来!素晴らしいです・・ヴァルポリと変らない出来です!ドライフルーツのような僅かな甘みとブケ!】--以前のレヴューを使用しています。
基本的にヴァルポリチェッラと同じなのかな・・と思います。ヴァルポリチェッラにしなかったヴァルポリチェッラ構成品種に、カベルネとサンジョヴェーゼをアッサンブラージュしているのでしょう。ですので、結構似た感じは有ります。
ですが、よりオレンジピールのような、柑橘系の果皮を乾かせた香りが強めに有ったり、わずかにアマローネを思わせるような「甘い」感じが強く出てきます。より高質なヴァルポリチェッラ・クラシコに対し、取っ付き易さを感じるロッソ・デル・ヴェロネーゼです。これも旨いです!是非飲んでみてください。早めの抜栓が良いようです!
以下は2004 ヴァルポリチェッラ・クラシコ・スペリオーレのコメントです。
━━━━━
【かなり複雑です!しかもバランスが滅茶苦茶良い! 】
前回はあまりに少なく、あっという間の完売でご迷惑をお掛けしました。ラルコの定番であるヴァルポリチェッラ・クラシコ・スペリオーレです。
ようやく飲めたんですが、まあ、これは・・・素晴らしいの一言ですね。ヴァルポリチェッラの御大クインタレッリで働いていたのが良く判ります。このワイン、ワインのポテンシャルを拾える方なら、その能力が高い方ほど美味しいとおっしゃるに違い有りません。
まず、とても緻密に凝縮しています。凝縮しているとは言っても、甘いフレーヴァーが浮いている・・・アメリカン好みのこってり味では全く有りません。滅茶苦茶ドライで、果皮の周りのみの存在が凝縮している・・・という感じです。抜栓仕立てはやや硬めですが、10分もすると妖艶な感じに変化。ボディも膨らみ始め、赤、黒、茶、橙のフルーツや有機物が放出されてきます。余計な修飾物は一切身に付けていないのに、果てには何と、アマローネのような僅かな甘やかさを含んだドライフルーツのニュアンスまで、ハッキリと飛び出してきます。余韻も長く、後口も長く美しいです。
もし、アマローネ的に、豪勢な味わいを楽しみたければ、平底デキャンタに落として翌日、翌々日に楽しむのも、全く問題無いでしょう。そのレベルにおいては、だらしなく落ちてしまってダレダレになることは考えられません。
もしくは、リストランテさんのグラスワインにも面白い存在になってくれると思いますよ。毎日1本、開けてみてください。当日もの、2日目、3日目~7日目みたいな感じでお客様に提供されると・・・、
「えぇ~?同じワインなんですか?」
と、ビックリされると思いますし、喜んでいただけるに違いないです。そのくらいはへっちゃらで持ってしまいます。反対に言えば、開けたてでも充分に美味しいとは言え、ポテンシャルから言ってまだまだこれから・・という証明でも有りますね。
でも、開けたての美味しさは重要です。2005年のこのワインも届いているようですが、2004年に比べるとまだまだ硬すぎるようです。
プライスも極上、味わいも素晴らしいです。是非ともご検討くださいね。久々の、売れる価格帯のヴァルポリチェッラです。お奨めします!
●
2021 Valpolicella Ripasso Classico Superiore
ヴァルポリチェッラ・リパッソ・クラシコ・スペリオーレ
【品切れしておりました「リパッソ」のヴァルポリがヴィンテージ変更で入荷です。非常にポテンシャル高いです!・・が、量的には非常に少ないです!】--以前のレヴューを使用しています。

何と2009年ものよりはリパッソで仕上げました。実にふくよかで複雑性に富み、色んな香りと味わいがします。
リパッソというのは、アマローネを絞った後の搾りかすが残る樽にヴァルポリチェッラを入れ、再度醸造したものを言います。
ですので、アマローネの搾りかすの糖分を加えて発酵したものになりますので、アマローネが持つ豊かなニュアンスが加えられ、大きな構成のワインになるんですね。
アマローネはアパッシメント(陰干しした葡萄)で造られますから、糖分も非常に高くなります。その残糖分が勿体無い・・・ので、下級のヴァルポリチェッラに使用します。それがリパッソしたヴァルポリチェッラです。
様々なドライフルーツのアロマティックな香り、味わいに、濃密さが加わります。普段はドライなラルコのヴァルポリチェッラですが、リパッソにしてからは僅かな甘みさえ感じますので、ロッソ・デル・ヴェロネーゼのパリオにも似たニュアンスです。非常に複雑性が高く旨いです!
思ったよりも黒くなく、美しい赤紫の色合いをしています。しっかりエキスが出ています!
少しだけ高くなりましたが、この豊かな味わいならご納得いただけるでしょう!お奨めします!是非飲んでみてください!
以下は以前のコメントです!
━━━━━
【かなり複雑です!しかもバランスが滅茶苦茶良い! 】
前回はあまりに少なく、あっという間の完売でご迷惑をお掛けしました。ラルコの定番であるヴァルポリチェッラ・クラシコ・スペリオーレです。
ようやく飲めたんですが、まあ、これは・・・素晴らしいの一言ですね。ヴァルポリチェッラの御大クインタレッリで働いていたのが良く判ります。このワイン、ワインのポテンシャルを拾える方なら、その能力が高い方ほど美味しいとおっしゃるに違い有りません。
まず、とても緻密に凝縮しています。凝縮しているとは言っても、甘いフレーヴァーが浮いている・・・アメリカン好みのこってり味では全く有りません。滅茶苦茶ドライで、果皮の周りのみの存在が凝縮している・・・という感じです。抜栓仕立てはやや硬めですが、10分もすると妖艶な感じに変化。ボディも膨らみ始め、赤、黒、茶、橙のフルーツや有機物が放出されてきます。余計な修飾物は一切身に付けていないのに、果てには何と、アマローネのような僅かな甘やかさを含んだドライフルーツのニュアンスまで、ハッキリと飛び出してきます。余韻も長く、後口も長く美しいです。
もし、アマローネ的に、豪勢な味わいを楽しみたければ、平底デキャンタに落として翌日、翌々日に楽しむのも、全く問題無いでしょう。そのレベルにおいては、だらしなく落ちてしまってダレダレになることは考えられません。
もしくは、リストランテさんのグラスワインにも面白い存在になってくれると思いますよ。毎日1本、開けてみてください。当日もの、2日目、3日目~7日目みたいな感じでお客様に提供されると・・・、
「えぇ~?同じワインなんですか?」
と、ビックリされると思いますし、喜んでいただけるに違いないです。そのくらいはへっちゃらで持ってしまいます。反対に言えば、開けたてでも充分に美味しいとは言え、ポテンシャルから言ってまだまだこれから・・という証明でも有りますね。
でも、開けたての美味しさは重要です。2005年のこのワインも届いているようですが、2004年に比べるとまだまだ硬すぎるようです。
プライスも極上、味わいも素晴らしいです。是非ともご検討くださいね。久々の、売れる価格帯のヴァルポリチェッラです。お奨めします!
インドミティ
インドミティ
イタリア Indomiti ヴェネト
[ oisy wrote ]
● 2023年のインドミティのご紹介です。一部上級キュヴェは2021,2022年もございます。
こんな凄い造り手がイタリアの、しかもヴェネトという比較的マイナーな地域にいるのか・・と驚愕しました。最初はセンスのある造り手だな~とくらいに思っていたんです。
ただなにか液体が持つオーラみたいのが違うな・・・とうっすら感じていたところ上級キュヴェを飲んで、その「心にくる」素晴らしさに愕然としました・・
そしてその正体に気付いたんです。それは・・・
フレデリック・コサールの言う「ヴァン・ヴィヴァン」がインドミティのワインにはある・・ということです!
「生きたワインには、魂が揺さぶられるような感動がある」
まさに心にくる、魂を揺さぶられるようなワインです。
巻き戻すように全てのキュヴェをテイスティングし直すと、どのキュヴェも感じたのは「ヴァン・ヴィヴァン」・・・でした! トップの2キュヴェ「ロッソ・セレステ」と「エニグマ」が非常にブルゴーニュ的で、さらにそのスタイルがかなりコサール的だと感じたので、気付いただけのことです。
さらに「エニグマ」の中にはヤン・ドリューの要素も垣間見ることができましたが、その詳細は各コラムにてご覧ください。
インドミティのシモーネ・・・天才だと思います。ぜひご検討くださいませ!
[ noisy wrote ]
以下は以前のレビューです。
--------
● ビックリしました~!・・
「・・誰なんだ・・こんなワインを造れるのは!」
「これが・・イタリアの・・ヴェネトのワインなのか?」
「穏やかで美しいのに、ちゃんと主張も有る・・これで1年目の造り手?!」
どうやら世の中から「一気に」消えたようですよ・・。世界でもそう、日本でもそのようです。でも、noisy としましてはちょっと不満も。
だって、
「こんなに穏やかでエレガントで、イタリアワインらしくない静かな味わいで・・墨絵さえ思わせるようなワイン」
って、世の中のワインの中心に有った訳じゃなく、ただただ noisy はそんなのが好きだから扱っていただけ・・なのに、世の中から一瞬で消えたって・・どういうことなの?・・と言うような、ちょっと嫉妬みたいなものが入った微妙な気持ちが有るんですね・・。
「・・何だかな~・・」
・・続く
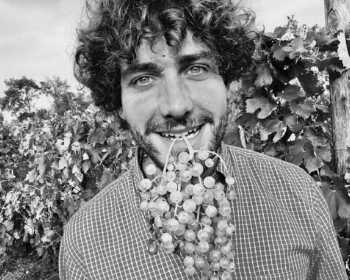
■エージェント情報 インドミティは今年28歳になるシモーネ・アンブロジーニが立ち上げたナチュラルワインのプロジェクト。シモーネは、高校卒業後、丸1年かけて世界を旅行。その後、トレンティーノやアゼルバイジャン、モンタルチーノ、ブルゴーニュ、ヴェネトなどの数々のワイナリーで研鑽。そして、2018年に地元ヴェネトで畑とセラーをレンタルしてナチュラルワイン造りを始めたミレニアル世代の造り手です。
シモーネはテクノロジーや化学を排した可能な限りアーティザナル(職人的)な方法で栽培をしたいと考え、長靴と剪定バサミ、ミニトラックを改造したトラクターだけで、たった一人で、ビオディナミの手法を取り入れたビオロジックでブドウ栽培を始めました。
インドミティのワインはアートワークであり、エチケットにはシモーネの人生の旅の美しい物語が表現されています。エレガントで美しく、生き生きとした活力を備えた彼のワインは、初ヴィンテージながらリリースと同時に欧米で大人気となりあっという間に完売してしまいました。
● 2023年のインドミティのご紹介です。一部上級キュヴェは2021,2022年もございます。
こんな凄い造り手がイタリアの、しかもヴェネトという比較的マイナーな地域にいるのか・・と驚愕しました。最初はセンスのある造り手だな~とくらいに思っていたんです。
ただなにか液体が持つオーラみたいのが違うな・・・とうっすら感じていたところ上級キュヴェを飲んで、その「心にくる」素晴らしさに愕然としました・・
そしてその正体に気付いたんです。それは・・・
フレデリック・コサールの言う「ヴァン・ヴィヴァン」がインドミティのワインにはある・・ということです!
「生きたワインには、魂が揺さぶられるような感動がある」
まさに心にくる、魂を揺さぶられるようなワインです。
巻き戻すように全てのキュヴェをテイスティングし直すと、どのキュヴェも感じたのは「ヴァン・ヴィヴァン」・・・でした! トップの2キュヴェ「ロッソ・セレステ」と「エニグマ」が非常にブルゴーニュ的で、さらにそのスタイルがかなりコサール的だと感じたので、気付いただけのことです。
さらに「エニグマ」の中にはヤン・ドリューの要素も垣間見ることができましたが、その詳細は各コラムにてご覧ください。
インドミティのシモーネ・・・天才だと思います。ぜひご検討くださいませ!
[ noisy wrote ]
以下は以前のレビューです。
--------
● ビックリしました~!・・
「・・誰なんだ・・こんなワインを造れるのは!」
「これが・・イタリアの・・ヴェネトのワインなのか?」
「穏やかで美しいのに、ちゃんと主張も有る・・これで1年目の造り手?!」
どうやら世の中から「一気に」消えたようですよ・・。世界でもそう、日本でもそのようです。でも、noisy としましてはちょっと不満も。
だって、
「こんなに穏やかでエレガントで、イタリアワインらしくない静かな味わいで・・墨絵さえ思わせるようなワイン」
って、世の中のワインの中心に有った訳じゃなく、ただただ noisy はそんなのが好きだから扱っていただけ・・なのに、世の中から一瞬で消えたって・・どういうことなの?・・と言うような、ちょっと嫉妬みたいなものが入った微妙な気持ちが有るんですね・・。
「・・何だかな~・・」
・・続く
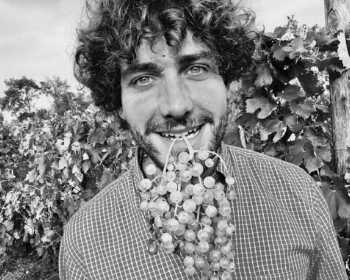
■エージェント情報 インドミティは今年28歳になるシモーネ・アンブロジーニが立ち上げたナチュラルワインのプロジェクト。シモーネは、高校卒業後、丸1年かけて世界を旅行。その後、トレンティーノやアゼルバイジャン、モンタルチーノ、ブルゴーニュ、ヴェネトなどの数々のワイナリーで研鑽。そして、2018年に地元ヴェネトで畑とセラーをレンタルしてナチュラルワイン造りを始めたミレニアル世代の造り手です。
シモーネはテクノロジーや化学を排した可能な限りアーティザナル(職人的)な方法で栽培をしたいと考え、長靴と剪定バサミ、ミニトラックを改造したトラクターだけで、たった一人で、ビオディナミの手法を取り入れたビオロジックでブドウ栽培を始めました。
インドミティのワインはアートワークであり、エチケットにはシモーネの人生の旅の美しい物語が表現されています。エレガントで美しく、生き生きとした活力を備えた彼のワインは、初ヴィンテージながらリリースと同時に欧米で大人気となりあっという間に完売してしまいました。
●
2023 Ramingo Bianco I.G.T.Veneto
ラミンゴ・ビアンコ I.G.T.ヴェネト
【わずか11.5度のAlc度数なのに・・ミネラリティと果皮の強烈な旨味が充実した、身体への負担が激少のピュアワインです!】[ oisy wrote ]
 [ oisy wrote ]
[ oisy wrote ]インドミティのワインは表情が豊かです・・・
テイスティングで要素を拾いに行こうとするとあれもこれもと出て来るような。この価格帯であればもう少し単調であってもおかしくないと思うんですが。
例えば「煙」というひとつの要素であったとしても、単調ではないんです。いくつかの「煙」が絡み合ったかのような、あるいは「煙」と「果実」の間に境目がなく、それによって「煙」と「果実」の両方の要素をもった「第3の香り」が生成されているような感覚です。
この複雑さを可能にしているひとつの重要な要素は・・・SO2の少なさかと思います。SO2によって閉じ込められているような感覚が全くなく、このワインも残存SO2は僅か4.8mg/L。使用量が少ないな、と感じる自然派の造り手でも20〜30mg/Lだったりしますから、その驚異的な少なさを数字でも実感できるかと思います。
また、SO2が少ないと、コアの緩いワインになりがちなんですが、インドミティのワインはしっかりとコアを感じられるんですよね。ミネラルの輪郭がしっかりしていて、焦点がちゃんと定まっているような感覚です。もうその時点でセンスが溢れ出ちゃっているよね・・・と感じます。
香りは煙、石を含む、スモーキーさとシャープな柑橘。フルーツの要素は超えた、「風格」を感じさせます。まだ若干還元的ではありますので、最低でもGW明け、できれば夏くらいにはかなり仕上がってくると思います。
味わいはオイリーでつるりとしたテカリのある液体、ミネラリティが表出されているんだと思います。そこに果皮接触由来の強烈な旨味も乗ってきているため、かなり充実感があります。残糖はほぼ感じられないほどにドライに発酵しきっていますが、アルコール度数は11.5・・!
これだけの充実感でこの低アルコール度数というのは、いかに液体が充実しているかを物語っていますね・・!ドライなのに「力み」がなく、度数に頼らないピュアな液体は、体感として身体へのダメージを全く感じません。
いや〜うまいです。しっかり実感させてくる旨さがあります。イタリアの自然派の良さを詰め込んだかのようなワインですね。あ、ちなみにめちゃ安定していてクリーンです。SO2含有量はかなり低いので、温度管理にはご注意くださいませ!
[ noisy wrote ]
以下は以前のレビューです。
--------
【こんなワインを1年目で造れるって・・もしかして・・天才?・・有り得ないようなエレガンス表現の本質に出会います!】---すみません、少なくて飲めませんでした。

なので、このインドミティについても初めて日本に入って来た訳ですから、
「飲んで確かめてから」
と思っていたんです。インポーターさんも何故かサンプルをくれる・・と言うので・・有難いことです。
で、サンプルが到着はしたんですが、その翌日に電話が有り、
「すみません・・サンプルは送らせていただいたんですが、品物がもう無い・・いや、1ケースずつは取ってありますんで・・」
「(・・はぁ?・・)」
なので、テイスティングアイテムに溢れてしまっていたので、そのまま放置せざるを得ない状況になってしまいました。
ところが2週間後位にお客様から「インドミティは無いか?」とお問い合わせが有り、
「・・ん~・・インドミティ?・・聞いたことはあるが・・何だっけ?」
と。
それでようやくテイスティングを始める気になって飲んでみた・・のが実情です。でも結果、1ケースずつでは無くなってしまい、結局数本ずつにまで減らされることになってしまいました。
ところがですね・・飲んでみて、ま~・・驚きました!・・マジでこんなワインを1年目の新人さんが造れるのかと!
いや~・・物凄い「センス」の持ち主であることは間違いないし、しかも、実際に3アイテムをきっちり造り分けてもいて、それぞれに個性豊かながらも、確実に「ナチュール」で有り、完全に「健全」であり、心を揺り動かされるような魅力に溢れたワインだったんです。

薄い?・・いや~・・全然!
実にちゃんとした、むっちりなボリューム感ですが、しつこさは無いです。ふくよかで柔らかで、でもきっちり芯を感じる味わいです。
2枚目の写真はラミンゴ白。こちらは非常にドライです。そして高貴なアロマが漂う・・ちょっと高級品の感覚すらして来ます。煙、石、おだやかな果実。そのすべてが高貴に感じられてしまう。ボディもアルガに比べるとややスレンダーでタイトながら、全く異なるタイプで実に旨い!・・アルコール分は何と・・12度ですよ。エレガントに感じるのも当然では有りますが、普通だと「物足りない」と言うイメージにしか、ならない危険性も生まれてしまうかもです。
3枚目の写真はロタイ・ロッソです。最初に言っておきましょう・・。アルコール度は12度です。イタリアンワインですよ・・これ。ヴェネトのワインです。ドイツや、ましてやブルゴーニュのピノ・ノワールでも有りませんよ。この淡~い色合いから、驚くべきエキスの旨味、そこから発っせられるアロマは、丸みと穏やかさたっぷりな、ブルゴーニュ・ピノ・ノワール的なエレガンス。味わいのイメージも全くそのものです!

敢えてもう、品種がどうこうは触れませんが、まるで穏やか、シミジミ美味しいピノ・ノワールの精を身体に取り込んでいるかのような錯覚に陥ってしまいます。素晴らしい・・です!
こんなに穏やかな、エキスそのもののワインをイタリアで造れるって・・どういうこと?なのか、まだ良く理解できていません。
もしブラインドで出されたら、イタリアは真っ先に消してしまいます。
穏やかでエキスたっぷりで、芯がちゃんと有って、So2なんて存在に頭が動いて行かないようなナチュラルな味わい・・どうみたってフレンチだろうと思ってしまいます。
それが経験則に寄る思い込みなんだと。良いワインはこのようにもなるんだと・・言っているかのようでした。
それにこんなワインが、
「世の中から一瞬で消えた」
ことが、ある意味・・嬉しくも感じています。いつものペースでのんびりしていた noisy がいけない訳でして、本当に素晴らしいワインはさっさと押さえるに限る訳です。
今回は少量ですので、申し訳ありませんがお一人様1本限りで、次回の入荷・・おそらく2019年ものになるかと思いますが、お楽しみにされてください。
いや~・・穏やかだけれど真実を手元に感じられるもの凄いワインでした!
●
2023 Osai Rosato I.G.T.Veneto
オサイ・ロザート I.G.T.ヴェネト
【ミネラリティが滲み出るツヤテカな液体・・!徐々に増幅するあまやかさの本格派ロゼです!!】[ oisy wrote ]
 [ oisy wrote ]
[ oisy wrote ]輝きが普通のロゼワインじゃないな・・・と思いテイスティングしてみると「やっぱり」でした。インドミティのワインってそんなのばっかり・・・
赤に近いロゼ色の液体の、「内から照り返す」ような輝き方は多分ミネラルの含有量とか、質とかを表現しているんだろうな・・と最近は思います。
テカテカとした輝きは見た目だけでなく、味わいにも表現されており、赤い果実を薄いガラスでコーティングしたような、ツルっとした液体です。少しオイリーでもあります。
ほぼ完全にドライな味スジの中に、エキスの積層による「あまやかさ」が産まれてきます。その赤果実のあまやかさは、味わいから徐々に香りへと「緩やかに」出現してきます。
行き渡り、輝きを放つミネラリティは味わいの隙間を埋め尽くし、液体の充実感を底上げしますね・・・
抜栓してから時間が経過すると、香りのあまやかさは「増幅」していきます。変化の仕方がポテンシャルワインのそれです。
これだけのミネラリティならば、熟成によるほぐれとともに、違った表情を見せるはず・・・!と思います。恐らくもっとエレガントに・・・華やかに、あまやかに・・・
残存15mg/Lという超低SO2でありながら、完全にノーマルワインと遜色ない安定感にはセンスしか感じ得ません。なぜSO2がこれほど少なくて、集中感のある、コアな味わいを表現できるのだろう・・・この点においてはブルゴーニュの生産者を上回っていると思います。
そして造りのセンスもさることながら、畑の選球眼も素晴らしいのかな・・・と。やはりミネラリティの素性は畑によって決まってしまうところが大きいですから・・・
最近自然派のロゼワインが秘かなマイブームになっていますが、その中でもトップクラスのクオリティです! うまいです。ご検討くださいませ!
[ noisy wrote ]
以下は以前のレビューです。
--------
【残留So2濃度が2mgって・・マジですか?・・ロタイ・ロッソを白ワインに仕上げました・・と言うような感覚!・・そのセンスが素晴らしい!】
 出来るんですね~~・・それって相当なマジックに近いと思うんですが・・いや、
出来るんですね~~・・それって相当なマジックに近いと思うんですが・・いや、「瓶詰時だけに少量So2を使う」
って、言うのは簡単ですが、出来るのかなぁ・・って出来てるんですよねぇ・・。
この鮮やかなパッションを感じさせるピンクに、一点の曇りも陰りも無いのが凄いですし、瓶詰時だけに少量So2を使う・・その結果、
「1年後の残留So2値が2mg!」
って・・そんなの聞いたことが無いレベルですよ。
普通は40mgでも少ないですからね・・80~100mgほどが普通じゃないでしょうか。それ以上になって来ますとちょっと多いですし、その倍ほどになってしまうと倉庫で足止めを食うことになってしまいます。
そんな数値ですから、
「とてつもなく美しく伸びやかなアロマ!」
なんですね。
そして、ミネラリティ由来の硬質でスレンダーなボディをしていて、テッカテカにコートされた新車のような輝きさえ感じます。
酸のボリューム感も通常のロゼワインには無い3D感覚。どことなく感じる黒葡萄の果皮のニュアンスと、その酸がバッチリ合っていて、滑らかでも有り、フレッシュさも感じるという微妙な表現をしようとしているように感じます。
 残糖分もほぼ無い・・滅茶ドライな味筋でありながら、薄辛さを感じさせないライン。むしろ太ささえ感じさせますが、硬質なクリスタル、石英のニュアンスがボディをコートしていますから・・やはりスレンダーなんですね。
残糖分もほぼ無い・・滅茶ドライな味筋でありながら、薄辛さを感じさせないライン。むしろ太ささえ感じさせますが、硬質なクリスタル、石英のニュアンスがボディをコートしていますから・・やはりスレンダーなんですね。これ、少し熟成させても滅茶面白いはずです。サンソニエールのロゼとはちょっと真逆の感覚なのに、似たもの同士のようにも感じます。
「おぬし、何者!?」
と思ってしまうのは・・前回も同様でした。美味しいです。日本のワインでは絶対に実現が無理筋な出来だと思います。素晴らしい!お勧めします。飲んでみてください。
以下は以前のレヴューです。
-----
【これほどまでにしっかり充実した味わいのロゼは久しぶりでした!ピュア感は味わいにバッチリと、ナチュール感はノーズで優しく感じられます!】
 実に美しい「赤」を見せつけてくる「ロゼ」です・・。黒葡萄を少し漬け込んで色合いを抽出してから圧搾、醸造したキュヴェです。赤ワインと白ワインをブレンドしたものとは異なります。
実に美しい「赤」を見せつけてくる「ロゼ」です・・。黒葡萄を少し漬け込んで色合いを抽出してから圧搾、醸造したキュヴェです。赤ワインと白ワインをブレンドしたものとは異なります。何ともエレガントな味わいですが、思いの外充実しています。線が細そうに思えるかもしれないんですが・・結構に太くなってくる感じです。でも決して、
「タンニンの存在が・・」
「抽出の強さが・・」
と言うような、軽妙さに対してのネガティヴな印象を強くするものでは有りません。
そしてやはり・・このインドミティならでは、と言うことになろうかと思いますが、
「So2を使用しないで醸造する」
ことが、このワインの全てを物語っている・・と言うか、インドミティの全てがそこに在る・・とも思います。まぁ、澱と一緒にマロラクティックを温度調整しないで自然に・・などと言うアプローチも、
「軽やかなのに充実した香りと味わい」
に寄与しているのも間違いないですが・・。
 アルコール分は12度ほどなので、決して強くは無いです。なので、ボディ感はむしろ乏しいはず・・なのに、最終的にはしっかりと大きさを感じさせてくれる・・エレガントなロゼ・・と言う不思議な味わいを持っています。
アルコール分は12度ほどなので、決して強くは無いです。なので、ボディ感はむしろ乏しいはず・・なのに、最終的にはしっかりと大きさを感じさせてくれる・・エレガントなロゼ・・と言う不思議な味わいを持っています。フリッツァンテの項でも書かせていただきましたが、どこかピエール・ボージェを彷彿させるように感じます。まぁ、もう少し放置主義は取らない、正統派なスタイルだとしても・・です。
色落ちはしますが、赤なので・・ちょっとくすんでくる感じで無くなってしまうと思います。
「発酵が・・終わらない・・」
などとシモーネが言い出さない方が良いかな・・。その辺は何とも言い難いですが、
「発酵が進まず10年も放っておいたキュヴェをリリース」
と言うのは、反対に怖いもの見たさで興味は沸いてしまいますよね。まぁ、ナチュラルワイン大好きな方限定かもしれませんが、もしラシーヌさんがおっしゃっていることが真実であれば、
「あのシルヴァン・パタイユの2019年もまだ発酵が終わらない」
と・・昨年暮れには言っておりましたので、noisy としましては・・
「・・それって・・ワインなの?」
と・・。色々と有ります。是非ご検討くださいませ。
●
2023 Lottai Rosso I.G.T.Veneto
ロタイ・ロッソ I.G.T.ヴェネト
【気づいてたら「酸」だけでレビューを書いていました・・が、それほどに多彩な表情の「酸」を持つワインです・・!】[ oisy wrote ]
 [ oisy wrote ]
[ oisy wrote ]シモーネのバランス感覚は脅威的である・・!と感じます。SO2の低さからは考えられないほどに安定しているからです。
このロタイ・ロッソも、その低〜いSO2の大きな恩恵を受けているワインのひとつです。
ラズベリーや木苺のような、小さくシャープな赤果実に、スレンダーなボディ感。そこから穏やかにエレガンスの立ち上がりも感じられます。
ほぼ完全にドライなエキス、このワインの味わいの大部分を締めるのは「酸」です。
マロをしていないか、かなり控えめです。なので、まろやかな乳酸はほぼ感じず、「シャープでハリのあるリンゴ酸」が主です。そのことからもロタイの元々の果実が持つ酸を大事にしたい意図が感じられます。
というのもこのロタイの酸、ひじょ〜に「健康的」で「活き活き」としているんですよね。これは素の果実が健康的であるということをダイレクトに感じれるレベルです。
SO2の少なさにより「酸の輪郭」がよりクリアーにはっきりとしています。酸も色々な酸がありますが、それら一つ一つが元気で、ハツラツとしていて、絡み合い、「表情が豊か」。単調さがありません。
酸自体が湿り気を帯びており、伸びやかで、艶やか。これはSO2により押さえつけられたワインにはない、「酸の表情」です。
そして、酸素と触れ合わせているうちに「酸のあまやかさ」がゆるゆると出てくるんですね。そうなるともうロタイの虜です。(後日他のレビューを書いているときに、この酸が持つ魅力の正体に気付きました。詳しくは「ロッソ・セレステ」のレビューにて。)
酸との触れ合いの隙間から、ミネラリティも見えるようになってきます。透明感があり、クリアー、酸に隠れるようにして見えずらかったですが行き渡りを感じ取れます。まあそれは輝きを見ればわかるんですけどね。これだけ冷ややかでシャープなのに粘性も高いですからポテンシャルもあるなーという感じます。
現状若干還元的です。今飲むなら前日抜栓でもいいと思います。還元感もそこまでではないので、初夏の頃には取れてきているはずです。
こういう酸の綺麗なワインはやはり夏に飲みたいですねー!こんな綺麗な酸が沁み渡ったら、最高に身体が喜んじゃいます。
既に真夏日を迎えている異常気象の今、これからの季節、身体を労るのはこのようなワインだと思います。ご検討くださいませ!
[ noisy wrote ]
以下は以前のレビューです。
--------
【一般的なヴェネトのワインとは・・ちょっと思えない、ブルゴーニュワイン的エレガンスと味わいに近い美しいエキスのピュア&ナチュラルな・・見事過ぎる味わいです!】
 いや~・・凄いですね~・・やはり天才なんでしょうか。イタリアでこんなワインを造れるって、相当どこかおかしくないと無理だと思ってしまいます・・いや・・すみません、貶しているんじゃなくて、めっちゃ褒めているんです。これなら・・
いや~・・凄いですね~・・やはり天才なんでしょうか。イタリアでこんなワインを造れるって、相当どこかおかしくないと無理だと思ってしまいます・・いや・・すみません、貶しているんじゃなくて、めっちゃ褒めているんです。これなら・・「世界中で人気で余り入って来ないから1ケースしかあげられないんですよ・・すみません・・」
と言うインポーターさんのK君の言葉も納得です。相当旨いです!
ほぼほぼ・・ブルゴーニュ・ピノ・ノワールでしょうか。ブルゴーニュほどはマロがキツク無いのと、フリウラーノ・ロッソと言うことでほんの僅かに伸びやかな緑のニュアンスが高周波に感じる部分・・がディテールとして感じられるかもしれません。
ですので、一般のヴェネトのワインのようなアパッシメントのニュアンスは完全に無いですし、中域の膨らみに頼った感のあるヴェネトのロッソの「詰まり感覚」も無し・・。当然のように滅茶ドライで甘みも無しですが、エキス感はバッチリ・・そして、伸びる伸びる・・どんどん上昇して行きます。
この人、絶対ブルゴーニュ好きだろう!?・・なんて思ってしまいますよ。そうじゃ無かったらこんなデザイン、するもんかな?・・とさえ思ってしまいました。
 美しく赤い苺のニュアンス、そして摘んだばかりの細やかな毛の生えた苺のフレッシュさをどこか残しながらの、ブルゴーニュ的なベリーと赤さが多めのチェリー。
美しく赤い苺のニュアンス、そして摘んだばかりの細やかな毛の生えた苺のフレッシュさをどこか残しながらの、ブルゴーニュ的なベリーと赤さが多めのチェリー。中域はヴェネトのワインとしますとむしろスレンダーです。でも普通のワインだとすると・・普通?・・徐々に膨らみますが、それでもそのスレンダーな姿を壊すほどでは有りません。
伸びやかですから・・香りの上がりも凄く良いです。そして何故か・・
「So2的な感覚がほぼ無い!」
ですから、身体への進入角度が優しいです・・。だから酔い覚めも軽いし凄く楽です。
しかも、
「余り食とのマリアージュを考えなくても大丈夫なほどのナチュール!」
なのに、
「揮発酸的サワー感も皆無に近い!」
んですね・・。ナチュールさを感じる割には美しくてとてもピュアです。
これは飲んだら惚れちゃうでしょうね・・素晴らしい!・・飲んでみてください。安くは無いが全く高く無い!・・そう思っていただけるでしょう。超お勧めです!
以下は以前のレヴューです。
-----
【こんなワインを1年目で造れるって・・もしかして・・天才?・・有り得ないようなエレガンス表現の本質に出会います!】--すみません、飲めていません。少量です。

なので、このインドミティについても初めて日本に入って来た訳ですから、
「飲んで確かめてから」
と思っていたんです。インポーターさんも何故かサンプルをくれる・・と言うので・・有難いことです。
で、サンプルが到着はしたんですが、その翌日に電話が有り、
「すみません・・サンプルは送らせていただいたんですが、品物がもう無い・・いや、1ケースずつは取ってありますんで・・」
「(・・はぁ?・・)」
なので、テイスティングアイテムに溢れてしまっていたので、そのまま放置せざるを得ない状況になってしまいました。
ところが2週間後位にお客様から「インドミティは無いか?」とお問い合わせが有り、
「・・ん~・・インドミティ?・・聞いたことはあるが・・何だっけ?」
と。
それでようやくテイスティングを始める気になって飲んでみた・・のが実情です。でも結果、1ケースずつでは無くなってしまい、結局数本ずつにまで減らされることになってしまいました。
ところがですね・・飲んでみて、ま~・・驚きました!・・マジでこんなワインを1年目の新人さんが造れるのかと!
いや~・・物凄い「センス」の持ち主であることは間違いないし、しかも、実際に3アイテムをきっちり造り分けてもいて、それぞれに個性豊かながらも、確実に「ナチュール」で有り、完全に「健全」であり、心を揺り動かされるような魅力に溢れたワインだったんです。

薄い?・・いや~・・全然!
実にちゃんとした、むっちりなボリューム感ですが、しつこさは無いです。ふくよかで柔らかで、でもきっちり芯を感じる味わいです。
2枚目の写真はラミンゴ白。こちらは非常にドライです。そして高貴なアロマが漂う・・ちょっと高級品の感覚すらして来ます。煙、石、おだやかな果実。そのすべてが高貴に感じられてしまう。ボディもアルガに比べるとややスレンダーでタイトながら、全く異なるタイプで実に旨い!・・アルコール分は何と・・12度ですよ。エレガントに感じるのも当然では有りますが、普通だと「物足りない」と言うイメージにしか、ならない危険性も生まれてしまうかもです。
3枚目の写真はロタイ・ロッソです。最初に言っておきましょう・・。アルコール度は12度です。イタリアンワインですよ・・これ。ヴェネトのワインです。ドイツや、ましてやブルゴーニュのピノ・ノワールでも有りませんよ。この淡~い色合いから、驚くべきエキスの旨味、そこから発っせられるアロマは、丸みと穏やかさたっぷりな、ブルゴーニュ・ピノ・ノワール的なエレガンス。味わいのイメージも全くそのものです!

敢えてもう、品種がどうこうは触れませんが、まるで穏やか、シミジミ美味しいピノ・ノワールの精を身体に取り込んでいるかのような錯覚に陥ってしまいます。素晴らしい・・です!
こんなに穏やかな、エキスそのもののワインをイタリアで造れるって・・どういうこと?なのか、まだ良く理解できていません。
もしブラインドで出されたら、イタリアは真っ先に消してしまいます。
穏やかでエキスたっぷりで、芯がちゃんと有って、So2なんて存在に頭が動いて行かないようなナチュラルな味わい・・どうみたってフレンチだろうと思ってしまいます。
それが経験則に寄る思い込みなんだと。良いワインはこのようにもなるんだと・・言っているかのようでした。
それにこんなワインが、
「世の中から一瞬で消えた」
ことが、ある意味・・嬉しくも感じています。いつものペースでのんびりしていた noisy がいけない訳でして、本当に素晴らしいワインはさっさと押さえるに限る訳です。
今回は少量ですので、申し訳ありませんがお一人様1本限りで、次回の入荷・・おそらく2019年ものになるかと思いますが、お楽しみにされてください。
いや~・・穏やかだけれど真実を手元に感じられるもの凄いワインでした!
グアポス・ワイン・プロジェクト
グアポス・ワイン・プロジェクト
ポルトガル Guapos Wine Project ヴィーニョ・ヴェルデ
● ポルトガルのヴィーニョ・ヴェルデから、
「デイリーには持って来い!・・のプライス・・ながら、たっぷりなポテンシャルを感じられるワイン!」
を見つけましたのでご案内させていただきます。
インポーターさんのオルヴォーさんも、
「こういうのが欲しかった!」
と喜んでいた・・んですが、急に連絡が取れなくなり、何と・・
「・・倒産した・・」
と電話があったようです。・・厳しい時代ですね・・でも在庫分は普通に販売できますのでご安心を。とにかくリーズナブルで美味しい白です。ご検討くださいませ。
 Guapos Wine Project(グアポス・ワイン・プロジェクト)はワインメーカーのBruno Valente(ブルノ・ヴァレンテ)とDaniel Costa(ダニエル・コスタ)の二人が立ち上げたワインのブランドです。ロゴマークに書かれた[1977]は二人の誕生年です。
Guapos Wine Project(グアポス・ワイン・プロジェクト)はワインメーカーのBruno Valente(ブルノ・ヴァレンテ)とDaniel Costa(ダニエル・コスタ)の二人が立ち上げたワインのブランドです。ロゴマークに書かれた[1977]は二人の誕生年です。
二人とも15年以上にわたりポルトガルでワイン造りに従事してきました。そんな二人が高品質でユニークなワインを造る為、2016年にこの新しいブランドを設立しました。
ポルトガル北部のヴィーニョ・ヴェルデ地方に本拠地を構え、地域・気候・ブドウ品種の個性を尊重したワイン造りを進めていきます。自社で畑は所有していませんが、長年の経験と人脈により優良な畑の所有者と契約し、畑の管理、ブドウ栽培を一緒に行う事で良質なブドウを手に入れる事が出来るのです。
 長い歴史を持つポルトガルワインは、戦争、紛争、宗教など、様々な要因で独自のワイン文化が形成されています。
長い歴史を持つポルトガルワインは、戦争、紛争、宗教など、様々な要因で独自のワイン文化が形成されています。
その為、現在でも250品種を超えるワイン用のブドウ品種が認められています。
1986年のEC加盟をきっかけにワイン法が整備され、設備投資、新しい技術の導入も進みました。そして、2000年代になり、それまでとは異なるビジョンを持った若いワインメーカーが増えてきました。ポルトガル独自の多様性を維持しながらも、以前とは違う個性を持つポルトガルワインの生産が増えています。この「グアポス・ワイン・プロジェクト」のブルノとダニエルも新しい世代のワインメーカーになります。
「デイリーには持って来い!・・のプライス・・ながら、たっぷりなポテンシャルを感じられるワイン!」
を見つけましたのでご案内させていただきます。
インポーターさんのオルヴォーさんも、
「こういうのが欲しかった!」
と喜んでいた・・んですが、急に連絡が取れなくなり、何と・・
「・・倒産した・・」
と電話があったようです。・・厳しい時代ですね・・でも在庫分は普通に販売できますのでご安心を。とにかくリーズナブルで美味しい白です。ご検討くださいませ。
 Guapos Wine Project(グアポス・ワイン・プロジェクト)はワインメーカーのBruno Valente(ブルノ・ヴァレンテ)とDaniel Costa(ダニエル・コスタ)の二人が立ち上げたワインのブランドです。ロゴマークに書かれた[1977]は二人の誕生年です。
Guapos Wine Project(グアポス・ワイン・プロジェクト)はワインメーカーのBruno Valente(ブルノ・ヴァレンテ)とDaniel Costa(ダニエル・コスタ)の二人が立ち上げたワインのブランドです。ロゴマークに書かれた[1977]は二人の誕生年です。二人とも15年以上にわたりポルトガルでワイン造りに従事してきました。そんな二人が高品質でユニークなワインを造る為、2016年にこの新しいブランドを設立しました。
ポルトガル北部のヴィーニョ・ヴェルデ地方に本拠地を構え、地域・気候・ブドウ品種の個性を尊重したワイン造りを進めていきます。自社で畑は所有していませんが、長年の経験と人脈により優良な畑の所有者と契約し、畑の管理、ブドウ栽培を一緒に行う事で良質なブドウを手に入れる事が出来るのです。
 長い歴史を持つポルトガルワインは、戦争、紛争、宗教など、様々な要因で独自のワイン文化が形成されています。
長い歴史を持つポルトガルワインは、戦争、紛争、宗教など、様々な要因で独自のワイン文化が形成されています。その為、現在でも250品種を超えるワイン用のブドウ品種が認められています。
1986年のEC加盟をきっかけにワイン法が整備され、設備投資、新しい技術の導入も進みました。そして、2000年代になり、それまでとは異なるビジョンを持った若いワインメーカーが増えてきました。ポルトガル独自の多様性を維持しながらも、以前とは違う個性を持つポルトガルワインの生産が増えています。この「グアポス・ワイン・プロジェクト」のブルノとダニエルも新しい世代のワインメーカーになります。
●
2022 Vinho Verde Ardina Avesso 400
ヴィーニョ・ヴェルデ・アルディナ・アヴェッソ・クアトロセントシュ
【「・・勿体無い!」・・ときっと思っていただけるに違い無い、リーズナブルで旨い白です。ちょっとビックリするはず!】
 noisy も忙しく無ければ、リーズナブルで美味しいワイン探しの旅に出たい・・のは山々なれど、なぜか判りませんが・・
noisy も忙しく無ければ、リーズナブルで美味しいワイン探しの旅に出たい・・のは山々なれど、なぜか判りませんが・・「歳を経るごとに忙しくなる!」
んです。なんででしょ・・。人は増えているから労働力は昔の比じゃ無いはずです。でも結局のところ、年間休日7日・・でも完全な休日は年間で1日有るかな?・・みたいな感じで、しかも毎日仕事に追われています。
「早く人間になりたい」
このヴィーニョ・ヴェルデの白ワインは、このところ絶好調のオルヴォーさんからご紹介されました。
「・・ん?・・軽くて水っぽいヴィーニョ・ヴェルデじゃ・・無いね・・。結構行けるじゃん!」
となったのは良いんですが、話しをよく聞いてみますと・・
「ワインは美味しいし安くて良いんですが、もう・・次が無いことが判ったんです・・」
とのこと。
なんと、連絡が付かなくなったので心配していたところ、「倒産した」と電話が有ったそう。
「(げげっ!)」
何か身につまされる出来事では有ります。日本も円安、ユーロ高、ドル高が恒常化し、お米もガソリンも高くなって来ました。まぁ・・内外価格差是正は必要不可欠なので予想通りでは有りますが、たしかに、
「Noisy wine で千円台のワインって、造り手はいくらもらってるの?」
と言う話です。・・ちょっと泣けてきます。
 僅かに緑を感じさせる薄めの黄色です。まぁ・・一瞬は、
僅かに緑を感じさせる薄めの黄色です。まぁ・・一瞬は、「シャバい味わいなのかな?」
などと思ってしまうでしょう。
細やかな泡が見えますから、少々はピチピチと感じられるガスが存在すると・・飲む前から想像が出来ます。
香りは軽やかな柑橘や桃、フラワリーで甘やかさを持ったハーブ、さわやかなシトラスなアロマです。口に含むとほんのりピチピチ、黄色と緑のフルーツ感、果皮感が拡がります。甘くは無くドライですが、まったく甘さが無いのか?・・と言うと微妙な感じ・・の残糖感ですので、ほぼドライです。フレッシュな美味しさが中域で膨らみますが酸っぱくは無く、・・そのまま収束に向かうのか?・・と思うと・・そこからもう一段、
「ぶぶぶっ」
と旨味とビターさを含んだ美しいエキスの味わいが押して来て膨らんでくるんですね。
「・・おっ・・これはスティルではあんまり無いタイプ!」
そうなんです。おそらくですが、さわやかさを感じさせる口入れ直後のガスの存在が、「後調子」的な後半の味わいを強めに感じさせているのかな?・・と感じます。
エキスの濃度はそれなりに肉厚で結構にしっかり感じますので、
「ん・・これは千円台のワインとすると秀逸・・」
と感じました。
まぁ・・フレッシュ系でもありますが、それを余り強く感じさせないほどの終盤の粘り腰がある・・と言えば良いでしょうか。良いワインだと思います。喉腰も素晴らしい!・・是非飲んでみてください。お薦めします!
P.S. エチケットの「400」は畑の標高です。
ガイヤーホフ
ガイヤーホフ
オーストリア Geyerhof ニーダーエスタライヒ
[ oisy wrote ]
● 古くから取り扱いのあるオーストリアの造り手、ガイヤーホフを今回はオイジーからご紹介させていただきます。
オイジーとしては初めてのテイスティングだったのですが・・・テイスティングした後、何度も価格を見直してしまいました。なぜなら・・・
え・・・間違いじゃないの・・?というくらい安いんですね・・・
もちろん昔の価格からは結構上がっているようなんですが、それでもどのキュヴェも、この味わいでこの価格なの・・・?となかなか信じられませんでした。
それと旧ビンテージは一部のキュヴェではビオ的な醸造にチャレンジした部分もあるようなのですが、今回の2021ビンテージはどのキュヴェもかなりクリーンで安定感があります。ビオの畑の良いところだけを残して安定感のある造りに戻ってきたのかな・・・と思います!
素晴らしいコスパのワインです。オーストリアワインですが、全方位のお客様にご提案できると感じております。ぜひご検討ください!
● ラシーヌさんがいきなり止めてしまったので大変困ったんですが、野村ユニソンさんが復活してくれました・・助かりました!・・オーストリア随一の白ワインです。
頑張って全てのワインをテイスティングさせていただきましたが、ビオ栽培は相変わらず素晴らしいですし、
「So2 の使用量が減り優しくふんわり感の強い、硬くなくポテンシャル高いワイン!」
になり、しかもさらに・・ビオ的にも進化をしていると感じました。
特にグリューナーの「HOFSTUDIEN」・・So2感の無いモロビオ風ではあるものの、決してアヴァンギャルドなビオには陥らない・・ギリギリを攻めた素晴らしい仕上がりです。
勿論、他のアイテムも相変わらずに素晴らしいです。もう、「ガイヤーホフ的」と言う言葉を造りたくなるような「張りのある見事な膨張感と緊密感」が良いです。是非ご堪能下さいませ。
■エージェント情報
 日本にも来日経験があり、長年日本のオーストリーワインファンを満足させてきたガイヤーホフが弊社正規代理店として復活致しました。純粋な和食に最も合うと思われる、グリューナーヴェルトリーナー。その名門として長年良質なワインを提供しているガイヤーホフ。今回入荷分も昔ながらの安定した酒質と、新しい事に挑戦し、新たにリリースした新キュヴェなど魅力満載です。 これからの季節に重宝する爽快なオーストリーワイン。是非、お試しください。
日本にも来日経験があり、長年日本のオーストリーワインファンを満足させてきたガイヤーホフが弊社正規代理店として復活致しました。純粋な和食に最も合うと思われる、グリューナーヴェルトリーナー。その名門として長年良質なワインを提供しているガイヤーホフ。今回入荷分も昔ながらの安定した酒質と、新しい事に挑戦し、新たにリリースした新キュヴェなど魅力満載です。 これからの季節に重宝する爽快なオーストリーワイン。是非、お試しください。
【ドメーヌ説明】
ガイヤーホフの名が確認できる最も古い文献は1135年。16~17世紀には特別な階級だったというマイヤー家が所有する特別なワイナリー。現オーナーはイルゼ マイヤー。ウィーンの大学でビオディナミと生態学を学び、1986年に実家のワイナリーを継ぐこととなりました。その後、二コラ ジョリー、マルク アンジェリ(ラ フェルム ド ラ サンソニエール)、ラルー=ビーズ ルロワとの出会いから、1988年に完全にビオロジック転換。しかし、当初は上手くいかず、様々な失敗を重ねて修正をしていく事となります。なお彼女の姉はもう一方の名門、ニコライホフのクリスティーネ サースです。
ガイヤーホフでは一貫してビオロジックに取り組み、全て手作業で収穫、全房圧搾、しっかりとコラージュした後にステンレスタンクで発酵する事を徹底しています。現在では23haを所有し、それらを息子のヨーゼフが後を継ぐべく、次世代へ引継ぎを徐々に進めています。
● 古くから取り扱いのあるオーストリアの造り手、ガイヤーホフを今回はオイジーからご紹介させていただきます。
オイジーとしては初めてのテイスティングだったのですが・・・テイスティングした後、何度も価格を見直してしまいました。なぜなら・・・
え・・・間違いじゃないの・・?というくらい安いんですね・・・
もちろん昔の価格からは結構上がっているようなんですが、それでもどのキュヴェも、この味わいでこの価格なの・・・?となかなか信じられませんでした。
それと旧ビンテージは一部のキュヴェではビオ的な醸造にチャレンジした部分もあるようなのですが、今回の2021ビンテージはどのキュヴェもかなりクリーンで安定感があります。ビオの畑の良いところだけを残して安定感のある造りに戻ってきたのかな・・・と思います!
素晴らしいコスパのワインです。オーストリアワインですが、全方位のお客様にご提案できると感じております。ぜひご検討ください!
● ラシーヌさんがいきなり止めてしまったので大変困ったんですが、野村ユニソンさんが復活してくれました・・助かりました!・・オーストリア随一の白ワインです。
頑張って全てのワインをテイスティングさせていただきましたが、ビオ栽培は相変わらず素晴らしいですし、
「So2 の使用量が減り優しくふんわり感の強い、硬くなくポテンシャル高いワイン!」
になり、しかもさらに・・ビオ的にも進化をしていると感じました。
特にグリューナーの「HOFSTUDIEN」・・So2感の無いモロビオ風ではあるものの、決してアヴァンギャルドなビオには陥らない・・ギリギリを攻めた素晴らしい仕上がりです。
勿論、他のアイテムも相変わらずに素晴らしいです。もう、「ガイヤーホフ的」と言う言葉を造りたくなるような「張りのある見事な膨張感と緊密感」が良いです。是非ご堪能下さいませ。
■エージェント情報
 日本にも来日経験があり、長年日本のオーストリーワインファンを満足させてきたガイヤーホフが弊社正規代理店として復活致しました。純粋な和食に最も合うと思われる、グリューナーヴェルトリーナー。その名門として長年良質なワインを提供しているガイヤーホフ。今回入荷分も昔ながらの安定した酒質と、新しい事に挑戦し、新たにリリースした新キュヴェなど魅力満載です。 これからの季節に重宝する爽快なオーストリーワイン。是非、お試しください。
日本にも来日経験があり、長年日本のオーストリーワインファンを満足させてきたガイヤーホフが弊社正規代理店として復活致しました。純粋な和食に最も合うと思われる、グリューナーヴェルトリーナー。その名門として長年良質なワインを提供しているガイヤーホフ。今回入荷分も昔ながらの安定した酒質と、新しい事に挑戦し、新たにリリースした新キュヴェなど魅力満載です。 これからの季節に重宝する爽快なオーストリーワイン。是非、お試しください。【ドメーヌ説明】
ガイヤーホフの名が確認できる最も古い文献は1135年。16~17世紀には特別な階級だったというマイヤー家が所有する特別なワイナリー。現オーナーはイルゼ マイヤー。ウィーンの大学でビオディナミと生態学を学び、1986年に実家のワイナリーを継ぐこととなりました。その後、二コラ ジョリー、マルク アンジェリ(ラ フェルム ド ラ サンソニエール)、ラルー=ビーズ ルロワとの出会いから、1988年に完全にビオロジック転換。しかし、当初は上手くいかず、様々な失敗を重ねて修正をしていく事となります。なお彼女の姉はもう一方の名門、ニコライホフのクリスティーネ サースです。
ガイヤーホフでは一貫してビオロジックに取り組み、全て手作業で収穫、全房圧搾、しっかりとコラージュした後にステンレスタンクで発酵する事を徹底しています。現在では23haを所有し、それらを息子のヨーゼフが後を継ぐべく、次世代へ引継ぎを徐々に進めています。
●
2022 Gruner Veltliner Hofstudien
グリューナー・ヴェルトリーナー・ホフステュディエン
【ナチュールスタイルからの揺り戻し・・・?グリューナーのこのキュヴェは・・クリーンでアロマティックに香る!】[ oisy wrote ]
 [ oisy wrote ]
[ oisy wrote ]アロマティックですね~!
ホフステュディエンはだいぶアロマティックに香ります。黄色の果実、リンゴの蜜、わずかに新鮮なハーブと若干ぺトロールも含まれているように感じます。そのどれもがピュア感を伴っていて心地よいです。
味スジはドライです・・が、凝縮感があります。その凝縮感によるエキスの密度の高まりからの果実のあまやかさがあります。
そしてオイリーさも感じます。少しむっちり・・とした感じも出てきました。
ベルクフリート、シュトックベルクは「果実のニュアンスが高め」で、ホーハーラインでは「ミネラルと果実が対等」なところまできて、ホフステュディエンで果実の凝縮感によってミネラルが覆われて「再び果実感が盛り返す、でも下のキュヴェの果実感とは意味合いが異なる!」というようなところでしょうか。
ですので、このキュヴェが一番格が高いというのをしっかりと実感することができます。キュヴェごとのニュアンスの違いというのもとても面白いですね。恐らくグリューナー・ヴェルトリーナーはニュートラルな品種なのでしょう。鏡のように畑の特徴を映しだしていると感じます。
しかしNoisyの以前のビンテージの写真とコメントを見るとけっこうにナチュール感強めですね。写真を比較していただけると如実にわかるかと思いますが、今回のビンテージは非常にクリーンです。SO2の量としては下のキュヴェと比較すると低いとは感じます。ただし揮発酸の「き」の字も感じません。めちゃくちゃキレイで健康的です。危うさはほぼ皆無でクラシックなスタイルがお好きな方にもご提案できるほど・・だと感じています。
つまり畑のビオ感だけをワインに落とし込んだ、安定したワインだと思います。もしかしたら昨年のビンテージでナチュールスタイルに大きくチャレンジした結果、ちょうど良い塩梅を掴み、今回のスタイルに揺り戻してきた・・・のかもしれません。
造り手の試行錯誤も透けて見えますが、あくなき探求心の現れとも取れますし、チャレンジしたことによって現在の良いとこどりのようなスタイルにたどり着いたのなら喜ばしいことではないでしょうか!
うま味の強い海老や蟹などの甲殻類との相性は抜群だと思います。温かい前菜やオイル系のパスタにもしっかり答えてくれると思います。このレベルまで来るとかなりマリアージュの許容範囲も広がってきますね!
アロマティックに果実が香る、エキシーな凝縮感を感じさせてくれるグリューナー・ヴェルトリーナーです。めちゃうまい!ぜひご検討ください。
[ noisy wrote ]
以下は以前のレヴューです。
-----
 【ガイヤーホフの進化とナチュールへの意欲が感じられるキュヴェ!・・このしなやかさと飲み心地は別格・・是非飲んでみてください!「解放」のグリューナー!】--以前のレヴューです。
【ガイヤーホフの進化とナチュールへの意欲が感じられるキュヴェ!・・このしなやかさと飲み心地は別格・・是非飲んでみてください!「解放」のグリューナー!】--以前のレヴューです。まぁ・・こんなことを言うと、超偉そうに・・もしくは嫌味に思われてしまいそうで・・何ですが、「絶対に旨いので購入すべき」と書けば、それはそれなりに販売可能かと思います。が、やはりそこには、飲む方それぞれの受け止め方をある程度想像していないと・・そんなことは出来ないんですね。
まぁ・・ブルゴーニュワインなら、その購入対象はブルゴーニュワインファンが多くを占める訳ですから、そちらに向けてはむしろ・・言いやすいです。
ですが、こと「ナチュール系」と言うことになりますと、そんな訳にも行かないんですね。アヴァンギャルド系の突き抜けたビオ・ナチュールを、昔からワインが好きで飲み続けられていらっしゃる方に
「美味しいから必飲です」
なんてやった日には、もう・・想像しただけで目を開けられない状況が浮かんで来ます・・まぁ・・判らないとは思いますが・・。
ですが、このガイヤーホフの意欲作、ホフステュディエンは、そんなアヴァンギャルド系では有りません。ですが、
「今までのガイヤーホフから、2~3歩踏み出したナチュール!」
と言うことが言えるでしょう。
まぁ・・ラシーヌさんが何故ガイヤーホフを手放したか・・と言えば、その理由の一つには・・きっと、
「So2の残存量(もしくは使用量)」
が有るんじゃないかと・・noisy は勝手に思っています。ですので正しくない、関係無い可能性も有りますから信じないでくださいね。
本来、自然派は、
「醸造スタイルは全く関係が無い」
訳です。自然派はなぜそう呼ばれるか・・は、栽培方法に由来する訳です。ですから、醸造において使用されるもの、もしくは方法は全く関係がありません。
 しかしながら、So2(酸化防止剤) の使用は、仕上がったワインの味わいにも大きく影響します。
しかしながら、So2(酸化防止剤) の使用は、仕上がったワインの味わいにも大きく影響します。言ってしまえば、通常の白ワインは収穫後にまず圧搾しますから・・できれば酸化を避けるためにSo2を使いたい訳です。ですがそれをしてしまいますと、果皮に付いている酵母まで使用できなくなってしまいますよね?・・だから自然派の多くの白ワインは、やや褐色の色彩をしています・・これは一般論で、醸造方法によっては異なります。
おそらくですが、ガイヤーホフはSo2の使用量の削減、ひいては残存So2の検出量の減少を目指すとともに、最終的には「So2 フリー」へと変身する道を歩み始めたのかな・・と感じています。このワインが・・そう語っているように思うんですね。
もう、「飲み心地」が今までのガイヤーホフのワインとだいぶ違うんですね。さらに柔らかく、尖った部分が無いです。ふんわりと柔らかで・・ほんの僅かですが揮発酸の影響が見られます。でもこれは完全に収まっていて、複雑な表情のひとつになり溶け込んでいます。
感じられる果実も「まるっ」としてふくよかです。リンゴやナシ、洋ナシ、僅かにアンズとか・・かなり複雑ですがリアルに感じます。中域の膨らみも・・他のキュヴェの「張り詰めた感」がむしろなく、より自然なエッジでその張り詰めた感を解放しているイメージです。
まぁ・・他のキュヴェが風船に入ったワインだとするなら、このホフステュディエンは・・風船には入っていない、グラスの中のワイン・・でしょう。
ですから、出来るだけ多くの方に飲んでいただきたいのですが、一般的に言うところのナチュール感は大きく膨らんでいますから、ビオ的なワイン、自然派ワインが得意じゃない方は・・ちょっと一歩下がった方が良いかもしれません。
ですが・・そうそう、言ってしまえば「ジェラール・シュレールを精緻にした感じ」・・でしょうか・・(^^;; ・・これはいけない表現かな・・でも結構、近いと思います。この辺の表現が響く方は是非飲んでみてください。お勧めします!
テッレ・ヴィヴェ・マトゥネイ
テッレ・ヴィヴェ・マトゥネイ
イタリア Terre Vive Matunei ピエモンテ
● それなりに長くこの世界にいる noisy も、まだまだ知らないことが多いようです。・・と言うか、有望な若い方々がどんどん出て来ているんですね~・・。ヴァーゼンハウスしかり、このテッレ・ヴィヴェ・マトゥネイも・・です。
数アイテム届いているんですが、テイスティングが進まず少し遅れてしまいました。ようやっと飲んでみると・・
「・・こりゃぁ・・只者では無いな・・」
と言う感覚で迎えることになりました。相当に美味しいですよ。
余り濃いのは得意では無い noisy では有りますが、それでもこういうのは大好きです。是非飲んでみてください!
 ■自然と田舎の風土を愛する夫妻の新たな挑戦
■自然と田舎の風土を愛する夫妻の新たな挑戦
マトゥネイは2015 年に誕生した小さなファーム(農園)です。アルベルト・ブリニョーロと妻のカルラは、四季の移ろいの中で仕事と人間が密接に絡み合っていた古来の仕事を通して、現代人が忘れてしまった人生の瞬間を取り戻しながら、持続可能な農業の新しい形態を再発見したいという想いから、それまでしていた仕事を辞めて、人口100 人に満たない小さな村アルフィアーノ・ナッタに移住し、カルドナの丘の耕作放棄地と古いブドウ畑を引き継いで農業を始めました。
■コスパの高いピエモンテのナチュラルワイン
二人が暮らす地方では、30 年前にランゲ地方で起こったような新しい世代のブドウ栽培家によって変革が起こっています。地元のナチュラルワインの造り手達に触発されて、二人も地場のローカル品種を栽培して、ナチュラルワインを造り始めました。栽培はビオディナミの手法も取り入れたビオロジックで、醸造面でも添加物は一切使わずに、野生酵⺟で発酵を行っています。私達も二人のワインを試飲しましたが、まだ初ヴィンテージから数年にも関わらず、非常にコストパフォーマンスが高く、クリーンなナチュラルワインで、感銘を受けました。
彼は化学薬品は一切使わず、地場の⾃然の⽣態系を守り、何よりもブドウの質を最重要視して、農作業を尊重しながら働いていました。良質なワイン造るためにはブドウの質が最も⼤切なことは明⽩です。しかし、イタリアでも買い取りブドウの価格は⽣産コストに対して十分なものでありません。このため、多くのブドウ栽培農家が低品質のブドウを⼤量に売却しています。これらのブドウは、質の低さを補うために⼤量の化学薬品を添加して醸造されています。貧しい農業政策による悪循環と⾔えます。とても残念なことです。
しかし、夫妻はこの隣人を通して、地元の他のナチュラルワイン造り⼿達とも知り合い、彼らから多くのことを学びました。そして、このモンフェッラート地⽅では、30 年前にランゲ地⽅で起こったような新しい世代のブドウ栽培家が物事を変え始め、⾃分でワインを造り、畑のテロワールを表現するワイン造りをしていること。素晴らしいワインが⽣まれ、忘れられていたブドウ品種が再発⾒されていることを知ったのです。ブドウとワイン、そしてその伝統には真の可能性があること。ワインとは、地元のテロワールと文化、そして地元の人々について、世界中の人とコミュニケーションする最良の⼿段の1 つであることを認識したのです。
そこからは、勉強と情熱が一緒になりました。ゼロからブドウ栽培とナチュラルワイン造りを始めることは非常に厳しいものでしたが、アルベルトとカルラは、偏⾒は持たず、好奇⼼に満ち溢れた「純粋な⼦供の目」でワインの世界に飛び込みました。そして、ナチュラルワインを造る地元の友人達から学びながら、ナチュラルワイン造りをしています。
■畑と栽培について
マトゥネイのブドウ畑は、アルフィアーノ・ナッタ村にあります。栽培面積は約3ha で地質は粘⼟石灰岩。5 つの異なる区画に分かれています。地場品種のグリニョリーノとフレイザ、バルベーラ、ネッビオーロを栽培しています。栽培はビオロジックで合成化学物質や除草剤などは一切使⽤しません。ビオディナミの⼿法も既に取り入れており、将来的にはビオディナミへの移⾏する計画です。畑作業は全て⼿作業で、四季と⾃然のリズムに応じて⾏われています。醸造は、添加物は一切使わずに野⽣酵⺟で発酵を⾏います。
マトゥネイのワインは、畑と醸造所における細⼼の注意を払った仕事と、ワイン造りへの情熱の結晶です。それぞれのワインについて、ストーリーを伝えることができる名前を付け、エチケットのデザインは、アーティストによるものです。マトゥネイの畑とワインは、Suolo e Salute「⼟と健康」を意味する、農産物加⼯と環境保護の管理運営及び認定を⾏うイタリアの組織によってビオの認証を受けています。
また、マトゥネイでは2016 年から考えを同じくする同じ村の造り⼿クレアルトとともに、協同組合「Terre Vive テッレ・ヴィヴェ」を創設しました。共同プロジェクトとして、昔の仕事や地場のロ-カル品種、テロワールなどについて学び、地元の古い⼯芸品や領地、⼟地固有のブドウを広く伝える活動をしています。そして、それぞれの畑で栽培されたブドウの一部を持ち寄って、マトゥネイのワインとは別に共同組合「ヴィノ・ディ・トゥッティ」のブランド名でワインを醸造して販売しています。
数アイテム届いているんですが、テイスティングが進まず少し遅れてしまいました。ようやっと飲んでみると・・
「・・こりゃぁ・・只者では無いな・・」
と言う感覚で迎えることになりました。相当に美味しいですよ。
余り濃いのは得意では無い noisy では有りますが、それでもこういうのは大好きです。是非飲んでみてください!
 ■自然と田舎の風土を愛する夫妻の新たな挑戦
■自然と田舎の風土を愛する夫妻の新たな挑戦マトゥネイは2015 年に誕生した小さなファーム(農園)です。アルベルト・ブリニョーロと妻のカルラは、四季の移ろいの中で仕事と人間が密接に絡み合っていた古来の仕事を通して、現代人が忘れてしまった人生の瞬間を取り戻しながら、持続可能な農業の新しい形態を再発見したいという想いから、それまでしていた仕事を辞めて、人口100 人に満たない小さな村アルフィアーノ・ナッタに移住し、カルドナの丘の耕作放棄地と古いブドウ畑を引き継いで農業を始めました。
■コスパの高いピエモンテのナチュラルワイン
二人が暮らす地方では、30 年前にランゲ地方で起こったような新しい世代のブドウ栽培家によって変革が起こっています。地元のナチュラルワインの造り手達に触発されて、二人も地場のローカル品種を栽培して、ナチュラルワインを造り始めました。栽培はビオディナミの手法も取り入れたビオロジックで、醸造面でも添加物は一切使わずに、野生酵⺟で発酵を行っています。私達も二人のワインを試飲しましたが、まだ初ヴィンテージから数年にも関わらず、非常にコストパフォーマンスが高く、クリーンなナチュラルワインで、感銘を受けました。
彼は化学薬品は一切使わず、地場の⾃然の⽣態系を守り、何よりもブドウの質を最重要視して、農作業を尊重しながら働いていました。良質なワイン造るためにはブドウの質が最も⼤切なことは明⽩です。しかし、イタリアでも買い取りブドウの価格は⽣産コストに対して十分なものでありません。このため、多くのブドウ栽培農家が低品質のブドウを⼤量に売却しています。これらのブドウは、質の低さを補うために⼤量の化学薬品を添加して醸造されています。貧しい農業政策による悪循環と⾔えます。とても残念なことです。
しかし、夫妻はこの隣人を通して、地元の他のナチュラルワイン造り⼿達とも知り合い、彼らから多くのことを学びました。そして、このモンフェッラート地⽅では、30 年前にランゲ地⽅で起こったような新しい世代のブドウ栽培家が物事を変え始め、⾃分でワインを造り、畑のテロワールを表現するワイン造りをしていること。素晴らしいワインが⽣まれ、忘れられていたブドウ品種が再発⾒されていることを知ったのです。ブドウとワイン、そしてその伝統には真の可能性があること。ワインとは、地元のテロワールと文化、そして地元の人々について、世界中の人とコミュニケーションする最良の⼿段の1 つであることを認識したのです。
そこからは、勉強と情熱が一緒になりました。ゼロからブドウ栽培とナチュラルワイン造りを始めることは非常に厳しいものでしたが、アルベルトとカルラは、偏⾒は持たず、好奇⼼に満ち溢れた「純粋な⼦供の目」でワインの世界に飛び込みました。そして、ナチュラルワインを造る地元の友人達から学びながら、ナチュラルワイン造りをしています。
■畑と栽培について
マトゥネイのブドウ畑は、アルフィアーノ・ナッタ村にあります。栽培面積は約3ha で地質は粘⼟石灰岩。5 つの異なる区画に分かれています。地場品種のグリニョリーノとフレイザ、バルベーラ、ネッビオーロを栽培しています。栽培はビオロジックで合成化学物質や除草剤などは一切使⽤しません。ビオディナミの⼿法も既に取り入れており、将来的にはビオディナミへの移⾏する計画です。畑作業は全て⼿作業で、四季と⾃然のリズムに応じて⾏われています。醸造は、添加物は一切使わずに野⽣酵⺟で発酵を⾏います。
マトゥネイのワインは、畑と醸造所における細⼼の注意を払った仕事と、ワイン造りへの情熱の結晶です。それぞれのワインについて、ストーリーを伝えることができる名前を付け、エチケットのデザインは、アーティストによるものです。マトゥネイの畑とワインは、Suolo e Salute「⼟と健康」を意味する、農産物加⼯と環境保護の管理運営及び認定を⾏うイタリアの組織によってビオの認証を受けています。
また、マトゥネイでは2016 年から考えを同じくする同じ村の造り⼿クレアルトとともに、協同組合「Terre Vive テッレ・ヴィヴェ」を創設しました。共同プロジェクトとして、昔の仕事や地場のロ-カル品種、テロワールなどについて学び、地元の古い⼯芸品や領地、⼟地固有のブドウを広く伝える活動をしています。そして、それぞれの畑で栽培されたブドウの一部を持ち寄って、マトゥネイのワインとは別に共同組合「ヴィノ・ディ・トゥッティ」のブランド名でワインを醸造して販売しています。
●
2020 Vino di Tutti Vino Rosso
ヴィノ・ディ・テュッティ・ヴィノ・ロッソ
【ミネラリティのツヤ感を手に入れた・・!?これ以上のデイリーバルベーラは無いんじゃないかと思うほどの激ピュアで密度感のあるバルベーラです!】
 [ oisy wrote ]
[ oisy wrote ]ヴィノ・ディ・トゥッティ、「みんなのワイン」です。マトゥネイはデイリーワインとカテゴライズしているようですが、今年は前年よりミネラリティが表に出てきているようで、その範疇に収まらない・・・素晴らしいワインに仕上がっています!
個人的には「トゥッティ」という言葉には非常に懐かしさを感じます。もう10年ほど前になりますが、イタリアンレストランで働いていた時に、厨房ではイタリア語でやり取りをしていたんですね。もちろん会話は日本語なんですが、ディナータイムの厨房は戦場なので、切羽詰まってるときに日本語だとただの喧嘩になっちゃうんですよ。それが不思議なものでイタリア語だと「活気のあるレストラン」を演出してくれるんですね。
トゥッティは日本語では「みんな、全部」とかの意味で使いましたから、「お客様全員」とか「これで全部」みたいな意味で使っていたと思います。
「トゥッティ?(これで全部?)」「トゥッティ!(全部です!)」みたいな使い方です。カタコトもいいとこです(笑)。営業前には「フォルツァ ! トゥッティ!(みんな、頑張ろうぜ!)」と気合を入れたものです。ですので、この言葉にはなんとなく「カジュアル」で「おおらか」な言葉の響きみたいなものを感じてしまいます。マトゥネイもこのワインには「みんなでおいしく飲もうよ!」みたいな意味合いを込めているんだと思います。
しかしヴィノ・ディ・トゥッティは一般的なカジュアルラインのワインでは、まず見かけないクオリティなんですよ・・・SO2無添加の激ピュアな果実。通常、カジュアルな自然派の造りの多くではここで終わってしまいます。しかししっかりとミネラリティが含有されていてツヤツヤ。果実のピュア感のみでは出てこない、ミネラリティと合わさったエレガンスがあります。そこに地場のハーブの要素が僅かに含まれている感覚です。
バルベーラといえば、レストランでも重宝していました。それなりに安い価格で果実のジューシー感がわかりやすく出るので使いやすかったんですね。それ故に「ジューシー感のみ」で終わってしまったり、「粗野で雑」な印象を受けることもしばしばでした。
しかしながらマトゥネイのバルベーラは非常に「丁寧」で「雑さが皆無」に近く、エキスの質感が非常にキレイです。それでいて「濃いめの果実エキス」でありながら「重さを感じない」という素晴らしいバランスです。バルベーラのエレガントな上澄みエキスの部分のみをワインに仕立て上げたような感覚です。
たまたまですが、店の前の角上というスーパーで半額になっていたステーキ用の牛肉と合わせました。結構に脂の噛んでいるチャックフィンガー(肩バラ)という部位だったのですが、このヴィノ・ディ・トゥッティとのマリアージュは最高でした・・・ステーキの脂と肉の旨みに「濃さ」で張り合うのではなく、しっかり「密度」で張り合ってきます。この価格帯のワインでこの張り合い方ができるワインは多く無いと思います。
Noisy談によると前年はもう少し果実感が主体でここまでミネラリティが前面に出ていなかったとのこと。これは単純にヴィンテージ差もあるかもしれませんが、マトゥネイの腕が上がったのかも・・・と思います。
実はこのワインは2本目のテイスティングです。一本目は10月頭にテイスティングしたんですが、還元の硫黄感がひどくて出せませんでした。それが2カ月でこれほど変わるのかというほどびっくりエレガントなワインに変わってきています。しかしまだ完全には抜けきっていないようなので、もし温泉卵のような硫黄のようなニュアンスを感じとられましたら、数日冷暗所に放置してみてください。還元は抜け、かなり変わるはずです。還元さえ抜ければ、不安定な要素は見当たりません。
逆にあれだけ還元していたということは相当酸素との接触は少ない作りだったのだと思います。このツヤ感やミネラリティもそれだけ酸素との接触を避けてたからこそ、「果実の皮」を剥いで表に出てきてくれたのでは・・・?と思いました。
デイリーワインと呼ぶにはもったいない、いやこれこそ真のデイリーワインなのかもしれません!ぜひご検討下さいませ。
以下は以前のレヴューです。
-------
[ noisy wrote ]
【脅威のデイリー!・・ナチュラルなバルベーラがピュアにぷっくり!・・しなやかテクスチュアの超バランスワイン!・・ポテンシャルも半端無い・・素晴らしいです!】

いや~・・「有難う!」と素直に言いたい、素晴らしいワインです!・・この際、品種などどうでも良いと思ってしまうほどに、
「美味い!」
と思っていただけるに違い無いです。
マトゥネイは数人の仲間と共にテッレ・ヴィヴェと言う協同組合を設立し、このワインを造っているそうですが・・
「価格が異常に安い!」
「テクスチュアがツヤッツヤ!」
「濃いのにスルッと飲めて後口が瑞々しい!」
「ナチュラル感はちゃんとあるのに滅茶ピュア!」
「バランスが素晴らしい!」
「いつ飲んでも硬くならない!(・・多分)」
「果実感がしっかり有るのにあざとくない!」
・・・いやいや・・もっと幾らでも書けちゃいますが、
「・・本当にありがとう!」
と握手したいほど、美味しくてリーズナブルです!・・山ほど買いたいワイン!・・だけどスペースが・・ない・・(^^;;
余りにセラーが一杯なので後口でもう少し入荷いたします。もし買えなくてもお待ちくださいね・・。
「飲んだら余りの美味しさにビックリする超リーズナブルワイン!」
です。
あ、一応品種は「バルベーラ」ですが、実はバルベーラらしいのに、バルベーラの有る種の「くどさ」が無い・・!素晴らしいワインです。是非ご検討くださいませ。超お勧めします!
以下は以前のレヴューです。
-----
【めちゃ旨!ピュアなアロマとナチュラルな濃密さのスルスルっと入って来る飲み口・・「濃いスル」なバルベーラです・・が、実は服を脱いでも凄かった?から・・本当に恋するワイン!?】
 このようなワインをご紹介できるのは実に嬉しいです!・・まぁ、noisy も長いことワインを飲んで来ましたので、流石に・・
このようなワインをご紹介できるのは実に嬉しいです!・・まぁ、noisy も長いことワインを飲んで来ましたので、流石に・・「・・濃い奴は・・なぁ・・身体が受け付けないんだよね・・」
と言うのは、良~~く判ります。一緒に飲む方が結構、そっち系を好きだったりして、気を使わないといけなかったりするでしょう?
でも安心してください。履いてま・・いやこのワインなら、全然オッケーなんですよ・・。
色合いを見てみるとそれなりに濃さの伝わって来るような感じです。「重そう!」とまでは行かないにせよ、「甘いかも・・」なんて疑問も生まれてしまうかな?
でも良~く見つめてみると、一面の濃さで覆われているようでは無いですよね?・・そして照りが有ってセクシーな感じが出てると思います。
アロマのスピードは速く、ツヤツヤしたミネラリティでコーティングされたような粒子が赤黒果実を含みつつノーズに飛び込んで来ます。口に含むとテクスチュアはテッカテカ・・液体はスルッと喉を目指して行きます。余り途中で留まらない感じ・・走り出したら止まらないぜ・・♪♪ みたいな感じでしょうか。
エキスの濃密さはしっかり有り、酸も綺麗なバランスで丸く球体なパレットを描きます。タンニンはそこそこに在るのでしょうが、それを全く意識させずに余韻に向かいます。赤黒果実のナチュラルなイメージが脳裏に描かれます。
「・・あれ_・・結構以上に・・旨いじゃん・・」
イメージ的にはエレガントなボルドー・・でしょうか。品種を考えると・・土地的にはピエモンテのテロワールが伝わって来ます。カベルネ的でも有りますが、ドシッと重いものでは無く中くらい・・でしょうか。華やかですし、重く無いし、濃くないし、甘く無いです。
もう、普段飲みのワインだとするなら・・想像以上に素晴らしいです。
が・・・これ、1時間くらいすると、かなり膨張してくるんですよ。中低域から中域に掛けての膨らみが物凄いです。すると膨大なミネラリティに囲まれていて外に出られなかったタンニンなどの要素が、顔を出し始めます・・膨らんでくるんですね~。
ただしもうその頃にはボトルの最後位までは飲んじゃってますから、このシュチュエーションには出会わないかもしれません。
つまり、デイリーとしても相当に美味しいが、ポテンシャルも想像以上に有る・・てことなんですね~。
どうやら相当に売れているようでして、エージェントさんの最後の在庫の最終分までを購入しました。それでも少ないですが、
「飲んだら相当にビックリする・・ピノ・ノワール系の淡い色合いのワインを好きな方でも全然オッケーな自然なワイン!」
と言えます。
誤解を恐れずに言ってみれば、エリオ・アルターレのバルベーラをピュアに、ナチュラルに、もっとミネラリティの高さを持っている方向に振ったようなワイン・・です。アルターレのバルベーラは結構に濃いですから・・でも、そんな濃さを全く感じさせない味筋で、しかも芳香が高いと言えます。
滅茶美味しいので、是非とも飲んでみてください。最近、頑張りが光る「ヴィヴィット」さんの扱いです。おそらく次回新着には上級キュヴェをご案内できるか・・と思いますのでご期待ください!・・買っておいて損は無い・・と言うか、絶対「お代わり」したくなるピエモンテワインです!
●
2020 Macaia Vino Rosso
マカイア・ ヴィノ・ロッソ
【これぞ新時代・・!激ピュアなぶどう果実からのダイレクトな果実エキスに、しっかりと深みとアロマを感じるピエモンテワインです!】[ oisy wrote ]
 [ oisy wrote ]
[ oisy wrote ]この「マトゥネイ」。イタリア・リグーリアの方言で、「怒りと混じり合ったメランコリーな気分」という意味をもつ言葉のようです。元々は航海や気象学で使われていた用語で、どんよりとした空の天候を指していたらしいです。
しかしなんとなくこのワインの味わいに言葉の印象がピタッとはこない気がするんですよね…マトゥネイという言葉には日本人にはなかなかイメージつかないリグーリアの言葉の響があるのかなと想像します。ラベルには航海中の船が雷の中、灯台の光に向かって進んでいくようなデザインです。どちらかといえば、言葉の持つ意味よりもこのラベルの方がなんとなくワインのイメージに近く感じます。
ネッビオーロとバルベーラ半々のブレンドなんですが、Noisyの過去のコメントにもある通りで、単純に半々にしたイメージではない・・・んですよね。色味は紫の入った赤で、透明感のあるミネラリティです。
香りはぶどう果実そのものがアロマ化したような・・・素晴らしいフルーツのアロマです。そこにスミレやポジティブな枯れ感、僅かな野趣味が加わります。ここに関しては若いネッビオーロやバルベーラに感じる要素であり、セパージュをダイレクトに反映していると思います。
しかしこと味わいになると少し印象が違くて、ピュアなメルローを飲んだときのような、「実に綺麗な果実感」です。ネッビオーロの持つ「陰」の要素をあまり感じず、「明るさのある果実」を感じます。故に探りにいくことなく、反射的に「うまっ」と声に出してしまいます。そして余韻にかけてまたネッビオーロやバルベーラが持つ、スミレ感や赤紫果実っぽさが顔を出して伸びやかに締めていきます。この中域をしめる雑味の無いピュアな果実感がなんというか・・・新時代を感じるピエモンテワインです。
そしてアルコール度数は14.5%と高めなんですが、そうとはとても思えないほど「鈍重さがない」です。これは酸の良さもあるとあると思いますが、液体全体から感じるピュアな果実の影響かと思います。果実の「じゅわ〜っ」としたおいしさがあるんですよね。最初から最後までをとてもピュアな果実が寄り添ってくれます。
しっかりと澱を落とせばタンニンは意識することないほど細かく、シルキーです。ただやはりこのピノ・ノワールやメルローにはない、ピエモンテのぶどう品種が持つタンニンから滲み出る深みが・・・ピュアな果実と混じり合って「めちゃ美味なエキス」を形成しています。
ピュアなだけだとそうでもないんですが、この深みを併せ持っているとやはり「肉」をチョイスしたくなります。赤みの牛肉のステーキをこのワインで流し込んだら・・・最高でしょうね。まさに掛け算のマリアージュだと思います。残念ながら私もNoisyと同じく焼いた魚とのマリアージュになってしまいましたが・・・ただこのピュア果実感があれば、ちょっと工夫すれば魚とのマリアージュもいけそうな気がします。
それと今年もコルクではなく王冠です。あ、このダイレクトなぶどう感は王冠によって酸素の浸透がないことも影響が大きそうです。コルクによる緩やかな酸化がないので生き生きとした果実のピュア感をダイレクトに感じます。かといって還元的なニュアンスもなく、ちゃんと王冠の意図がワインに反映されていて素晴らしいです。
ダイレクトなぶどう果実の旨みとアロマを感じる、新時代・・ピエモンテワインです!ぜひご賞味くださいませ。
[ noisy wrote ]
以下は以前のレヴューです。
-----
 こんな手が有ったのか!・・とちょっとビックリしましたよ。このマカイアは、
こんな手が有ったのか!・・とちょっとビックリしましたよ。このマカイアは、「単にネッビオーロとバルベーラの半々ブレンドでは無い!」
と言うことが・・飲めば伝わって来ます。
しかも抜栓する前から・・
「これ、王冠で止まってるのね・・」
と視認することになります。
で、ようやく飲み始めるんですが・・なるほど・・です!・・そう、まるで・・「質の良いメルロ」のようです。でもこれはネッビオーロとバルベーラなんです。そして、
「タンニンが一杯!」
存在しています。そしてそのタンニンの質が・・分厚くて、甘くて、めちゃ質が良いんですよ。
 メルロだと粘土由来だと思うんですが、きっと・・このネッビオーロもバルベーラも、結構に粘土質のある土壌に植わっているのかなぁと・・想像させてくれます。
メルロだと粘土由来だと思うんですが、きっと・・このネッビオーロもバルベーラも、結構に粘土質のある土壌に植わっているのかなぁと・・想像させてくれます。果実も茶・黒・赤と色とりどりに有って複雑性はあるものの、決して「果実果実」しておらず、単に果実だけに振った味わいでは無いんですね。ほんのりリキュールっぽさも有りつつのピュアな風情も有って結構に複雑性も高いんです。
そして・・おそらく、
「ピエモンテ風何とか・・」
のような、獣、ジビエなどの焼いただけ、煮込んだだけみたいなシンプルな料理に、ベタピンでマリアージュすると思うんですよ。・・まぁ、noisy の場合はしっかり焼き魚で強制マリアージュしなければなりませんでしたが・・(^^;;
そこでこの「王冠」。この味わいをそのまんまにしたかった・・変化させたくないと考えたのかな?・・と思うんですね。決して「ガス」「泡」は有りません。ボトル詰めの時に少量だけSo2を入れた様です。
もう・・本当にワイン造りはセンスだと感じさせます。「ヴィノ・デ・テュッティ」も滅茶苦茶美味しいでしょう?・・こちらもリーズナブルで滅茶美味しいです!是非飲んでみて下さい。追加はご用意できません。
イル・ファルネート
イル・ファルネート
イタリア Il Farneto エミーリア=ロマーニャ
● エミーリアの新しい生産者をご紹介させていただきます。イル・ファルネートです。
実は・・相当以前に何本かテイスティングさせていただいてました。その時は・・
「ん~・・イマイチ・・ピンと来ないなぁ・・内向きで、ちょっとネガ背負ってる感じ・・」
だと判断してスルーしていました。
ですが最近、「イル・ファルネート」と言う言葉を聞くようになってきまして・・同じ埼玉のインポーターさんのエヴィーノさんのN社長さんに聞いてみると、随分と良くなったと・・言うことで、今回の入荷分をオーダーさせていただき、全アイテムをテイスティングさせていただきました。
「以前の暗さはどこへ?・・軽やかさのある外交的で垢抜けたナチュラルな味わい!」
で・・
「・・ありゃりゃ・・しばらく飲まない間に・・随分変わった?」
と、またNさんに聞いてみると、
「若い人が入ったので、その方の影響でしょう。すごく変わりました。」
とのこと。
まぁ、noisy も毎日のテイスティングで忙しいですが、やはり時折はチェックしていないと置いて行かれる・・そんな気になりました。
エミーリア=ロマーニャのワインらしく、快活で・・勿論、ガスが有ったり、適度な軽量感、しかし浅過ぎる感じも無くしっかりミネラリティも有って、非常にバランスの良いワインでした。そしてバルサミコも造っていまして、これがまたリーズナブルだけど結構な濃度も有り・・おいしいんですね。
ですので、
「クイクイ飲めるが薄辛くない・・バランス良く充実した味わいを楽しめるリーズナブルなイタリアン!」
です。是非飲んでみていただきたいと思います。お勧めです!
■エージェント情報
 レッジョ エミリアの南にあるカステッララーノの町。当主のマルコ ベルトーニは2001年、町から離れた丘陵地に念願の土地を手に入れ、ゼロからのブドウ栽培を開始する。畑は標高250m、サッスオーロを含むこの当たりは強い粘土質を持ち、年間の降雨量が少なく非常に乾燥している、この辺りではほとんど見られなくなった、手作業によるブドウ栽培にこだわるマルコ。湿度の問題が起きない畑では、当然カビの影響がほとんどないため、ボルドー液を必要としない環境が整うことに驚く。樹に全く負荷をかけない、自然環境と樹の自己管理力を尊重する栽培を心がけている。醸造は、彼の理想ともいえる日常を感じるワイン、幼い頃に見てきたサッスオーロの情景を尊重したワイン造り。不必要な介入を避け、冬場の寒さを利用してオリ引きするなど、あくまでも地元の手法にこだわるマルコ。ワインはどれも果実をそのまま感じつつも、決して飲み飽きない気軽さを持っています。経験の少なさを補うのに十分な環境と素材の良さ。将来性を感じる造り手です。
レッジョ エミリアの南にあるカステッララーノの町。当主のマルコ ベルトーニは2001年、町から離れた丘陵地に念願の土地を手に入れ、ゼロからのブドウ栽培を開始する。畑は標高250m、サッスオーロを含むこの当たりは強い粘土質を持ち、年間の降雨量が少なく非常に乾燥している、この辺りではほとんど見られなくなった、手作業によるブドウ栽培にこだわるマルコ。湿度の問題が起きない畑では、当然カビの影響がほとんどないため、ボルドー液を必要としない環境が整うことに驚く。樹に全く負荷をかけない、自然環境と樹の自己管理力を尊重する栽培を心がけている。醸造は、彼の理想ともいえる日常を感じるワイン、幼い頃に見てきたサッスオーロの情景を尊重したワイン造り。不必要な介入を避け、冬場の寒さを利用してオリ引きするなど、あくまでも地元の手法にこだわるマルコ。ワインはどれも果実をそのまま感じつつも、決して飲み飽きない気軽さを持っています。経験の少なさを補うのに十分な環境と素材の良さ。将来性を感じる造り手です。
 レッジョエミリアとモデナの中間、南側に位置するカステッララーノの町。全くゼロの状態からこのワイナリーをスタートさせたマルコ ベルトーニ、彼には決して譲れないこだわりと強い意志があった。 2000年、町はずれの丘陵地(Collina)、第二次大戦前にはブドウ畑が広がっていた土地でありながら、現在は放棄地とされている土地を手に入れたマルコ。標高250mの緩やかな斜面は、昼夜の寒暖差、そして強い粘土質、乾燥した風とまさに恵まれた環境が整っていた。元来ブドウ農家ではなかったマルコ、しかしながらサッスオーロの町で幼い頃から見てきたワイン造りに強い憧れを持ってきた。地域伝統のランブルスコ、そして彼が最も魅力を感じていた地酒ともいえるベスメイン(マルツェミーノの古い呼び名)、そしてスペルゴラ。2001年より、段階的に植樹を行い、現在8ha。黒ブドウはマルツェミーノ、カベルネ、ランブルスコ、グラスパロッサ。白ブドウはスペルゴラ、ソーヴィニヨンブラン、シャルドネを栽培。
レッジョエミリアとモデナの中間、南側に位置するカステッララーノの町。全くゼロの状態からこのワイナリーをスタートさせたマルコ ベルトーニ、彼には決して譲れないこだわりと強い意志があった。 2000年、町はずれの丘陵地(Collina)、第二次大戦前にはブドウ畑が広がっていた土地でありながら、現在は放棄地とされている土地を手に入れたマルコ。標高250mの緩やかな斜面は、昼夜の寒暖差、そして強い粘土質、乾燥した風とまさに恵まれた環境が整っていた。元来ブドウ農家ではなかったマルコ、しかしながらサッスオーロの町で幼い頃から見てきたワイン造りに強い憧れを持ってきた。地域伝統のランブルスコ、そして彼が最も魅力を感じていた地酒ともいえるベスメイン(マルツェミーノの古い呼び名)、そしてスペルゴラ。2001年より、段階的に植樹を行い、現在8ha。黒ブドウはマルツェミーノ、カベルネ、ランブルスコ、グラスパロッサ。白ブドウはスペルゴラ、ソーヴィニヨンブラン、シャルドネを栽培。
醸造においては、少なからず温度の管理はするものの、不必要な酵母添加を行わず、ごく最低限の亜硫酸を使用するのみ。
「ここ最近、ようやく品種として確立されたスペルゴラというブドウ、結実のまばらさと、粒の小ささ。そして最も特徴的ともいえる強い酸を持ったブドウ。」
梗の部分まで完熟させたスペルゴラは除梗せずにそのまま圧搾。果汁のみの状態で醗酵を行い熟成。2013年よりリリースされたフリッツァンテは、醗酵が終わったのちにボトル詰め。スペルゴラから造ったモストコット(煮詰めた果汁)を少量添加し瓶内二次醗酵を行う。その後スボッカトゥーラ(オリ抜き)せずにリリース。
マルツェミーノは屋外にある大型のセメントタンクにて約2週間のマセレーション(果皮浸漬)、野生酵母による醗酵を促す。圧搾後春まで、外気の寒さを利用してオリ引きを行う。使い古した木樽(500L)に移し12か月の熟成。酸が非常にデリケートで、栽培の難しいとされるマルツェミーノでありながら、驚くほど純粋で直観的な味わい。そして、すべてのワインに共通する骨太な酸と果実的な雰囲気。醸造的な未熟さを埋めるのに十分な素材のよさ。素晴らしい信念と情熱を持った造り手の一人。
実は・・相当以前に何本かテイスティングさせていただいてました。その時は・・
「ん~・・イマイチ・・ピンと来ないなぁ・・内向きで、ちょっとネガ背負ってる感じ・・」
だと判断してスルーしていました。
ですが最近、「イル・ファルネート」と言う言葉を聞くようになってきまして・・同じ埼玉のインポーターさんのエヴィーノさんのN社長さんに聞いてみると、随分と良くなったと・・言うことで、今回の入荷分をオーダーさせていただき、全アイテムをテイスティングさせていただきました。
「以前の暗さはどこへ?・・軽やかさのある外交的で垢抜けたナチュラルな味わい!」
で・・
「・・ありゃりゃ・・しばらく飲まない間に・・随分変わった?」
と、またNさんに聞いてみると、
「若い人が入ったので、その方の影響でしょう。すごく変わりました。」
とのこと。
まぁ、noisy も毎日のテイスティングで忙しいですが、やはり時折はチェックしていないと置いて行かれる・・そんな気になりました。
エミーリア=ロマーニャのワインらしく、快活で・・勿論、ガスが有ったり、適度な軽量感、しかし浅過ぎる感じも無くしっかりミネラリティも有って、非常にバランスの良いワインでした。そしてバルサミコも造っていまして、これがまたリーズナブルだけど結構な濃度も有り・・おいしいんですね。
ですので、
「クイクイ飲めるが薄辛くない・・バランス良く充実した味わいを楽しめるリーズナブルなイタリアン!」
です。是非飲んでみていただきたいと思います。お勧めです!
■エージェント情報
 レッジョ エミリアの南にあるカステッララーノの町。当主のマルコ ベルトーニは2001年、町から離れた丘陵地に念願の土地を手に入れ、ゼロからのブドウ栽培を開始する。畑は標高250m、サッスオーロを含むこの当たりは強い粘土質を持ち、年間の降雨量が少なく非常に乾燥している、この辺りではほとんど見られなくなった、手作業によるブドウ栽培にこだわるマルコ。湿度の問題が起きない畑では、当然カビの影響がほとんどないため、ボルドー液を必要としない環境が整うことに驚く。樹に全く負荷をかけない、自然環境と樹の自己管理力を尊重する栽培を心がけている。醸造は、彼の理想ともいえる日常を感じるワイン、幼い頃に見てきたサッスオーロの情景を尊重したワイン造り。不必要な介入を避け、冬場の寒さを利用してオリ引きするなど、あくまでも地元の手法にこだわるマルコ。ワインはどれも果実をそのまま感じつつも、決して飲み飽きない気軽さを持っています。経験の少なさを補うのに十分な環境と素材の良さ。将来性を感じる造り手です。
レッジョ エミリアの南にあるカステッララーノの町。当主のマルコ ベルトーニは2001年、町から離れた丘陵地に念願の土地を手に入れ、ゼロからのブドウ栽培を開始する。畑は標高250m、サッスオーロを含むこの当たりは強い粘土質を持ち、年間の降雨量が少なく非常に乾燥している、この辺りではほとんど見られなくなった、手作業によるブドウ栽培にこだわるマルコ。湿度の問題が起きない畑では、当然カビの影響がほとんどないため、ボルドー液を必要としない環境が整うことに驚く。樹に全く負荷をかけない、自然環境と樹の自己管理力を尊重する栽培を心がけている。醸造は、彼の理想ともいえる日常を感じるワイン、幼い頃に見てきたサッスオーロの情景を尊重したワイン造り。不必要な介入を避け、冬場の寒さを利用してオリ引きするなど、あくまでも地元の手法にこだわるマルコ。ワインはどれも果実をそのまま感じつつも、決して飲み飽きない気軽さを持っています。経験の少なさを補うのに十分な環境と素材の良さ。将来性を感じる造り手です。 レッジョエミリアとモデナの中間、南側に位置するカステッララーノの町。全くゼロの状態からこのワイナリーをスタートさせたマルコ ベルトーニ、彼には決して譲れないこだわりと強い意志があった。 2000年、町はずれの丘陵地(Collina)、第二次大戦前にはブドウ畑が広がっていた土地でありながら、現在は放棄地とされている土地を手に入れたマルコ。標高250mの緩やかな斜面は、昼夜の寒暖差、そして強い粘土質、乾燥した風とまさに恵まれた環境が整っていた。元来ブドウ農家ではなかったマルコ、しかしながらサッスオーロの町で幼い頃から見てきたワイン造りに強い憧れを持ってきた。地域伝統のランブルスコ、そして彼が最も魅力を感じていた地酒ともいえるベスメイン(マルツェミーノの古い呼び名)、そしてスペルゴラ。2001年より、段階的に植樹を行い、現在8ha。黒ブドウはマルツェミーノ、カベルネ、ランブルスコ、グラスパロッサ。白ブドウはスペルゴラ、ソーヴィニヨンブラン、シャルドネを栽培。
レッジョエミリアとモデナの中間、南側に位置するカステッララーノの町。全くゼロの状態からこのワイナリーをスタートさせたマルコ ベルトーニ、彼には決して譲れないこだわりと強い意志があった。 2000年、町はずれの丘陵地(Collina)、第二次大戦前にはブドウ畑が広がっていた土地でありながら、現在は放棄地とされている土地を手に入れたマルコ。標高250mの緩やかな斜面は、昼夜の寒暖差、そして強い粘土質、乾燥した風とまさに恵まれた環境が整っていた。元来ブドウ農家ではなかったマルコ、しかしながらサッスオーロの町で幼い頃から見てきたワイン造りに強い憧れを持ってきた。地域伝統のランブルスコ、そして彼が最も魅力を感じていた地酒ともいえるベスメイン(マルツェミーノの古い呼び名)、そしてスペルゴラ。2001年より、段階的に植樹を行い、現在8ha。黒ブドウはマルツェミーノ、カベルネ、ランブルスコ、グラスパロッサ。白ブドウはスペルゴラ、ソーヴィニヨンブラン、シャルドネを栽培。醸造においては、少なからず温度の管理はするものの、不必要な酵母添加を行わず、ごく最低限の亜硫酸を使用するのみ。
「ここ最近、ようやく品種として確立されたスペルゴラというブドウ、結実のまばらさと、粒の小ささ。そして最も特徴的ともいえる強い酸を持ったブドウ。」
梗の部分まで完熟させたスペルゴラは除梗せずにそのまま圧搾。果汁のみの状態で醗酵を行い熟成。2013年よりリリースされたフリッツァンテは、醗酵が終わったのちにボトル詰め。スペルゴラから造ったモストコット(煮詰めた果汁)を少量添加し瓶内二次醗酵を行う。その後スボッカトゥーラ(オリ抜き)せずにリリース。
マルツェミーノは屋外にある大型のセメントタンクにて約2週間のマセレーション(果皮浸漬)、野生酵母による醗酵を促す。圧搾後春まで、外気の寒さを利用してオリ引きを行う。使い古した木樽(500L)に移し12か月の熟成。酸が非常にデリケートで、栽培の難しいとされるマルツェミーノでありながら、驚くほど純粋で直観的な味わい。そして、すべてのワインに共通する骨太な酸と果実的な雰囲気。醸造的な未熟さを埋めるのに十分な素材のよさ。素晴らしい信念と情熱を持った造り手の一人。
●
2021 Frizant Rosso
フリザン・ロッソ
【「開栓前に瓶底に沈んだオリを戻してから抜栓して下さい」と有りますが、必ず吹いても大丈夫なようにして開けて下さいね!バランス良い軽さがクセになる味わいです!】
 良いですね~・・ロゼほどのエキス昇華感は無く、反対に生果実感が凄いのがこのロッソです。
良いですね~・・ロゼほどのエキス昇華感は無く、反対に生果実感が凄いのがこのロッソです。見てお判りのように・・まさにこの色の果実がそのまんま・・生感覚で味わえます。ラズベリー、ベリー、そしてむしろ葡萄・・(^^;; 何も足さない、何も引かない・・なんてウイスキーか何かの上出来な CF が有りましたが、
「生の果実のニュアンスが伝わって来るフリッザンテ!」
だとご紹介したいと思います。それも相当に出来が良い・・。
で、もっと生感覚を得られるんですよね・・。エージェントさんの情報には、
※開栓前に瓶底に沈んだオリを戻してから抜栓して下さい。
と有ります。
これをやりますと・・まさに澱も舞って、さらに「生感覚果実」を得られます。これも美味しい!
ですが、つまり・・
「ボトルをちょっと振って澱を舞わせて・・」
と言うことになりますから、何も考えず、「あ・・そうすか・・」と安易にやってしまうと部屋中に赤い染みを付けることになりますので注意が必要です。
 まず、キッチンに行き、自分以外の人を追い出すことから始めます。
まず、キッチンに行き、自分以外の人を追い出すことから始めます。そして、優しく少しだけ振って・・ボトルの下に有る澱を浮き立たせましょう。少し浮かんで来ればそれで大丈夫。
そうしたら、ボトルを斜め30~40度ほどに傾け、胃の辺りの肋骨くぼみにボトルの底を当て、栓抜きを当てて栓の部分をもう片方の手で上から抑え・・。
そして抑えたままゆっくりと王冠を抜きに掛かり、ガスが「シューッ」と言わなくなるまで抑え続けて下さい。その後ゆっくりボトルを起こしますが目を離さず、泡が上がって来ないようならサービス出来る場所まで行ってグラスに注ぎます。これでOKです。
ボトルを必要以上に無理に振らないように・・お願いします。
そうしましたら、この「センス抜群の造り手が造ったリーズナブルな発泡性ワイン」を楽しめる準備が完了です。安くておいしい!・・しかもこの滅茶暑い夏にぴったり!です。是非飲んでみて下さい。お勧めします!
●
2021 Frizant Rosato
フリザン・ロザート
【激旨です!ロゼ嫌い、泡嫌いは是非!・・享楽感をバッチリ得られます!・・有り得ないほどの美味しさを感じられます!】
 もう、細かいことはどうでも良いかと・・思ってしまうほど、滅茶心地良い飲み心地でして・・しかも探求しようと探しに出ると・・
もう、細かいことはどうでも良いかと・・思ってしまうほど、滅茶心地良い飲み心地でして・・しかも探求しようと探しに出ると・・「あらま・・ちゃんとあるじゃん・・」
と言う結果になってしまいまして、
「おいおい・・こんな2000円もしないワインにそんなに入り込んでどうすんのよ!」
と言う悪魔のささやきと、
「・・いや、だからこそ、しっかりポテンシャルを取りに行かなきゃならないんだ・・」
みたいな何とも締まらないニッチなワイン屋の義務感みたいなものが争うことになってしまう訳です。
しかもこの期に及んで定休日に長い文章を時間を掛けて書こうとしているなんて、ほとんど自虐的な人間のやることにしか思えなくなってきてしまいます。
ですが・・
「これ、本当に・・旨いです!」
 ロゼと言うより赤に近い・・。でも果皮が持つ美味しさだけで果皮の重さは無い・・ですね。それでいて、この適度なガスの存在が味わいをソフトに・・軽やかにしているんですが、その心地良さだけは変わらないにせよ、
ロゼと言うより赤に近い・・。でも果皮が持つ美味しさだけで果皮の重さは無い・・ですね。それでいて、この適度なガスの存在が味わいをソフトに・・軽やかにしているんですが、その心地良さだけは変わらないにせよ、「ワインとしての出来の良さが光る!」
んですよ。
やはりこれは・・造る人間のセンス!・・なんでしょう。以前・・noisy がスルーしていたイル・ファルネートのネガティヴさがワインを覆っている味わいは、もうどこにも有りません。
軽やかなのに実は充実・・でもやっていることは以前と変わらないのに、全く印象を異なるものにしている。
勿論、ヴィンテージの良さは有るのでしょうが、イル・ファルネート、一皮剥けた出来映えが、デイリーを席巻するような予感さえしてきました。是非とも!・・飲んでみて下さい。楽しい時間が待ってます!一推しです!
ポデーレ414
ポデーレ414
イタリア Podere 414 トスカーナ
● あ、そうだ・・忘れてたと、シモーネ・カステッリのポデーレ414の非常にリーズナブルなバディランチを仕入れさせていただきました。そこそこに美味しければと思っていたんですが、マストロヤンニにグラッタマッコですから・・
「もしかして?」
と期待を忍ばせてテイスティングさせていただきましたら・・
「・・げげっ・・以前の印象とまるっきり違う!」
とビックリしてしまいました。
ま~・・初めて入って来た時は、どちらかと言えばパキッとしてあっけらかんな味わいだったのに、
「とても千円台で買えるワインじゃない味筋!」
だったんですね。
これ幸いとばかりに上級キュヴェもオーダーさせていただいたのでぜひお楽しみにお待ちください。
「相当旨いです!」
-----
トスカーナは南部のマレンマの新規生産者をご紹介します。あのマストロヤンニ、グラッタマッコ・・懐かしいですね~・・覚えてますでしょうか・・かなり昔からのお客様は覚えていらっしゃるかもしれませんが、もう20年近く前に一生懸命ご紹介していた生産者ですが、そこのエノロゴをされていたカステッリさんの息子さんだそうで・・ちょっとだけセンチな気持ちになっています。
 《ポデーレ414》モレリーノ・ディ・スカンサーノが到着します。ヴィニタリー会場内で、サンジョヴェーゼを集中的にテイスティングしたなかでも、深く印象に残ったワインです。素晴らしくバランスのとれた上品な味わいで、活き活きとした味わいのなかに温かさを感じます。ヴィニタリー後にローマに出る道程で、日曜日でしたが思い切ってセラーを訪ねてみました。テニスから戻ったオーナー兼エノロゴのシモーネ・カステッリさんにセラーを案内していただき、幸運にも取引が決まりました。
《ポデーレ414》モレリーノ・ディ・スカンサーノが到着します。ヴィニタリー会場内で、サンジョヴェーゼを集中的にテイスティングしたなかでも、深く印象に残ったワインです。素晴らしくバランスのとれた上品な味わいで、活き活きとした味わいのなかに温かさを感じます。ヴィニタリー後にローマに出る道程で、日曜日でしたが思い切ってセラーを訪ねてみました。テニスから戻ったオーナー兼エノロゴのシモーネ・カステッリさんにセラーを案内していただき、幸運にも取引が決まりました。
《ポデーレ414》は、シモーネさんが1998年に創立したものですが、その父君は高名なエノロゴである、マウリツィオ・カステッリ(グラッタマッコ、マストロヤンニの醸造コンサルタント)です。マウリツィオはバートン・アンダーソン著『イタリア―味の原点を求めて』にしばしば登場するので、読者はご記憶のことでしょう。その父親から受け継いだワイン造りの叡智が、ここでは良い意味で発揮されています。ナチュラルをモットーにして、見事に美しく仕上げられた、魅力あふれるワインです。ちなみにワイナリー名にある〝414″は、1960年代に大農園の再分割がなされた時に、この農地につけられた区画番号だとか。モレリーノ・ディ・スカンサーノは、トスカーナの南部、グロセートの東南に位置するスカンサーノ地区で造られます。
 モレリーノはこの地域ではサンジョヴェーゼを意味しますが、キャンティと比べるとより柔らかくて軽やかで、たっぷりとした豊かな果実味があり、やや大柄で、上質なものは美しく熟成します。モレリーノという言葉は、ワインの色調に由来する、小さなサクランボを意味するという説と、かつて生活に欠かせなかった馬の繁殖(cavalli morelli)に由来するという両説があります。歴史的には、沼地が点在するマレンマに住む人たちが、厳しい夏をしのぐために、丘陵地のこのエリアに避暑にやってきて、ワインを造るようになったのが始まりです。
モレリーノはこの地域ではサンジョヴェーゼを意味しますが、キャンティと比べるとより柔らかくて軽やかで、たっぷりとした豊かな果実味があり、やや大柄で、上質なものは美しく熟成します。モレリーノという言葉は、ワインの色調に由来する、小さなサクランボを意味するという説と、かつて生活に欠かせなかった馬の繁殖(cavalli morelli)に由来するという両説があります。歴史的には、沼地が点在するマレンマに住む人たちが、厳しい夏をしのぐために、丘陵地のこのエリアに避暑にやってきて、ワインを造るようになったのが始まりです。
「もしかして?」
と期待を忍ばせてテイスティングさせていただきましたら・・
「・・げげっ・・以前の印象とまるっきり違う!」
とビックリしてしまいました。
ま~・・初めて入って来た時は、どちらかと言えばパキッとしてあっけらかんな味わいだったのに、
「とても千円台で買えるワインじゃない味筋!」
だったんですね。
これ幸いとばかりに上級キュヴェもオーダーさせていただいたのでぜひお楽しみにお待ちください。
「相当旨いです!」
-----
トスカーナは南部のマレンマの新規生産者をご紹介します。あのマストロヤンニ、グラッタマッコ・・懐かしいですね~・・覚えてますでしょうか・・かなり昔からのお客様は覚えていらっしゃるかもしれませんが、もう20年近く前に一生懸命ご紹介していた生産者ですが、そこのエノロゴをされていたカステッリさんの息子さんだそうで・・ちょっとだけセンチな気持ちになっています。
 《ポデーレ414》モレリーノ・ディ・スカンサーノが到着します。ヴィニタリー会場内で、サンジョヴェーゼを集中的にテイスティングしたなかでも、深く印象に残ったワインです。素晴らしくバランスのとれた上品な味わいで、活き活きとした味わいのなかに温かさを感じます。ヴィニタリー後にローマに出る道程で、日曜日でしたが思い切ってセラーを訪ねてみました。テニスから戻ったオーナー兼エノロゴのシモーネ・カステッリさんにセラーを案内していただき、幸運にも取引が決まりました。
《ポデーレ414》モレリーノ・ディ・スカンサーノが到着します。ヴィニタリー会場内で、サンジョヴェーゼを集中的にテイスティングしたなかでも、深く印象に残ったワインです。素晴らしくバランスのとれた上品な味わいで、活き活きとした味わいのなかに温かさを感じます。ヴィニタリー後にローマに出る道程で、日曜日でしたが思い切ってセラーを訪ねてみました。テニスから戻ったオーナー兼エノロゴのシモーネ・カステッリさんにセラーを案内していただき、幸運にも取引が決まりました。《ポデーレ414》は、シモーネさんが1998年に創立したものですが、その父君は高名なエノロゴである、マウリツィオ・カステッリ(グラッタマッコ、マストロヤンニの醸造コンサルタント)です。マウリツィオはバートン・アンダーソン著『イタリア―味の原点を求めて』にしばしば登場するので、読者はご記憶のことでしょう。その父親から受け継いだワイン造りの叡智が、ここでは良い意味で発揮されています。ナチュラルをモットーにして、見事に美しく仕上げられた、魅力あふれるワインです。ちなみにワイナリー名にある〝414″は、1960年代に大農園の再分割がなされた時に、この農地につけられた区画番号だとか。モレリーノ・ディ・スカンサーノは、トスカーナの南部、グロセートの東南に位置するスカンサーノ地区で造られます。
 モレリーノはこの地域ではサンジョヴェーゼを意味しますが、キャンティと比べるとより柔らかくて軽やかで、たっぷりとした豊かな果実味があり、やや大柄で、上質なものは美しく熟成します。モレリーノという言葉は、ワインの色調に由来する、小さなサクランボを意味するという説と、かつて生活に欠かせなかった馬の繁殖(cavalli morelli)に由来するという両説があります。歴史的には、沼地が点在するマレンマに住む人たちが、厳しい夏をしのぐために、丘陵地のこのエリアに避暑にやってきて、ワインを造るようになったのが始まりです。
モレリーノはこの地域ではサンジョヴェーゼを意味しますが、キャンティと比べるとより柔らかくて軽やかで、たっぷりとした豊かな果実味があり、やや大柄で、上質なものは美しく熟成します。モレリーノという言葉は、ワインの色調に由来する、小さなサクランボを意味するという説と、かつて生活に欠かせなかった馬の繁殖(cavalli morelli)に由来するという両説があります。歴史的には、沼地が点在するマレンマに住む人たちが、厳しい夏をしのぐために、丘陵地のこのエリアに避暑にやってきて、ワインを造るようになったのが始まりです。●
2021 Morellino di Scansano
モレッリーノ・ディ・スカンサーノ
【濡れてしっとり、深みのある赤黒果実にほんのりと官能感・・素晴らしいトスカーナワインです!・・ルカ・マローニは何と・・95ポイント!!】
 良いですね~・・この、何かちょっと湿ったようなテクスチュアと濡れたノーズは、新鮮な果実が良く熟していて、ちょっと冷えた朝露がしたたり落ちるような・・そんな情景を見せてくれます。
良いですね~・・この、何かちょっと湿ったようなテクスチュアと濡れたノーズは、新鮮な果実が良く熟していて、ちょっと冷えた朝露がしたたり落ちるような・・そんな情景を見せてくれます。ほんのりと熟したプラム、ベリーとチェリーの赤と黒っぽいのが混じって粘り、何とも艶っぽいノーズが僅かに含まれるんですね・・これは・・
「滅茶美味しい!・・価格もめっちゃ安い!」
と言えるんじゃないでしょうか!?。
で、余り期待しないで海外メディアの評価を探してみましたら・・
「なんと・・今やイタリアワイン評価の重鎮、ルカ・マローニさんが95ポイントも!!」
付けていたんですね・・
しかもですよ・・ルカ・マローニの評価は・・
「99ポイントが最高!」
で100点法じゃないんですね。
で、彼によりますと、92~99 ポイントのワインは、「滅多に出会うことの無いワイン」とのことなんですね~・・。
 まぁ・・滅茶美味しいんですが・・もし noisy が慣れた100点法で評価して、そこから1点引いたとしたら、95点は有り得るか?・・と聞かれますと・・
まぁ・・滅茶美味しいんですが・・もし noisy が慣れた100点法で評価して、そこから1点引いたとしたら、95点は有り得るか?・・と聞かれますと・・「・・・」
ん~・・辿り付くことは無いかな・・と・・(^^;;
じゃぁ・・その1点を引かないとしたら辿り着くか?・・と聞かれましたら・・
「・・ちょっと・・でも惜しい!」
実は激推しでお薦めしているんですが・・申し訳ありません・・根が正直ではあるんですが、少し捻くれてますんで・・はい・・。だからその位までは最高点では有り得ると感じます。
ただし、ルカ・マローニさんの評価はちょっと見方が違いまして、バランス重視だと思うんですね・・バランスと言っても色んなバランスが有りますから、99点満点で95 ポイントまで辿り着くことは有るのでしょう。因みにポデーレ414のバディランテ2022には、ルカ・マローニさんは93ポイントと、しっかり弾けています。ガンベロロッソも2ベッキエリ、ルカ・ガルディーニさんも92ポイントと、
「千円台のバディランテでさえ・・凄い評価!」
が出てました。今回、調べてみて・・ビックリしましたので、バディランテのページも少々更新しました。
基本的にドライで良く熟しているにも関わらずピュアさが有り、スモーキーさにほんのりと官能的なノーズと粘り感が混じり、ミッドパレットの適度な膨れと締まり、そのエッジも濡れてグラデュエーションを感じさせつつ、それまでの盛り上がり壊さない美しい余韻を持続します。
2024 ボージョレ・ヌーヴォー
2024 ボージョレ・ヌーヴォー
フランス 2024 Beaujolais Nouveau ブルゴーニュ
◆ 2024年11月21日(木)解禁日お届け!自然派ボージョレ・ヌーヴォーのご予約を承ります!
勿論、解禁日にお届け可能!ご検討くださいませ。
 今年もヌーヴォーの季節がやってきました。毎年楽しみにされていらっしゃるお客様が多くいらっしゃる Noisy wine のヌーヴォー・・いつもありがとうございます。今年も noisy的なセレクトで自然派の重鎮を中心に、お奨めをご紹介させていただきます。
今年もヌーヴォーの季節がやってきました。毎年楽しみにされていらっしゃるお客様が多くいらっしゃる Noisy wine のヌーヴォー・・いつもありがとうございます。今年も noisy的なセレクトで自然派の重鎮を中心に、お奨めをご紹介させていただきます。
昨今は世界情勢も有り、運賃もワインも高騰しています。そのためかワインファンにとっての唯一のイヴェント、秋の風物詩とも言える「ボージョレ・ヌーヴォー航空便」の入荷自体、もしくは製造自体が激減しています。
Noisy wine もワイングラスや熟成ヌーヴォーのプレゼントなどのキャンペーンを続けて来ましたが、もはや・・ワインが揃いません・・。時代なんでしょうね。
ですが、せっかくの「秋の風物詩」であるボージョレ・ヌーヴォー航空便で、解禁と共に華やかフルーティなヌーヴォーを、その年のブルゴーニュ南部の出来栄えを感じながら楽しむことが出来る訳ですから、何とか存続させたいと考えています。
2023年ものはNoisy wine のお薦めを4アイテム、厳選させていただきました。
そして、その中でも通常は船便のみの扱いになってしまった新井順子さんのヌーヴォーも、順子さん本人の働きかけで2023年ものは・・
「ジュンコ・アライ・ヌーヴォー航空便復活!」
が決まっています。
しかも・・
「なんと・・アンフォラ仕込み!に挑戦中!(写真がそのものズバリです)」
の連絡が入ってます!・・順子さんの新たなトライに期待しましょう!
他には仲田さんのルー・デュモン、ボージョレの自然派大御所のマルセル・ラピエールのシャトー・カンボン、そして今や高嶺の花どころじゃないルロワは、ボージョレ=ヴィラージュ・プリムールをご案内させていただきます。
今のところ、中々出来は良いようですよ・・。是非ともご検討くださいませ。
勿論、解禁日にお届け可能!ご検討くださいませ。
 今年もヌーヴォーの季節がやってきました。毎年楽しみにされていらっしゃるお客様が多くいらっしゃる Noisy wine のヌーヴォー・・いつもありがとうございます。今年も noisy的なセレクトで自然派の重鎮を中心に、お奨めをご紹介させていただきます。
今年もヌーヴォーの季節がやってきました。毎年楽しみにされていらっしゃるお客様が多くいらっしゃる Noisy wine のヌーヴォー・・いつもありがとうございます。今年も noisy的なセレクトで自然派の重鎮を中心に、お奨めをご紹介させていただきます。昨今は世界情勢も有り、運賃もワインも高騰しています。そのためかワインファンにとっての唯一のイヴェント、秋の風物詩とも言える「ボージョレ・ヌーヴォー航空便」の入荷自体、もしくは製造自体が激減しています。
Noisy wine もワイングラスや熟成ヌーヴォーのプレゼントなどのキャンペーンを続けて来ましたが、もはや・・ワインが揃いません・・。時代なんでしょうね。
ですが、せっかくの「秋の風物詩」であるボージョレ・ヌーヴォー航空便で、解禁と共に華やかフルーティなヌーヴォーを、その年のブルゴーニュ南部の出来栄えを感じながら楽しむことが出来る訳ですから、何とか存続させたいと考えています。
2023年ものはNoisy wine のお薦めを4アイテム、厳選させていただきました。
そして、その中でも通常は船便のみの扱いになってしまった新井順子さんのヌーヴォーも、順子さん本人の働きかけで2023年ものは・・
「ジュンコ・アライ・ヌーヴォー航空便復活!」
が決まっています。
しかも・・
「なんと・・アンフォラ仕込み!に挑戦中!(写真がそのものズバリです)」
の連絡が入ってます!・・順子さんの新たなトライに期待しましょう!
他には仲田さんのルー・デュモン、ボージョレの自然派大御所のマルセル・ラピエールのシャトー・カンボン、そして今や高嶺の花どころじゃないルロワは、ボージョレ=ヴィラージュ・プリムールをご案内させていただきます。
今のところ、中々出来は良いようですよ・・。是非ともご検討くださいませ。
●
2024 Beaujolais Nouveau Vieilles Vignes de Plus de Soixante-Dix Ans Lou Dumont by Air
ボージョレ・ヌーヴォー・ヴィエイユ・ヴィーニュ・ド・プリュス・ドゥ・ソワサント・ディザン ルー・デュモン 航空便
【期待できそうです!仲田さんの完熟葡萄のヌーヴォー、是非ご検討ください。】
 仲田さんから、ヌーヴォーの作柄についての最新レポートが届きましたので、下記に転載させていただきます。
仲田さんから、ヌーヴォーの作柄についての最新レポートが届きましたので、下記に転載させていただきます。7月は雷雨が数回発生し、南ボージョレの一部では雹害も見られました。気温が30度を超える日が多く、高温と湿気のためボージョレ全体でミルデューの被害が広がりました。
8月も雷雨が多く、また、日によって20度~30度と気温が目まぐるしく変わったため、不安な毎日が続きました。
ただ、今年は春から乾燥した気候が続き水不足気味でしたので、水不足が解消されたことは大きなメリットともなりました。また、私の区画は標高400メートルの高台斜面にあり年中強い風が吹いているため、ミルデューなども一切発生しませんでした。今日現在、ぶどうも葉も本当にきれいで素晴らしい状態です。
今年の収穫解禁日は9月1日で、今週末前後から一斉に収穫がはじまります。しかし私はぶどうを完璧に完熟させたいので、当初の予定日よりさらに10日ほど遅らせて、9月19日頃から収穫を開始するつもりです。
ここにきて好天が続いていますので、このまま収穫まで多雨に見舞われなければ、想定していた通りの素晴らしいヴィンテージになると思います。収獲が完了し醸造が一段落しましたら、またご報告申し上げます。
2023年8月29日
メゾン・ルー・デュモン
仲田晃司
●
2024 Beaujolais-Village Primeur Maison Leroy by Air Pre-Orders
ボージョレ=ヴィラージュ・プリムール メゾン・ルロワ 航空便
【熟成タイプ??焦らずに飲んで下さい..ん??】
しっかりしてますよねえ..ホント..。「ベストは数年後です..」等と笑えないジョークが出てきそうです。実際、リリース直後は固いことが多いです。MCじゃないんでしょうね..。一度は飲んでみてください。価格は..安いでしょ?毎年かなりの数量がしっかりと販売されていることからも、このワインの人気が判りますよね。まあ、ルロワと言えばDRCと並ぶ巨頭ですから、それも理解できますし、味わいに間違いは有りません。2021年はプライスが若干上がりましたが、出来うる限りリーズナブルになるように頑張って調整しましたので、是非飲んでみてくださいね。
 メゾンワインは、マダム・ルロワの厳しいテイスティングによるチェックの上で買い求めた良質のワインを、自社で熟成させ、出荷しているワインです。飲みごろを迎えるまでルロワ社のセラーで熟成させることで、深い味わいを追及したトラディショナルなスタイルのワインです。
メゾンワインは、マダム・ルロワの厳しいテイスティングによるチェックの上で買い求めた良質のワインを、自社で熟成させ、出荷しているワインです。飲みごろを迎えるまでルロワ社のセラーで熟成させることで、深い味わいを追及したトラディショナルなスタイルのワインです。
■マダム・ラルー・ビーズ・ルロワ
「類稀なテイスティング能力を持つ女性」
と称されるマダムはルロワ社のオーナーであり、且つ醸造家でもあります。自社畑の管理から醸造までを手がけ、妥協を許さない厳格な品質管理のもと、世界から注目されるワインを数多く生産しています。
 メゾンワインは、マダム・ルロワの厳しいテイスティングによるチェックの上で買い求めた良質のワインを、自社で熟成させ、出荷しているワインです。飲みごろを迎えるまでルロワ社のセラーで熟成させることで、深い味わいを追及したトラディショナルなスタイルのワインです。
メゾンワインは、マダム・ルロワの厳しいテイスティングによるチェックの上で買い求めた良質のワインを、自社で熟成させ、出荷しているワインです。飲みごろを迎えるまでルロワ社のセラーで熟成させることで、深い味わいを追及したトラディショナルなスタイルのワインです。■マダム・ラルー・ビーズ・ルロワ
「類稀なテイスティング能力を持つ女性」
と称されるマダムはルロワ社のオーナーであり、且つ醸造家でもあります。自社畑の管理から醸造までを手がけ、妥協を許さない厳格な品質管理のもと、世界から注目されるワインを数多く生産しています。
フラ・イ・モンティ
フラ・イ・モンティ
イタリア Fra I Monti ラッツィオ
● ラッツィオの新たな生産者をご紹介させていただきます。元ソムリエが生産者を目指して設立した「フラ・イ・モンティ」、ロッコさんです。
最近は飛ぶ鳥を落とす勢いの「ヴィヴィット」さんが輸入するビオ系(ビオロジック)な生産者です。ヴィヴィットさんの門前には、お取引を待つ方々の順番待ちが長~く・・出来ているそうです・・。・・判らなくもないですよ。魅力的なワインを次々に海外から持って来てくれていますから・・。「・・おっ!」と思わせてくれるようなワインに、良い確率で出会えているような感じがします。まぁ、何事も出会いから始まる訳で、ワイン屋にしても、自分で海外まで出かけて行って、お取引をお願いして、輸入の手配をして、代金を支払って・・なんてやっていたら、それは仕事と言えるようなものにはならず、ほぼほぼ道楽になってしまいますから・・。ヴィヴィットさんも品物は面白いんですが、あっという間に全数量を捌いてしまうのと、某社ほどでは無いにせよ、数本しか割り当てが無いリーズナブルなワイン・・・なんて言うのも混在します。
今回はそんな訳で、数本しか無いアイテムはテイスティングを回避させていただきましたが、それでも、
「ビオ系だがアヴァンギャルドに陥らず、健康的でセンスの良い味わい」
が魅力のワインでした。是非ご堪能くださいませ。

フラ・イ・モンティは、2018年設立されたローマの南東約75kmにある人口360人の小さな村Terelleテレッレに本拠を置くワイナリーです。もともとソムリエをしていたロッコは、ワインはセラーではなくブドウ畑で造られるという考えに立ち返り、テロワールを再発見することを目的として、長年見捨てられていた、栗の木立に囲まれた古いブドウ畑を復興させてワイナリーを創設しました。畑では化学薬品は一切使用せず、ビオディナミの手法を取り入れたビオロジックで栽培が行われています。フラ・イ・モンティの哲学は、現在の流行を追い求めることではなく、真にテロワールを表現するナチュラルワインを造ることです。それは、人工的な添加物は一切使わない、テロワールを100%語ってくれるピュアな本物のワイン、全ての人にとって手頃で飲みやすく、複雑さを備えた、喜びを与えてくれるワインです。
最近は飛ぶ鳥を落とす勢いの「ヴィヴィット」さんが輸入するビオ系(ビオロジック)な生産者です。ヴィヴィットさんの門前には、お取引を待つ方々の順番待ちが長~く・・出来ているそうです・・。・・判らなくもないですよ。魅力的なワインを次々に海外から持って来てくれていますから・・。「・・おっ!」と思わせてくれるようなワインに、良い確率で出会えているような感じがします。まぁ、何事も出会いから始まる訳で、ワイン屋にしても、自分で海外まで出かけて行って、お取引をお願いして、輸入の手配をして、代金を支払って・・なんてやっていたら、それは仕事と言えるようなものにはならず、ほぼほぼ道楽になってしまいますから・・。ヴィヴィットさんも品物は面白いんですが、あっという間に全数量を捌いてしまうのと、某社ほどでは無いにせよ、数本しか割り当てが無いリーズナブルなワイン・・・なんて言うのも混在します。
今回はそんな訳で、数本しか無いアイテムはテイスティングを回避させていただきましたが、それでも、
「ビオ系だがアヴァンギャルドに陥らず、健康的でセンスの良い味わい」
が魅力のワインでした。是非ご堪能くださいませ。

フラ・イ・モンティは、2018年設立されたローマの南東約75kmにある人口360人の小さな村Terelleテレッレに本拠を置くワイナリーです。もともとソムリエをしていたロッコは、ワインはセラーではなくブドウ畑で造られるという考えに立ち返り、テロワールを再発見することを目的として、長年見捨てられていた、栗の木立に囲まれた古いブドウ畑を復興させてワイナリーを創設しました。畑では化学薬品は一切使用せず、ビオディナミの手法を取り入れたビオロジックで栽培が行われています。フラ・イ・モンティの哲学は、現在の流行を追い求めることではなく、真にテロワールを表現するナチュラルワインを造ることです。それは、人工的な添加物は一切使わない、テロワールを100%語ってくれるピュアな本物のワイン、全ての人にとって手頃で飲みやすく、複雑さを備えた、喜びを与えてくれるワインです。
●
2022 Tinto di Rosso Roze
ティント・ディ・ロッソ・ロゼ
【オール・レディーズ・ドゥ・イット?・・正確な意味は知りませんが、何となく想像が付く・・(^^;; いや、知っているからって女性の前では決してそれを口にしないでくださいね・・何とメルロのフリッツァンテです!しかもサン・スフル!】
 意味深なエチケッタに見えました。
意味深なエチケッタに見えました。「・・ん?・・なんだこれ・・こんなジャケ買いみたいなの・・発注したっけ?」
と記憶に無かったんですが、しっかり入れていたのを確認しました。
赤いヒールでお尻出して何やってるのかな・・と、全く意味が分からなかったんですが、エージェントさんから資料をいただいてようやっと少し判り、ネットを検索して・・
「・・なるほど~!」
と理解出来ました。
因みにイー・ベイで・・この絵の元になった画像を発見しましたのでコピーペで是非ご覧ください。ご購入いただいても構いませんよ。
https://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_nkw=all+ladies+do+it+dvd+english&mkevt=1&mkcid=1&mkrid=710-53481-19255-0&campid=5338792814&toolid=10001
なるほど・・でしょう?・・
まぁ、余り上品ではないジョークだと思いますが、
「全てのご婦人はこのロゼを飲んでいるぜ」
と言いたいのでしょう。
 ふんわりとしたテクスチュアの弱発泡性の・・
ふんわりとしたテクスチュアの弱発泡性の・・「メルロのロゼ!・・しかも酸化防止剤無添加!」
です。
しかも・・
「ブドウ果汁での二次発酵をした本格派!」
です。シャンパーニュでもめったにそんなことはしないです。
ふんわりとベリーっぽいアロマが優しく香り、泡の細やかさも上々、・・まぁ、引けはやや早いですが、このまま栓をし続けると結構に溶け込んでいくかもしれません。
非常にドライで、酸のパレットも丸く、飲み心地も最高で、酔い覚めも・・良いですので・・
「気付いたら無くなっていた・・」
と言うことに気付くかもしれません。
あ・・それか・・?
「気付いたらいなくなっていた?」
と言うことを言いたい訳・・の「オール・レディーズ・ドゥ・イット」なのかもしれません。旨いです!飲んでみて下さい。少量です。
●
2021 Sempre in Due Bianco
センプレ・イン・ドゥエ・ビアンコ
【ラッツィオの絶滅寸前の地場品種、マトゥラーノを野生酵母のみでマセラシオン、アンフォラ仕込み、しかもSo2無添加でこの照りのある美しい色彩を実現した、活き活きとしたナチュールな白です!】
 中々このようなマセラシオン系の白で、ここまで活き活きとした色彩を見せるワインは無いんじゃないでしょうか。
中々このようなマセラシオン系の白で、ここまで活き活きとした色彩を見せるワインは無いんじゃないでしょうか。しかもフラ・イ・モンティは、
「So2を使わない」
ので・・半端無いです。
そしてアンフォラで育んで、葡萄以外の・・つまりは樽の要素を全く加えずに、
「自然な白ワインに仕上げた!」
と言えるワインです。
それに加えまして、このラッツィオの地場品種のマトゥーラと言う種なんですが、ほぼ絶滅しているそうで・・なので余計にフラ・イ・モンティはこのマトゥーラに力を注いでいるのでしょう。
マセラシオンした白ですが、お茶や紅茶、落ち葉と言ったニュアンスだけが主になりやすくなります。しかしこのワイン、ほんのり柑橘、結構に白・黄色・橙の果実を感じさせ、ボディ感として僅かなタンニンを赤ワインのように感じさせてくれます。
 ですので、So2をしっかり使用した白ワインの、
ですので、So2をしっかり使用した白ワインの、「美しい黄色を持った果実たっぷりに仕上げた・・実はほんのり甘いシャルドネ」
のような普通の白ワインと比較しますと、
「ある意味真逆」
です。それらは飲んだ後、少し・・酔います。飲み過ぎると・・かなり酔い、頭が痛くなるかもしれません。
しかし、So2を無添加、So2の生成も少ないこのマトゥラーノの、So2を転嫁したシャルドネのように甘く無い果実のニュアンスは、劇的に繊細なのに飲みごたえは充実、マリアージュも魚、肉、野菜を選ばず、非常に懐の深いところを見せてくれます。
同時にご案内の「イル・ビアンコ・ディ・チヴィタ」の方がより果実感は鮮明ですが、この・・ちょっとシミジミ感もあるマトゥラーノ100%のニュアンスを、フラ・イ・モンティは伝えたいのでしょう。
何とも心地良い・・ある意味、オレンジワインと言って良い白だと思います。ご検討いただけましたら幸いです。
以下は以前のレヴューです。
-----
【美味しそうなので手を掛けましたが・・止めました!・・地場品種マトゥラーノをマセラシオンしたキュヴェです!】
「あのさ~・・せめて12本無いとね・・飲めないんだよね・・何とかしてよ・・」
「・・あ、はい・・でも・・いや・・何とか・・調整してみますが・・」
と言うようなやりとりを毎回しています。ヴィヴィットさんは全ての入荷数をほぼほぼ一気に販売してしまいますので、「追加」と言う概念が無く、また数が無いアイテムは「バラ」が当然なので、このように数本しか入らないキュヴェが時折有るんですね。
まぁ、それでも案内をいただけるだけ有難い訳ですが、バラはねぇ・・困っちゃう訳ですね。でも今はワイン屋さんでも2~3本単位の発注が普通だそうですからね・・時代は変わったと言うか何と言うか・・老兵はただ去るのみなのでしょうね。でも、水前寺清子さんの「365歩のマーチ」のように・・いや、知らない人がほとんどでしょうが、
「1、2、1、2、1、2、1、2、休まないで歩け~♪」
そのまんまのデイリー価格な自然派ワインの発注なんて、noisy には一生できやしません。そんな感じならもう出来ないよと、何となく疎遠になってしまったインポーターさんもいらっしゃいますしね。
なので、このワインも飲めていません。しかしながら、 「ア・ラ・ヴォレ・ビアンコ 」の美味しさを見れば何となくは想像できます。こちらはマトゥーラのみでセミヨンは無しのマセラシオンタイプで、ガスはもしかしたら有るかもしれませんのでご注意くださいね。開け方は・・念のため書いておきましょうか。
注:吹き出し注意!
必ず零れても問題ない場所で抜栓してください。また照明に掛からないよう注意してくださいね。
開け方:
流し台などでボトルを斜め45度前後、中の液が王冠に掛からない程度に前方に傾け、王冠に栓抜きを宛て、栓抜きを持った手でその王冠を飛ばないように抑えながら、ゆっくりとガスを逃がしながら、音がしなくなるまで「耐えて」ください。
また音がしなくなっても、すぐには立てず、様子を見ながら・・泡がボトルの口を目指さないようになったら立ててください。個体差は有ると思いますが、思ったよりガス圧は高いかもしれません。
と言う訳でどうぞよろしくお願いいたします。
●
2021 Il Bianco di Civita
イル・ビアンコ・ディ・チヴィタ
【繊細な表情が何とも言えない絶滅危惧種マトゥラーノ80%に、フィアーノのふんわり感たっぷりな果実感を加えた、単独でも美味しいマセラシオン系、So2無添加、アンフォラ仕込みです!】
 ようやっと飲めました!・・まぁ・・こういうのは中々にライター泣かせですよね。何しろマトゥラーノが経験薄い訳ですし、
ようやっと飲めました!・・まぁ・・こういうのは中々にライター泣かせですよね。何しろマトゥラーノが経験薄い訳ですし、「しかもフィアーノを20%加えている」
「しかもSO2添加無しのマセラシオン系」
「しかもアンフォラ発酵で温度管理無し・・マロラクティックも自発的に起きる」
まぁ・・ナチュール系生産者さんの、どちらかと言えば、
「ギラギラと尖がった感じの造り」
に思えてしまいます。
ところが飲んでみますと、非常に優しい、心地良い飲み口でして、
「まったくアヴァンギャルドなところが見当たらない!」
と感じる訳ですから驚いてしまいます。
色彩も、まるで柑橘果実がそこに存在しているかのような、「生きた色」をしているような照りのあるものです。実際に柑橘果実、果実とも、マトゥラーノ100パーセントのキュヴェよりも伸び良く、多い感じがします。ミネラリティも縦延び系で、リアルな果実を感じさせる数少ないマセラシオン系白ワインです。これはめちゃお美味しい!
 名前がチヴィタなので・・
名前がチヴィタなので・・「ん?チビ太と言えば・・おそ松くん?」
noisy の年代ですと、串に刺したおでんを持った、何故か頭に1本しか毛が生えていない少年を思い出してしまうんですが、どうやらエチケッタに描かれているのは、
「フランチェスコの祖母の91歳になるお婆ちゃん、チヴィタさん」
だそうですが・・
「誰?・・フランチェスコって?」
この「フラ・イ・モンティ」は、ロッコ・トティとベネデット・レオーネの幼馴染同士で2018年に始めた・・そしてレオーネさんはご夫妻で絡んでいると海外のサイトで調べが済んでいます。インポーターさんの資料では「ロッコ」しか出て来ないので・・
「ん~・・判るように書いてくれないかな~」
と・・。
とにかく、誰かのお婆ちゃんのチヴィタさんに捧げるワインだそうです。出来はナチュールとしても、ワインとしても素晴らしいと思います。ご検討くださいませ。
以下は以前のレヴューです。
-----
【高貴種フィアーノを配したSO2無添加のアンフォラによるトップ・キュヴェ!・・これも飲みたかったです・・】
いや・・この「フラ・イ・モンティ」さんち、とても面白いですし、かなりのセンスをお持ちの様です。それに、結構義理堅い性格な感じがしていますが・・チヴィタとおっしゃるお婆ちゃんの白ワイン・・と言うお名前だそうです。
葡萄はフィアーノを使用していますので、ちょっと高級ですね。マトゥラーノ80%にフィアーノ20%で、破砕して1週間ちょっと漬け込みして圧搾(ここは大事かも)、そのあとアンフォラに入れるそうで、ちょっと手が込んでますね。
しかもSo2無しで生成残が22.4mgですから、相当ナチュラルです。是非期待して飲んでみて下さい。
こちらも一応・・多分大丈夫かとは思いますが・・
注:吹き出し注意!
必ず零れても問題ない場所で抜栓してください。また照明に掛からないよう注意してくださいね。
開け方:
流し台などでボトルを斜め45度前後、中の液が王冠に掛からない程度に前方に傾け、王冠に栓抜きを宛て、栓抜きを持った手でその王冠を飛ばないように抑えながら、ゆっくりとガスを逃がしながら、音がしなくなるまで「耐えて」ください。
また音がしなくなっても、すぐには立てず、様子を見ながら・・泡がボトルの口を目指さないようになったら立ててください。個体差は有ると思いますが、思ったよりガス圧は高いかもしれません。
と言う訳でどうぞよろしくお願いいたします。
●
2021 Sam Illon Vino Bianco
サム・イロン・ヴィノ・ビアンコ
【政治的?・・か思想的か、社会に疑問を投げかけているのか・・それにしても印象的なエチケッタですが、高貴種セミヨンを本家ソーテルヌよりも見事に仕上げていると言えるかもしれません!】
 セミヨンをアンフォラで仕上げた見事なビオの白ワインです。しかも、
セミヨンをアンフォラで仕上げた見事なビオの白ワインです。しかも、「So2無添加!」
です・・
「(・・有り得ね~~!)」
とソーテルヌ近郊の生産者さんは内心、驚いているに違い無いと思います。
だって・・ソーテルヌの美味しさは
「硫黄有りき」
で成り立っているようなものですから・・。このサム・イロンは甘く無い、ドライな仕上げではありますが、特に甘く仕上げる白ワインでSo2無しは、恐怖でしかないんじゃないかと思います。ドライで有っても、様々な菌・・それこそ貴腐菌をワインに生かそうと思ったら(貴腐葡萄では無く・・)どうなってしまうのか・・
ですがその前に、このエチケッタですね。このワインは「サム・イロン」と言う名前でして、フラ・イ・モンティのアシスタント・セラーマスターの移民の方をイメージした、
セミヨン-->セミ・ヨン-->サム・イロン
みたいな言葉遊びの命名だそうです。
フラ・イ・モンティのワイン造りも移民の方の力がなければ成り立たない・・と言うことらしいですし、他の多くのカンティーナも同様だそうです。
日本でも・・まぁ・・ただ居座っている不良外国人は別にしても、多くの海外労働者がいらっしゃらなければ、
「牛丼もうな丼も・・コンビニの卵サンドイッチも作れない」
と言う状況のようです。
昨年末から Noisy wine で再び働き始めた甥っ子の Oisy が10年ほど前に勤めていた時には、仕事を終えた Oisy が店の外で何か声を出しているので行ってみると、どう見ても外国人の方・・日本語も全くと言って良いほど判らない方でしたが、身振り手振り、片言の英語で話しを聞いてみるとどうやら、
「Noisy wine から少し行ったところにある工業団地で働いているが、休日なので浅草に出かけたところ、帰り道が判らなくなって寮に帰れない」
らしいと言うことなんですね。
Oisy に、
「・・どうする?」
と言ったところ、
「送って行ってあげたい」
と言うので、車で工業団地の中を走り回って、迷子の外国人の方の記憶に有りそうな場所を見つけました・・パン工場にお勤めの様でした。
 もう10年も前の話しですが、昨今は牛丼屋さんもコンビニエンスも・・うちの前の角X魚類の誘導員さんも外国の方が多いです。そもそも東京は外人さんでいっぱいです。
もう10年も前の話しですが、昨今は牛丼屋さんもコンビニエンスも・・うちの前の角X魚類の誘導員さんも外国の方が多いです。そもそも東京は外人さんでいっぱいです。日本では、職業訓練と言う名目で労働力を確保していたのを、ようやっと少しまともな方向に動いているようです。
フラ・イ・モンティも似た部分が有るのか、そしてそれを言いたいのか・・もっと進んで思想や政治に絡んで表現しているのかは不明ですが、
「仲良くやろうよ・・」
みたいなものかな・・とも感じます。
で、このセミヨンですが・・いや、物凄く良いです。セミヨンは・・ご存じないかもしれませんが、
「A.O.C.ボルドーの辛口白では高級品」
ですし、当然ながら村名のソーテルヌはさらに高級品で、主品種はセミヨンです。ソーヴィニヨン・ブランが入ることも有ります。
質感で言いますと、そんなソーテルヌの高級シャトーが造るドライなセミヨンよりもポテンシャルは高いかと・・さえ感じます。品格としますと少し不足するかもしれませんが、
「ナチュール・・ビオでSo2無し、そしてこの素晴らしい濃い目のゴールドの色彩」
から言っても、相当出来が良いのは伝わって来るかと思います。
蜜っぽいアロマとセミヨンの薄くソリッドなニュアンス、しかしアンフォラでのベクトル変換が済んでいる性でしょうか、ふんわりとして、訴えかけてくる表情がストレートです。非常に心地よい飲み口です。ドライですが甘やかなニュアンスが有り、余韻が非常に長いです。酸もしっかり有りますが、優しく滑らかです。樽は無いですね。
お茶とか紅茶とかも有りますが、果実のフレーヴァーも白、黄色、薄い赤まで非常に多様・・ちょっとこれは飲んでみるべきでは?・・と思います。
まぁ・・ちょっと絵面の捉え方も有るかと思いますが、ワインとしますと大成功だと思います。貴重なセミヨン、飲んでみてください。お薦めします。
●
2021 Una al Giorno Vino Rosso
ウナ・アル・ジョルノ・ヴィノ・ロッソ
【何と、メルロ100%のセンツァSo2!・・しかもラッツィオ・・「ほんまでっか?」】---以前のレヴューを使用しています。
 メルロ100%のSO2無添加、クラシカルに足踏み破砕・・(^^;; ん~・・やりたい放題では有りますが、仕上がったワインは非常にちゃんとしているのでビックリです。
メルロ100%のSO2無添加、クラシカルに足踏み破砕・・(^^;; ん~・・やりたい放題では有りますが、仕上がったワインは非常にちゃんとしているのでビックリです。しかも、noisy の場合、ほとんどのワインのテクニカルは目を通さずにテイスティングするので、出たところ勝負・・なんですが、
「・・げっ・・あれ、メルロだったの!?」
と、メルロの「メ」の字も出て来てませんでした。まぁ、そんなに大きく外すことは普段は余り無いんですけどね・・この味わいから、
「ん・・多分、地場品種かなぁ・・」
と決めて掛かっていたんでしょうね。何でも「鵜呑み」や「思い込み」はいかんですね。
言われてみればそう・・確かに重厚な重さも有る味わいでは有りました。しかしながら、一般的に想像しやすい、
「土っぽく、黒く、重厚・・もしくはテロワールや醸造法により軽やか」
みたいなメルロのイメージには、そのまんまは当てはまらなかったと思います。
結構に「赤い果実」がしっかり有り、ドライで、黒く無く、中域はたっぷりだが低域は大きくは出ていない感じで、中域に重みを置いた赤果実中心の味わいと思っていました。
飲み進めると、ほんのりとしたスパイシーな部分が解け始め、中域をさらにふくよかに、豊かにしてくれます。
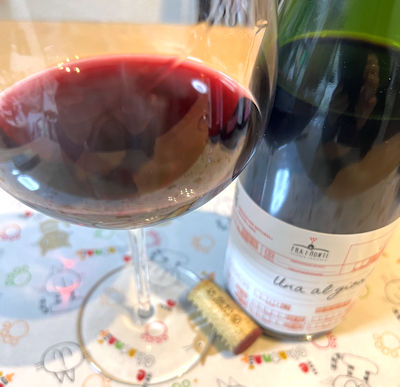 なるほど・・後になって思えば、湿った粘土では無くて、より乾いた土なテロワールなのかな?・・と思えます。ラッツィオの捨てられた畑は標高の高いところに有る場合が多いようなんですが、テクニカルを見る限りにおいては判りません。
なるほど・・後になって思えば、湿った粘土では無くて、より乾いた土なテロワールなのかな?・・と思えます。ラッツィオの捨てられた畑は標高の高いところに有る場合が多いようなんですが、テクニカルを見る限りにおいては判りません。フリーランジュースのみの優しい味わいになっていたことも、メルロを当てられなかった一因かもしれませんが、30分もすると確かにボディも膨らんで来て、赤果実が良い感じに熟れて来た感じがしました。
なるほど、これはラッツィオのメルロなんですね・・。コペルニクス的転回のカベルネと、むしろこちらもそう呼びたいメルロ・・どちらもSo2無添加の身体に優しい味わいです。是非飲んでみて下さい。お勧めします。結構に本格派です。
●
2021 Rivoluzione Cabernicana Vino Rosso
リヴォルジーネ・カベルニカーナ・ヴィノ・ロッソ
【カベルネの華やかな一面を表現!・・していますが、結構にしっかりしたがっちりな味わいも備わっているナチュラルワインです!So2無添加!】
 いや~・・はっちゃけたエチケッタですね~・・「コペルニクス的転回」をもじった命名・・と言うことで、その絵に描かれているのは、
いや~・・はっちゃけたエチケッタですね~・・「コペルニクス的転回」をもじった命名・・と言うことで、その絵に描かれているのは、「ニコラウス・コペルニクス」
その人であろうと思うんですね。
でも、どう見ても「KISS」の誰かか 「T. Rex」のマーク・ボランか・・noisy にはそんな風に見えてしまいます。
本人、カベルネの軽やかな面を表現しているので・・みたいな感じではいますが、そう・・確かに飲み始めは軽やかなカベルネのフラワリーな美味しさでクイクイ・・飲ませてくれます。メルロのように土っぽく無く、乾いた感じで重くない・・そして、「赤い果実・花」のニュアンスを感じさせてくれる美味しいワインです。
しかし・・こう言ってしまうと身も蓋も無くなってしまいますが・・地動説でも天動説でも良くなってしまう訳では有るにせよ、
「カベルネの乾いた重量感」
も、実はちゃんと存在しているんですね。
カベルネは、若いうちは結構に低い周波数の部分は無いですが、熟して行くうちに、中域から中低域が出て来ます。ただしメルロのようにドシっと重い、低周波は出ないと思うんですね。・・一般論では有ります。
彼は軽いと思っているのかもしれませんが、いやいや、決して軽いだけじゃないですよ。結構にしっかりしています。
乾いたカベルネのニュアンスが現状で目立つけれど、丁寧に造られたナチュラルな味わいが見事・・と言うべきでしょうか。So2 無添加でナチュラルですが、決してアヴァンギャルドでは無い・・noisy的にはぜひ見習って欲しい生産者が沢山います・・(^^
それでいて、これ・・かなりアヴァンギャルドなエチケッタで、さも・・
「エチケッタで売るワイン」
にしか見えないかもしれませんが、結構熟成も期待できるちゃんとしたワインですよ。
ですので、肉系のワイルドなお料理と一緒にさっさと飲むと言う手も有りますが、10年後を目指して貯蔵する・・と言うのも一興と思います。是非トライしてみてください、お勧めします!
ヴィノ・ルネサンサ
ヴィノ・ルネサンサ
スロヴェニア Vino Renesansa シュタイエルスカ
● なんと・・あのヴェロニク・ド・マクマオンのアントワーヌが、20年余の時を超えて復活しました!・・
「・・って・・誰だっけ?」
と言われてしまうに違い無いんですが・・それでも、Noisy wine の古いお客様は、
「・・えっ?・・あのマクマオンが?!」
と言っていただけると思うんですよね。
まぁ、今度この造り手さんを引っ張って来た、今やだれもが注目しているに違い無い「オルヴォー」さんですから・・。そりゃぁ・・黙って見逃す手は無いと思いません?
因みにオルヴォーさんは、マクマホンとおっしゃっていますが、noisy 的には「マクマオン」です。そもそもヴェロニク・ド・マクマオンとは言っても、その造り手自体は、
「アントワーヌ・ヴェルシェールさん」
です。
「・・・ん?・・ヴェルシェール?・・じゃぁ?」
そうなんですね・・あのローヌの「ジャブレ・ヴェルシェール」「ポール・ジャブレ・エネ」の血筋なんですね・・。マクマオンと言うのは姻族の血筋で、「ド」が付く・・伯爵家のご出身です。・・だから、ドメーヌ・ド・何とかと名乗りが有ったら「ド」は略さないでね・・と昔はHPでお願いしていました。
で、アントワーヌさんの写真も見つけたんですが、ちょっと使用権の問題が出そうなので今回はすみません。代わりに、2019年~2020年頃の・・
「・・みんなある意味、超驚いた・・味わいにも価格にも!」
と言う貴重な写真?を再度調整してアップさせていただきます。・・これです!・・さすがにもう持っていらっしゃる方はいないでしょうね・・。
 下の大きめの写真は、少量だけ残っていたムルソー・メイ=シャボーを再度取り直して再掲載した時の写真でしょう。昔は非常に小さな写真でやっていたんですよ・・ネットも創世記でしたから・・。
下の大きめの写真は、少量だけ残っていたムルソー・メイ=シャボーを再度取り直して再掲載した時の写真でしょう。昔は非常に小さな写真でやっていたんですよ・・ネットも創世記でしたから・・。
ま、ある意味・・ネットで写真付きでワインを販売しはじめたのは、決して・・X天さんじゃ有りませんで、noisy が初です。エライ苦労して・・出始めたばかりの映りの悪いデジカメを駆使して、騙し騙し小さな写真でやっていたのが1990年代後半です。このワインはその少し後になってから、ラシーヌさんが輸入したものでした。
まるでエネルギーの塊を口にしているようなワインでした。その頃、少し前から正体が判明しつつあった、
「自然派ワイン」
ですね。
まぁ・・ポール・ジャブレ、ジャブレ=ヴェルシェールですから・・その流れも有ったのかと・・今になっては理解出来ます。
そしてそのアントワーヌは5年ほどドメーヌを閉じてしまったんですが・・
「その原因がここに在った!」
そうです。
まさにエネルギーをミネラリティで包み込んだ素晴らしいリーズリングやケルナー、シャルドネ、ヴェルシュリースリングです!
あ・・因みに「ジャンシス・ロビンソンさん」の評点を掲載していますが、
「まったく同意できない評点」
でした。点の高低についてではなく、どのワインが白眉な仕上がりか・・と言う一点です。やはり価格も一番高い、
「2021 レンシュキ・リーズリング 」
は、頭一つ抜けています・・とんでもなく素晴らしい出来です!
他のキュヴェも素晴らしいですが、レンシュキには追い付かないのが事実です。なのでジャンシスさんの評点には惑わされないよう・・お願いいたします。彼女はワインにミネラルは内包していない・・などと言っていたので・・noisyは個人的にイマイチです。
安くないにせよ、高くないです。レンシュキ・リーズリングを今飲めば、どなたでも・・
「半端ない出来だ!・・素晴らしい!」
と言っていただけるでしょう。
その他のキュヴェは、比較しますと現時点では幾分判り辛いかもしれませんが、1996~2001年あたりのヴェロニク・ド・マクマオンのワインに親しまれた方なら全く問題なく、ご理解いただけるはずです。ぜひご検討くださいませ。お勧めします!(Noisy wine の登録としましては、1996年シャサーニュ=モンラッシェ・アビィ・ド・モルジョも有りました・・)
■ エージェント情報
ブルゴーニュのバブルとも言える狂乱の高騰が続く中、ブルゴーニュで研鑽を磨いた造り手たちが新天地を求めて旅立ちました。今やワインにおける国境すら感じさせない珠玉のワインを造り出しています。
ブルゴーニュ、オーセイ・デュレスの地で唯一無二の個性とも言えるワインを造り出していた Veronique de Mac Mahon(ヴェロニク・ド・マク=マホン)、わずか5年程度のリリースしかなかったためご存知の方は多くはないかと思います。
貴族の名門に生まれたアントワーヌ・ヴェルシェール氏は2000年にドメーヌを設立しましたが、2005年に家庭の事情で已む無く畑を手放すこととなりました。そして今、スロベニアの地で、現代的ブルゴーニュが失った個性を輝くように放つワインをリリースしました。
当時、長期の樽熟成に由来するエネルギーに満ちた個性は先端を走るどの造り手にも類似していなかったように記憶しています。
ルネサンサを試飲して、内に秘めた巨躯、圧倒的なダイナミズムと静謐さ、現代的な造りには無い樽香を纏うような荘厳な存在感に打ちのめされました。
2007年のワイナート誌で当時の主筆である田中克幸氏はヴェロニク・ド・マクマホンのワインについてこう書いています。
 『高い凝縮度と、うねりのあるエネルギー感と、芯の強いミネラルと、全体を貫く品位のレベルが違う。これが村名格付けとは信じがたい。やはりこれは造り手の個性だ』。
『高い凝縮度と、うねりのあるエネルギー感と、芯の強いミネラルと、全体を貫く品位のレベルが違う。これが村名格付けとは信じがたい。やはりこれは造り手の個性だ』。
ルネサンサの畑は既にビオロジック転換が始まっているとはいえこれがアントワーヌ氏による初ヴィンテージとは思えないほどの完成度です。力みのない凝縮感、精緻な構成ながら緊張感を強いない余韻。ブルゴーニュが高騰したと嘆く愛好家の方、それでもやっぱりブルゴーニュから離れられない僕のような方にはこの上ない朗報です。
入荷数量が非常に少ないため、限定での案内になってしまい申し訳ございません。未来に向けて是非ともお力添えをいただければ幸いです。
先述したワイナート誌には続きがあります。スロベニア、マリボルの地を見出すことを予見するようなことばでした。
アントワーヌ氏の才能を認める田中克幸氏に対して。
『それより僕はウィーンに住みたい。オーストリアに畑を買ってワインを造りたい。リースリングが好きだ。どの産地がいいだろう。姉ふたりの娘の教育にもウィーンがいいと思う……』。
ブルゴーニュにリースリングを植えたら?
そんな妄想に答えを出すようなワインを造ってくれました。どうぞよろしくお願い致します。
(村岡)
 ボーヌで醸造の勉強をし、イタリアのFranciacorta(フランチャコルタ)で6ヶ月間スタージュをしたAntoine Jaboulet-Vercherre(アントワーヌ・ジャブレ=ヴェルシェール)はブルゴーニュのオーセイ・デュレスで白ワイン(Meursault. Auxey-Duresses. Bourgogne Grand ordinaire. Bourgogne Aligoté)を造っていました。初ヴィンテージは2000 年でした。順調に経験を重ねてはいましたが、家族の事情で畑を売らなければならないことになり、ブルゴーニュでのワイン造りには終止符を打つこととなったのです。それから10年。パリの不動産業で働いていたアントワーヌは再びワインの世界に戻ることを決意しました。新しい機会を探していたアントワーヌはスロベニアを訪れ、その国の進歩に驚きました。
ボーヌで醸造の勉強をし、イタリアのFranciacorta(フランチャコルタ)で6ヶ月間スタージュをしたAntoine Jaboulet-Vercherre(アントワーヌ・ジャブレ=ヴェルシェール)はブルゴーニュのオーセイ・デュレスで白ワイン(Meursault. Auxey-Duresses. Bourgogne Grand ordinaire. Bourgogne Aligoté)を造っていました。初ヴィンテージは2000 年でした。順調に経験を重ねてはいましたが、家族の事情で畑を売らなければならないことになり、ブルゴーニュでのワイン造りには終止符を打つこととなったのです。それから10年。パリの不動産業で働いていたアントワーヌは再びワインの世界に戻ることを決意しました。新しい機会を探していたアントワーヌはスロベニアを訪れ、その国の進歩に驚きました。
20年前、アントワーヌはスロベニアに恋に落ちていました、そして白ワインに相応しい畑をこのMaribor(マリボル)に見出したのです。彼はパートナーとスロベニアでワイン畑を探し、ここでワインを造り住むことを決意しました。レンシュキ・リースリング(Renski Rizling). ラシュキ・リースリング(Laski Rizling)、シャルドネ、 ケルナー(Kerner)、彼の2.5 ヘクタールのブドウ畑はおよそ35年前に植樹された古木の畑です。コロナ渦の影響でスタートは遅くなってしまったが、2021 年には本格的に栽培を始めることが出来ました。ブルゴーニュでの経験同様、すぐにビオ栽培への変換を進めています。
栽培:2.5 ヘクタールの畑には4 品種植えています。去年の夏に追加で5 ヘクタールにブドウを植えることが許可され、今から2年間かけて進めていきたいと考えています。畑では化学肥料は一切使用せず、手摘み作業で収穫を行っています。畑には雑草を生やしています。醸造::手摘みで収穫したブドウは全房で空気圧搾機でプレス。その後タンクに入れ、軽いデブルバージュをしてから木樽に移します。バトナージュとルモンタージュを行う。温度調節あり、マロラクティック発酵あり。フィルター掛けをし、ワインのPH に応じてSO2わずかに添加します。
「・・って・・誰だっけ?」
と言われてしまうに違い無いんですが・・それでも、Noisy wine の古いお客様は、
「・・えっ?・・あのマクマオンが?!」
と言っていただけると思うんですよね。
まぁ、今度この造り手さんを引っ張って来た、今やだれもが注目しているに違い無い「オルヴォー」さんですから・・。そりゃぁ・・黙って見逃す手は無いと思いません?
因みにオルヴォーさんは、マクマホンとおっしゃっていますが、noisy 的には「マクマオン」です。そもそもヴェロニク・ド・マクマオンとは言っても、その造り手自体は、
「アントワーヌ・ヴェルシェールさん」
です。
「・・・ん?・・ヴェルシェール?・・じゃぁ?」
そうなんですね・・あのローヌの「ジャブレ・ヴェルシェール」「ポール・ジャブレ・エネ」の血筋なんですね・・。マクマオンと言うのは姻族の血筋で、「ド」が付く・・伯爵家のご出身です。・・だから、ドメーヌ・ド・何とかと名乗りが有ったら「ド」は略さないでね・・と昔はHPでお願いしていました。
で、アントワーヌさんの写真も見つけたんですが、ちょっと使用権の問題が出そうなので今回はすみません。代わりに、2019年~2020年頃の・・
「・・みんなある意味、超驚いた・・味わいにも価格にも!」
と言う貴重な写真?を再度調整してアップさせていただきます。・・これです!・・さすがにもう持っていらっしゃる方はいないでしょうね・・。
 下の大きめの写真は、少量だけ残っていたムルソー・メイ=シャボーを再度取り直して再掲載した時の写真でしょう。昔は非常に小さな写真でやっていたんですよ・・ネットも創世記でしたから・・。
下の大きめの写真は、少量だけ残っていたムルソー・メイ=シャボーを再度取り直して再掲載した時の写真でしょう。昔は非常に小さな写真でやっていたんですよ・・ネットも創世記でしたから・・。ま、ある意味・・ネットで写真付きでワインを販売しはじめたのは、決して・・X天さんじゃ有りませんで、noisy が初です。エライ苦労して・・出始めたばかりの映りの悪いデジカメを駆使して、騙し騙し小さな写真でやっていたのが1990年代後半です。このワインはその少し後になってから、ラシーヌさんが輸入したものでした。
まるでエネルギーの塊を口にしているようなワインでした。その頃、少し前から正体が判明しつつあった、
「自然派ワイン」
ですね。
まぁ・・ポール・ジャブレ、ジャブレ=ヴェルシェールですから・・その流れも有ったのかと・・今になっては理解出来ます。
そしてそのアントワーヌは5年ほどドメーヌを閉じてしまったんですが・・
「その原因がここに在った!」
そうです。
まさにエネルギーをミネラリティで包み込んだ素晴らしいリーズリングやケルナー、シャルドネ、ヴェルシュリースリングです!
あ・・因みに「ジャンシス・ロビンソンさん」の評点を掲載していますが、
「まったく同意できない評点」
でした。点の高低についてではなく、どのワインが白眉な仕上がりか・・と言う一点です。やはり価格も一番高い、
「2021 レンシュキ・リーズリング 」
は、頭一つ抜けています・・とんでもなく素晴らしい出来です!
他のキュヴェも素晴らしいですが、レンシュキには追い付かないのが事実です。なのでジャンシスさんの評点には惑わされないよう・・お願いいたします。彼女はワインにミネラルは内包していない・・などと言っていたので・・noisyは個人的にイマイチです。
安くないにせよ、高くないです。レンシュキ・リーズリングを今飲めば、どなたでも・・
「半端ない出来だ!・・素晴らしい!」
と言っていただけるでしょう。
その他のキュヴェは、比較しますと現時点では幾分判り辛いかもしれませんが、1996~2001年あたりのヴェロニク・ド・マクマオンのワインに親しまれた方なら全く問題なく、ご理解いただけるはずです。ぜひご検討くださいませ。お勧めします!(Noisy wine の登録としましては、1996年シャサーニュ=モンラッシェ・アビィ・ド・モルジョも有りました・・)
■ エージェント情報
ブルゴーニュのバブルとも言える狂乱の高騰が続く中、ブルゴーニュで研鑽を磨いた造り手たちが新天地を求めて旅立ちました。今やワインにおける国境すら感じさせない珠玉のワインを造り出しています。
ブルゴーニュ、オーセイ・デュレスの地で唯一無二の個性とも言えるワインを造り出していた Veronique de Mac Mahon(ヴェロニク・ド・マク=マホン)、わずか5年程度のリリースしかなかったためご存知の方は多くはないかと思います。
貴族の名門に生まれたアントワーヌ・ヴェルシェール氏は2000年にドメーヌを設立しましたが、2005年に家庭の事情で已む無く畑を手放すこととなりました。そして今、スロベニアの地で、現代的ブルゴーニュが失った個性を輝くように放つワインをリリースしました。
当時、長期の樽熟成に由来するエネルギーに満ちた個性は先端を走るどの造り手にも類似していなかったように記憶しています。
ルネサンサを試飲して、内に秘めた巨躯、圧倒的なダイナミズムと静謐さ、現代的な造りには無い樽香を纏うような荘厳な存在感に打ちのめされました。
2007年のワイナート誌で当時の主筆である田中克幸氏はヴェロニク・ド・マクマホンのワインについてこう書いています。
 『高い凝縮度と、うねりのあるエネルギー感と、芯の強いミネラルと、全体を貫く品位のレベルが違う。これが村名格付けとは信じがたい。やはりこれは造り手の個性だ』。
『高い凝縮度と、うねりのあるエネルギー感と、芯の強いミネラルと、全体を貫く品位のレベルが違う。これが村名格付けとは信じがたい。やはりこれは造り手の個性だ』。ルネサンサの畑は既にビオロジック転換が始まっているとはいえこれがアントワーヌ氏による初ヴィンテージとは思えないほどの完成度です。力みのない凝縮感、精緻な構成ながら緊張感を強いない余韻。ブルゴーニュが高騰したと嘆く愛好家の方、それでもやっぱりブルゴーニュから離れられない僕のような方にはこの上ない朗報です。
入荷数量が非常に少ないため、限定での案内になってしまい申し訳ございません。未来に向けて是非ともお力添えをいただければ幸いです。
先述したワイナート誌には続きがあります。スロベニア、マリボルの地を見出すことを予見するようなことばでした。
アントワーヌ氏の才能を認める田中克幸氏に対して。
『それより僕はウィーンに住みたい。オーストリアに畑を買ってワインを造りたい。リースリングが好きだ。どの産地がいいだろう。姉ふたりの娘の教育にもウィーンがいいと思う……』。
ブルゴーニュにリースリングを植えたら?
そんな妄想に答えを出すようなワインを造ってくれました。どうぞよろしくお願い致します。
(村岡)
 ボーヌで醸造の勉強をし、イタリアのFranciacorta(フランチャコルタ)で6ヶ月間スタージュをしたAntoine Jaboulet-Vercherre(アントワーヌ・ジャブレ=ヴェルシェール)はブルゴーニュのオーセイ・デュレスで白ワイン(Meursault. Auxey-Duresses. Bourgogne Grand ordinaire. Bourgogne Aligoté)を造っていました。初ヴィンテージは2000 年でした。順調に経験を重ねてはいましたが、家族の事情で畑を売らなければならないことになり、ブルゴーニュでのワイン造りには終止符を打つこととなったのです。それから10年。パリの不動産業で働いていたアントワーヌは再びワインの世界に戻ることを決意しました。新しい機会を探していたアントワーヌはスロベニアを訪れ、その国の進歩に驚きました。
ボーヌで醸造の勉強をし、イタリアのFranciacorta(フランチャコルタ)で6ヶ月間スタージュをしたAntoine Jaboulet-Vercherre(アントワーヌ・ジャブレ=ヴェルシェール)はブルゴーニュのオーセイ・デュレスで白ワイン(Meursault. Auxey-Duresses. Bourgogne Grand ordinaire. Bourgogne Aligoté)を造っていました。初ヴィンテージは2000 年でした。順調に経験を重ねてはいましたが、家族の事情で畑を売らなければならないことになり、ブルゴーニュでのワイン造りには終止符を打つこととなったのです。それから10年。パリの不動産業で働いていたアントワーヌは再びワインの世界に戻ることを決意しました。新しい機会を探していたアントワーヌはスロベニアを訪れ、その国の進歩に驚きました。20年前、アントワーヌはスロベニアに恋に落ちていました、そして白ワインに相応しい畑をこのMaribor(マリボル)に見出したのです。彼はパートナーとスロベニアでワイン畑を探し、ここでワインを造り住むことを決意しました。レンシュキ・リースリング(Renski Rizling). ラシュキ・リースリング(Laski Rizling)、シャルドネ、 ケルナー(Kerner)、彼の2.5 ヘクタールのブドウ畑はおよそ35年前に植樹された古木の畑です。コロナ渦の影響でスタートは遅くなってしまったが、2021 年には本格的に栽培を始めることが出来ました。ブルゴーニュでの経験同様、すぐにビオ栽培への変換を進めています。
栽培:2.5 ヘクタールの畑には4 品種植えています。去年の夏に追加で5 ヘクタールにブドウを植えることが許可され、今から2年間かけて進めていきたいと考えています。畑では化学肥料は一切使用せず、手摘み作業で収穫を行っています。畑には雑草を生やしています。醸造::手摘みで収穫したブドウは全房で空気圧搾機でプレス。その後タンクに入れ、軽いデブルバージュをしてから木樽に移します。バトナージュとルモンタージュを行う。温度調節あり、マロラクティック発酵あり。フィルター掛けをし、ワインのPH に応じてSO2わずかに添加します。
●
2021 Kerner Z.G.P. Stajerska
ケルナー Z.G.P.シュタイエルスカ
【この地域では一般的な白の品種です。エレガントで縦延び系・・やがて横へも拡がって、エレガントさと相反するようなエナジー溢れる味わいに!】
 そもそも・・今さらですが、誰も言わないので一応・・
そもそも・・今さらですが、誰も言わないので一応・・スロヴェニアはイタリア北部の東に接する国です。スロヴェニアの北はオーストリアです。そのスロヴェニアの東に接するのがハンガリーですね。
その昔はオーストリアとハンガリーが強かった時代、ドイツが強かった時代も有り、この辺りを制していた国はコロコロ変わっているはずです。イタリアもそうですからね・・。
で、noisy も教職課程をもし、ちゃんと受けていれば・・社会(位しかできない)の先生の目も有ったのでしょうが、授業に出ない(出られない?)ことが多かったので・・ならずにいます。が、ここは歴史は・・飛ばして・・
そして、スロヴェニアでもハンガリーに近い方ですね・・そこに、シュタイエルスカ地方が有ります。そこの有力な町(村?)がマーリボルです。
「めっちゃ美しい!」
街並みが川のそばに有るんですよね・・。そして、
「山と川、町がせめぎ合っている」
感じです。
その斜面に・・この畑は存在します。上の造り手のコラムに、
「冬の写真と夏の写真・・」
をドメーヌのHPからいただいて来ました。スキーをやるにはちょうど急~中斜面かと思いますが、
「葡萄を育てるのは凄い大変!」
に感じます。
スロヴェニアではどうか知りませんが、ドイツでは急斜面を落ちて毎年亡くなる方が出るそうです。ユベール・ラミーのところも斜面が急で大変だと言ってます。
 このケルナーは比較的に多産で熟度を高く出来、しかも早熟な方なので、このスロヴェニアやオーストリア辺りでは沢山造られています。
このケルナーは比較的に多産で熟度を高く出来、しかも早熟な方なので、このスロヴェニアやオーストリア辺りでは沢山造られています。ですがルネサンサでは、多く造ると言うよりも質を高くして凝縮した葡萄を造っているのが判ります。
「涙も太く、黄色はやや薄目で透明感がとても強い」
でしょう?
ん・・そう言う味わいなんですね・・面白いですよね・・そのまんまです。
透明・半透明のミネラリティが膨大にある、縦延び系の味わいです。柑橘はしっかりありますが、リースリングが親のクセに・・余りリースリングっぽくない・・(^^;;
むしろもう・・
「ケルナーっぽい!」
と言い切りたい感じです。結構飲む機会も増えましたよね・・ケルナー。
縦に伸びて行く棒状、もしくは円柱を想像していただけると判りやすいかと思います。若いうちはそのニュアンスが強く、やがてそれが横に膨らみを持ってくる感じです。ちょっと蜜っぽさも有り、これも徐々に増えて行くかと想像しています。
白眉の「2021 レンシュキ・リーズリング・シュタイエルスカ」には及びませんが、それでもこの「縦延び系」は他の3アイテムには無い個性です。素晴らしい出来・・是非、アントワーヌの思い描く白ワインの世界を覗いてみてください。お勧めします!
●
2021 Laski Rizling Z.G.P. Stajerska
ラシュキ・リーズリング Z.G.P.シュタイエルスカ
【まるで関係無いのに、どこか似ている・・と言う・・ヴェルシュ・リースリング!・・マクマオン的な棒状エナジーに似非リースリング的柑橘がとてもエレガントです!】
 まぁ・・noisy 的にはとても懐かしい造り手です。苦労はしたよなぁ・・と思います。
まぁ・・noisy 的にはとても懐かしい造り手です。苦労はしたよなぁ・・と思います。なにせ・・
「・・えっ?ブルゴーニュ・グランドルディネールが・・いくらだって?」
と聞き返したくらいです。その場面は覚えています。エライ・・高かったので、
「そんなの・・売れないよ・・」
と・・確か泰子さんに言ったような気がします・・W君だったかな?
で結局オーセ=デュレッスとムルソー類を扱ったんじゃなかったかなあ・・と思い出します。
結局ですが、オーセやムルソーを飲んで・・
「ここまでワインの中にエナジーを閉じ込められる造り手がいたんだ!」
と驚いたんですね。高いのも仕方が無いのかと・・。
で、その頃は・・おそらくですが、「新樽(225L)」を2~3割使用していたかと思います。そして熟成も長かったので、それなりに・・
「樽っぽかった」
です。
その樽っぽさがほどけて来ると、実に良い感じになってくるんですよね・・。ですが、
「ルネサンサは樽っぽさはほぼ無い」
ですのでお間違いの無きよう。
 で、他のコラムでもご紹介させていただいた、2002~2004年の間位かと思いますが、noisy が書いたコラムを見つけました。こちらは、オーセ=デュレッス・ブラン2001年です。
で、他のコラムでもご紹介させていただいた、2002~2004年の間位かと思いますが、noisy が書いたコラムを見つけました。こちらは、オーセ=デュレッス・ブラン2001年です。『 2001 オーセ=デュレッス・ブラン
【彼のワインでは最も楽天的な性格のワインです。 】
ヴェロニック・ド・マク・マオンのワインを知るので有れば、このワインが最も判りやすいと思います。「古典的」という難しい言葉の意味合い、樽の使い方の絶妙さ、葡萄の健全さを理解するに違い有りません。そしてきっと..3 Ans Fut も飲みたくなるんでしょうね。
「すくっ」と背筋が伸びた風情で石灰系ミネラルが香り、やや黄色く色づいた小さめの果実、そしてその皮、ナッツ類..。口中でやや粘り、実はリッチさがこんなに有るんだよと呟く..。ミネラルと果実の気配を残しながら、まったりと続く余韻。とても質の高い味わいです。(良くある「さらっ」とした爽やかなオーセ=デュレッスでは有りません。この当たりの表現は、ややもすると勘違いされやすいものになってしまいますが、あくまで、ド・マク・マオンのワインの中での比較である、と考えてください。)
いや、とても旨いシャルドネです。やや固めの印象が有りますが、飲んでいる内に少しずつ解けてくるでしょう。1~2年の間に熟成し、その後3~5年間美味しく飲めるでしょう。是非とも飲んでみてください。』
ここから・・ですね、ナッツっぽい感じのニュアンスを除き、高質リースリング的なあの・・何とも心地良いシトラスっぽさ・・でしょうか。そんな果実やドライフルーツ、ハーブのニュアンスを足してゆくと、
「この2021年ラシュキ・リーズリングに近くなる」
と言うようなイメージなんですね。
いや・・2021年ものですからちょうど20年ほどですよ・・良かった・・まだ覚えていて・・物凄い昔のようで、つい、この間のようです。
20年前だとしますと2004年ですよね?・・ようやっとネットショッピングが認知され始めた頃です。2000年ころに某モールの楽Ⅹさんがオープンし、雨後の筍みたいに、物凄い勢いで色々なモールが出来ました。
でも Noisy wine は「うちの方がネット開設は早い」とばかりに単独店のまま頑張りました。まだ大企業さんもHPはまともには無かったですし、
「インターネット不要論」
なんて・・ね~・・。インターネットは危ないからやらないようにしよう・・なんて動きが有ったんですね。
我々がそんな苦労をしている頃、
「アントワーヌはリースリングに魅せられて、たまたま訪れたスロヴェニアに恋してた」
訳で、20年掛けて造ったのがこの「ルネサンサ」な訳です。
マクマオン的な膨大なエナジーを詰め込んだ見事な味わいです。少しだけ早いですが、それでも美味しく頂けると思います。ご検討くださいませ。
桝田酒造店
桝田酒造店
日本 Masudasyuzouten 富山
● 2024年1月1日の能登半島地震で被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。
また半島だけで無く、近郊でも多くの被害が出たと聞きます。何かできないかと・・考えますが中々・・。酒を扱う店はやはりお酒を販売させていただいて協力させていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
能登半島の北の付け根、富山は東岩瀬に有る枡田酒造店さんをご紹介します。銘柄は満寿泉(ますいずみ
)。日本を代表する銘酒です。
美味求眞
美味しいものを食べている人しか美味しい酒は造れない。私共は美味求眞はもう一つのモットーと考えます。富山という地は海の幸、山の幸にふんだんに恵まれ、当然舌が肥えます。
日本酒も新鮮な素材を活かす事が求められます。
立山連峰からの膨大な雪解水が富山湾に注ぎ込み、富山ならではの甘海老やシロエビ、寒ブリ、バイ貝、ホタルイカ、ズワイガニが育ちます。あじ、さより、きすなどの小魚の種類の多いこと。深い雪の下から芽吹く
山の精気を蓄えた山菜の数々はまさに精神的な薬膳です。自然の味が濃く凝縮した素材には、流行りの淡麗辛口は役不足。綺麗であるが味のしっかりした旨い満寿泉はこうして磨かれています。
また半島だけで無く、近郊でも多くの被害が出たと聞きます。何かできないかと・・考えますが中々・・。酒を扱う店はやはりお酒を販売させていただいて協力させていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
能登半島の北の付け根、富山は東岩瀬に有る枡田酒造店さんをご紹介します。銘柄は満寿泉(ますいずみ
)。日本を代表する銘酒です。
美味求眞
美味しいものを食べている人しか美味しい酒は造れない。私共は美味求眞はもう一つのモットーと考えます。富山という地は海の幸、山の幸にふんだんに恵まれ、当然舌が肥えます。
日本酒も新鮮な素材を活かす事が求められます。
立山連峰からの膨大な雪解水が富山湾に注ぎ込み、富山ならではの甘海老やシロエビ、寒ブリ、バイ貝、ホタルイカ、ズワイガニが育ちます。あじ、さより、きすなどの小魚の種類の多いこと。深い雪の下から芽吹く
山の精気を蓄えた山菜の数々はまさに精神的な薬膳です。自然の味が濃く凝縮した素材には、流行りの淡麗辛口は役不足。綺麗であるが味のしっかりした旨い満寿泉はこうして磨かれています。
●
N.V. Masuizumi Genteidaiginjou Gift Box
満寿泉 限定大吟醸 化粧箱入
【吟醸の満寿泉。香り、コク、キレと3拍子揃った地酒です。】
 左の写真は「限定大吟醸」です。黒い化粧箱に入っています。輝き、照りの有る綺麗な色をしていますね。香りも自然で穏やか、適度な膨らみと余韻、そこからの切れの有る味わいが素晴らしいです。
左の写真は「限定大吟醸」です。黒い化粧箱に入っています。輝き、照りの有る綺麗な色をしていますね。香りも自然で穏やか、適度な膨らみと余韻、そこからの切れの有る味わいが素晴らしいです。今のロットはやや若めで僅かな渋みが有りますが、いずれ消えて行きます。熟成が大事なんですね。ワインと同じです。
日本酒の話しになりますと、noisy は「製造年月日」の話しを良くしますが、何とかのひとつ覚えみたいに、
「日付の新しいのが良い」
とおっしゃる方が多いです。
まぁ、地酒ファンの方は、比較的人の話をちゃんと聞かない・・と言うか、自身の考えを押し通したい方が多いように・・すみません・・見受けられます。
それが正しいものなら良いんですが、間違って覚えてしまったものを訂正したくない、それが正しいと相手にも強制したがる・・と言うか、まぁ、地酒の世界の方は、造り手も売り手も飲み手もその傾向が強いかな・・と感じています。
ちゃんと保存した日本酒は、まぁ、細かいことを言いますと例外も有りますが、ワインと同様に長い命を持っています。出来立ての日本酒はまだ・・赤ちゃんなんですね。ワインで言うところのヌーボーやプリムールです。これが日本酒の全てだ・・と言われてしまいますと・・そうは言わないにせよ製造年月日の新しい奴をください・・と言うのはそれと同じです・・
「(・・判ってない・・)」
と感じてしまいます。
満寿泉の枡田社長さんとは旧知の間柄でして、いや、noisy がそう思っているだけでしょうが、その昔は色々と教えていただきました。でも noisy よりも全然お若いですよ。noisy のように汚いナリはしておらず、いつも綺麗です。
先日はたまたまテレビを観て居たら、北陸新幹線の開業で富山駅の様子を映していまして、その中にシッカリ!・・枡田社長の細身で長身のお姿が有りました。懐かしいなぁ・・と思うと同時に、頑張ってるんだなぁ・・そんな場面には必ずいらっしゃるよなぁ・・と・・感激しました。
蔵にも訪問させていただいたことが有り、海の近くの立派な蔵で、しかも昔は富山駅からかなり離れている(おそらく6~7キロ)にも関わらず、他人の土地を歩かずに蔵まで来れた・・と聞き、ビックリしたものです。
そんな若社長に連れられて、ワインのオークションに参加させていただいたことも有ります。実際にアメリカン・クラブに行き、ハンマープライスを経験しました。
まぁ、前以って入札はしておいたのですが、何か落とせたのか、何も落とせなかったのか・・覚えていませんが、ワインの勉強を始めてしばらく経っていた頃では有りますが、
「ワインの世界は・・地酒の世界とはちょっと違うなぁ・・」
と、その自由さにワクワクしたものです。
神谷町の交差点近くに有る(有った?)シガーバーに連れて行ってもらったのもその頃です。若社長はワインだけじゃなくて葉巻にも凝っていて・・タバコは吸わないんですけどね・・その吸い方とか、高級ワインとシガーのマリアージュとか、実際に色々と試させていただき、驚くことばかりでした。
「シャトー・マルゴーのxx年ものと、キューバのxxの何年ものがどうのこうの・・」
マルゴーが判ってもシガーが判りませんから、若社長の言うことを丸飲みするしかないですよね・・。それで、シガーの口を切り、温め、火を付け、1~2時間、ワインやブランデーと共に楽しむ・・・と言うような、ブルジョワな世界を教えていただきました。
その頃若社長は、フランスからシャルドネの使用樽をコンテナ一杯に仕入れて来て、それに純米大吟醸や純米吟醸を詰めて熟成させ、ワインボトルに入れたり、本来は蒸米を使うべきところに麹米を使用し、「全麹仕込み」を完成させたりと、大活躍でした。
使用済バリックはドメーヌ・ラモネから・・その風味を閉じ込めたのが「シャルドネ樽仕込」ですし、「全麹仕込」は、まるでソーテルヌのような甘~いニュアンスを日本酒で実現したものです。
実行力も有りますが、何より企画力、その原動力となるのは「尽きない興味」なんだろうと・・凄いなぁと感心したものです。
あらら・・ご紹介する満寿泉のお酒の話しじゃなくなっちゃいましたね。すみません。
限定大吟醸は、そんな訳で「非常にドライ」「穏やかな吟醸香(上立香)」「滑らか」な、大吟醸の見本のような大吟醸酒です。
純米大吟醸は枡田さんの看板とも言えるアイテムです。兵庫県産山田錦、9号系酵母、精米歩合50%と言うテクニカルですが、磨きに磨いて35%までに落とすとか、あるいはそれ以上に磨く・・などの過剰とも思えるような精米歩合による香りで勝負するのではなく、
「あくまで食を考えた酒」
が枡田さんの意図する酒です。
日本海の豊かな漁場からの恵みに合わないような過剰な吟醸香や、線の細過ぎる味わいは目指すところでは無い・・と言うことでしょう。ある種、「完璧な日本酒」と言うことになるかと思います。いずれ写真も撮って掲載したいと思っています。
特別大吟醸「寿」は、枡田さんの目指す最高の酒をイメージし、実現している日本酒です。毎年仕入れられるお米の出来や量も有りますんで、実際に伺った時は、
「必ずしも35%とか40%とかの精米でやると決めている訳では無く、実際には仕込みにより色々」
とのことで、沢山の小さい仕込みのタンクが並んでいるのにはビックリしました。
因みに、例えば大吟醸の造りなら、限定大吟醸と特別大吟醸 寿 は同じ「大吟醸」で、どこが違うの?・・と言うような疑問も有るかもしれませんね。
「それは飲めば判る」
ものです。
やはり蔵のトップのお酒は、蔵元さんがトップと認めた酒になります。使用米も精米歩合も違いますし、粕歩合と言いまして、元のお米をどれだけお酒したか・・と言う指標が有ります。これが全然違って来てしまうんですね。同じようにやっても、全然違う場合も有ります。
名杜氏、能登四天王である三盃幸一さんが醸す銘酒です。勿論、ワインと同様に飲み頃も有りますし、保存の仕方も有ります。ワインセラーでは温度は高過ぎます。保存は冷蔵庫の冷蔵室で大丈夫です。まぁ、その前に無くなってしまうと思いますが、20年経ったら・・滅茶苦茶旨いですよ。ご検討くださいませ。
●
N.V. Masuizumi Junmaidaiginjou Gift Box
満寿泉 純米大吟醸 化粧箱入
【吟醸の満寿泉。香り、コク、キレと3拍子揃った地酒です。】
 左の写真は「限定大吟醸」です。黒い化粧箱に入っています。輝き、照りの有る綺麗な色をしていますね。香りも自然で穏やか、適度な膨らみと余韻、そこからの切れの有る味わいが素晴らしいです。
左の写真は「限定大吟醸」です。黒い化粧箱に入っています。輝き、照りの有る綺麗な色をしていますね。香りも自然で穏やか、適度な膨らみと余韻、そこからの切れの有る味わいが素晴らしいです。今のロットはやや若めで僅かな渋みが有りますが、いずれ消えて行きます。熟成が大事なんですね。ワインと同じです。
日本酒の話しになりますと、noisy は「製造年月日」の話しを良くしますが、何とかのひとつ覚えみたいに、
「日付の新しいのが良い」
とおっしゃる方が多いです。
まぁ、地酒ファンの方は、比較的人の話をちゃんと聞かない・・と言うか、自身の考えを押し通したい方が多いように・・すみません・・見受けられます。
それが正しいものなら良いんですが、間違って覚えてしまったものを訂正したくない、それが正しいと相手にも強制したがる・・と言うか、まぁ、地酒の世界の方は、造り手も売り手も飲み手もその傾向が強いかな・・と感じています。
ちゃんと保存した日本酒は、まぁ、細かいことを言いますと例外も有りますが、ワインと同様に長い命を持っています。出来立ての日本酒はまだ・・赤ちゃんなんですね。ワインで言うところのヌーボーやプリムールです。これが日本酒の全てだ・・と言われてしまいますと・・そうは言わないにせよ製造年月日の新しい奴をください・・と言うのはそれと同じです・・
「(・・判ってない・・)」
と感じてしまいます。
満寿泉の枡田社長さんとは旧知の間柄でして、いや、noisy がそう思っているだけでしょうが、その昔は色々と教えていただきました。でも noisy よりも全然お若いですよ。noisy のように汚いナリはしておらず、いつも綺麗です。
先日はたまたまテレビを観て居たら、北陸新幹線の開業で富山駅の様子を映していまして、その中にシッカリ!・・枡田社長の細身で長身のお姿が有りました。懐かしいなぁ・・と思うと同時に、頑張ってるんだなぁ・・そんな場面には必ずいらっしゃるよなぁ・・と・・感激しました。
蔵にも訪問させていただいたことが有り、海の近くの立派な蔵で、しかも昔は富山駅からかなり離れている(おそらく6~7キロ)にも関わらず、他人の土地を歩かずに蔵まで来れた・・と聞き、ビックリしたものです。
そんな若社長に連れられて、ワインのオークションに参加させていただいたことも有ります。実際にアメリカン・クラブに行き、ハンマープライスを経験しました。
まぁ、前以って入札はしておいたのですが、何か落とせたのか、何も落とせなかったのか・・覚えていませんが、ワインの勉強を始めてしばらく経っていた頃では有りますが、
「ワインの世界は・・地酒の世界とはちょっと違うなぁ・・」
と、その自由さにワクワクしたものです。
神谷町の交差点近くに有る(有った?)シガーバーに連れて行ってもらったのもその頃です。若社長はワインだけじゃなくて葉巻にも凝っていて・・タバコは吸わないんですけどね・・その吸い方とか、高級ワインとシガーのマリアージュとか、実際に色々と試させていただき、驚くことばかりでした。
「シャトー・マルゴーのxx年ものと、キューバのxxの何年ものがどうのこうの・・」
マルゴーが判ってもシガーが判りませんから、若社長の言うことを丸飲みするしかないですよね・・。それで、シガーの口を切り、温め、火を付け、1~2時間、ワインやブランデーと共に楽しむ・・・と言うような、ブルジョワな世界を教えていただきました。
その頃若社長は、フランスからシャルドネの使用樽をコンテナ一杯に仕入れて来て、それに純米大吟醸や純米吟醸を詰めて熟成させ、ワインボトルに入れたり、本来は蒸米を使うべきところに麹米を使用し、「全麹仕込み」を完成させたりと、大活躍でした。
使用済バリックはドメーヌ・ラモネから・・その風味を閉じ込めたのが「シャルドネ樽仕込」ですし、「全麹仕込」は、まるでソーテルヌのような甘~いニュアンスを日本酒で実現したものです。
実行力も有りますが、何より企画力、その原動力となるのは「尽きない興味」なんだろうと・・凄いなぁと感心したものです。
あらら・・ご紹介する満寿泉のお酒の話しじゃなくなっちゃいましたね。すみません。
限定大吟醸は、そんな訳で「非常にドライ」「穏やかな吟醸香(上立香)」「滑らか」な、大吟醸の見本のような大吟醸酒です。
純米大吟醸は枡田さんの看板とも言えるアイテムです。兵庫県産山田錦、9号系酵母、精米歩合50%と言うテクニカルですが、磨きに磨いて35%までに落とすとか、あるいはそれ以上に磨く・・などの過剰とも思えるような精米歩合による香りで勝負するのではなく、
「あくまで食を考えた酒」
が枡田さんの意図する酒です。
日本海の豊かな漁場からの恵みに合わないような過剰な吟醸香や、線の細過ぎる味わいは目指すところでは無い・・と言うことでしょう。ある種、「完璧な日本酒」と言うことになるかと思います。いずれ写真も撮って掲載したいと思っています。
特別大吟醸「寿」は、枡田さんの目指す最高の酒をイメージし、実現している日本酒です。毎年仕入れられるお米の出来や量も有りますんで、実際に伺った時は、
「必ずしも35%とか40%とかの精米でやると決めている訳では無く、実際には仕込みにより色々」
とのことで、沢山の小さい仕込みのタンクが並んでいるのにはビックリしました。
因みに、例えば大吟醸の造りなら、限定大吟醸と特別大吟醸 寿 は同じ「大吟醸」で、どこが違うの?・・と言うような疑問も有るかもしれませんね。
「それは飲めば判る」
ものです。
やはり蔵のトップのお酒は、蔵元さんがトップと認めた酒になります。使用米も精米歩合も違いますし、粕歩合と言いまして、元のお米をどれだけお酒したか・・と言う指標が有ります。これが全然違って来てしまうんですね。同じようにやっても、全然違う場合も有ります。
名杜氏、能登四天王である三盃幸一さんが醸す銘酒です。勿論、ワインと同様に飲み頃も有りますし、保存の仕方も有ります。ワインセラーでは温度は高過ぎます。保存は冷蔵庫の冷蔵室で大丈夫です。まぁ、その前に無くなってしまうと思いますが、20年経ったら・・滅茶苦茶旨いですよ。ご検討くださいませ。
●
N.V. Masuizumi Tokubetudaiginjou Kotobuki Gift Box
満寿泉 特別大吟醸 寿 化粧箱入
【吟醸の満寿泉。香り、コク、キレと3拍子揃った地酒です。】
 左の写真は「限定大吟醸」です。黒い化粧箱に入っています。輝き、照りの有る綺麗な色をしていますね。香りも自然で穏やか、適度な膨らみと余韻、そこからの切れの有る味わいが素晴らしいです。
左の写真は「限定大吟醸」です。黒い化粧箱に入っています。輝き、照りの有る綺麗な色をしていますね。香りも自然で穏やか、適度な膨らみと余韻、そこからの切れの有る味わいが素晴らしいです。今のロットはやや若めで僅かな渋みが有りますが、いずれ消えて行きます。熟成が大事なんですね。ワインと同じです。
日本酒の話しになりますと、noisy は「製造年月日」の話しを良くしますが、何とかのひとつ覚えみたいに、
「日付の新しいのが良い」
とおっしゃる方が多いです。
まぁ、地酒ファンの方は、比較的人の話をちゃんと聞かない・・と言うか、自身の考えを押し通したい方が多いように・・すみません・・見受けられます。
それが正しいものなら良いんですが、間違って覚えてしまったものを訂正したくない、それが正しいと相手にも強制したがる・・と言うか、まぁ、地酒の世界の方は、造り手も売り手も飲み手もその傾向が強いかな・・と感じています。
ちゃんと保存した日本酒は、まぁ、細かいことを言いますと例外も有りますが、ワインと同様に長い命を持っています。出来立ての日本酒はまだ・・赤ちゃんなんですね。ワインで言うところのヌーボーやプリムールです。これが日本酒の全てだ・・と言われてしまいますと・・そうは言わないにせよ製造年月日の新しい奴をください・・と言うのはそれと同じです・・
「(・・判ってない・・)」
と感じてしまいます。
満寿泉の枡田社長さんとは旧知の間柄でして、いや、noisy がそう思っているだけでしょうが、その昔は色々と教えていただきました。でも noisy よりも全然お若いですよ。noisy のように汚いナリはしておらず、いつも綺麗です。
先日はたまたまテレビを観て居たら、北陸新幹線の開業で富山駅の様子を映していまして、その中にシッカリ!・・枡田社長の細身で長身のお姿が有りました。懐かしいなぁ・・と思うと同時に、頑張ってるんだなぁ・・そんな場面には必ずいらっしゃるよなぁ・・と・・感激しました。
蔵にも訪問させていただいたことが有り、海の近くの立派な蔵で、しかも昔は富山駅からかなり離れている(おそらく6~7キロ)にも関わらず、他人の土地を歩かずに蔵まで来れた・・と聞き、ビックリしたものです。
そんな若社長に連れられて、ワインのオークションに参加させていただいたことも有ります。実際にアメリカン・クラブに行き、ハンマープライスを経験しました。
まぁ、前以って入札はしておいたのですが、何か落とせたのか、何も落とせなかったのか・・覚えていませんが、ワインの勉強を始めてしばらく経っていた頃では有りますが、
「ワインの世界は・・地酒の世界とはちょっと違うなぁ・・」
と、その自由さにワクワクしたものです。
神谷町の交差点近くに有る(有った?)シガーバーに連れて行ってもらったのもその頃です。若社長はワインだけじゃなくて葉巻にも凝っていて・・タバコは吸わないんですけどね・・その吸い方とか、高級ワインとシガーのマリアージュとか、実際に色々と試させていただき、驚くことばかりでした。
「シャトー・マルゴーのxx年ものと、キューバのxxの何年ものがどうのこうの・・」
マルゴーが判ってもシガーが判りませんから、若社長の言うことを丸飲みするしかないですよね・・。それで、シガーの口を切り、温め、火を付け、1~2時間、ワインやブランデーと共に楽しむ・・・と言うような、ブルジョワな世界を教えていただきました。
その頃若社長は、フランスからシャルドネの使用樽をコンテナ一杯に仕入れて来て、それに純米大吟醸や純米吟醸を詰めて熟成させ、ワインボトルに入れたり、本来は蒸米を使うべきところに麹米を使用し、「全麹仕込み」を完成させたりと、大活躍でした。
使用済バリックはドメーヌ・ラモネから・・その風味を閉じ込めたのが「シャルドネ樽仕込」ですし、「全麹仕込」は、まるでソーテルヌのような甘~いニュアンスを日本酒で実現したものです。
実行力も有りますが、何より企画力、その原動力となるのは「尽きない興味」なんだろうと・・凄いなぁと感心したものです。
あらら・・ご紹介する満寿泉のお酒の話しじゃなくなっちゃいましたね。すみません。
限定大吟醸は、そんな訳で「非常にドライ」「穏やかな吟醸香(上立香)」「滑らか」な、大吟醸の見本のような大吟醸酒です。
純米大吟醸は枡田さんの看板とも言えるアイテムです。兵庫県産山田錦、9号系酵母、精米歩合50%と言うテクニカルですが、磨きに磨いて35%までに落とすとか、あるいはそれ以上に磨く・・などの過剰とも思えるような精米歩合による香りで勝負するのではなく、
「あくまで食を考えた酒」
が枡田さんの意図する酒です。
日本海の豊かな漁場からの恵みに合わないような過剰な吟醸香や、線の細過ぎる味わいは目指すところでは無い・・と言うことでしょう。ある種、「完璧な日本酒」と言うことになるかと思います。いずれ写真も撮って掲載したいと思っています。
特別大吟醸「寿」は、枡田さんの目指す最高の酒をイメージし、実現している日本酒です。毎年仕入れられるお米の出来や量も有りますんで、実際に伺った時は、
「必ずしも35%とか40%とかの精米でやると決めている訳では無く、実際には仕込みにより色々」
とのことで、沢山の小さい仕込みのタンクが並んでいるのにはビックリしました。
因みに、例えば大吟醸の造りなら、限定大吟醸と特別大吟醸 寿 は同じ「大吟醸」で、どこが違うの?・・と言うような疑問も有るかもしれませんね。
「それは飲めば判る」
ものです。
やはり蔵のトップのお酒は、蔵元さんがトップと認めた酒になります。使用米も精米歩合も違いますし、粕歩合と言いまして、元のお米をどれだけお酒したか・・と言う指標が有ります。これが全然違って来てしまうんですね。同じようにやっても、全然違う場合も有ります。
名杜氏、能登四天王である三盃幸一さんが醸す銘酒です。勿論、ワインと同様に飲み頃も有りますし、保存の仕方も有ります。ワインセラーでは温度は高過ぎます。保存は冷蔵庫の冷蔵室で大丈夫です。まぁ、その前に無くなってしまうと思いますが、20年経ったら・・滅茶苦茶旨いですよ。ご検討くださいませ。
ラ・トッレ・アッレ・トルフェ
ラ・トッレ・アッレ・トルフェ
イタリア La Torre alle Tolfe トスカーナ
● ポルタ・ディ・ヴェルティーネで活躍したジャコモ・マストレッタさんがキャンティで醸造家として造り始めたラ・トッレ・アッレ・トルフェをご紹介します。オーナーはマニア・カステッリさん。最初の年から・・全開ですね。相当に美味しいです。

ワイナリーは敷地からもカンポ広場の鐘楼が見える、シエナからも近いトルフェ村にある。
ワイナリー【ラ・トッレ・アッレ・トルフェ(La Torre alle Tolfe)】は、8世紀に建てられた塔(Torre)を住居やオリーブ畑、ブドウ畑が囲む、大きな農園とも小さな集落ともいえるヴィッラ(貴族の郊外の別宅)だった。ヴィッラは、現オーナーであるマニア・カステッリの曽祖父に買い取られて、現在に至る。ワイン生産を稼業としてきたわけではなかったが、マニアの祖父は特にワイン造りに凝っていたそうで、13haのブドウ畑から少量だけ、自家消費用のワインを造っていた。彼女自身は2015年、レ・トルフェへと戻ってくるまではイギリスに住んでいた。現在シエナ大学に籍を置く夫のマークは、自然保護の活動に長年携わっており、子供たちを含め一家でレ・トルフェへと移り住んだ。
いっぽうジャコモはこの数年、ワイン造りをするべくワイナリーを探していた。ブルネッロやキアンティ・クラッシコのワイナリーからも話はあったようだが、中~長期間働いてみたいと思えるワイナリーはなかなかなかった。10年以上も心血を注いできた、ラ・ポルタ・ディ・ヴェルティーネが閉業してからというもの、コンサルタントでもなんでも、深くワイン造りにかかわりたいと思えるようなワイナリーは簡単には見つからない。
そんな時、当時ラ・トッレ・アッレ・トルフェで雇われていた醸造家の友人から、自分の後任にどうかという申し出を受けた。実際に訪れると、2003年からバイオロジック栽培に取り組んできたという、状態の良い畑。1900年代にヴィッラに増築されたセラーは、使い込まれたセメントタンクを中心にしたシンプルな醸造施設。マニアとマーク夫妻は、二人とも地域の歴史に関心が深く、二人の自然を尊重しようと努めるヴィッラ運営の姿勢にもジャコモは共感を持った。
コッリ・セネージのワインには、ガイオーレのように力強いタンニンと黒い果実味の印象がなく、柔らかなタンニンと、赤く明るい果実味が特徴的。そこにジャコモのワインらしい、酸味と垂直性をつよく感じる。
ジャコモがワイナリーにやってきたのは、2018年の収穫の少し前だとかで、さらに深くワイナリーとかかわっていくこれからのヴィンテージが楽しみだ。
今回は、ロザートとキアンティ・コッリ・セネージ、チリエジョーロ、カナイオーロの4キュヴェが入荷。ロザートとキアンティはほぼセメントタンク熟成だけれど、チリエジョーロとカナイオーロの2つは木樽熟成をしており、明瞭な骨格が特徴的。

ワイナリーは敷地からもカンポ広場の鐘楼が見える、シエナからも近いトルフェ村にある。
ワイナリー【ラ・トッレ・アッレ・トルフェ(La Torre alle Tolfe)】は、8世紀に建てられた塔(Torre)を住居やオリーブ畑、ブドウ畑が囲む、大きな農園とも小さな集落ともいえるヴィッラ(貴族の郊外の別宅)だった。ヴィッラは、現オーナーであるマニア・カステッリの曽祖父に買い取られて、現在に至る。ワイン生産を稼業としてきたわけではなかったが、マニアの祖父は特にワイン造りに凝っていたそうで、13haのブドウ畑から少量だけ、自家消費用のワインを造っていた。彼女自身は2015年、レ・トルフェへと戻ってくるまではイギリスに住んでいた。現在シエナ大学に籍を置く夫のマークは、自然保護の活動に長年携わっており、子供たちを含め一家でレ・トルフェへと移り住んだ。
いっぽうジャコモはこの数年、ワイン造りをするべくワイナリーを探していた。ブルネッロやキアンティ・クラッシコのワイナリーからも話はあったようだが、中~長期間働いてみたいと思えるワイナリーはなかなかなかった。10年以上も心血を注いできた、ラ・ポルタ・ディ・ヴェルティーネが閉業してからというもの、コンサルタントでもなんでも、深くワイン造りにかかわりたいと思えるようなワイナリーは簡単には見つからない。
そんな時、当時ラ・トッレ・アッレ・トルフェで雇われていた醸造家の友人から、自分の後任にどうかという申し出を受けた。実際に訪れると、2003年からバイオロジック栽培に取り組んできたという、状態の良い畑。1900年代にヴィッラに増築されたセラーは、使い込まれたセメントタンクを中心にしたシンプルな醸造施設。マニアとマーク夫妻は、二人とも地域の歴史に関心が深く、二人の自然を尊重しようと努めるヴィッラ運営の姿勢にもジャコモは共感を持った。
コッリ・セネージのワインには、ガイオーレのように力強いタンニンと黒い果実味の印象がなく、柔らかなタンニンと、赤く明るい果実味が特徴的。そこにジャコモのワインらしい、酸味と垂直性をつよく感じる。
ジャコモがワイナリーにやってきたのは、2018年の収穫の少し前だとかで、さらに深くワイナリーとかかわっていくこれからのヴィンテージが楽しみだ。
今回は、ロザートとキアンティ・コッリ・セネージ、チリエジョーロ、カナイオーロの4キュヴェが入荷。ロザートとキアンティはほぼセメントタンク熟成だけれど、チリエジョーロとカナイオーロの2つは木樽熟成をしており、明瞭な骨格が特徴的。
●
2021 Chianti Colli Senesi
キャンティ・コッリ・セネージ
【ツヤツヤのテクスチュアに美しい果実!・・思いっきりシミジミ系のコッリ・セネージでは無く、外交的な美味しさをしっかり感じさせてくれます!】

「久々にキャンティで大ヒット間違い無し!」
と言える見事な味わいでした。素晴らしいバランスをしています。
本来、キャンティ・コッリ・セネージのワインは、少し「ひなびた感」が滲み出てくるような、しんみり系のサンジョヴェーゼの味わいがほとんどを占めると思います。
が、さすがにポルタ・ディ・ヴェルティーネ醸造家、コッリ・セネージの葡萄の個性を自分のものにしている感じが伝わって来ます。しかも、
「 ラ・トッレ・アッレ・トルフェ に来たのは2018年の収穫の直前!」
とのことですから・・飲んでビックリ、聞いてビックリです。
この実に滑らかなテクスチュアは、セメント槽での発酵によるもののようです。やや襞の有るテクスチュアが特徴でもあるサンジョヴェーゼですし、コッリ・セネージは強い果実やたっぷりとしたタンニンは出にくいのでしょう。
「・・これがコッリ・セネージ!?」
と思っていただけると思いますよ。
 あ、写真が見つかりましたが・・赤い果実の色合いがポルタ・ディ・ヴェルティーネのワインから感じられますよね。ある意味、非常に似ていると思いますが、コッリ・セネージの方が集中しているかもしれませんね。
あ、写真が見つかりましたが・・赤い果実の色合いがポルタ・ディ・ヴェルティーネのワインから感じられますよね。ある意味、非常に似ていると思いますが、コッリ・セネージの方が集中しているかもしれませんね。素晴らしいバランスをしています。是非飲んでみてください。お勧めします!
白玉醸造
白玉醸造
日本 Shiratama Jouzou 鹿児島
● 魔王で一世を風靡している?白玉醸造です。ホームページが無いので詳細は書けず・・すみません。
●
(N.V.) Shiratama no Tsuyu 25°
白玉の露 25度
【でも魔王とはタイプが全然違います。】
白玉醸造の、魔王と同じ芋焼酎です。魔王は芋の個性を余り出さず、日本酒の吟醸系のアロマを出せるようにしている感じがします。
ですが、こちらはもっと「芋!」と言ったイメージが伝わって来ると思います。結構にファンがいらっしゃる聞きますが・・どうなんでしょう。ワイン屋なので・・判りません。
判りませんとは言いましたが、魔王がまだ知名度の無かった頃、取引の話しが有りました。ワインで忙しいので・・断っちゃいました~・・(^^;; まあ、それも「定め」なんでしょうね~。間髪入れずに断っちゃいましたんで・・はい。その頃はまだ5ケースずつは送って貰えたんですね~。百年の孤独で酷い目に遭ったもんで、どこか偏見が有ったんでしょうかね。ホント、売れるようになると、いきなりスパッと切って来ますから。「そうじゃないだろ!」とは思うんですが、相手を値踏みをして、意に合わないと思ったらそうしちゃうんでしょう。もしくはそれすらしないかもしれません。
ですが、こちらはもっと「芋!」と言ったイメージが伝わって来ると思います。結構にファンがいらっしゃる聞きますが・・どうなんでしょう。ワイン屋なので・・判りません。
判りませんとは言いましたが、魔王がまだ知名度の無かった頃、取引の話しが有りました。ワインで忙しいので・・断っちゃいました~・・(^^;; まあ、それも「定め」なんでしょうね~。間髪入れずに断っちゃいましたんで・・はい。その頃はまだ5ケースずつは送って貰えたんですね~。百年の孤独で酷い目に遭ったもんで、どこか偏見が有ったんでしょうかね。ホント、売れるようになると、いきなりスパッと切って来ますから。「そうじゃないだろ!」とは思うんですが、相手を値踏みをして、意に合わないと思ったらそうしちゃうんでしょう。もしくはそれすらしないかもしれません。
●
(N.V.) Shiratama no Tsuyu 25°
白玉の露 25度
【でも魔王とはタイプが全然違います。】
白玉醸造の、魔王と同じ芋焼酎です。魔王は芋の個性を余り出さず、日本酒の吟醸系のアロマを出せるようにしている感じがします。
ですが、こちらはもっと「芋!」と言ったイメージが伝わって来ると思います。結構にファンがいらっしゃる聞きますが・・どうなんでしょう。ワイン屋なので・・判りません。
判りませんとは言いましたが、魔王がまだ知名度の無かった頃、取引の話しが有りました。ワインで忙しいので・・断っちゃいました~・・(^^;; まあ、それも「定め」なんでしょうね~。間髪入れずに断っちゃいましたんで・・はい。その頃はまだ5ケースずつは送って貰えたんですね~。百年の孤独で酷い目に遭ったもんで、どこか偏見が有ったんでしょうかね。ホント、売れるようになると、いきなりスパッと切って来ますから。「そうじゃないだろ!」とは思うんですが、相手を値踏みをして、意に合わないと思ったらそうしちゃうんでしょう。もしくはそれすらしないかもしれません。
ですが、こちらはもっと「芋!」と言ったイメージが伝わって来ると思います。結構にファンがいらっしゃる聞きますが・・どうなんでしょう。ワイン屋なので・・判りません。
判りませんとは言いましたが、魔王がまだ知名度の無かった頃、取引の話しが有りました。ワインで忙しいので・・断っちゃいました~・・(^^;; まあ、それも「定め」なんでしょうね~。間髪入れずに断っちゃいましたんで・・はい。その頃はまだ5ケースずつは送って貰えたんですね~。百年の孤独で酷い目に遭ったもんで、どこか偏見が有ったんでしょうかね。ホント、売れるようになると、いきなりスパッと切って来ますから。「そうじゃないだろ!」とは思うんですが、相手を値踏みをして、意に合わないと思ったらそうしちゃうんでしょう。もしくはそれすらしないかもしれません。
●
(N.V.) Genrouin 25°
元老院 25度
【魔王も良いけれど元老院も滅茶美味しい!香り良くマイルドで非常に滑らか!お湯割りも旨いしロックも・・そのままでも飲めてしまいます。】
 ついにnoisy も焼酎のレヴューを書く様になってしまいました・・いや、たまたまテイスティングの穴の日が有って、目の前にこのボトルが有ったので・・
ついにnoisy も焼酎のレヴューを書く様になってしまいました・・いや、たまたまテイスティングの穴の日が有って、目の前にこのボトルが有ったので・・「ただ売るだけ・・じゃぁなぁ・・」
と言うような気も有ったので、清水の舞台から飛び降りるような決心で・・(笑 テイスティングしてみました。
麦と芋のブレンドと言うことで、臭~い芋のニュアンスは全く無し!・・むしろ麦系のスレンダーな香りがマイルドさを持って感じられます・・あ、勿論ストレートでのスタートですよ。
そのままじゃキツイかな?・・と思いきや、相当に舌触りはマイルドです。キツさはアルコール分の低さ(25度)でほぼほぼ無し(noisy的には・・)。安い焼酎はトゲトゲしいですが、それなりに熟成をしているのが判るほどまろやかです。
そこに氷を投入してみました。・・いや、飲みやすいですね・・適度に氷が解け、僅かに感じたアルコールの主張は消えてしまいました。これは美味しい!・・淡~~い旨味が何とも良いです。
飲み切ってしまったので今度は茶碗を持ち出し、お湯を沸かして6対4ほどのお湯割りにしてみました。あ、焼酎が6ですよ・・
いや・・これは良いですね~・・アルコール分が25度ですから、6:4で16度ほどになりますか・・大体、日本酒のアルコール分ですね。
焼酎が持っている僅かな酸と僅かに有る甘味が引き立たせられる感じで、しかも身体がほっこりと温まって来ます。しかも、ワインと違って魚でも肉でも調味料次第・・な感じで、繊細系でもガッツリ系のお食事でも合わせるのが簡単・・と言うか、考えなくて良いのがポイントですね。でも新鮮な魚のお刺身はロックが少し溶けた位の方が好きかもしれません。
魔王ばかりが人気ですが、この元老院・・飲んでみなんしょ?・・ちょっと飲み足りない時・・とか、しばれる(寒い)外から帰って来た時とか、お湯を沸かすだけで・・3分で相当温まれます。しかも相当旨いです!是非飲んでみて下さい。
以下は以前のレヴューです。
-----
【麦とさつま芋をブレンド、樽貯蔵でまろやかさを出したプレミアム系の限定酒です。】
こちらはどちらかと言えばライトなタイプで、言ってしまえば魔王寄りでは有りますが、芋だけではなく麦もブレンドしていますので、相当異なる印象になると思います。
●
(N.V.) Genrouin 25°
元老院 25度
【魔王も良いけれど元老院も滅茶美味しい!香り良くマイルドで非常に滑らか!お湯割りも旨いしロックも・・そのままでも飲めてしまいます。】
 ついにnoisy も焼酎のレヴューを書く様になってしまいました・・いや、たまたまテイスティングの穴の日が有って、目の前にこのボトルが有ったので・・
ついにnoisy も焼酎のレヴューを書く様になってしまいました・・いや、たまたまテイスティングの穴の日が有って、目の前にこのボトルが有ったので・・「ただ売るだけ・・じゃぁなぁ・・」
と言うような気も有ったので、清水の舞台から飛び降りるような決心で・・(笑 テイスティングしてみました。
麦と芋のブレンドと言うことで、臭~い芋のニュアンスは全く無し!・・むしろ麦系のスレンダーな香りがマイルドさを持って感じられます・・あ、勿論ストレートでのスタートですよ。
そのままじゃキツイかな?・・と思いきや、相当に舌触りはマイルドです。キツさはアルコール分の低さ(25度)でほぼほぼ無し(noisy的には・・)。安い焼酎はトゲトゲしいですが、それなりに熟成をしているのが判るほどまろやかです。
そこに氷を投入してみました。・・いや、飲みやすいですね・・適度に氷が解け、僅かに感じたアルコールの主張は消えてしまいました。これは美味しい!・・淡~~い旨味が何とも良いです。
飲み切ってしまったので今度は茶碗を持ち出し、お湯を沸かして6対4ほどのお湯割りにしてみました。あ、焼酎が6ですよ・・
いや・・これは良いですね~・・アルコール分が25度ですから、6:4で16度ほどになりますか・・大体、日本酒のアルコール分ですね。
焼酎が持っている僅かな酸と僅かに有る甘味が引き立たせられる感じで、しかも身体がほっこりと温まって来ます。しかも、ワインと違って魚でも肉でも調味料次第・・な感じで、繊細系でもガッツリ系のお食事でも合わせるのが簡単・・と言うか、考えなくて良いのがポイントですね。でも新鮮な魚のお刺身はロックが少し溶けた位の方が好きかもしれません。
魔王ばかりが人気ですが、この元老院・・飲んでみなんしょ?・・ちょっと飲み足りない時・・とか、しばれる(寒い)外から帰って来た時とか、お湯を沸かすだけで・・3分で相当温まれます。しかも相当旨いです!是非飲んでみて下さい。
以下は以前のレヴューです。
-----
【麦とさつま芋をブレンド、樽貯蔵でまろやかさを出したプレミアム系の限定酒です。】
こちらはどちらかと言えばライトなタイプで、言ってしまえば魔王寄りでは有りますが、芋だけではなく麦もブレンドしていますので、相当異なる印象になると思います。
●
(N.V.) Tentyuu 25°
天誅 25度
【減圧蒸留でスッキリ薫り高い味わいに仕上げた芋と米の焼酎です。】
飲んでいないので判りませんが、香りの良い魔王にやや似たスタイルだと思いますが、米を使って旨味を増しているタイプかと思います。元老院は飲ませていただきましたが、熟成感が有り滑らか、コクの豊かなタイプで美味かったですよ。そのうち機会を作って天誅もテイスティングしてみます。
長島研醸有限会社
長島研醸有限会社
日本 Nagashimakenjo 鹿児島
● 鹿児島県は最北部・・と言いますか、天草の南にある島・・と言った方が判りやすいかもしれません。長島にある長島研醸さんです。
阿久根市や出水市が近いですね。八代海にも外海にも面していて魚介も美味しいところだと聞きます。
■ 長島研醸有限会社
鹿児島県の最北端にある町・長島町(ながしまちょう)。大小23の温暖な島々に囲まれた山の幸・海の幸に恵まれた土地に、長島研醸はあります。昭和42年2月、長島町にある五つの蔵元の共同瓶詰工場として長島研醸有限会社は設立されました。(宮内酒造株式会社・宮乃露酒造株式会社・長山酒造有限会社・杉本酒造株式会社・南洲酒造合資会社)五つの蔵元がそれぞれの伝統と技で醸し出した焼酎を巧みにブレンドし、生まれた焼酎は設立時からも変わらぬ味わいを貫き、現在にも受け継いでいます。
『さつま島美人』をはじめ『黒島美人』『さつま島娘』『島乙女』『だんだん』すべての銘柄が、五つの蔵元の原酒をブレンドした焼酎で造られています。
阿久根市や出水市が近いですね。八代海にも外海にも面していて魚介も美味しいところだと聞きます。
■ 長島研醸有限会社
鹿児島県の最北端にある町・長島町(ながしまちょう)。大小23の温暖な島々に囲まれた山の幸・海の幸に恵まれた土地に、長島研醸はあります。昭和42年2月、長島町にある五つの蔵元の共同瓶詰工場として長島研醸有限会社は設立されました。(宮内酒造株式会社・宮乃露酒造株式会社・長山酒造有限会社・杉本酒造株式会社・南洲酒造合資会社)五つの蔵元がそれぞれの伝統と技で醸し出した焼酎を巧みにブレンドし、生まれた焼酎は設立時からも変わらぬ味わいを貫き、現在にも受け継いでいます。
『さつま島美人』をはじめ『黒島美人』『さつま島娘』『島乙女』『だんだん』すべての銘柄が、五つの蔵元の原酒をブレンドした焼酎で造られています。
●
N.V. Kagoshimabijin 25°
鹿児島美人 25度
【通常は鹿児島県内のみの販売のようです。長島研醸さんを構成する5社の焼酎をブレンドしています。】
この長島研醸さんは5社の共同瓶詰工場として誕生されています。県内向けに造られているようですので、さつま島美人よりも「通向け」?なのかもしれません。違っていたらすみません。
佐多宗二商店
佐多宗二商店
日本 Sata Souji Syouten 鹿児島
● 蒸留方法にこだわった造りをしている佐多宗二商店さんをご紹介させていただきます。
何とイタリアから蒸留器を輸入されているそうで・・直接的に熱を入れ蒸留したり、間接的な熱入れで蒸留したり・・は、他の生産者さんは余りやっていないようです。
何とイタリアから蒸留器を輸入されているそうで・・直接的に熱を入れ蒸留したり、間接的な熱入れで蒸留したり・・は、他の生産者さんは余りやっていないようです。
●
(N.V.) Sengokusaikyou Juujimon
戦国最強 十字紋
【ネットを検索しても余り情報は無い・・でもあの、「島津の退き口」で有名な島津義弘の流れをくむ加治木島津家と佐多宗二商店のコラボ企画で生まれた芋焼酎です。】
限定数量で仕入れたので・・飲んでいません。非常にバランスの良い香りと味わいのようです。
まぁ、「戦国最強」とは・・凄い名前ですよね~。おまけに「十字紋」ですから・・。
でも詳しいことは知りませんが、丸に十文字が島津の家紋・・としますと、単に「十」と毛筆体で書かれたのは加治木島津家の家紋なのかな?・・と思います。
島津の退き口・・有名ですよね。noisy でもその位は知ってます。関ヶ原の戦いで西軍(豊臣方)につくことになった島津義弘は、兄義久と仲違いしながらも少数の兵を集めて陣を張った訳ですが、小早川秀秋の裏切りで西軍が総崩れ・・もはやこれまで!・・のところを家臣団に止められ、戦場のど真ん中から脱出する・・と言う話しです。
東軍の家康の本陣めがけて突進、福島正則と刀を合わせた直後、その脇を通り抜け、捨て奸(すてがまり)と言う戦法で大将を逃がすと言う・・決死の脱出を図った訳です。
まぁ、生きて薩摩に戻れたのは80名余りだったようです。「捨て奸」は興味があったらお調べください。
関ケ原の合戦は島津義弘にとっては負け戦では有りますが、島津氏(義久)にとっては決して家康に弓を引いた訳では無く、義弘は加治木に隠居(蟄居?)したようです。
それに島津氏は九州を大方丸めた大大名ですし、家康は島津氏を結局潰せなかった訳で・・九州の戦国最強は島津氏・・と言うことなのでしょうね。
そんなところで、地元の縁でしょうか、加治木島津家と佐多宗二商店のコラボでこの芋焼酎が生まれたようですので、余り出回っていないようです。価格も決して高くなく、バランスの良い味わいで「臭く無い」方の芋のようです。ご検討くださいませ。
まぁ、「戦国最強」とは・・凄い名前ですよね~。おまけに「十字紋」ですから・・。
でも詳しいことは知りませんが、丸に十文字が島津の家紋・・としますと、単に「十」と毛筆体で書かれたのは加治木島津家の家紋なのかな?・・と思います。
島津の退き口・・有名ですよね。noisy でもその位は知ってます。関ヶ原の戦いで西軍(豊臣方)につくことになった島津義弘は、兄義久と仲違いしながらも少数の兵を集めて陣を張った訳ですが、小早川秀秋の裏切りで西軍が総崩れ・・もはやこれまで!・・のところを家臣団に止められ、戦場のど真ん中から脱出する・・と言う話しです。
東軍の家康の本陣めがけて突進、福島正則と刀を合わせた直後、その脇を通り抜け、捨て奸(すてがまり)と言う戦法で大将を逃がすと言う・・決死の脱出を図った訳です。
まぁ、生きて薩摩に戻れたのは80名余りだったようです。「捨て奸」は興味があったらお調べください。
関ケ原の合戦は島津義弘にとっては負け戦では有りますが、島津氏(義久)にとっては決して家康に弓を引いた訳では無く、義弘は加治木に隠居(蟄居?)したようです。
それに島津氏は九州を大方丸めた大大名ですし、家康は島津氏を結局潰せなかった訳で・・九州の戦国最強は島津氏・・と言うことなのでしょうね。
そんなところで、地元の縁でしょうか、加治木島津家と佐多宗二商店のコラボでこの芋焼酎が生まれたようですので、余り出回っていないようです。価格も決して高くなく、バランスの良い味わいで「臭く無い」方の芋のようです。ご検討くださいませ。
●
(N.V.) Sengokusaikyou Juujimon
戦国最強 十字紋
【ネットを検索しても余り情報は無い・・でもあの、「島津の退き口」で有名な島津義弘の流れをくむ加治木島津家と佐多宗二商店のコラボ企画で生まれた芋焼酎です。】
限定数量で仕入れたので・・飲んでいません。非常にバランスの良い香りと味わいのようです。
まぁ、「戦国最強」とは・・凄い名前ですよね~。おまけに「十字紋」ですから・・。
でも詳しいことは知りませんが、丸に十文字が島津の家紋・・としますと、単に「十」と毛筆体で書かれたのは加治木島津家の家紋なのかな?・・と思います。
島津の退き口・・有名ですよね。noisy でもその位は知ってます。関ヶ原の戦いで西軍(豊臣方)につくことになった島津義弘は、兄義久と仲違いしながらも少数の兵を集めて陣を張った訳ですが、小早川秀秋の裏切りで西軍が総崩れ・・もはやこれまで!・・のところを家臣団に止められ、戦場のど真ん中から脱出する・・と言う話しです。
東軍の家康の本陣めがけて突進、福島正則と刀を合わせた直後、その脇を通り抜け、捨て奸(すてがまり)と言う戦法で大将を逃がすと言う・・決死の脱出を図った訳です。
まぁ、生きて薩摩に戻れたのは80名余りだったようです。「捨て奸」は興味があったらお調べください。
関ケ原の合戦は島津義弘にとっては負け戦では有りますが、島津氏(義久)にとっては決して家康に弓を引いた訳では無く、義弘は加治木に隠居(蟄居?)したようです。
それに島津氏は九州を大方丸めた大大名ですし、家康は島津氏を結局潰せなかった訳で・・九州の戦国最強は島津氏・・と言うことなのでしょうね。
そんなところで、地元の縁でしょうか、加治木島津家と佐多宗二商店のコラボでこの芋焼酎が生まれたようですので、余り出回っていないようです。価格も決して高くなく、バランスの良い味わいで「臭く無い」方の芋のようです。ご検討くださいませ。
まぁ、「戦国最強」とは・・凄い名前ですよね~。おまけに「十字紋」ですから・・。
でも詳しいことは知りませんが、丸に十文字が島津の家紋・・としますと、単に「十」と毛筆体で書かれたのは加治木島津家の家紋なのかな?・・と思います。
島津の退き口・・有名ですよね。noisy でもその位は知ってます。関ヶ原の戦いで西軍(豊臣方)につくことになった島津義弘は、兄義久と仲違いしながらも少数の兵を集めて陣を張った訳ですが、小早川秀秋の裏切りで西軍が総崩れ・・もはやこれまで!・・のところを家臣団に止められ、戦場のど真ん中から脱出する・・と言う話しです。
東軍の家康の本陣めがけて突進、福島正則と刀を合わせた直後、その脇を通り抜け、捨て奸(すてがまり)と言う戦法で大将を逃がすと言う・・決死の脱出を図った訳です。
まぁ、生きて薩摩に戻れたのは80名余りだったようです。「捨て奸」は興味があったらお調べください。
関ケ原の合戦は島津義弘にとっては負け戦では有りますが、島津氏(義久)にとっては決して家康に弓を引いた訳では無く、義弘は加治木に隠居(蟄居?)したようです。
それに島津氏は九州を大方丸めた大大名ですし、家康は島津氏を結局潰せなかった訳で・・九州の戦国最強は島津氏・・と言うことなのでしょうね。
そんなところで、地元の縁でしょうか、加治木島津家と佐多宗二商店のコラボでこの芋焼酎が生まれたようですので、余り出回っていないようです。価格も決して高くなく、バランスの良い味わいで「臭く無い」方の芋のようです。ご検討くださいませ。
三岳酒造株式会社
三岳酒造株式会社
日本 MitakeSyuzou 鹿児島
● 品物が有って仕入れられれば入れている、屋久島銘酒、三岳です。
●
N.V. Mitake Imo 25°
三岳 芋 25°
【巷では人気なのか?・・判りません。】
まぁ、地酒などもそうですが、欲しい方はどうしても、何が何でも欲しいようです。気持ちは何となく判りますが、販売する方も中々に難しく、
「2ケースください」
などと平気でおっしゃる方もいらっしゃって、どうするのかと調べてみると、どうやら転売しているということが判り・・まぁ、ダフ屋さんと同じですね。ですので、お断りするようになってしまいます。
バランス良く、臭味無く、ほんのりと甘みを感じる・・超優等生タイプでしょうか。水割りもお湯割りも行けると思います。宣伝も全くしないとてもローカルな蔵元さんですが、それでも大人気のようです。
「2ケースください」
などと平気でおっしゃる方もいらっしゃって、どうするのかと調べてみると、どうやら転売しているということが判り・・まぁ、ダフ屋さんと同じですね。ですので、お断りするようになってしまいます。
バランス良く、臭味無く、ほんのりと甘みを感じる・・超優等生タイプでしょうか。水割りもお湯割りも行けると思います。宣伝も全くしないとてもローカルな蔵元さんですが、それでも大人気のようです。
西酒造
西酒造
日本 Nishisyuzou 鹿児島
● 芋焼酎がほとんど・・と言う鹿児島にあって、勿論ですが西酒造さんは「富乃宝山」で著名では有るんですが、
「麹まで全て麦で造った焼酎!」
をリリースしています。
麦焼酎を言えば「大分」が有名ですよね。でも、「大分麦焼酎」とはだいぶ違うようですよ。鹿児島流の麦焼酎のご案内です。
「麹まで全て麦で造った焼酎!」
をリリースしています。
麦焼酎を言えば「大分」が有名ですよね。でも、「大分麦焼酎」とはだいぶ違うようですよ。鹿児島流の麦焼酎のご案内です。
●
(N.V.) Hitotsubu no Mugi
一粒の麦
【芋中心の鹿児島で造る麦焼酎!】
富乃宝山で薫り高くスッキリ系の芋をリリース、世に大いに受け入れられた鹿児島の焼酎メーカーさんです。
でも宝山じゃなくて「一粒の麦」ですから麦焼酎。しかも、麹にまで麦麹をしている全麦焼酎ですね。芋焼酎の生産がほぼ全てを占める鹿児島県では珍しいです。しかも売れているメーカーさんですから・・。
麦焼酎と言えば、やはり大分が本場かな・・勿論他の県にも存在しますが、土地の組成も有るんでしょう、九州北部は麦、南部は芋、中部は米・・みたいなイメージです(例外は有ります)。
飲まれたことの有る方のご意見ですと、やはり「い・・こ」とか「に・・・う」などの麦焼酎とはだいぶ違うようですよ。結構にドライなようで・・いや、伏字にしたメーカーさんのが甘いと言ってる訳じゃないですが・・まぁ、noisy にも大っぴらには言えないことは多々有ります。でもどこかで書いちゃったかもしれませんけど。
で、宝山シリーズで有名な西酒造さんのサイトを見させていただいたんですが、この「一粒の麦」、あんまり出てこないんですよね。散々探してようやくちょびっとだけ書いて有りました。ドライでスッキリ、クセの少ない味わいのようです。ご検討くださいませ。
でも宝山じゃなくて「一粒の麦」ですから麦焼酎。しかも、麹にまで麦麹をしている全麦焼酎ですね。芋焼酎の生産がほぼ全てを占める鹿児島県では珍しいです。しかも売れているメーカーさんですから・・。
麦焼酎と言えば、やはり大分が本場かな・・勿論他の県にも存在しますが、土地の組成も有るんでしょう、九州北部は麦、南部は芋、中部は米・・みたいなイメージです(例外は有ります)。
飲まれたことの有る方のご意見ですと、やはり「い・・こ」とか「に・・・う」などの麦焼酎とはだいぶ違うようですよ。結構にドライなようで・・いや、伏字にしたメーカーさんのが甘いと言ってる訳じゃないですが・・まぁ、noisy にも大っぴらには言えないことは多々有ります。でもどこかで書いちゃったかもしれませんけど。
で、宝山シリーズで有名な西酒造さんのサイトを見させていただいたんですが、この「一粒の麦」、あんまり出てこないんですよね。散々探してようやくちょびっとだけ書いて有りました。ドライでスッキリ、クセの少ない味わいのようです。ご検討くださいませ。
須木酒造
須木酒造
日本 Shukisyuzou 宮崎
● 比較的強い個性を発揮する宮崎の芋焼酎です。
■すき酒造 『醸し続け百年、永劫の百年へ』
すき酒造は宮崎県の西部に位置し、九州山脈の山々が連なり、熊本県の県境に隣接する自然豊かな景観の山里 「須木」 にて焼酎造りを百年。2010年、更なる永劫の百年を目指し、手造り麹・麹室・総甕壺仕込みが行える、「本物」を追求し、「伝統」を継承する総木造の焼酎蔵を新築・完全移転しました。
2020 / 03 / 0910:59
2020年 山猪発売のお知らせ
皆様、お世話になります。
まず、新型コロナウィルスで、亡くなられた方、被患されている方々、また不安でつらい日々を過ごされているすべての皆様に御見舞い申し上げます。
そしてそんな中では御座いますが、明日より、いよいよ狩猟解禁!今年も「山猪 ヤマジシ」の発売日がやって参りました。
昨年「亥年」に醸し出された「亥年醸造山猪」です!また、今回は昨年と違い、同じタイミングで1.8Lと720mlと出荷させて頂きます。試しに720mlからというお客様、大歓迎です!
2020年度の山猪も香りあり、旨味あり、甘味あり、余韻まで美味しい!しかも写真撮りしたら虹までかかって神々しい!こんな時では御座いますが、是非、お楽しみに!ちなみに、明日よりの蔵元発送ですので、お店の店頭に並ぶのは後日となります。今暫らくお待ち下さいませ。また、数量限定ですので、お早めに。
■すき酒造 『醸し続け百年、永劫の百年へ』
すき酒造は宮崎県の西部に位置し、九州山脈の山々が連なり、熊本県の県境に隣接する自然豊かな景観の山里 「須木」 にて焼酎造りを百年。2010年、更なる永劫の百年を目指し、手造り麹・麹室・総甕壺仕込みが行える、「本物」を追求し、「伝統」を継承する総木造の焼酎蔵を新築・完全移転しました。
2020 / 03 / 0910:59
2020年 山猪発売のお知らせ
皆様、お世話になります。
まず、新型コロナウィルスで、亡くなられた方、被患されている方々、また不安でつらい日々を過ごされているすべての皆様に御見舞い申し上げます。
そしてそんな中では御座いますが、明日より、いよいよ狩猟解禁!今年も「山猪 ヤマジシ」の発売日がやって参りました。
昨年「亥年」に醸し出された「亥年醸造山猪」です!また、今回は昨年と違い、同じタイミングで1.8Lと720mlと出荷させて頂きます。試しに720mlからというお客様、大歓迎です!
2020年度の山猪も香りあり、旨味あり、甘味あり、余韻まで美味しい!しかも写真撮りしたら虹までかかって神々しい!こんな時では御座いますが、是非、お楽しみに!ちなみに、明日よりの蔵元発送ですので、お店の店頭に並ぶのは後日となります。今暫らくお待ち下さいませ。また、数量限定ですので、お早めに。
●
N.V. Yamasuzume Imo 25do
山雀 夏季限定 芋 25度
【何だ?・・二段割り?】
芋の香りが抜群に濃く、味は力強い「豪傑」な芋焼酎・・を謳っているのがこの山猪(やまじし)です。なので、好きな方とそうでない方に分かれやすいかもしれませんね。このような系統の芋は「お湯割り」にすると美味しい・・と思います。
また、「二段割り」などと言う、超ローテクながら「掟破り」な手段をも勧めていると言う、心優しい蔵元さんでも有ります。
二段割りは、なんと・・
「他の本格焼酎と混ぜる!」
だそうですよ・・やったことがない・・と言うか、やる暇も無い・・。
例えば、強烈な個性を持ち、そのクセから離れられなくなったファンも多い「鶴見」と割ると、甘みも香りも膨らんで旨い!・・そうです。・・いや、聞いた話です。
なので、「ひや(そのまま)」「オンザロック」「水割り」「お湯割り」「二段割り」を・・楽しんでみてはいかがでしょうか。ま、「ソーダ割り」「ウーロン茶割り」までは何とか許せるとしても、「ハイサワー割り」とかは邪道かな・・とは思いますが、それでもご自由にお楽しみください。
また、「二段割り」などと言う、超ローテクながら「掟破り」な手段をも勧めていると言う、心優しい蔵元さんでも有ります。
二段割りは、なんと・・
「他の本格焼酎と混ぜる!」
だそうですよ・・やったことがない・・と言うか、やる暇も無い・・。
例えば、強烈な個性を持ち、そのクセから離れられなくなったファンも多い「鶴見」と割ると、甘みも香りも膨らんで旨い!・・そうです。・・いや、聞いた話です。
なので、「ひや(そのまま)」「オンザロック」「水割り」「お湯割り」「二段割り」を・・楽しんでみてはいかがでしょうか。ま、「ソーダ割り」「ウーロン茶割り」までは何とか許せるとしても、「ハイサワー割り」とかは邪道かな・・とは思いますが、それでもご自由にお楽しみください。
●
N.V. Yamajishi Imo 25°
山猪 芋 25度
【何だ?・・二段割り?】
芋の香りが抜群に濃く、味は力強い「豪傑」な芋焼酎・・を謳っているのがこの山猪(やまじし)です。なので、好きな方とそうでない方に分かれやすいかもしれませんね。このような系統の芋は「お湯割り」にすると美味しい・・と思います。
また、「二段割り」などと言う、超ローテクながら「掟破り」な手段をも勧めていると言う、心優しい蔵元さんでも有ります。
二段割りは、なんと・・
「他の本格焼酎と混ぜる!」
だそうですよ・・やったことがない・・と言うか、やる暇も無い・・。
例えば、強烈な個性を持ち、そのクセから離れられなくなったファンも多い「鶴見」と割ると、甘みも香りも膨らんで旨い!・・そうです。・・いや、聞いた話です。
なので、「ひや(そのまま)」「オンザロック」「水割り」「お湯割り」「二段割り」を・・楽しんでみてはいかがでしょうか。ま、「ソーダ割り」「ウーロン茶割り」までは何とか許せるとしても、「ハイサワー割り」とかは邪道かな・・とは思いますが、それでもご自由にお楽しみください。
また、「二段割り」などと言う、超ローテクながら「掟破り」な手段をも勧めていると言う、心優しい蔵元さんでも有ります。
二段割りは、なんと・・
「他の本格焼酎と混ぜる!」
だそうですよ・・やったことがない・・と言うか、やる暇も無い・・。
例えば、強烈な個性を持ち、そのクセから離れられなくなったファンも多い「鶴見」と割ると、甘みも香りも膨らんで旨い!・・そうです。・・いや、聞いた話です。
なので、「ひや(そのまま)」「オンザロック」「水割り」「お湯割り」「二段割り」を・・楽しんでみてはいかがでしょうか。ま、「ソーダ割り」「ウーロン茶割り」までは何とか許せるとしても、「ハイサワー割り」とかは邪道かな・・とは思いますが、それでもご自由にお楽しみください。
パーネヴィーノ
パーネヴィーノ
イタリア Panevino サルディーニャ
●久し振りにご案内のパーネヴィーノです。
「ウダッとしてない、南イタリアの赤って何か無い?」
みたいなノリの中から見つけた秀逸なイゾーラ・デイ・ヌラギのビオ系造り手です。かなり旨いんですが、いつも発注が出遅れて購入できない事態になっていました。
 左は以前ご案内させていただいたワイン・・2006年ものですが、もうだいぶ経ってますね・・。この頃はリアルワインガイドでイタリアワインのページが有ったので、随分とこの辺りもご紹介させていただきました。その後、2012年ものをご案内しましたが、もう数がほとんど入ってこなくなっちゃいました。
左は以前ご案内させていただいたワイン・・2006年ものですが、もうだいぶ経ってますね・・。この頃はリアルワインガイドでイタリアワインのページが有ったので、随分とこの辺りもご紹介させていただきました。その後、2012年ものをご案内しましたが、もう数がほとんど入ってこなくなっちゃいました。
Panevino / パーネヴィーノ
造り手:Panevino / パーネヴィーノ
人:Gianfranco Manca / ジャンフランコ マンカ
産地(州):サルデーニャ
ワイン:Girotondo、Pikade、Alvas…等(ほぼ毎年新しいワインがリリースされるので恐らく一番多くのワインがあります)
所在地:Localita Perda Coddura、08035 Nurri | CA ? Italia
現当主ジャンフランコ マンカは、代々受け継がれてきた畑でのブドウ栽培を1986年から彼自身で手がけ始め、1994年からは公式にワイナリーとしての活動を始める。標高450mから700mまで、土壌も火山岩質から粘土-片岩質と様々な特性の、5つの区画に合計3ヘクタールの畑を持ち、サルデーニャの土着品種を栽培する(カンノナウ、ムリステッル、カニュラーリ、カリニャーノ、モニカ、モレットゥ、ジロ、モスカート、マルヴァジーア、ヴェルメンティーノ、セミダーノ、ヌラーグス)。樹齢も品種、区画によっては100年を超えるものも。年生産量7500-9000リットル。大地、人、その他の生命に対して最大限の敬意を払うべく、畑では一切の施肥を行わず、畑に自生する草を鋤き込むことで緑肥として利用しているほか、ボルドー液さえも使用せず、細かい粉末状の土と硫黄を混ぜたものを農薬代わりに6月に1度(年、畑によっては一度も撒かない)する以外には一切何も畑には散布しない。ワイナリーでも、醸造からボトリングまでの全ての工程で一切の薬剤を使用しない。
 ワイン生産以外に、パン屋も生業としており、地元の無農薬の粉を使い、代々受け継いできた自然発酵種(小麦粉が勝手に醗酵したもの、とでも言えば良いのでしょうか)をもとにを、薪釜でパンを焼いている。ブドウ以外にもオリーヴ、野菜、フルーツ、穀物を栽培し、それらは彼が経営するアグリトゥリズモで供される。
ワイン生産以外に、パン屋も生業としており、地元の無農薬の粉を使い、代々受け継いできた自然発酵種(小麦粉が勝手に醗酵したもの、とでも言えば良いのでしょうか)をもとにを、薪釜でパンを焼いている。ブドウ以外にもオリーヴ、野菜、フルーツ、穀物を栽培し、それらは彼が経営するアグリトゥリズモで供される。
Vini Naturali(ナチュラル ワイン)という言葉に対して、”そもそもワインとはブドウだけで造る、極めてナチュラルなものなわけで、ワインにナチュラルななどという形容詞を付ける事自体が間違っている”と言い放つジャンフランコが考え出した、ナチュラルワインでも、ビオワインでも、自然派ワインでも、有機ワインでもない言葉、それがVini Liberi(自由な、何の束縛もない、ブドウ以外の何物も使用しないワイン)。
いい言葉だと思いませんか?
ジャンフランコは、パオロ ヴォドピーヴェッツと対極をなす天才なんだと僕は考えています。かたやヒューマニティ溢れまくっているワインを醸すことを良しとし、そしてもう一方はワインから“我”をどこまで消し去ることができるかを追い求め…ワインに対するアプローチは全くもって交わらない感のある2人ですが、互いに滅茶苦茶尊敬し合っていたりするのも非常に興味深く…。結局のところ、“する”も“しない”もどちらかを選択している時点で“している”ことになるわけで、場面場面で訪れる“する”か“しない”の選択は、その造り手のその瞬間の感性、観点、哲学、知識、経験、良心、精神状態、経済状況などに強く影響を受けたものである…ということも“自然”なことなんですよね…。これだからこういうワインって面白いのかと!!!
「ウダッとしてない、南イタリアの赤って何か無い?」
みたいなノリの中から見つけた秀逸なイゾーラ・デイ・ヌラギのビオ系造り手です。かなり旨いんですが、いつも発注が出遅れて購入できない事態になっていました。
 左は以前ご案内させていただいたワイン・・2006年ものですが、もうだいぶ経ってますね・・。この頃はリアルワインガイドでイタリアワインのページが有ったので、随分とこの辺りもご紹介させていただきました。その後、2012年ものをご案内しましたが、もう数がほとんど入ってこなくなっちゃいました。
左は以前ご案内させていただいたワイン・・2006年ものですが、もうだいぶ経ってますね・・。この頃はリアルワインガイドでイタリアワインのページが有ったので、随分とこの辺りもご紹介させていただきました。その後、2012年ものをご案内しましたが、もう数がほとんど入ってこなくなっちゃいました。Panevino / パーネヴィーノ
造り手:Panevino / パーネヴィーノ
人:Gianfranco Manca / ジャンフランコ マンカ
産地(州):サルデーニャ
ワイン:Girotondo、Pikade、Alvas…等(ほぼ毎年新しいワインがリリースされるので恐らく一番多くのワインがあります)
所在地:Localita Perda Coddura、08035 Nurri | CA ? Italia
現当主ジャンフランコ マンカは、代々受け継がれてきた畑でのブドウ栽培を1986年から彼自身で手がけ始め、1994年からは公式にワイナリーとしての活動を始める。標高450mから700mまで、土壌も火山岩質から粘土-片岩質と様々な特性の、5つの区画に合計3ヘクタールの畑を持ち、サルデーニャの土着品種を栽培する(カンノナウ、ムリステッル、カニュラーリ、カリニャーノ、モニカ、モレットゥ、ジロ、モスカート、マルヴァジーア、ヴェルメンティーノ、セミダーノ、ヌラーグス)。樹齢も品種、区画によっては100年を超えるものも。年生産量7500-9000リットル。大地、人、その他の生命に対して最大限の敬意を払うべく、畑では一切の施肥を行わず、畑に自生する草を鋤き込むことで緑肥として利用しているほか、ボルドー液さえも使用せず、細かい粉末状の土と硫黄を混ぜたものを農薬代わりに6月に1度(年、畑によっては一度も撒かない)する以外には一切何も畑には散布しない。ワイナリーでも、醸造からボトリングまでの全ての工程で一切の薬剤を使用しない。
 ワイン生産以外に、パン屋も生業としており、地元の無農薬の粉を使い、代々受け継いできた自然発酵種(小麦粉が勝手に醗酵したもの、とでも言えば良いのでしょうか)をもとにを、薪釜でパンを焼いている。ブドウ以外にもオリーヴ、野菜、フルーツ、穀物を栽培し、それらは彼が経営するアグリトゥリズモで供される。
ワイン生産以外に、パン屋も生業としており、地元の無農薬の粉を使い、代々受け継いできた自然発酵種(小麦粉が勝手に醗酵したもの、とでも言えば良いのでしょうか)をもとにを、薪釜でパンを焼いている。ブドウ以外にもオリーヴ、野菜、フルーツ、穀物を栽培し、それらは彼が経営するアグリトゥリズモで供される。Vini Naturali(ナチュラル ワイン)という言葉に対して、”そもそもワインとはブドウだけで造る、極めてナチュラルなものなわけで、ワインにナチュラルななどという形容詞を付ける事自体が間違っている”と言い放つジャンフランコが考え出した、ナチュラルワインでも、ビオワインでも、自然派ワインでも、有機ワインでもない言葉、それがVini Liberi(自由な、何の束縛もない、ブドウ以外の何物も使用しないワイン)。
いい言葉だと思いませんか?
ジャンフランコは、パオロ ヴォドピーヴェッツと対極をなす天才なんだと僕は考えています。かたやヒューマニティ溢れまくっているワインを醸すことを良しとし、そしてもう一方はワインから“我”をどこまで消し去ることができるかを追い求め…ワインに対するアプローチは全くもって交わらない感のある2人ですが、互いに滅茶苦茶尊敬し合っていたりするのも非常に興味深く…。結局のところ、“する”も“しない”もどちらかを選択している時点で“している”ことになるわけで、場面場面で訪れる“する”か“しない”の選択は、その造り手のその瞬間の感性、観点、哲学、知識、経験、良心、精神状態、経済状況などに強く影響を受けたものである…ということも“自然”なことなんですよね…。これだからこういうワインって面白いのかと!!!
●
2020 Tanka Salina Vino Rosso
タンカ・サリナ・ヴィノ・ロッソ
【...】
カンノナウ、ボヴァーレ、ティンティッル、モニカで造られるサルディーニャのワインです。先日、コルスのワインをご紹介させていただきましたが、そことの比較も面白いのではないかと・・。パーネヴィーノのワインはレベルが高いと思いますが、判るのは相変わらずの入荷数の少なさと、
「塩っぽさが有る」
こと位でしょうか。ご検討くださいませ。
「塩っぽさが有る」
こと位でしょうか。ご検討くださいませ。
●
2020 Onna Vino Rosso
オンナ・ヴィノ・ロッソ
【1~4本ずつしかないので・・どうにもご紹介の仕様もありません。】---以前のレヴューを掲載しています。
これでもかなり遠慮して1ケースずつ頼んで1~4本ずつですので・・もうテイスティングは無理ですね。申し訳ありません。
以下は以前のパーネヴィーノご紹介時のレヴューです。
━━━━━
【珍しく太田社長と意見が合った?!! 】
 ペッジョの2・・R212を飲ませていただきました。何しろ12本ずつしかないもので・・すみません。昔はいつでも有ったと記憶してますが、凄い人気のようです。
ペッジョの2・・R212を飲ませていただきました。何しろ12本ずつしかないもので・・すみません。昔はいつでも有ったと記憶してますが、凄い人気のようです。
太田社長もおっしゃるように、確かに「揮発酸」の存在は、グラスに注ぐと判るレベル・・結構有ります。
しかしながら、エキスの集中度が半端無く、揮発酸の存在を全く問題視しないかのような濃密な味わいなんですね。
濃密・・・と言っても、酸度が弱いイタリア南部のワインを想像すると全く当たりません。しっかりとバランス良く存在する酸と、ミネラリティも半端無く存在しています。
しかも揮発酸はその後、数値を上げるようなことは無く、完全に止まっている上体ですんで、時系列経過による味わいの深まりで、素晴らしい美しい膨らみある味わいになって行きます。これは美味しい!
因みに飲んでない方Peggio1の方が揮発酸の数値は低いようです。
これなら物凄く受けているのが理解できるな・・と思いました。
おそらく、ビオに慣れていない方でも何とかなるレベルです。ビオ好きにはもう・・これは堪らない味わいでしょう!
数が無いので・・何とか買占めのようなことは避けていただき、楽しんで飲んでいただければよいかなと思います。ジャンフランコもオオタの社長もそれを望んでいらっしゃるでしょう。
■新米ソムリエ oisy の熱血テイスティングコメント(一応、調理師免許も持ってます・・)
 Peggio-2 R212 Vino Rosso 2012 Panevino
Peggio-2 R212 Vino Rosso 2012 Panevino
アヴァンギャルドなサルディーニャのカンノナウです。アルコール度数15度からも想像できるようにワーオ!と驚くジューシーでインパクトのある完熟感です。そしてカシスやレーズンに刺激的なスパイス。揮発酸も出ていますが要素の一つに収まる範疇です。
怒りや失望を込めたワイン、だという事ですが、確かにこのワインからは得体のしれないパワーを感じるような。。。
おそらく、完熟感だけが目立つワインだと野暮ったいワインになってしまうんでしょうがちゃんとミネラリティが存在しているのでバランスが取れているのだと感じます。
イタリアのヴァンナチュール好きの方にはぜひ一度試してみてもらいたいピュアパワフルなワインです。
以下は以前のパーネヴィーノご紹介時のレヴューです。
━━━━━
【珍しく太田社長と意見が合った?!! 】
 ペッジョの2・・R212を飲ませていただきました。何しろ12本ずつしかないもので・・すみません。昔はいつでも有ったと記憶してますが、凄い人気のようです。
ペッジョの2・・R212を飲ませていただきました。何しろ12本ずつしかないもので・・すみません。昔はいつでも有ったと記憶してますが、凄い人気のようです。太田社長もおっしゃるように、確かに「揮発酸」の存在は、グラスに注ぐと判るレベル・・結構有ります。
しかしながら、エキスの集中度が半端無く、揮発酸の存在を全く問題視しないかのような濃密な味わいなんですね。
濃密・・・と言っても、酸度が弱いイタリア南部のワインを想像すると全く当たりません。しっかりとバランス良く存在する酸と、ミネラリティも半端無く存在しています。
しかも揮発酸はその後、数値を上げるようなことは無く、完全に止まっている上体ですんで、時系列経過による味わいの深まりで、素晴らしい美しい膨らみある味わいになって行きます。これは美味しい!
因みに飲んでない方Peggio1の方が揮発酸の数値は低いようです。
これなら物凄く受けているのが理解できるな・・と思いました。
おそらく、ビオに慣れていない方でも何とかなるレベルです。ビオ好きにはもう・・これは堪らない味わいでしょう!
数が無いので・・何とか買占めのようなことは避けていただき、楽しんで飲んでいただければよいかなと思います。ジャンフランコもオオタの社長もそれを望んでいらっしゃるでしょう。
■新米ソムリエ oisy の熱血テイスティングコメント(一応、調理師免許も持ってます・・)
 Peggio-2 R212 Vino Rosso 2012 Panevino
Peggio-2 R212 Vino Rosso 2012 Panevinoアヴァンギャルドなサルディーニャのカンノナウです。アルコール度数15度からも想像できるようにワーオ!と驚くジューシーでインパクトのある完熟感です。そしてカシスやレーズンに刺激的なスパイス。揮発酸も出ていますが要素の一つに収まる範疇です。
怒りや失望を込めたワイン、だという事ですが、確かにこのワインからは得体のしれないパワーを感じるような。。。
おそらく、完熟感だけが目立つワインだと野暮ったいワインになってしまうんでしょうがちゃんとミネラリティが存在しているのでバランスが取れているのだと感じます。
イタリアのヴァンナチュール好きの方にはぜひ一度試してみてもらいたいピュアパワフルなワインです。
アリアンナ・オッキピンティ
アリアンナ・オッキピンティ
イタリア Arianna Occhipinti シチリア
● 久しぶりのオッキピンティです。上級クラスを3アイテム、全てテイスティングしました!・・相当旨いですね~。それぞれに特徴が有りつつも、見事な出来栄えです。
 造り手:Arianna Occhipinti / アリアンナ オッキピンティ
造り手:Arianna Occhipinti / アリアンナ オッキピンティ
人:Arianna Occhipinti / アリアンナ オッキピンティ
産地(州):シチリア
ワイン:Grotte Alte、Il Frappato、Siccagno、SP68 Rosso、SP68 Bianco、Passo Nero
所在地:SP68 VITTORIA-PEDALINO KM 3.3 97019 VITTORIA (RG) SICILIA. ITALIA
Web : http://www.agricolaocchipinti.it/
シチリアの生産者、アリアンナ オッキピンティ。2004年が彼女のファーストヴィンテージです。2004年の収穫は、なんとまだミラノの醸造学校で卒論に取り組んでいる真っ最中でした。ミラノとシチリアを行ったり来たりしながら、無我夢中で収穫していたはずです。
デビューした当時は、生まれたてほやほやのひよっこで、彼女を”醸造家”という言葉で呼ぶのさえ、ためらわれたものでした。ところが、翌年イタリアで初ヴィンテージがリリースされるやいなや、あっという間に業界の話題をかっさらってしまったのです。というより、彼女の場合、デビューする前から、ちょっとした有名人になってしまったエピソードがあるのです。
少女の嘆きにおじさま殺到
それは2003年のこと。醸造学校に通う彼女が、ヴェロネッリという、イタリアのガストロノミー界では超有名な出版社の筆頭記者、ジーノ・ヴェロネッリに宛てて、手紙を書いたのです。そう長くはないあの文章が、彼女をここまで有名にしてしまうだなんて、彼女自身、想像していなかったことでしょう。
ヴェロネッリ誌の中で全文紹介されたその手紙は、後にガイドブックでも繰り返し賞賛されることになります。それは、ワイン造りを夢見るひとりの少女が、現代のワイン造りが過剰なテクニックと科学的アプローチによって、本来の神聖さを失ってゆくことを涙ながらに訴えた内容でした。
しかも、その嘆きがまた、非常に詩的でナイーブな表現に彩られているものですから(醸造学校で教えられることを鵜呑みにする友人達への心配やら、価値ある樹齢の高い樹が生産効率を重視するために抜かれていくことの悲しみなど)「こんな痛々しい少女を放っておいてはいけない!」とおじさまたちが立ち上がってしまったわけです。その手紙は、あちこちのフェアーで配られたり、新聞や雑誌、ワイン関係者のブログなどで引用され、彼女がワインをリリースする頃にはすでに「あのヴェロネッリへの手紙の娘か!」で通じるくらいに評判になっていました。
ですから、彼女のワインを味見する前から「全量くれ!あるだけ買うぞ」といわんばかりの勢いで、酒屋、エージェント、レストランなどの(なぜか、というかやはり)おじさま達が殺到し、少量しか生産されていなかった彼女のワインを取り合うようなデビュー戦となってしまったのです。
注目を集める地中海美人
今でも見られる光景ですが、自然派ワインのフェアなどに参加しているアリアンナを見ると、老若男女、もとい、老若男男、常に人だかりが出来ています。彼女のブースに真っ赤なバラの特大花束が用意されていて、驚かされたこともあります(犯人はパンテッレリア島の生産者でしたが)。
少し浅黒い肌に漆黒の長髪、りりしい眉毛、鋭い眼差しと…そしてやっぱり豊満なボディー。イタリア人の夢見る、地中海美人を絵に描いたような容姿の彼女。加えて、耳障りなほどのハスキーボイス。ヨーロッパでは、セクシーさの象徴です。それでいて、生産者の中ではダントツの若さ、かつ独身なのですから、どんな女性に対しても賞賛を態度で示さずにはいられないイタリア人が、放っておくわけがないのです。
問題は、ものすごく太り易いという家系的な体質で、収穫などで忙しい時期とそうでない時期の体重差が10kgくらいあったりします。日本料理を作ってあげると「ダイエット中だけど日本料理はヘルシーだから」と3人前くらい食べていました。2008年に来日して試飲会のためにあちこち回ったときにも随分と…。こんなこと書いたら怒られそうだけれど、あまり細かいことは気にしなさそう。ほれぼれするほど男っぽい性格なのです。
自ら理想を探し当て交渉する
ヴィットリア市外の小高い丘にあるパルメント(伝統的な大型のワイン醸造施設)。ここでは50人以上は入れそうな、足で踏むための巨大なステージと発酵槽、馬がひいていた木製のトルキオ(圧搾機)、発酵から熟成に使用される大樽を擁する熟成庫まで、すべて天然石で作られています。このような施設はイタリア各地で廃墟となって打ち捨てられていましたが、近年その魅力・実用性が再評価され、非常に高額で売買されるようになりました。このパルメントに一目ぼれしたアリアンナは、そこで自分のワイナリーを開くため、ミラノから帰省する度に様々な準備を始めます。
石灰質を多く含む白い軟石だけでつくられた、美しいパルメントの魅力もさることながら、夏は砂漠のように暑く乾燥してしまうヴィットリアにおいて、昼夜の寒暖差を生む海風が吹き抜ける丘と丘の狭間に建ち、さらに石灰質を多く含む白い土壌と粘土質の混在する周囲の土地が、長い間人の手に汚されずに何十ヘクタールも広がっているという最高のロケーションに、すっかり魅了されてしまったのです。
新しく植える畑だけでは何年も採算がとれませんから、その周辺で立地の良い区画を周り、樹齢の高い伝統的なアルベレッロで仕立ててある畑を捜しました。年老いた農夫たちに自分で交渉して、剪定から全ての畑作業をやらせてもらうという条件で、畑をいくつか借りられることになりました。
自分のセラーと畑を構えることになるヴィットリアという町は、彼女の生まれ育った町でもあり、また叔父のジュースト・オッキピンティがワイナリーCOS(コス)の拠点を構える土地でもあります。
彼女より20年以上も前からヴィットリアで、ジューストを含む建築家の学生3人が、やはり在学中に立ち上げてしまったワイナリーCOSは、シチリアの中だけでなく、イタリア全国で既に知名度が高く、彼の力を借りればもっと簡単に話は進んだはずですが、負けん気の強いアリアンナは、独自に自分の理想の畑を探しあて、交渉したのです。
大規模施設を手に入れる
小さい頃から叔父の後ばかり追い回し、ブドウ畑とセラーで多くの時間を過ごしていました。14歳のとき既に「いつか必ず自分のワインをリリースする」と決意していたといいます。10年と経たずにその夢を実現したアリアンナ。
若いのに頑固で、融通が利かない面もありますが、彼女の意思の強さは、シチリアのド田舎で閉鎖的な男社会である腰の曲がった農夫たちに、自分のやり方で畑を任せてくれという小娘の主張を受け入れさせるほどの迫力になるのでしょう。とはいえ、彼女はまだ学生。1ヘクタールの畑を借りる口約束はできても、不動産の売買など金銭的にも立場的にも手の届く話ではありません。建築家である父親(オッキピンティ一族は建築家か教師だけ。アリアンナの姉もパリでランドスケープのプロジェクトに参加。)が廃墟の買取り手続きを進めることになります。そしてなんと、翌年本当にそのパルメントを購入してしまうのです。パルメントにもさまざまな規模がありますが、アリアンナのパルメントは、3、4棟の建物とアラブ式庭園を擁するかなり大きな施設で、おそらく修復だけでも億単位の話だったはず。この辺りの成り行きが、アリアンナが地元の名士を親に持ち、叔父も有名なワイナリーの経営者、など、ワイン界のサラブレット、ラッキーガール的イメージで語られてしまう理由なのでしょう。確かに、醸造学校に通う一介の学生が、たとえどんなに才能に恵まれていたとしても、容易に実現できてしまう規模の話ではありません。
ヘビーなワイン哲学
同じ時期にエトナ火山でほぼ無一文でワイナリーをはじめたフランク・コーネリッセンが、初期のアリアンナ・オッキピンティのワイン造りにもっとも大きな影響を与えた人物になります。2002年と2003年の、まだ畑を探している段階では、車で片道3時間もあるヴィットリアからエトナまでの道のりを、毎週通ってきてはフランクの畑やセラーを見学して手伝ったり、他の生産者のワインを開けては一晩中語り合ったりしていました。偶然誕生日も同じこの二人は、もともと性格も嗜好も似通ったところが多いうえ、若いアリアンナはフランクに感化されて、当時彼に教えられてどっぷりはまってしまったニック・ケイヴの音楽のように重く、どっしりと彼女の上にヘビーなワイン哲学が覆いかぶさっていきました。
アリアンナも、実際にワインを造りを始める前までは、完全亜硫酸無添加でのワイン造りを念頭においていましたし、またフランクがそうであったように、亜硫酸を添加されたワインは屍に等しいなどというような、過激な哲学にまで傾きかけていた頃もありました。
自由な思想と不自由な借金
彼女のもっとも恵まれた点は、若い頃からイタリアやフランス、スペインなどの様々な生産者と交流を深めることができたことではなかったかと思います。
特に、エミリア・ロマーニャのラ・ストッパのエレナ・パンタレオーネ女史とは、アリアンナが中学生の頃からの長い付き合いで、今では一緒に食品会社を共同経営するほどの仲です。ピエルパオロ・ペコラーリの章でもでてきますが、エレナのワイナリーはそこそこに規模が大きく、リスクに対してのマネージメントのシビアさは、フランク・コーネリッセンのそれとは比べ物にならない責任をともないます。
彼女との付き合いや、ニコラ・ジョリー率いるルネッサンスAOCの生産者との交流、自然に造られたものであっても、飲んだ味わいとして決定的な欠点があると思わずにはいられないような亜硫酸無添加のワインとの出会い。そういった様々な要素が、彼女を冷静に、理想だけに飛びつくことなく、地に足をついた生産へと向かう道しるべとなっていったように思います。そして何より、スポンサーである父親は、良くも悪くも、アリアンナの自由を制限している最も大きな存在です。建築家であるブルーノは、巨額のお金を娘に貸した形でワイナリーの経営に携わっているのですが、この人がまた、異常に細かい。ボトリングされたワインを売るという、唯一の収入にありつくまでの長い時間に生じる、ありとあらゆる出費に関して、彼女を問い詰めてしまうのです。
実際に、食べてゆくのには困らないはずの彼女が、ワインを売り急いでしまいがちなのは、ひとえにブルーノの干渉が耐え難いから。ファーストヴィンテージのリリースのタイミングにしろ、もっと長い熟成を必要とするチェラスオーロD.O.C.G.の生産量にしろ、アリアンナ自身は、もっと寝かせてからリリースしたいのは山々だし、念願のチェラスオーロだって、ひと樽といわず沢山試してみたいはずだし、けれど、なんといっても、先立つものはお金。背に腹は変えられない、という切迫感が、始めてから数年は、彼女の言葉の端々からひしひしと感じられました。
与えられた中での最善
親子で壮絶な絶交状態が何ヶ月も続いたことも過去に一、二度ならずともあり、叔父のジューストが心配して仲を取り持とうとし、双方から拒絶されていたこともありました。
学生の頃は、父親の言うことを受け入れるしかありませんでしたが、ある程度業界でも認められ、自分のワインに商品としての自信も生まれてきています。そろそろ、自分のワインに関しては自分で責任をとる、と言い切りたいはずですが、あと何年かかれば父親への借金を返せるのでしょう。彼女には精神的負担が大きいのかもしれませんが、そういう制約があることは、必ずしも彼女にとってマイナス要素ばかりではなかったと思います。
金銭的に恵まれた環境にある生産者が、そうでない生産者から批判の対象にされてしまうのを頻繁に見てきましたが、後者が望まずして恵まれない状況に置かれたのと全く同様に、アリアンナだって、現在の、傍から見ればラッキーな立場を、自分の意志で選べたわけではないのです。
アリアンナのような立場の人間を、甘ちゃん呼ばわりするのは、やはり少し不公平な態度である気がします。その人が何を持っているのかということではなく、与えられた情況の中で、どう最善を尽くしているのかを、見てあげてほしいなと思ってしまいます。
 造り手:Arianna Occhipinti / アリアンナ オッキピンティ
造り手:Arianna Occhipinti / アリアンナ オッキピンティ人:Arianna Occhipinti / アリアンナ オッキピンティ
産地(州):シチリア
ワイン:Grotte Alte、Il Frappato、Siccagno、SP68 Rosso、SP68 Bianco、Passo Nero
所在地:SP68 VITTORIA-PEDALINO KM 3.3 97019 VITTORIA (RG) SICILIA. ITALIA
Web : http://www.agricolaocchipinti.it/
シチリアの生産者、アリアンナ オッキピンティ。2004年が彼女のファーストヴィンテージです。2004年の収穫は、なんとまだミラノの醸造学校で卒論に取り組んでいる真っ最中でした。ミラノとシチリアを行ったり来たりしながら、無我夢中で収穫していたはずです。
デビューした当時は、生まれたてほやほやのひよっこで、彼女を”醸造家”という言葉で呼ぶのさえ、ためらわれたものでした。ところが、翌年イタリアで初ヴィンテージがリリースされるやいなや、あっという間に業界の話題をかっさらってしまったのです。というより、彼女の場合、デビューする前から、ちょっとした有名人になってしまったエピソードがあるのです。
少女の嘆きにおじさま殺到
それは2003年のこと。醸造学校に通う彼女が、ヴェロネッリという、イタリアのガストロノミー界では超有名な出版社の筆頭記者、ジーノ・ヴェロネッリに宛てて、手紙を書いたのです。そう長くはないあの文章が、彼女をここまで有名にしてしまうだなんて、彼女自身、想像していなかったことでしょう。
ヴェロネッリ誌の中で全文紹介されたその手紙は、後にガイドブックでも繰り返し賞賛されることになります。それは、ワイン造りを夢見るひとりの少女が、現代のワイン造りが過剰なテクニックと科学的アプローチによって、本来の神聖さを失ってゆくことを涙ながらに訴えた内容でした。
しかも、その嘆きがまた、非常に詩的でナイーブな表現に彩られているものですから(醸造学校で教えられることを鵜呑みにする友人達への心配やら、価値ある樹齢の高い樹が生産効率を重視するために抜かれていくことの悲しみなど)「こんな痛々しい少女を放っておいてはいけない!」とおじさまたちが立ち上がってしまったわけです。その手紙は、あちこちのフェアーで配られたり、新聞や雑誌、ワイン関係者のブログなどで引用され、彼女がワインをリリースする頃にはすでに「あのヴェロネッリへの手紙の娘か!」で通じるくらいに評判になっていました。
ですから、彼女のワインを味見する前から「全量くれ!あるだけ買うぞ」といわんばかりの勢いで、酒屋、エージェント、レストランなどの(なぜか、というかやはり)おじさま達が殺到し、少量しか生産されていなかった彼女のワインを取り合うようなデビュー戦となってしまったのです。
注目を集める地中海美人
今でも見られる光景ですが、自然派ワインのフェアなどに参加しているアリアンナを見ると、老若男女、もとい、老若男男、常に人だかりが出来ています。彼女のブースに真っ赤なバラの特大花束が用意されていて、驚かされたこともあります(犯人はパンテッレリア島の生産者でしたが)。
少し浅黒い肌に漆黒の長髪、りりしい眉毛、鋭い眼差しと…そしてやっぱり豊満なボディー。イタリア人の夢見る、地中海美人を絵に描いたような容姿の彼女。加えて、耳障りなほどのハスキーボイス。ヨーロッパでは、セクシーさの象徴です。それでいて、生産者の中ではダントツの若さ、かつ独身なのですから、どんな女性に対しても賞賛を態度で示さずにはいられないイタリア人が、放っておくわけがないのです。
問題は、ものすごく太り易いという家系的な体質で、収穫などで忙しい時期とそうでない時期の体重差が10kgくらいあったりします。日本料理を作ってあげると「ダイエット中だけど日本料理はヘルシーだから」と3人前くらい食べていました。2008年に来日して試飲会のためにあちこち回ったときにも随分と…。こんなこと書いたら怒られそうだけれど、あまり細かいことは気にしなさそう。ほれぼれするほど男っぽい性格なのです。
自ら理想を探し当て交渉する
ヴィットリア市外の小高い丘にあるパルメント(伝統的な大型のワイン醸造施設)。ここでは50人以上は入れそうな、足で踏むための巨大なステージと発酵槽、馬がひいていた木製のトルキオ(圧搾機)、発酵から熟成に使用される大樽を擁する熟成庫まで、すべて天然石で作られています。このような施設はイタリア各地で廃墟となって打ち捨てられていましたが、近年その魅力・実用性が再評価され、非常に高額で売買されるようになりました。このパルメントに一目ぼれしたアリアンナは、そこで自分のワイナリーを開くため、ミラノから帰省する度に様々な準備を始めます。
石灰質を多く含む白い軟石だけでつくられた、美しいパルメントの魅力もさることながら、夏は砂漠のように暑く乾燥してしまうヴィットリアにおいて、昼夜の寒暖差を生む海風が吹き抜ける丘と丘の狭間に建ち、さらに石灰質を多く含む白い土壌と粘土質の混在する周囲の土地が、長い間人の手に汚されずに何十ヘクタールも広がっているという最高のロケーションに、すっかり魅了されてしまったのです。
新しく植える畑だけでは何年も採算がとれませんから、その周辺で立地の良い区画を周り、樹齢の高い伝統的なアルベレッロで仕立ててある畑を捜しました。年老いた農夫たちに自分で交渉して、剪定から全ての畑作業をやらせてもらうという条件で、畑をいくつか借りられることになりました。
自分のセラーと畑を構えることになるヴィットリアという町は、彼女の生まれ育った町でもあり、また叔父のジュースト・オッキピンティがワイナリーCOS(コス)の拠点を構える土地でもあります。
彼女より20年以上も前からヴィットリアで、ジューストを含む建築家の学生3人が、やはり在学中に立ち上げてしまったワイナリーCOSは、シチリアの中だけでなく、イタリア全国で既に知名度が高く、彼の力を借りればもっと簡単に話は進んだはずですが、負けん気の強いアリアンナは、独自に自分の理想の畑を探しあて、交渉したのです。
大規模施設を手に入れる
小さい頃から叔父の後ばかり追い回し、ブドウ畑とセラーで多くの時間を過ごしていました。14歳のとき既に「いつか必ず自分のワインをリリースする」と決意していたといいます。10年と経たずにその夢を実現したアリアンナ。
若いのに頑固で、融通が利かない面もありますが、彼女の意思の強さは、シチリアのド田舎で閉鎖的な男社会である腰の曲がった農夫たちに、自分のやり方で畑を任せてくれという小娘の主張を受け入れさせるほどの迫力になるのでしょう。とはいえ、彼女はまだ学生。1ヘクタールの畑を借りる口約束はできても、不動産の売買など金銭的にも立場的にも手の届く話ではありません。建築家である父親(オッキピンティ一族は建築家か教師だけ。アリアンナの姉もパリでランドスケープのプロジェクトに参加。)が廃墟の買取り手続きを進めることになります。そしてなんと、翌年本当にそのパルメントを購入してしまうのです。パルメントにもさまざまな規模がありますが、アリアンナのパルメントは、3、4棟の建物とアラブ式庭園を擁するかなり大きな施設で、おそらく修復だけでも億単位の話だったはず。この辺りの成り行きが、アリアンナが地元の名士を親に持ち、叔父も有名なワイナリーの経営者、など、ワイン界のサラブレット、ラッキーガール的イメージで語られてしまう理由なのでしょう。確かに、醸造学校に通う一介の学生が、たとえどんなに才能に恵まれていたとしても、容易に実現できてしまう規模の話ではありません。
ヘビーなワイン哲学
同じ時期にエトナ火山でほぼ無一文でワイナリーをはじめたフランク・コーネリッセンが、初期のアリアンナ・オッキピンティのワイン造りにもっとも大きな影響を与えた人物になります。2002年と2003年の、まだ畑を探している段階では、車で片道3時間もあるヴィットリアからエトナまでの道のりを、毎週通ってきてはフランクの畑やセラーを見学して手伝ったり、他の生産者のワインを開けては一晩中語り合ったりしていました。偶然誕生日も同じこの二人は、もともと性格も嗜好も似通ったところが多いうえ、若いアリアンナはフランクに感化されて、当時彼に教えられてどっぷりはまってしまったニック・ケイヴの音楽のように重く、どっしりと彼女の上にヘビーなワイン哲学が覆いかぶさっていきました。
アリアンナも、実際にワインを造りを始める前までは、完全亜硫酸無添加でのワイン造りを念頭においていましたし、またフランクがそうであったように、亜硫酸を添加されたワインは屍に等しいなどというような、過激な哲学にまで傾きかけていた頃もありました。
自由な思想と不自由な借金
彼女のもっとも恵まれた点は、若い頃からイタリアやフランス、スペインなどの様々な生産者と交流を深めることができたことではなかったかと思います。
特に、エミリア・ロマーニャのラ・ストッパのエレナ・パンタレオーネ女史とは、アリアンナが中学生の頃からの長い付き合いで、今では一緒に食品会社を共同経営するほどの仲です。ピエルパオロ・ペコラーリの章でもでてきますが、エレナのワイナリーはそこそこに規模が大きく、リスクに対してのマネージメントのシビアさは、フランク・コーネリッセンのそれとは比べ物にならない責任をともないます。
彼女との付き合いや、ニコラ・ジョリー率いるルネッサンスAOCの生産者との交流、自然に造られたものであっても、飲んだ味わいとして決定的な欠点があると思わずにはいられないような亜硫酸無添加のワインとの出会い。そういった様々な要素が、彼女を冷静に、理想だけに飛びつくことなく、地に足をついた生産へと向かう道しるべとなっていったように思います。そして何より、スポンサーである父親は、良くも悪くも、アリアンナの自由を制限している最も大きな存在です。建築家であるブルーノは、巨額のお金を娘に貸した形でワイナリーの経営に携わっているのですが、この人がまた、異常に細かい。ボトリングされたワインを売るという、唯一の収入にありつくまでの長い時間に生じる、ありとあらゆる出費に関して、彼女を問い詰めてしまうのです。
実際に、食べてゆくのには困らないはずの彼女が、ワインを売り急いでしまいがちなのは、ひとえにブルーノの干渉が耐え難いから。ファーストヴィンテージのリリースのタイミングにしろ、もっと長い熟成を必要とするチェラスオーロD.O.C.G.の生産量にしろ、アリアンナ自身は、もっと寝かせてからリリースしたいのは山々だし、念願のチェラスオーロだって、ひと樽といわず沢山試してみたいはずだし、けれど、なんといっても、先立つものはお金。背に腹は変えられない、という切迫感が、始めてから数年は、彼女の言葉の端々からひしひしと感じられました。
与えられた中での最善
親子で壮絶な絶交状態が何ヶ月も続いたことも過去に一、二度ならずともあり、叔父のジューストが心配して仲を取り持とうとし、双方から拒絶されていたこともありました。
学生の頃は、父親の言うことを受け入れるしかありませんでしたが、ある程度業界でも認められ、自分のワインに商品としての自信も生まれてきています。そろそろ、自分のワインに関しては自分で責任をとる、と言い切りたいはずですが、あと何年かかれば父親への借金を返せるのでしょう。彼女には精神的負担が大きいのかもしれませんが、そういう制約があることは、必ずしも彼女にとってマイナス要素ばかりではなかったと思います。
金銭的に恵まれた環境にある生産者が、そうでない生産者から批判の対象にされてしまうのを頻繁に見てきましたが、後者が望まずして恵まれない状況に置かれたのと全く同様に、アリアンナだって、現在の、傍から見ればラッキーな立場を、自分の意志で選べたわけではないのです。
アリアンナのような立場の人間を、甘ちゃん呼ばわりするのは、やはり少し不公平な態度である気がします。その人が何を持っているのかということではなく、与えられた情況の中で、どう最善を尽くしているのかを、見てあげてほしいなと思ってしまいます。
●
2017 Vino di Contrada Bombolieri Pettineo
ヴィノ・ディ・コントラーダ・ペッティネオ
【ヴィノ・ディ・コントラーダ・シリーズのペッティネオ は水はけの良い畑からのエレガントな味わいだそうです!】
こちらも4本のみの入荷、フラッパートの特別なクラスです。エレガントな味わいになる・・とのことですが、通常のシリーズのフラッパートやネロ・ダヴォラを飲ませていただいたところ、以前のような「力強さ」は抑えられ、どのキュヴェも結構にエレガント系に変わって来ていましたから・・もしかすると、「激エレガント系」なのかもしれません。
Copyright(C) 1998-2023 Noisy Wine [ Noisy's Wine Selects ] Reserved