頻繁なリロード禁止のお願い
大変お世話になっております。切実なお願いです。
ページのリロードが必要以上に行われるようになっています。サーバーへの過大な負荷でページ更新が滞る状況になっていますので、頻繁なリロードはお止めくださるようお願いいたします。
また、「503 Server is busy」のエラードギュメントページが表示され、一定時間アクセスが制限される場合がございます。いずれ元に戻りますが、そのようなことにならないようお願いいたします。
詳細ページ
ページのリロードが必要以上に行われるようになっています。サーバーへの過大な負荷でページ更新が滞る状況になっていますので、頻繁なリロードはお止めくださるようお願いいたします。
また、「503 Server is busy」のエラードギュメントページが表示され、一定時間アクセスが制限される場合がございます。いずれ元に戻りますが、そのようなことにならないようお願いいたします。
詳細ページ
■新着情報メールサービスのご登録
Noisy wine の新着情報メールサービスにご登録いただきますと、ご登録いただきましたメールアドレスに「タイムリーに」更新情報をお届けいたします。希少性のあるワインをご希望でしたら登録必須のサービスです。
■お届け情報他
現在以下の宛先に対し新着情報メールをお届けするすることが出来ません。世界情勢を反映してか、各社様メールのフィルターを厳しくしています。申し訳ありませんが gmail.com や yahoo.co.jp (yahoo.comは厳しいです) などのフリーアドレスに変更をご検討の上、再登録をお願いいたします。不明な方は最下段中央の「e-mail to noisy」よりお問い合わせください。
■新着情報メール不達の宛先(新規登録も出来ません)
icloud.com nifty.com me.com mac.com hi-ho.ne.jp tiki.ne.jp enjoy.ne.jp docomo.ne.jp plala.or.jp rim.or.jp suisui.ne.jp teabreak.jp outlook.com outlook.jp hotmail.co.jp hotmail.com msn.com infoseek.jp live.jp live.com
etc.
■お届け情報他
現在以下の宛先に対し新着情報メールをお届けするすることが出来ません。世界情勢を反映してか、各社様メールのフィルターを厳しくしています。申し訳ありませんが gmail.com や yahoo.co.jp (yahoo.comは厳しいです) などのフリーアドレスに変更をご検討の上、再登録をお願いいたします。不明な方は最下段中央の「e-mail to noisy」よりお問い合わせください。
■新着情報メール不達の宛先(新規登録も出来ません)
icloud.com nifty.com me.com mac.com hi-ho.ne.jp tiki.ne.jp enjoy.ne.jp docomo.ne.jp plala.or.jp rim.or.jp suisui.ne.jp teabreak.jp outlook.com outlook.jp hotmail.co.jp hotmail.com msn.com infoseek.jp live.jp live.com
etc.
noisy のお奨め

Spiegelau Grand Palais Exquisit
シュピゲラウ・グランパレ・エクスクイジット・レッドワイン 424ML
軽くて薄くて香り立ちの良い赤ワイン用グラスです。使い勝手良し!
Comming soon!

Spiegelau Grand Palais Exquisit
シュピゲラウ・グランパレ・エクスクイジット・ホワイト 340ML
軽くて薄くて香り立ちの良い白ワイン用グラスです。使い勝手良し!
Comming soon!
有 る と 便 利 な グ ッ ズ !
WEBの情報書込みもSSLで安心!


Noisy Wine [NOISY'S WINE SELECTS] のサイトでは、全ての通信をSSL/TLS 情報暗号化通信し、情報漏洩から保護しています。
◆◆Twitter 開始のご案内

時折、Twitter でつぶやき始めました。もう・・どうしようもなくしょうもない、手の施しようの無い内容が多いですが、気が向いたらフォローしてやってくださいね。RWGの徳さん、アルXXロのせんむとか・・結構性格が出るもんです。
https://twitter.com/noisywine
● ビオの素晴らしい生産者です!これも凄い!・・・でも白の方は好みが出るかな・・と思います。赤は全くの純粋無垢な味わいですので、どんな方でも「美味しい!」と言って頂けると確信しています!
 オスミッツァという文化、土地のワイン造りを守るため。マテイの静かな、そして揺るぐことのない決意。
オスミッツァという文化、土地のワイン造りを守るため。マテイの静かな、そして揺るぐことのない決意。
トリエステから北西に10km、内陸の町サレス。海までは15kmと離れていて、スロヴェニアとの国境までは2~3kmと近い。標高は260~300m、大地のほとんどが固い岩石(石灰岩)、岩盤質でできており、表層土がほとんどないのが特徴。カルソ地域はこうしたカルスト地形、石灰岩、鍾乳石などの水溶性の岩石が覆い尽くす土地。そのため、現在ある畑はすべて人工的に造られたもの。上の岩石を取り除いて、海岸の町(ドゥイーノ)から赤土を運び入れて作った。また雨が少なく、そして何より冬に吹く強い風ボーラ(Bora)は風速150km、気温はマイナス8℃にもなり、立っていられないほどの強い風は、植物の栽培にとってかなり厳しい環境を作りだしている。オリーヴなど根の深く伸びない樹は簡単に倒れてしまう、建物も風に強い石造りの街並みも特徴的。
 ほとんどの土地はこの石灰質の岩盤に覆われており表層土が全くないため、伝統的に農業よりも畜産、放牧といった産業が盛んにおこなわれてきた地域。サレスの町に、今でも残っている地域伝統のオスミッツァ※を現在も続けているスケルリ家。
ほとんどの土地はこの石灰質の岩盤に覆われており表層土が全くないため、伝統的に農業よりも畜産、放牧といった産業が盛んにおこなわれてきた地域。サレスの町に、今でも残っている地域伝統のオスミッツァ※を現在も続けているスケルリ家。
地域の現実的な問題(離農、人口減少、食文化の希薄化、、、etc)の中、薄れていくオスミッツァの文化。このサレスの文化・伝統を愛し、本気で残したいと立ち上がった次期当主こそ、マテイスケルリである。
※オスミッツァ・・・(カルソ地域に限られた、農家が一時的に開くオステリアのようなもの。田舎道の道端に木の枝が飾られているのが目印。そこの家で造ったワインに、生ハム、チーズ、野菜料理などを提供。語源は「Osem」はスラブ語で「8」を意味し、オーストリア統治下、農家が食事処を出すのは禁止されていた中、18世紀末に「農家は1年間に8日間だけお店を開くことを許す」という皇帝令が布告されたことで始まり、現在も一部のカルソ地域で行われている。)
 2006年、まだ27歳という若さでありながら、自家醸造用の1haの畑を基本に周囲の放棄されたブドウ畑(高齢化、離農が進み、多くの畑が手入れさえされていない)を借り、自家醸造・ボトル詰め用のワインの生産を開始。畑は代々引き継いできた樹齢の高い畑(40~60年)が0.6ha、他には2003年、2006年と自ら切り開いた畑が各0.5ha。
2006年、まだ27歳という若さでありながら、自家醸造用の1haの畑を基本に周囲の放棄されたブドウ畑(高齢化、離農が進み、多くの畑が手入れさえされていない)を借り、自家醸造・ボトル詰め用のワインの生産を開始。畑は代々引き継いできた樹齢の高い畑(40~60年)が0.6ha、他には2003年、2006年と自ら切り開いた畑が各0.5ha。
どちらも放棄地をゼロから開墾(地中にある分厚い石灰岩層を削岩機で砕き、表土は近隣に点在するDulineと呼ばれる場所より赤土を運ぶ、という途方もない作業、、。)、高密植、アルベレッロ仕立てにてヴィトフスカ、マルヴァージアイストゥリアーナを植樹。テッラーノは樹の特徴からグイヨーに仕立てる。
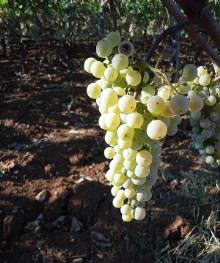
開墾当初のみ、微量ながら堆肥を使用したものの、高樹齢の土地や2年目以降の畑では一切の肥料、堆肥を使わない。もちろん薬品類も一切使用せず、最低限の銅と硫黄物のみ。基本的には畑の自然環境を整えることで土地自体のバランス感、しいてはブドウ樹の自己管理能力を高めることを尊重。収穫した果実は除梗したのち、開放式の大樽にて約2週間のマセレーション。野生酵母による醗酵を行う。途中一切の温度管理を行わない。
状況として醸造学的に“危険”といわれる状況に陥った場合でも、果実的な安定が取れている限り“欠陥のあるワイン”にはなりえない、と考えるマテイ。圧搾後約12か月間、大樽にて熟成。SO2の使用はボトル詰めの際にごく少量のみ行う。

果皮の恩恵を受けたヴィトフスカ、マルヴァージア、それでいて全くと言っていいほど「強さ」というものを感じない。土地由来の重厚なミネラル分を持ちつつも圧倒的なしなやかさ、親しみやすさを持ったワイン。
マテイ曰く
「自分にとってのワインとは、偉大な物というよりも、もっと昔から身近にあったものなんだ。自分の開墾した畑の成長とともにワインの力も増していくと思うけど、このサレスのワイン、オスミッツァの雰囲気を忘れないワインを造り続けていきたいと思う。」
経験値の少なさ、畑の若さをものともしない、マテイの柔軟かつ、感覚的な栽培・醸造哲学。土地への強い愛情と、地域の伝統を守る彼の決意と行動に心からの敬意と表したい。



 オスミッツァという文化、土地のワイン造りを守るため。マテイの静かな、そして揺るぐことのない決意。
オスミッツァという文化、土地のワイン造りを守るため。マテイの静かな、そして揺るぐことのない決意。 トリエステから北西に10km、内陸の町サレス。海までは15kmと離れていて、スロヴェニアとの国境までは2~3kmと近い。標高は260~300m、大地のほとんどが固い岩石(石灰岩)、岩盤質でできており、表層土がほとんどないのが特徴。カルソ地域はこうしたカルスト地形、石灰岩、鍾乳石などの水溶性の岩石が覆い尽くす土地。そのため、現在ある畑はすべて人工的に造られたもの。上の岩石を取り除いて、海岸の町(ドゥイーノ)から赤土を運び入れて作った。また雨が少なく、そして何より冬に吹く強い風ボーラ(Bora)は風速150km、気温はマイナス8℃にもなり、立っていられないほどの強い風は、植物の栽培にとってかなり厳しい環境を作りだしている。オリーヴなど根の深く伸びない樹は簡単に倒れてしまう、建物も風に強い石造りの街並みも特徴的。
 ほとんどの土地はこの石灰質の岩盤に覆われており表層土が全くないため、伝統的に農業よりも畜産、放牧といった産業が盛んにおこなわれてきた地域。サレスの町に、今でも残っている地域伝統のオスミッツァ※を現在も続けているスケルリ家。
ほとんどの土地はこの石灰質の岩盤に覆われており表層土が全くないため、伝統的に農業よりも畜産、放牧といった産業が盛んにおこなわれてきた地域。サレスの町に、今でも残っている地域伝統のオスミッツァ※を現在も続けているスケルリ家。地域の現実的な問題(離農、人口減少、食文化の希薄化、、、etc)の中、薄れていくオスミッツァの文化。このサレスの文化・伝統を愛し、本気で残したいと立ち上がった次期当主こそ、マテイスケルリである。
※オスミッツァ・・・(カルソ地域に限られた、農家が一時的に開くオステリアのようなもの。田舎道の道端に木の枝が飾られているのが目印。そこの家で造ったワインに、生ハム、チーズ、野菜料理などを提供。語源は「Osem」はスラブ語で「8」を意味し、オーストリア統治下、農家が食事処を出すのは禁止されていた中、18世紀末に「農家は1年間に8日間だけお店を開くことを許す」という皇帝令が布告されたことで始まり、現在も一部のカルソ地域で行われている。)
 2006年、まだ27歳という若さでありながら、自家醸造用の1haの畑を基本に周囲の放棄されたブドウ畑(高齢化、離農が進み、多くの畑が手入れさえされていない)を借り、自家醸造・ボトル詰め用のワインの生産を開始。畑は代々引き継いできた樹齢の高い畑(40~60年)が0.6ha、他には2003年、2006年と自ら切り開いた畑が各0.5ha。
2006年、まだ27歳という若さでありながら、自家醸造用の1haの畑を基本に周囲の放棄されたブドウ畑(高齢化、離農が進み、多くの畑が手入れさえされていない)を借り、自家醸造・ボトル詰め用のワインの生産を開始。畑は代々引き継いできた樹齢の高い畑(40~60年)が0.6ha、他には2003年、2006年と自ら切り開いた畑が各0.5ha。どちらも放棄地をゼロから開墾(地中にある分厚い石灰岩層を削岩機で砕き、表土は近隣に点在するDulineと呼ばれる場所より赤土を運ぶ、という途方もない作業、、。)、高密植、アルベレッロ仕立てにてヴィトフスカ、マルヴァージアイストゥリアーナを植樹。テッラーノは樹の特徴からグイヨーに仕立てる。
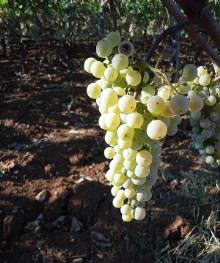
開墾当初のみ、微量ながら堆肥を使用したものの、高樹齢の土地や2年目以降の畑では一切の肥料、堆肥を使わない。もちろん薬品類も一切使用せず、最低限の銅と硫黄物のみ。基本的には畑の自然環境を整えることで土地自体のバランス感、しいてはブドウ樹の自己管理能力を高めることを尊重。収穫した果実は除梗したのち、開放式の大樽にて約2週間のマセレーション。野生酵母による醗酵を行う。途中一切の温度管理を行わない。
状況として醸造学的に“危険”といわれる状況に陥った場合でも、果実的な安定が取れている限り“欠陥のあるワイン”にはなりえない、と考えるマテイ。圧搾後約12か月間、大樽にて熟成。SO2の使用はボトル詰めの際にごく少量のみ行う。

果皮の恩恵を受けたヴィトフスカ、マルヴァージア、それでいて全くと言っていいほど「強さ」というものを感じない。土地由来の重厚なミネラル分を持ちつつも圧倒的なしなやかさ、親しみやすさを持ったワイン。
マテイ曰く
「自分にとってのワインとは、偉大な物というよりも、もっと昔から身近にあったものなんだ。自分の開墾した畑の成長とともにワインの力も増していくと思うけど、このサレスのワイン、オスミッツァの雰囲気を忘れないワインを造り続けていきたいと思う。」
経験値の少なさ、畑の若さをものともしない、マテイの柔軟かつ、感覚的な栽培・醸造哲学。土地への強い愛情と、地域の伝統を守る彼の決意と行動に心からの敬意と表したい。



●2011 Terrano I.G.T.Rosso
テッラーノ・I.G.T.
【新世代ビオ!要注目の造り手です!地場品種をナチュラルに仕上げています!特に赤は実に純・ピュアです!】
おっかし~な・・・ヴィトフスカの写真がどうあっても見当たらないんですよね・・。でもしっかり飲んでますんで大丈夫・・信用してください・・。
白はヴィトフスカ100%。圧搾時にSo2を使わないので、色合いは落ちてます。かなり黄ばんでいると言うか、赤い色が入って来ていると思ってください。
そして味わいですが、緑のニュアンスを非常に感じる、まさにビオ好きが求める味わいかと思います。揮発酸もほぼ無く、お茶っぽい(グリーンティー)ニュアンスや、ハーブ、花、スパイス、黄色・白の果実がたっぷり有ります。
中域はしっかり有るのですが、So2をしっかり使用した普通の白とは全く違う、やや襞を感じるものです。普通の白ですと、そこにナトリウム系、カルシウム系のミネラリティの恩恵の連続性を見るんですが、このビオ系のヴィトフスカには、「そこには」見当たりません。なので、少し盛り上がりに欠ける様...
白はヴィトフスカ100%。圧搾時にSo2を使わないので、色合いは落ちてます。かなり黄ばんでいると言うか、赤い色が入って来ていると思ってください。
そして味わいですが、緑のニュアンスを非常に感じる、まさにビオ好きが求める味わいかと思います。揮発酸もほぼ無く、お茶っぽい(グリーンティー)ニュアンスや、ハーブ、花、スパイス、黄色・白の果実がたっぷり有ります。
中域はしっかり有るのですが、So2をしっかり使用した普通の白とは全く違う、やや襞を感じるものです。普通の白ですと、そこにナトリウム系、カルシウム系のミネラリティの恩恵の連続性を見るんですが、このビオ系のヴィトフスカには、「そこには」見当たりません。なので、少し盛り上がりに欠ける様...
●2011 Vitovska I.G.T.Bianco
ヴィトフスカ・I.G.T.
【新世代ビオ!要注目の造り手です!地場品種をナチュラルに仕上げています!特に赤は実に純・ピュアです!】
おっかし~な・・・ヴィトフスカの写真がどうあっても見当たらないんですよね・・。でもしっかり飲んでますんで大丈夫・・信用してください・・。
白はヴィトフスカ100%。圧搾時にSo2を使わないので、色合いは落ちてます。かなり黄ばんでいると言うか、赤い色が入って来ていると思ってください。
そして味わいですが、緑のニュアンスを非常に感じる、まさにビオ好きが求める味わいかと思います。揮発酸もほぼ無く、お茶っぽい(グリーンティー)ニュアンスや、ハーブ、花、スパイス、黄色・白の果実がたっぷり有ります。
中域はしっかり有るのですが、So2をしっかり使用した普通の白とは全く違う、やや襞を感じるものです。普通の白ですと、そこにナトリウム系、カルシウム系のミネラリティの恩恵の連続性を見るんですが、このビオ系のヴィトフスカには、「そこには」見当たりません。なので、少し盛り上がりに欠ける様...
白はヴィトフスカ100%。圧搾時にSo2を使わないので、色合いは落ちてます。かなり黄ばんでいると言うか、赤い色が入って来ていると思ってください。
そして味わいですが、緑のニュアンスを非常に感じる、まさにビオ好きが求める味わいかと思います。揮発酸もほぼ無く、お茶っぽい(グリーンティー)ニュアンスや、ハーブ、花、スパイス、黄色・白の果実がたっぷり有ります。
中域はしっかり有るのですが、So2をしっかり使用した普通の白とは全く違う、やや襞を感じるものです。普通の白ですと、そこにナトリウム系、カルシウム系のミネラリティの恩恵の連続性を見るんですが、このビオ系のヴィトフスカには、「そこには」見当たりません。なので、少し盛り上がりに欠ける様...
Copyright(C) 1998-2023 Noisy Wine [ Noisy's Wine Selects ] Reserved






















