頻繁なリロード禁止のお願い
大変お世話になっております。切実なお願いです。
ページのリロードが必要以上に行われるようになっています。サーバーへの過大な負荷でページ更新が滞る状況になっていますので、頻繁なリロードはお止めくださるようお願いいたします。
また、「503 Server is busy」のエラードギュメントページが表示され、一定時間アクセスが制限される場合がございます。いずれ元に戻りますが、そのようなことにならないようお願いいたします。
詳細ページ
ページのリロードが必要以上に行われるようになっています。サーバーへの過大な負荷でページ更新が滞る状況になっていますので、頻繁なリロードはお止めくださるようお願いいたします。
また、「503 Server is busy」のエラードギュメントページが表示され、一定時間アクセスが制限される場合がございます。いずれ元に戻りますが、そのようなことにならないようお願いいたします。
詳細ページ
■新着情報メールサービスのご登録
Noisy wine の新着情報メールサービスにご登録いただきますと、ご登録いただきましたメールアドレスに「タイムリーに」更新情報をお届けいたします。希少性のあるワインをご希望でしたら登録必須のサービスです。
■お届け情報他
現在以下の宛先に対し新着情報メールをお届けするすることが出来ません。世界情勢を反映してか、各社様メールのフィルターを厳しくしています。申し訳ありませんが gmail.com や yahoo.co.jp (yahoo.comは厳しいです) などのフリーアドレスに変更をご検討の上、再登録をお願いいたします。不明な方は最下段中央の「e-mail to noisy」よりお問い合わせください。
■新着情報メール不達の宛先(新規登録も出来ません)
icloud.com nifty.com me.com mac.com hi-ho.ne.jp tiki.ne.jp enjoy.ne.jp docomo.ne.jp plala.or.jp rim.or.jp suisui.ne.jp teabreak.jp outlook.com outlook.jp hotmail.co.jp hotmail.com msn.com infoseek.jp live.jp live.com
etc.
■お届け情報他
現在以下の宛先に対し新着情報メールをお届けするすることが出来ません。世界情勢を反映してか、各社様メールのフィルターを厳しくしています。申し訳ありませんが gmail.com や yahoo.co.jp (yahoo.comは厳しいです) などのフリーアドレスに変更をご検討の上、再登録をお願いいたします。不明な方は最下段中央の「e-mail to noisy」よりお問い合わせください。
■新着情報メール不達の宛先(新規登録も出来ません)
icloud.com nifty.com me.com mac.com hi-ho.ne.jp tiki.ne.jp enjoy.ne.jp docomo.ne.jp plala.or.jp rim.or.jp suisui.ne.jp teabreak.jp outlook.com outlook.jp hotmail.co.jp hotmail.com msn.com infoseek.jp live.jp live.com
etc.
noisy のお奨め

Spiegelau Grand Palais Exquisit
シュピゲラウ・グランパレ・エクスクイジット・レッドワイン 424ML
軽くて薄くて香り立ちの良い赤ワイン用グラスです。使い勝手良し!
Comming soon!

Spiegelau Grand Palais Exquisit
シュピゲラウ・グランパレ・エクスクイジット・ホワイト 340ML
軽くて薄くて香り立ちの良い白ワイン用グラスです。使い勝手良し!
Comming soon!
有 る と 便 利 な グ ッ ズ !
WEBの情報書込みもSSLで安心!


Noisy Wine [NOISY'S WINE SELECTS] のサイトでは、全ての通信をSSL/TLS 情報暗号化通信し、情報漏洩から保護しています。
◆◆Twitter 開始のご案内

時折、Twitter でつぶやき始めました。もう・・どうしようもなくしょうもない、手の施しようの無い内容が多いですが、気が向いたらフォローしてやってくださいね。RWGの徳さん、アルXXロのせんむとか・・結構性格が出るもんです。
https://twitter.com/noisywine
ドメーヌ・クロード・デュガ
クロード・デュガ
フランス Domaine Claude Dugat ブルゴーニュ
● クロード・デュガです。こちらは正規の「フィネスさん」ものです。ようやくチェック・・テイスティング終了しました。・・いや~・・村名ジュヴレの2014年がかなり旨いです!
1990年代中盤の判り易く価格も適正だったクロード・デュガさんのワインならちゃんとご紹介しましたが、誰の性だか・・某エージェントさんと某評価機関のジョイントからの差し金か、ワインの濃度の上昇とともに暴騰してしまい、人気に翳りが出始め、折りしもネット販売が認知されはじめた頃には、某ショッピングモールではお山の大将たちの陣取り安売り合戦の目玉にもされて、ほとんど原価販売アイテムになってしまってからは、noisyは・・
「・・アホか・・」
と手を引いてしまいましたので、余りご紹介しない状況になっていました。
価格の方は流石にもう下がりませんが、品質が良ければ・・そして、そこに意味が見出せれば、扱うことはヤブサカでは無いので・・フィネスさんのアイテムを扱うことにしました。
で、今回ご紹介の2/3アイテムを飲んで・・ある意味少しショックを受けました。村名ジュヴレの2014年が目茶旨いんですよ!・・まぁ、このプライスで大したことが無いなどと書いた日にゃ、暗い夜道を無防備には歩けなくなっちゃいますから。2013年も旨かったですけどね。
冗談は置いておくとして、2013年よりも下がったこのプライスとこの質なら必ず納得いただけると確認、確信してのご案内です。
13世紀に建てられた教会をそのままカーヴとしている当家は現在約6haの葡萄畑を所有しています。物腰静かで高貴な印象の現当主クロードデュガ氏は、良いワインができる条件は葡萄の品質の良さという考えに基づき、畑の手入れを入念に行い、化学肥料は使わずに健康な葡萄を育てています。
また、庭でJonquille(ジョンキーユ:黄水仙の花という意味)という名前の牝馬を飼っていて、小さな区画や古木の区画を耕させています。特に古木の畑は葡萄の根が地中に広く張り巡らされていてトラクターで根を傷つけたり、トラクターの重みで土を固くしてしまったりするのでこの牝馬が活躍しています。収穫された葡萄は温度調節の容易な、酒石がびっしり付着しているコンクリートタンクに運ばれ、アルコール発酵が行われます。新樽がズラリと並んだ地上のカーヴでは最新のヴィンテージのワインのマロラクティック醗酵が行われ、地下水が壁から染み出ている、砂利が敷き詰められた地下のカーヴではその前年のワインが熟成されています。瓶詰めの際にはフィルターもコラージュも行いませんが、ワインは非常に透明感があります。

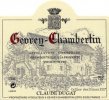
1990年代中盤の判り易く価格も適正だったクロード・デュガさんのワインならちゃんとご紹介しましたが、誰の性だか・・某エージェントさんと某評価機関のジョイントからの差し金か、ワインの濃度の上昇とともに暴騰してしまい、人気に翳りが出始め、折りしもネット販売が認知されはじめた頃には、某ショッピングモールではお山の大将たちの陣取り安売り合戦の目玉にもされて、ほとんど原価販売アイテムになってしまってからは、noisyは・・
「・・アホか・・」
と手を引いてしまいましたので、余りご紹介しない状況になっていました。
価格の方は流石にもう下がりませんが、品質が良ければ・・そして、そこに意味が見出せれば、扱うことはヤブサカでは無いので・・フィネスさんのアイテムを扱うことにしました。
で、今回ご紹介の2/3アイテムを飲んで・・ある意味少しショックを受けました。村名ジュヴレの2014年が目茶旨いんですよ!・・まぁ、このプライスで大したことが無いなどと書いた日にゃ、暗い夜道を無防備には歩けなくなっちゃいますから。2013年も旨かったですけどね。
冗談は置いておくとして、2013年よりも下がったこのプライスとこの質なら必ず納得いただけると確認、確信してのご案内です。
13世紀に建てられた教会をそのままカーヴとしている当家は現在約6haの葡萄畑を所有しています。物腰静かで高貴な印象の現当主クロードデュガ氏は、良いワインができる条件は葡萄の品質の良さという考えに基づき、畑の手入れを入念に行い、化学肥料は使わずに健康な葡萄を育てています。
また、庭でJonquille(ジョンキーユ:黄水仙の花という意味)という名前の牝馬を飼っていて、小さな区画や古木の区画を耕させています。特に古木の畑は葡萄の根が地中に広く張り巡らされていてトラクターで根を傷つけたり、トラクターの重みで土を固くしてしまったりするのでこの牝馬が活躍しています。収穫された葡萄は温度調節の容易な、酒石がびっしり付着しているコンクリートタンクに運ばれ、アルコール発酵が行われます。新樽がズラリと並んだ地上のカーヴでは最新のヴィンテージのワインのマロラクティック醗酵が行われ、地下水が壁から染み出ている、砂利が敷き詰められた地下のカーヴではその前年のワインが熟成されています。瓶詰めの際にはフィルターもコラージュも行いませんが、ワインは非常に透明感があります。


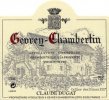
●2014 Bourgogne Rouge
ブルゴーニュ・ルージュ
【クロード・デュガのスタイル確定!凝縮感は以前のままに、濃度を無理に出さず、エレガントで美しさを表現するように!】
 2013年ものに続き、2014年ものをフィネスさんから分けていただきました。クロード・デュガについてはもう、皆さんの方が詳しい位かとは思いますが、2014年の仕上がりはどうかと、A.C.ブルゴーニュとA.C.ジュヴレ=シャンベルタンを飲んでみました。傾向は2013年と同様でしたね。
2013年ものに続き、2014年ものをフィネスさんから分けていただきました。クロード・デュガについてはもう、皆さんの方が詳しい位かとは思いますが、2014年の仕上がりはどうかと、A.C.ブルゴーニュとA.C.ジュヴレ=シャンベルタンを飲んでみました。傾向は2013年と同様でしたね。しかし、濃密さは2014年に分が有りますし、このスタイルでデュガさんは固まるのかな?・・と、noisy 的判断の一応の結論を見ましたので、それを少しお話しましょう。
クロード・デュガさんと言えば、濃密でバリック派でしたよね。90年代のデュガさんの日本での評価は非常に高く、今も上級キュヴェは・・高いですが、非常に人気が有ります。
しかし、1999~2000年頃に入ると希少だったクロード・デュガさんのワインが高騰したんですね。某**店さん(フィネスさんじゃないですよ)が、
「デュガさんのワインは日本ではプレミアが付いて売られてますよ・・」
等とお伝えしたらしいです。あくまで聞いた話ですけど。それで蔵出しが上がったとかなんとか・・。
で、さらに高騰したことも有って、ネットのワイン屋が目玉商品にしてしまい、価格競争で日々値が下がり、結局原価販売をするようになってしまいまして・・今の状況です。でもフィネスさんは決してそんな事に足を突っ込まず、ドメーヌとのパートナーシップを重要に販売していたと記憶しています。
また、時代もPKさんに踊らされた90年代を反省してか、濃いピノに飽きたか・・、ブルゴーニュらしいエレガントなワインに回帰して行って、現在に至るんですね。
デュガさんも2010年くらいまでは、それでも濃密、凝縮感たっぷりなワインにしていたと・・思います。しかしながらその凝縮感は衰えないまでも「濃密・濃厚」と言う部分に関しては、
「今では決してそのようなスタンスでは無い。」
と言えると思います。エレガント系だが凝縮感はちゃんと有りますし、テロワールをしっかり現していると思います。
しかしながら、そうなってくると・・若いうちには「濃さ」で飲ませていた部分が欠如しますよね?・・そうなると、ACブルクラスはどうしてもリリース直後は「硬い」感じになっちゃうんですね・・。
バリック派は辞めてないようですから、緩やかな酸化を促すバリックの多量の使用は、リリース直後の抜栓では、酸素と出会った時の急激な変化は望めず、すでに総量的に飽和している酸素含有率を持っていますんでそのようになっちゃうんでしょう。
2014年もののこのACブルゴーニュは、2013年と同様、ACジュヴレと比較するとやや硬いです。しかも、彼のワインは・・
「3~15年経過して初めて本性を発揮する」
タイプが多いので、若い時の濃度を捨てたクロード・デュガさんのワインは、決して外向きのベクトルに向かず、内向きなベクトルを持っていると言えます。それが熟成・・時間の経過で徐々にベクトルの向きが外向きになってきまして、開いて来ると・・
「滅茶官能的!まるで右岸のボルドーが熟したんじゃないかと思えるほどのパフォーマンスを見せる」
ことになります。以前、古いデュガさんのジュヴレを、あるワイン会で・・まぁ、ずいぶん前に抜栓されていたのを遅刻して行ったのも有りますが、「ポムロル」と言ったのを覚えてます。あ・・、思い出した・・そのデュガを出したが今のオルヴォーの社長さんですよ。
で、今でもその方向性はしっかりみえます。飲めなくは無いですがやや硬いのを感じつつ、男っぽい、ドライでタイトなやや黒い果実と出会うことになるでしょう。ワインは美しいですし、ミネラリティもたっぷりです。色合いも非常に綺麗ですよね?
それに、何と言ってもこのプライスです。随分安くなりましたよね。かなりお得になったと思います。是非セラーで少し寝かせつつ、タイミングを見てお楽しみくださいませ。
以下は2013年のこのワインのレヴューです。
━━━━━
【悩んでいたか?・・のクロード・デュガ復活の年!この凄い味わいは確認しておくべきではないでしょうか!】
 え~・・ACブルの写真が見当たらないので掲載していませんが、2013年はもう2度ほど飲んでますんで・・はい・・ほぼ完璧に理解したつもりです。
え~・・ACブルの写真が見当たらないので掲載していませんが、2013年はもう2度ほど飲んでますんで・・はい・・ほぼ完璧に理解したつもりです。で、価格の安いACブルをお奨めしたいところなんですが、残念ながら「今飲んで」の評価を無理して上げることなど出来ませんで、残念ながら3年後を目処にとさせていただきました。
しかし村名ジュヴレの素晴らしさにはビックリです。フィネスさんの扱いの良さを感じることも出来るかと思います。
上記では、「クロード・デュガはしばらく扱って無かった」と書きましたが、定期的では無いにせよ、ちょくちょく飲んでいましたので、彼のワインの変化も気付いていました。
昨年も2000年のグリオットを開けたりして・・良かったですよ。
そして2008年もの位から、ブローカーものを中心に時折ご紹介させていただいています。現在もブローカーものの2011年村名ジュヴレを新着に掲載しています。・・まぁ、価格差は見ないでくださいね・・別に「ボッてる」訳じゃぁ無いんです。本当に仕入れの価格がね・・違うんですよ。
で、2008年ものの記事の時にはしっかり書いた記憶が有るんですが、
「もしかしたらデュガは迷っている?・・悩んでいる?」
みたいな記事です。
それまで、まるでメルロかと思えるような重厚さのある味筋だったものが、エキス系の綺麗なものに変化していたんですね。ただし、受け取る側の印象が予定調和で終わらなかった性も有るとは言え、余りの変化、そして何となくの「中途半端感」が有ったのは事実です。
綺麗なのは綺麗なんだが、何か途中で途切れてしまうような・・例えば余韻ですね・・。続いていて、長くない・・とは言わないものの、何となく途中で途切れ・・弱弱しく復活・・で途切れ・・みたいな感じでしょうか。中域も何となく「イビツ」な形状で、素直に丸みがあるとも言えないような・・です。
ところがですね・・この2013年の村名ジュヴレ・・エライ美しいじゃないですか!・・エキスがたっぷりで、しかも美しいパレットを描きます。いつものデュガさんのように、やや遅い収穫を思わせる「黒味」を持ち、「赤味」も当然ながら有るんですが、黒味から赤味に向かう部分に途切れは無く、何層にも自然なグラデュエーションが有るんですよ。滑らかで深く、非常にドライです。
それに加え、ジュヴレらしい質のミネラリティもしっかり持ち、濡れたような質感、アロマの上がりのスピードはまるで自然派並みでしかも美しいです。「す~っ」と入って来ておだやかに質感を見せ、中盤以降から消えるまでの間に様々な表現をしてくれます。
例えばフーリエはもっと赤く、若々しい部分の高い周波数領域の表現がちゃんとしていますが、デュガさんはその部分はやや黒味で覆われ、より低い周波数領域での表現になります。
しかし、この厳冬期のように品温が下がりやすい時期には、フーリエのような全域にバランスの良い、赤い味わい中心のブルゴーニュは、中域と低域のパフォーマンスをやや落とします。デュガさんは高い周波数領域は黒で置換していますから、フレッシュな部分を持たず、中高域、中域、低域をしっかり持ち、品温度が下がってもバランスを崩さないんですね。
なので、13度~14度で飲み始めても・・重厚で香りも上がり、全体のバランスも素晴らしいんです。調子に乗って随分と飲んでしまいました。
反面、ACブルは、確かに村名ジュヴレにそっくりなんですが・・残念ながら村名ほどのポテンシャルが不足しています。美味しく飲めますが15度ほどまでに上げないと厳しいですし、その表情はやや硬く、内向的です。しかし3年ほど置きますと持っているポテンシャルを発揮しはじめ、村名と同様なパフォーマンスを見せるでしょう。
つまりよりタイトに薄く仕上がって居るわけですね。なので熟成に時間が掛かっちゃう訳です。
それにしても村名ジュヴレはビックリするほど旨かった!・・質も素晴らしいです。このプライスはこの質なら仕方が無いと確認できるでしょう!コンディションも素晴らしいです。是非飲んで欲しい・・です!ご検討くださいませ。
Copyright(C) 1998-2023 Noisy Wine [ Noisy's Wine Selects ] Reserved


















