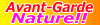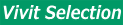頻繁なリロード禁止のお願い
大変お世話になっております。切実なお願いです。
ページのリロードが必要以上に行われるようになっています。サーバーへの過大な負荷でページ更新が滞る状況になっていますので、頻繁なリロードはお止めくださるようお願いいたします。
また、「503 Server is busy」のエラードギュメントページが表示され、一定時間アクセスが制限される場合がございます。いずれ元に戻りますが、そのようなことにならないようお願いいたします。
詳細ページ
ページのリロードが必要以上に行われるようになっています。サーバーへの過大な負荷でページ更新が滞る状況になっていますので、頻繁なリロードはお止めくださるようお願いいたします。
また、「503 Server is busy」のエラードギュメントページが表示され、一定時間アクセスが制限される場合がございます。いずれ元に戻りますが、そのようなことにならないようお願いいたします。
詳細ページ
■新着情報メールサービスのご登録
Noisy wine の新着情報メールサービスにご登録いただきますと、ご登録いただきましたメールアドレスに「タイムリーに」更新情報をお届けいたします。希少性のあるワインをご希望でしたら登録必須のサービスです。
■お届け情報他
現在以下の宛先に対し新着情報メールをお届けするすることが出来ません。世界情勢を反映してか、各社様メールのフィルターを厳しくしています。申し訳ありませんが gmail.com や yahoo.co.jp (yahoo.comは厳しいです) などのフリーアドレスに変更をご検討の上、再登録をお願いいたします。不明な方は最下段中央の「e-mail to noisy」よりお問い合わせください。
■新着情報メール不達の宛先(新規登録も出来ません)
icloud.com nifty.com me.com mac.com hi-ho.ne.jp tiki.ne.jp enjoy.ne.jp docomo.ne.jp plala.or.jp rim.or.jp suisui.ne.jp teabreak.jp outlook.com outlook.jp hotmail.co.jp hotmail.com msn.com infoseek.jp live.jp live.com
etc.
■お届け情報他
現在以下の宛先に対し新着情報メールをお届けするすることが出来ません。世界情勢を反映してか、各社様メールのフィルターを厳しくしています。申し訳ありませんが gmail.com や yahoo.co.jp (yahoo.comは厳しいです) などのフリーアドレスに変更をご検討の上、再登録をお願いいたします。不明な方は最下段中央の「e-mail to noisy」よりお問い合わせください。
■新着情報メール不達の宛先(新規登録も出来ません)
icloud.com nifty.com me.com mac.com hi-ho.ne.jp tiki.ne.jp enjoy.ne.jp docomo.ne.jp plala.or.jp rim.or.jp suisui.ne.jp teabreak.jp outlook.com outlook.jp hotmail.co.jp hotmail.com msn.com infoseek.jp live.jp live.com
etc.
noisy のお奨め

Spiegelau Grand Palais Exquisit
シュピゲラウ・グランパレ・エクスクイジット・レッドワイン 424ML
軽くて薄くて香り立ちの良い赤ワイン用グラスです。使い勝手良し!
Comming soon!

Spiegelau Grand Palais Exquisit
シュピゲラウ・グランパレ・エクスクイジット・ホワイト 340ML
軽くて薄くて香り立ちの良い白ワイン用グラスです。使い勝手良し!
Comming soon!
有 る と 便 利 な グ ッ ズ !
WEBの情報書込みもSSLで安心!


Noisy Wine [NOISY'S WINE SELECTS] のサイトでは、全ての通信をSSL/TLS 情報暗号化通信し、情報漏洩から保護しています。
◆◆Twitter 開始のご案内

時折、Twitter でつぶやき始めました。もう・・どうしようもなくしょうもない、手の施しようの無い内容が多いですが、気が向いたらフォローしてやってくださいね。RWGの徳さん、アルXXロのせんむとか・・結構性格が出るもんです。
https://twitter.com/noisywine
バティスト・ナイラン
バティスト・ナイラン
フランス Baptiste Nayrand ブルゴーニュ
[ oisy wrote ]
ブルゴーニュはコトー・デュ・リヨネより、ナチュール界の新星バティスト・ナイランをご紹介いたします。
コトー・デュ・リヨネというアペラシオンはご存知ない方もいらっしゃるかと多いかと思います。調べてみると、ソムリエ教本にはブルゴーニュのページの最後に一行記載されているのみでした。ボジョレーから南、リヨン西側の丘陵地帯で、ガメイが主体の地域です。
バティストのスタイルは「ナチュール系」です。しかも結構「攻め攻め」です。この1年私もNoisy Wineに入荷するワインを毎日テイスティングしてきましたが、その中でも「最もアヴァンギャルド」かもしれません。
揮発酸もあります。ですので「揮発酸のニュアンスが全くダメ」という方はお手に取らないようご注意ください。
赤はそれほどもないですが、白のゼニスは「ギリギリまで攻めて」います。ナチュール好き、という方もゼニスに関しては特にコラムをよくご確認の上、ご購入ください。
しかしこの攻めたスタイルだからこそ辿りつける、「激ピュアな世界」があることを知りました。アヴァンギャルドレベルがトップクラスなら、ピュア感もトップレベルです。エキスの抽出が驚くほど上手いです。
お好きな方の手に届くことを祈っております。各コラムに詳細を記載しております。キュヴェによってアヴァンギャルドさは大きく異なりますので、よくよくご確認の上ご購入いただけますよう、よろしくお願い申し上げます。
 ■エージェント情報
■エージェント情報
世界的な食のライト&ヘルシー化によって、今ではピノ・ノワールに並ぶ人気品種となったガメィ。そんなガメィの新たな可能性を表現する造り手が現れました。2015ヴィンテージからナチュラルワイン造りを始めたバティスト・ナイランです。バティストは、ピエール・オヴェルノワやマルセル・ラピエールのワインに強い感銘を受け、30歳の時にそれまでの仕事を辞めて、ジュリアン・ギィヨとミシェル・ギニエの下で研鑽。生まれ故郷であるリヨン近隣のコトー・デュ・リヨネ南部のミルリーで1ヘクタールの古木のガメィの畑を引き継いで、ドメーヌを設立しました。
2015年が初ヴィンテージですが、欧米のガメラーのナチュラルワイン愛好家の間では大人気で、既にドメーヌからの割り当て数量しか購入することができません。北の品種が好きなバチストはピノ・ノワールやアリゴテ、シャルドネなどのワインも手掛けています。
ブルゴーニュはコトー・デュ・リヨネより、ナチュール界の新星バティスト・ナイランをご紹介いたします。
コトー・デュ・リヨネというアペラシオンはご存知ない方もいらっしゃるかと多いかと思います。調べてみると、ソムリエ教本にはブルゴーニュのページの最後に一行記載されているのみでした。ボジョレーから南、リヨン西側の丘陵地帯で、ガメイが主体の地域です。
バティストのスタイルは「ナチュール系」です。しかも結構「攻め攻め」です。この1年私もNoisy Wineに入荷するワインを毎日テイスティングしてきましたが、その中でも「最もアヴァンギャルド」かもしれません。
揮発酸もあります。ですので「揮発酸のニュアンスが全くダメ」という方はお手に取らないようご注意ください。
赤はそれほどもないですが、白のゼニスは「ギリギリまで攻めて」います。ナチュール好き、という方もゼニスに関しては特にコラムをよくご確認の上、ご購入ください。
しかしこの攻めたスタイルだからこそ辿りつける、「激ピュアな世界」があることを知りました。アヴァンギャルドレベルがトップクラスなら、ピュア感もトップレベルです。エキスの抽出が驚くほど上手いです。
お好きな方の手に届くことを祈っております。各コラムに詳細を記載しております。キュヴェによってアヴァンギャルドさは大きく異なりますので、よくよくご確認の上ご購入いただけますよう、よろしくお願い申し上げます。
 ■エージェント情報
■エージェント情報世界的な食のライト&ヘルシー化によって、今ではピノ・ノワールに並ぶ人気品種となったガメィ。そんなガメィの新たな可能性を表現する造り手が現れました。2015ヴィンテージからナチュラルワイン造りを始めたバティスト・ナイランです。バティストは、ピエール・オヴェルノワやマルセル・ラピエールのワインに強い感銘を受け、30歳の時にそれまでの仕事を辞めて、ジュリアン・ギィヨとミシェル・ギニエの下で研鑽。生まれ故郷であるリヨン近隣のコトー・デュ・リヨネ南部のミルリーで1ヘクタールの古木のガメィの畑を引き継いで、ドメーヌを設立しました。
2015年が初ヴィンテージですが、欧米のガメラーのナチュラルワイン愛好家の間では大人気で、既にドメーヌからの割り当て数量しか購入することができません。北の品種が好きなバチストはピノ・ノワールやアリゴテ、シャルドネなどのワインも手掛けています。
●2022 Sauvage Rouge V.d.F.
ソヴァージュ・ルージュ V.d.F.
【果実酸の旨み、あまみが激ウマ!激ピュア!ガメイの亜種が主体の20品種のフィールド・ブレンドです!】[ oisy wrote ]
 [ oisy wrote ]
[ oisy wrote ]赤白約20品種混植のフィールド・ブレンドとのことですが、製法、色味的に赤ワイン寄りだと思っていただいた方がいいかと思います。ただしその色味はかなりクリアーで透明感を持ち、白ブドウがブレンドされていることは見た目からもわかります。
最近、マルセルダイスのラルシュやクロヴァロンのレ・ザンディジェーヌなどのワインを飲ませていただき、「フィールド・ブレンドのワインにしかない良さ」があると感じております。
それは色んなブドウ品種由来の味がする、ということではなく、「様々な特徴を持ったブドウ品種が一体となった時の美しさ」が素晴らしいということです。単一品種がピアノの独奏とするならば、さながらオーケストラのような感じです。お、ちょっとうまいこと言えたかもしれません。
とにかくピュアな、赤い果実です。そこに探せば、アンズ、オレンジ、枇杷、アメリカンチェリー、金木犀、バラ、ラベンダーなど様々な要素が入り乱れています。
しかし不思議と一体感があり、じゃあ誰がこれを指揮しているのかといえば、この土地のミネラリティ、すなわちテロワールだと思います。
バティストの他のワインを飲むと、全体的にツヤ感のあるミネラリティを感じます。このワインも白ブドウ由来の透明感かな、と思っていましたがそれだけではなく、石灰系のミネラリティ由来の透明感もあるような気がします。ですのでどのワインもはっきりと「赤い果実」が主体に来ます。
またこのワインを飲んでイメージしたのはヴァーゼン・ハウスの激うまグラン・ドルディネールです。「弾けるような赤い果実の旨みとピュア感」がよく似ていて、テクニカルを見るとセミ・マセラシオンカルボニックを用いているところから手法的にも近しい感性で作られているのかなと思いますが、ヴァーゼンハウスは親しみやすいワインを造るという目的で導入しているかと思いますが、バティストはこの区画のブドウには「この手法が良い」ということで採用しているように感じます。というのもこのワインが他のバティストのワインと比べて飛び抜けてエレガンスを持っているからなんですね。
そしてほぼ気づかない程度の甘さがあります。果実のあまやかさと僅かな残糖、そして果実酸の旨みがワイン全体をまとめ上げています。この「あまみが激うま」です。(ワインとしてはドライ・・・いや中口というのが適切かと思います。)
そしてこのワインも揮発酸は僅かにありますが、問題ないです。むしろこのワインに関しては他のワインよりも揮発酸以外の要素が先んじて上がってきているので(セミ・マセラシオン・カルボニックの影響かな・・・)今時点で最も安定してきています!
ただし激ピュアですので、温度管理にはお気をつけくださいませ。14度前後での保管が推奨です。20度を超えると劣化の恐れがあります。昨今スーパーなどで色んな理屈をつけて「生ワイン」と謳っているものを散見しますが、こういうワインこそ「生ワイン」と言いたくなりますね!ご検討くださいませ。
Copyright(C) 1998-2023 Noisy Wine [ Noisy's Wine Selects ] Reserved